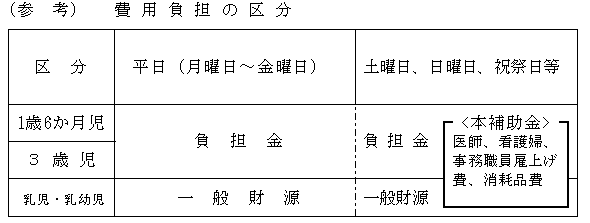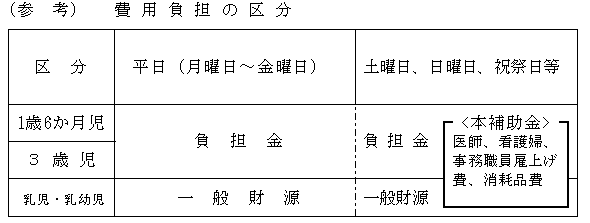目次へ戻る
(母子保健課関係)
1 総合的母子保健対策の推進について
母子保健は、生涯の健康の基礎であり、また、次の世代を健やかに生み育てるための基礎であることから極めて重要であると認識しており、今後とも、住民の多様なニーズに対応した母子保健対策の一層の推進を図って行くこととしている。
このため、平成12年度においても、(1)周産期医療対策事業、(2)生涯を通じた女性の健康支援事業、(3)子どもの心の健康づくり対策事業等、少子社会に対応した総合的な母子保健対策の充実強化を図ることとしている。
また、平成9年4月より、母子保健サービスの主たる実施主体を市町村に移譲したところであるが、都道府県におかれては、引き続き、改正の趣旨を踏まえ管下市町村に対する指導・助言を願いたい。
2 21世紀の母子保健に係る国民運動計画(「健やか親子21」)について
これまでの母子保健の取組みの成果を踏まえるとともに、残された課題と新たな課題を整理し、21世紀の母子保健の取組みの方向性を提示すると同時に、目標値を設定し、関係機関・団体が一体となって推進する国民運動計画として、「健やか親子21」を関係専門家等による検討を経て、平成12年中に策定、実施することとしている。
本計画は、国民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現を図るための国民の健康づくり運動(「健康日本21」)の一環となるものである。
3 乳幼児健康支援一時預かり事業の充実について
(1)実施施設等の拡充
乳幼児健康支援一時預かり事業については、事業の一層の拡大のため、
- (1) 実施施設に保育所を追加
(2) 派遣対象に
- ・保護者が病気等になった家庭
・出産後間もないため家事や育児が困難な核家族家庭
を追加することとしたので、各市町村の積極的な取り組みについて指導されたい。
また、引き続き労働省のファミリー・サポート・センター事業の会員の保育士等を活用とするとともに、同事業において本事業の申請代行、送り迎え、情報提供を行う。(平成12年度 200市町村)
(2)施設整備
平成12年度予算案において、児童福祉施設(保育所、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設)に本事業のための施設整備(利用定員1人当たり7.2平方メートル)を社会福祉施設等施設整備費により行うこととしたので、これが整備方についても活用するようお願いしたい。
また、本事業は子育て支援のための拠点施設の対象事業でもあるので、拠点施設の整備についても活用されたい。
4 児童虐待防止市町村ネットワーク事業について
本事業については、児童虐待への対応の強化を図るため、「子どもの心の健 康づくり対策事業」の一環として、平成12年度に創設予定である。
各市町村においては、児童虐待に関する昨今の状況に鑑み、緊急に対応すべき課題として、本事業の積極的な実施をお願いするとともに、各都道府県においても、管下市町村における取組みの促進が図られるよう助言・指導に努められたい。
なお、児童虐待対策の一層の推進を図る観点から、子どもの心の健康づくり対策事業中の「虐待・いじめ対策事業」及び「出産母子支援事業」についても、市町村の積極的な実施をお願いしたい。
- (1) 趣 旨
- 近年、児童虐待の問題が深刻な社会問題となっており、住民に身近な市町村域において、関係者による密接な連携を図ることにより、児童虐待への取組みの強化を図る。
- (2) 事業内容
- 保健、医療、福祉、教育、警察、司法等の関係機関・団体等から構成する 「児童虐待防止協議会」を設置し、次の事項を検討するため、定期的な連絡会 議を開催するとともに、事例検討を随時に実施する。
- ア) 児童虐待についての情報提供に関すること
イ) 被虐待児童の発見からサポートに至るシステムに関すること
ウ) 児童虐待についての地域社会への啓発活動に関すること
エ) その他児童虐待に関すること
- (3) 実施主体 市町村
- (4) 補助率 1/3(国 1/3 都道府県 1/3 市町村 1/3)
- (5) 補助年限 原則として2年間とする。
5 周産期医療ネットワークの整備について
妊産婦死亡、周産期死亡等のさらなる改善により安心して出産ができる体制を整備するため、新エンゼルプランにおいて、総合周産期母子医療センターを中核とした周産期医療ネットワーク(システム)の整備を進めることとしている。
地域医療計画の改訂に際しては、周産期医療について計画に盛り込むとともに、平成16年度までに原則として各県に1ヶ所の総合周産期母子医療センターを整備し、これを中心とした地域周産期母子医療センター及び一般産科との母体及び新生児の搬送体制をはじめとする連携体制の整備をお願いしたい。
また、総合周産期母子医療センターの運営費については、補助対象を当面各都道府県1か所としていたが、周産期医療ネットワークの整備を進める一環として人口規模が大きい等の理由で複数設置する場合には、複数か所も補助対象とすることとしている。
なお、整備に当たっては、医療施設等施設整備費・設備整備費(小児医療施設及び周産期医療施設)を活用するとともに総合周産期母子医療センターについては、原則として総合周産期特定集中治療室管理の施設基準(母体・胎児集中治療室については、現行の9床以上から6床以上に緩和される予定)を満たすようにされたい。
6 不妊専門相談センター事業の整備について
(1)不妊専門相談センター事業
不妊に悩む方々に的確な情報を提供し、専門的な相談に応じられる体制を地域において整備することは重要であることから、平成8年度から「生涯を通じた女性の健康支援事業」の一環として、不妊専門相談センター事業を実施しているが、本事業について、今般の新エンゼルプランの中で、計画的に整備すべき重点施策として位置づけられたところであるので、各都道府県の積極的な実施をお願いし
たい。
-
<平成12年度対象数>
24ヶ所 |
→ |
<平成16年度目標値>
47ヶ所 |
(2)不妊治療の情報提供事業
- (1) 趣 旨
- 不妊治療を望む夫婦にとって、不妊治療の実施医療機関の情報が乏しく、経済的・身体的に大きな負担となる場合があることから、相談者に対し実施医療機関の実施状況等の情報を提供を行うことにより、こうした家庭の負担軽減を図る。
- (2) 事業内容
- ア 実施場所
- 不妊専門相談センターや保健所等とする。
- イ 情報提供の内容
- 都道府県域やその近隣地域における不妊治療の実施状況について、情報提供を行う。
- (例)
・不妊治療実施機関の名称、内容
・年齢等の条件に応じた成功率 等
- ウ 情報提供の方法
- ・実施状況を掲載した情報冊子等を作成し、不妊相談に来た者に配布する。
- ・地方の医師会や産婦人科医等の密接な連携を図り、最新の情報収集に努める。
- (3) 実施主体 都道府県、指定都市、中核市
- (4) 補助率 1/2(国 1/2 都道府県等 1/2)
- (5) 留意事項
- 本事業は、不妊専門相談センター事業を実施する都道府県等において実施することを原則とし、同センターのほか保健所等においても情報を活用し相談に応じることができるようにするなど、不妊専門相談センター、保健所等のネットワークを強化する。
7 乳幼児事故防止対策等に関する普及啓発について
平成12年度においては、次のとおり、乳幼児の事故防止対策及び乳幼児突然死症候群対策(SIDS)に関する普及啓発事業を実施することとしているので、関係機関等への配布方につき、ご協力をお願いしたい。
なお、SIDSに関する平成11年度の普及啓発事業として、一般家庭向けのリーフレットを新たに作成し、都道府県等に対し3月末頃に送付する予定であるので、各家庭への配布方ご協力をお願いしたい。
また、各都道府県等においても、これらの対策について創意工夫に努め積極的な取組みをお願いしたい。なお、この場合には、母子保健強化推進特別事業などの活用も検討されたい。
(1)乳幼児事故防止対策に関する普及啓発
乳幼児のうち1歳〜4歳児の死亡原因として、溺水、誤飲等の不慮の事故が第一位となっているため、乳幼児の事故予防は重要な課題となっている。
これらについては、周囲の大人が目を光らせることで事故の6割が防げると言われていることから、一般家庭や保育所等の児童福祉施設等の職員に対して、こうした事故予防の方法や、万一の際の応急処置などの普及啓発を行うこととし、事故防止対策のポスターを作成するとともに、一般家庭等に対する講習会(4か所)を開催することとしている。
(2)乳幼児突然死症候群(SIDS)対策に関する普及啓発
乳幼児突然死症候群(SIDS)については、平成9年度の心身障害研究報告を踏まえ、発症の予防に対する対策を進めているところであるが、平成12年度においても、引き続きその取組みの推進を図ることとし、乳児院、保育所等の児童福祉施設等に対し普及啓発用のパンフレットを作成・配布することとしている。
なお、平成10年におけるSIDSによる乳幼児の死亡数は399人と、前年比25%程度の減少となるなど、キャンペーンの効果が現れているのではないかと考えており、各都道府県においても対策の一層の強化をお願いしたい。
-
(参考)SIDSによる乳幼児の死亡数
| 7年 |
8年 |
9年 |
10年 |
| 579人 |
526人 |
538人 |
399人(-139) |
8 休日健診・相談等事業について
本事業は、共働き家庭等にとって平日に休みが取りにくいこと等により、健康診査・保健指導等を受けることが困難な場合があることから、平成12年度予算案においてこうした家庭に対する子育て支援策の充実を図るため、新たに育児等健康支援事業のメニュー事業として創設することとしている。こうした趣旨に鑑み、各市町村の積極的な取組みをお願いしたい。
- (1) 趣 旨
- 乳幼児健康診査や保健指導等について、休日における実施を図ることにより、母子保健分野における基本的サービスである、これらの事業の受診機会の整備を図るとともに、受診率の向上に資する。
- (2) 事業内容
- ア 対象となる事業
- 休日において、乳幼児に対する健康診査及び保健指導又はその他の相談事業を実施する。なお、本事業でいう「休日」とは、土曜日及び日曜日・祝祭日等の休日とする。
- イ 対象児童
- ア)母子保健法に基づき実施する健康診査(1歳6か月児、3歳児、乳児等)又は保健指導の対象者であるが、保護者の勤務等の都合により、これらの母子保健事業を平日に受けることが困難な者。
- イ)保健相談やその他の相談が必要な者。
- ウ 実施方法
- 健康診査等の実施は、原則として、集団方式により市町村保健センター等、対象者が利用しやすい施設で実施する。
- エ 実施回数
- 健康診査、保健指導等の開催回数(同一日に同一会場で実施する場合には、1回とする。)は、合わせて概ね月2回以上実施する。
- (3) 実施主体 市町村
(4) 補助単価(予定) 1,057千円 (メニュー事業としての単価)
(5) 対象経費 医師、看護婦、事務職員の雇上費、消耗品費
(6) 補助率 1/3(国 1/3 都道府県 1/3 市町村 1/3)
(7) 留意事項
- ア 利用者の利便性の向上を図ることが本事業の目的であることから、これまで平日に実施してきた健康診査等を本事業に振り替えるなどにより、平日における受診機会が減るなど、結果として利便性が損なわれることのないように留意する。
- イ 育児等健康支援事業のメニュー事業のうち、「その他母子の健全な育成に資する事業」については、平成11年度限りで廃止する予定である。
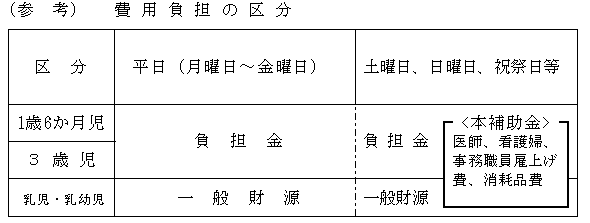
| (注) |
1 |
休日に健康診査等を実施するために特別に医師等を雇い上げて事業を行う場合に、医師等の報酬等及び消耗品費を本補助金の対象とする。 |
| 2 |
市町村職員の給与費(給料、職員手当等)、薬品費等は、本補助金の対象としない(負担金の対象)。 |
| 3 |
同じ経費に対し、本補助金と負担金が2重払いとならないよう区分する。 |
9 先天性代謝異常等検査の充実について
障害の早期発見・早期治療を図る観点から、従来より先天性代謝異常等検査を実施しているが、平成12年度予算案においては、次のように拡充を図ることとしているので、各都道府県・指定都市における積極的な対応をお願いしたい。
(1)新生児聴覚障害検査(平成12年10月から実施)
- (1) 趣 旨
- 難聴児に対する適切なケアを早期から開始することは、乳幼児の生育環境を整備する上で重要なことであるが、一方で、新生児や乳幼児期の聴覚障害は、他覚的兆候に乏しいこともあり、年齢が進んでから発見されることが多いのが現状となっている。
このため、近年の医療技術の進歩を踏まえ、聴覚障害を早期に発見し、早期治療を進める観点から、聴覚スクリーニングの普及を図る。
なお、当面は、試行的に事業を実施し、スクリーニングに適した実施方法等を検討することとする。
- (2) 事業内容
- ア 乳児等に対し、自動聴性脳幹反応検査装置(AABR)等の検査装置を使用して実施する。
- イ 検査の実施場所は、年間出生数が概ね250人以上の医療機関等とする。
- (3) 実施主体 都道府県、指定都市
(4) 補 助 率 1/3(国 1/3 都道府県・指定都市 2/3)
(5) 留意事項
- ア 検査を実施する医療機関等と、療育を実施する福祉施設等、関係機関の密接な連携体制の確立に努める。
- イ 具体的な実施方法や療育体制については、平成11年度の厚生科学研究費において研究を行っているところであり、研究報告を踏まえて、改めて事業の詳細(補助単価を含む)についてお知らせすることとする。
(2)神経芽細胞腫検査の精度管理事業
- (1) 趣 旨
- 神経芽細胞腫のスクリーニング検査においては、患者の発見漏れを引き起こした場合に、重大な結果を招く恐れがあるため、精度管理機関による精度管理事業を実施することにより、検査精度の維持向上を図る。
- (2) 事業内容
- ア 次に掲げる事項について、適当な精度管理機関に委託して行う。
- ア) 神経芽細胞腫検査に関する精度の維持向上を図るための精度試験
イ) 必要な技術指導
ウ) 検査用試薬及びスタンダード血液等の品質管理
エ) その他精度管理上必要なもの
- イ 精度管理機関は、検査機関に対し精度管理に必要な相当数の標準検体を定期的に送付する。
- (3) 実施主体 都道府県、指定都市
(4) 補助率 1/3(国 1/3 都道府県・指定都市 2/3)
(5) 留意事項
- ア 精度管理の一定水準の確保や統一的な技術指導を図る必要があることから、精度管理機関については、関係学会のご意見を踏まえ、適当な機関を選定する予定である。
- イ なお、従来から実施している先天性代謝異常等検査の精度管理機関については、かねてご案内(平成11年10月 6日母子保健係長事務連絡)のとおり、平成12年4月から財団法人東京顕微鏡院に変更するものである。
10 乳幼児健康診査費等の一般財源化について
乳幼児健康診査(昭和23年度創設)及び乳児健康診査(昭和44年度創設)は、制度創設後相当の年数が経過し市町村の経常的な事務として同化・定着していることから、地方分権推進委員会の第2次勧告の趣旨に沿って、平成11年度及び平成12年度の2か年間で一般財源化を行うこととしている。
なお、所要の財源については地方交付税措置されることとなるので、一般財源化によって事業の低下を招くことのないよう管下市町村に対し指導願いたい。
11 都道府県母子保健医療推進費の廃止について
都道府県母子保健医療推進費については、平成9年度の母子保健事業の市町村移譲後における市町村の母子保健に関する情報を収集・解析・還元することにより、有効かつ的確な地域母子保健医療対策の確立及び推進を図ることを目的に、平成8年度から実施してきたところであるが、平成12年度で市町村移譲後から3年を経過し、母子保健事業が市町村の行う事業として定着してきたことから、廃止することとしたものである。
12 思春期保健対策の推進について
核家族化や、一人っ子家庭の増加等により他者とのふれあいが減少し、命の大切さへの意識が希薄となる一方で、性の軽視、薬物等の誤った情報が氾濫するなど、思春期の男女を取り巻く環境は著しく悪化している。
このような状況を放置することは、健全な父性、母性の醸成が困難となるばかりでなく、不妊症や生活習慣病など、健康に対し取り返しのつかない悪影響を及ぼすことが懸念されるところである。
このため、都道府県、市町村においては、父性、母性の涵養等、思春期保健対策への取り組みの一層の強化をお願いするとともに、思春期の男女に対して、性や健康問題に関する正しい情報の提供に努められたい。
なお、厚生省においても、こうした取り組みを行う場合には、育児等健康支援事業(思春期における保健・福祉体験学習事業、健全母性育成事業)や、母子保健強化推進特別事業等により、積極的に助成を行うこととしているので、都道府県等の取り組みをお願いしたい。
13 「多胎児育児支援ハンドブック」及び「低出生体重児育児支援ハンドブック」の配布について
多胎児や低出生体重児の家庭においては、出産費用や育児費用等の経済的負担のみならず、精神的・身体的負担も大きいことから、こうした家庭への支援が必要となっている。
このため、妊娠中の生活や留意点、出産の状況に応じた育児の仕方や体験談等を掲載した「多胎児育児支援ハンドブック」及び「低出生体重児育児支援ハンドブック」を現在作成中であり、3月末までに各都道府県等に送付することとしているので、多胎等の家庭に対する配布方について、特段のご配慮をお願いしたい。
(資料1)
「健やか親子21」の概要
○ 我が国の母子保健は、20世紀中の取組みの成果として既に世界最高水準にあるが、妊産婦死亡や乳幼児の事故死について改善の余地があるなどの残された課題や思春期における健康問題、親子の心の問題の拡大などの新たな課題が存在する。また、小児医療や地域母子保健活動の水準の低下を防止する等、保健医療環境の確保についても対応すべき課題が存在する。
「健やか親子21」は、これまでの母子保健の取組みの成果を踏まえるとともに、残された課題と新たな課題を整理し、21世紀の母子保健の取組みの方向性を提示するものであると同時に、目標値を設定し、関係機関・団体が一体となって推進する国民運動計画である。関係専門家等による詳細な検討を経て、平成12年中に策定し実施する。
- 「健やか親子21」のイメージ
・21世紀の母子保健の主たる課題を提示
-
(1)思春期の保健対策の強化と健康教育の推進
(2)妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援
(3)子供のからだの健やかな発達を図るための環境整備
(4)育児不安の解消と子供の心の安らかな成長の促進
・各課題に関する2010年の目標値を提示
・関係機関・団体等による国民運動の展開方法を具体的に提示 |
○ 「健やか親子21」は、安心して子供を産み、健やかに子供を育てることの基礎となる少子化対策としての意義に加え、少子・高齢社会において、国民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現を図るための国民の健康づくり運動(「健康日本21」)の一環となるもの。
- (注)「健康日本21」について
- ・ 全ての国民が、健康で明るく元気に生活できる社会の実現のため、壮年死亡の減少、痴呆や寝たきりにならない状態で生活できる期間の延伸等を目標に、国民の健康づくりを総合的に推進。
・2010年を目標年度として2000年から計画を実施。
(資料2)
乳幼児健康支援一時預かり事業
1 趣 旨
子育てと就労の両立支援の一環として、保育所へ通所中の児童等が「病気回復期」であることから、自宅での養育を余儀なくされる期間、当該児童を保育所、病院等の付設された施設等において一時預かる事業を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援し、併せて児童福祉の向上にも資することを目的とするものである。
また、訪問型(派遣方式)により病気回復期の乳幼児、保護者が病気等になった家庭や産後で体調不良である家庭に保育士等が訪問し、保育等を行う。
2 事業内容
(1)病気の回復期である児童を保育所、病院等の専用スペース又は派遣された保育士等が児童の自宅等で一時的に預かる事業
- (1)病後児への適切な対応が可能な、保育所(保育所は平成12年度新規対象)等の児童福祉施設、病院、診療所に併設した一時預かり施設等において実施する。
施設型に加え保育士等訪問型として市町村(委託も可)に登録した保育士、看護婦等が施設の空き部屋や自宅等を利用して保育を実施する。
- (2)一時預かりの期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭での育児を行うことのできない期間の範囲内とする。
- (3)実施施設の利用児童の定員は、乳幼児2人以上はB型とし、4人以上はA型とする。
- (4)実施施設には、原則看護婦及び保育士等を利用児童2名に対して1名配置する。
- (5)実施施設には、保育室、観察室又は安静室及び調理室等の事業の実施に必要な設備を有する。
(2)出産後間もないため家事や育児が困難な核家族家庭に対して、訪問して身の回りの世話や育児を行う事業(新規)
- (1)派遣対象となる家庭
- ・出産後間もない核家族等で昼間に介助する者がいない家庭であって、体調が不調のため、身の回りのことや家事、育児が困難となっているもの。
・出産後間もない多胎の家庭。
- (2)派遣内容
- ・家事の援助及び助言・相談、育児の援助及び助言・相談
・派遣時間は1回4時間以内
・派遣日数については、原則退院後1か月で10日を限度とし、多胎児については前記の10日とは別に出産後1年の間で15日を限度とする。
- (3)派遣職員
- 看護婦、保育士、乳幼児の養育に経験がある者等
(3)保護者の傷病・入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童に対して保育士等が保護者宅に訪問して保育を行う事業(新規)
- (1)対象児童
- 保護者の傷病・入院等により、保護者宅において緊急・一時的に保育が必要となる児童
- (2)派遣職員
- 保育士、乳幼児の養育に経験がある者等
3 事業費等(12年度予算単価(案))
| 体 型 |
対 象 |
定 員 |
職 員 |
実施場所 |
事業費 |
利用者負担 |
| 施設型 |
病気回復期
にある乳幼児
(保育所利用児童等) |
A型(従来型)
1日利用
4人以上 |
常勤看護婦1人
非常勤保育士等
1人 |
保育所、病院
等の空き部屋 |
年額
8,739千円 |
(1)生活保護法による
被保護世帯、市町村
民税非課税世帯
0円
(2)所得税非課税世帯
((1)を除く)
1,000円
(3)所得税課税世帯
2,000円 |
B型(新規)
1日利用
2名以上 |
常勤的非常勤看
護婦1人 |
保育所、病院
等の空き部屋 |
年額
5,553千円 |
| 訪問型 |
病気回復期にある乳幼児
(保育所利用児童等) |
実施施設で職員
を置かない場合
非常勤看護婦等 |
保育所、病院
等の空き部屋 |
日額
6,570円 |
| 非常勤看護婦等 |
児童の自宅等 |
保護者が病気になった家庭(新規)
(在宅保育児童) |
非常勤保育士等 |
児童の自宅 |
日額
6,120円 |
事業費の1/2
3,060円
(一時保育並び) |
産後で体調不良である家庭(新規)
(新生児及び産褥婦) |
非常勤看護婦等 |
産褥婦(児童)
の自宅 |
半日
3,280円 |
上記
(1)0円
(2)500円
(3)全額徴収 |
4 補助基準額(病気回復期にある乳幼児)
| |
A型(従来型)
(1カ所) |
B型(新規)
(1カ所) |
実施施設で職員
を置かない場合
(1市町村) |
| 定額分 |
6,739千円 |
4,454千円 |
2,169千円 |
| 加算額 |
1,000人以上
1名につき
4,570円 |
500人以上
1名につき
4,570円 |
1名につき
4,570円 |
生活保護法による被保護世帯、
市町村民税非課税世帯 |
1名につき
2,000円 |
1名につき
2,000円 |
1名につき
2,000円 |
| 所得税非課税世帯 |
1名につき
1,000円 |
1名につき
1,000円 |
1名につき
1,000円 |
5 市町村事務費(基準額)
1市町村 625千円(研修費、登録費、パンフレット等)
6 実施主体……………市町村(特別区を含む。)
| 7 補助率…………… |
1/3(負担割合 国1/3,都道府県1/3,市町村1/3 ) |
| (負担割合 国1/3,指定都市2/3 ) |
8 留意事項
- ・施設型として保育所で行う場合は、センター方式とし他の保育所等の児童も受け入れること。
- ・実施施設型(A型、B型)及び実施施設で職員を置かない場合は、当分の間厚生省に協議するものとする。
目次へ戻る