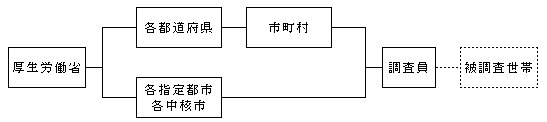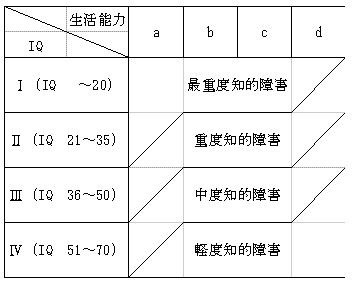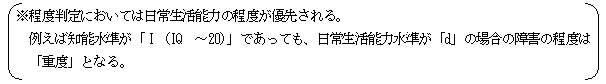|
平成17年度知的障害児(者)基礎調査結果の概要
社会・援護局障害保健福祉部 企画課
調 査 の 概 要
| 1 | 調査の目的 |
| この調査は、在宅知的障害児(者)の生活の実状とニーズを正しく把握し、今後における知的障害児(者)福祉行政の企画・推進の基礎資料を得ることを目的とした。 |
| 2 | 調査の対象及び客体 |
| 全国の在宅知的障害児(者)を対象として、平成12年国勢調査により設定された調査区から、150分の1の割合で無作為抽出された地区を対象調査区としたところ、客体は2,584人、調査票の回収数は2,123で回収率は82.2%、有効回答数は2,075件で有効回答率は80.3%であった。 |
| ※ | この調査は在宅を対象とし、社会福祉施設入所者(知的障害児施設、自閉症児施設、重症心身障害児施設、知的障害者更生施設(入所)、知的障害者授産施設(入所)は対象とされていない。(グループホーム、通勤寮、福祉ホーム利用者は対象としている。) |
| 3 | 調査の時期 |
| 平成17年11月1日現在 |
4 調査の機関
| 5 | 調査の方法 | |
| (1) | 調査員が、調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無の確認を行う。 | |
| (2) | 調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼する。 (自計郵送方式) |
|
| (3) | 調査票は、原則として調査対象者本人が記入する。 | |
| 6 | 調査の集計 |
| 調査の集計は、社会・援護局障害保健福祉部が行った。 |
| 7 | 利用上の注意 | |||||
| (1) | 表章記号の規約
|
|||||
| (2) | この概況に掲載の数値は四捨五入してあるため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。 | |||||
| (3) | この概況に掲載の表の単位は「人」、( )は%である。 | |||||
調 査 結 果 の 概 要
1 知的障害児(者)の総数及び年齢分布(推計値)
(1)総 数
平成17年11月現在、全国の在宅知的障害児(者)は、419,000人と推計される。
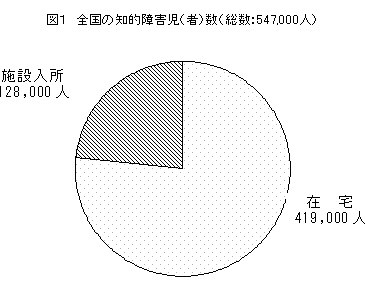
| ※ | 「在宅」は、今回の調査結果による。 | |
| ※ | 「施設入所」は、社会福祉施設等調査(平成16年10月1日現在)によるものであり、参考 として載せたものである。 |
○参 考:知的障害児(者)数の推移
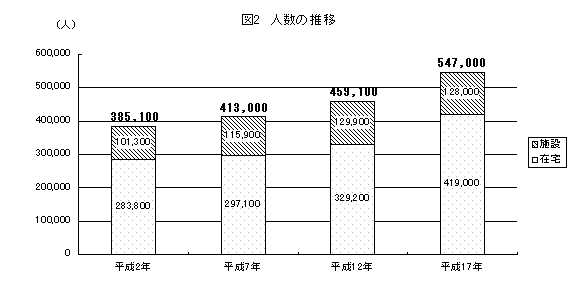
(2)年齢分布
在宅の知的障害児(18歳未満)は117,300人、知的障害者(18歳以上)は289,600人と推計される。
(なお、12,100人の年齢不詳の人あり)
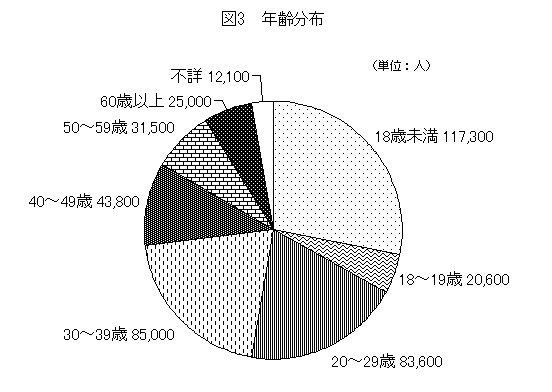
○参 考:知的障害児(者)の年齢分布の推移
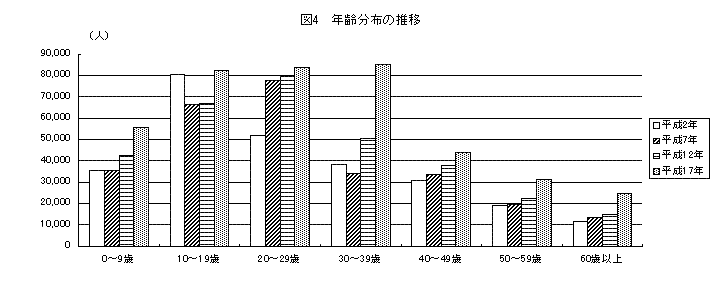
| ※平成17年度調査における人口千人当たりの人数(人) | ||||||||||||||
|
2 障害の程度(推計値)
(1)障害の程度
「最重度」「重度」が39.3 %、「中度」「軽度」は48.8 %となっている。18歳未満の「最重度」「重度」は42.7 %、「中度」「軽度」は50.8 %、18歳以上の「最重度」「重度」は39.2 %、「中度」「軽度」は49.0 %となっている。
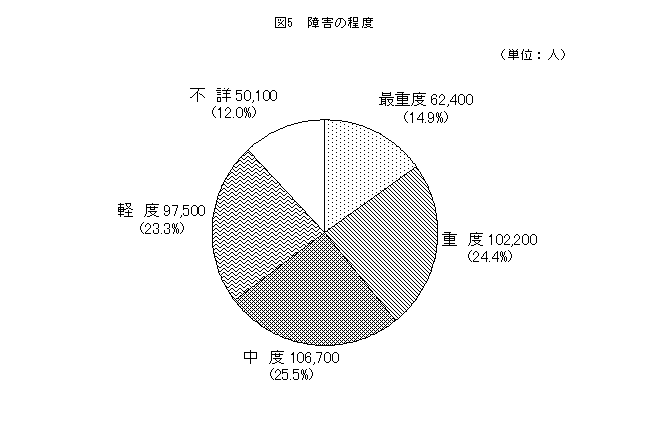
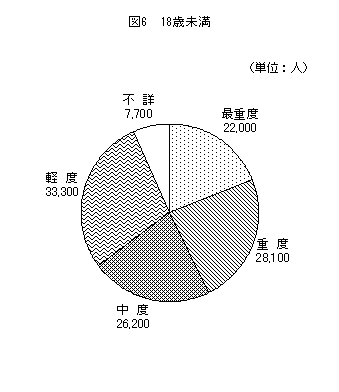 |
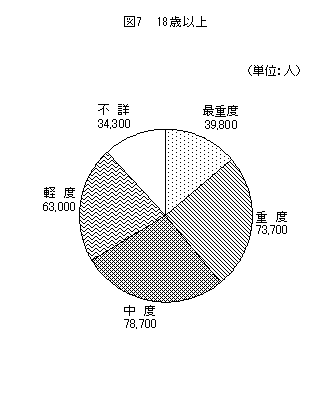 |
○参 考:障害の程度の推移
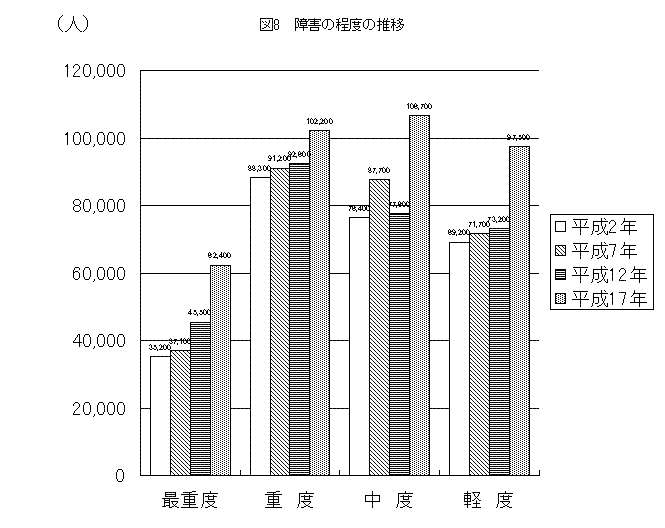
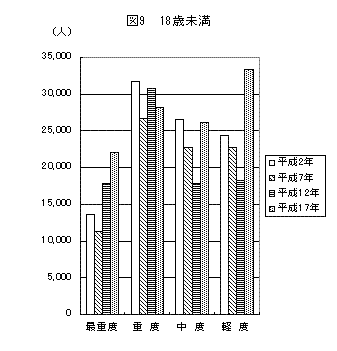 |
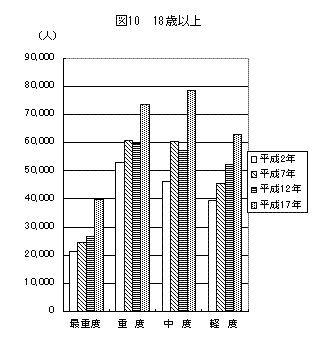 |
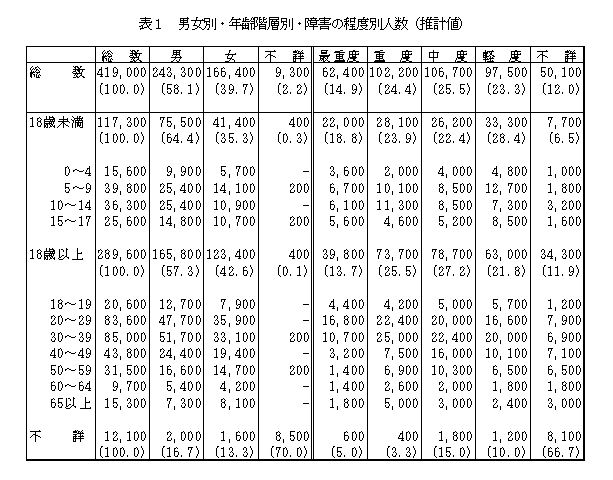
※ 以降は、実際の回答数(有効回答数 2,075件)による集計結果である。
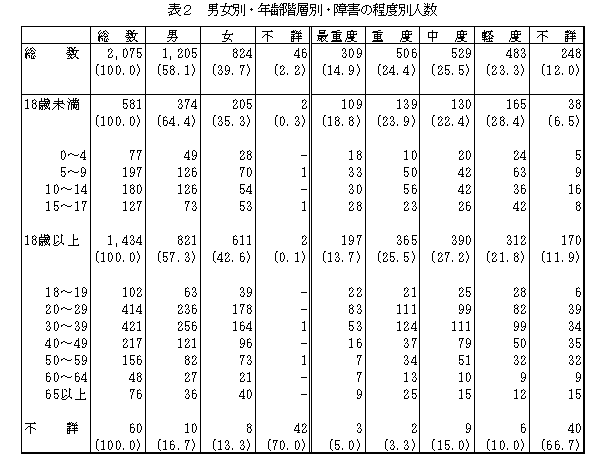
3 保健面、行動面
保健面では身体的健康に厳重な看護が必要な「1度」が3.9%となっている。行動面では行動上の障害が顕著で常時付添い注意が必要な「1度」が7.8%となっている。その他の程度については、「用語の定義」を参照されたい。
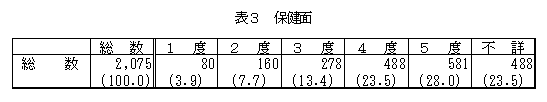
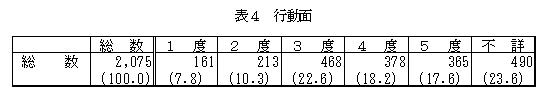
4 生活の場の状況
(1)生活の場の状況
「自分の家やアパートで暮らしている」が、85.7 %となっており、地域における生活の場の大部分を占めている。
18歳以上でみると、「グループホーム」が前回から3.5ポイント増えている。
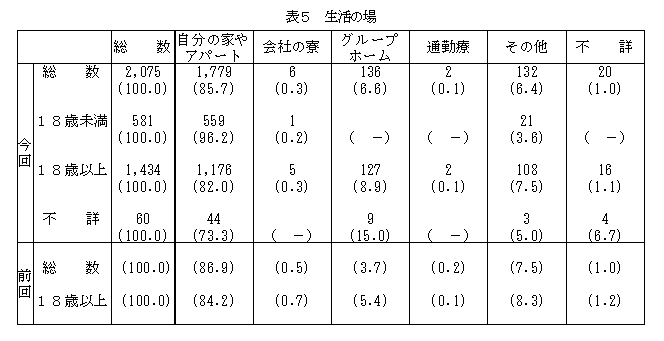
(2)生活同居者
「親、兄弟姉妹と暮らしている」は42.1 %、「親と暮らしている」は34.3 %となっており、親等の家族と暮らしている者は76.3 %となっている。18歳以上では、「ひとりで暮らしている」が5.6 %、「夫婦で暮らしている」が3.1 %となっている。
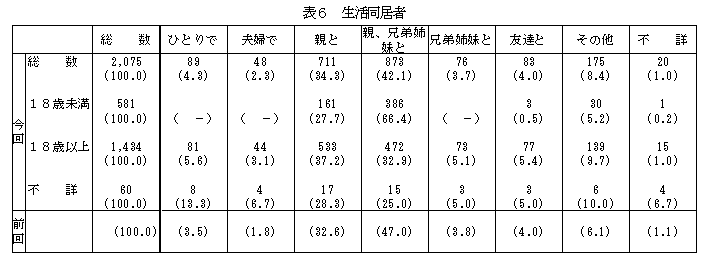
5 将来の生活の場の希望
「親と暮らしたい」「兄弟姉妹と暮らしたい」が合わせて38.5 %となっている。「夫婦で暮らしたい」が12.9 %、「グループホーム」が12.8 %、「施設」が7.5 %となっている。
前回と比較すると、「親と暮らしたい」「施設」等が減少しているのに対し、「ひとりで」「グループホーム」が増えている。
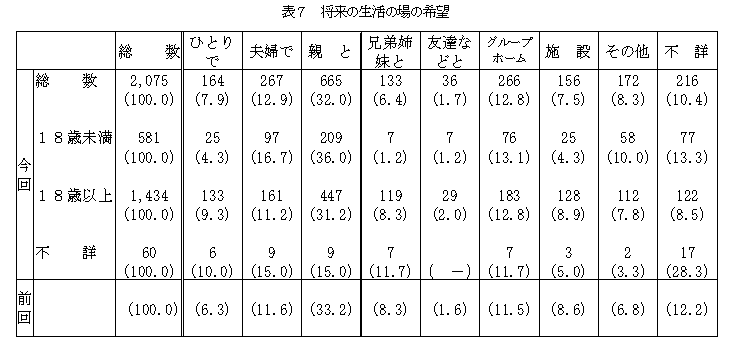
6 日中活動の場の状況
「就学前」では「自分の家」が35.9 %、「就学」では「障害児のための学校」が55.4 %となっている。「卒業」している人では、「作業所」「通所施設」が合わせて46.1 %、「自分の家」が25.0 %、「職場・会社」が17.5 %となっている。
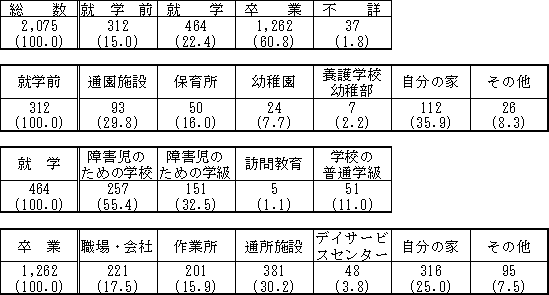
7 将来の日中活動の場の希望
昼間の過ごし方について翌年における希望を聞いたところ、「就学前」では「自分の家」が30.4 %、「就学」では「障害児のための学校」が55.1 %となっている。「卒業」後は、「作業所」「通所施設」が合わせて43.9 %、「職場・会社」が25.4 %、「自分の家」が20.6 %となっている。
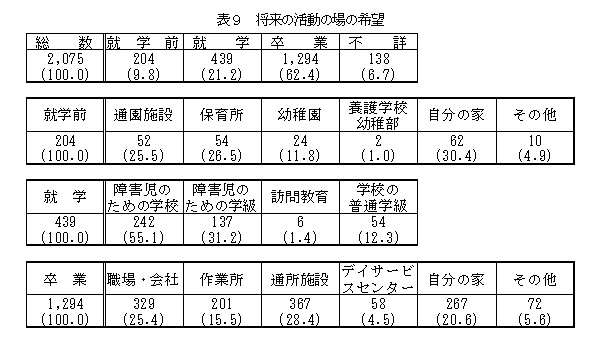
学校を卒業予定及び卒業している者の現在の状況と将来の希望を比較してみると、現在「自分の家」と回答している人のうち25.5%の人が「職場・会社」「作業所」等、外での活動を希望している。また、現在「自分の家」の人のうち14.4%、「作業所」「通所施設」の人についても約1割の人が、「職場・会社」での一般就労を希望している。
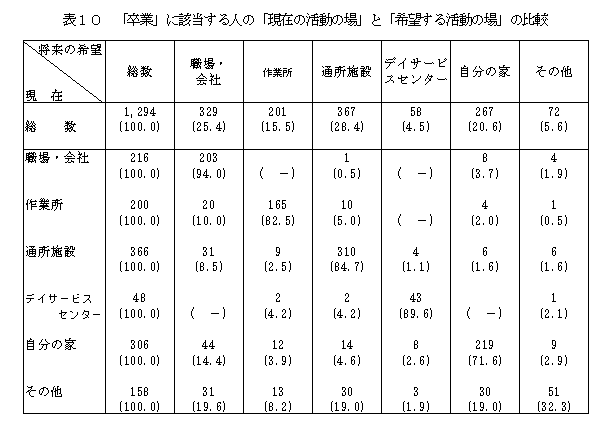
8 外出の状況
(1)ひとりでの外出状況
ひとりでの外出状況をみると、「よく出かける」「時々出かける」が合わせて35.5 %である。
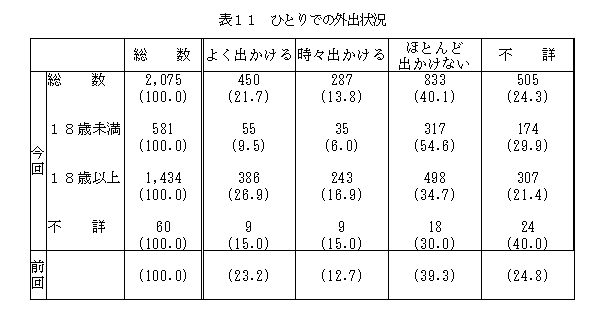
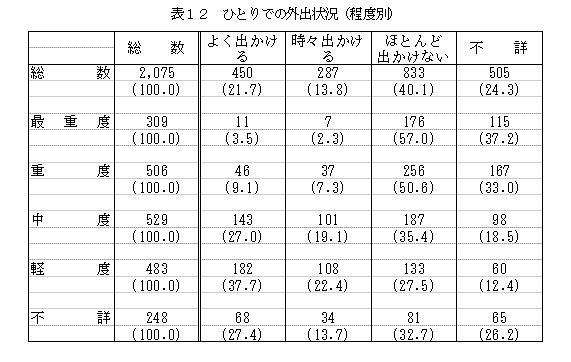
(2)だれかとの外出状況
だれかとの外出状況を見ると、「よく出かける」「時々出かける」が合わせて72.3 %である。
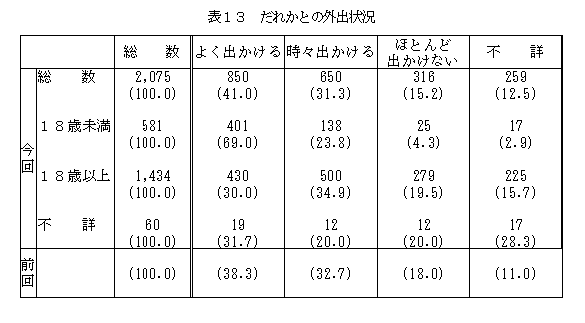
9 地域活動の状況
(1)地域活動への参加状況
「よく参加する」「時々参加する」が合わせて25.9 %であり、「ほとんど参加しない」「参加したことはない」が合わせて67.5 %である。
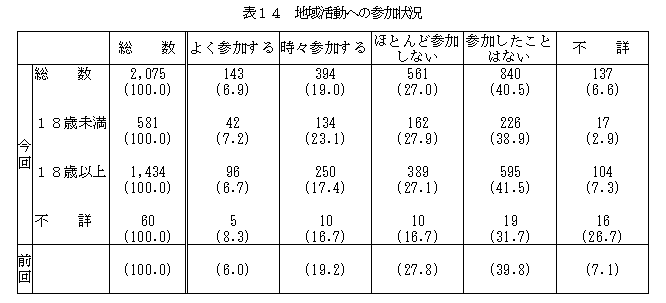 |
||||
|
(2)地域活動不参加者((1)で「ほとんど参加しない」「参加したことはない」と答えた人)の地域活動への参加希望
地域活動不参加者の地域活動の参加希望状況は、「わからない」が36.2 %となっているが、「機会や場所があれば」参加したいが36.2 %である。
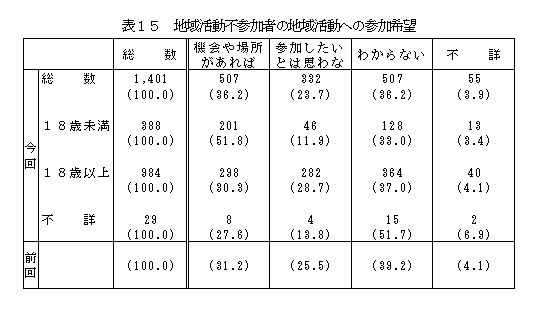
(3)地域活動不参加者の地域活動への参加条件
地域活動不参加者のうち、「いっしょに行ってくれる人がいれば」参加しやすいと答えた者が、32.9 %である。
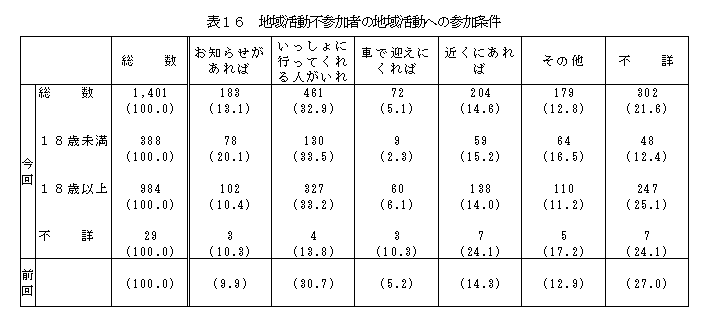
(4)現在学校を卒業している者の地域活動への参加状況
学校を卒業している者の日中活動の場別に、地域活動への参加状況をみると、「自分の家」にいる人のうち、「ほとんど参加しない」「参加したことはない」が合わせて80.0%である。
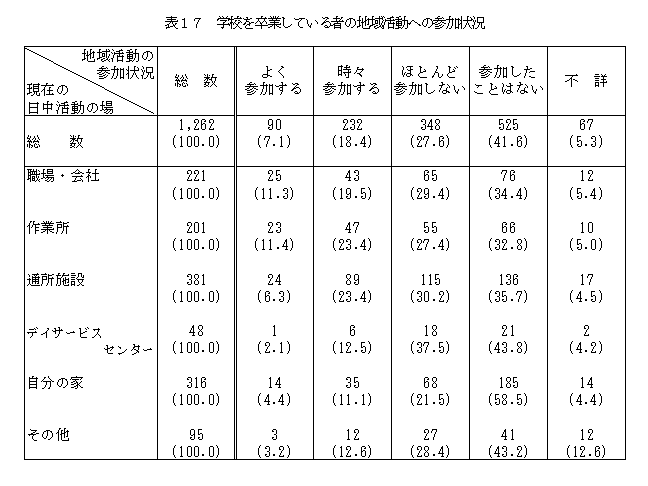
表17で日中活動の場が「自分の家」で地域活動の参加状況が「ほとんど参加しない」「参加したことはない」者のひとりでの外出状況をみると、「よく出かける」「時々出かける」が合わせて45.0%である。一方、「ほとんど出かけない」は39.1%である。
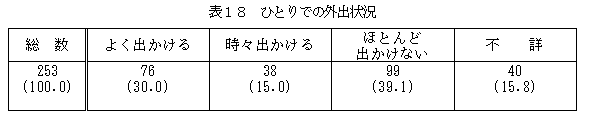
10 相談相手
18歳未満では、「親、祖父母」72.3 %、「会社の人・学校の先生」43.2 %、「医師」21.7 %の順となっている。18歳以上では、「親、祖父母」62.3 %、「施設の職員・グループホームの世話人」38.1 %、「兄弟姉妹」30.8 %の順である。
表19 相談相手
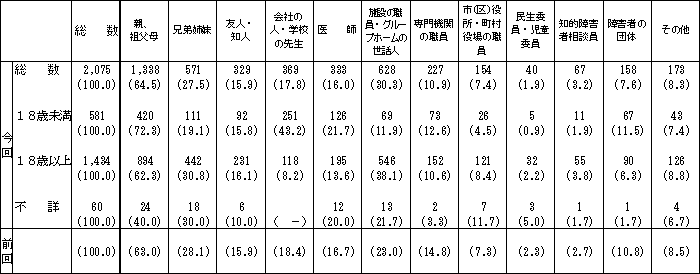 |
| ※3つまでの重複選択 |
11 くらしの充実の希望
(1)福祉行政などに期待すること
前回と同じく「障害者に対する周りの人の理解」が42.1 %と最も多く、次いで「必要な時に施設を利用できる制度」「経済的援助」「相談や指導」となっている。
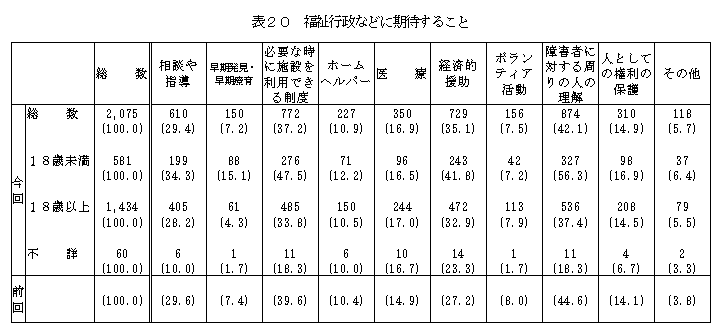 |
| ※3つまでの重複選択 |
(2)働く場所や生活する上で期待すること
「老後の生活」38.8 %、「働く場所」33.4 %、「通所施設」24.6 %の順になっている。
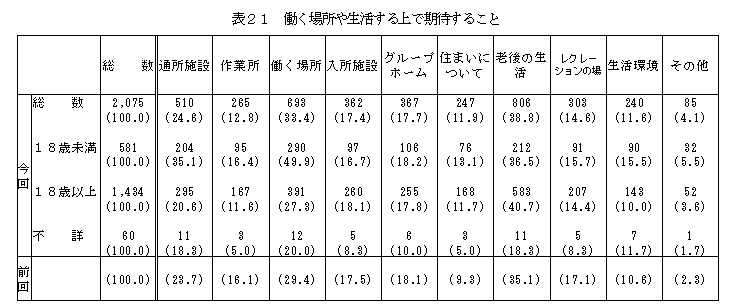 |
| ※3つまでの重複選択 |
12 いやな思いや差別の有無
「いやな思いがある」が前回調査時の56.9%より21.5ポイント減少しているが、依然として35.4%の人が「いやな思いがある」としている。
「いやな思い」の内容を聞いたところ、「じろじろ見られる」「サービスを拒否される」等、視線や態度に関するものが多いが、直接、「差別的なことを言われる」というような内容のものもあった。
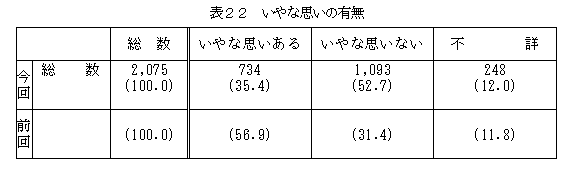
13 仕事をしている人の状況
(1)業務
一般就労や福祉的就労など、仕事をしている者は全体の37.5 %であり、そのうち業務内容をみると、「作業所」が56.5 %、「製造・加工業」が15.7 %、「農畜産業、林業、漁業」が3.9 %となっている。
表23 就労知的障害児(者)の業務
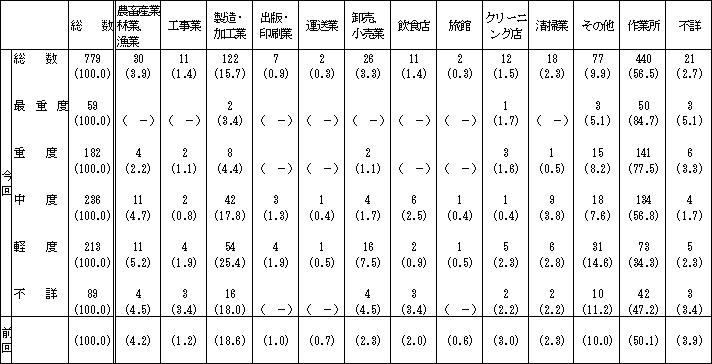 |
| ※作業所は通所施設を含む |
(2)就労形態
「作業所」の58.3 %に次いで、「正規の職員」が15.7 %となっている。
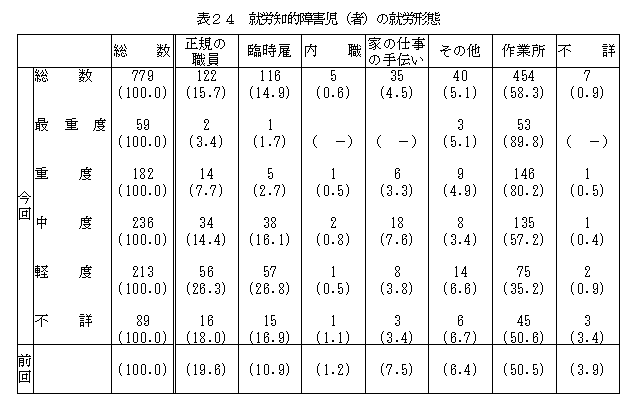 |
(3)就労時間
一日の実働時間(残業を含む)は、「4時間から6時間まで」が44.7 %となっている。
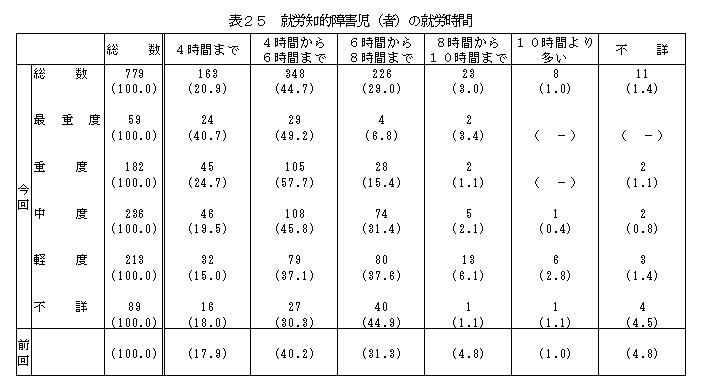
(4)就労日数
1か月の就労日数は、「16日から20日まで」が46.1 %、「21日から25日まで」が36.6 %となっている。
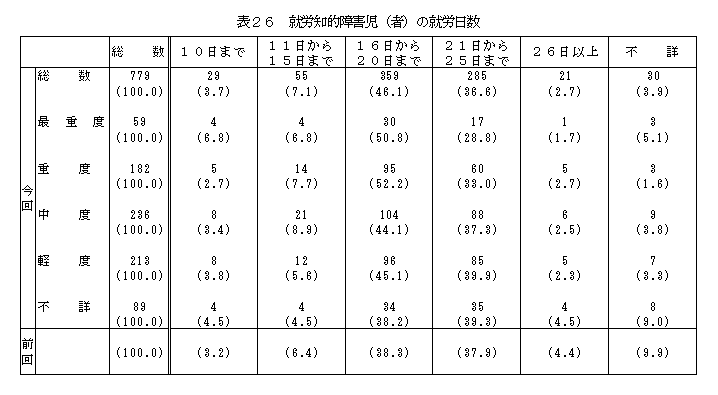
(5)給料
1ヶ月の給料をみると、5万円までが全体の67.3%になる。就労形態別の給料をみると、正規の職員・臨時雇として雇用されている者は「7万円〜10万円まで」が26.1%と最も多く、作業所で働いている者では「1万円まで」が70.7%と最も多い。
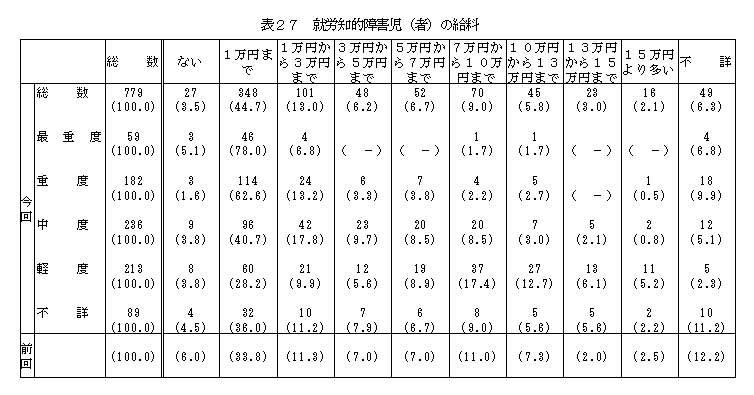
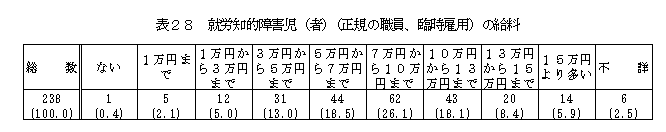
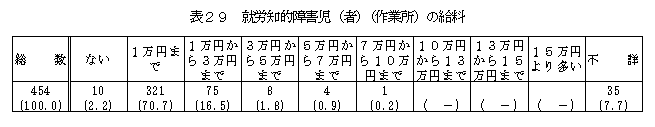
14 手当・年金の受給状況
(1)手当・年金の受給の有無
手当・年金の受給者は、69.4 %となっている。
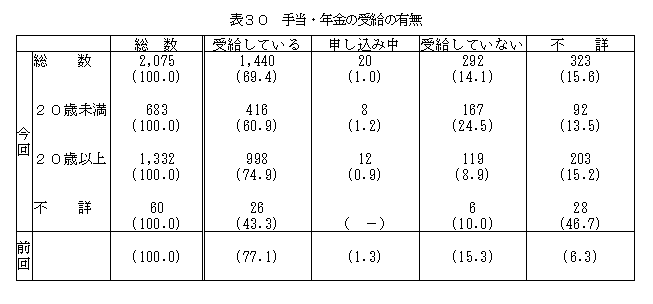
(2)手当・年金不受給者の不受給の理由
手当・年金を受給していない者の理由としては、「障害が軽いため」が50.3 %となっている。
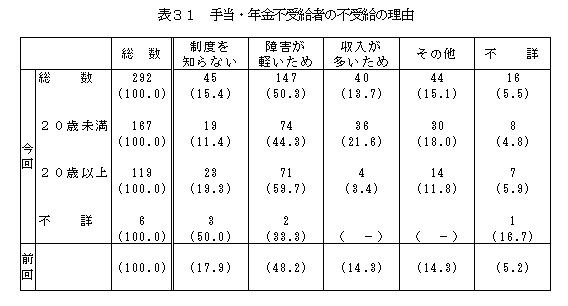
(3)手当・年金受給者の手当・年金の種類
手当・年金受給者の手当・年金の種類をみると、20歳未満では「特別児童扶養手当」が87.7 %、20歳以上では、「障害基礎年金」が89.7 %となっている。
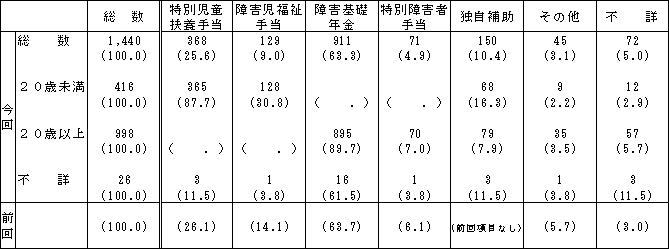
(4)都道府県・市区町村独自の手当・補助受給額
都道府県・市区町村独自の手当・補助受給者は全体の7.2%であり、20歳未満では「5万円まで」が72.1 %、20歳以上では、「5万円まで」が59.5 %となっている。
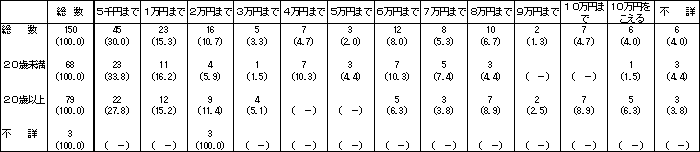
15 親元からの仕送り額
親元から離れて生活している者は全体の12.0%であり、そのうち親元からの仕送り額をみると、20歳未満では「仕送りなし」が85.0 %、20歳以上では、「仕送りなし」が79.5 %となっている。
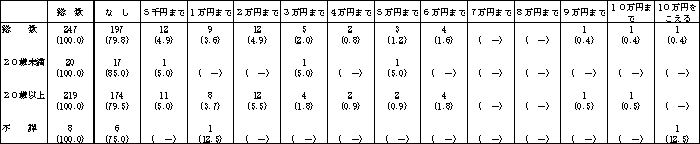
16 診断・判定を受けた時期、機関
(1)診断・判定を受けた時期
「出生直後」から「小学校に入る時」までに、全体では52.6 %、18歳未満では79.0 %の者が「診断・判定を受けた」となっている。
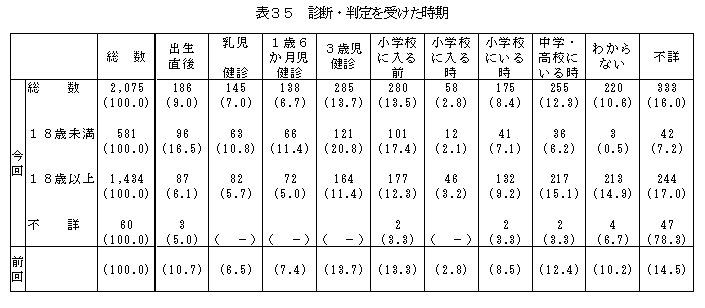
(2)診断・判定を受けた機関
「児童相談所」が38.5 %、「病院」が29.0 %の順になっている。
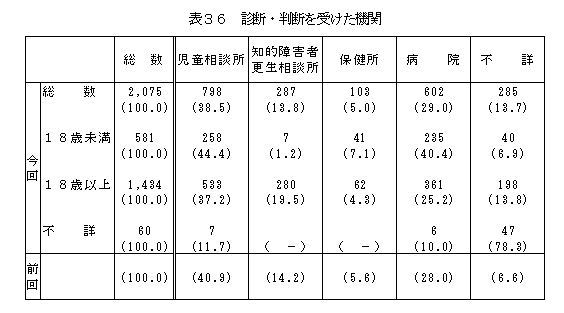
17 療育手帳の所持状況
(1)療育手帳の有無
91.0 %の者が、療育手帳を所持している。
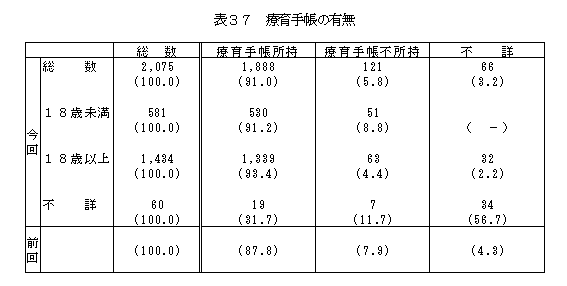
(2)療育手帳の程度
療育手帳所持者の程度別の状況を見ると、「最重度」8.9 %、「重度」34.3 %、「中度」37.2 %そして「軽度」は13.1 %となっている。
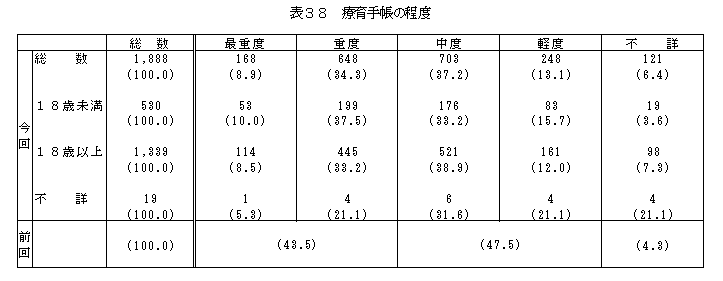
(3)療育手帳の取得年齢
18歳未満の児童では、4歳までに54.9 %の者が手帳を取得している。
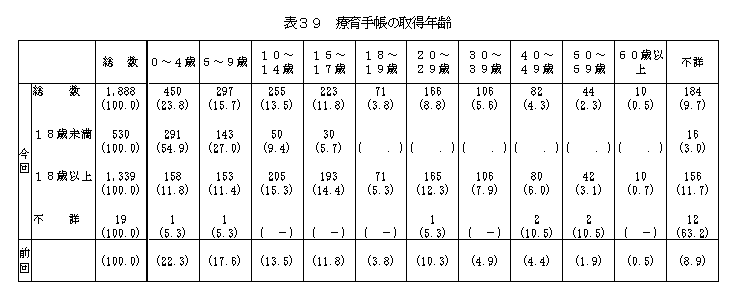
(4)療育手帳不所持者の不所持理由
療育手帳不所持者の主な不所持理由をみると、18歳未満では「その他」が56.9 %、18歳以上では「制度を知らない」が47.6 %となっている。
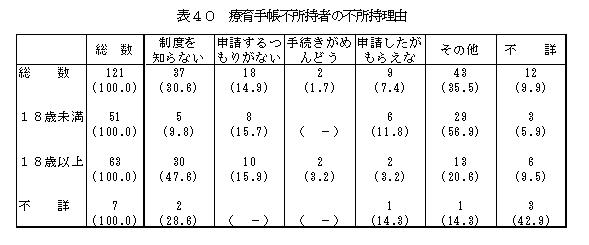
18 身体障害者手帳所持状況等
(1)身体障害の種類
在宅知的障害児(者)の全体の17.1 %が身体障害者手帳を所持している。そのうち、身体障害の種類をみると、「肢体不自由」が68.5 %と最も多い。
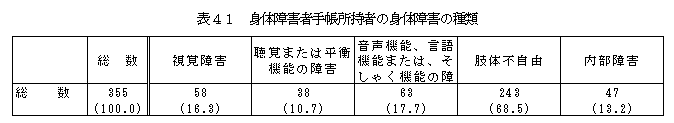
(2)身体障害者手帳の等級
身体障害者手帳の等級をみると、1級と2級を合わせて68.7 %となっている。知的障害の程度別に見ると、最重度の者は、身体障害者手帳の1、2級が87.4 %、重度の者は、1、2級が66.3 %となっている。
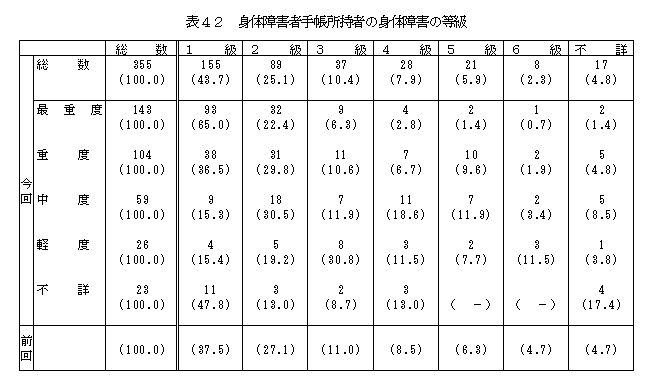
(3)てんかん等の有無
(1)「てんかんがある」者は、在宅知的障害児(者)の11.3%となっている。
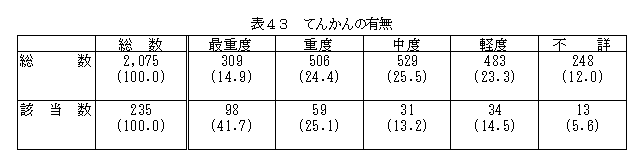
(2)「統合失調症、その他の精神疾患がある」者は、在宅知的障害児(者)の3.2%となっている。
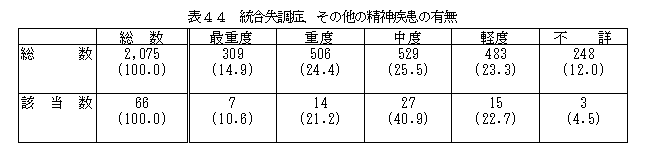
(3)「自閉症がある」者は、在宅知的障害児(者)の9.3%となっている。
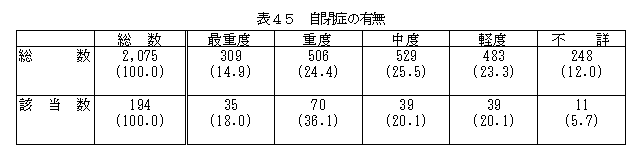
19 精神保健福祉手帳所持状況
「精神保健福祉手帳を所持している」者は、在宅知的障害児(者)の1.7%となっており、そのうち1級が25.0 %、2級が41.7 %となっている。
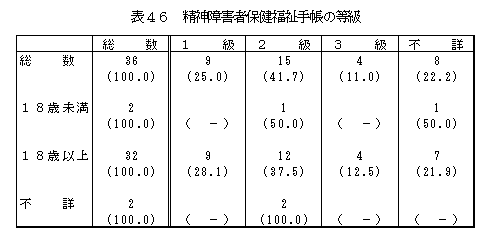
20 精神障害者通院医療公費負担決定の状況
「精神障害者通院医療公費負担決定を受けている」者は、在宅知的障害児(者)の6.8%となっている。
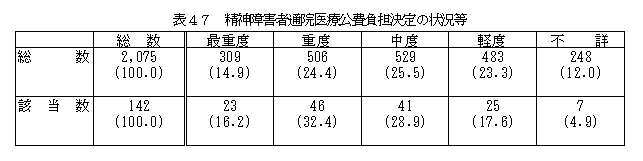
用語の定義
この調査における用語は次のように定義して用いている。
1 知的障害
「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義した。
なお、知的障害であるかどうかの判断基準は、以下によった。
次の(a)及び(b)のいずれにも該当するものを知的障害とする。
(b)「日常生活能力」について
|
|||||||
2 知的障害の程度
以下のものを、基準として用いた。
* 知能水準がI〜IVのいずれに該当するかを判断するとともに、日常生活能力水準がa〜dのいずれに該当するかを判断して、程度別判定を行うものとする。その仕組みは下図のとおりである。
・程度別判定の導き方
|
|||||||||||||
3 保健面・行動面について
保健面・行動面について「保健面・行動面の判断」によって、それぞれの程度を判定し、程度判定に付記するものとした。
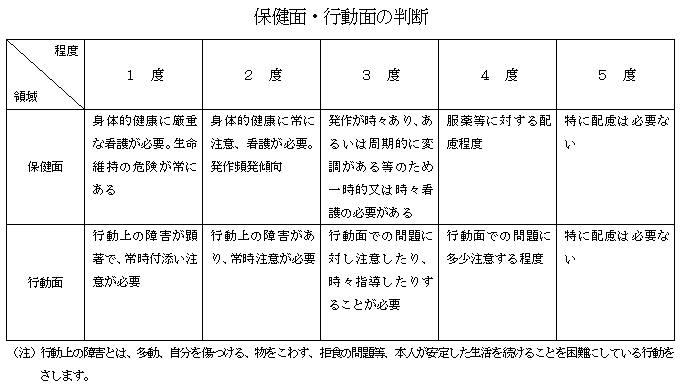 |