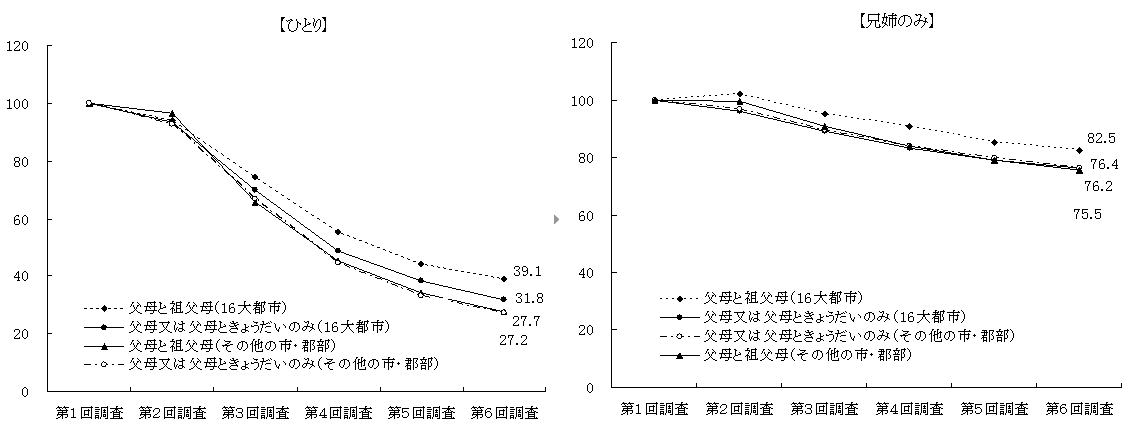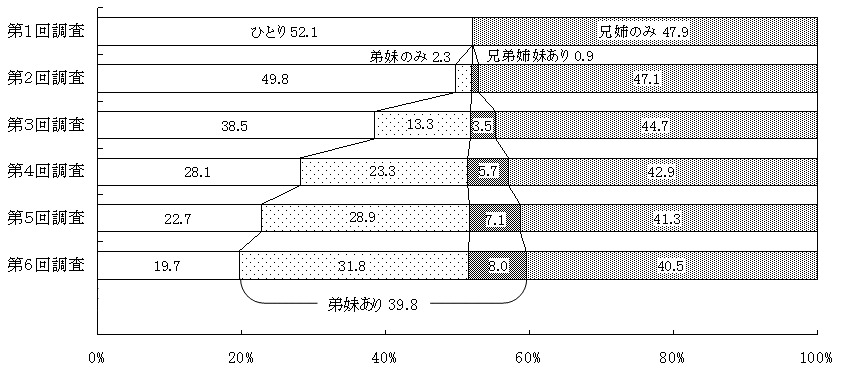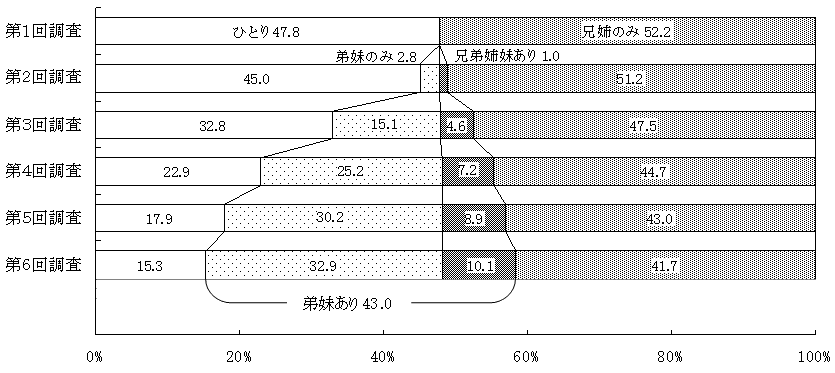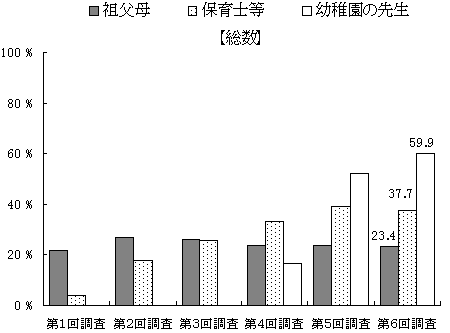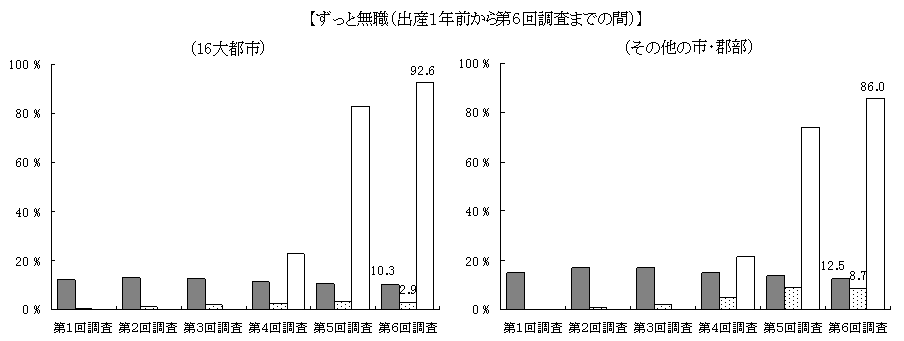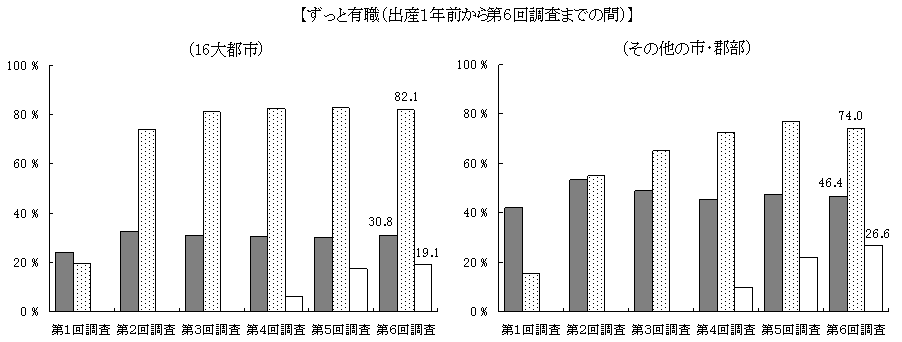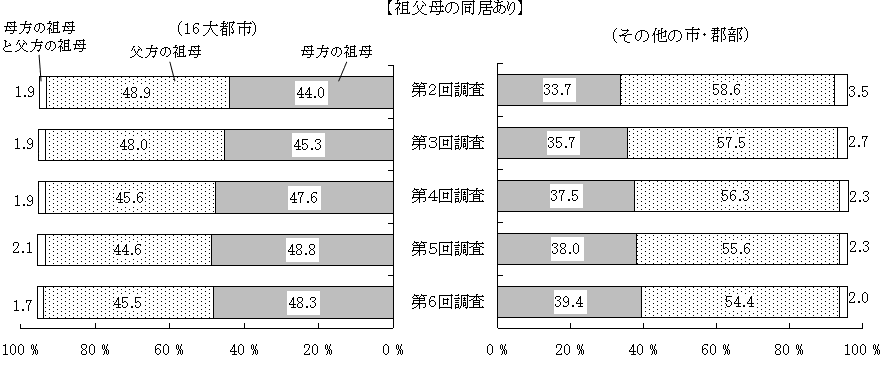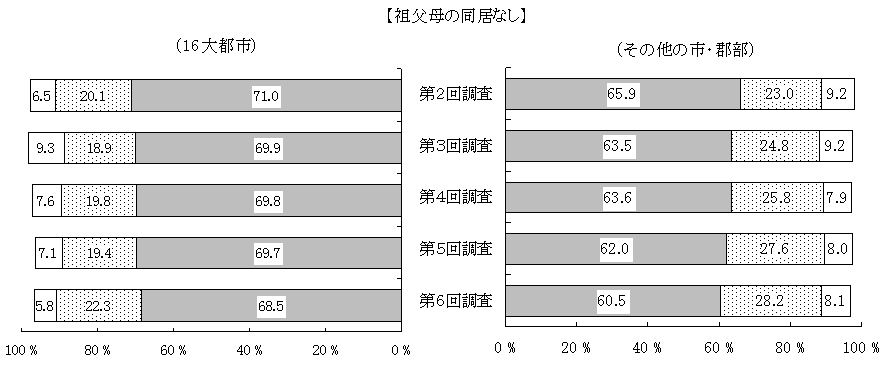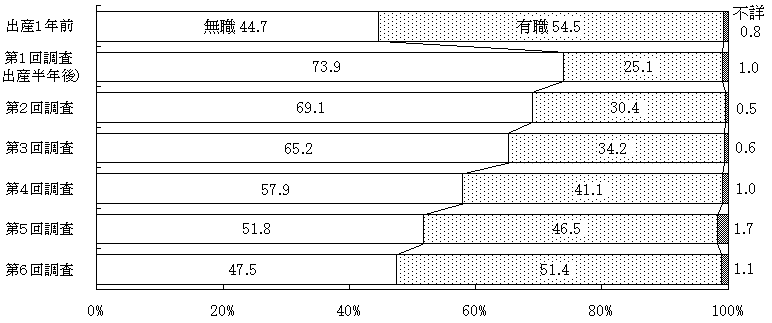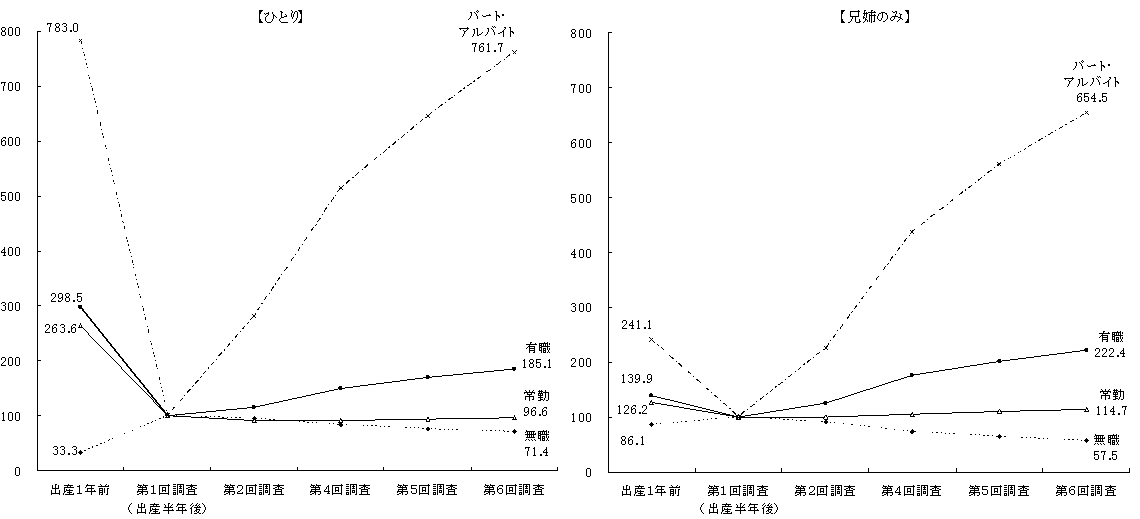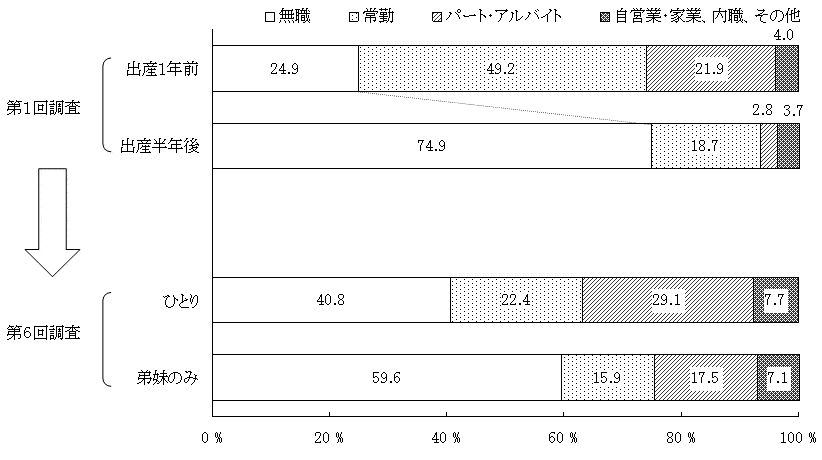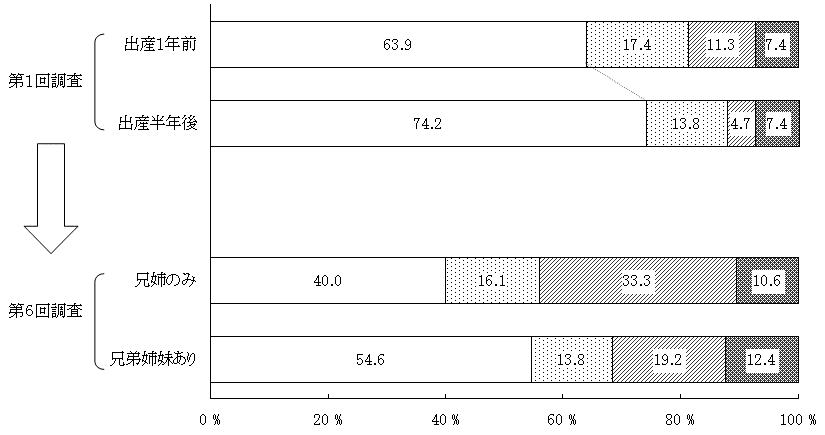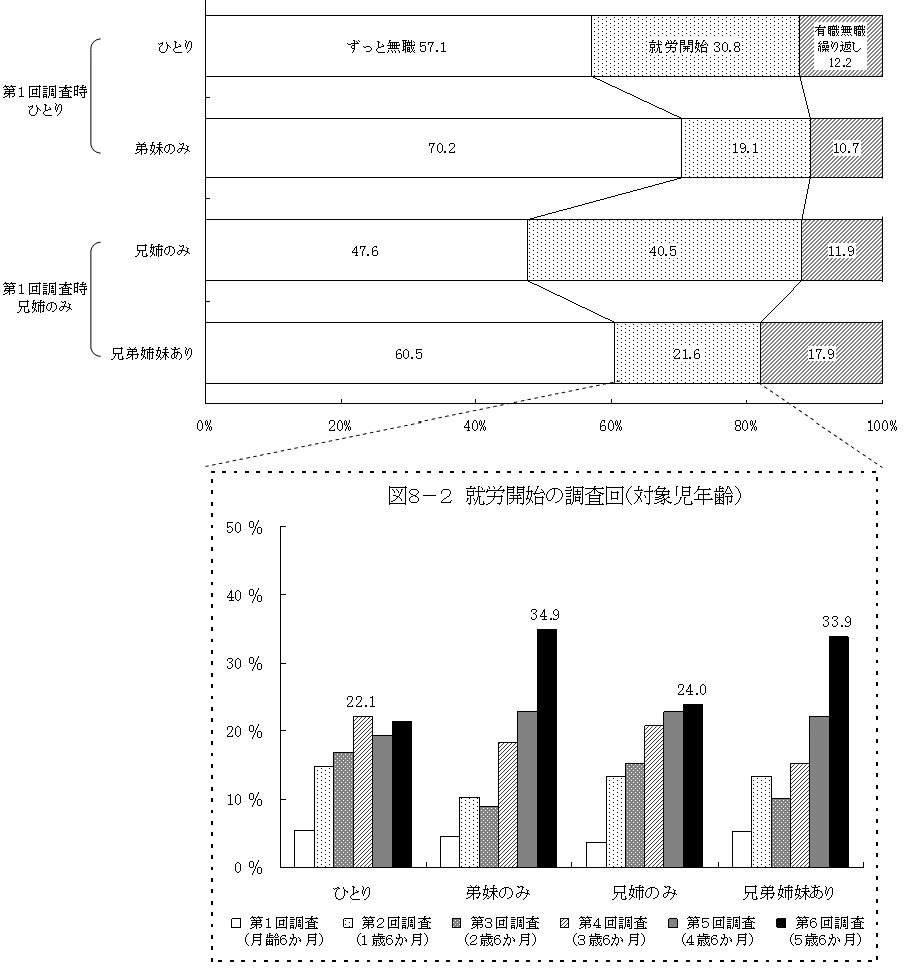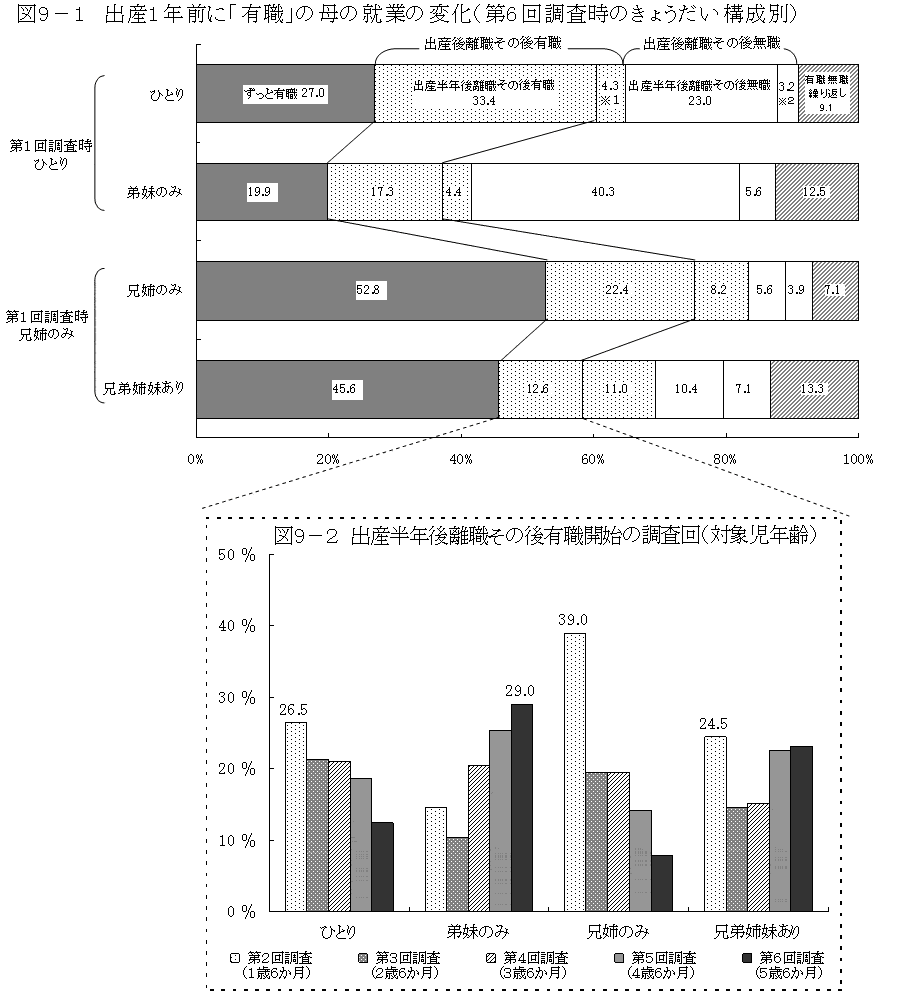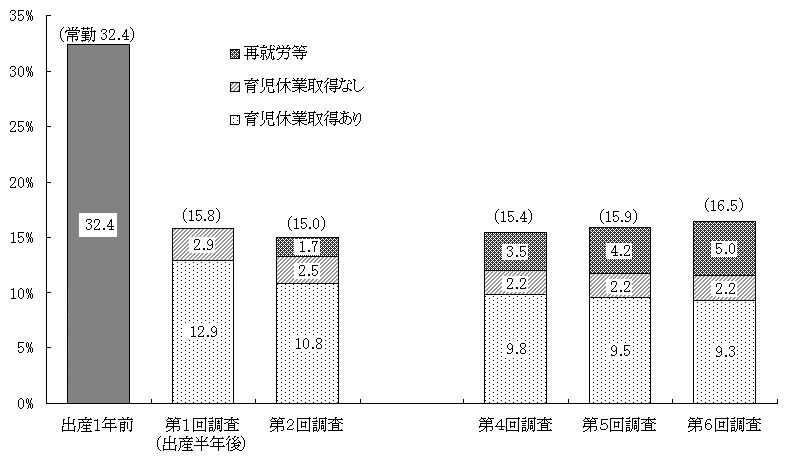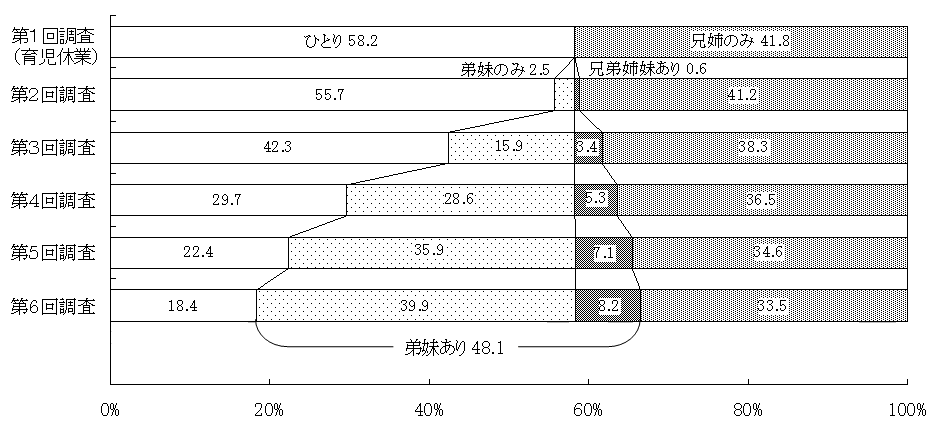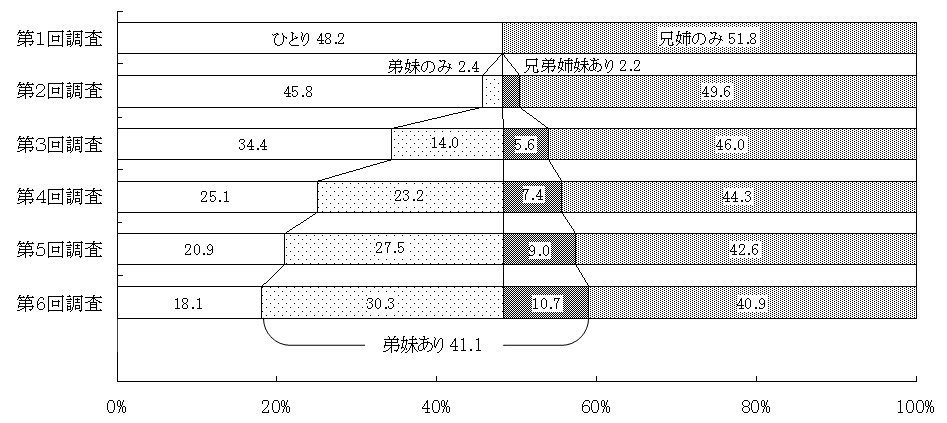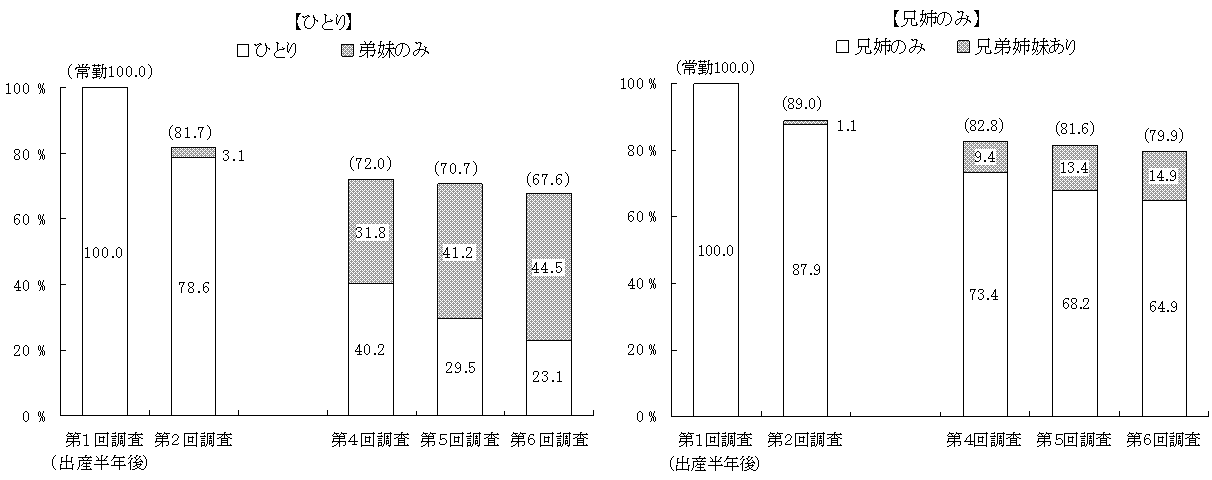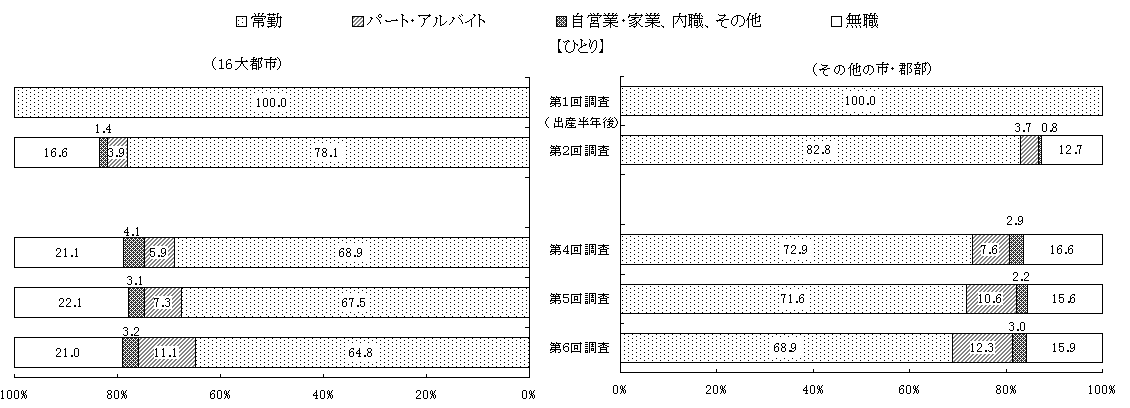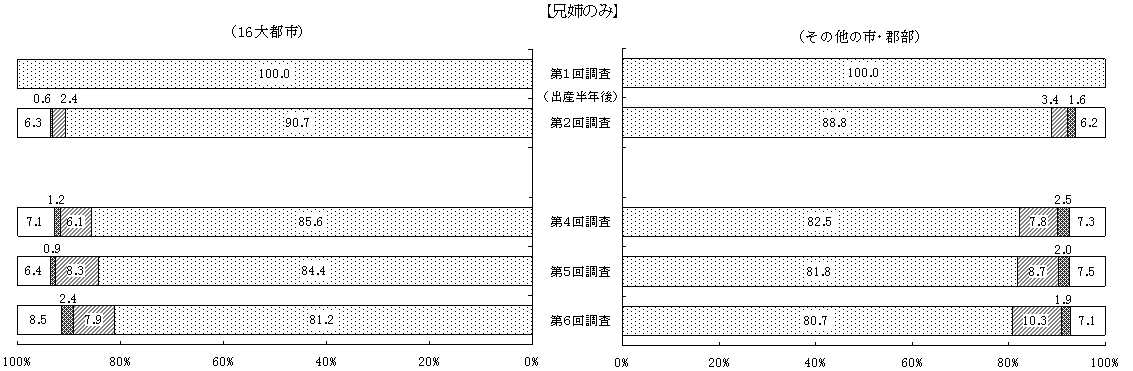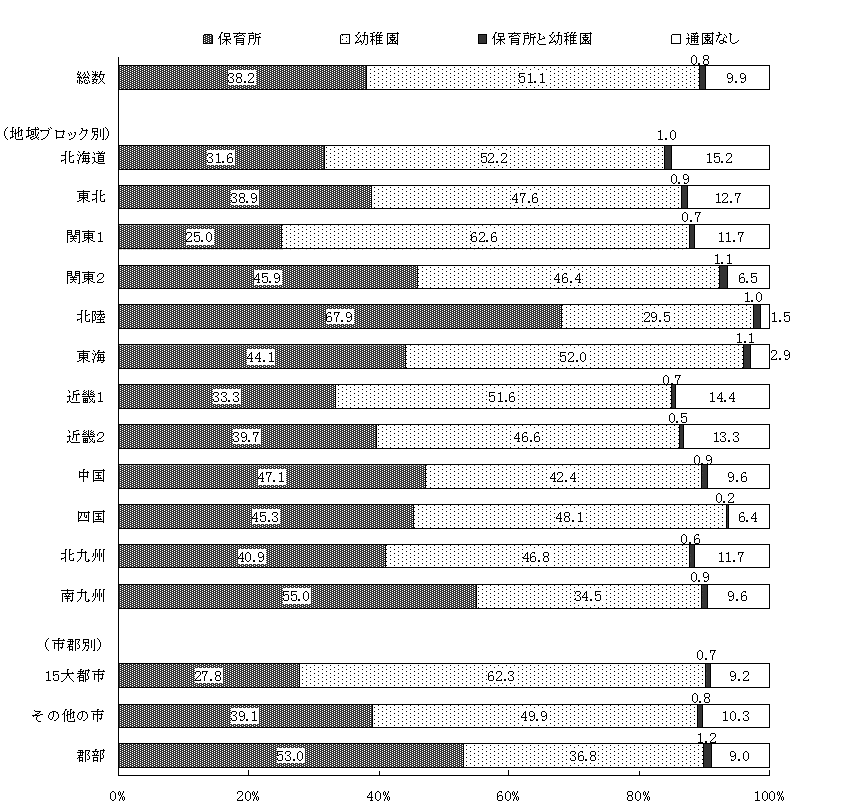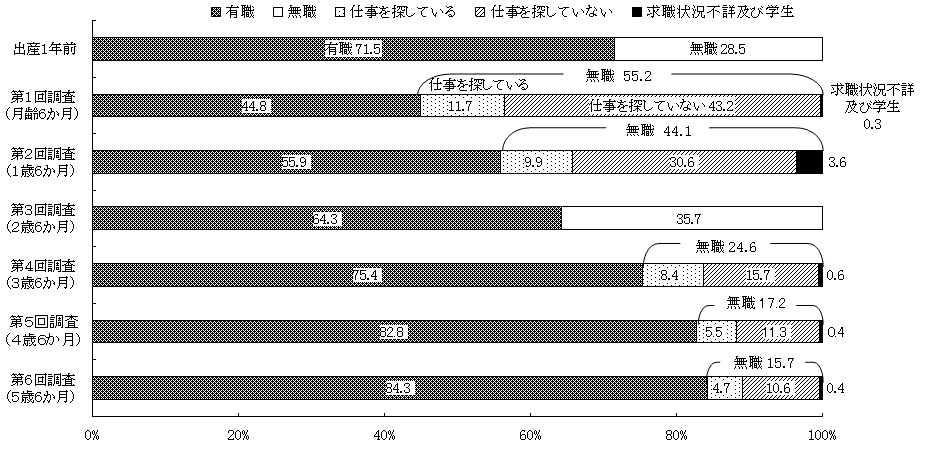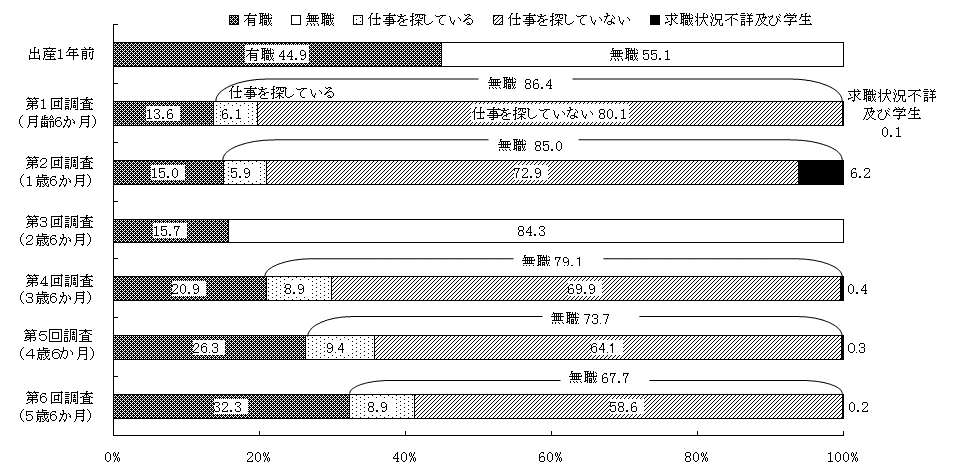結果の概要
1 家族の状況
(1) 同居者の構成
第1回調査時を基準として、主な同居者構成の変化をみると、「16大都市」では「父母又は父母ときょうだいのみ」は第6回調査までに年々減少しており、「父母と祖父母」が微増の傾向にある。一方、「その他の市・郡部」は「父母又は父母ときょうだいのみ」は「16大都市」と同様に第6回調査までに年々減少しているが、「父母と祖父母」の変化はそれほどみられない。(表1)
表1 主な同居者構成の変化(指数:第1回調査=100)
| |
第1回調査
(月齢6か月) |
第2回調査
(1歳6か月) |
第3回調査
(2歳6か月) |
第4回調査
(3歳6か月) |
第5回調査
(4歳6か月) |
第6回調査
(5歳6か月) |
| |
(単位:%) |
総数 |
| 総数 |
(100.0) |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
| 父母と同居 |
(98.2) |
100.0 |
99.1 |
98.2 |
97.2 |
96.1 |
95.1 |
| 父母又は父母ときょうだいのみ |
(77.4) |
100.0 |
98.1 |
96.9 |
96.1 |
95.0 |
93.9 |
| (再掲)ひとり |
(38.8) |
100.0 |
93.0 |
67.8 |
46.0 |
34.8 |
28.6 |
| (再掲)兄姉のみ |
(38.6) |
100.0 |
96.6 |
89.4 |
84.0 |
79.8 |
76.6 |
| 父母と祖父母 |
(20.5) |
100.0 |
103.2 |
102.6 |
101.7 |
100.5 |
99.7 |
| (再掲)ひとり |
(8.7) |
100.0 |
96.2 |
66.8 |
46.7 |
35.4 |
29.2 |
| (再掲)兄姉のみ |
(11.8) |
100.0 |
100.0 |
91.2 |
84.7 |
80.0 |
76.3 |
| 父母とその他 |
(0.4) |
100.0 |
94.9 |
108.1 |
94.9 |
86.8 |
91.2 |
| 父又は母と同居 |
(1.7) |
100.0 |
148.1 |
203.6 |
256.0 |
313.5 |
366.7 |
| その他 |
(0.0) |
100.0 |
242.9 |
228.6 |
257.1 |
771.4 |
1200.0 |
| |
|
16大都市 |
| 総数 |
(100.0) |
100.0 |
98.9 |
97.7 |
96.9 |
96.8 |
96.5 |
| 父母と同居 |
(98.3) |
100.0 |
98.1 |
96.2 |
94.3 |
93.4 |
92.0 |
| 父母又は父母ときょうだいのみ |
(87.5) |
100.0 |
97.6 |
95.4 |
93.2 |
92.2 |
90.6 |
| (再掲)ひとり |
(46.1) |
100.0 |
93.4 |
70.0 |
48.9 |
38.3 |
31.8 |
| (再掲)兄姉のみ |
(41.4) |
100.0 |
95.9 |
89.1 |
83.3 |
79.2 |
76.4 |
| 父母と祖父母 |
(10.5) |
100.0 |
102.3 |
102.8 |
103.5 |
103.8 |
104.5 |
| (再掲)ひとり |
(4.7) |
100.0 |
94.2 |
74.4 |
55.4 |
44.1 |
39.1 |
| (再掲)兄姉のみ |
(5.8) |
100.0 |
101.8 |
95.0 |
90.7 |
85.3 |
82.5 |
| 父母とその他 |
(0.3) |
100.0 |
100.0 |
111.1 |
100.0 |
74.1 |
77.8 |
| 父又は母と同居 |
(1.6) |
100.0 |
144.6 |
186.3 |
252.5 |
299.3 |
357.6 |
| その他 |
(0.0) |
100.0 |
366.7 |
166.7 |
100.0 |
266.7 |
566.7 |
| |
|
その他の市・郡部 |
| 総数 |
(100.0) |
100.0 |
100.3 |
100.5 |
100.7 |
100.6 |
100.7 |
| 父母と同居 |
(98.2) |
100.0 |
99.4 |
98.6 |
97.8 |
96.6 |
95.7 |
| 父母又は父母ときょうだいのみ |
(74.2) |
100.0 |
98.2 |
97.3 |
96.8 |
95.6 |
94.6 |
| (再掲)ひとり |
(36.4) |
100.0 |
92.7 |
66.6 |
44.6 |
33.2 |
27.2 |
| (再掲)兄姉のみ |
(37.8) |
100.0 |
96.8 |
89.4 |
83.9 |
79.7 |
76.2 |
| 父母と祖父母 |
(23.6) |
100.0 |
103.3 |
102.6 |
101.4 |
100.0 |
99.0 |
| (再掲)ひとり |
(9.9) |
100.0 |
96.5 |
65.7 |
45.4 |
34.1 |
27.7 |
| (再掲)兄姉のみ |
(13.7) |
100.0 |
99.7 |
90.7 |
83.9 |
79.2 |
75.5 |
| 父母とその他 |
(0.4) |
100.0 |
93.6 |
107.3 |
92.7 |
87.2 |
92.7 |
| 父又は母と同居 |
(1.8) |
100.0 |
149.1 |
208.6 |
256.6 |
316.8 |
368.8 |
| その他 |
(0.0) |
100.0 |
150.0 |
275.0 |
375.0 |
1150.0 |
1675.0 |
注:1)第1回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数35,785)を集計。
2)第1回調査の( )は縦構成比である。
3)(再掲)ひとり、兄姉のみは、第1回調査時のきょうだい構成をとりあげ、第2回調査以降の弟妹のみ、兄弟姉妹ありは表章していない。
4)「16大都市」は、第1回調査から第5回調査までの住所地を、第6回調査時の「16大都市」の地域に区分した。
調査対象児の第6回調査時における住所地は以下のとおりである。
「16大都市」 東京都区部、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市
「その他の市・郡部」 16大都市以外の市及び郡部
5)総数には同居者構成「不詳」、外国在住分を含む。
(2) きょうだいの構成
きょうだい構成の変化をみると、第1回調査時のきょうだい構成「ひとり」は、「その他の市・郡部」では年を重ねるごとに弟妹が生まれる割合が「16大都市」より高く、「ひとり」の割合が少ない。一方、第1回調査時に「兄姉のみ」では、「ひとり」と比べ変化は少ないが、「その他の市・郡部」では「16大都市」に比べ「兄弟姉妹あり」の割合が高くなっている。(図1、図2)
|
図1 主な同居者構成別にみたきょうだい構成の変化(指数:第1回調査=100)
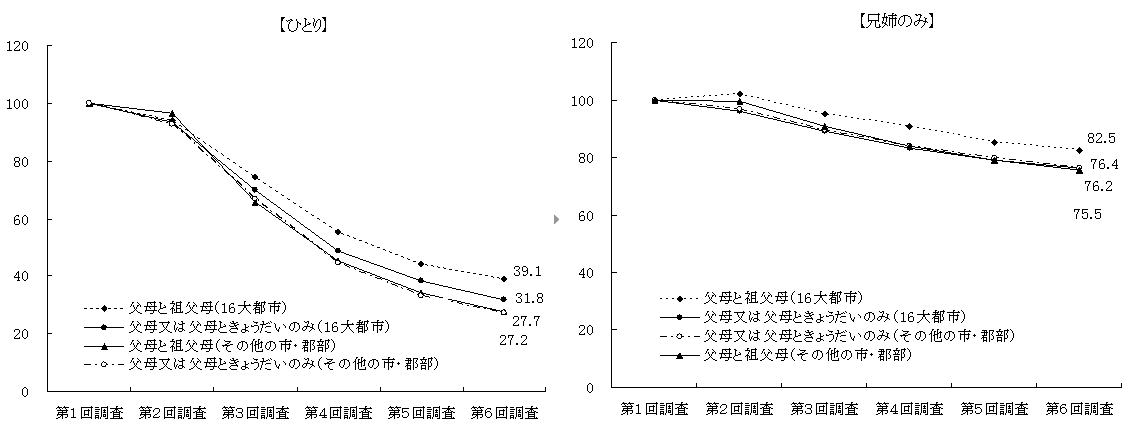
注:1)第1回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数 35,785)を集計。
2)「16大都市」は、第1回調査から第5回調査までの住所地を、第6回調査時の「16大都市」の地域に区分した。
|
図2 きょうだい構成の変化
【16大都市】
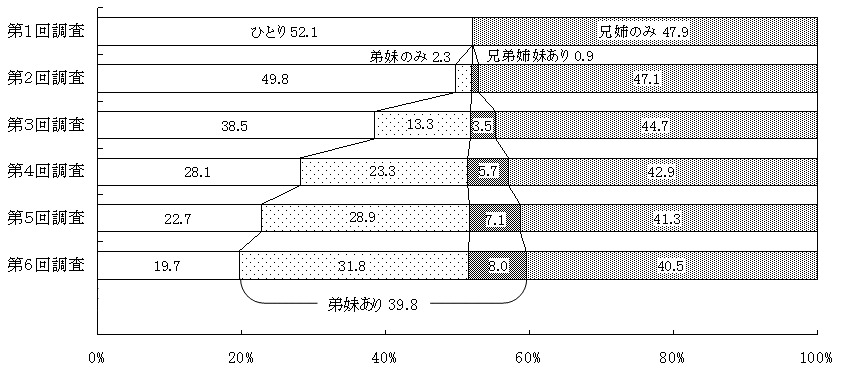
【その他の市・郡部】
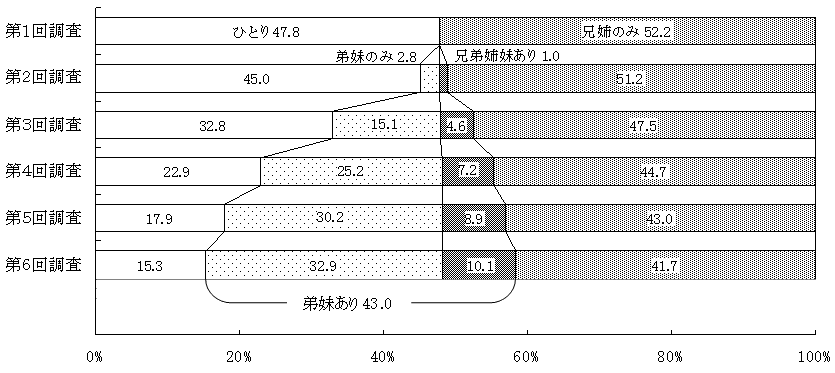
注:1)第1回調査から第6回調査まで回答を得た、きょうだい構成の「不詳」を除く者(総数 35,634)を集計。
2)「16大都市」は、第1回調査から第5回調査までの住所地を、第6回調査時の「16大都市」の地域に区分した。
|
(3) 保育者
ア ふだんの保育者
母の就業の有無別に父母以外のふだんの保育者(複数回答)をみると、「ずっと無職」(出産1年前から第6回調査までの間)は、「16大都市」で第5回調査から「幼稚園の先生」の割合が高くなり、第6回調査では9割を超えて「幼稚園の先生」となっている。「その他の市・郡部」においても「16大都市」と同様に「幼稚園の先生」が第5回調査から高くなっているが、「保育士等」の割合もわずかであるが高くなっている。
「ずっと有職」(出産1年前から第6回調査までの間)は「ずっと無職」に比べ「祖父母」、「保育士等」の割合が全体で高くなっている。特に「16大都市」では第2回調査以降の「保育士等」の割合が7割を超え、「その他の市・郡部」では「祖父母」の割合が各回で4割を超えている。(図3)
図3 母の就業の有無別にみたふだんの保育者(複数回答)の変化
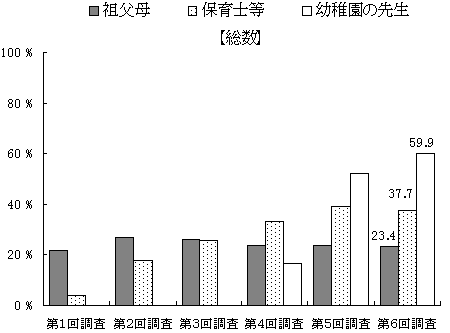
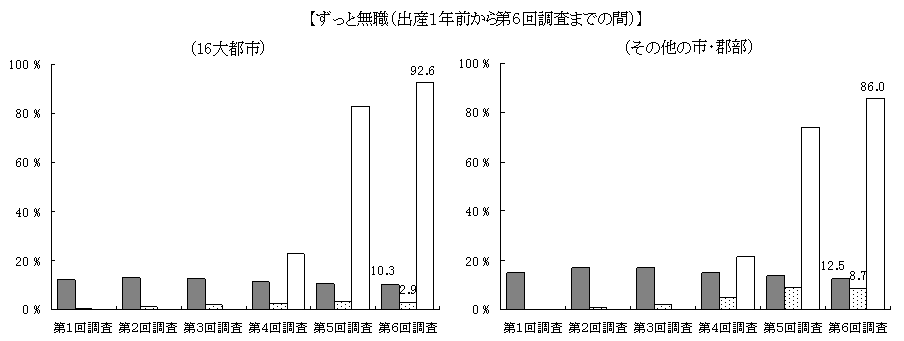
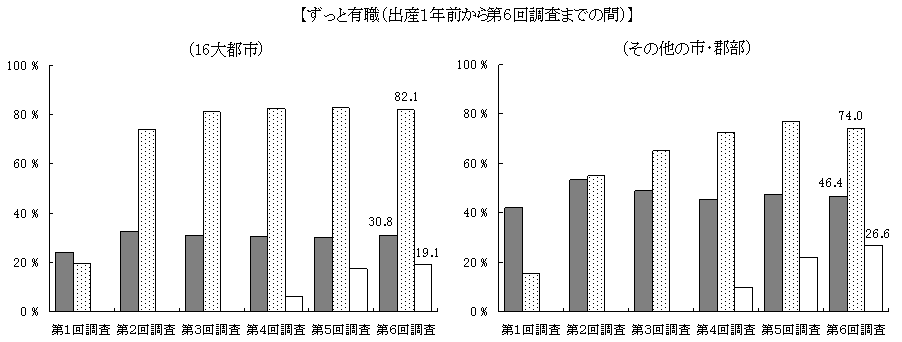
注:1)母と同居している、第1回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数 35,363)を集計。
2)ふだんの保育者のうち「母」、「父」、「その他」は表章していない。
3)「保育士等」には「保育所・託児所の保育士など」「保育ママさんやベビーシッター」を含む。
4)「16大都市」は、第1回調査から第5回調査までの住所地を、第6回調査時の「16大都市」の地域に区分した。
|
イ 祖父母
祖父母の同居の有無別に祖父母の保育状況をみると、「16大都市」では同居の割合が低いが、「祖父母の同居あり」のうち「ふだんの保育者」の割合が、「その他の市・郡部」に比べ第3回調査以降、若干であるが高い傾向にある。一方「祖父母の同居なし」では「その他の市・郡部」が「16大都市」に比べ高くなっている。(表2)
ふだんの保育者(複数回答)が祖父母のうち「祖母」についてみると、「祖父母の同居あり」では「16大都市」が第2回、第3回調査では、「父方の祖母」(対象児の父の母親)の割合が高いが、第4回調査以降は「母方の祖母」(対象児の母の母親)の割合が高くなっており、「その他の市・郡部」では、いずれの回でも「父方の祖母」の割合が高い。一方「祖父母の同居なし」では、「16大都市」、「その他の市・郡部」いずれにおいても「母方の祖母」の割合が高く、また「祖父母の同居あり」に比べ「母方の祖母と父方の祖母」が高くなっている。(図4)
|
表2 祖父母の同居の有無、ふだんの保育者(複数回答)が「祖父母」の割合
(単位:%)
| |
祖父母の
同居あり
(総数) |
16大都市 |
その他の市・郡部 |
| 祖父母の同居あり |
祖父母の同居なし |
祖父母の同居あり |
祖父母の同居なし |
| |
ふだんの保育者 |
|
ふだんの保育者 |
|
ふだんの保育者 |
|
ふだんの
保育者 |
| 第1回調査 |
21.5 |
11.3 |
56.3 |
88.7 |
9.7 |
24.7 |
58.0 |
75.2 |
12.6 |
| 第2回調査 |
22.7 |
12.1 |
63.6 |
87.9 |
12.8 |
25.9 |
63.8 |
74.1 |
17.6 |
| 第3回調査 |
23.0 |
12.3 |
61.1 |
87.7 |
13.0 |
26.2 |
59.6 |
73.8 |
17.2 |
| 第4回調査 |
23.1 |
13.0 |
59.0 |
87.0 |
11.5 |
26.2 |
56.7 |
73.8 |
15.1 |
| 第5回調査 |
23.1 |
13.1 |
57.0 |
86.9 |
11.7 |
26.2 |
55.7 |
73.8 |
15.3 |
| 第6回調査 |
23.3 |
13.4 |
57.0 |
86.6 |
11.2 |
26.4 |
55.7 |
73.6 |
14.9 |
|
注:1)第1回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数35,785)を集計。
2)総数には外国在住分を含む。
3)「16大都市」は、第1回調査から第5回調査までの住所地を、第6回調査時の「16大都市」の地域に区分した。
4)「祖父母の同居あり」、「祖父母の同居なし」は総数に対する割合。
5)「ふだんの保育者」は、「祖父母の同居あり」、「祖父母の同居なし」に対する割合。
図4 祖父母の同居の有無、ふだんの保育者(複数回答)が祖父母のうち「祖母」の割合
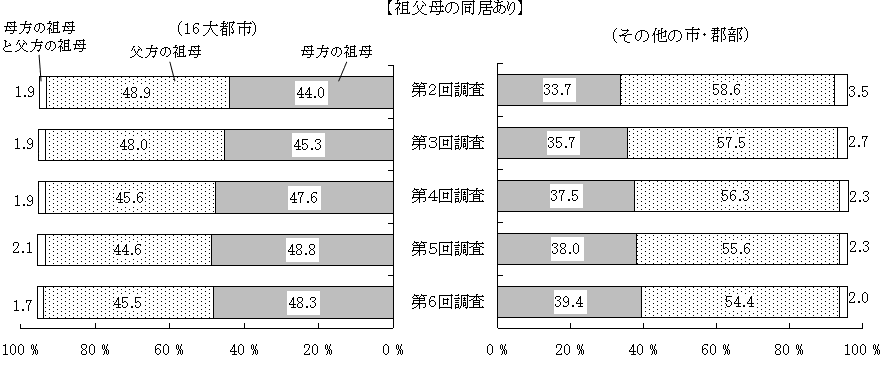
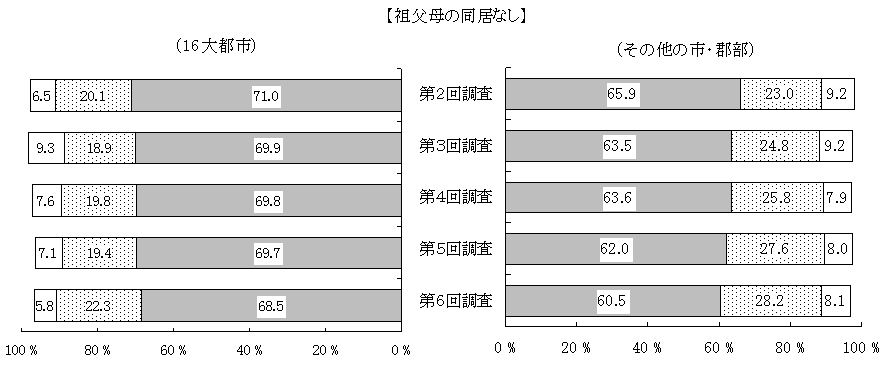
注:1)第1回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数 35,785)を集計。
2)第1回調査のふだんの保育者「祖父母」は「母方」と「父方」を区分して調査していない。
3)ふだんの保育者「祖父母」のうち、「祖父のみ」は表章していない。
4)「16大都市」は、第1回調査から第5回調査までの住所地を、第6回調査時の「16大都市」の地域に区分した。
|
(4) 母の就業状況
ア 就業の有無
出産1年前に54.5%であった母の「有職」の割合は、第1回調査(出産半年後)で25.1%と減少したが、年々増加して第6回調査では51.4%となり、出産1年前に近づきつつある(図5)。
図5 母の就業の有無の変化
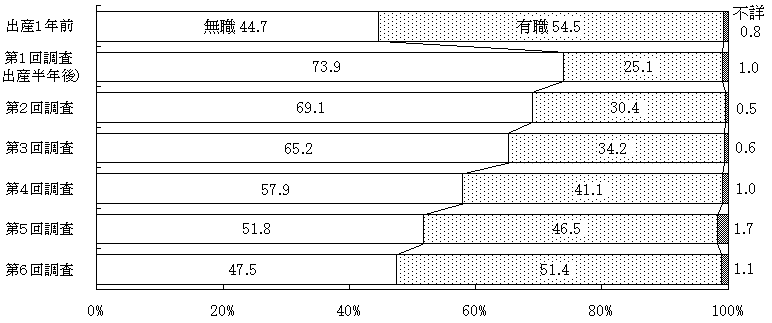
注:母と同居している、第1回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数 35,363)を集計。
イ きょうだい構成別にみた母の就業状況の変化
第1回調査時のきょうだい構成別に母の就業状況の変化を指数(出産半年後=100)でみると、「ひとり」では「パート・アルバイト」が出産1年前の指数が783.0となっており、第6回調査(指数761.7)で出産1年前の値に近づきつつあるが、「有職」では第6回調査においても出産1年前の値に達していない。一方の「兄姉のみ」では「パート・アルバイト」が出産1年前の指数が241.1となっており、第6回調査(指数654.5)においては出産1年前の約2.7倍となり、「有職」でも第4回調査以降で出産1年前より高く推移している。(図6)
図6 第1回調査時のきょうだい構成別にみた母の就業状況の変化
(指数:第1回調査(出産半年後)=100)
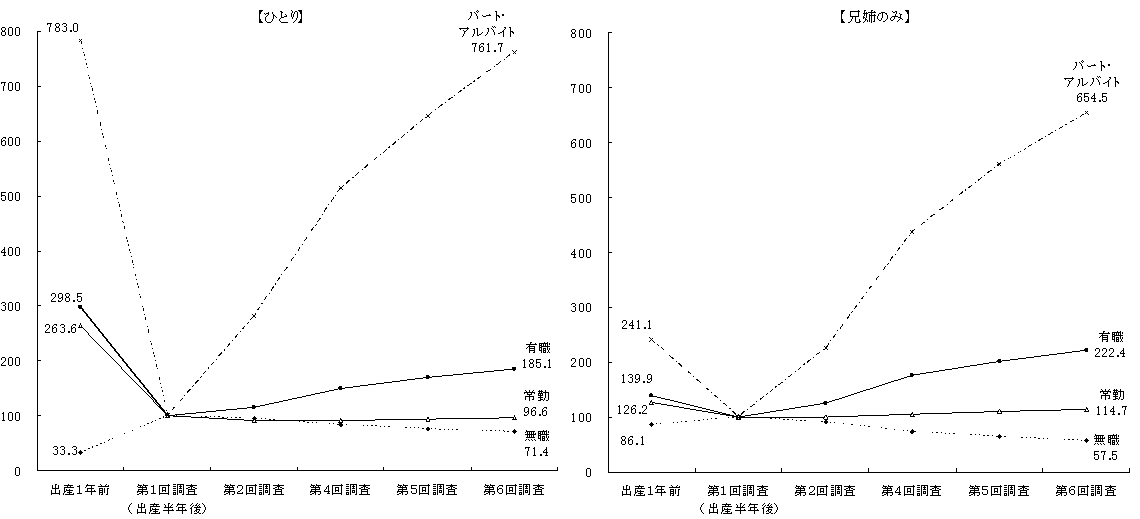
注:1)母と同居している、第1回調査から第6回調査まで回答を得た、母の就業状況「不詳」を除く者(総数33,395)を集計。
2)第3回調査は母の就業状況を調査していない。
|
第1回調査時(月齢6か月)のきょうだい構成別に、出産1年前からの母の就業状況の変化をみると、第1回調査時のきょうだい構成「ひとり」は、出産1年前では「有職」が75.1%、「無職」が24.9%であったが、出産半年後では出産を機に「有職」から「無職」に変化し、「無職」が74.9%、「有職」が25.1%となった。
一方、きょうだい構成「兄姉のみ」では、出産1年前では「無職」の割合が高く63.9%で、「有職」が36.1%となっている。出産半年後では「無職」の割合が微増し74.2%で、「有職」が25.8%となった。
いずれのきょうだい構成をみても、第6回調査では、「ひとり」及び「兄姉のみ」は約6割まで就業は増えており、他方、対象児より下のきょうだいがいる母の就業の割合は低くなっている。(図7)
図7 第1回調査時のきょうだい構成別にみた母の就業状況及びきょうだい構成の変化
【ひとり】
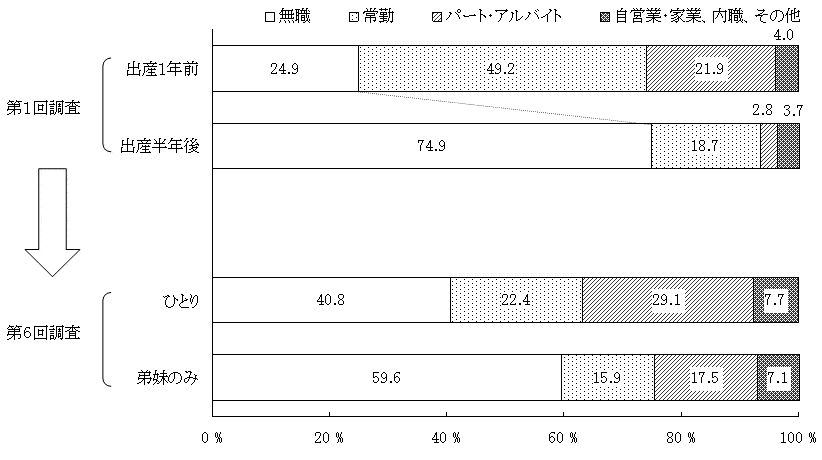
【兄姉のみ】
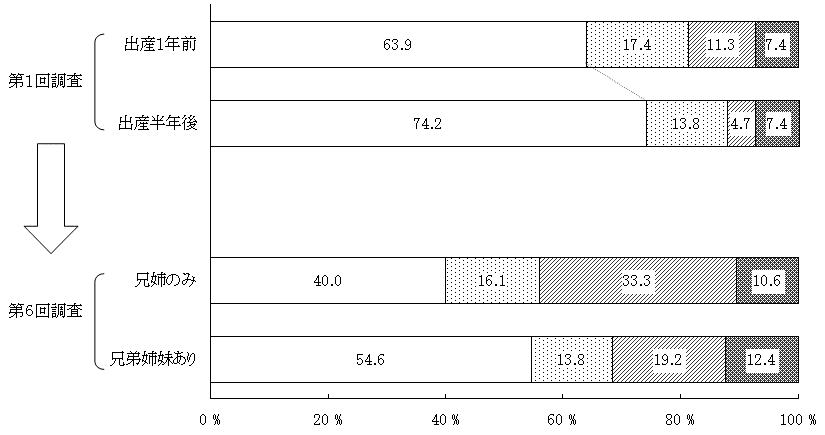
注:母と同居している、第1回調査から第6回調査まで回答を得た、母の就業状況「不詳」を除く者(総数33,395)を集計。
|
ウ 出産1年前に「無職」の母の就業の変化(第6回調査時のきょうだい構成別)
出産1年前に「無職」の母の就業の変化を、第6回調査時(5歳6か月)のきょうだい構成別にみると、「弟妹のみ」は出産1年前から第6回調査まで「ずっと無職」(70.2%)の割合が最も高く、「就労開始」(19.1%)は低くなっている。また「兄姉のみ」は「ずっと無職」(47.6%)が最も低く、「就労開始」(40.5%)が高くなっている。(図8−1)
出産1年前に「無職」の母が、「就労開始」をした調査回(対象児年齢)を、第6回調査時のきょうだい構成別にみると、「ひとり」は第4回調査(3歳6か月)が22.1%と最も高い。他は第6回調査(5歳6か月)で「弟妹のみ」34.9%、「兄弟姉妹あり」33.9%、「兄姉のみ」24.0%と最も高くなっている。(図8−2)
図8−1 出産1年前に「無職」の母の就業の変化(第6回調査時のきょうだい構成別)
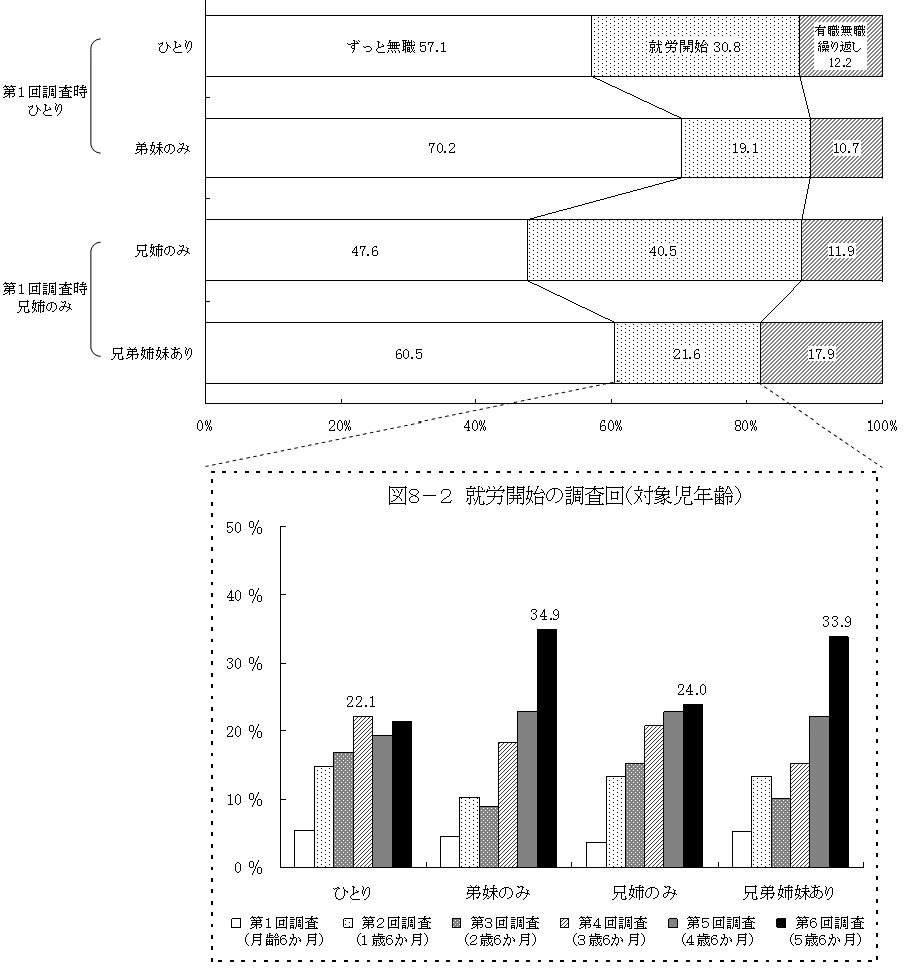
図8−1注:1)母と同居している、第1回調査から第6回調査まで回答を得た、母の就業状況「不詳」を除く者(総数33,395)を集計。
2)出産1年前に「無職」の母の就業状況の区分は以下のとおりである。
「ずっと無職」出産1年前から第6回調査まで、全て無職。
「就労開始」出産後いずれかの時点から有職を継続している。
「有職無職繰り返し」 出産後有職、無職を繰り返す。第6回調査時の有職、無職は問わない。
図8−2注:母と同居している、第1回調査から第6回調査まで回答を得た、母の就業状況「不詳」を除く、出産1年前が「無職」の母の就業状況が「有職」になり、第6回調査まで「有職」を継続した者(総数4,996)を集計。図8−1の「就労開始」を100としている。
エ 出産1年前に「有職」の母の就業の変化(第6回調査時のきょうだい構成別)
出産1年前に「有職」の母の就業の変化を、第6回調査時(5歳6か月)のきょうだい構成別にみると、出産1年前から第6回調査まで「ずっと有職」では、「兄姉のみ」(52.8%)、「兄弟姉妹あり」(45.6%)の割合が高い。「出産後離職その後有職」では、「ひとり」(37.7%)、「兄姉のみ」(30.6%)の割合が高くなっている。「出産後離職その後無職」の場合、「弟妹のみ」(45.9%)の割合が高い。(図9−1)
出産1年前に「有職」の母が、「出産半年後離職その後有職」開始をした調査回(対象児年齢)を、第6回調査時のきょうだい構成別にみると、「兄姉のみ」39.0%、「ひとり」26.5%、「兄弟姉妹あり」24.5%と、第2回調査(1歳6か月)の割合が最も高い。「弟妹のみ」は第6回調査(5歳6か月)が29.0%と最も高くなっている。(図9−2)
|
図9−1注:1)母と同居している、第1回調査から第6回調査まで回答を得た、母の就業状況「不詳」を除く者(総数 33,395)を集計。
2)出産1年前に「有職」の母の就業状況の区分は以下のとおりである。
「ずっと有職」出産1年前から第6回調査まで、全て有職。
「出産後離職その後有職」出産後いずれかの時点で離職し、その後有職になり、有職を継続している。
「出産半年後離職その後有職」出産半年後までに離職し、その後有職になり有職を継続している。
※1:出産半年後は有職でその後離職し、その後有職になり有職を継続している。
「出産後離職その後無職」出産後いずれかの時点で離職し、その後無職を継続している。
「出産半年後離職その後無職」出産半年後までに離職し、その後無職を継続している。
※2:出産半年後は有職でその後離職し、その後無職を継続している。
「有職無職繰り返し」出産後有職、無職を繰り返す。第6回調査時の有職、無職は問わない。
図9−2注:母と同居している、第1回調査から第6回調査まで回答を得た、母の就業状況「不詳」を除く、出産1年前が「有職」の母の就業状況が、出産半年後「無職」、その後「有職」になり第6回調査まで「有職」を継続した者(総数3,997)を集計。
図9−1の「出産半年後離職その後有職」を100としている。
|
オ 出産半年後に育児休業を取得した母の就業状況の変化
出産半年後に「常勤」の母の育児休業取得の有無をみると、「常勤」15.8%のうち「育児休業取得あり」12.9%、「育児休業取得なし」2.9%、いずれも年を重ねるごとに微減傾向にあり、第6回調査では、それぞれ9.3%、2.2%となっている(図10)。
育児休業取得の有無別にきょうだい構成をみると、「育児休業取得あり」では「ひとり」58.2%、「兄姉のみ」41.8%、「育児休業取得なし」では「ひとり」48.2%、「兄姉のみ」51.8%となっている。その後の変化をみると年を重ねるごとにいずれも弟妹が生まれ、第6回調査では、「育児休業取得あり」で「ひとり」18.4%、「弟妹あり」48.1%、「育児休業取得なし」では「ひとり」18.1%、「弟妹あり」41.1%となっており、「育児休業取得あり」での「弟妹あり」の割合が7.0%高くなっている。(図11)
図10 母の就業状況「常勤」の変化
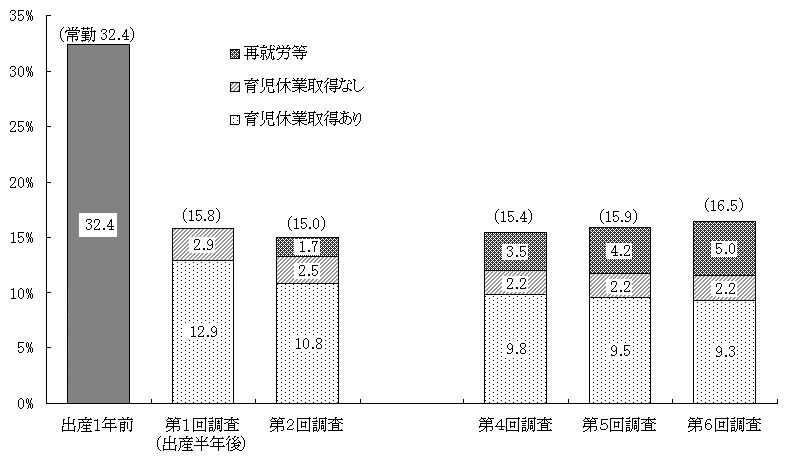
注:1)母と同居している、第1回調査から第6回調査まで回答を得た者(総数 35,363)を集計。
2)「育児休業取得あり」とは、第1回調査(出産半年後)に育児休業を「すでに取得した」、「現在、育児休業中である」、「これから取得する予定である」者をいう。
3)「再就労等」とは、第1回調査(出産半年後)に「常勤」以外の者をいう。
4)「常勤」には第1回調査(出産半年後)の「育児休業取得の有無不詳」を含む。
5)第3回調査は母の就業状況を調査していない。
図11 母の育児休業取得の有無別にみたきょうだい構成の変化
【育児休業取得あり】
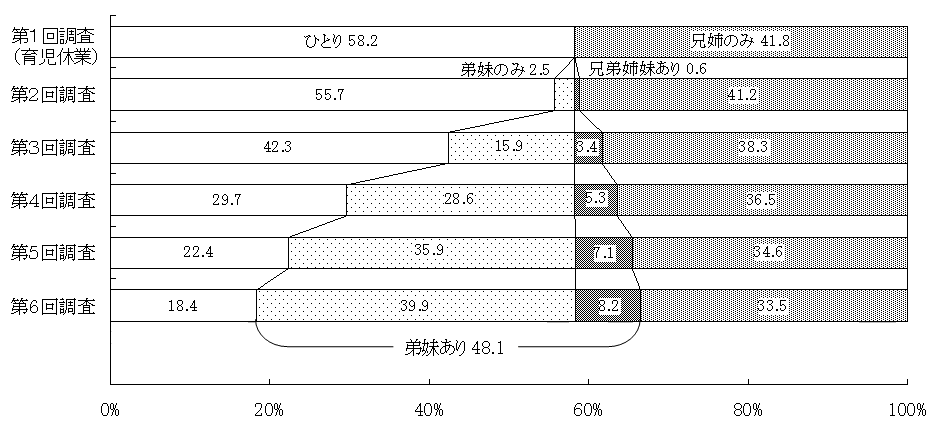
【育児休業取得なし】
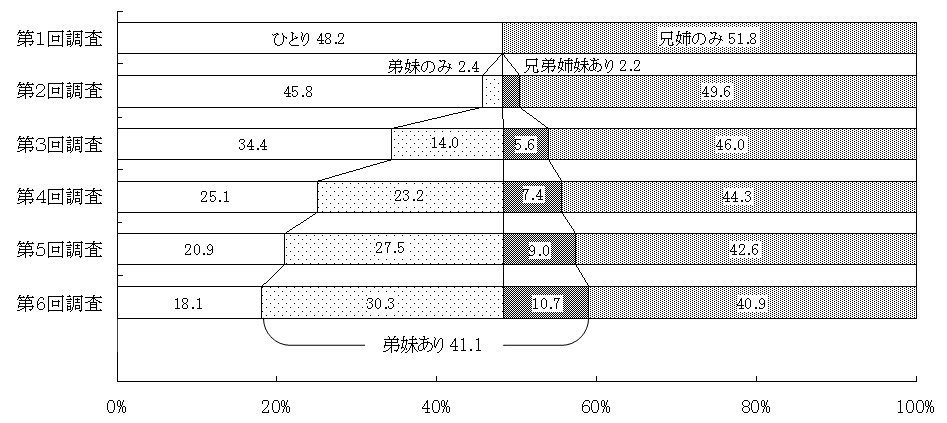
注:1)第1回調査から第6回調査まで回答を得た、第1回調査(出産半年後)の就業状況が「常勤」の母と同居している、きょうだい構成の「不詳」を除く者(総数5,636)を集計。
2)「育児休業取得あり」とは、第1回調査(出産半年後)に育児休業を「すでに取得した」、「現在、育児休業中である」、「これから取得する予定である」者をいう。
|
育児休業を取得した母の就業状況「常勤」の変化を、第1回調査時のきょうだい構成別にみると、「ひとり」では第2回調査で約2割減少して81.7%となり、弟妹の割合が増えるが第6回調査では常勤が67.6%となっている。一方「兄姉のみ」でも常勤の割合は減少しているが第6回調査で79.9%と、「ひとり」に比べ「常勤」として継続している割合が高い。(図12)
就業状況の変化を第1回調査時のきょうだい構成別にみると、「ひとり」が「兄姉のみ」に比べ「常勤」から移動する者が多くなっている。特に「16大都市」で移動が多く、「無職」が第2回調査で16.6%、第6回調査で21.0%となり、「常勤」の割合は64.8%と少なくなっている。
(図13)
図12 出産半年後に育児休業を取得した母の就業状況「常勤」及びきょうだい構成の変化
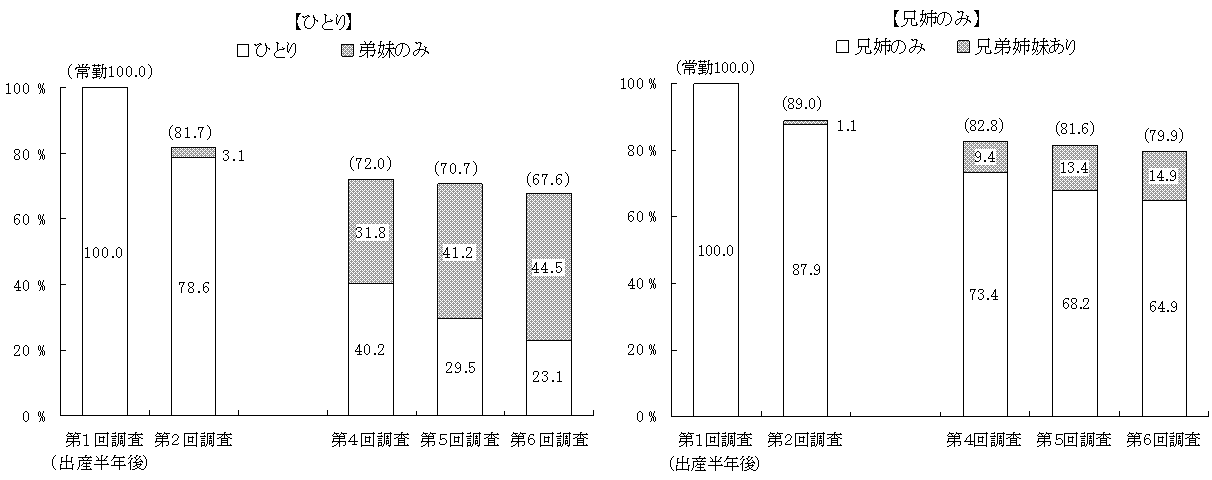
注:1)母と同居している、第1回調査から第6回調査まで回答を得た、母の就業状況「不詳」を除く者(総数 33,395)を集計。
2)「育児休業取得あり」とは、第1回調査(出産半年後)に育児休業を「すでに取得した」、「現在、育児休業中である」、「これから取得する予定である」者をいう。
3)第3回調査は母の就業状況を調査していない。
図13 出産半年後に育児休業を取得した母の就業状況の変化
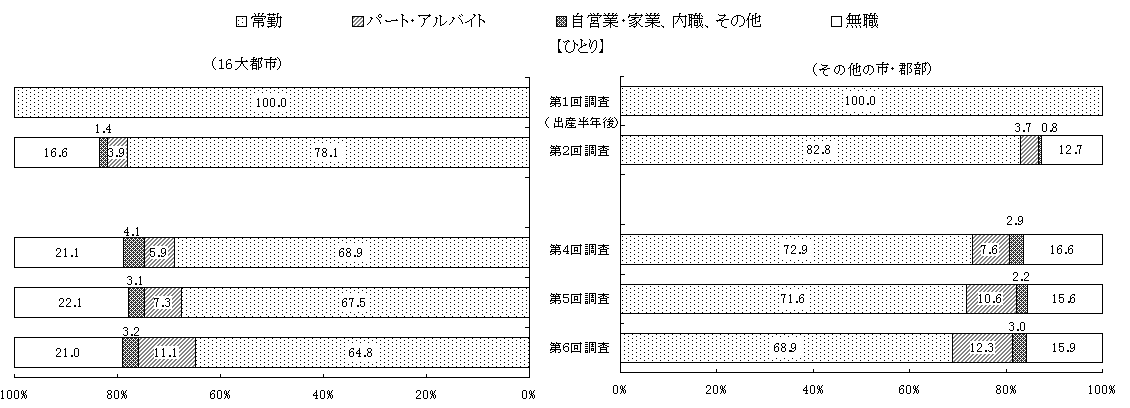
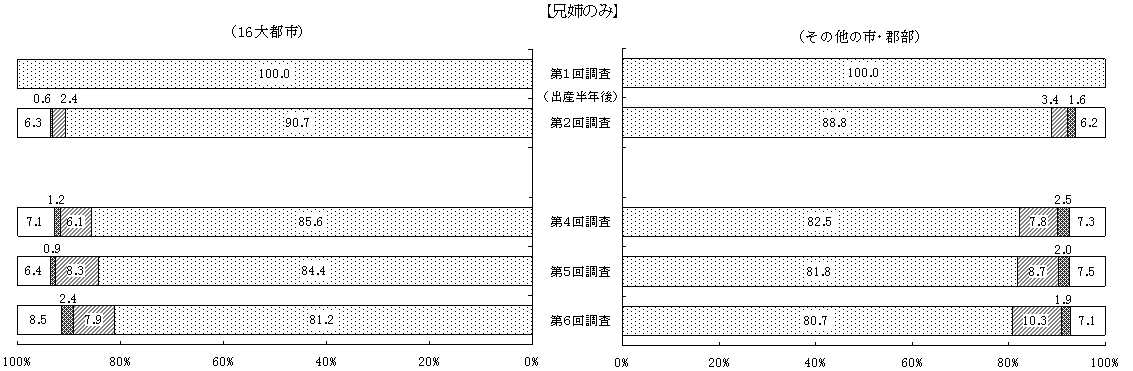
注:1)母と同居している、第1回調査から第6回調査まで回答を得た、母の就業状況「不詳」を除く者(総数 33,395)を集計。
2)「育児休業取得あり」とは、第1回調査(出産半年後)に育児休業を「すでに取得した」、「現在育児休業中である」、「これから取得する予定である」者をいう。
3)第3回調査は母の就業状況を調査していない。
4)「16大都市」は、第1回調査から第5回調査までの住所地を、第6回調査時の「16大都市」の地域に区分した。
|
カ 地域別にみた通園の状況
第5回調査時(4歳6か月)の通園の状況をみると、総数では「保育所」が38.2%、「幼稚園」が51.1%と「幼稚園」に通園の割合が多いが、地域ブロック別でみると、「保育所」は「北陸」(67.9%)と「南九州」(55.0%)が高く、幼稚園では「関東1」(62.6%)と「北海道」(52.2%)が高い。また市郡別にみると、「15大都市」では「幼稚園」(62.3%)の割合が高く、「郡部」では逆に「保育所」(53.0%)が高くなっている。(図14)
図14 地域ブロック・市郡別にみた第5回調査時(4歳6か月)の通園の状況
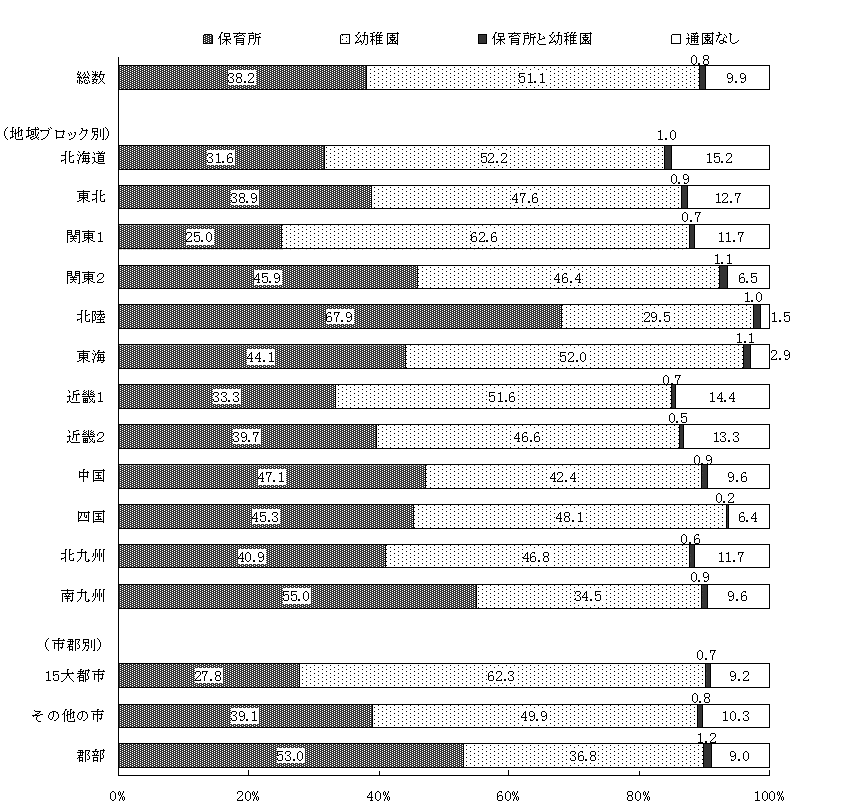
注:1)母と同居している、第1回調査から6回調査まで回答を得た、母の就業状況「不詳」、通園状況「不詳」を除く(総数 33,371)を集計。
2)総数には外国在住分を含む。
3)「地域ブロック」「市郡」は第5回調査の状況である。
「地域ブロック」の区分は以下のとおりである。
「北海道」北海道「東北」青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
「関東1」埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県「関東2」茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
「北陸」新潟県、富山県、石川県、福井県「東海」岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
「近畿1」京都府、大阪府、兵庫県「近畿2」滋賀県、奈良県、和歌山県
「中国」鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県「四国」徳島県、香川県、愛媛県、高知県
「北九州」福岡県、佐賀県、長崎県、大分県「南九州」熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
「15大都市」の区分は以下のとおりである。
東京都区部、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市
|
キ 通園の状況別にみた母の就業状況の変化
第5回調査時(4歳6か月)の通園状況別に母の就業状況の変化をみると、保育所に通園している子の母は、出産1年前では「有職」71.5%、「無職」28.5%で、第1回調査(月齢6か月)では「有職」が44.8%と減少したが、年々増加して、第6回調査(5歳6か月)では、「有職」84.3%、「無職」15.7%となっている(図15)。
図15 第5回調査時(4歳6か月)の通園状況別にみた母の就業状況の変化
【「保育所」に通園している子の母の就業状況】
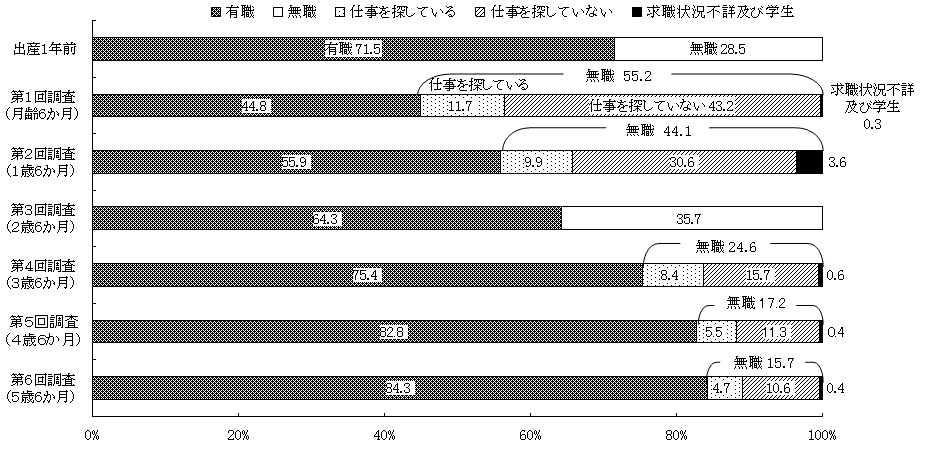
【「幼稚園」に通園している子の母の就業状況】
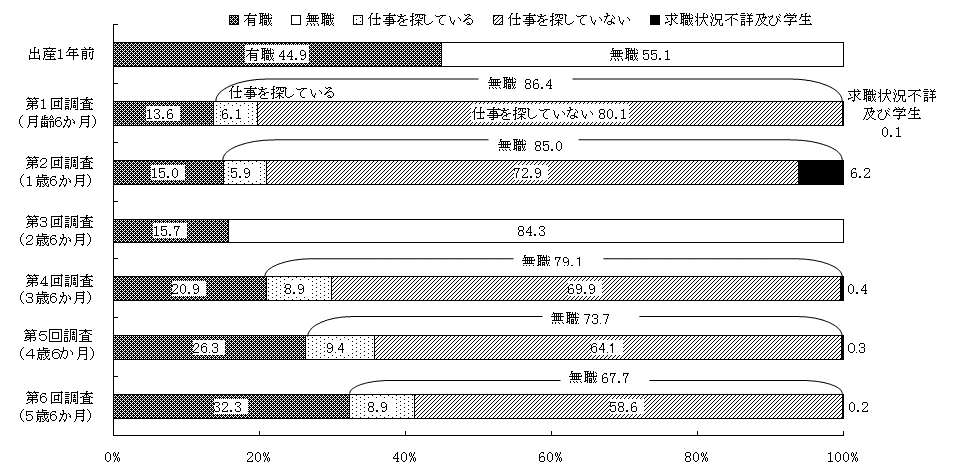
注:1)母と同居している、第1回調査から6回調査まで回答を得た、母の就業状況「不詳」、通園状況「不詳」を除く者(総数33,371)を集計。
2)出産1年前、第3回調査は求職状況を調査していない。
|