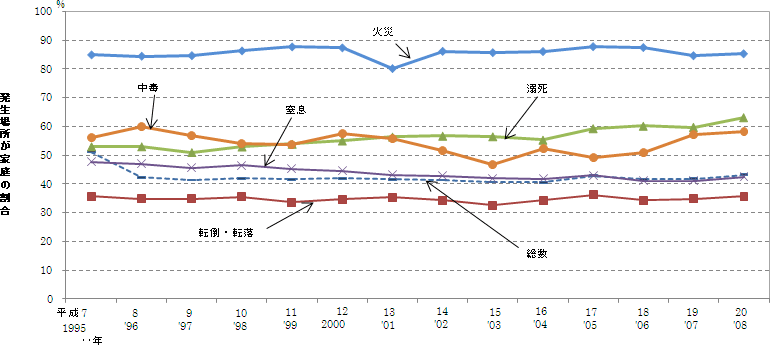1 不慮の事故による死亡の年次推移
(1)不慮の事故による死亡数の年次推移
不慮の事故による死亡数の年次推移をみると、第2次世界大戦前は、関東大震災があった大正12年を除くと増加傾向で推移している。第2次世界大戦後もしばらくは増加傾向が続いていたが、昭和44年から47年の4万2千人台から4万3千人台をピークに急激に減少に転じ、52年から63年は2万8千人台から3万人台で推移している。その後、増加傾向で推移した後、平成8年から20年は3万7千人台から4万人台で推移している。(図1、統計表第1表)
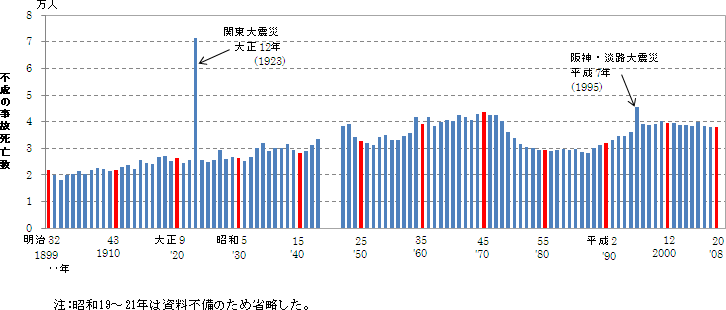
(2)主な不慮の事故の種類別にみた死亡数の年次推移
主な不慮の事故の種類別に平成7年以降の死亡数の年次推移をみると、交通事故は7年の15,147人から20年の7,499人まで一貫して減少している。一方、窒息は平成7年の7,104人から20年の9,419人まで、転倒・転落は7年の5,911人から20年の7,170人まで、溺死は7年の5,588人から20年の6,464人まで、それぞれ増減を繰り返しながら増加傾向にある。(図2、統計表第2表)
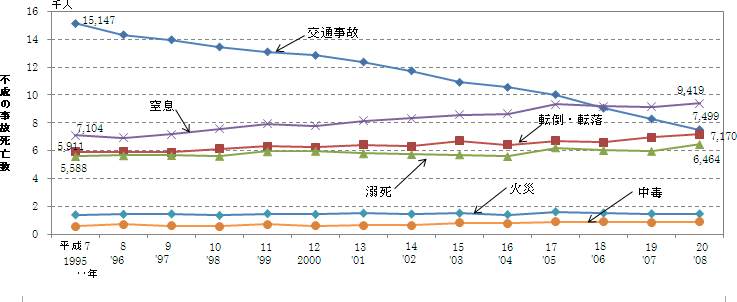
(3)主な不慮の事故の種類別にみた年齢階級別死亡率の年次比較
平成7年以降の主な不慮の事故の種類別に年齢(5歳階級)別死亡率(人口10万対)をみると、総数、交通事故、転倒・転落、溺死及び窒息は全体として低下している。特に交通事故では、ほとんどの年齢階級で半減している。(図3、統計表第3表)
したがって、転倒・転落、溺死及び窒息で死亡数が増加傾向にあるのは、死亡率が上昇したためではなく、死亡率の高い高齢者が増加しているためである。
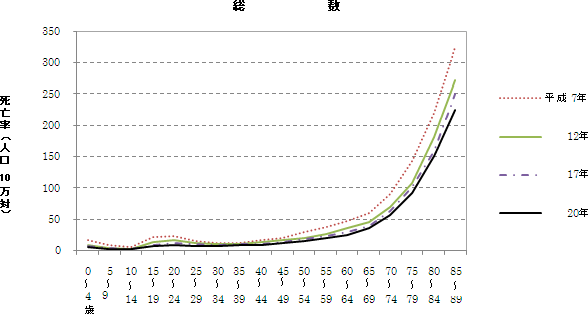
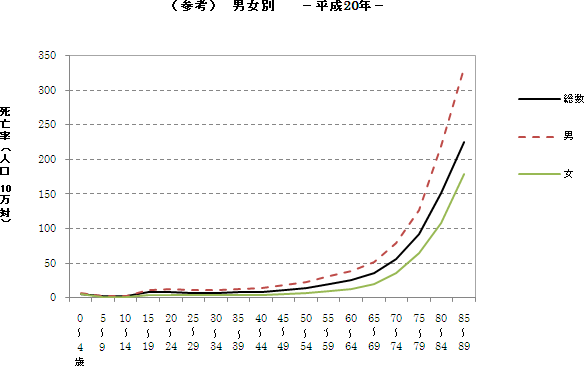
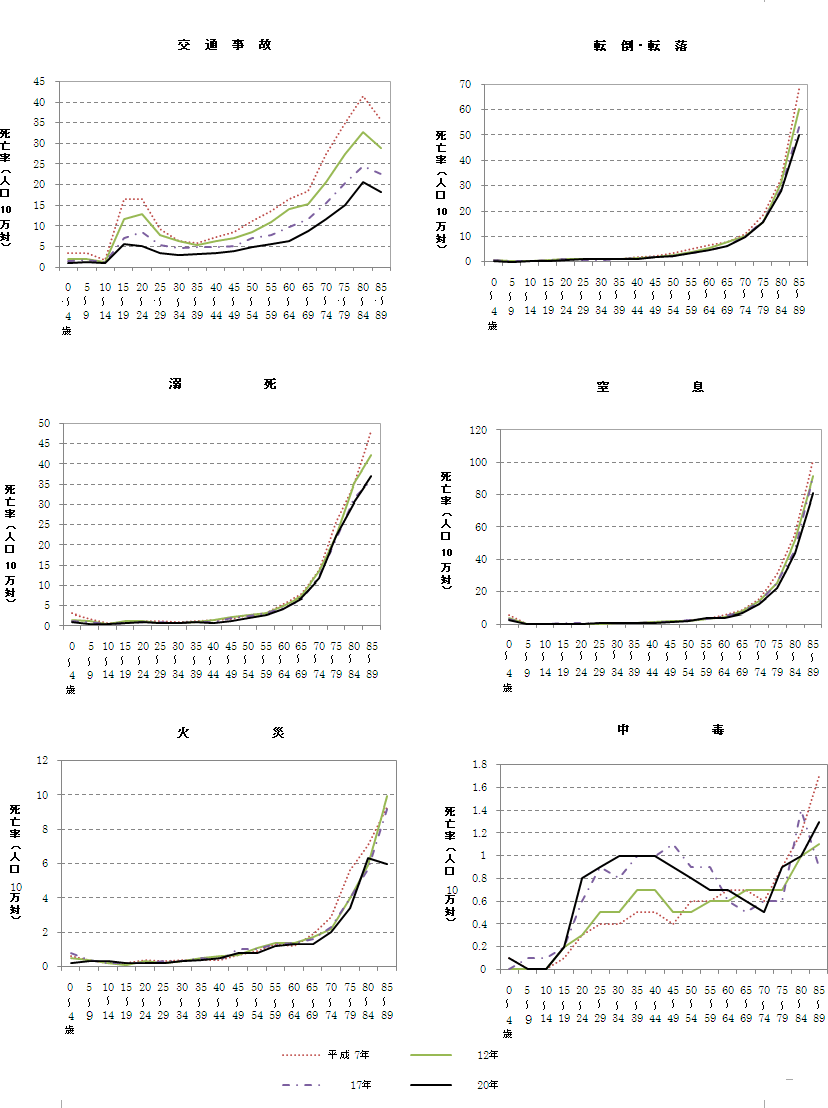
(4)交通事故の種類別にみた死亡数の年次推移
交通事故の種類別に平成7年以降の交通事故死亡数の年次推移をみると、歩行者は7年の4,335人から20年の2,446人(7年を100とした場合の割合は56.4%)まで一貫して減少しており、自転車乗員は7年の1,998人から20年の1,116人(同55.9%)まで、オートバイ乗員は7年の2,551人から20年の1,148人(同45.0%)まで、乗用車乗員は7年の4,281人から20年の1,739人(同40.6%)まで、それぞれ増減を繰り返しながら減少傾向にある。特に乗用車乗員の減少が大きい。(図4、統計表第4表)
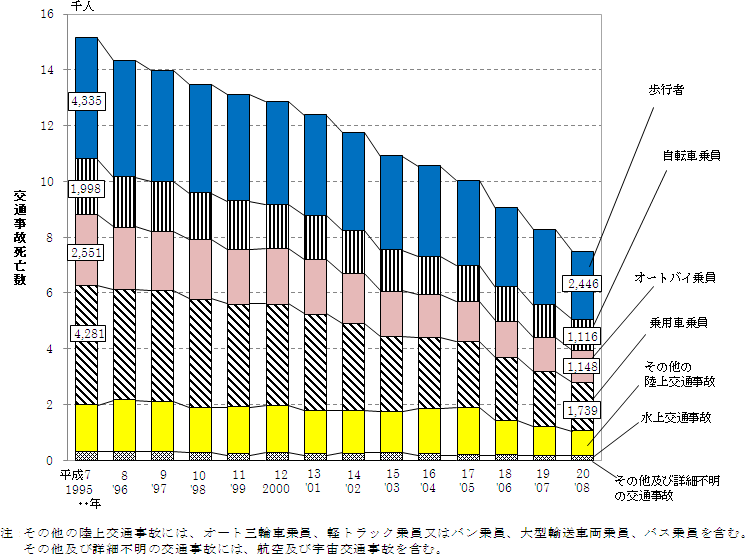
(5)発生場所別にみた交通事故以外の不慮の事故による死亡数の年次推移
交通事故以外の不慮の事故について傷害の発生場所別に平成7年以降の死亡数の年次推移をみると、総数では阪神・淡路大震災があった7年を除くと増加傾向にあるが、居住施設は7年の544人から20年の1,452人まで一貫して増加しており、家庭は8年の10,500人から20年の13,240人まで、増減を繰り返しながら増加傾向にある。一方、公共の地域は平成7年の1,639人から20年の1,295人まで、工業用地域は7年の1,304人から20年の668人まで、その他は7年の3,588人から20年の2,966人まで、それぞれ増減を繰り返しながら減少傾向にある。(図5、統計表第5表)
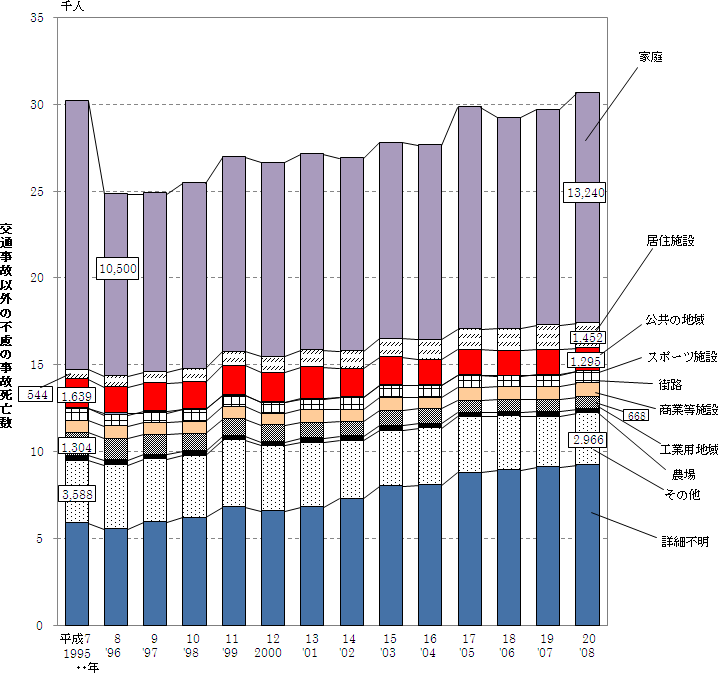
(6)家庭における主な不慮の事故の種類別にみた死亡数の年次推移
家庭における主な不慮の事故の種類別に平成7年以降の死亡数の年次推移をみると、窒息は7年の3,393人から20年の3,995人まで、溺死は7年の2,966人から20年の4,079人まで、転倒・転落は7年の2,115人から20年の2,560人まで、それぞれ増減を繰り返しながら増加傾向にある。一方、火災は平成7年の1,174人から20年の1,238人にほぼ横ばいで推移している。(図6、統計表第6表)
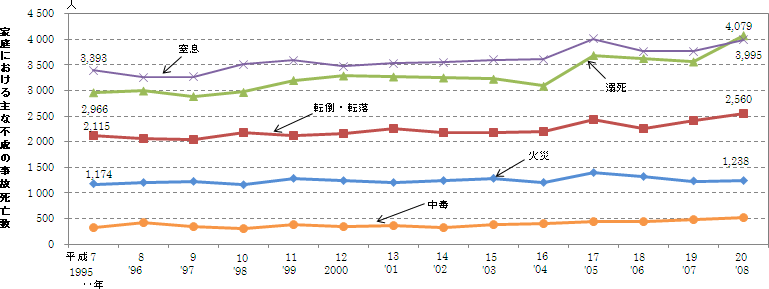
(7)交通事故以外の主な不慮の事故の種類別にみた発生場所が家庭の割合の年次推移
交通事故以外の主な不慮の事故による死亡について、不慮の事故の種類別に平成7年以降の発生場所が家庭の割合の年次推移をみると、総数では平成7年を除くと40%台となっており、家庭の割合が最も高いのは火災となっている。次に高いのは溺死と中毒となっており、最も低いのは転倒・転落となっている。(図7、統計表第7表)