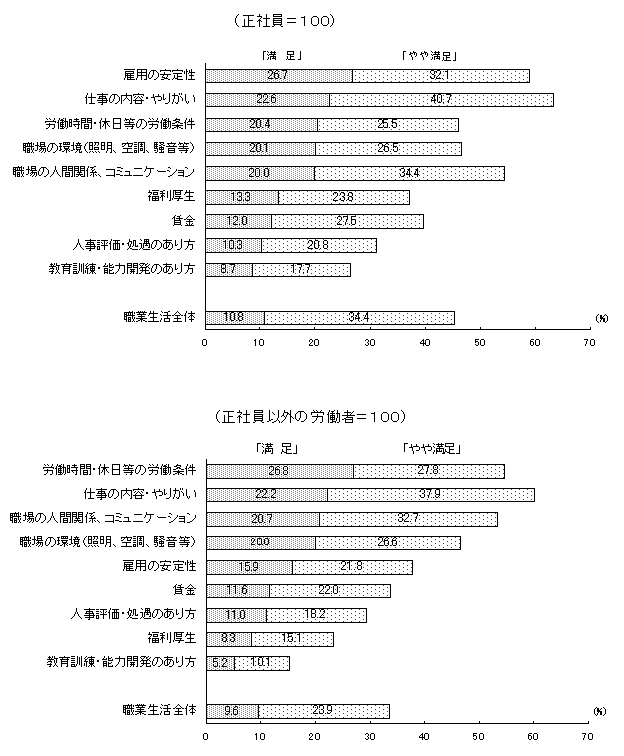|
厚生労働省大臣官房統計情報部 担当:雇用統計課労働経済第一係 電話:03(5253)1111内線7622 03(3595)3145(夜間直通) |

|
||
|
平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果の概況
○結果のポイントは以下のとおりです。・正社員以外の労働者がいる事業所は全体の8割、パートタイム労働者がいる事業所は6割
・正社員以外の労働者の活用理由では「賃金の節約のため」、「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」が多い
・正社員・出向社員以外の労働者で現在の就業形態を選んだ理由は「自分の都合のよい時間に働けるから」、「家計の補助、学費等を得たいから」など
【事業所調査】
1正社員以外の労働者がいる事業所の割合は77.2%であり、就業形態別に最も割合が多いのは、パートタイム労働者がいる事業所の59.0%となっている。(P6表1−1、P7表1−2、第1図)
2正社員以外の労働者の割合は37.8%で、就業形態別にはパートタイム労働者が22.5%と最も多く、飲食店,宿泊業、卸売・小売業の産業で割合が高い。(P8表2−1、P9表2−2、第2図)
3正社員以外の労働者の活用理由(複数回答3つまで)としては、「賃金の節約のため」40.8%、「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」31.8%、「即戦力・能力のある人材を確保するため」25.9%を挙げる事業所が多い。(P13表5、P14第4−1図)
【個人調査】
1正社員・出向社員以外の労働者で現在の就業形態を選んだ理由(複数回答3つまで)としては、「自分の都合のよい時間に働けるから」42.0%、「家計の補助、学費等を得たいから」34.8%を挙げる者が多い。(P22表12、P23第7−1図)
2正社員以外の労働者の今後の就業に対する希望としては、「現在の会社で働きたい」が66.7%と多い。一方、希望する働き方としては、「現在の就業形態を続けたい」が68.8%、「他の就業形態に変わりたい」が30.6%となっている。(P24表13、表14−1)「他の就業形態に変わりたい」とした労働者のうち、90.9%が「正社員」を希望している。(P25表14−2)
3正社員になりたい理由(複数回答3つまで)としては、「正社員の方が雇用が安定しているから」80.3%、「より多くの収入を得たいから」74.1%を挙げる者が多い。(P26表15、P27第9−1図)
目次
|
調査の概要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 結果の概要 【事業所調査】1就業形態別就労状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 2正社員以外の労働者比率の変化‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 3正社員以外の労働者の活用等について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 【個人調査】1生活をまかなう主な収入源‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17 2就業の実態‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18 3仕事に対する意識‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22 4現在の職場での満足度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28 |
平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果の概況は、厚生労働省のホームページにも掲載されています。
調査の概要
1調査の目的
近年、労働者の就業形態の多様化への対応が重要な課題となっており、関連して格差問題等への社会的関心も高まっており、就業形態の多様化の実態を把握することが求められている。
このため、本調査では就業形態の実態、労働者の意識、就業環境全般等について把握し、今後の経済的社会構造の変化に的確に対応した各種施策の検討、実施の基礎資料とすることを目的とする。
2調査の範囲及び対象
(1)地域
日本国全域とする。ただし、一部島しょ等を除く。
(2)事業所調査
日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に基づく14大産業〔鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(ただし、その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び外国公務を除く。)〕に属する常用労働者を5人以上雇用している民営事業所のうちから抽出した約16,000事業所。
(3)個人調査
上記(2)の事業所調査の調査対象事業所において就業している労働者のうち、一定の方法により抽出した者。
3調査の実施時期
事業所調査は、平成19年10月1日現在の状況について、平成19年10月1日から10月31日までの間に行った。
個人調査は、平成19年10月1日現在の状況について、平成19年10月1日から11月20日までの間に行った。
4主な調査事項
(1)事業所調査
事業所の属性、就業形態・性別労働者数、正社員以外の労働者比率の変化、正社員以外の労働者の活用理由・活用上の問題点等
(2)個人調査
個人の属性、賃金、資格・免許、就業形態を選択した理由、今後の就業に対する希望、職場での満足度等
5調査機関
(1)事業所調査
厚生労働省大臣官房統計情報部−都道府県労働局−公共職業安定所−統計調査員−調査対象事業所
(2)個人調査
厚生労働省大臣官房統計情報部−都道府県労働局−公共職業安定所−統計調査員−調査対象労働者
6調査の方法
(1)事業所調査
事業所票は、厚生労働省大臣官房統計情報部から直接、調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所において記入した後、統計調査員がこれを回収。
(2)個人調査
個人票は、統計調査員が調査対象事業所において調査対象労働者数を算出し、調査対象事業所に配付を依頼、調査対象労働者が調査票に記入した後、直接、厚生労働省大臣官房統計情報部に郵送。
7調査対象数、有効回答数及び有効回答率
|
事業所調査:調査対象数15,638有効回答数10,791有効回答率69.0% |
|
個人調査:調査対象数56,212有効回答数28,783有効回答率51.2% |
8主な用語の説明
(1)労働者
この調査で「労働者」とは、調査対象事業所で雇用されている者のほか、派遣労働者や出向社員を含む。(派遣労働者は派遣元事業所から派遣されてきている者、出向社員は他の事業所から出向してきている者とする。)
(2)就業形態
この調査においては、労働者を以下の8つの就業形態に区分している。
また、「契約社員」、「嘱託社員」、「出向社員」、「派遣労働者」、「臨時的雇用者」、「パートタイム労働者」、「その他」を合わせて「正社員以外の労働者」とする。
ア正社員
雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者などを除いた、いわゆる正社員。
イ契約社員
特定職種に従事し、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者。
ウ嘱託社員
定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する者。
エ出向社員
他企業より出向契約に基づき出向してきている者。出向元に籍を置いているかどうかは問わない。
オ派遣労働者
「労働者派遣法(注)」に基づき派遣元事業所から派遣されてきている者。
なお、調査対象事業所が労働者派遣事業を行っている場合、派遣労働者として雇用している労働者についてはその事業所での調査対象としない。
「登録型」とは、派遣会社に派遣スタッフとして登録しておく形態をいう。
「常用雇用型」とは、派遣会社に常用労働者として雇用されている形態をいう。
(注)「労働者派遣法」とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」をいい、派遣元事業所とは、同法に基づく厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に届出を行っている事業所をいう。
カ臨時的雇用者
臨時的に又は日々雇用している労働者で、雇用期間が1か月以内の者。
キパートタイム労働者
正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない者。
クその他
ア〜キ以外の労働者で雇用している者。
(3)職種分類
ア専門的・技術的な仕事
高度の専門的水準において、科学的知識を応用した技術的な仕事に従事する者及び医療・法律・芸術・その他の専門的性質の仕事に従事する者をいう。(例えば、科学研究者、機械・電気技術者、プログラマー、医師、薬剤師、看護師、公認会計士、税理士、記者など)
イ管理的な仕事
課(課相当を含む。)以上の組織の管理的仕事に従事する者をいう。(例えば、部長、課長、支店長、工場長など)
ウ事務的な仕事
一般に課長(課長相当職を含む。)以上の職務にあるものの監督を受けて、庶務・文書・人事・会計・調査・企画、運輸・通信・生産関連・営業販売・外勤に関する事務及び事務用機械の操作の仕事に従事する者をいう。(例えば、一般事務員、集金人、レジ係、オペレーター、速記者、出改札係など)
エ販売の仕事
商品(サービスを含む。)・不動産・証券などの売買、売買の仲立・取次・代理などの仕事、保険外交、商品の売買・製造などに関する取引上の勧誘・交渉・受注の仕事に従事する者をいう。(例えば、一般商店・デパートなどの販売店員、保険外交員、不動産仲介人など)
オサービスの仕事
理容・美容・クリーニング・調理・接客・娯楽など個人に対するサービス、居住施設・ビルなどの管理サービス及びその他のサービスの仕事に従事する者をいう。(例えば、理容・美容師、クリーニング工、調理人、ホームヘルパー、駐車場・ビル管理人など)
カ保安の仕事
社会・個人・財産の保護、法と秩序の維持などの仕事に従事する者をいう。(例えば、守衛、警備員、監視員、建設現場誘導員など)
キ運輸・通信の仕事
電車・自動車・船舶・航空機等運転・操縦の仕事、通信機の操作及びその他の関連作業に従事する者をいう。(例えば、鉄道運転士、タクシー運転者、電話交換手など)
ク生産工程・労務の仕事
機械・器具・手道具などを用いて原料・材料を加工する仕事、各種の機械器具を組立・調整・修理する仕事、製版・印刷・製本の作業、定置機関・機械及び建設機械を操作する仕事、ダム・トンネルの掘削などの仕事、建設の仕事、商店・会社・病院などの雑務、及び他に分類されない運搬・清掃など労務的作業に従事する者をいう。(例えば、大工、左官、溶接工、自動車整備工、清掃作業員など)
(4)事業所規模
この調査において、事業所規模とは、その事業所に雇用されている常用労働者の人数である。
常用労働者とは、次のア、イのいずれかに該当する者をいう。
ア期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇用されている者。
イ日々雇われている者又は1か月以内の期間を定めて雇用されている者で、平成19年8月及び9月の各月に各々18日以上雇われた者。
9利用上の注意
(1)構成比は小数点以下第二位を四捨五入としているため、計は必ずしも100.0とはならない。
(2)統計表中「0.0」は、表章単位未満の数値を示す。
(3)統計表中「−」は、該当数値がないことを示す。
(4)統計表中「…」は、調査をしていないことを示す。
(5)統計表中「・」は、統計項目があり得ないことを示す。
(6)事業所調査で把握した労働者割合と個人調査の労働者割合は、集計上の理由により一致しないことがある。
結果の概要
【事業所調査】
1就業形態別就労状況
(1)正社員及び正社員以外の労働者の有無
平成19年10月1日現在で、就業形態別に労働者がいる事業所の割合をみると、「正社員がいる事業所」の割合は94.4%(平成15年調査(以下「前回」という)96.3%)となっており、「正社員以外の労働者がいる事業所」の割合は77.2%(前回75.3%)となっている。
また、「正社員と正社員以外の労働者の両方がいる事業所」の割合は71.6%(前回71.6%)となっている。(表1−1)
表1−1正社員・正社員以外別就労状況(事業所割合)
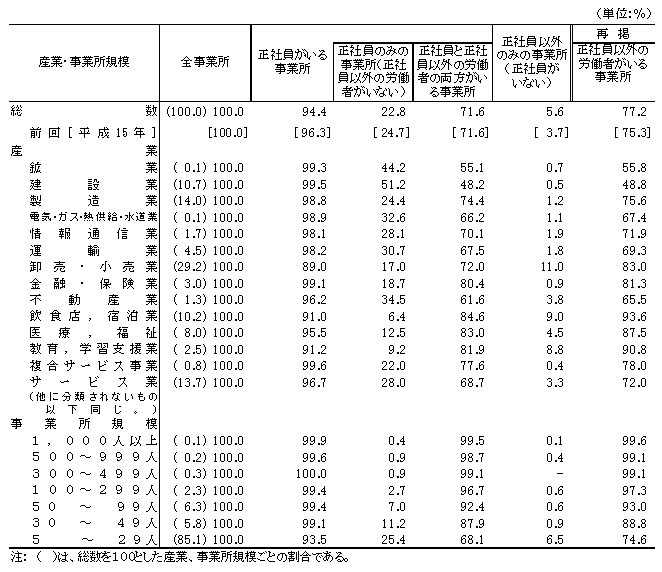
(2)正社員以外の労働者がいる事業所
正社員以外の労働者がいる事業所の割合を就業形態別にみると、パートタイム労働者がいる事業所の割合が59.0%(前回57.7%)と最も多く、次いで嘱託社員が12.9%(前回11.3%)、派遣労働者が11.6%(前回7.6%)の順となっている。また、産業別にみると、パートタイム労働者がいる事業所の割合についてはおおむねどの産業でも多くなっている。それ以外の就業形態をみると、派遣労働者がいる事業所の割合では金融・保険業、情報通信業が高く、契約社員がいる事業所の割合では教育,学習支援業、情報通信業が高い。(表1−2、第1図)
表1−2就業形態別就労状況(事業所割合)
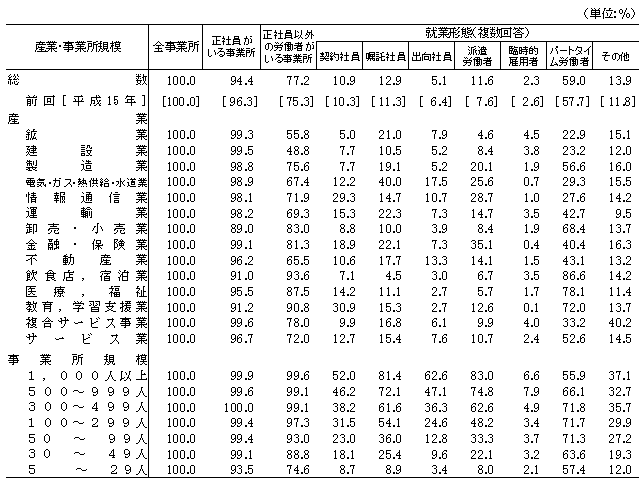
第1図事業所における就労状況(事業所割合)
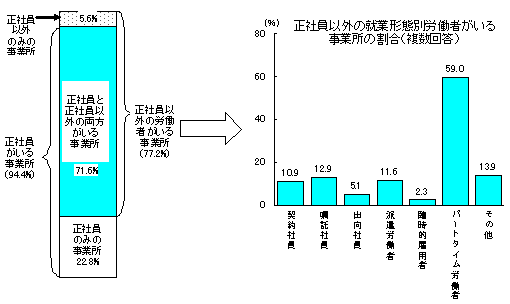
(3)就業形態別労働者の割合
就業形態別に労働者の割合をみると、正社員が62.2%(前回65.4%)、正社員以外の労働者が37.8%(前回34.6%)となっている。正社員以外の労働者では、パートタイム労働者が22.5%(前回23.0%)、派遣労働者が4.7%(前回2.0%)となっている。
また、就業形態ごとに男女別の割合をみると、正社員で男71.6%(前回72.3%)、女28.4%(前回27.7%)となっているのに対し、正社員以外の労働者では、男37.2%(前回34.3%)、女62.8%(前回65.7%)と女の割合が高くなっている。特にパートタイム労働者では男26.5%(前回24.7%)、女73.5%(前回75.3%)と女の割合が最も高い。(表2−1、第2図)
正社員以外の労働者について労働者の割合を産業別にみると、パートタイム労働者では飲食店,宿泊業、卸売・小売業の産業で、派遣労働者では情報通信業、製造業、金融・保険業で、契約社員では教育,学習支援業、情報通信業で、それぞれ他の産業に比べて割合が高い(表2−2)。
表2−1性別にみた就業形態別就労状況(労働者割合)
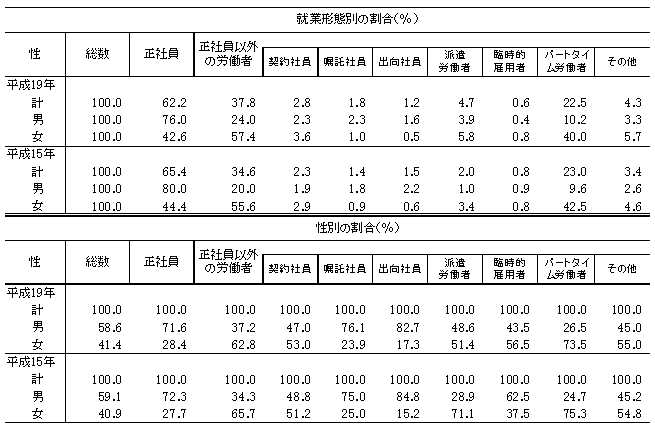
表2−2就業形態別就労状況(労働者割合)
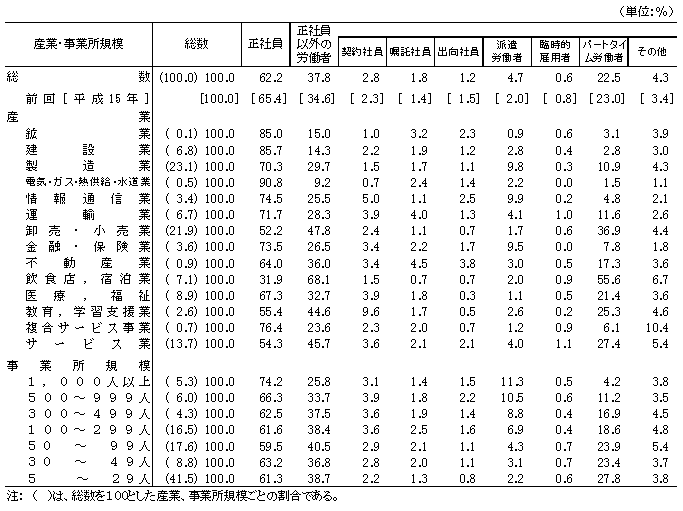
第2図労働者の就業形態(労働者割合)
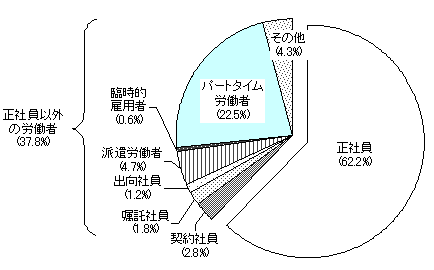
2正社員以外の労働者比率の変化
(1)3年前(平成16年)と比べた変化及び今後の変化
3年前(平成16年)と比べた正社員以外の労働者比率の変化をみると、「比率が上昇した」事業所の割合が13.6%(前回19.1%)で、「比率が減少した」事業所の割合が9.8%(前回8.9%)となっており、「比率が上昇した」事業所の方が多い。
事業所規模別にみると、「比率が減少した」事業所の割合は規模間で目立った傾向がないのに対して、「比率が上昇した」事業所の割合は、事業所規模が大きくなるほど高い。
さらに、今後の変化をみると、正社員以外の労働者の「比率が上昇する」と思われる事業所の割合が12.6%(前回19.8%)、「比率が減少する」と思われる事業所の割合が4.4%(前回3.6%)となっており、事業所規模別にみると、概ね事業所規模が大きくなるほど「比率が上昇する」と思われる事業所の割合が高い。(表3)
表33年前と比べた正社員以外の労働者比率の変化及び今後の労働者比率の変化(事業所割合)
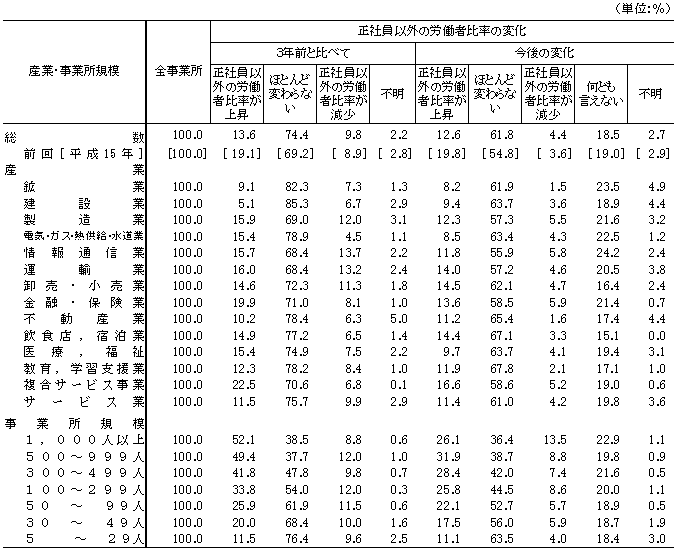
(2)3年前と比べて比率が上昇した就業形態
3年前と比べて正社員以外の労働者比率が上昇した事業所について、比率が上昇した就業形態をみると、パートタイム労働者が56.2%(前回64.4%)と最も多く、次いで派遣労働者18.3%(前回13.3%)、嘱託社員15.1%(前回9.7%)の順となっている。
事業所規模別にみると、パートタイム労働者では規模が小さいほど比率が上昇した事業所の割合が高い傾向があるのに対して、派遣労働者、嘱託社員、契約社員などでは規模が大きいほど比率が上昇した事業所の割合が高い傾向がある。(表4−1、第3−1図)
表4−13年前と比べて比率が上昇した就業形態(事業所割合)
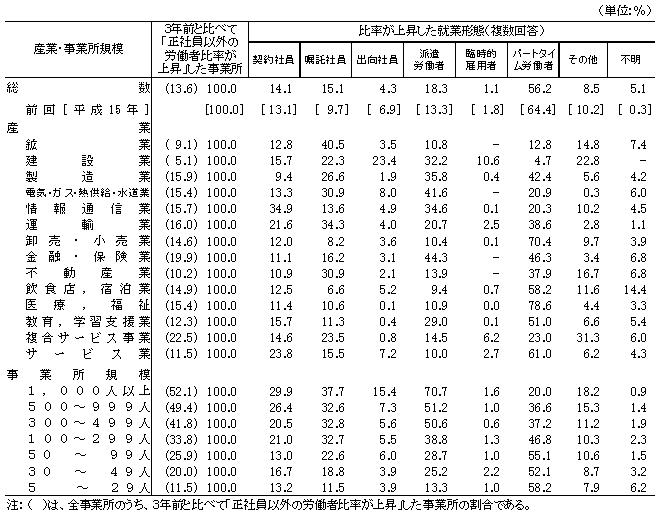
第3−1図3年前と比べ比率が上昇した就業形態(事業所割合、複数回答)
(正社員以外の労働者比率が上昇した事業所=100)
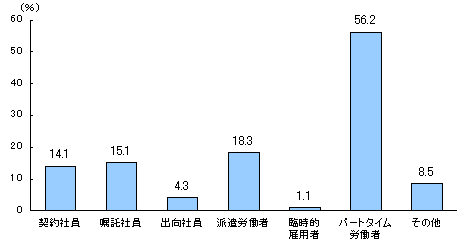
(3)今後、比率が上昇すると思われる就業形態
今後、正社員以外の労働者比率が上昇すると思われる事業所について、比率が上昇すると思われる就業形態をみると、パートタイム労働者が69.7%(前回71.2%)と最も多く、次いで嘱託社員21.2%(前回13.0%)、派遣労働者19.5%(前回16.6%)の順となっている(表4−2、第3−2図)。
表4−2今後、比率が上昇すると思われる就業形態(事業所割合)
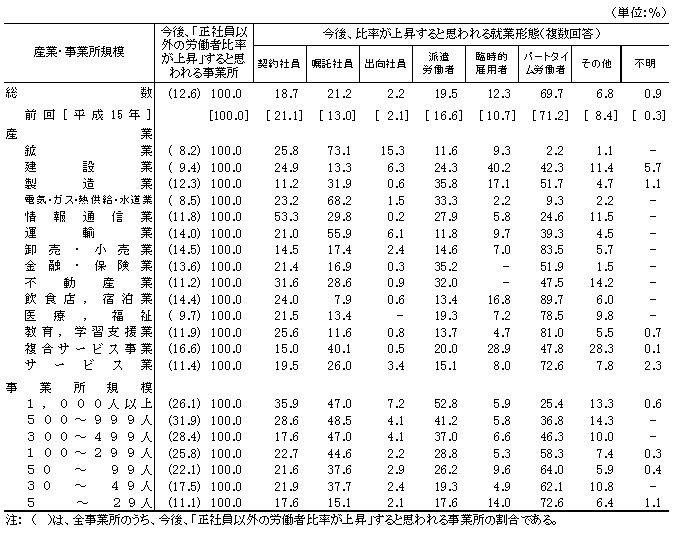
第3−2図今後比率が上昇すると思われる就業形態(事業所割合、複数回答)
(今後正社員以外の労働者比率が上昇すると思われる事業所=100)
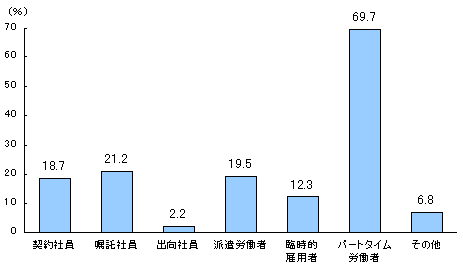
3正社員以外の労働者の活用等について
(1)正社員以外の労働者を活用する理由
正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者の活用理由(複数回答3つまで)をみると、「賃金の節約のため」が40.8%(前回51.7%)と最も多く、次いで「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」31.8%(前回28.0%)、「即戦力・能力のある人材を確保するため」25.9%(前回26.3%)の順となっている。
就業形態別にみると、特に契約社員では「専門的業務に対応するため」が43.6%(前回44.9%)と最も多く、次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」38.3%(前回37.9%)、「賃金の節約のため」28.3%(前回30.3%)の順となっている。派遣労働者では「即戦力・能力のある人材を確保するため」が35.2%(前回39.6%)と最も多く、次いで「正社員を確保できないため」26.0%(前回16.9%)、「景気変動に応じて雇用量を調節するため」25.7%(前回26.4%)の順となっている。パートタイム労働者では「賃金の節約のため」が41.1%(前回55.0%)と最も多く、次いで「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」37.2%(前回35.0%)、「長い営業(操業)時間に対応するため」21.7%(前回20.4%)の順となっている。(表5、第4−1図、第4−2図)
表5正社員以外の労働者を活用する理由(事業所割合)
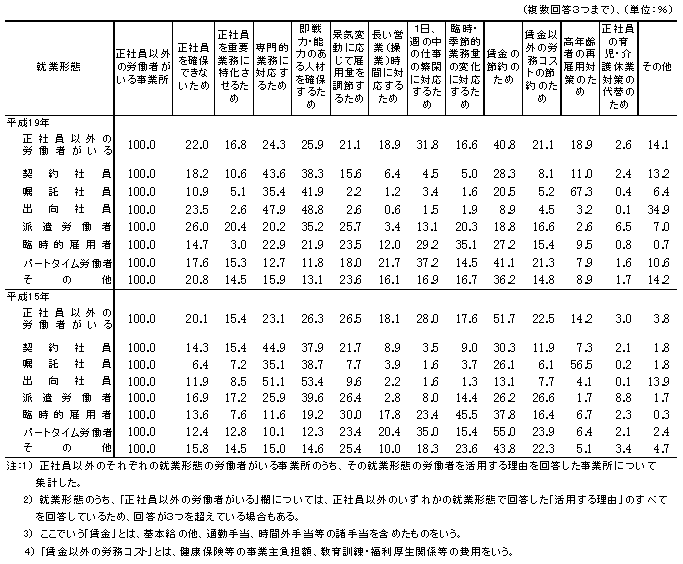
第4−1図正社員以外の労働者の活用理由(事業所割合、複数回答3つまで)
(正社員以外の労働者がいる事業所=100)
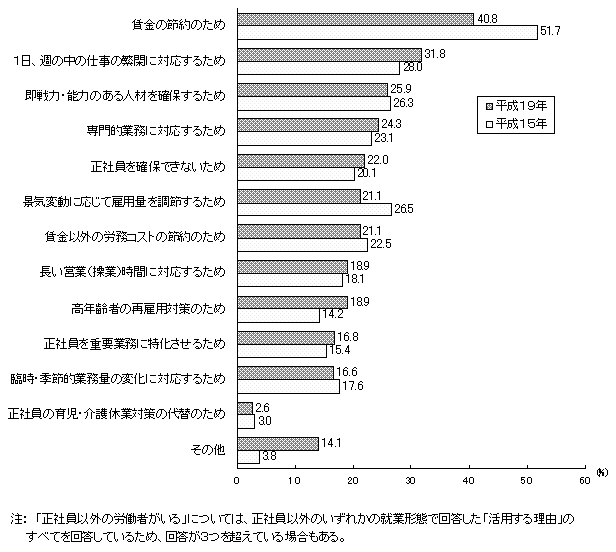
第4−2図主な就業形態別活用理由(上位7つまで)(事業所割合、複数回答3つまで)
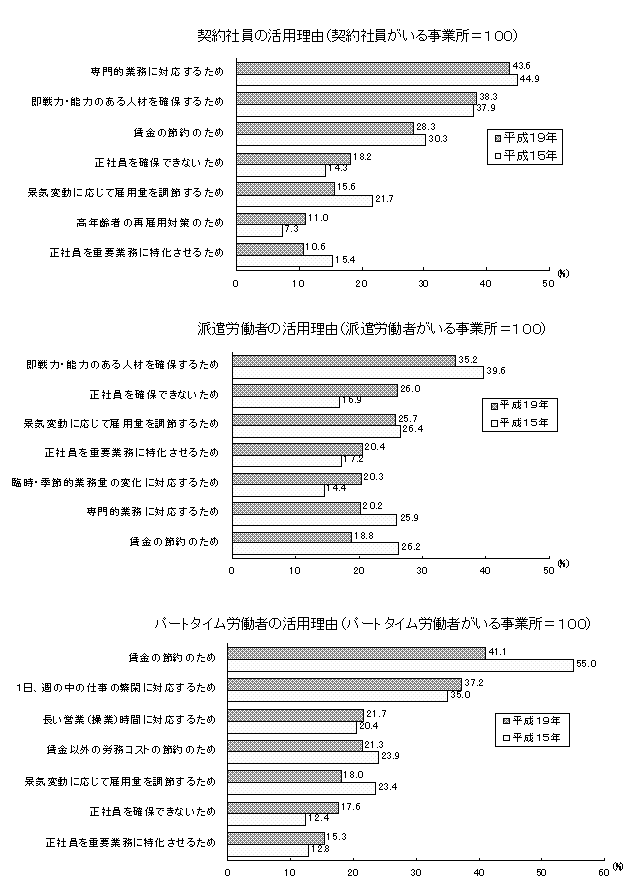
(2)活用上の問題点
正社員以外の労働者がいる事業所について、活用する上での問題点(複数回答)をみると、「良質な人材の確保」が51.4%(前回49.8%)と最も多く、次いで「仕事に対する責任感」48.3%(前回50.2%)、「仕事に対する向上意欲」37.5%(前回37.4%)の順となっている。
就業形態別にみると、ほとんどの就業形態において「良質な人材の確保」と「仕事に対する責任感」を挙げる割合が多い。(表6)
表6正社員以外の労働者の活用上の問題点(事業所割合)
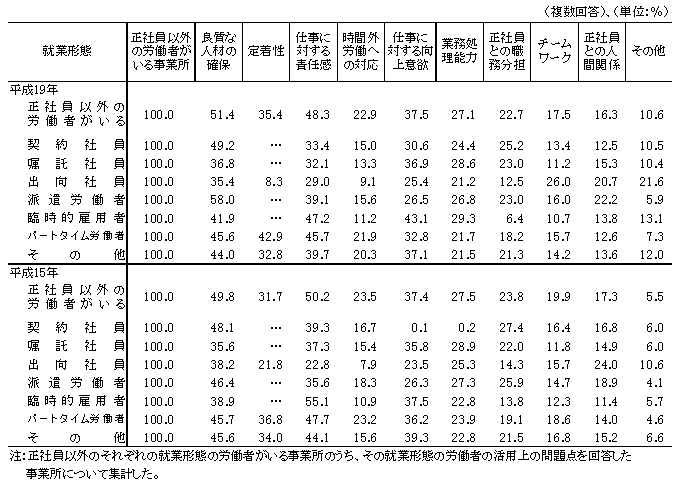
【個人調査】
1生活をまかなう主な収入源
生活をまかなう主な収入源について、就業形態ごとに男女別の労働者割合をみると、正社員では、男女ともに「自分自身の収入」とする割合が最も多く、それぞれ97.4%、52.6%となっている。正社員以外の労働者では、男では「自分自身の収入」が77.2%、女では「配偶者の収入」が63.2%と最も多い。
また、正社員以外の労働者について、就業形態別にみると、パートタイム労働者以外の就業形態では「自分自身の収入」とする割合が5割を超えている。一方、パートタイム労働者では「自分自身の収入」が28.6%と他の就業形態と比べて低く、代わって「配偶者の収入」とする割合が56.4%と高い。(表7)
表7生活をまかなう主な収入源(労働者割合)
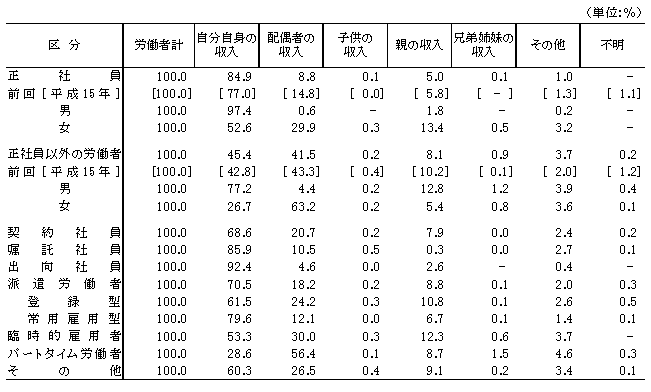
2就業の実態
(1)職種
就業形態ごとに労働者の職種別割合をみると、正社員では、「事務的な仕事」が35.4%(前回44.7%)と最も多く、次いで「専門的・技術的な仕事」19.4%(前回13.4%)、「管理的な仕事」19.1%(前回14.7%)の順となっている。男女別にみると、男では「管理的な仕事」、「事務的な仕事」の割合が多く、女では「事務的な仕事」、「専門的・技術的な仕事」の割合が多くなっている。
正社員以外の労働者では、「事務的な仕事」が26.1%(前回25.5%)と最も多く、次いで「サービスの仕事」20.8%(前回24.0%)、「生産工程・労務の仕事」18.1%(前回17.0%)の順となっている。男女別にみると、男では「生産工程・労務の仕事」、「サービスの仕事」の割合が多く、女では「事務的な仕事」、「サービスの仕事」の割合が多くなっている。
また、正社員以外の労働者について、就業形態別にみると、契約社員では「専門的・技術的な仕事」が27.0%、派遣労働者、出向社員、嘱託社員では「事務的な仕事」がそれぞれ38.6%、30.4%、19.7%、パートタイム労働者、臨時的雇用者では「サービスの仕事」がそれぞれ27.6%、19.9%と最も多い。(表8、第5図)
表8職種(労働者割合)
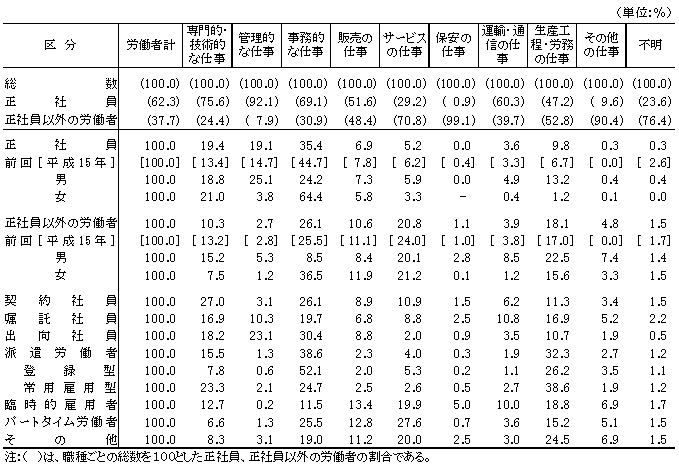
第5図職種別にみた正社員と正社員以外の労働者の構成(労働者割合)
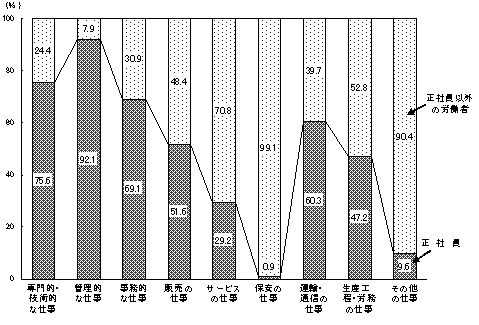
(2)9月の賃金総額(税込み)
就業形態別に9月の1か月間に支払われた賃金総額(税込み)をみると、正社員では「20〜30万円未満」が39.0%(前回33.3%)と最も多く、次いで「30〜40万円未満」25.5%(前回25.2%)、「40〜50万円未満」13.8%(前回10.3%)の順となっている。正社員以外の労働者では「10万未満」が40.5%(前回37.2%)と最も多く、次いで「10〜20万円未満」37.4%(前回40.8%)、「20〜30万円未満」14.2%(前回12.7%)の順となっている。
正社員以外の労働者について、就業形態別にみると、パートタイム労働者、臨時的雇用者では「10万円未満」とする割合がそれぞれ60.3%、51.1%、契約社員、派遣労働者、嘱託社員では「10〜20万円未満」がそれぞれ49.7%、42.2%、41.5%と最も多い。出向社員では「20万円以上」の割合が89.6%となっている。(表9)
表99月の賃金総額(税込み)階級(労働者割合)
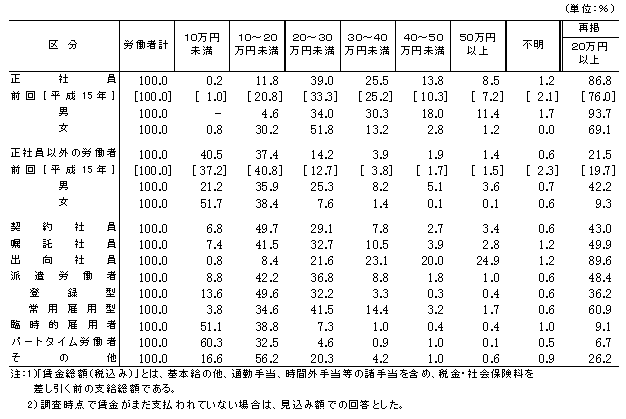
(3)仕事に関する資格・免許
就業形態別に現在の仕事に関する資格・免許の必要性をみると、「資格・免許がぜひ必要だと思う」割合では正社員が35.8%、正社員以外の労働者が17.1%となっている。
正社員以外の労働者について、就業形態別にみると、契約社員が31.2%と最も高く、次いで嘱託社員29.3%、出向社員27.2%の順となっている。(表10、第6図)
また、取得の有無についてみると、「現在の仕事で役立つ資格・免許を持っている」割合では正社員が50.8%(前回43.6%)、正社員以外の労働者が24.8%(前回24.6%)となっている。
正社員以外の労働者について、就業形態別にみると、嘱託社員が46.3%と最も高く、次いで出向社員44.6%、契約社員43.2%の順となっている。
さらに、役立つ資格・免許を持っていない労働者の取得の意志をみると、「役立つ資格・免許を取得したいと思う」割合では正社員が31.3%(前回29.2%)、正社員以外の労働者が23.1%(前回22.0%)となっている。(表11、第6図)
表10現在の仕事に関する資格・免許取得の必要性(労働者割合)
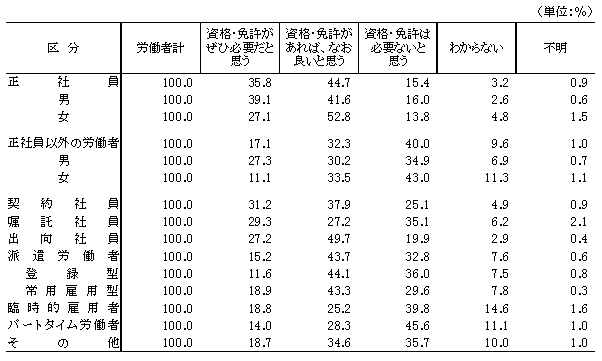
表11現在の仕事で役立つ資格・免許の取得の有無及び取得の意志(労働者割合)
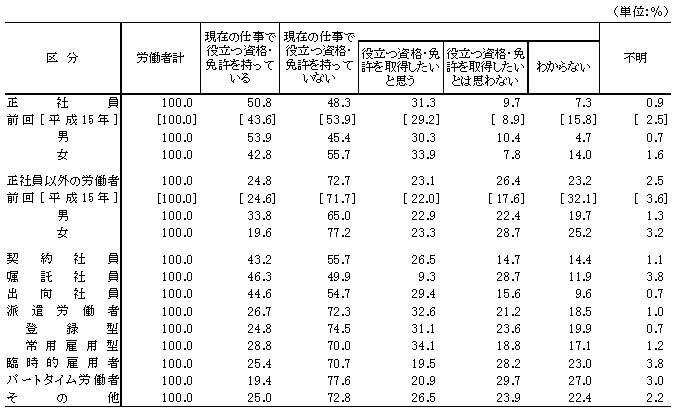
第6図現在の仕事に関する資格・免許の取得の必要性と取得状況(労働者割合)
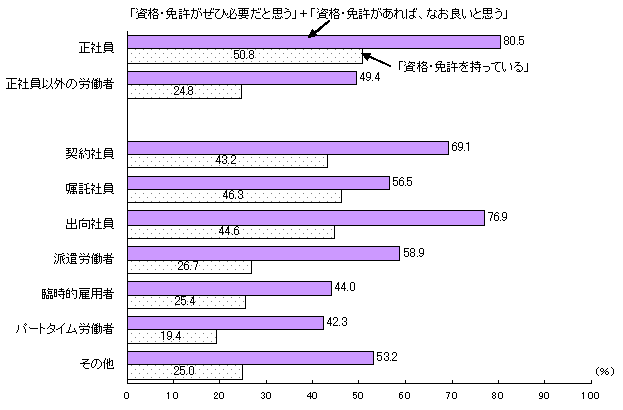
3仕事に対する意識
(1)現在の就業形態を選んだ理由
正社員・出向社員以外の労働者について、現在の就業形態を選んだ理由(複数回答3つまで)をみると、「自分の都合のよい時間に働けるから」が42.0%と最も多く、次いで「家計の補助、学費等を得たいから」34.8%、「家庭の事情(家事・育児・介護等)や他の活動(趣味・学習等)と両立しやすいから」25.3%の順となっている。
また、「正社員として働ける会社がなかったから」と答えた者の割合をみると、全体では18.9%だが、就業形態別では派遣労働者で37.3%、契約社員で31.5%となっている。年齢別には、25〜29歳でこの割合が高い。(表12、第7−1図、第7−2図)
表12現在の就業形態を選んだ理由(労働者割合)(正社員・出向社員以外の労働者)
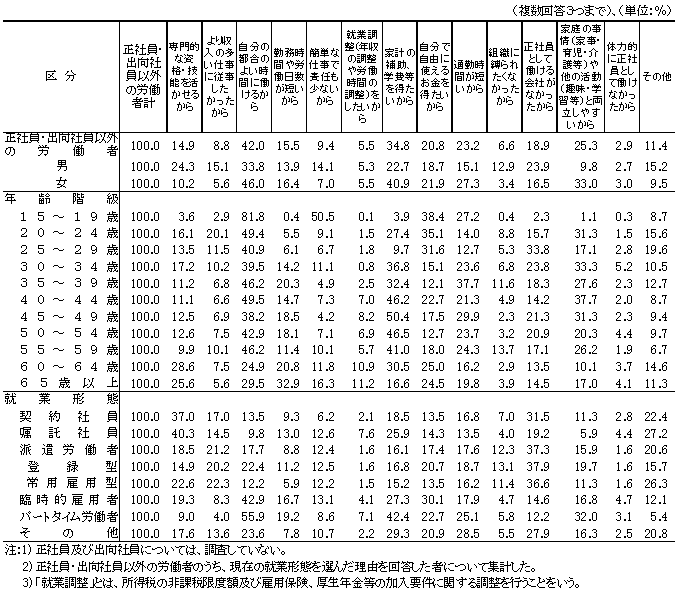
第7−1図現在の就業形態を選んだ理由(労働者割合、複数回答3つまで)
(正社員・出向社員以外の労働者のうち、回答があった労働者=100)
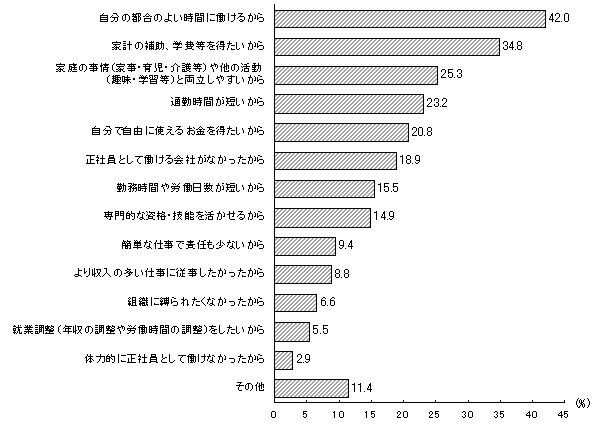
第7−2図主な就業形態の現在の就業形態を選んだ理由(上位8つまで)(労働者割合、複数回答3つまで)
(各就業形態の労働者のうち、回答があった労働者=100)
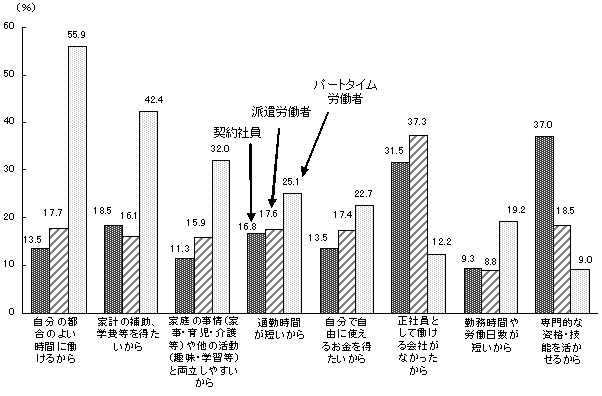
(2)今後の就業に対する希望
正社員以外の労働者について、今後の就業に対する希望をみると、「現在の会社で働きたい」が66.7%(前回73.7%)、「別の会社で働きたい」が14.1%(前回14.5%)となっている。
就業形態別にみると、「現在の会社で働きたい」の割合は出向社員で78.3%、「別の会社で働きたい」の割合は派遣労働者で27.4%とそれぞれ最も高い。(表13)
また、「現在の会社で働きたい」又は「別の会社で働きたい」と回答した者の今後の働き方に対する希望をみると、「現在の就業形態を続けたい」が68.8%、「他の就業形態に変わりたい」が30.6%となっている。
就業形態別にみると、「現在の就業形態を続けたい」の割合は嘱託社員で82.9%、「他の就業形態に変わりたい」の割合は派遣労働者で51.6%とそれぞれ最も高い。(表14−1、第8−1図)
なお、「他の就業形態に変わりたい」と希望している労働者のうち、90.9%(前回84.6%)が正社員を希望している(表14−2、第8−2図)。
表13今後の就業に対する希望(労働者割合)
(正社員以外の労働者)
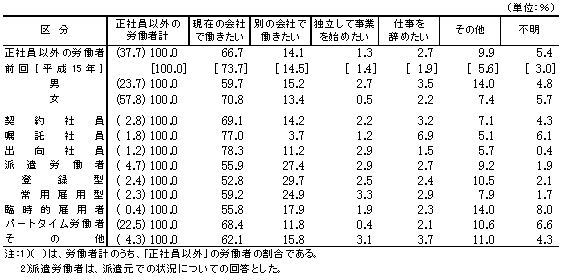
表14−1今後の働き方に対する希望(労働者割合)
(正社員以外で、「現在の会社」又は「別の会社」で働きたい労働者)
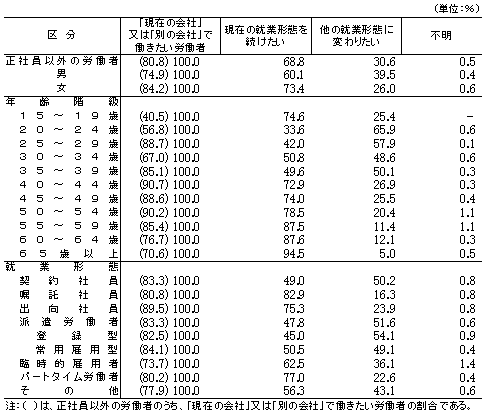
表14−2希望する就業形態(労働者割合)
(正社員以外で「他の就業形態に変わりたい」労働者)
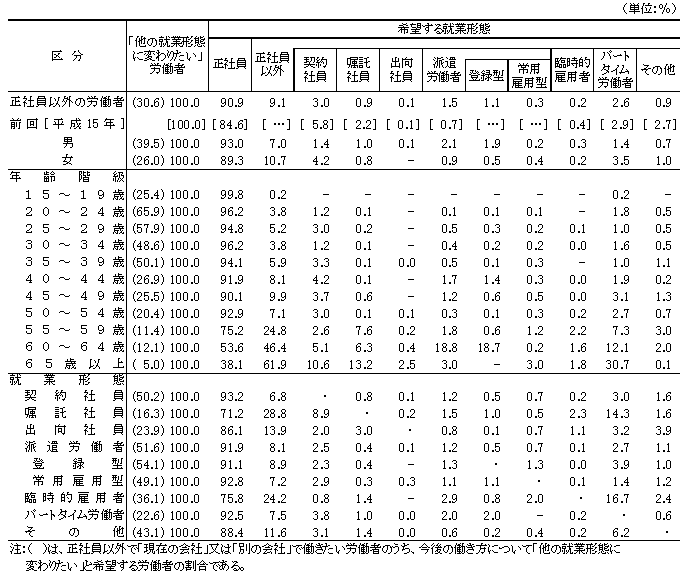
|
第8−1図他の就業形態に変わりたい(労働者割合) (正社員以外で「現在の会社」又は「別の会社」で働きたい労働者=100) |
第8−2図「正社員」になりたい(労働者割合) (正社員以外で「他の就業形態に変わりたい」労働者=100) |
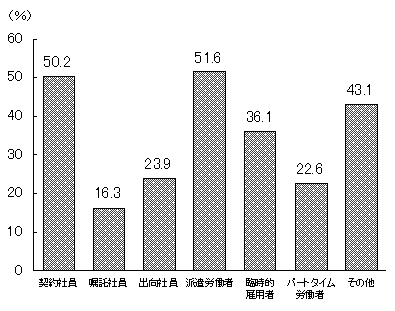
|
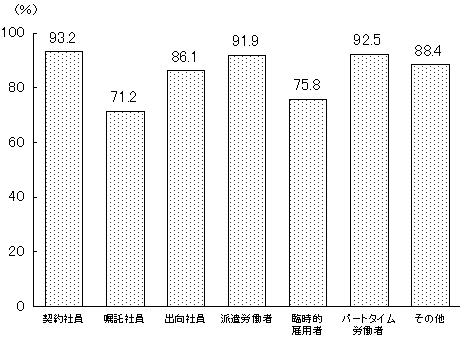
|
(3)正社員になりたい理由
正社員になりたいと回答した正社員以外の労働者について、正社員になりたい理由(複数回答3つまで)をみると、「正社員の方が雇用が安定しているから」が80.3%と最も多く、次いで「より多くの収入を得たいから」74.1%、「自分の意欲と能力を十分に活かしたいから」30.8%の順となっている。
また、上記以外の理由の中で特に就業形態で高いものは、「より経験を深め、視野を広げたいから」では出向社員が40.2%、「専門的な資格・技能を活かしたいから」では臨時的雇用者が23.8%、「家事・育児・介護等の制約がなくなる(なくなった)から」ではパートタイム労働者が22.7%と比較的多い。
また、年齢別にみると、「より経験を深め、視野を広げたいから」、「キャリアを高めたいから」では比較的若い層ほどこの割合が高い傾向がある。(表15、第9−1図、第9−2図)
表15正社員になりたい理由(労働者割合)
(正社員以外で、「正社員になりたい」労働者)
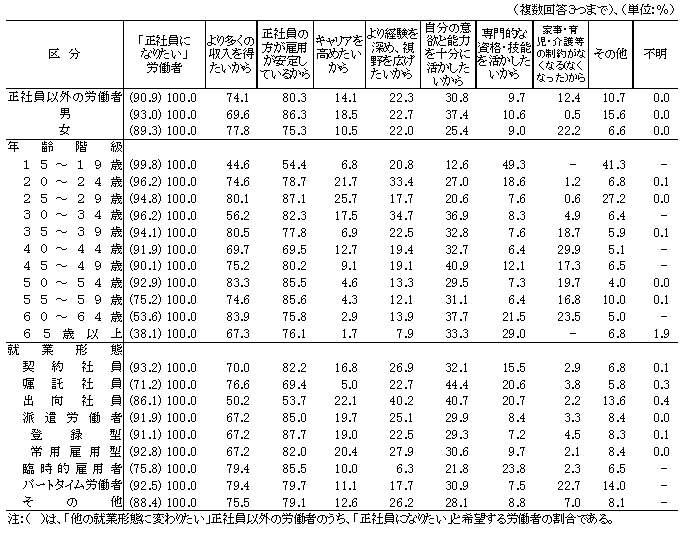
第9−1図正社員になりたい理由(労働者割合、複数回答3つまで)
(正社員以外で「正社員になりたい」労働者=100)
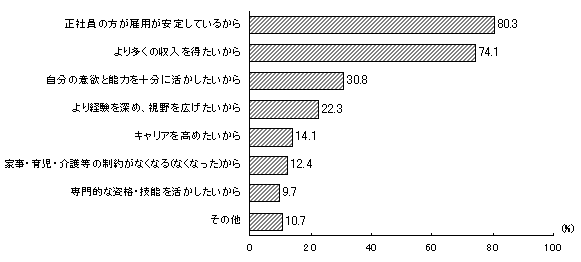
第9−2図主な就業形態の正社員になりたい理由(上位6つまで)(労働者割合、複数回答3つまで)
(各就業形態の労働者のうち、「正社員になりたい」労働者=100)
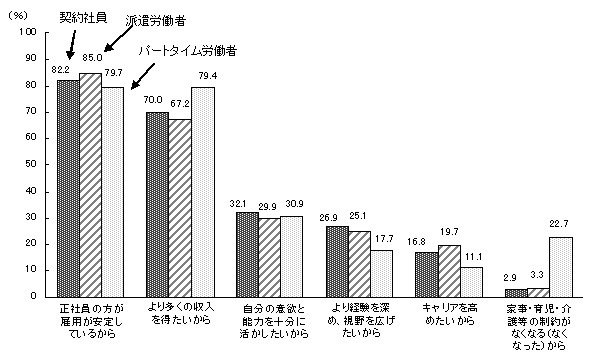
4現在の職場での満足度
現在の職場での満足度について、就業形態別にみると、正社員で「満足」の回答が多いのは「雇用の安定性」が26.7%、「仕事の内容・やりがい」が22.6%、「労働時間・休日等の労働条件」が20.4%となっている。正社員以外の労働者で「満足」の回答が多いのは「労働時間・休日等の労働条件」が26.8%、「仕事の内容・やりがい」が22.2%、「職場の人間関係、コミュニケーション」が20.7%となっている。
また、「満足」について、正社員と正社員以外の労働者を比較してみると、「雇用の安定性」、「福利厚生」、「教育訓練・能力開発のあり方」では正社員の方がその割合が高い。一方、「労働時間・休日等の労働条件」では正社員以外の労働者の方がその割合が高い。(表16、第10図)
表16現在の職場での満足度(労働者割合)
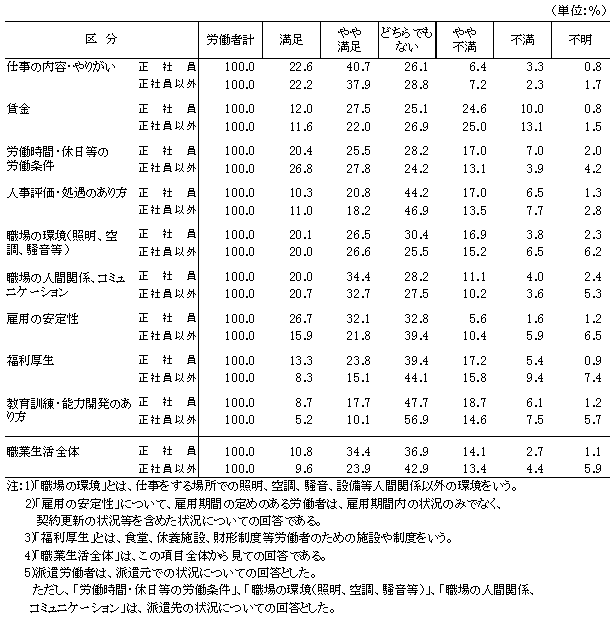
第10図現在の職場での満足度(労働者割合)