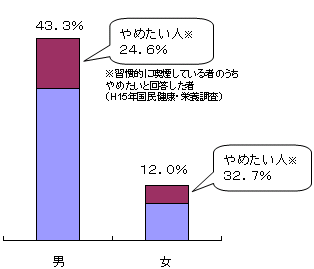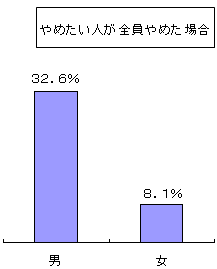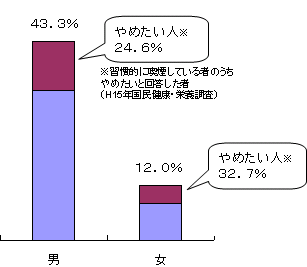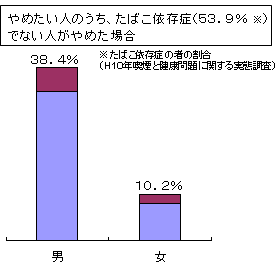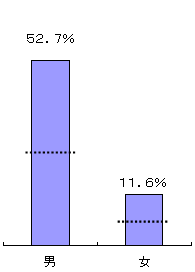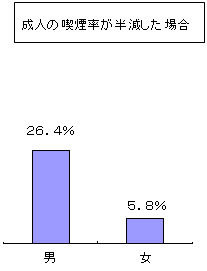たばこ対策に関する検討状況
厚生科学審議会等におけるたばこ対策に関する検討状況について
| H17年9月 | | 「今後の生活習慣病対策の推進について(中間とりまとめ)」(別紙)
厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(H17.9.15)
|
| 11月 | 第5回健康日本21中間評価作業チーム
| ○ | 現状値等の分析について |
| ○ | 未設定目標値について |
| ○ | 新規目標項目について |
第19回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会
| ○ | たばこ対策について
| ・ | 日本たばこ産業(株)及びフィリップモリスジャパン(株)からの意見陳述 |
|
| ※ 参考人出席: | 日本たばこ産業(株)
フィリップ モリス ジャパン(株) |
|
| H18年1月 | 第20回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会
| ○ | 平成18年度予算(案)及び平成18年度税制改正について
|
| ○ | その他
|
|
| 2月 | 第6回健康日本21中間評価作業チーム
| ○ | 現状値等の分析について |
| ○ | 未設定目標値ついて |
| ○ | 新規目標項目について |
|
| H18年3月 | 第21回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会
| ○ | たばこ対策について
| ・ | 政府における主なたばこ対策について |
| ・ | たばこ規制枠組条約締約国会議の報告について |
| ・ | 健康日本21中間評価作業チームにおける検討状況について |
| ・ | たばこ業界からの意見陳述について
日本たばこ産業(株)
フィリップ モリス ジャパン(株)
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン(株)
(社)日本たばこ協会 |
|
| ※ 参考人出席: | 日本たばこ産業(株)、
フィリップ モリス ジャパン(株)、
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン(株)、
(社)日本たばこ協会 |
|
| 6月 | 第22回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会
| ○ | たばこ対策について
| ・ | 最近のたばこに関する状況(報告) |
| ・ | たばこに関する施策一覧 |
| ・ | 喫煙率に関する数値目標について(諸外国、都道府県の実例) |
| ・ | 健康日本21中間評価作業チームにおける喫煙率の目標値検討状況 |
| ・ | 日本薬剤師会での新たな取組について(「禁煙運動宣言」の改定について) |
|
| ※ 参考人出席: | 日本たばこ産業(株)、
フィリップ モリス ジャパン(株)、
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン(株) |
|
| 8月 | 第7回健康日本21中間評価作業チーム
|
「今後の生活習慣病対策の推進について(中間とりまとめ)」
(平成17年9月15日)【抜粋】
たばこ対策(禁煙支援マニュアルの策定、普及、活用等)
| | たばこ対策については、平成14年12月25日の厚生科学審議会意見具申「今後のたばこ対策の基本的な考え方について」において、「国民の健康増進の観点から、今後、たばこ対策に一層取り組むことにより、喫煙率を引き下げ、たばこの消費を抑制し、国民の健康に与える悪影響を低減させていくことが必要である」と指摘された。
本年2月には、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約が発効したことを踏まえ、関係省庁の密接な連携の下にたばこ対策を促進するため、たばこ対策関係省庁連絡会議を設け、たばこ対策の充実強化を図るための体制整備を行ったところである。
たばこ対策に関しては、部会の議論の中で、(1)喫煙率の低下についての数値目標を設定すべき、(2)未成年者の喫煙防止対策として自動販売機の規制を大幅に強化すべき、(3)受動喫煙防止対策の取組が遅れている施設について積極的に対策を推進すべき、(4)受動喫煙防止対策の推進に向け、公共の場の禁煙・分煙の状況の調査を進めるべき、(5)たばこの価格又は税を引き上げ、その財源を生活習慣病予防対策に充当することを検討してはどうか、といった意見が出された。
また、本年5月の世界禁煙デー記念シンポジウムにおけるパネル討論においても、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会により同様の内容の決議文がとりまとめられている。
こうした意見については、関係省庁が十分に連携し、検討、さらには取組を進めていくことが必要である。また、特に喫煙率が高い20歳代から30歳代の女性を中心に禁煙の意思を有する者の自主的な禁煙の試みを積極的に支援するため、禁煙を支援するマニュアルを策定し、その普及、活用を進めるとともに、喫煙率の低下についての新たな数値目標の設定の検討も含め、国民全体の喫煙率の低下を目指すべきである。 |
健康日本21中間評価作業チームにおける喫煙率の目標値検討状況
<提案1> 「やめたい人」が全員やめた場合の喫煙率
| | | <ベースライン値※> |
| 男性 | 43.3% |
| 女性 | 12.0% |
|
| → |
|
|
<提案2> 「やめたい人」の一部がやめた場合の喫煙率
| | | <ベースライン値※> |
| 男性 | 43.3% |
| 女性 | 12.0% |
|
| → |
|
|
<提案3> 「成人の喫煙率」を半減させた場合の喫煙率
| | | <ベースライン値※> |
| 男性 | 52.7% |
| 女性 | 11.6% |
|
| → |
|
|
|
第22回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(H18.6.13)提出資料
<提案1> 「やめたい人」が全員やめた場合の喫煙率
| | | <ベースライン値※> |
| 男性 | 43.3% |
| 女性 | 12.0% |
|
| → |
|
|
H16年喫煙率
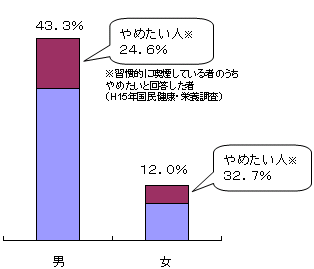 |
→ |
喫煙率の目標値
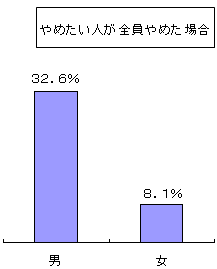 |
第22回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(H18.6.13)提出資料
<提案2> 「やめたい人」の一部がやめた場合の喫煙率
| | | <ベースライン値※> |
| 男性 | 43.3% |
| 女性 | 12.0% |
|
| → |
|
|
H16年喫煙率
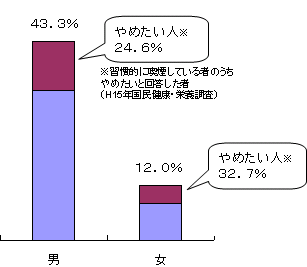 |
→ |
喫煙率の目標値
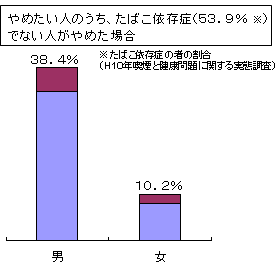 |
第22回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(H18.6.13)提出資料
<提案3> 「成人の喫煙率」を半減させた場合の喫煙率
| | | <ベースライン値※> |
| 男性 | 52.7% |
| 女性 | 11.6% |
|
| → |
|
|
H9年喫煙率
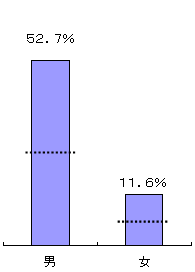 |
→ |
喫煙率の目標値
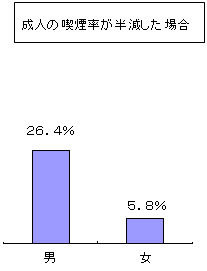 |
第22回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(H18.6.13)提出資料