ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 重要事例情報の分析について > 重要事例分析結果
重要事例分析結果
| 事例718:(手術中におけるブレーカ落ち停電) |
|
| 発生部署 (手術部門) キーワード(機器一般) |
|
| ■事例の概要(全般コード化情報より) |
| 発生月【7月】 発生曜日【水曜日】曜日区分【平日】発生時間帯【12時〜13時台】 発生場所【手術室】 |
|
| 患者の性別【女性】 患者の年齢【72歳】 患者の心身状態【麻酔中・麻酔前後】 |
|
| 発見者【当事者本人】 | |
| 当事者の職種【看護師】 当事者の職種経験年数【3年0ヶ月】 当事者の部署配属年数【3年0ヶ月】 |
|
| 発生場面 | 【開胸】 |
| (薬剤・製剤の種類) | 【】 |
| 発生内容 | 【診察・治療等のその他のエラー】 |
| 発生要因-確認 | 【】 |
| 発生要因-観察 | 【】 |
| 発生要因-判断 | 【】 |
| 発生要因-知識 | 【】 |
| 発生要因-技術(手技) | 【】 |
| 発生要因-報告等 | 【】 |
| 発生要因-身体的状況 | 【 】 |
| 発生要因-心理的状況 | 【 】 |
| 発生要因-システムの不備 | 【 】 |
| 発生要因-連携不適切 | 【 】 |
| 発生要因-勤務状態 | 【 】 |
| 発生要因-医療用具 | 【 】 |
| 発生要因-薬剤 | 【 】 |
| 発生要因-諸物品 | 【 】 |
| 発生要因-施設・設備 | 【施設構造物に関する問題】 |
| 発生要因-教育・訓練 | 【 】 |
| 発生要因-患者・家族への説明 | 【 】 |
| 発生要因-その他 | 【】 |
| 間違いの実施の有無及びインシデントの影響度【間違いが実施されたが、患者に影響がなかった事例】 | |
| 備考【 】 | |
■ヒヤリ・ハットの具体的内容
| 胸部下行大動脈の人工血管置換術の手術中に、手術室内のブレーカーが落ち、麻酔器、生体監視モニターの電源が切れた。(部屋の照明は切れなかった。人工心肺装置もまだつないではいなかった。)直ちに麻酔科指導医、リーダー看護師、主任看護師に報告し、ブレーカーを点検し復電させる前に出来るだけ不要な電源を切り、必要な電源については他の使用していない手術室から電源を確保した後復電させた。停電から復電までの時間は約3分であった。(ブレーカーは部屋から20mほど離れた位置にある。)停電時には手術操作に伴い患者は出血しており、血圧が低下していた状態であった。生体監視モニターの電源も切れたため、バイタルサインが観察できなかったが、復電後の患者の状態には大きな変化はなくそのまま手術は継続となった。 |
■ヒヤリ・ハットの発生した要因
|
■実施したもしくは考えられる改善策
|
■記入方法に関するコメント
| ブレーカーが落ちたときの状況を具体的に記載しましょう ME機器の台数は要因のところに記載されていますが、すべてが作動していた状況下でブレーカーが落ちたのでしょうか。ある機器を起動させた時に落ちたのでしょうか。具体的に分からないと原因究明と対策立案が困難です。 通常の手順だったかどうかも記載しましょう いつもと同じ使用機械台数、同じ手順だったのでしょうか。もし違いがあれば、そのことも要因の一つと考えられます。 |
■改善策に関するコメント
| 臨床工学士の役割 臨床工学士が手術室のME機器管理を行うことが必要です。事前に使用する機器の電気容量のシミュレーションも臨床工学士に行ってもらいましょう。 施設設備上の改善
ME機器使用上の注意
【参考資料】 「もっと関心をもとう『病院の電気設備』」クリニカルエンジニアリング,Vol.7,秀潤社,1996 |
| 事例734:(指示受けにおけるコミュニケーションエラー) |
|
| 発生部署 (外来部門一般) キーワード(与薬(注射・点滴)、情報・記録) |
|
| ■事例の概要(全般コード化情報より) |
| 発生月【 】 発生曜日【 】曜日区分【 】発生時間帯【 】 発生場所【 】 |
|
| 患者の性別【 】 患者の年齢【 】 患者の心身状態【 】 |
|
| 発見者【 】 | |
| 当事者の職種【 】 当事者の職種経験年数【 】 当事者の部署配属年数【 】 |
|
| 発生場面 | 【 】 |
| (薬剤・製剤の種類) | 【 】 |
| 発生内容 | 【 】 |
| 発生要因-確認 | 【 】 |
| 発生要因-観察 | 【 】 |
| 発生要因-判断 | 【 】 |
| 発生要因-知識 | 【 】 |
| 発生要因-技術(手技) | 【 】 |
| 発生要因-報告等 | 【 】 |
| 発生要因-身体的状況 | 【 】 |
| 発生要因-心理的状況 | 【 】 |
| 発生要因-システムの不備 | 【 】 |
| 発生要因-連携不適切 | 【 】 |
| 発生要因-勤務状態 | 【 】 |
| 発生要因-医療用具 | 【 】 |
| 発生要因-薬剤 | 【薬剤名が似ていた】 |
| 発生要因-諸物品 | 【 】 |
| 発生要因-施設・設備 | 【 】 |
| 発生要因-教育・訓練 | 【 】 |
| 発生要因-患者・家族への説明 | 【 】 |
| 発生要因-その他 | 【】 |
| 間違いの実施の有無及びインシデントの影響度【 】 | |
| 備考【 】 | |
■ヒヤリ・ハットの具体的内容
| 昼食前の血糖値が高値であり、1年目NsがDrに指示をもらう。ヒューマリンRとの指示であり元々、ヒューマカートRを使用していたため、おかしいと思ったが確認しなかった。(先週の指示欄には、ヒューマリンと記載されており、又Drの指示であり間違いはないと思った。)他のNsが、その指示を引き継ぎ患者にヒューマリンRを投与した。後で、他Nsより指摘を受けてDrに確認するとヒューマカートRであった。 |
■ヒヤリ・ハットの発生した要因
| おかしいと思った時点で、Drに確認できなかった。引継ぎをうけた後も、Drに確認できていなかった。 |
■実施したもしくは考えられる改善策
| おかしいと気付いた時点で、すぐに確認していく。 |
■記入方法に関するコメント
■ヒヤリ・ハットの具体的内容 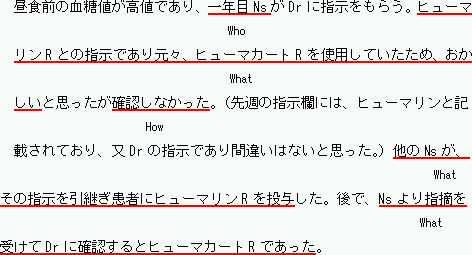 上記に示す通り、「いつ」、「何処」という要素の記入がなされていないため、事例状況を把握できないことになってしまいます。本事例を記入された方も、ヒヤリ・ハットの要因を理解し、同様のヒヤリ・ハットが起きないようにする手段を提言できないのではないでしょうか。大切な時間を割いて記入されるのですから、せめて同じ事が起きないよう、記入すべき事案の経過に基づき、どなたがお読みになられても状況を理解できるようヒヤリ・ハットの具体的内容を記入するよう心がけましょう。 また、全体的に、一年目Nrが医師から指示を受けた時、おかしいと思いながら確認をしなかったとことに重点をおいた記載になっています。ヒヤリ・ハット発生状況を具体的に書くためには、本事例に直接的に関わった本人の行動、心理状態だけに着目するのではなく、その他の情報を客観的に記入することが重要です。不十分な情報だけでは根本的な要因分析をし、再発防止につなげることが出来ません。その他の情報として必要なものは、SHELモデルや4M4Eにある要因だけでなく、嶋森らの「コミュニケーションエラーの発生要因に関する研究」報告書にある12の背景要因1)なども活用しましょう。まずは、個人的な情報や要因以外のシステム上のエラーに関する情報を網羅することが大切です。 また、インスリン製剤を使用するときの普段のプロトコールや手順と比較して、本事例の対応方法は異なっていたのでしょうか。通常の手順と比較し、手順を逸脱していないか、逸脱している場合、その理由は何か情報を追加しましょう。 本事例は、報告内容の不足を指摘させていただけること、そして、最近、医療機関勤務医療従事者のコミュニケーション欠如により発生する重大な医療事故が散見されることから、今後の医療事故防止に重要な示唆を与えることとなりましょう。本報告の記入方法を分析し、ヒヤリ・ハットの具体的内容が伝わりやすくなるよう考えてみましょう。 【参考資料】
|
■改善策に関するコメント
| 医師、薬剤師、看護師およびその他の医療の担い手は、それぞれの専門性に基づき業務分担しているはずであり、互いの専門性を尊重し、同一医療機関内で「患者」に最善の医療を提供することに集約すべきでしょう。本件は業務上「おかしい」と思った時点や引継ぎを受けた後も医師に確認できていない理由を明確にしていないことから、「確認」できない「風習」あるいは「慣習」が職場環境を支配している可能性も窺えます。医療機関の長は早急に古く悪しき風習や慣習を除き、職員間の連携を良好に導くため患者本位の医療に必要な具体策を職員と共にディスカッションし、実行することが推奨されます。 また、改善策が個人の努力のみになっています。医療はチームで実施しているので、システム上のエラーと個人のヒューマンエラーへの対策の双方を検討する必要があります。 システム上のエラー対策
個人のヒューマンエラーへの対策 「おかしい」とリスクを感知していながら、漫然と業務を実施しています。日本看護協会「看護業務基準」(1997)では、医師の指示を実施するに当たり、「医師の指示の理論的根拠と倫理性」、「適切な手順」、「患者の観察と対応」について専門職独自の判断をするよう明記されています。看護業務基準を遵守出来るよう訓練しましょう。 |
| 事例747:(インスリンの過量与薬) |
|
| 発生部署 (入院部門一般) キーワード(与薬(注射・点滴)) |
|
| ■事例の概要(全般コード化情報より) |
| 発生月【 】 発生曜日【 】曜日区分【 】発生時間帯【 】 発生場所【 】 |
|
| 患者の性別【 】 患者の年齢【 】 患者の心身状態【 】 |
|
| 発見者【 】 | |
| 当事者の職種【 】 当事者の職種経験年数【 】 当事者の部署配属年数【 】 |
|
| 発生場面 | 【 】 |
| (薬剤・製剤の種類) | 【 】 |
| 発生内容 | 【 】 |
| 発生要因-確認 | 【 】 |
| 発生要因-観察 | 【 】 |
| 発生要因-判断 | 【 】 |
| 発生要因-知識 | 【 】 |
| 発生要因-技術(手技) | 【 】 |
| 発生要因-報告等 | 【 】 |
| 発生要因-身体的状況 | 【 】 |
| 発生要因-心理的状況 | 【 】 |
| 発生要因-システムの不備 | 【 】 |
| 発生要因-連携不適切 | 【 】 |
| 発生要因-勤務状態 | 【 】 |
| 発生要因-医療用具 | 【 】 |
| 発生要因-薬剤 | 【 】 |
| 発生要因-諸物品 | 【 】 |
| 発生要因-施設・設備 | 【 】 |
| 発生要因-教育・訓練 | 【 】 |
| 発生要因-患者・家族への説明 | 【 】 |
| 発生要因-その他 | 【】 |
| 間違いの実施の有無及びインシデントの影響度【 】 | |
| 備考【 】 | |
■ヒヤリ・ハットの具体的内容
| 夕食前の血糖値が、304mg/dlだった為スケールに従い次行の点滴内のインスリン量を増やす際に5単位のところを50単位増で点滴内に混入し更新した。 |
■ヒヤリ・ハットの発生した要因
| 残務が沢山あり、焦っていたまた、起床後からの時間経過が長く疲れていた。焦りから、指示を目で追っていた。単位の記号が慣れないものであり、ゼロに見えてしまった。患者対応などと重なり慌てていた為、おかしいと気付かなかった。 |
■実施したもしくは考えられる改善策
| 焦らない。業務を時間内に出来るよう工夫する。慎重に指示を確認する。 |
■記入方法に関するコメント
| この事例は食前の血糖値が高かったことから、医師の約束指示であるスライディングスケールに従って、混入したインスリンが10倍の量だったと解釈しました。 ヒヤリ・ハットの具体的内容では、患者の病名、状況、どのような血糖コントロールの患者か、混入前の点滴内にはどのタイプのインスリンが何単位入っていたのか、混入したインスリンのタイプ、また発見までに何単位入ってしまったのか、そして過量与薬の発見に至った経緯、つまり、いつ、誰が、どのように発見したのか、その時の患者は何らかの症状を示していたのか、その後の過量与薬の影響、などを記述する必要があります。 ヒヤリ・ハットの発生した要因では、発生時間は夜勤帯で、当事者は日勤者であると考えられますが、この患者の受け持ち看護師だったのかどうか、この行為に対する経験の有無、インスリンの種類や作用、使用量などの知識の有無についてはどうだったのでしょう。 また、他の患者も含めて夕食前の血糖コントロールに関わる責任体制、血糖値とスケールの確認、実施時のダブルチェック体制、スケールの表示が慣れないもので0に見えたとありますが、指示スケールの表示の仕方が手書きなのか、スケールが変更される場合の職員間の共有の仕方なども記述されると対策につながります。 |
■改善策に関するコメント
| スケールの表示の仕方とスケールの統一 まずスケールの表示の仕方は誰が見ても見間違いの無いように、インスリンのタイプや量をきちんと明記することです。インスリンの単位を表すときに「U」と「E」の書き表し方があると思いますが、手書きの「U」が0に見えたことも考えられます。「E」は0と見間違う可能性が低いと考えられますので、単位の表示の取り決めをしておくことも必要でしょう。 医師ごとのスケールを可能な限り医師間で統一して、インスリンのタイプを整理し薬剤の種類を制限することも一策です。スケール変更に当たっては職員間の共有の仕方や新人職員も理解できるように教育システムを整えることが必要です。 インスリン用注射器の選択 インスリンは濃度の異なる製剤が販売されていました。例えば日本では20単位/ml、40単位/ml、100単位/mlが使われており、製剤の取り違えによる事故の可能性が指摘されていました。これを受けてIDF(国際糖尿病連合)は、100単位/ml製剤へ統一することとし、世界的に移行を進めてきました。 日本においても、100単位/ml製剤への移行のため、40単位/ml製剤を2004年4月薬価削除とし、2004年3月まで経過措置品目扱いとなりました。 上記理由から全国施設で切り替えが始まり、関連して、注射器も従来主流であった40単位/ml用から100単位/ml用へ切り替わっています。 100単位/ml用注射器には、1目盛りが2単位の100単位/ml注射器と1目盛りが1単位の50単位/0.5ml注射器がありますが、インスリンの1回指示量が50〜100単位になることは多くないこと、また、注射器の1目盛りが1単位と分かり易いため、50単位/0.5ml注射器を選択することが望ましいと考えます。 この事例を考えた場合、0.5ml注射器であれば、見間違った50単位は内筒が外れるほどの量を吸わなければなりません。無意識の行動においても、通常用いられる単位との差が大きいほど間違いに気付き易いと考えられます。 業務の整理 発生時間が日勤と準夜勤の交替時間で、処理しなければならない課題も集中し、タイムプレッシャーがあります。交代時間に集中しそうな業務を洗い出して、日勤と準夜勤の業務分けの検討も必要でしょう。 教育とチェックシステムの確立 当事者が50単位に疑問を持たなかったことは、知識や経験が無かったということでしょうか。新人、勤務交代者の教育プログラムの整備、実施が必要です。 また血糖値測定から実施まで一連の行為を、一人の看護師が行うとエラーに気付きにくいため、ダブルチェック体制など第三者の目を加えたシステムとすることも必要でしょう。継続的に血糖コントロールが必要で、患者が理解力のある人なら、自身の血糖やインスリンについての知識を持ち、確認の流れの中に参加できるようにすることも患者教育の一環として有効です。 血糖値上昇のアセスメント 最近スケールは良く使われるようになりましたが、血糖が高かったら即インスリンと、スケールに依存するのではなく、なぜ血糖が上昇したのかアセスメントすること、医師と話し合いを持ち、適切な血糖コントロールとインスリンの選択をしていくことが必要です。 |
| 事例820:(研修医の処方による散剤の10倍量投与) |
|
| 発生部署 (入院部門一般) キーワード(処方) |
|
| ■事例の概要(全般コード化情報より) |
| 発生月【 】 発生曜日【 】曜日区分【 】発生時間帯【 】 発生場所【 】 |
|
| 患者の性別【 】 患者の年齢【 】 患者の心身状態【 】 |
|
| 発見者【 】 | |
| 当事者の職種【 】 当事者の職種経験年数【 】 当事者の部署配属年数【 】 |
|
| 発生場面 | 【 】 |
| (薬剤・製剤の種類) | 【 】 |
| 発生内容 | 【 】 |
| 発生要因-確認 | 【 】 |
| 発生要因-観察 | 【 】 |
| 発生要因-判断 | 【 】 |
| 発生要因-知識 | 【 】 |
| 発生要因-技術(手技) | 【 】 |
| 発生要因-報告等 | 【 】 |
| 発生要因-身体的状況 | 【 】 |
| 発生要因-心理的状況 | 【 】 |
| 発生要因-システムの不備 | 【 】 |
| 発生要因-連携不適切 | 【 】 |
| 発生要因-勤務状態 | 【 】 |
| 発生要因-医療用具 | 【 】 |
| 発生要因-薬剤 | 【 】 |
| 発生要因-諸物品 | 【 】 |
| 発生要因-施設・設備 | 【 】 |
| 発生要因-教育・訓練 | 【 】 |
| 発生要因-患者・家族への説明 | 【 】 |
| 発生要因-その他 | 【】 |
| 間違いの実施の有無及びインシデントの影響度【 】 | |
| 備考【 】 | |
■ヒヤリ・ハットの具体的内容
| 研修医師が、担当していた患者様の内服薬(散剤)の投与量の計算を誤り10倍量で処方し、薬剤監査でも気付かず調剤され看護師がそのまま3日間投与した。 |
■ヒヤリ・ハットの発生した要因
| 担当医が変わり処方記載法が統一されていなかったため薬剤の成分量で記載されるものと思い込んでしまった。前担当医は総量で記載していたため投与量を誤り10倍量となってしまった。上級医への確認不足もあった。 |
■実施したもしくは考えられる改善策
|
■記入方法に関するコメント
| 事案について簡潔に記されていますが、「実施したもしくは考えられる改善策」に「多剤併用処方をしないよう工夫する」と報告者が記した背景は、事案から読み取れませんでした。また、薬剤師が薬剤の量の誤りを発見できなかった背景についても、事案から読み取れませんでした。 |
■改善策に関するコメント
| 処方の業務フロー 処方・調剤・投薬・与薬は、医師・薬剤師・看護師が関わる業務です。この業務の流れを用いられる物と情報のあらましと共に図に示しました。 「処方箋作成」での誤りのパターン 医師が処方箋を作成する場合に発生する誤りのパターンは、ヒューマンエラーの3パターン(Random Error, Systematic Error, Sporadic Error)それぞれが見られます。Random Errorの典型としては錬度が不十分な医師が十分な知識無く、不適切な薬剤を処方したり、不適切な量の薬剤を処方するというものがあります。Systematic Errorの典型としては、類似する薬品名(例:アマリール、アルマール)を取り違えるというものがあります。Sporadic Errorには多様なものがありえます。 本事例での原因としては、処方医が薬剤の常用量を十分知っていなかったというKnowledge Baseの誤り(Random Error)の部分、医療機関内での散剤に関する処方箋記載の規約が存在しなかったというRule Baseの誤り(Systematic Error)が想定されます。 Random Errorに対する対策としては、教育・訓練がその主を占めるのが原則ですが、未熟な作業者(この場合は研修医)が作業を行う場合は十分な監督の下に行うのが当然です。多くの病院で、処方は研修医が単独で行う作業として許されていますが、妥当なのでしょうか。 Systematic Errorに対する対策としては、手順の整備がその主を占めます。この事例でいえば、医療機関内での散剤に関する処方箋記載の規約を定めるというのが手順の整備に当たります。手順は整備するだけでは実効がありません。手順を修正した時点で関連する職員に教育し、さらに新規採用者に教育を提供する必要があります。ある大学では、医学部の学生と研修医に対して同様の基準で処方箋の記載の仕方を指導し、さらに実際に処方箋を書かせてその内容を添削するという実習が研修医として勤務する前に実施されています。(資料) 散剤の処方を行うとき、原末量(成分量、力価)で記載するべきか、調製済み薬剤の製剤量で記載するべきかは、悩ましい問題です。 調製済み薬剤(例:テオドール顆粒)が多く販売される以前は、散剤の成分は原末から記載せざるを得ず、原末の種類と量に賦形の方法(賦形剤の種類と量)を共に記していました。グッドマンギルマンの薬理書では、今もこの種の記載方法が紹介されています。しかし、現在は単成分の調製済み薬剤(例:テオロング顆粒)のみならず、複数成分の調製済み薬剤(例:PL顆粒)が数多く販売されており、製品としては原末よりも使用される頻度が高くなっているといわざるを得ません。 このような状況では、商品名を明記した上で製剤量を主として表記に用い、成分量を用いる際にはその旨明記することの方が妥当といえるかもしれません。 国内で表記方法を統一することが可能であればそれが望ましいとはいえますが、たとえそのような統一がされたとしても、医療従事者全体に十分な浸透を図るまでには年余を要しますので、日々診療する医療従事者は、医療機関ごとの原則を作り、それを遵守していくことが現実的な対応と考えられます。 処方箋鑑定での誤りのパターン 処方箋に表示された情報の曖昧さを吟味し、処方医に照会し明確化するのが薬剤師による処方箋鑑定の主たる機能ですが、医薬に関する専門家として医師と同等以上の知識と経験をもって医薬の使用の妥当性を吟味するのも薬剤師に期待されている役割です。本事例では、薬剤師が何故この誤りを見出せなかったのかについては、参考となる情報が示されていませんが、医療機関内での散剤に関する処方箋記載の規約が存在しなかったというRule Baseの誤り(Systematic Error)であった可能性があります。記載上不明確であれば、不明確な部分を明確にすることが薬剤師に期待されていたと考えることもできます。 散剤・水剤・軟膏の特徴 錠剤、カプセル剤の場合は、調剤後も薬剤の形は変わりなく、処方箋の内容と一致しているかを判断することが容易ですが、本事案のような散剤、そしてこれ以外にも、水剤、混合した軟膏は、処方箋の内容と製剤が一致しているかを判別することは困難になるという特徴があります。したがって、これらの形態の薬剤の場合は、調剤後に独立して監査を行うという作業工程では、製剤の誤りを発見できないという特徴があり、調剤の誤りを防止するためには、これらの形態の薬剤にあわせた監査方法を開発・採用する必要があります。たとえば、散剤を賦形するまえ、水剤を混合する前に監査し、監査者が混合するという業務プロセスを考慮するのも、各種の状況が適すれば対策の一案であるかもしれません。 なお、いわゆる処方から離れますが、注射の混合の作業でも同様の問題をかかえていることを意識しておく必要があります。 【図】処方の業務フロー 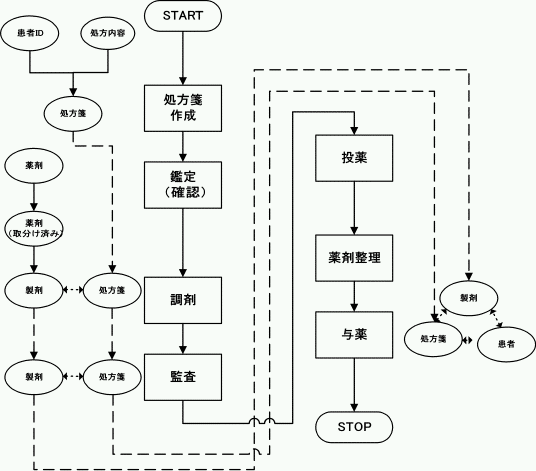 【資料】処方箋の書き方 Pre-BSLガイダンス 処方箋の書き方
医師法 第22条(処方箋の交付義務) 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんを必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
医師法施行規則第21条(処方せんの記載事項) 医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 2. 記載方法 2.1 共通項目 患者の氏名,年齢,発行の年月日,(処方箋の)使用期間(*),記名押印又は署名 病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所(*) 麻薬処方箋の場合は、患者の住所(*)、処方医の麻薬施用者免許番号 (*)は院内処方の場合に省略することが許される項目 2.2 薬名、分量、用法、用量の書き方 2.2.0.1 協定(約束)処方 各医療機関の内部で、しばしば使われる処方の組を協定処方とよび、各医療機関内の処方箋では協定処方の名称を記すことで、詳細な記載を省略する慣習がある。協定処方は、医療機関の内部で用いるものなので、院外処方では使用してはならない。 2.2.0.2 混合剤 水剤、散剤は、特に別々に渡すよう指定されず、混合しても配合が変化しない場合は、混合して渡される。 外用薬のうち軟膏を混合する場合には、混合(mix)と明示する。 2.2.1 薬名 薬名は、販売名を記入するのが一般的である。(しかし、一般名を記載してもよい。この場合、どの会社の薬品が調剤されるかは、薬剤師の判断に任される。) 記載する文字は、日本語の文字で表記をするのが一般的である。(正しい表記であればアルファベットで記すことは禁じられていないが、推奨はされない。) ××大学附属病院では、処方箋に薬名を記すにあたって、販売名で記し、カタカナ・漢字で記すことになっている。 例) 販売名 メプチン錠 一般名 塩酸プロカテロール 同一名称の薬剤で、剤型(錠、カプセル、散など)、含有量、含有濃度、含有比率の異なる複数の規格が存在する場合は、どの剤型規格であるかを明示する。
2.2.2 分量 内服(服用)の場合は、一日総量を書く。 外用の場合は、一回の使用量を書く。 (注意) 数回に分けて使用する外用薬の場合で、一回の使用量を特定できないときは、処方総量を記す。 薬剤の量は、製剤量で記すのが原則である。 例) 1錠、1カプセル、1g、1ml、1本 (注意!!) 散剤の時には、製剤量であることをはっきり意識して書かなければ、倍量投与等になってしまう。
単位は略さない。 (ただし、歴史的には以下のように取り扱われてきたので、他人が書いた処方を判読する際の参考として知っておくことが必要である。現在は、規格が過去に比べて複雑化しているため、単位を略すべきではない。) 省略されている時、
2.2.3 用法・用量 2.2.3.1 内用
薬量を成分量で記す場合は、(成分量)(原末)などと付記すること。
水剤の場合 顆粒と同様に扱う。
テオドールシロップは1ml中にテオフィリンが20mg含まれる。
(例)販売名「プレドニン錠」(一般名 プレドニゾロン)(一錠あたりプレドニゾロンを5mg含有する)を、一日10mg 隔日で内服するよう、30日分処方する場合
一回の服用量を記し、服用時期を記し、日数に代えて、回数を記す。
2.2.3.2 外用
(1) 一回の使用量を記し、使用時期を記し、使用回数を記す。
(2) 一回の使用量が示しがたい場合は、総量を記し、使用方法を記す。
(3) 内服薬と同様に毎日定量使用する外用薬については、稀に内服と同様の記載方法がされることがある。(現時点では、推奨しない。)
3. 略語 上記の様に、日本語で記載することが原則である。しかし、歴史的に以下のような略語が用いられてきた。 これらの使用は推奨しないが、現在でも使用される頻度の高い略語を読み取る際の参考として掲げる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事例1382:(物品管理の不備による新生児仮死状態への対応遅れ) |
|
| 発生部署 (入院部門一般) キーワード(救急処置・酸素吸入) |
|
| ■事例の概要(全般コード化情報より) |
| 発生月【8月】 発生曜日【金曜日】曜日区分【平日】発生時間帯【4時〜5時台】 発生場所【分娩室】 |
|
| 患者の性別【男性】 患者の年齢【0歳】 患者の心身状態【麻酔中・麻酔前後】 |
|
| 発見者【他職種者】 | |
| 当事者の職種【助産師】 当事者の職種経験年数【3年4ヶ月】 当事者の部署配属年数【3年4ヶ月】 |
|
| 発生場面 | 【その他の医療機器等の使用・管理に関する場面、アンビューバック】 |
| (薬剤・製剤の種類) | 【】 |
| 発生内容 | 【機器の点検管理ミス】 |
| 発生要因-確認 | 【確認が不十分であった】 |
| 発生要因-観察 | 【】 |
| 発生要因-判断 | 【判断に誤りがあった、その他】 |
| 発生要因-知識 | 【知識が不足していた】 |
| 発生要因-技術(手技) | 【】 |
| 発生要因-報告等 | 【】 |
| 発生要因-身体的状況 | 【 】 |
| 発生要因-心理的状況 | 【慌てていた】 |
| 発生要因-システムの不備 | 【 】 |
| 発生要因-連携不適切 | 【看護職間の連携不適切】 |
| 発生要因-勤務状態 | 【 】 |
| 発生要因-医療用具 | 【管理が不十分だった】 |
| 発生要因-薬剤 | 【 】 |
| 発生要因-諸物品 | 【 】 |
| 発生要因-施設・設備 | 【】 |
| 発生要因-教育・訓練 | 【 】 |
| 発生要因-患者・家族への説明 | 【 】 |
| 発生要因-その他 | 【】 |
| 間違いの実施の有無及びインシデントの影響度【その他】 | |
| 備考【 】 | |
■ヒヤリ・ハットの具体的内容
| 深夜勤で分娩係をし、分娩経過中のA氏を受け持った。2〜3分おきに緊満があったが20秒ほどの持続で、子宮口は順調に開き、破水後は徐々に児の下降も見られていた。Stの高いうちから心音が80台に低下することもあったが体位交換や呼吸法の促し、酸素投与により回復が見られ、ずっと付き添いながら呼吸法の誘導をしていた。St+3になるころからVDが頻発したが回復が見られるため児の下降によるものと判断した。児娩出まえにベースが200まで上昇しLDが見られた。児娩出後、吸引、タッピングするが筋緊張見られず臍帯切断しインファントウォーマーへと運んだ。しかしアンビューバックにマスクが装着されておらず、LDR倉庫よりもう一つを持ってきて使用した。また、母に酸素を使っていたためインファントに接続が出来ていなかった。そのため、処置が遅れた。(Apgar3/6) |
■ヒヤリ・ハットの発生した要因
| アンビューにマスクがついているという思い込みがあり、外れていることに気が付かず用意していた。また、使う可能性が高いと判断できていなかった。分娩の用意をした時点での確認不足があった。児の状態を出生時に判断し他のスタッフに接続を母からベビー側に変更してもらうよう依頼できていない。 |
■実施したもしくは考えられる改善策
| 用意の時点での確認を必ずもれなく行い、実際に使ってみる。出生児の状態の判断、伝達を正確にすばやく行う。 |
■記入方法に関するコメント
時間経過にそって簡潔に書かれていると思います。以下の点についてさらに記述すると具体的な改善策をたてることが容易になるでしょう。
|
■改善策に関するコメント
| この事例は、新生児仮死の処置としては比較的多い対処ですので緊急処置マニュアルのようなもので準備、報告、連携システムが徹底される必要があると思います。 定期的な物品管理とチェック体制 まず、チェックリスト等で勤務が始まる前にチェックすることを習慣化して業務内容に盛り込むことが効果的でしょう。また、使用後は、どのように補充し誰がセットするのか等、実践で活用できるマニュアルを作成しましょう。 インファントウォーマー上を急変時に対応する場と考えたなら、必ず救急蘇生ができる物品準備の点検が各勤務帯で管理されている必要もあるでしょう。さらに、この事例ではLDR室に物品を取りに行っていますが、補充物品がすぐ出せるところにないというのは非常に重篤な結果をもたらすことだと思います。補充、および準備がない場合でもすぐ取り出せる場所に数個配置しておく必要があります。 この事例の発生時間は4時〜5時となっています。夜間帯の人員の少ない状況になってからではなく、勤務交代時の人員が確保されている時間帯で基本設備をチェックするなど周産期全体で話し合って実用的なマニュアルを作成することが重要だと思います。 Y字アダプターの使用による酸素確保 また、母体に酸素を使用しているとインファントウォーマーに酸素が配管できないという内容から、ハード面でも改善する点があるのではないかと思われます。あるいは、要因の中に「使う可能性が高いと判断できていなかった。」とありますが、常に母体が重症な合併症を発症し、新生児仮死に至るケースを想定し、酸素ボンベを常備するなどの対策が必要でしょう。特に今回のような、酸素投与が遅れるということは、新生児の処置ではあってはならないケースだと思われ、リスクが高い低いに関わらず基本設備としてセット管理しておくことが必要でしょう。人工呼吸器使用中の患者のみならず、このようなケースの場合にも医療ガス中央配管にY字アダプターを使用することで緊急時の酸素確保に努めることが可能となります。 緊急時の連携体制のルール化 通常このような夜間の異常分娩ケースの場合、どのような方法で連絡をとり、何人で役割分担をするシステムになっているのか等もルール化してマニュアル化する必要があるでしょう。 教育・訓練 緊急時や早朝夜間などスタッフ人数が限られた状況下での分娩あるいは、異常分娩の介助をしなくてはならないこともあり、日頃より、シミュレーションを繰り返す等の訓練を行い実際に速やかに動けるように行っていくことは効果的で必要な訓練です。 |
| 事例1410:(ほぼ全盲の入院患者の所在不明) |
|
| 発生部署 (入院部門一般) キーワード(その他) |
|
| ■事例の概要(全般コード化情報より) |
| 発生月【 】 発生曜日【 】曜日区分【 】発生時間帯【 】 発生場所【 】 |
|
| 患者の性別【 】 患者の年齢【 】 患者の心身状態【 】 |
|
| 発見者【 】 | |
| 当事者の職種【 】 当事者の職種経験年数【 】 当事者の部署配属年数【 】 |
|
| 発生場面 | 【 】 |
| (薬剤・製剤の種類) | 【 】 |
| 発生内容 | 【 】 |
| 発生要因-確認 | 【 】 |
| 発生要因-観察 | 【 】 |
| 発生要因-判断 | 【 】 |
| 発生要因-知識 | 【 】 |
| 発生要因-技術(手技) | 【 】 |
| 発生要因-報告等 | 【 】 |
| 発生要因-身体的状況 | 【 】 |
| 発生要因-心理的状況 | 【 】 |
| 発生要因-システムの不備 | 【 】 |
| 発生要因-連携不適切 | 【 】 |
| 発生要因-勤務状態 | 【 】 |
| 発生要因-医療用具 | 【 】 |
| 発生要因-薬剤 | 【 】 |
| 発生要因-諸物品 | 【 】 |
| 発生要因-施設・設備 | 【 】 |
| 発生要因-教育・訓練 | 【 】 |
| 発生要因-患者・家族への説明 | 【 】 |
| 発生要因-その他 | 【】 |
| 間違いの実施の有無及びインシデントの影響度【 】 | |
| 備考【 】 | |
■ヒヤリ・ハットの具体的内容
| ほぼ全盲の為、日中付き添いの必要な患者様が病室におらず、所在が不明であった。 |
■ヒヤリ・ハットの発生した要因
| 付き添いについて説明がされていたが、説明が不十分であり、また患者様の看護師への遠慮があったため。 |
■実施したもしくは考えられる改善策
| 付き添いの必要性について再度説明した。患者様が病室にいない時は、周りのスタッフに声をかけ、所在を確認する。 |
■記入方法に関するコメント
| 具体的な内容の関して 「日中の付き添いの必要な患者」との記載がありますが、日中だけ付き添いが必要な理由があったのでしょうか。また、家庭での日常生活における行動範囲や行動方法については聞き取りが出来ていたのでしょうか。事例が発生した後、患者を何時、どこで、何をしていたところを発見されたのでしょうか。 この事例の発生要因を検討するうえで、患者の日常生活に関する情報など、事例の背景や発生時の状況を把握する必要があり、そういった点に留意し、具体的な記述をしましょう。 発生要因に関して 「付き添いについての説明が不十分」との記載がありますが、必要性の説明はどのような方法でされたのでしょうか。口頭で本人にだけ言ったのでしょうか。家族へも説明されたのでしょうか。また、看護師への遠慮があったとは、どのようなことから判断されたのでしょうか。発生要因を分析し、改善策を導き出すためには、より具体的な記述が必要でしょう。 |
■改善策に関するコメント
| 行動範囲や注意事項についての話し合いと理解 まず、入院生活を送るうえでの注意事項などは明確にしておかなければなりません。入院開始時に、患者が自分で行動できる範囲や守っていただかなければならないことについて十分話し合うことが必要です。看護師が手引きをして一緒に院内の行動範囲を確認しながら説明することも有効だと思います。 看護師への不必要な遠慮を患者にされないためには、患者の日常生活を理解し、患者の気持ちになった説明が必要でしょう。 病院のサポート体制 付き添いの時間指定ができるができるのであればガイドヘルパーを依頼されるのが良いでしょう。 また、ボランティア登録制度が公共団体や社会福祉協議会にありますので、病院が窓口となって手続きをすることも可能だと考えます。 次に、院内にボランティア登録制度を導入することなどが考えられます。要綱等を制定し、インターネットを通じ募集します。経験や人柄など面接により決定しお願いすることになります。 緊急時や上記のサポートが利用できないときは、職員の手引きによる移動ということになり、基本的な手順の作成と教育が必要でしょう。専門家による研修会を開催し、受け入れ体制の充実が必要だと考えます。 |
| 事例1442:(一次的胸腔ドレナージに伴う胸腔内への空気の逆流) |
|
| 発生部署 (入院部門一般) キーワード(その他) |
|
| ■事例の概要(全般コード化情報より) |
| 発生月【8月】 発生曜日【金曜日】曜日区分【平日】発生時間帯【16時〜17時台】 発生場所【病室】 |
|
| 患者の性別【女性】 患者の年齢【68歳】 患者の心身状態【障害なしその他】 |
|
| 発見者【当事者本人】 | |
| 当事者の職種【看護師】 当事者の職種経験年数【6年4ヶ月】 当事者の部署配属年数【3年7ヶ月】 |
|
| 発生場面 | 【その他のチューブ類の挿入、胸腔穿刺】 |
| (薬剤・製剤の種類) | 【】 |
| 発生内容 | 【方法(手技)の誤り】 |
| 発生要因-確認 | 【確認が不十分であった】 |
| 発生要因-観察 | 【確認が不十分であった】 |
| 発生要因-判断 | 【判断に誤りがあった、その他】 |
| 発生要因-知識 | 【その他】 |
| 発生要因-技術(手技) | 【技術(手技)を誤った】 |
| 発生要因-報告等 | 【不十分であった、不適切であった】 |
| 発生要因-身体的状況 | 【 】 |
| 発生要因-心理的状況 | 【慌てていた、緊張していた、他のことに気を取られていた】 |
| 発生要因-システムの不備 | 【作業マニュアルの不備】 |
| 発生要因-連携不適切 | 【医師と看護婦の連携不適切、看護職間の連携不適切】 |
| 発生要因-勤務状態 | 【多忙であった、勤務の管理に不備、作業が中断した】 |
| 発生要因-医療用具 | 【 】 |
| 発生要因-薬剤 | 【 】 |
| 発生要因-諸物品 | 【管理が不十分だった】 |
| 発生要因-施設・設備 | 【】 |
| 発生要因-教育・訓練 | 【教育・訓練が不十分だった】 |
| 発生要因-患者・家族への説明 | 【その他】 |
| 発生要因-その他 | 【】 |
| 間違いの実施の有無及びインシデントの影響度【その他】 | |
| 備考【 】 | |
■ヒヤリ・ハットの具体的内容
| 胸腔穿刺を留置針により行なっていた。2000mlほど排液予定。15分おきに訪室し滴下の様子を見た。16時10分1000mlの血性排液があり、徐々に排液中。16時20分、患者の家族から、排液が止ったとナースコールがあり訪室。管内に排液が無くなっていたためスタッフルームに帰り主治医に報告した。管のクランプをしていなかったため、空気が逆流し、胸腔内にエアーが入った。 |
■ヒヤリ・ハットの発生した要因
| ・状況を見て付き添うという観察をしなかった。・排液があるので、まだ大丈夫だろうと油断していた。・夕方の忙しい時間帯だった。・発見時、慌てていた。クランプしようという考えが浮かばなかった。(触れては行けないという思い込みがあった。知識不足があった。) |
■実施したもしくは考えられる改善策
| 自然圧の排液であることを考え、一人の看護師か医師が付き添う。もしくは、5分毎など、短時間で観察ができるようにする。それができる時間帯に、できる場所で行なう。マニュアルを見直す。 |
■記入方法に関するコメント
| 以下のような情報があれば、より総合的な分析が可能ではないかと考えます。 《患者に関する情報》
《担当看護師に関する情報》
《組織的な卒後教育の体制》
《処置が行われていた時の病棟全体の状況》
《関係者のコミュニケーション》
|
■改善策に関するコメント
| 胸腔ドレナージ処置方法に関する基礎的知識の理解 胸腔内は陰圧側で変動しているので、通常は低圧持続吸引を行いますが、呼気圧を利用して排液するにしても、逆流防止弁は必須です。 大量胸水が発見されドレナージする場合、1980年代後半からは、一体型に成形された胸腔ドレナージ留置セット(箱形)を使用するのが一般的で、製品には逆流防止弁が組み込まれています。これを使用していれば、かかる事象は通常起こりえません。 初回ドレナージであれば、上記ドレーン留置を行うべきですが、例外的に、胸水の内容と貯留する頻度などがはっきりしている場合、留置針を使用して、胸腔穿刺とドレナージを行うこともありえます。その際には、途中に三方活栓をつけて、シリンジを用いて、胸腔側から胸水を吸い出し、排液ボトル側に押し出します。三方活栓をひねるときには、呼吸によって空気が吸い込まれないよう、息を止めてもらうか、呼気時に素早くひねります。 これら一連の処置は、看護師ではなく、すべて医師により遂行されるべきものです。 看護師による観察のポイントと医師との連携 看護師は排液状態のみに注目しているようですが、「診療の補助業務」における責任としては、変化するであろう患者の呼吸状態を初めとする全身状態を観察し、治療の効果と危険の兆候を観察し判断するという、専門職としての役割が期待されていると思います。 ドレナージには種々ありますが、排液しようとする身体部位の特性と、ドレナージの原理を良く理解しておくことが重要です。胸腔内は陰圧ですから、穿刺針が開通して体外と交通すれば、空気が逆流するのは当然です。自然落下という一時的吸引を選択するからには、貯留液が少なくなればたちまち空気が逆流して、穿刺した側の肺が虚脱してしまうことは予測できていなければなりません。そのような危険を予測して、最も危険の少ない方法を検討し、危険に対処できる体制で臨むべきでしょう。 この方法で実施するのであれば、順調に排液されているかを観察し、逆流の兆候を発見したら直ちにチューブをクランプできるよう、医師か看護師が常時付き添う体制を整える必要があります。十分な体制で臨めるよう、医師と実施時間を調整したり、医師と交代で付き添うなど、患者の安全のために医師との連携と協働も重要です。また、勤務者間での役割や業務分担の調整も重要となります。 |
| 事例1550:(滅菌中断による未滅菌手術器具の混入) |
|
| 発生部署 (手術部門) キーワード(その他) |
|
| ■事例の概要(全般コード化情報より) |
| 発生月【 】 発生曜日【 】曜日区分【 】発生時間帯【 】 発生場所【 】 |
|
| 患者の性別【 】 患者の年齢【 】 患者の心身状態【 】 |
|
| 発見者【 】 | |
| 当事者の職種【 】 当事者の職種経験年数【 】 当事者の部署配属年数【 】 |
|
| 発生場面 | 【 】 |
| (薬剤・製剤の種類) | 【 】 |
| 発生内容 | 【 】 |
| 発生要因-確認 | 【 】 |
| 発生要因-観察 | 【 】 |
| 発生要因-判断 | 【 】 |
| 発生要因-知識 | 【 】 |
| 発生要因-技術(手技) | 【 】 |
| 発生要因-報告等 | 【 】 |
| 発生要因-身体的状況 | 【 】 |
| 発生要因-心理的状況 | 【 】 |
| 発生要因-システムの不備 | 【 】 |
| 発生要因-連携不適切 | 【 】 |
| 発生要因-勤務状態 | 【 】 |
| 発生要因-医療用具 | 【 】 |
| 発生要因-薬剤 | 【 】 |
| 発生要因-諸物品 | 【 】 |
| 発生要因-施設・設備 | 【 】 |
| 発生要因-教育・訓練 | 【 】 |
| 発生要因-患者・家族への説明 | 【 】 |
| 発生要因-その他 | 【】 |
| 間違いの実施の有無及びインシデントの影響度【 】 | |
| 備考【 】 | |
■ヒヤリ・ハットの具体的内容
| 翌日の整形外科手術の準備をしていた。翌日の整形外科手術にて使用予定の機器が○月○日15時からアンプロレン滅菌されていた。アンプロレンでの滅菌では滅菌が完了するのに12時間要するのだが、○月○日午後18時30分に(滅菌開始から約3時間後)誤って未滅菌なままでアンプロレンの袋を開けてしまい翌日の手術当日までそのまま放置されていた。他のスタッフによって未滅菌であることが発見された。 |
■ヒヤリ・ハットの発生した要因
| 当日の日付を誤って認識していた(○月○日なのに翌日だと認識していた)ために、滅菌開始日時から12時間経過していると誤った判断をした。また、整形外科手術は医療機器メーカーから手術前日に術中使用する機器を借りて、アンプロレン滅菌をしているという流れを理解していなかった。メーカーからの借用する機器は特に代用が効かないということが理解できていなかったので、慎重に取り扱いをしていなかった。 |
■実施したもしくは考えられる改善策
| 滅菌が完了しているかどうかを判断する時は、滅菌開始日時、検知テープ、現在の日時を思い込みだけでなく日付等が明記されているものを用いて確認してから滅菌完了か否かを確認する。また、手術の準備をするとき自分がいつの何の準備をしているのかを手術票にて確認して、正しい認識をもって準備に取り組む。そして手術で使用される機器がどのような流れにて使用されているのかを整形外科に限らず把握する。アンプロレン滅菌は人体に有毒なガスをガス抜きしなくてはならないので使用する時より前に袋を開けて用意しておかなくてはならないが、その責任は実際に手術に直接介助または間接介助としてつく者にあるということを理解しておく。 |
■記入方法に関するコメント
機器の具体的な使用状況に関する情報がほとんどありません。また、そもそもなぜ滅菌開始3時間で滅菌を終了してしまったのかに関する情報がないため、エラーが発生した直接的な原因を分析することが困難になっています。次のような情報があればより具体的な原因探索、解決策立案ができるでしょう。
|
■改善策に関するコメント
| アンプロレン並びにEOGによる滅菌法 アンプロレンとは、米アンダーソン・ステリライザース社が製造するアンプル式酸化エチレン滅菌システムです。高温や湿度に影響されやすく高圧蒸気滅菌が困難な光学機器やプラスチック・ゴム製品などの医療機器の滅菌が可能で、ガス配管設備も不要なため研究用、小規模医療施設や補助的な滅菌器具として使用されています。 酸化エチレンガス(EOG)の微生物に対する殺菌作用は、酵素系核酸のalkylationによるもので、核酸のカルボキシル基、アミノ基、ヒドロキシル基などと反応して微生物を不活化または死滅させると一般に考えられています。この反応を成立させるためには、ガスの濃度、温度、湿度、時間の4つの要素が必要です。現在使用されている酸化エチレン滅菌方式は、以下の三通りです。
まず始めに被滅菌物を必要に応じて滅菌包装材料で包装し、缶内になるべく広げて収容します(ガスの浸透性はあまりよくないため、ガスの対流、加温、加湿が行われやすいようにするためです)。多くの滅菌器ではプログラムを設定した後は、ほぼ自動で工程が進みます。
EOGの滅菌効果の検知には、高圧蒸気滅菌同様、ケミカルインジケータ(エチレンガスとの接触により滅菌条件が整うと特殊インク部分が指定された色に変色する検知カード)とバイオロジカルインジケータ(指標菌にはEOGに対して強い抵抗を有するBacillus subtilis ATCC9372など)が用いられます。バイオロジカルインジケータは判定までに通常滅菌処理後48時間から7日間の培養が必要ですが、現在一部のメーカーから短時間で判定可能な商品が販売されています。 この滅菌法の問題点として、(1)滅菌に要する時間が長いこと、(2)可燃性・人体への毒性があること、(3)化学反応により化合物を生成することが挙げられます。 ヒヤリ・ハット発生の原因と対策 アンプロレンの場合、はじめに被滅菌物と専用加湿紙をライナーバッグに入れ、専用の缶体に収容した後は、エアレーションまで自動で工程が進行します。滅菌時の周囲温度が20℃と通常のEOG滅菌に比べて低いため、滅菌時間は12時間必要となっています。初期設定ではエアレーションは2時間(任意停止可能)となっています。 このエラー発生の原因を考えるとき、最も大きな疑問は滅菌開始から3時間しかたっていない被滅菌物が缶体から取り出されたという点です。アンプロレン滅菌器本体には液晶ディスプレイがついており、プログラムを開始するとディスプレイに表示が出るようになっています。また途中で開扉する場合、洗浄が行われてからでないと扉は開きません。従ってプログラムを変更して開扉させない限り、中のものを取り出すことはできません。この事例の場合、特別な設定変更等を行わずに開閉を行っているようなので、そもそも滅菌プログラムが開始されていなかったのではないかと考えられます。 つまり、
滅菌に関する記録と滅菌完了の確認 日本医科器械学会は「医療現場における滅菌保証のガイドライン2000」においてEOG滅菌の工程管理のために、1)機械的制御の監視と記録、2)化学的インジケータの使用、3)生物学的インジケータまたは標準化されたテストパックによるテスト(少なくとも週に1回、できれば毎日使用)の3点を推奨しています。 今回のようなエラーを防止するためには、まず、缶体から滅菌物を取り出す際の確認事項や条件を全面的に見直し、その実施を周知徹底する必要があります。滅菌工程開始忘れは、比較的発生しやすいエラーのひとつです。このため、どんな滅菌器でも、清潔区域側へ未滅菌物が入り込むことがないように、工程が終了したことを液晶パネルや計器記録を確認してからでなければ開扉すべきではありません。しかしアンプロレンのような簡易型の滅菌器は付属計器記録計を有しておらず、適切な滅菌工程が達成されていたことを確認することが困難です。簡易型の滅菌器を使用する場合は、何らかの記録を独自に作成することも必要になってきます。もうひとつ確認する必要があるのが、インジケータです。もし滅菌工程に入っていなければ当然インジケータは変色しません。これを確認していれば、まだ滅菌が終了していないことが明らかになったはずです。 滅菌物の管理 次に、滅菌物が使用できるようになる時期はどのように定められ、それまで滅菌物はどこに保管されているのでしょうか。既滅菌物に酸化エチレンが吸着したものは、滅菌後も数時間ないし数日間残留するため、それが直接身体に接触すると害を及ぼす可能性があります。従って残留ガスを使用時までに、ある一定水準まで減少させなければなりません。残留ガス除去の必要最小時間は材料によって異なりますが、例えば紙の場合、エアレーターによる強制換気で8時間、室内での自然放置で24時間(米陸軍規格)が必要です。ポリ塩化ビニルなど酸化エチレンの吸着しやすい物質の場合、残留ガス除去の必要最小時間は自然放置で7日間、エアレーターを用いても12時間かかるとされています。EOG滅菌における残留ガス濃度の限度値については、国際標準化機構第194専門委員会(ISO/TC194)国内対策委員会のガイドライン(案)が取りまとめられているので併せて確認していただくとよいでしょう。 この事例では、被滅菌物が金属製品であると仮定して滅菌終了が翌日の3時、その後エアレーションの必要があるので翌日の11時まで器械は使用できません。もし自然放置であれば翌々日の3時まで使用できません。この事例の場合、たとえ15時に滅菌が開始されていたとしても安全なレベルまで残留ガスが除去されていなかった可能性があります。EOG滅菌を使用しなければならない機器を借用する場合、手術準備時刻までに安全な時間が確保できるように納品時間を調整し、滅菌スケジュールを組まなければなりません。部門の中で機器の素材なども考慮した残留ガス除去基準を明示し、そのスケジュールを守れるように滅菌を行う必要があります。滅菌業務に関する担当者を決めて調整や進行の確認を行うことで、より円滑で確実な滅菌業務が行えます。 また、この事例では準備のために缶体から直接取り出していますが、本来は滅菌工程が終了したら速やかに缶体から取り出し、インジケータを確認の上、所定の場所に保管する必要があります。使用可能になる時刻を明示して、別に保管しておけば誤って残留ガス除去終了前に開封してしまうリスクを回避することができるからです。 滅菌業務の安全管理 適切な医療器材を提供するためには厳しいリスク管理が必要です。そのためには滅菌手法上の相違や注意を十分に理解して業務にあたれるような職員教育と体制整備を行わなければなりません。この事例が発生した根本の原因は、記録や残留ガス除去の手順など滅菌器材の取扱いに関する基本的な知識とルールが部門内に確立されていなかったところにあると考えられます。 多くの医療機関では中央材料部などの部門が一元的に滅菌業務を行っていますが、手術部門に関しては器材の滅菌に対する要求度が他の部門より高いこと、特殊な器械が多いこと、時間的な制約が他部門に比べて多いこと、今回の事例のようにメーカーなどからの借用機器があることなどから独自に滅菌業務を行っている場合が少なくありません。しかし、そのための人員確保や滅菌機器・技法に精通した職員の配置を行っている機関は多くありません。もちろん、手術部門のすべての看護師が滅菌技法に関する最低限の知識を身につけることは重要ですが、それだけでなく滅菌機器や技法に精通した職員を養成・配置していく必要があります。また、手洗い・外回り業務の合間に洗浄・滅菌などの業務を行うのでなく、器械の準備に専念できるような業務分担や責任体制を確立することも安全管理のためには必要でしょう。 最後に、職場環境の安全もまた重要です。これまで延べてきたように酸化エチレンは人体に有毒です。職場環境におけるEOG許容濃度については、わが国では法的規制はありませんが、日本産業衛生学会が1992年に勧告値として8時間荷重平均(TWA)1ppmと言う数値を出しているほか、1999年には殺菌ガス懇話会が旧労働省科学物質調査課監修の「酸化エチレン殺菌ガス取扱い指針」で職場環境の保全対策に関する注意を喚起しています。なお労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則および特定化学物質等障害予防規則において、酸化エチレンを用いて滅菌作業を行う場合、暴露防止措置を講じることや特定化学物質等作業主任者の選任、作業環境測定(6ヶ月に1度)、特定業務従事者健康診断(配置換えおよびその後6ヶ月以内に1回)などが義務付けられています。取り扱いを行う部門ではこうした点も考慮の上、取り扱いの手順を作成することが望まれます。 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 重要事例情報の分析について > 重要事例分析結果

