ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 全般コード化情報の分析について
全般コード化情報の分析について
次ページ
第6回全般コード化情報の分析について
3 分析項目
以下の項目について、単純集計、クロス集計を行い、この結果を集計表とグラフに整理した。
<単純集計>
以下の項目について単純集計を行った。
・発生月(A)
・発生曜日(B)
・発生時間帯(C)
・発生場所(D)
・患者の性別(E)
・患者の年齢(F)
・患者の心身状態(G;多重回答)
・発見者(H)
・当事者の職種(I;多重回答)
・当事者の勤続年数(J)
・当事者の部署配属年数(K)
・ヒヤリ・ハット事例が発生した場面(L)
・ヒヤリ・ハット事例が発生した要因(N;多重回答)
・間違いの実施の有無および事例の影響度(O)
<クロス集計>
以下の項目間のクロス集計を行った。
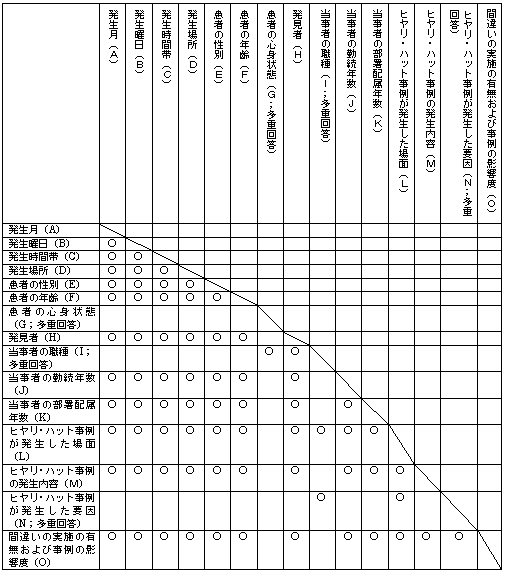
1)全事例【8740事例】
○発生時間帯【図1−3−1、図1−3−2】
前回集計から8〜9時台に発生した件数が多くなっており、それ以前の集計結果(10〜11時台にピーク)とは異なっている。発生時間別の発生場面をみると、8〜9時台に診療情報管理に関するヒヤリ・ハットが集中しており、これが最頻値に影響したものと考えられた。
○患者年齢【図1−6−1、図1−6−2】
これまでと同様、71歳〜80歳が多い。一方、0歳〜10歳がやや多い。
患者年齢別の発生場面をみると、小児患者では給食に関するヒヤリ・ハットが他の年齢層に比べ多く見られた。高齢患者では、療養上の世話等、ドレーン・チューブ類の使用・管理に関する事例が多く見られた。
○発見者【図1−8−1〜図1−8−3】
全体的には当事者本人が発見する件数が多く、ついで同職種者、他職種者であった。これを当事者別に見ると、当事者が医師・薬剤師の場合は、他職種者によって発見されるケースが多かった。
また、患者本人、家族・付き添い、他患者が発見者となった事例が764件(8.7%)あった。とくに他患者が発見した場面の約8割が転倒・転落を含む「療養上の世話等」であった。また、患者自身が発見した事例の中では「給食・栄養」が占める割合も高かった。
○経験年数【図1−10−1、図1−10−2】
これまでの結果と同様、職種経験年数の少ないものにヒヤリ・ハットの発生が集中している。当事者が医師・看護師・薬剤師の場合について発生頻度の累積割合を見ると、相対累積度数グラフの曲線は、看護師がもっとも凸となっており、他職種よりも経験年数の少ない層における集中傾向が見られた。経験が浅い場合、知識不足や慣れない業務を実施するため、ヒヤリ・ハット事例を発生しやすい状況が考えられる。当事者の属性に合わせた人員配置や院内教育の拡充も必要である。
○発生場面【図1−12】
処方・与薬の件数がもっとも多く、ついでドレーン・チューブ類の使用・管理、その他の療養生活の場面、療養上の世話の順に多く、これまでの集計結果と同様の傾向であった。
○発生要因【図1−13、表1−1】
発生要因として「確認不十分」をあげているものが3分の1となっており、当事者個人の要因に帰属させる傾向が強い。一方、「連携」などシステム要因を挙げている件数は少なく、いまだインシデントの要因を個人の問題として捉えていることが多く、システム全体を見直していくという発想につながっていない現状を示したものであると考えられる。
○影響度【図1−14−1、図1−14−2、表1−6、1−7】
間違った行為が実施される前に発見された割合は約3割であった。実施された割合を発生場面別に見ると、「処方・与薬」、「療養上の世話」、「ドレーン・チューブ類の使用・管理」等が多かった。
実施されていれば患者への影響度が大きいと思われた61例の内訳を見ると、「ドレーン・チューブの使用・管理」:10例、「処方・与薬」:8例であった。「輸血」は5例であったが、割合としては8%と高かった。
2)処方・与薬
○発生内容【図2−1】
事例の内容としては、「無投薬」が最も多く、ついで「過剰与薬」、「投与速度速すぎ」の順に多かった。
○発生時間帯【図2−2】
午前は8〜9時、午後は18〜19時にピークがあった。「投与速度速すぎ」は0〜1時に夜間のピークがあった。
○発見者【図2−3】
同職種者が発見する件数が多く、ついで当事者本人が発見している。発見内容を見ると同職種者が発見している内容は「無投薬」が多かった。
○発生要因【表2−1】
当事者要因は、4割以上が「確認不十分」であった。ついで、「思い込んでいた」「あわてていた」などの「心理的条件」の件数が多かった。
当事者に影響を及ぼした環境要因として、「多忙であった」など「勤務状況」、「看護職間の連携不適切」「医師と看護師の連携不適切」など「連携」の件数が多かった。
3)ドレーン・チューブ類の使用管理
○発生内容【図3−1】
発生内容の詳細を見ると、栄養チューブ、末梢静脈チューブなどの自己抜去が多かった。
○発生曜日・発生時間帯【図3−2、図3−3】
土曜、日曜日も平日と変わらない件数であった。時間帯による件数の違いもあまりみられなかった。
○患者の性別・心身状態【図3−4、図3−6】
男性患者に多くみられた。心身状態では床上安静の件数がもっとも多く、意識障害、痴呆、せん妄が多かった。
○発生要因【図3−10、表3−1】
発生要因として「観察不十分」、「確認不十分」、「判断に誤りがあった」などが多くあげられた。患者の状態を的確にアセスメントし、抜去のタイミングなどを適切に判断することが重要と考えられた。
○影響度【図3−11】
もし実施された場合、影響度中または大である事例の数が、影響度小である事例の数を上回っていた。
4)医療機器の使用・管理
○発生内容【図4−1】
輸液・輸注ポンプおよび人工呼吸器による事例が半数以上を占めた。輸液・輸注ポンプに関する事例では「条件設定忘れ」、「条件設定間違い」、「機器の誤操作」、「機器の不適切使用」が多いのに対して、人工呼吸器に関する事例では「組立」、「条件設定間違い」、「その他の使用・管理エラー」が多かった。
○発生時間帯【図4−2】
午前は8時〜11時、午後は14時〜15時にピークがあった。8〜11時台には「機器の点検ミス」、「機器の破損」などが見られ、14〜15時には「機器の不適切使用」による事例がやや多く見られた。
○発生要因【図4−6、表4−1】
発生要因としては、3分の1以上が「確認不十分」であった。ついで「観察不十分」、「多忙であった」、「管理不十分」が挙げられている。
3)輸血
○発生内容【図5−1】
「輸血検査」に関する事例と「輸血実施」に関する事例が同数あった。また「検体取り違え」、「患者取り違え」の事例も報告されている。
○発生曜日【図5−2】
水曜日と金曜日の件数が多かった。理由としては業務手順上のものと推察されるものの、今回のデータからは明確な理由が判明しなかった。
○当事者の職種【図5−8】
他の場面に比べ、医師が当事者となる割合が高かった。
○発生要因【図5−11、表5−1】
発生要因は、「確認不十分」が4割を占めた。ついで、「慌てていた」、「他のことに気をとられていた」など「心理的条件」の件数が多かった。
全体の頻度では、「確認」、「勤務状況」、「医療機器・器具・材料」の件数が多かった。
○影響度【図5−12】
間違いが実施された割合は相対的に低い(34%)が、これは当事者側のインシデントの認識度が高く、報告率が高いためと推察された。
6)療養上の世話等
○発生内容【図6−1】
「転倒・転落」が3分の2を占めた。
○発生曜日【図6−2】
発生件数は、曜日にかかわらず同程度であった。
○発生時間帯【図6−3】
時間帯にかかわらず、同程度の発生件数であったが、6時〜9時台及び14時〜15時台に発生した事例がやや多かった。
6〜7時台の転倒件数が多かった。これは、患者が起床し、活動時間帯に入るためと思われた。
○患者の心身状態【図6−5】
歩行障害、下肢障害など、患者が何らかの障害をもっている場合が多かった。
○発見者【図6−6】
当事者本人が発見する件数が多く、ついで同職種者、他患者の件数がややあった。
○発生要因【図6−7、表6−1】
発生要因は、3割が「観察」であった。ついで「患者・家族への説明」の件数が440件(14%)あった。
第6回全般コード化情報集計結果
図表目次
次ページ
| 1 | 全般コード化情報の収集状況
|
| 2 | 分析方針 分析は以下の方針に基づき実施した。 |
| 1) | 収集した事例について、頻度を単純集計した。なお、患者の年齢、勤続年数、部署配属年数については、年代別など範囲を設定して集計した。 |
| 2) | 収集した事例について、項目間の相互関係を把握するため、それらのクロス集計を行った。 |
| 3) | 報告事例の多い「処方・与薬」「ドレーン・チューブ類の使用・管理」「療養上の世話、療養生活の場面」および影響度の大きい事例の割合が高い「医療機器の使用・管理」「輸血」については、該当するデータを抽出のうえ、項目間のクロス集計を行った。 |
3 分析項目
以下の項目について、単純集計、クロス集計を行い、この結果を集計表とグラフに整理した。
<単純集計>
以下の項目について単純集計を行った。
・発生月(A)
・発生曜日(B)
・発生時間帯(C)
・発生場所(D)
・患者の性別(E)
・患者の年齢(F)
・患者の心身状態(G;多重回答)
・発見者(H)
・当事者の職種(I;多重回答)
・当事者の勤続年数(J)
・当事者の部署配属年数(K)
・ヒヤリ・ハット事例が発生した場面(L)
・ヒヤリ・ハット事例が発生した要因(N;多重回答)
・間違いの実施の有無および事例の影響度(O)
<クロス集計>
以下の項目間のクロス集計を行った。
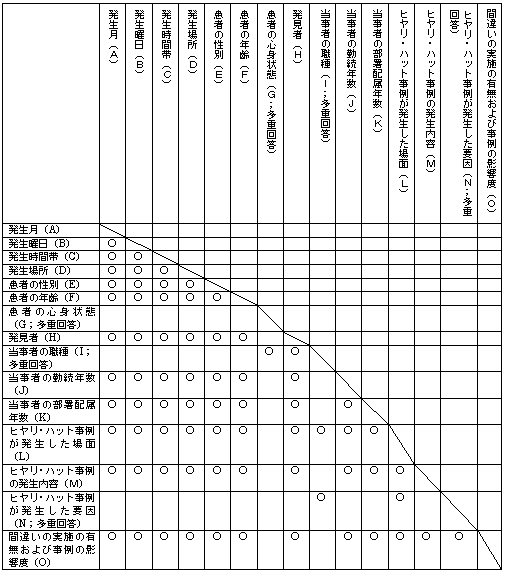
| 4 | 分析結果 |
1)全事例【8740事例】
○発生時間帯【図1−3−1、図1−3−2】
前回集計から8〜9時台に発生した件数が多くなっており、それ以前の集計結果(10〜11時台にピーク)とは異なっている。発生時間別の発生場面をみると、8〜9時台に診療情報管理に関するヒヤリ・ハットが集中しており、これが最頻値に影響したものと考えられた。
○患者年齢【図1−6−1、図1−6−2】
これまでと同様、71歳〜80歳が多い。一方、0歳〜10歳がやや多い。
患者年齢別の発生場面をみると、小児患者では給食に関するヒヤリ・ハットが他の年齢層に比べ多く見られた。高齢患者では、療養上の世話等、ドレーン・チューブ類の使用・管理に関する事例が多く見られた。
○発見者【図1−8−1〜図1−8−3】
全体的には当事者本人が発見する件数が多く、ついで同職種者、他職種者であった。これを当事者別に見ると、当事者が医師・薬剤師の場合は、他職種者によって発見されるケースが多かった。
また、患者本人、家族・付き添い、他患者が発見者となった事例が764件(8.7%)あった。とくに他患者が発見した場面の約8割が転倒・転落を含む「療養上の世話等」であった。また、患者自身が発見した事例の中では「給食・栄養」が占める割合も高かった。
○経験年数【図1−10−1、図1−10−2】
これまでの結果と同様、職種経験年数の少ないものにヒヤリ・ハットの発生が集中している。当事者が医師・看護師・薬剤師の場合について発生頻度の累積割合を見ると、相対累積度数グラフの曲線は、看護師がもっとも凸となっており、他職種よりも経験年数の少ない層における集中傾向が見られた。経験が浅い場合、知識不足や慣れない業務を実施するため、ヒヤリ・ハット事例を発生しやすい状況が考えられる。当事者の属性に合わせた人員配置や院内教育の拡充も必要である。
○発生場面【図1−12】
処方・与薬の件数がもっとも多く、ついでドレーン・チューブ類の使用・管理、その他の療養生活の場面、療養上の世話の順に多く、これまでの集計結果と同様の傾向であった。
○発生要因【図1−13、表1−1】
発生要因として「確認不十分」をあげているものが3分の1となっており、当事者個人の要因に帰属させる傾向が強い。一方、「連携」などシステム要因を挙げている件数は少なく、いまだインシデントの要因を個人の問題として捉えていることが多く、システム全体を見直していくという発想につながっていない現状を示したものであると考えられる。
○影響度【図1−14−1、図1−14−2、表1−6、1−7】
間違った行為が実施される前に発見された割合は約3割であった。実施された割合を発生場面別に見ると、「処方・与薬」、「療養上の世話」、「ドレーン・チューブ類の使用・管理」等が多かった。
実施されていれば患者への影響度が大きいと思われた61例の内訳を見ると、「ドレーン・チューブの使用・管理」:10例、「処方・与薬」:8例であった。「輸血」は5例であったが、割合としては8%と高かった。
2)処方・与薬
○発生内容【図2−1】
事例の内容としては、「無投薬」が最も多く、ついで「過剰与薬」、「投与速度速すぎ」の順に多かった。
○発生時間帯【図2−2】
午前は8〜9時、午後は18〜19時にピークがあった。「投与速度速すぎ」は0〜1時に夜間のピークがあった。
○発見者【図2−3】
同職種者が発見する件数が多く、ついで当事者本人が発見している。発見内容を見ると同職種者が発見している内容は「無投薬」が多かった。
○発生要因【表2−1】
当事者要因は、4割以上が「確認不十分」であった。ついで、「思い込んでいた」「あわてていた」などの「心理的条件」の件数が多かった。
当事者に影響を及ぼした環境要因として、「多忙であった」など「勤務状況」、「看護職間の連携不適切」「医師と看護師の連携不適切」など「連携」の件数が多かった。
3)ドレーン・チューブ類の使用管理
○発生内容【図3−1】
発生内容の詳細を見ると、栄養チューブ、末梢静脈チューブなどの自己抜去が多かった。
○発生曜日・発生時間帯【図3−2、図3−3】
土曜、日曜日も平日と変わらない件数であった。時間帯による件数の違いもあまりみられなかった。
○患者の性別・心身状態【図3−4、図3−6】
男性患者に多くみられた。心身状態では床上安静の件数がもっとも多く、意識障害、痴呆、せん妄が多かった。
○発生要因【図3−10、表3−1】
発生要因として「観察不十分」、「確認不十分」、「判断に誤りがあった」などが多くあげられた。患者の状態を的確にアセスメントし、抜去のタイミングなどを適切に判断することが重要と考えられた。
○影響度【図3−11】
もし実施された場合、影響度中または大である事例の数が、影響度小である事例の数を上回っていた。
4)医療機器の使用・管理
○発生内容【図4−1】
輸液・輸注ポンプおよび人工呼吸器による事例が半数以上を占めた。輸液・輸注ポンプに関する事例では「条件設定忘れ」、「条件設定間違い」、「機器の誤操作」、「機器の不適切使用」が多いのに対して、人工呼吸器に関する事例では「組立」、「条件設定間違い」、「その他の使用・管理エラー」が多かった。
○発生時間帯【図4−2】
午前は8時〜11時、午後は14時〜15時にピークがあった。8〜11時台には「機器の点検ミス」、「機器の破損」などが見られ、14〜15時には「機器の不適切使用」による事例がやや多く見られた。
○発生要因【図4−6、表4−1】
発生要因としては、3分の1以上が「確認不十分」であった。ついで「観察不十分」、「多忙であった」、「管理不十分」が挙げられている。
3)輸血
○発生内容【図5−1】
「輸血検査」に関する事例と「輸血実施」に関する事例が同数あった。また「検体取り違え」、「患者取り違え」の事例も報告されている。
○発生曜日【図5−2】
水曜日と金曜日の件数が多かった。理由としては業務手順上のものと推察されるものの、今回のデータからは明確な理由が判明しなかった。
○当事者の職種【図5−8】
他の場面に比べ、医師が当事者となる割合が高かった。
○発生要因【図5−11、表5−1】
発生要因は、「確認不十分」が4割を占めた。ついで、「慌てていた」、「他のことに気をとられていた」など「心理的条件」の件数が多かった。
全体の頻度では、「確認」、「勤務状況」、「医療機器・器具・材料」の件数が多かった。
○影響度【図5−12】
間違いが実施された割合は相対的に低い(34%)が、これは当事者側のインシデントの認識度が高く、報告率が高いためと推察された。
6)療養上の世話等
○発生内容【図6−1】
「転倒・転落」が3分の2を占めた。
○発生曜日【図6−2】
発生件数は、曜日にかかわらず同程度であった。
○発生時間帯【図6−3】
時間帯にかかわらず、同程度の発生件数であったが、6時〜9時台及び14時〜15時台に発生した事例がやや多かった。
6〜7時台の転倒件数が多かった。これは、患者が起床し、活動時間帯に入るためと思われた。
○患者の心身状態【図6−5】
歩行障害、下肢障害など、患者が何らかの障害をもっている場合が多かった。
○発見者【図6−6】
当事者本人が発見する件数が多く、ついで同職種者、他患者の件数がややあった。
○発生要因【図6−7、表6−1】
発生要因は、3割が「観察」であった。ついで「患者・家族への説明」の件数が440件(14%)あった。
以上
図表目次
次ページ
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 全般コード化情報の分析について

