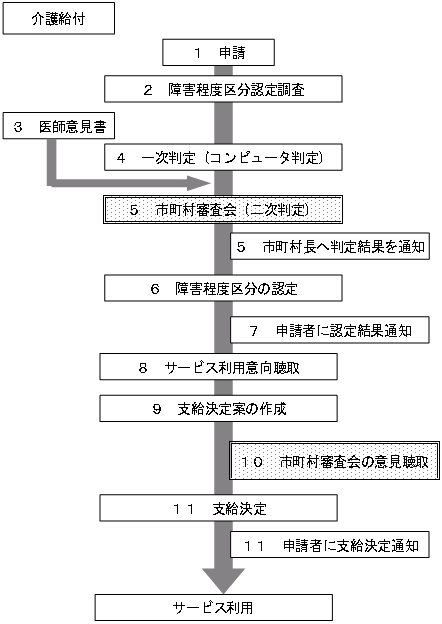(参考資料4)
市町村審査会委員マニュアル案
暫定版(Vol.1)
平成17年12月
厚生労働省 社会・援護局
障害保健福祉部
はじめに
介護給付の申請の場合を例に、支給決定までの流れについて、図1「支給決定の流れと審査会の位置づけ」に沿って、説明します。
なお、以下の項目と図に記した番号は一致していますので、図も併せてご覧ください。
| (1) |
市町村は、本人又は家族等から申請があった場合、申請書の内容、医師意見書を作成していただける医師がいるか等の確認をします。 |
| (2) |
申請書を受理した場合、市町村は次の手順で事務処理をします。 |
| (1) |
医師意見書の記載を医師(医療機関)に依頼します。 |
| (2) |
指定相談支援事業者等に認定調査を委託する場合は、委託契約を締結し、調査票
の提出期日を指定して、委託先に調査を依頼します。 |
| (1) |
障害程度区分認定調査
障害程度区分を判定するために、認定調査員は、申請のあった本人及び保護者等
と面接をし、3障害共通の調査項目等について認定調査を行います。(このとき同
時にサービスの利用意向聴取も行うことがあります。)
調査員が判断に迷うような場合は、回数や頻度等の具体的な状況、判断の根拠について「特記事項」に記載します。 |
| (2) |
概況調査
概況調査は、認定調査に併せて、本人及び家族等の状況や、現在のサービス内容や家族からの介護状況が詳しく記載されます。特に、日中活動関連、介護者関連、居住関連は詳細に記載されます。 |
医師意見書は、疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見など、申請者の医学的知見から意見を求めるものです。
これは、二次判定において、一次判定を補足する資料として使用するものです。
| (1) |
市町村は認定調査の結果を国が配布する一次判定用ソフトウェアを導入したコン
ピュータに入力し、一次判定処理を行います。調査内容に不整合がある(警告コー
ドが発生した)場合は、認定調査員に確認し、調査項目の整理を行います。 |
| (2) |
医師意見書が届いた時に、認定調査票と医師意見書の共通項目の突合を行い、矛盾点は両者から聞き取り、整理を行います。 |
| (1) |
市町村は、一次判定結果、概況調査、特記事項及び医師意見書を揃え、市町村審
査会に審査判定を依頼します。 |
| (2) |
市町村審査会(合議体)は、一次判定結果、医師意見書及び特記事項の内容を
踏まえ審査判定を行います。 |
| (3) |
この場合、市町村審査会が特に必要と認めた場合は、本人、その家族、医師、そ
の他関係者に意見を求めることができます。 |
| (4) |
市町村審査会は、審査判定結果を市町村へ通知します。 |
市町村は、市町村審査会の審査判定結果に基づき、障害程度区分の認定を行います。
| (1) |
市町村は、障害程度区分の認定結果を申請者に通知します。 |
| (2) |
認定結果通知には、不服申し立てに関する教示をしなければなりません。不服申
し立て先は都道府県知事となりますが、認定結果についての疑問等は、第一義的に
は結果を通知した市町村が対応します。 |
市町村は、認定結果が通知された申請者の支給決定を行うために、申請者の介護給
付に対するサービスの利用意向を聴取します。
市町村は、障害程度区分やサービス利用意向聴取の結果等を踏まえ、市町村が定め
る支給決定基準に基づき、支給決定案を作成します。
市町村は、作成した支給決定案が当該市町村の定める支給基準と乖離するような場合、市町村審査会に意見を求めることができます。
市町村審査会は、支給決定案を作成した理由等の妥当性を審査し、支給決定案等について審査会の意見を市町村に報告します。
市町村審査会は、意見を述べるに当たり、必要に応じて、関係機関や障害者、その家族、医師等の意見を聴くことができます。
| (1) |
市町村は、支給決定調査の勘案事項(※)、審査会の意見等の内容を踏まえ、支給決定を行います。
(※)支給決定調査の勘案事項(認定調査(概況調査)も参照ください。)
| ○ |
「障害程度区分認定調査項目」の結果による心身の状況 |
| ○ |
「サービスの利用意向」障害者又は障害児の保護者のサービス利用に関する意向の具体的内容 |
| ○ |
「介護者関連」介護者の有無、介護を行う者の状況(介護者の健康状況等) |
| ○ |
「地域生活関連」外出の頻度、社会参加の状況、過去の入所歴や入院歴 |
| ○ |
「就労関連」就労状況、過去の就労経験、就労希望の有無 |
| ○ |
「日中活動関連」自宅、施設、病院 |
| ○ |
「居住関連」生活の場所及び単身、同居、グループホーム、病院、入所 |
| ○ |
「サービスの提供体制関連」地域におけるサービスの提供体制の整備状況 |
| ○ |
「その他」障害の状況による特徴的状況、介護等の時間間隔 |
|
| (2) |
支給決定通知には、不服申し立てに関する教示をしなければなりません。不服申し立て先は都道府県知事となりますが、決定についての疑問等は、第一義的には結果を通知した市町村が対応します。 |
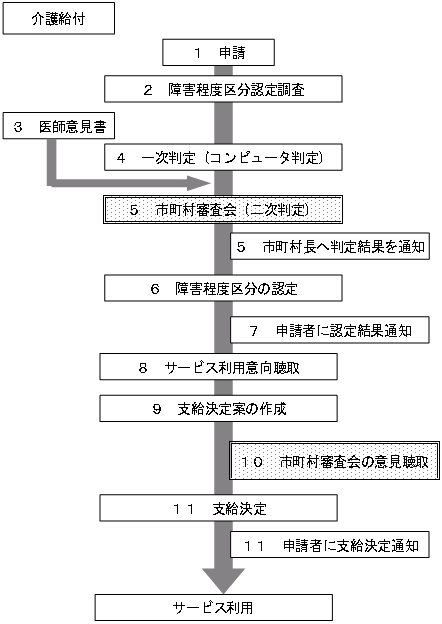
図1 支給決定の流れと審査会の位置付け
|
| 2 |
介護給付・訓練等給付と障害程度区分の関係について |
| ○ |
介護給付と訓練等給付のそれぞれの給付の基本的な性格としては、
・介護給付は、障害に起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援であり、ホームヘルプや施設における生活介護などが該当します。
・訓練等給付は、障害のある方が地域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的支援であり、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などが該当します。
| ※ |
一定期間とは、サービス種類や個々の障害者の方の状況に応じて異なります。また、訓練実施により一定の効果があり、今後も効果が期待できるなどの場合に期間の更新もあります。 |
・自立訓練のうち生活訓練の場合には、通所してサービスを利用する形態の他、訓練期間内に居宅における生活を支援するために、居宅等を訪問して行う訪問型や、短期間、居住サービスを利用する短期滞在型もあります。 |
| ○ |
介護給付についてのみ、障害程度区分の審査・判定を行います。 |
| ○ |
障害程度区分とは、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障害者の心身の状態を総合的に表す区分であり、市町村がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つであります。 |
| ○ |
なお、一人ひとりの障害者の方に対する介護給付の支給決定は、障害程度区分の他、サービスの利用意向、家族等の介護者の状況、社会参加の状況など概況調査で得られる勘案事項を加味して、サービスの種類や量について、個別に支給決定されます。 |
| ○ |
障害程度区分は、生活介護や療養介護等のサービス利用対象者の要件や国からの市町村に対するホームヘルプサービスの国庫負担基準等として用いられます。 |
障害者自立支援法に係る介護給付と訓練等給付
| |
サービス名 |
サービス内容 |
| 介護給付 |
居宅介護 |
居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与する |
| 介護給付 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与する |
| 介護給付 |
行動援護 |
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等の便宜を供与する |
| 介護給付 |
療養介護 |
医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院等において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与 |
| 介護給付 |
生活介護 |
常時介護を要する障害者につき、主として昼間において、障害者支援施設等において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供等の便宜を供与する |
| 介護給付 |
児童デイサービス |
障害児につき、肢体不自由児施設等に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の便宜を供与す |
| 介護給付 |
短期入所 |
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与する |
| 介護給付 |
重度障害者等包括支援 |
常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものにつき、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供すること |
| 介護給付 |
共同生活介護 |
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与する |
| 介護給付 |
施設入所支援 |
施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与する |
| 訓練等給付 |
自立訓練 |
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与する |
| 訓練等給付 |
就労移行支援 |
就労を希望する障害者につき、一定期間、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与する |
| 訓練等給付 |
就労継続支援 |
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与する |
| 訓練等給付 |
共同生活援 |
助地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うこと |
訓練等給付の支給決定
| ○ |
訓練等給付は、できる限り障害者本人の希望を尊重し、暫定的に支給決定を行った上で、実際にサービスを利用した結果を踏まえて正式の支給決定が行われます。 |
| ○ |
したがって、明らかにサービス内容に適合しない場合を除き、暫定支給決定の対象となります。しかしながら、地域内のサービス資源に限りがあり、利用希望者が定員枠を超えるような場合には、自立訓練事業(機能訓練・生活訓練)に限り、訓練等給付に関連する項目の調査結果をスコア化し、暫定支給決定の優先順位を考慮する際の参考としてのみ用います。 |
| ○ |
なお、この訓練等給付に関連するスコアは、暫定支給決定の際に用いられる参考指標であり、障害程度区分ではありません。 |
|