(参 考)
資料No.1−3
地域における産業保健活動の現状及び課題
1 地域産業保健センター及び都道府県産業保健推進センターの関係
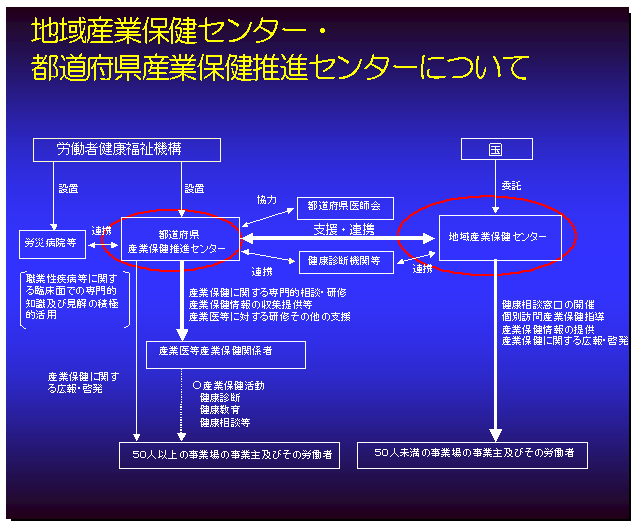
2 地域産業保健センター事業の現状と課題
(1)現状( 平成18年度の地域産業保健センター事業実績)
相談件数、訪問事業場数推移グラフ
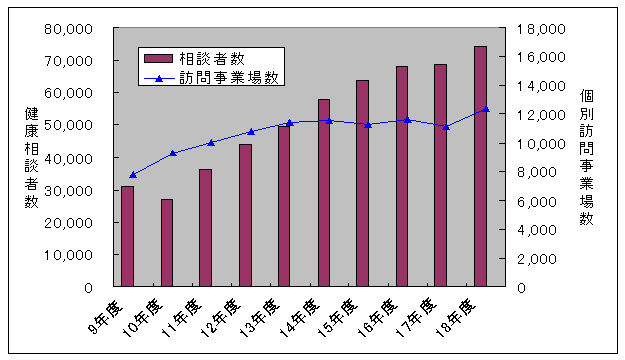
ア 地域産業保健センターの状況
(ア)地域産業保健センター数 347カ所
(イ)拡充センター数((ア)の内数) 87カ所
イ 健康相談窓口
※通常センターでは週1回程度、拡充センターでは週複数回、健康相談窓口を開設
(ア)健康相談窓口実施回数 24,311回
(イ)健康相談窓口利用者延べ人数 74,169人(1センター当たり、平均213.7人)
(ウ)窓口別利用者数
| 地域産業保健センター内 | サテライト ( 地域医療機関) |
その他 (イベント時など) |
|
| 平成18年度 | 38,453 人 | 13,630 人 | 22,086 人 |
| 平成17年度 | 39,444 人 | 11,596 人 | 17,774 人 |
| 増減 | △ 991人 (2.5%減) |
2,034人 (17.5%増) |
4,312人 (24.2%増) |
(エ)サテライト方式の導入による相談者数の増加
平成18年度導入(東京都区部及び大阪市)の地域産業保健センターの相談者数
| 17年度 | 18年度 | 増加率 | |
| 東京都区部( 13センター) | 3,061人 | 3,489人 | 14.0% |
| 大阪市( 6センター) | 945人 | 1,268人 | 34.2% |
| 合 計 | 4,006人 | 4,757人 | 18.7% |
※サテライト方式による相談を実施した効果が見られる
ウ 個別訪問指導
(ア)登録事業場数 48,970事業場
(イ)個別訪問実施事業場数 12,455事業場(1センター当たり、平均36事業場)
エ 周知広報活動
(ア)説明会実施回数 1,832回(1センター当たり、平均 5.3回)
(イ)コーディネーターによる周知広報活動
事業場訪問 39,627回(1センター当たり、平均114.2回)
パンフレット配布 188,192枚(1センター当たり、平均542.3枚)
電話による周知 37,099回(1センター当たり、平均106.9回)
オ 地域産業保健センターの知名度
総務省の調査によると、調査対象小規模事業場160 事業場中87 事業場(54.4%)が地域産業保健センターを知らないと回答したとのこと。
(2)課題
[1] 健康相談窓口利用者数、個別訪問実施事業場数とも増加してきているものの、平成18年度実績では、それぞれ、1センター当たり、平均213.7人、平均36事業場と活動は未だ少ないこと、地域産業保健センターのことを未だ知らない事業場も多いこと等の状況にあり、それらに対応する必要があるのではないか。
[2] 窓口別利用者数について、地域産業保健センター内での人数は減少しているが、サテライト(地域医療機関)、その他(イベント時など)での人数は大幅に増加しており、地域産業保健センターの活動が未だ少ない状況を踏まえると、窓口開設場所、時期などの工夫が必要ではないか。
<参考>
<産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会報告書(12ページ)>
事業者の理解が十分でないために、労働者に産業保健サービスが十分に提供されていない場合もあることから、国、都道府県産業保健推進センター等と連携し、商工会、中小企業組合等の事業者団体から事業者に対し、産業保健サービスの重要性等について周知啓発を行うことが必要である。
<産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会報告書(12ページ)>
これまで、地域産業保健センターにおいては、小規模事業場における労働衛生水準の改善のために、郡市区医師会等関係者の努力により様々な取組みが行われてきたところであるが、今後とも、地域産業保健センターが地域の産業医とも連携をとりつつ、地域のニーズ、特性に応じ、一層効率的に運用されることが期待される。例えば、面接指導等の窓口が地域産業保健センターに設置されるものだけでは、窓口に至るまでの地理的・時間的制約は少なくないため、地域産業保健センター以外の場所(医療機関等)に相談窓口を設置する、いわゆるサテライト方式の拡大も考えられるほか、地域産業保健センターの医師等が事業場を訪問し、面接指導等を行う方式も考えられる。
3 地域におけるメンタルヘルス対策の現状と課題
(1)現状
ア 地域産業保健センターにおける実施体制
| ┌ │ │ │ └ |
「「地域産業保健センターにおける産業医登録数」及び「精神科医等のための |
┐ │ │ │ ┘ |
産業医登録数 31,042人(1センター当たり、平均89.5人)
うち、精神科医等登録数 1,131人(1センター当たり、平均 3.3人)
イ 地域産業保健センターにおける健康相談人数(平成18年度)
74,169人(1センター当たり、平均213.7人/年)
うち、メンタルヘルス相談 3,706人(1センター当たり、平均 10.7人/年)
(労働者による相談 2,945人(79.5%))
0〜10人のセンターが286センターで、全体の82.4%(下図参照)
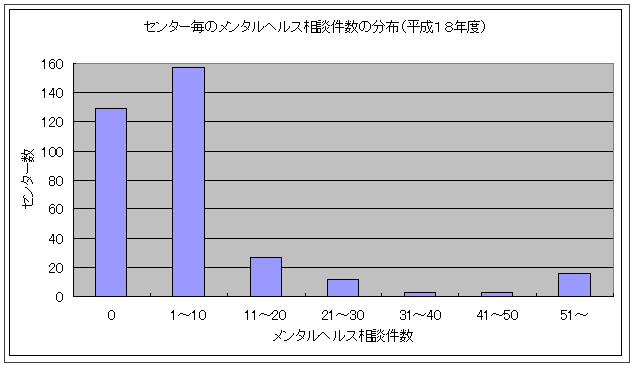
ウ 働き盛り層のメンタルヘルスケア支援事業の実施状況(平成18年度)
セミナー 200回開催で 9,469人参加(1回当たり、平均47.3人)
個別相談会 220回開催で、 459人参加 (1回当たり、平均 2.1人)
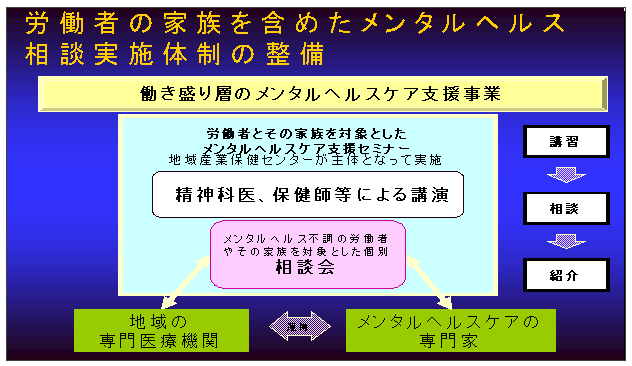
(2)課題
[1] 平成20年度から、一定の基準を満たす相談機関を登録・公表・紹介する機能などを有する「メンタルヘルス対策支援センター」(平成20年度は、都道府県産業保健推進センター内)が設置され、地域におけるメンタルヘルス対策(職域関係)を推進するセンターが、「メンタルヘルス対策支援センター」、「都道府県産業保健推進センター」及び「地域産業保健センター」の3つのセンターの体制となったため、それらの連携や支援体制を明確に位置付けるため、各々の役割分担の明 確化やそれらを踏まえた地域におけるメンタルヘルス対策(職域関係)の拠点づくりが必要ではないか。
[2] [1]の職域における社会資源と地域障害者職業センター等の社会資源や精神保健福祉センター等の地域保健における社会資源との連携が不十分であり、これらを活性化する必要があるのではないか。(→「地域保健との連携の現状と課題」において検討願います。)
[3] 面接指導や一般の健康相談、働き盛り層支援事業における相談等において、労働者のメンタルヘルス不調が深刻な状況にあることが把握された場合、適切に、精神科医等に繋げる方策が必要ではないか。
[4] メンタルヘルス対策において、産業医と精神科医等とのネットワークを強化することが必要ではないか。(→「地域の各種関係者とのネットワークの現状と課題」において検討願います。)
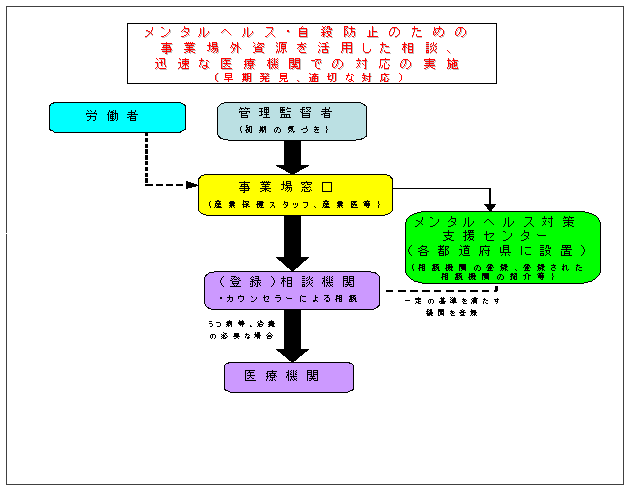
<参考>
<産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会報告書(9ページ)>
さらに、今後とも、(中略)より効果のあるメンタルヘルス対策について検討していくことが必要である。
<産業保健活動の推進のあり方に関する有識者会議報告書(11ページ)>
推進センター(都道府県産業保健推進センター)に対する相談件数は年々増加している。相談は、産業保健スタッフのうち労務管理担当者からのものが最も多いが、労働者からの相談も多く、このうち、特にメンタルヘルスに関する相談が増加している。(中略)特に個別のメンタルヘルス不調者に関する相談では、対象となる労働者の状況について専門家の判断がない限り、相談窓口として機能しない。このため、例えば、労働者からの直接の相談に応じることをPRし、積極的に対応する。
<産業保健活動の推進のあり方に関する有識者会議報告書(12ページ)>
推進センターはそれぞれの地域事情に応じ、都道府県精神福祉協議会、都道府県医師会産業保健部会、日本精神科診療所協会・日本精神科病院協会の各支部、労働局、都道府県の精神保健担当部局等との連携のもと、地域における産業医と精神科医とのネットワークを構築し、交流の場と機会を提供する必要がある。
4 都道府県産業保健推進センターの現状と課題
(1)現状
ア 事業場の産業保健関係者への支援
[1] 研修の開催
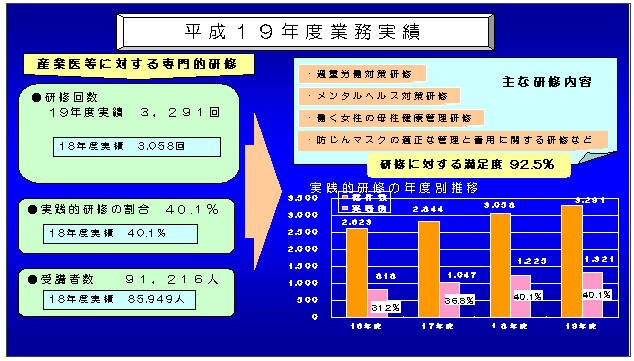
[2] 情報の収集・提供(情報誌・パンフレット等の配布、図書・ビデオの貸出、ホームページ・メールマガジンによる情報発信、調査研究)
[3] 相談対応
各推進センターに、6分野の専門家(産業医学、労働衛生工学、メンタルヘルス、労働衛生関係法令、カウンセリング、保健指導)で構成される産業保健相談員(非常勤)を配置(全1,296人)
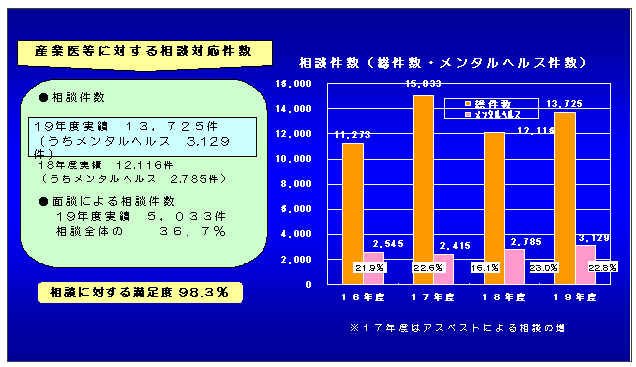
[4] 広報、啓発(事業主セミナー)
[5] 事業者団体等への支援(研修講師の派遣・斡旋、研修器材の貸与)
イ 助成金の支給
・小規模事業場産業保健活動支援促進助成金、自発的健康診断受診支援助成金
ウ 地域産業保健センターへの支援
[1] 地域産業保健センターのコーディネーターに対する研修の開催
地域産業保健センターの活性化のためには、コーディネーターの資質の向上が必要であることから、推進センターが主催して、コーディネーター研修を開催している。(平成19年度 79回開催 参加者860人)
[2] 地域産業保健センターの登録産業医に対する研修の開催
地域産業保健センターに登録されている登録産業医の資質向上のために、登録医研修を開催している。(平成19年度 83回開催)
[3] 地域産業保健センター運営協議会等への出席
推進センターの職員が、地域産業保健センター運営協議会に出席して、小規模事業場に対する産業保健活動支援に関する協議、支援等を行っている。
(平成19年度 434回出席)
[4] その他、地域産業保健センターのコーディネーター等からの問合せに対し、推進センターの産業保健相談員等が専門的立場から対応している。
(2)課題
[1] 都道府県産業保健推進センターにおける域内の地域産業保健センターの活動に対する支援を充実することが必要ではないか。
[2] 地域における産業保健活動の拠点としての役割を明確にする必要があるのではないか。
<参考>
<小規模事業場における健康確保方策の在り方に関する検討会報告書(7ページ)>
産業保健推進センターと地域産業保健センターとの連携の推進により、産業保健に新たに求められるニーズに即応した活動が可能となり、さらには業務の効率化が図られることが期待されることから、今後、両センターがそれぞれの機能の整合性を図り、各地域の産業保健活動を推進していくことが必要である。
<産業保健委員会答申(20ページ)>
小規模事業場における対策は、地域産業保健センターが中心となって、都道府県産業保健推進センター、中央労働災害防止協会、労災病院勤労者予防医療センター等の事業場外資源の支援を受けながら推進されることが望ましい。
<産業保健活動の推進のあり方に関する有識者会議報告書(10ページ)>
以下のような方策により、両センター(地域産業保健センター及び都道府県産業保健推進センター)の連携を強化するための取り組みが必要である。
・ 地域センター(地域産業保健センター)活動の好事例や活動のノウハウを共有するため、コーディネーターによる情報交換と交流の機会を提供する。これに先立って、各労働局から地域センターに対する参加勧奨が必要。
・ 推進センターが実施しているコーディネーター初任時研修の経験を踏まえ、個別事業場へのアプローチなどコーディネーター活動に求められる要件を明らかにし、その要件に適った人材を確保するよう国に働きかける。
・ 地域センターの登録産業医に対して情報交換の場と機会を提供する。
・ 地域の特性に応じ、研修及び相談事業を共同開催する。
・ 推進センターの地域相談員を登録産業医の指導・助言のため地域センターへ派遣する。
・ 地域センターとの連携に係る好事例を示し、全国の推進センターでの展開を図る。
5 地域の各種関係者とのネットワークの現状と課題
(1)現状
| ┌ │ │ │ └ |
「「過重労働・メンタルヘルス対策に関する研修会」及び「精神科医等のた |
┐ │ │ │ ┘ |
ア 産業医に対する過重労働・メンタルヘルス対策に関する研修会の実施
平成17年度〜平成19年度において、11,460人修了
イ 精神科医等に対する産業保健に関する研修会の実施
研修受講者のうち、その情報提供に同意した者については、地域産業保健センターに登録。
平成17年度〜平成19年度において、 1,646人修了
うち、 1,131人が登録
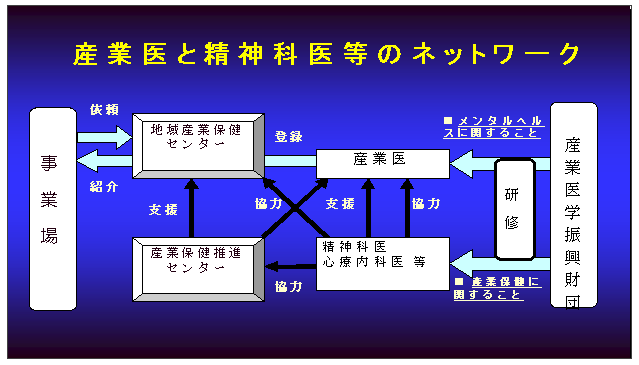
ウ 地域産業保健センターにおける保健師の活用実績
平成18年度における保健師の活用 236人(1センター当たり、平均0.7人)
エ 日本医師会認定産業医の状況(平成20年5月現在、別紙参照)
全国で、 74,310人
なお、産業医を選任する義務のある50人以上の規模の事業所数は全国で約14万事業所(総務省「事業所・企業統計調査」(平成16年))
(2)課題
[1] 平成17年度〜平成19年度の間、産業医に対して過重労働・メンタルヘルス対策に関する研修を、精神科医等に対して産業保健に関する研修を実施してきており、それぞれ、11,460人、1,646人(うち、精神科医等に対する産業保健に関する研修受講者のうち、その情報提供に同意した者については、地域産業保健センターに登録:1,131人が登録)修了しているので、引き続き、研修を実施するとともに、今後は、産業医と精神科医等とのネットワークの強化に努める必要があるのではないか。
[2] 地域産業保健センターにおける保健師の活用実績が少ないので、保健師等産業保健スタッフの積極的な活用を図る必要があるのではないか。
[3] 産業保健について習熟している専属産業医と臨床医としても活動する嘱託産業医の連携を考える必要があるのではないか。
<参考>
ア 共通
<産業保健委員会答申(15ページ)>
就業者のメンタルヘルス対策を推進するうえで、(1)産業医と事業場外資源の医師との連携、(2)産業医と看護職・心理専門職との連携、(3)地域保健と産業保健の連携を図るための具体的な方法についてのガイドラインを作成する必要がある。
イ 産業医と精神科医等とのネットワークの強化関係
<産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会報告書(15ページ)>
職場で生ずる種々の疾病や健康確保上の問題について、ケースによっては早期に臨床医による対応の必要があることなどから、産業医と臨床医の連携が確保されることが必要である。
例えば、メンタルヘルス対策に関しては、臨床精神科医との連携が十分とれていないとの回答が4割を超えているという調査(産業医科大学)がある。
<産業保健委員会答申(15ページ)>
日頃から、産業医は、自らうつ病や自殺対策について理解を深めておくとともに、精神科医、心療内科医等のメンタルヘルスに関わる医師、医療関係者とのネットワークづくりをしておく必要がある。
ウ 産業医と保健師等産業保健スタッフとの連携関係
<産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会報告書(15ページ)>
事業場における産業保健サービスの実施には、産業医が保健師等の産業保健スタッフと連携して活動する必要がある。特に今後対応を進めていく必要のあるメンタルヘルス対策においては、保健師や産業カウンセラーなどが産業医と協力しながら相談に対応するなど専門スタッフとの連携が極めて重要である。
今後、スタッフの専門性を育てつつ、積極的な活用を図るとともに、密接に連携を図っていくことが期待される。
<小規模事業場における健康確保方策の在り方に関する検討会報告書(6ページ)>
健康診断結果に基づく保健指導の充実を図るため、保健婦・士を積極的に活用する必要がある。(中略)そのため、地域産業保健センターや地域の保健婦・士等の活用促進についての支援策について検討する必要がある。
<産業保健委員会答申(17ページ)>
また、メンタルヘルス対策を担う専門職として、産業カウンセラー、精神保健福祉士の活用を検討する必要がある。
エ 専属産業医と嘱託産業医の連携関係
<産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会報告書(15ページ)>
地域産業保健センター、地域の医師会等を核として、産業保健について習熟している専属産業医と臨床医としても活動する嘱託産業医の連携等産業医間のネットワークを構築することにより、その両者の特性を活かし産業保健サービスの質の向上を図ることが期待される。
6 地域保健との連携の現状と課題
(1)メンタルヘルス、自殺対策に係る地域の社会資源
ア 現状
メンタルヘルス・自殺対策に関する主な地域の社会資源には、以下のものが挙げられる。なお、社会資源ごとに提供できるサービスの種類(例:一次予防、二次予防、三次予防等)は異なる。
[1] 医療機関(病院、診療所)(日精協会員1,215、日精診会員1,469)
[2] 医療機関併設のメンタルヘルス対策支援機関
(労災病院勤労者予防医療センター・勤労者予防医療部(32)、勤労者メンタルヘルスセンター(13)、など)
[3] 精神保健福祉センター(66)
[4] 保健所(571)
[5] 健診機関
[6] 民間有料相談機関
[7] 民間無料相談機関(いのちの電話、NPO法人など)
[8] 健康保険組合(健康保険組合連合会会員1,502など)
イ 課題
[1] 職域の社会資源と地域の社会資源の連携が十分に図られておらず、それへの対応が必要ではないか。
[2] 地域にある社会資源の種類・数、提供できるサービスについて、サービスを求めている事業場・労働者・家族等が把握しておらず、それにより、必要なサービスが提供されていないのではないか。
(2)地域・職域連携推進協議会の活用促進
ア 現状
[1] 位置づけ
・地域保健法第4条に基づく基本指針及び健康増進法第9条に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針において、地域と職域の連携推進のため、関係機関等から構成される協議会としての位置づけがなされている。
・地域・職域連携推進協議会は、都道府県及び2次医療圏を単位として設置し、地域・職域連携共同事業の企画・実施・評価等において中核的役割を果たしている。
[2] 目的と役割
| 都道府県協議会 | 2次医療圏協議会 |
|
○各関係者(医療保険者、市町村衛生部門、事業者、関係団体等)の実施している保険事業等の情報交換、分析及び第三者評価 ○都道府県健康増進計画や特定健康診査等実施計画等に位置づける目標の策定、評価、連携推進方策等の協議 ○各関係者が行う各種事業の連携促進の協議及び共同実施 ○事業者等の協力の下、特定健診・特定保健指導等の総合的推進方策の検討 ○協議会の取組の広報、啓発 |
○2次医療圏固有の健康課題の明確化 ○共通認識として明確化された健康課題に対して、各構成機関・団体として担える役割の確認と推進 ○健診の実施状況及び結果等の健康に関する情報の収集、健康意識調査等によるニーズ把握等の実施 ○健康づくりに関する社会資源の情報交換、有効活用、連携、調整 ○健康に影響を及ぼす地域の環境要因に関する情報交換、方策の協議、調整 ○具体的な事業の企画・実施・評価等の推進及び事業に関する広報 ○圏域の市町村、事業所への支援 ○協議会の取組の広報、啓発 |
[3] 構成メンバー
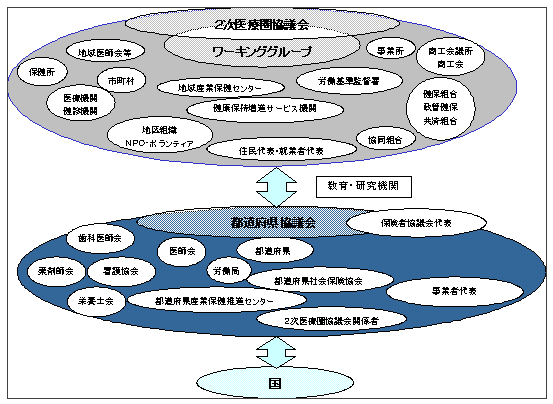
[4] 実績
平成18年3月31日現在、都道府県協議会は43カ所、2次医療圏協議会は194カ所設置。
イ 課題
[1] 職域関係者のメンバーは労働行政関係者にとどまり、事業者の参加が少ないことが指摘されている。(具体的には、どこに声をかけてよいかわからない、事業者の情報が少ない。)
[2] 2次医療圏と労働基準監督署の管轄区域が異なるため、複数の2次医療圏協議会に労働基準監督署が参画をしなければならず、協力が得られにくいことが指摘されている。
[3] 職域関係者との連携については、関係者の連携事業のメリット等について明確化されていないことから、都道府県や2次医療圏での具体的な連携事業の取組が進んでいないことが指摘されている。
(指摘内容は平成18年度地域・職域連携支援検討会報告書から抜粋)
<参考1>
● 歯周疾患 〜地域・職域を通じた検診機会の確保〜
「歯周疾患の予防等に関する労働者への配慮について」平成20年5月30日基発第 0530003号
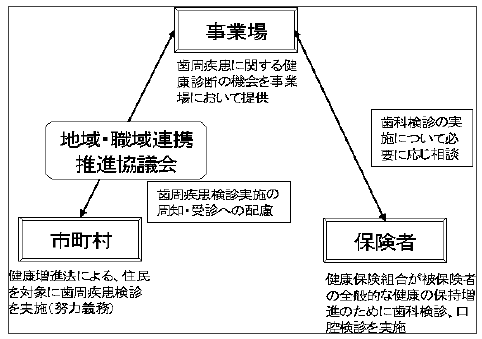
●がん検診 〜がん検診事業の評価に関する委員会報告書より抜粋〜
[1] 現状及び基本的な考え方
現在国民の受けているがん検診の約半数は職場におけるがん検診であり、特に比較的若年の男性(〜50歳代)においては、多くが職場においてがん検診を受けている。また、妊婦健康診査時にも子宮がん検診が実施されることがあり、これら職場におけるがん検診や妊婦健康診査において実施されているがん検診についても、精度管理及び事業評価を行うことが望まれる。
[2] 具体的な対応
具体的には、以下のような取組が考えられる。
・ 生活習慣病検診等管理指導協議会は、「地域・職域連携推進協議会」、「保険者協議会」及び母子保健担当部局との協力を得た上で、職場等における検査項目や受診者数等の把握を行う。
・ 都道府県や市町村は、がん検診実施機関毎の精度管理の状況について、企業、保険者及び母子保健担当部局等に情報提供を行う。
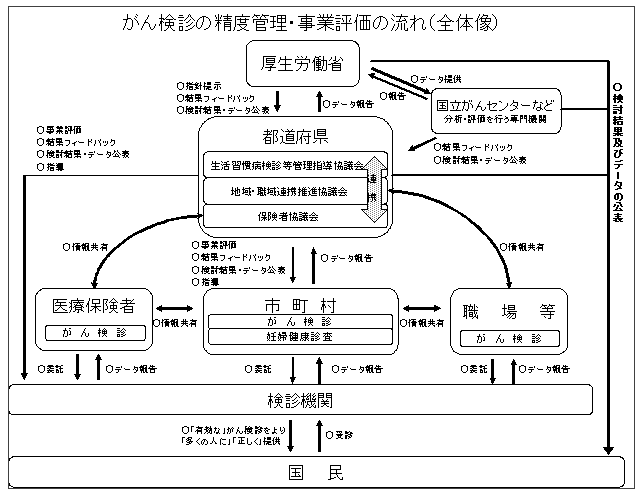
<参考2>
<産業保健委員会答申(12ページ)>
都道府県や二次医療圏に設置される地域・職域連携推進協議会には、小規模事業場の産業保健について熟知した者を含めて議論する必要がある。地域・職域連携推進協議会は、都道府県医師会産業医部会や産業保健推進センターが主導して推進する必要がある。
