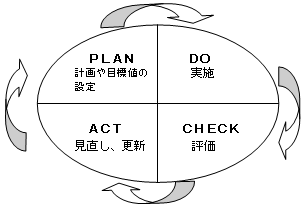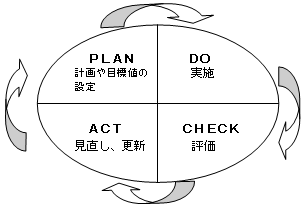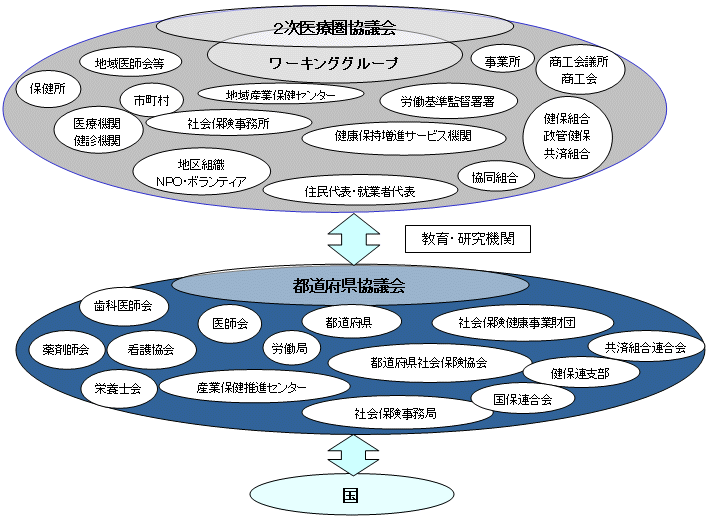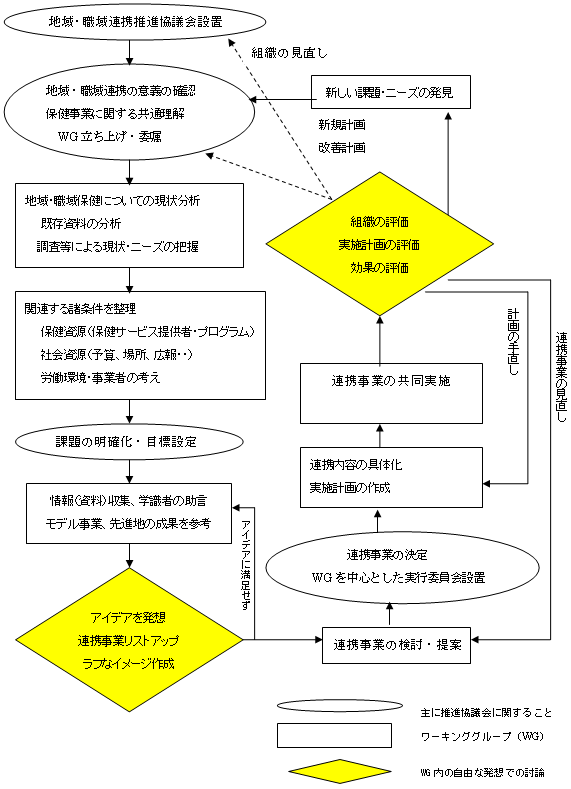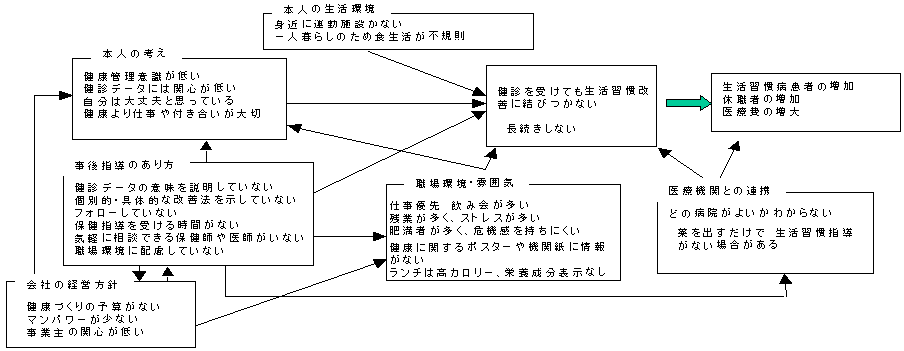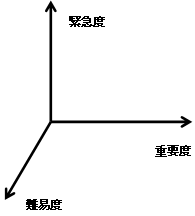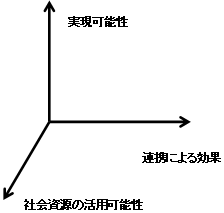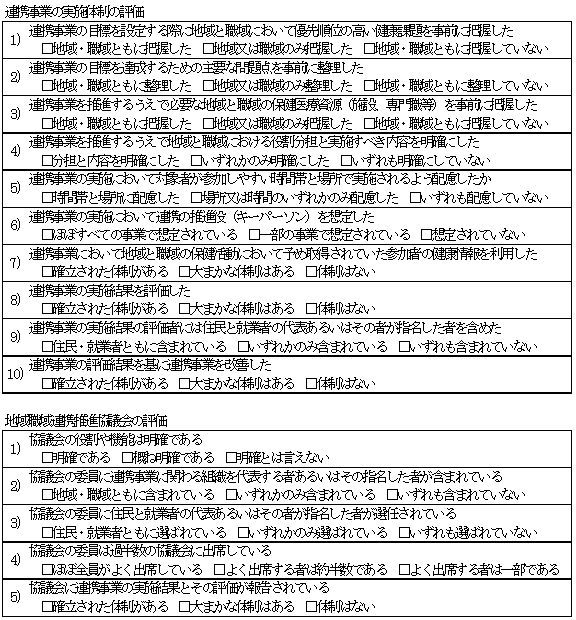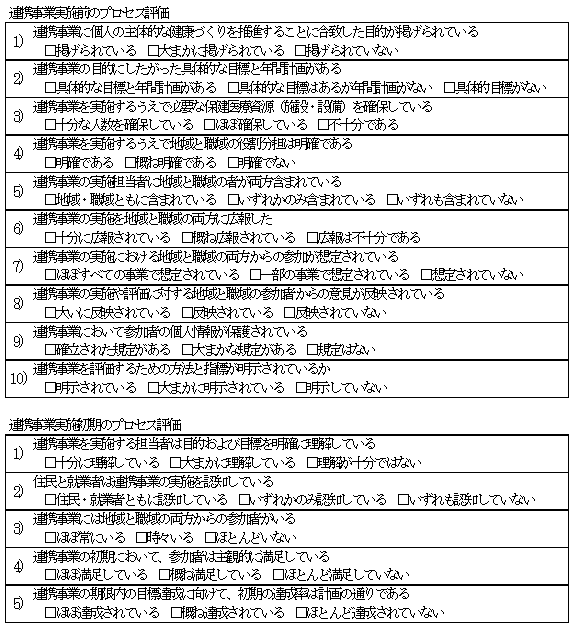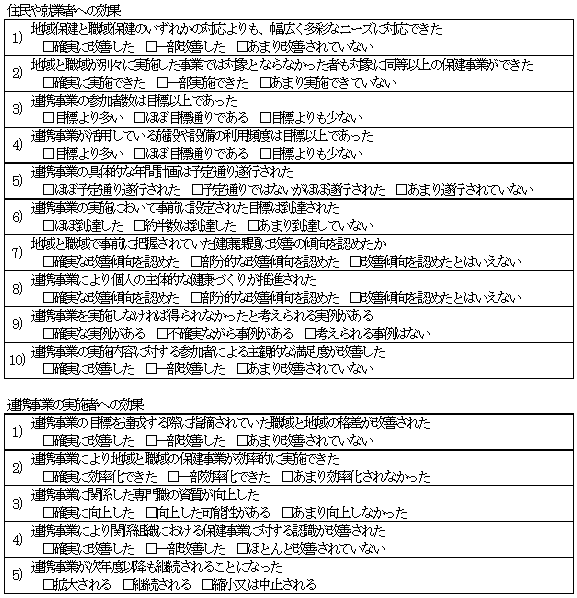地域・職域連携推進事業ガイドライン
平成17年3月
地域・職域連携共同モデル事業評価検討会
目次
はじめに
おわりに
参考資料
はじめに
近年の急速な高齢化が進む中で、疾病構造が変化し、がんや心臓病、糖尿病等の生活習慣病が増加している。生活習慣病は、日々の生活習慣の積み重ねがその発症に大きく関与することが明らかになっており、これを予防するためには、個人の主体的な健康づくりへの取組みが重要であり、健康教育、健康相談、健康診査等の保健事業による生涯を通じた継続的な健康管理の支援が必要となる。
一方、青壮年層を対象に行われている保健事業は、老人保健法や労働安全衛生法、健康保険法等の根拠法令によって目的や対象者、実施主体、事業内容がそれぞれ異なっており、制度間のつながりがないことから、地域全体の健康状況を把握できなかったり、退職後の保健指導が継続できないといった問題が指摘されている。このような問題を解決し、継続的、かつ包括的な保健事業を展開していくためには、地域保健と職域保健が連携し、健康情報のみでなく、健康づくりのための保健事業を共有していくことが重要となる。
こうしたことから、厚生労働省においては、平成11年度より3年間、生活習慣病予防を目的とした地域保健と職域保健の連携の在り方について検討し、地域保健と職域保健の連携を推進するため、平成14年度及び15年度に地域・職域連携共同モデル事業を実施したところである。また、平成16年度には、地域・職域連携共同モデル事業の成果をもとに、地域保健及び職域保健の連携を全国的に普及するため、ガイドラインを作成することとした。平成17年度からは、生活習慣病対策の推進と介護予防を柱とした「健康フロンティア戦略」を展開することとしており、働き盛り層を主に総合的予防対策を推進するための「働き盛りの健康安心プラン」に基づき、地域と職域を通じた保健事業を展開していくこととしている。
このガイドラインには、地域・職域連携を行うための基本的な考え方や地域・職域連携共同事業の企画、地域・職域連携推進協議会の運営、事業の実施結果に関する評価等についてわかりやすく記述している。今後の地域保健と職域保健の連携をより有効に行うために、ご活用いただければ幸いである。
| |
地域保健は、主に地域保健法や健康増進法、老人保健法、母子保健法などの法令を基に乳幼児、思春期、高齢者までの地域住民を対象として、生涯を通じてより健康的な生活を目指した健康管理・保健サービスを提供している。一方、職域は主に労働基準法、労働安全衛生法などの法令を基に就業者の安全と健康の確保のための方策の実践を事業者、就業者に課している。さらに、医療保険制度は健康保険法などの法令を基に、国民が安心して医療を受けるための制度であり、就業者を対象とした社会保険、地域住民や自営業を対象とした国民健康保険制度が存在し、これらもまた、被保険者に健康保持増進のための保健サービスを提供している。
地域保健、職域保健(医療保険を含む)とそれぞれの目的は必ずしも一致しているわけではないが、提供している保健サービスには共通したものがある。平成15年に施行された健康増進法は、健康に向けての努力を国民に求めると共に、それぞれの健康増進実施事業者の連携を促し、効果的な保健サービスの実行を求めている。
実態に目を移すと、職域には過重労働、メンタルヘルスなど多くの健康課題があり、特に小規模事業所における産業保健サービスの提供が大きな課題である。また、地域保健は、職域保健の現状を把握し連携していく方策が未確立であり、十分に対応できないという課題や、健康寿命の延伸に向けての実効的な対策を採らなければいけないという課題がある。健康寿命の延伸、生活の質の向上という健康日本21の目的を達成するためには、これまで蓄積した方策を互いに提供し合い、職域保健と地域保健が連携した対策を講じることが不可欠であるといえる。
地域保健と職域保健における連携とは、それぞれの機関が有している健康教育、健康相談、健康情報等を共有化し、より効果的、効率的な保健事業を展開することである。そのためには、お互いの情報を交換し、理解しあう場(地域・職域連携推進協議会)を持ち、互いの知恵を出し合い、課題を明確にし、Plan−Do−Check−Actサイクル(PDCAサイクル)を展開していくことが必要である。 |
図1.PDCAサイクル
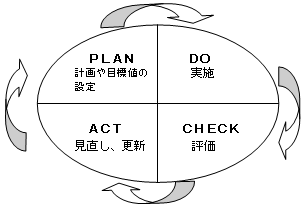
| |
地域保健と職域保健が連携を行うことにより、以下のようなメリットが得られると考えられる。 |
| 1) |
連携により地域保健情報に、職域保健情報を加えて検討することにより、地域全体の健康課題がより明確となる。
|
| 2) |
生涯を通じた継続的な健康支援を受けることができる。
|
| 3) |
健康課題に沿った、個人のニーズへの幅広い対応が可能となり、対象者にとって保健サービスの量的な拡大になる。
|
| 4) |
生活の場である地域を核として、就業者を含めた家族の健康管理を、家族単位で共通の考え方に沿って指導ができることにより、保健指導の効果を上げることができる。
|
| 5) |
地域保健と職域保健が共同で事業等を行うことにより、整合性のとれた保健指導方法の確立ができ、保健事業担当者の資質の向上につながる。
|
| 6) |
地域保健における保健事業の活用により、事業者による自主的な健康保持増進活動の推進がより容易になり、就業者の健康の保持、増進が図れるようになり、生産性の向上に寄与できる。
|
| 7) |
地域と職域が共通認識を持ち、健康づくりを推進することは、健康日本21の推進に資すると共に、生活習慣病が予防できることにより、将来的に医療費への影響が考えられる。 |
地域・職域連携推進協議会(以下、「協議会」という。)の設置については、地域保健法第4条に基づく基本指針及び健康増進法第9条に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針において、地域と職域の連携推進にあたり、関係機関等から構成される協議会等の設置が位置付けられた。なお、本協議会は、都道府県及び2次医療圏を単位として設置し、地域・職域連携共同事業(以下、「連携事業」という。)の企画・実施・評価等において中核的役割を果たすものとする。また、各地方公共団体の健康増進計画(健康日本21地方計画)の推進に寄与することを目的とする。
| |
地域・職域において、生涯を通じた健康づくりを継続的に支援するための効果的な保健事業を構築する。すなわち生活習慣病を予防し、健康寿命の延伸を図るために、ヘルスプロモーションの視点に立って自治体、事業者及び医療保険者等の関係者が相互に情報交換を行い、保健事業に関する共通理解のもと、それぞれが有する保健医療資源を相互活用、又は保健事業の共同実施により連携体制を構築する。 |
| 1) |
都道府県を単位とする協議会(以下、「都道府県協議会」という。)では、地域及び職域保健の広域的観点での連携により体制整備を図る。 |
| 2) |
2次医療圏を単位とする協議会(以下、「2次医療圏協議会」という。)では、より地域の特性を活かす観点から、地域特性に応じた協力体制による継続的な健康管理が可能となるよう体制を構築する。 |
| 1) |
都道府県協議会では、都道府県内の広域的な連携に関わる地域保健及び職域保健の行政機関、関係機関、関係団体、事業所の代表者等で構成する。 |
| 2) |
2次医療圏協議会では、2次医療圏において連携事業に関わる行政関係者、関係機関代表者、関係団体、医療機関、健診機関、事業者、学識経験者、住民・就業者の代表等で構成する。
なお、具体的な関係機関・関係団体等は参考資料を参照していただきたい。 |
| 1) |
都道府県協議会では、都道府県における健康課題を明確化し、管内全体の目標、実施方針、連携推進方策を協議することなどにより、管内の関係者による連携事業の計画・実施・評価の推進的役割を担うと共に地域・職域における保健事業担当者の資質向上を図るための研修会を開催するなど、地域の人材育成を行う。
また、2次医療圏協議会における連携事業の効果や協議会の役割機能の評価など、2次医療圏協議会の取り組みについての広域的な調整を図る。 |
| 2) |
2次医療圏協議会では、地域における関係機関への情報提供と連絡調整や健診の実施状況及び結果等の健康に関する情報の収集、健康意識調査等によるニーズ把握等を行うと共に、地域特性を活かした具体的な連携事業の計画・実施・評価等を行う。 |
| |
都道府県協議会は地域保健主管課が、2次医療圏協議会は保健所等が事務局を担う。 |
| 1) |
ワーキンググループの設置
2次医療圏協議会においては、連携事業の核となり、連携を円滑に推進するために、直接、連携事業を担当する者で構成するワーキンググループ等を設置する。ワーキンググループは、具体的な事業の企画・実施に向けて意見交換を行い、現状分析や実施計画の企画立案、運営、評価を行う。 |
| 2) |
キーパーソンの配置及び役割
2次医療圏協議会は、地域・職域保健の連携が円滑に行われるために、地域保健と職域保健の両方に理解のあるスーパーバイザー的なキーパーソンを配置することが望ましい。キーパーソンは、連携事業が効果的に推進できるよう広域的・総合的視点により助言、支援等を行う。 |
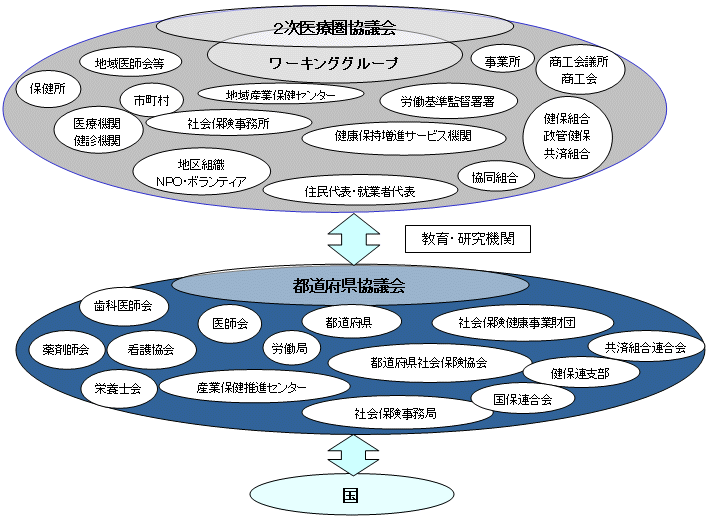
図2 地域・職域連携の概念図 |
地域・職域の健康課題やニーズを把握した上で、計画、運営・実施、評価、見直しという一連の流れに沿って企画していく(図3)。連携事業を継続的に発展させていくためには、評価、見直しのプロセスをあらかじめ計画しておくことが大切である。
| |
地域・職域における健康管理体制や健康状態について調査し、現場のニーズを把握する。これらの調査を行うことによって、(1)在職中から退職後へと、個人の生涯を通して円滑な保健サービスを提供する必要性を共通認識できる、(2)地域において職域の保健情報を入手できるため、健康日本21をはじめとした地域保健の推進体制を強化することができる、(3)事業者、就業者の「健康管理」に対する意識を喚起することができる、などの初期効果を期待でき、連携事業に向けた協力体制構築の第一歩を踏み出すことが可能となる。
初期の段階としては、地域・職域ともに大きな負担をかけず、おおまかに現状を把握し、課題を発見することを目的とする。国民健康栄養調査、就業者健康状況調査、都道府県産業保健推進センターや当該圏域の地域産業保健センターによる調査報告などの既存資料を活用したり、一部関係者を対象とした健診状況や生活習慣、就業者の健康に対する悩み等の聞き取り調査を行い、ワーキンググループで分析する。さらに踏み込んだ現状分析が必要であると判断される場合には、もう少し範囲を広げた聞き取り調査や、アンケート調査、現地調査などを企画・実施・分析する。 |
具体的な調査項目としては、以下のような項目が上げられる。
| 1) |
健診実施状況・健診結果の動向(既存資料)
| ・ |
自治体や事業所における健診の実施状況(回数、方法、受診率等) |
| ・ |
健診の結果(有病率、性別・年代別の分析、動向等) |
|
| 2) |
事後指導実施状況(聞き取り調査、既存資料)
| ・ |
事後指導実施の対象者の選定方法、指導担当者、指導方法、指導内容等 |
| ・ |
事後指導の実施率、効果、問題点等 |
|
| 3) |
生活習慣状況(聞き取り調査、現地調査、アンケート等)
| ・ |
栄養、食生活(食習慣(行動)アンケート、栄養成分表示の利用等) |
| ・ |
身体活動、運動(労働・通勤による身体活動量、余暇時間の使い方等) |
| ・ |
休養、こころの健康(睡眠の状況、うつ対策、時間外労働、職場環境等) |
| ・ |
喫煙状況(喫煙率、分煙対策や禁煙啓発活動の状況等) |
| ・ |
アルコール(飲酒状況、肝機能障害者の割合、啓発活動の状況等) |
| ・ |
歯の状況(歯周病健診受診率、口腔ケアの状況等) |
|
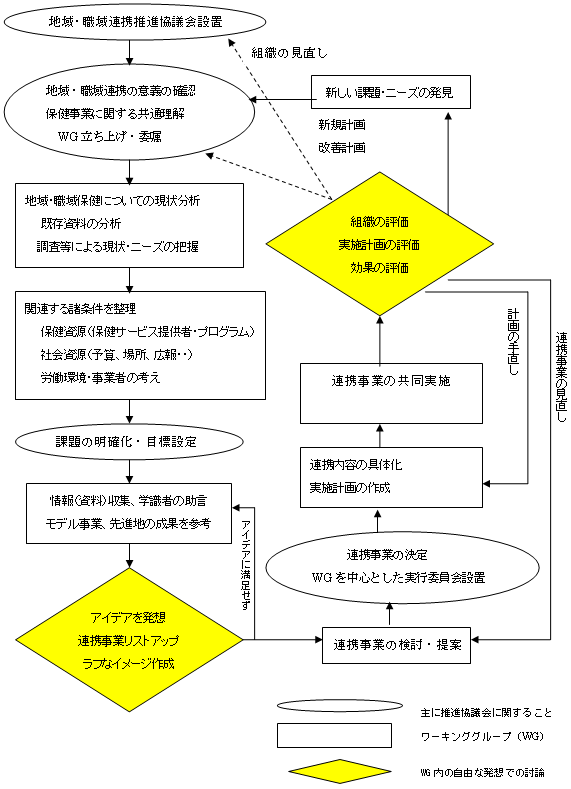
図3.連携事業の流れ |
| 4) |
住民や就業者の保健事業に関するニーズ把握(聞き取り調査、簡単なアンケート)
| ・ |
住民や就業者の健康意識、健康について気になること、聞きたいこと |
| ・ |
健診情報を考慮した健康行動をとっているか |
| ・ |
どのような健康づくり活動を望むか(講演会、個別相談、資料、環境整備等) |
| ・ |
保健事業に希望する条件(実施時間帯、回数、対象範囲及び人数、予算等)
さらに、連携事業の企画に向けて、関連する諸条件についての情報を事前に得る。
|
|
| 5) |
健康づくりのための社会資源
連携事業のツールとしての社会資源(媒体等)に関する情報を収集する。
| ・ |
会場、運動施設(使用可能時間、利用料金等) |
| ・ |
健康教育媒体(リーフレット、冊子、スライド、ビデオ等) |
| ・ |
広報媒体(ポスター、チラシ、インターネット、電子メール、マスコミ(TV、CATV、ラジオ、新聞、業界ニュース等))
|
|
| 6) |
保健事業担当者の配置状況
| ・ |
地域・職域において活用できる人材(関係機関の項目参照)
職種・専門分野、指導可能なテーマ、対応可能な時間、講師料等 |
|
| |
「1.現状分析」を通して情報収集された、対象地域や職域における課題間の要因を整理し、両者間で情報を共有する。ワーキンググループにおいて、KJ法、要因効果図(図4.問題点をグループ化し、命名する。グループ間の関係を矢印で結ぶ。)などを用いて課題間の関連(因果関係、並列関係など)について整理することにより、課題を絞りこむことができる。 |
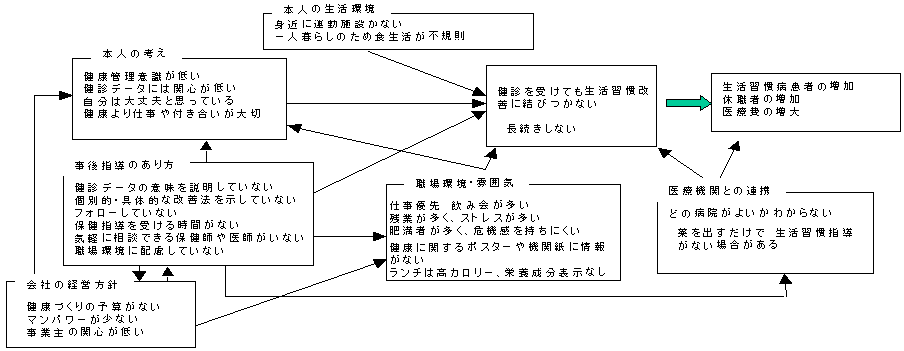
図4.要因効果図(例示) |
| |
その上で、緊急度、重要度、難易度を考慮し、課題に優先順位をつける。
初期段階としては、重要度、緊急度が高く、難易度が低いものから手がけるとよい。しかし、難易度が高いものでも、重要度の高い課題については、長期的な目標としておく。
優先順位の高い課題について、具体的な目標を設定する。数値目標を立てることが可能であれば、評価の際に役立つ。 |
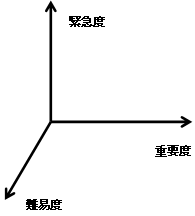
図5.課題の優先順位
| |
ワーキンググループにおいて、設定された目標に対して、考えられる連携事業を自由な発想でできるだけ多くリストアップする。生活習慣改善意欲を高め、行動変容を促すような健康教育の共同開催や、やる気になった個人が求める健康情報を入手できる情報マップ、食堂のメニューの見直しや栄養成分表示、運動しやすい環境づくりなど、就業者を含めた地域住民の主体的な健康行動につながる事業を、当事者の視点に立って発想していく。
また、地域保健・職域保健においてこれまでそれぞれが独立して実施してきた保健事業を参考にするだけでなく、モデル事業等の先行事業や研究報告の資料を集める、先進地での実施状況や評価結果を問い合わせる、学識経験者の助言を聞くなどして、できるだけ多くの候補を上げるとよい。このことにより、ワーキンググループ内の情報交換が活性化し、それまでとは違った視点での連携事業の開発が可能になる等、相乗的な効果が期待される。
このうち、地域・職域が単独で実施できるものは除外し、社会資源等の状況を勘案して連携事業(案)のリストを作成する。 |
| |
前項でリストアップした連携事業の中から、(1)実現可能性が高く、(2)連携による効果が期待でき、(3)健康増進計画の目標と合致しており、(4)当該地域における社会資源を活用できるものを、ワーキンググループで選ぶ。初期段階では「まず、やれること」からスタートし、就業者の共感や事業者の理解を得ながら段階的に実績を積み上げていくという姿勢が大切である。実現可能性としては、予算、人的資源、これまでの事業実績などを勘案する。
地域・職域のいずれかが依存的になり過ぎる片方に負担感が大きいという場合には、学識経験者など第三者の助言を受けたり、もう一度連携の目的を再確認しておくとよい。
原案を作成したら、協議会等において関連する組織・団体等に提示し、理解を求め、実施体制を決定する。必要に応じてワーキンググループを立ち上げ、事業実施に向けて、役割分担を明確にする。 |
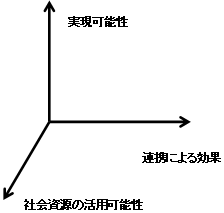
図6.連携事業の優先順位の考え方
| |
連携事業の目的、対象者、内容、実施方法(出前型、シリーズ型、イベント型等)、会場、時期、主催・共催、募集人数、従事スタッフ、費用等を具体化し、要綱(実施計画)を作成する。また、実施主体、運営方法、関係機関の役割分担や対象者にあった広報を工夫する。さらに、プログラムや教材等の作成、必要物品の調達、講師の手配、受付方法等、企画の流れに沿って整備を進める。なお、参加者を事前に把握できる場合には、参加者の同意を得て健康に関する個人情報を確認することが効果的な場合も考えられる。
こうしたことから、実施計画作成にあたっては、これまで単独で行ってきた事業の枠組みから一歩外に出ることもありうる(時間設定等)が、地域住民の健康向上の理念にどこまで歩み寄れるかを念頭に、調整することが望ましい。 |
| |
より効果的・効率的に連携事業を展開することを目指すためには、連携事業実施中及び事後に評価を行い、改善策を検討することが欠かせない。そのため、評価指標や評価結果の活用法については、事業企画時に前もって検討し、円滑な事業展開に資するとよい。事業の効果やプロセスを評価することにより、連携事業の方法(教材や教育方法等)を変更する、予算を獲得する、目標を修正するなどの改善案を作成することが可能となる。また、組織づくりについて評価することにより、新メンバーの加入を促すなど協議会やワーキンググループの発展にもつなげることができる。
評価結果を協議会で協議し、次年度の事業についての検討や、他事業所・他地区へも波及させることに活用していく。 |
連携事業の実施にあたっては、ワーキンググループなどで分析・検討を行い、連携事業を企画・提案する。地域の実情を考慮しながら連携内容の具体化及び実施計画を作成し連携事業を進めていく。連携事業の実施は、人的資源の相互活用を始めとして場所や情報、知識、技術などの共有化を図ることにより総合的、効果的、効率的、継続的な事業展開ができるものである。
| 1) |
地域・職域の共通課題やニーズを把握するための調査事業(実態調査、意識調査等) |
| 2) |
健康づくりに関する事業(健康教育、健康相談等) |
| 3) |
全体企画としての事業(フォーラム、健康情報マップ作成、ポスター作成等) |
| 4) |
関係者の資質の向上に関する事業(マニュアル作成、研修会等) |
| 1) |
地域・職域の共通課題やニーズを把握するための調査事業(実態調査・意識調査等) |
| (1) |
目的・内容
健康課題を解決するために、より踏み込んだ現状分析を行う必要がある場合に、実態調査や健康意識調査を行う。調査項目については前章の連携事業の企画(6ページ)を参考とし、その地域に必要な項目を付加する。
なお、健康増進計画において、数値目標、行動目標、環境づくり目標が設定されていれば、その目標値などを活かし、評価できる内容を組み込む。 |
| (2) |
方法
| (1) |
ワーキンググループで調査目的、対象、調査項目、調査方法等について検討を行い、協議会と調整を行う |
| (2) |
協議会は、ワーキンググループが作成した調査表に基づき調査を行う |
| (3) |
調査結果は、ワーキンググループにおいて分析を行い、結果の活用方法を検討し、連携事業の企画に活かす |
|
| (3) |
モデル事業の具体例
| ・ |
美唄市における小規模事業所の健康管理に関する調査(北海道) |
| ・ |
小規模事業所における健康意識実態調査(山形県) |
| ・ |
企業における健康づくり実態調査(富山県) |
| ・ |
地域における分煙推進状況調査(岐阜県) |
| ・ |
実態調査(愛知県) |
| ・ |
事業所における健康づくりアンケート調査(山口県) |
|
| 2) |
健康づくりに関する事業(健康教育、健康相談等) |
| (1) |
目的・内容
地域保健や職域保健において実施されている健康づくりに関する保健事業を住民や就業者が相互に活用できるよう、共同して健康教育や健康相談を行う。このような連携事業によって、多くの対象者が保健サービスを受けることができる。
健康教育、健康相談等の企画にあたっては、現状分析された健診実施状況・健診結果の動向や生活習慣状況、また住民や就業者の保健事業に関するニーズ把握などの現状分析を踏まえて、連携事業を企画する。 |
| (2) |
方法
ワーキンググループで検討し具体化された目的、対象、内容について、連携事業の趣旨を踏まえ、参加しやすい時間帯や場所の設定を行い、連携事業の従事者の調整や役割分担を行う。具体的には、以下の実施方法が考えられる。
| (1) |
地域保健で開催される糖尿病教室や禁煙教室などの健康教育の場に就業者が参加できる設定を行う |
| (2) |
職域保健で開催される保健事業に、地域保健担当者が出向いて健康教育を行う(出前健康教室) |
| (3) |
地域・職域が共同で課題別の健康教育をシリーズ的に開催する |
| (4) |
効果的な健康教育を行うために健康講座プログラムなどを作成し、教育内容の標準化を図る |
| (5) |
住民及び就業者が生活習慣改善を図られるように、健診事後指導に使用するパンフレットを共同で作成し、標準化を図る |
|
| (3) |
モデル事業の具体例
| ・ |
出前健康講座(北海道・山形県) |
| ・ |
働きざかり健康講座(福島県) |
| ・ |
健康教室(ヘルスアップカレッジ)の実施(富山県) |
| ・ |
“出前”元気な職場づくりの実践(山口県) |
| ・ |
たばこ、騒音対策、腰痛予防、飲酒についての指導(高知県) |
|
| 3) |
全体企画としての事業(フォーラム、健康情報マップ、ポスター作成等) |
| (1) |
フォーラムの開催
| (1) |
目的・内容
地域・職域が共同して、休日などに体育館などの大きな会場で健康に関する様々なイベントを行う。この事業は住民、就業者を含めて地域全体で健康づくりの機運を盛り上げることができ、また、正しい健康情報の提供や気軽に相談できる場などを設けることで、家族単位の健康づくりを支援することができる事業である。
フォーラムは、地域・職域連携を開始した初期段階においても比較的スムースに企画運営ができる、取り組みやすい事業である。 |
| (2) |
方法
| ア |
フォーラムの目的を確認し、テーマを設定する。テーマやイベントの内容は、地域・職域の現状分析や参加者のニーズを十分考慮して決定する。また、多くの住民や就業者が参加しやすい日程や会場を選択する |
| イ |
事業の実施にあたっては、リーダーを決定し、関係者の役割分担を行い、効果的、効率的な広報を行う |
| ウ |
フォーラム開催当日は、参加者及び事業担当者が主体的に楽しく健康づくりができるような企画とする |
| エ |
フォーラムは1日の単発事業であることが多いが、事業の効果を継続するために、関連事業の計画やパンフレットの配布等を行い、参加者の健康に対する意識が、より高まるような方策を講じることが重要である |
|
| (3) |
モデル事業の具体例
| ・ |
地域・職域連携推進フォーラム(山形県) |
| ・ |
簡易チェックと健康日本21あいち計画推進フォーラム(愛知県) |
| ・ |
南知多産業まつり健康相談コーナー(愛知県) |
|
|
| (2) |
健康情報マップの作成
| (1) |
目的・内容
地域・職域で行われている保健事業や健康づくりに役立つ施設等に関する情報を、住民や就業者に提供することにより、地域全体の自主的な健康づくり活動を支援するとともに、健康に関連した社会資源の有効活用を図るために、情報マップを作成する。
また、事業者が就業者の健康管理に役立てられるように、地域における保健医療福祉関連情報を集約した情報マップもある。
| ア |
公園、体育館等の運動施設、ウォーキングコース |
| イ |
カロリー表示等の健康づくり協力店、分煙実施施設 |
| ウ |
健康診査実施機関、2次健診実施機関、事後指導実施機関、健康相談機関等に関する場所、内容、対象者、料金、補助制度等 |
| エ |
人間ドック実施機関、健診結果の見方や相談窓口、心の健康相談窓口、栄養相談窓口等 |
| オ |
健康講座講師派遣制度の提供機関、健康づくりに関する研修会開催機関 |
| カ |
健康づくり関連機関連絡先一覧、関係機関の事業案内等 |
|
| (2) |
方法
| ア |
地域、職域それぞれが有する社会資源及び保健事業等の情報をを収集する |
| イ |
相互活用できる社会資源及び保健事業について、対象別、種類別などに分類し整理する |
| ウ |
情報不足が判明すれば新たに調査を行い、追加情報の整理をする |
| エ |
得られた社会資源等の情報を地図に落とし、健康情報マップを作成する |
| オ |
作成したマップの活用方法について検討し、有効活用を図る |
| カ |
マップ作成後、定期的に情報の更新ができ、改善が図れるような体制をつくる |
|
| (3) |
モデル事業の具体例
|
|
| 4) |
関係者の資質の向上に関する事業(マニュアル作成・研修会) |
| (1) |
保健事業マニュアルの作成
| (1) |
目的・内容
地域保健で行われている保健事業と職域保健の保健事業は類似した内容であるが、保健事業の目的、対象者の相違等から若干異なっている。連携事業を共同で行う場合、その違いを理解し、明確にした上で整合性のとれた保健事業を実施することが必要であるためがあることから、保健事業マニュアルを作成するものである。
また、連携事業を共同で実施するために、事業目的の共有化を図り、連携事業に携わる者が共通の知識、手法を持つことにより、資質の向上が図られる。 |
| (2) |
方法
| ア |
地域・職域の関係者が集まり、連携事業を推進するための資質向上を目指したマニュアルの作成目的、必要性を明確にする |
| イ |
地域・職域、それぞれの事業実施スタンスを確認し、共通認識のもとで、マニュアル作成を行う |
| ウ |
マニュアルの内容として、事業の基本方針、期待できる効果なども記述し、作業手順を書く |
| エ |
マニュアルを活用する者の職種や経験を考慮し、階層別に記述する |
| オ |
成功事例だけではなく、失敗事例も掲載する
|
|
|
| (2) |
研修会の開催
| (1) |
目的・内容
地域・職域連携は、立場の異なる多くの組織が参画することから、協議会の開催や連携事業の実施にあたっては、連携の目的を共有化し、共通認識に立って事業を行う必要がある。このためには、知識や技術を共有する場として研修事業の実施がある。
研修会の企画にあたっては、参加者の理解度や関心度を勘案して、研修内容のレベルを段階的に上げていくようなプログラムとする。
研修内容としては、以下のものが考えられる。
| ア. |
連携事業に携わる者の相互理解を進めるために各組織の事業紹介や、既存事業の見直しなどを行うグループワーク |
| イ. |
事業に関わる知識、技術を共有化するための講義や実習 |
| ウ. |
健康課題を解決する能力を習得のするための事例検討やグループワーク |
| エ. |
事業評価をするために第V章に掲載されているチェックリスト活用方法の実践 |
|
| (2) |
方法
| ア. |
協議会で研修の目的等、研修事業の骨格を検討し、ワーキンググループが研修会の具体的な企画を行い、研修運営のリーダーを決定する |
| イ. |
研修の対象者は、協議会メンバーや連携事業に携わる者であるが、地域・職域全般の研修に加え、事業担当別、専門分野別に分けた研修会の開催も行う |
| ウ. |
研修に必要な講師を依頼し、研修会場の確保、関係者への周知を図るが、この場合でも、関係者が参加しやすい日程、時間帯、会場を十分に考慮する。モデル事業では、火曜日から木曜日が集合しやすかった、土曜日開催したところもあった。会場は交通のアクセスがよいところが選ばれていた |
| エ. |
研修会の出席率を高めるため、協議会から通知を出すなどの工夫をする |
| オ. |
研修の内容や成果などを記録に残し、マニュアル化することが望ましい |
|
| (3) |
モデル事業の具体例
| ・ |
働きざかりの健康づくり研修会(福島県) |
| ・ |
事業所における健康づくり研修会(山口県) |
|
|
| |
連携事業は、それに参加あるいは関与した組織及び個人の全てが、地域と職域との連携のメリットを認識することあるいは享受することができ、自律的に発展していく事業であることが望まれる。しかし、連携事業は既成の組織の範囲を超えた事業である。そこで、その事業を企画して実施する者が自ら評価を行い、より良く改善していくよう努めなければならない。また、連携事業は年間計画の下で実施されるものや当初は単年度の企画であるものが多いことから、事業が終了してから評価や改善を行うのでは、次回の実施を検討する際には活用できないおそれがある。そこで、事業の評価や改善は事業の企画や実施と併行して行われることが望ましい。
このように、連携事業の評価は、連携事業を実施する者自身が常に連携事業を効果的に改善しようとする視点から、自ら又は相互に実施されるべきものである。また、連携事業の各段階にあわせて、実施体制、協議会の体制、目標の設定、事業運営の方法、計画の進捗、目標の達成度、参加者の健康指標の改善などといった評価項目が検討されるべきである。そこで、以下に、体制や資源について評価する構造評価、計画や方法を評価するプロセス評価、結果や達成度を評価する効果評価の3つに大別して、実際の評価や改善に使用することができるチェックリストの具体例を示した。これらは、連携事業の内容や実態に合うように作り変えて使用することが望まれる。 |
| 1) |
指標
連携事業の実施体制及び協議会の体制を評価することで、より効果的な事業の推進を図る。実施体制に関する課題は、連携事業に関わる組織の代表者や上位の意思決定機関に報告して、改善するための方策を検討する。通常想定される具体的な評価項目の例を、連携事業の実施体制の評価と協議会の評価に分けて別紙1のチェックリストに示す。 |
| 2) |
方法
連携事業の構造評価を実施するには、連携事業全体の計画書、協議会の議事録、ワーキンググループの議事録などの内容を調査する方法、連携事業の関係組織や担当者を対象に面接や質問紙により調査する方法がある。 |
| 1) |
指標
プロセス評価とは、企画された連携事業を、その実施前や経過中に評価することで、その後の目標や事業運営方法の修正に活用するものである。プロセス評価は、連携事業ごとに行われる。プロセス評価は、連携事業を実施する前及び実施した初期に行われる。通常想定される具体的な評価項目の例を、連携事業実施前のプロセス評価と連携事業実施初期のプロセス評価に分けて別紙2のチェックリストに示す。 |
| 2) |
方法
連携事業のプロセス評価を実施するには、各事業の計画書を調査する方法、各事業の参加者の名簿又は人数を調査する方法、各連携事業の参加者や関係者を対象に面接や質問紙により調査する方法、あるいは、地域と職域の保健医療資源(専門職数、関係施設等)や健康指標に関する既存の資料を調査する方法がある。 |
| 1) |
指標
連携事業実施後にその効果を評価する。効果評価は、定量的な評価により測定できるものばかりとは限らないことから、適宜、定性的な評価を含める。住民や就業者だけでなく、専門職に対する効果も対象とする。個人の健康度だけでなく、組織についても評価の対象とする。実施可能であれば、科学的な評価を実施する。効果評価の結果は、次の連携事業にフィードバックする。通常想定される具体的な評価項目の例を、住民や就業者への効果と連携事業の実施者への効果に分けて別紙3のチェックリストに示す。 |
| 2) |
方法
連携事業の効果評価を実施するには、連携事業の結果報告書の内容を調査する方法、連携事業に参加した者の名簿又は人数を調査する方法、連携事業の参加者や関係者を対象に面接や質問紙により調査する方法、あるいは、連携事業の実施前に到達度を評価するために設定された指標や主観的な満足度等を測定して比較する方法がある。ただし、科学的に実施するには、連携事業を実施した群と実施しなかった群に分けてあらかじめ設定された指標の変化を測定して比較することが望ましい。 |
別紙1
評価基準(例)
左から2点、1点、0点を配点し、合計点(30点満点)のうち、24点以上を「優れている」、18点以上を「やや優れている」、12点以上を「やや劣っている」、11点以下を「劣っている」と判定する。
別紙2
評価基準(例)
左から2点、1点、0点を配点し、合計点(30点満点)のうち、24点以上を「優れている」、18点以上を「やや優れている」、12点以上を「やや劣っている」、11点以下を「劣っている」と判定する。
別紙3
評価基準(例)
左から2点、1点、0点を配点し、合計点(30点満点)のうち、24点以上を「優れている」、18点以上を「やや優れている」、12点以上を「やや劣っている」、11点以下を「劣っている」と判定する。
連携事業を有効に活用するためには、モデル事業により明確となった推進要因を最大にし、事業により指摘された阻害要因の縮小、解消に努めることが必要である。
| 1) |
地域・職域の共通認識
連携事業の実施には、地域と職域といった異なる分野で実施されてきた関係者の意識を改革することが必要である。連携事業によりもたらされる将来的な健康増進効果を認識して、連携事業に取り組む関係者の熱意が期待される。 |
| 2) |
地域保健医療計画での記載
行政として、地域保健医療計画に連携事業が記載されていることは事業を推進するうえで有用である。さらに、市町村の健康増進計画に青壮年期の健康づくりが位置付けられていることは、具体的に市町村と事業所の理解を助ける上で有用である。以上のような環境のもとで、連携事業に関係する団体の協力を得ることは重要なステップである。 |
| 3) |
共通課題の選択
たばこ対策事業は地域と職域共通の健康課題として連携事業の1つとして関心が持たれやすいので連携事業が促進される。連携事業を実施するに際して、成功事例を持つことは関係者に具体的方向性を示すうえでも有用である。 |
| 4) |
地域保健資源の積極的発掘
地域保健における資源を積極的に発掘しておくことは、具体的な連携事業を提示するうえで有用であり、新たな事業を企画する際にも参考になる。 |
| 5) |
キーパーソンの確保
連携事業においてキーパーソンを確保することが必要である。キーパーソンは、地域保健、職域保健の両分野に精通していて、企画調整能力を持つ人材が適当である。
また、連携事業に関心がある人材を確保することは、事業の展開に有用であることから、地元の大学等の協力を得ることは、地域保健と職域保健をつなぐ人材として、その人材確保に期待される。 |
| 6) |
連携事業に必要な人材の確保
職域保健に必要な人材の確保のために、保健事業担当者の研修や潜在している人的資源を活用したり、ボランティアの育成等の工夫が考えられる。 |
| 7) |
連携事業の拡大
事業の連携を図る上で、地域保健と職域保健に限定せず、学校保健等と連携を図ることで、家族構成にあわせた連携事業を展開することが期待される。 |
| |
連携事業に対する阻害因子はできる限り縮小、解消することが望まれる。 |
| 1) |
法規上の限界
健康増進に関する法規と労働衛生に関する法規の目的や手法が違うため、連携がとりにくいことが指摘される。
この対応策としては、相互の法規の相違を理解した上で共通点に注目して、連携事業を行う。関係法規の相違があっても、健康増進は共通の課題であり、地域と職域の関心が高まり、共通の認識がもてることで事業を展開する基盤を形成することができる。 |
| 2) |
限られた予算
連携事業のための予算には限界がある。
対応策としては、既存の社会資源を最大限に活用していくことが必要である。地域に既存の保健サービスを積極的に発掘するなど有効に活用することが期待される。 |
| 3) |
限られた人的資源
連携事業に関わる人脈不足や担当する人的資源不足が問題になる。
対応策としては、現在の人員を有効に活用することで解決の糸口を見つけることが可能である。地域産業保健センターや社会保険健康事業財団等の保健師を連携事業に活用するなど、既存の組織に属する人材を活用することが考えられる。 |
| 4) |
時間帯の相違
連携事業を行う上で、希望する時間帯が、職域と地域で異なることがある。
対応策として、地域保健側と職域保健側の保健事業担当者が協力し、事業所のニーズに応えられるように工夫するなどして、需要に応えることが期待される。 |
| 5) |
共通の情報の欠落
集団の健康状態等、地域・職域が相互に活用できる情報が乏しく、効果的な連携事業が実践できない。
対応策として、個人情報の取扱いに十分留意しながら、可能な範囲で健診情報等を相互に活用するなど工夫をすることが必要である。 |
| 6) |
職域側の認識や関心の温度差
職域側の阻害因子として、事業者の健康管理に対する認識や関心の程度に差があることが指摘される。
対応策として、地域産業保健センターなどの諸機関を通して、健康管理に対する認識や関心を高めていく方法も考えられる。 |
| 7) |
異なる医療保険制度
医療保険の種類が対象集団で異なることも連携事業を推進する上で制限になることがある。
対応策としては、保険者協議会を通して各制度の被保険者も包含する体制を構築することが必要である。 |
| 8) |
個人情報保護
個人情報を保護するために、連携事業に必要な情報が共有できないという問題点がある。
その対策として、保健事業としての主旨を十分に説明して、必要最低限の情報を共有できるよう本人の同意を得ることが必要である。 |
| |
地域・職域連携推進協議会は保健事業の連携による事業の効果的・効率的な活用等による生涯を通じた健康づくりの促進を課題とし、都道府県単位又は2次医療圏単位で健康づくりに携わる者により構成していることに対し、保険者協議会は保険運営の安定化を図るため、医療保険者による保健事業等を共同実施することを課題に、都道府県単位の国保、組合健保、政管健保等の医療保険者で構成されている。各々の協議会に関わる人が重なることも多いことから、互いに連携を図り適切な運用を図る必要がある。 |
| Q1. |
地域保健が職域保健と連携するといっても、何から取りかかったらよいのか、職域保健側のどのような人と相談すればよいのかわかりません。何から始めるのがよいのですか。 |
| A1. |
まずは、地域産業保健センターや健康保険組合連合会、社会保険健康事業財団等の関係機関の保健担当者と連絡をとり、対象者の健康状況や地域・職域における保健事業の実施状況など相互の情報を交換することから始めるとよいでしょう。「まず、やれること」からスタートし、対象になる方々や事業者の理解を得ながら段階的に積み上げていくことが大切です。 |
| Q2. |
事業所側が地域保健と連携事業を実施したいと思う場合、地域保健側のどこに連絡をすればよいですか。 |
| A2. |
まずは、保健所、又は該当する市町村の健康づくり(健康増進、健康推進等)の担当者と連絡をとるとよいでしょう。 |
| Q3. |
事業所における健康管理について、事業者の関心を高めるためにはどのような方法がよいのでしょうか。 |
| A3. |
健康管理の必要性を一方的に伝えるだけではなく、具体的に健康に関する情報(就業者の健康情報の分析結果等)を提示したり、実際に健康管理に取り組んでいる事業者の事例や体験を紹介をすることで健康管理に対する関心を高めていくとよいでしょう。 |
| Q4. |
キーパーソンとしては、どのような人を選んだらよいのでしょうか。 |
| A4. |
特に職種を限定はしていませんが、地域保健と職域保健の両方に理解がある方をキーパーソンにすると、より具体的な助言や支援が得られ、協議会や保健事業の運営もスムースになるようです。モデル事業では、学識経験者(大学教員等、例:山形県、福島県、富山県、愛知県、山口県)や地域産業保健センター長(医師、例:福島県)がキーパーソンになり、計画段階から助言や支援をしていただいています。 |
| Q5. |
協議会を形骸化させないために、どのようなことに気をつければよいでしょうか。 |
| A5. |
地域保健、職域保健相互の情報交換や、富山県や山口県のモデル事業のように商工会議所広報に健康情報を掲載していくことなど、様々な情報の発信等小さいこと(事業)でよいので、とにかく続けていくことが大切です。また、成功事例を持つことも、継続していく上での励みになります。 |
| Q6. |
市町村の保健師は日常業務に追われてしまい、これ以上手を広げることはできません。負担が少なくなる方法はありますか。 |
| A6. |
協議会やワーキンググループの中で、職域保健や健診機関などの専門職を有する機関と相談を行い、現在いる人的資源の有効活用を考えることも1つの解決策でしょう。また、連携事業を市町村の施策として位置付けることにより、他部門の協力を得ることも可能になります。 |
| Q7. |
連携事業を推進するためには、専門職以外の人的資源が必要ですが、どのようにしたらよいでしょうか。 |
| A7. |
健康づくりに関する事業には、住民主体のものや様々な分野が実施できるものがありますので、民生委員や健康づくりの自主グループなどの地区組織や、NPO等のを巻き込んで、連携事業を行うことが必要です。また、研修を行いそのような人材を育てていくことも重要です。 |
| Q8. |
連携事業を行う予算がありませんが、どのように確保できるのでしょうか。また、予算がなくても運営できる方法はあるのでしょうか。 |
| A8. |
財政状況が厳しいことから、予算には限界があります。自治体に予算化してもらえるよう働きかけることも重要ですが、地域保健、職域保健分野の保健事業や、会場となる施設、保健事業担当者、民間組織、地域組織等といった人的資源、健康教育に使用する設備や教材、広報やチラシを利用するなど、限られた条件の中で最大限に可能なことを考え、事業につなげていきましょう。 |
| Q9. |
健康教育の手法として、何か工夫する点、気をつけなければいけない点はありますか。 |
| A9. |
地域保健や職域保健の資源(人的資源、会場、設備、教材、情報等)、マスコミやインターネット、電子メール、電話、FAX等の情報手段を十分に活用しましょう。対象の意識に働きかけるために、映像(写真、スライド等)の使用や演劇等を行うこともよいようです。また、家庭での生活や仕事を行う上でも有用な内容で、かつ継続できるような具体的な内容にするとともに、一方的な指導や単なる知識の押しつけにならないようにしましょう。 |
| Q10. |
健康増進に関する法規と労働衛生に関する法規の違いがあり、連携がとりにくいのですが、どうすればよいでしょうか。 |
| A10. |
相互の法規には目的や手法等に違いがありますが、地域保健と職域保健が互いの社会資源を使用したり、共同で保健事業を展開することで、より効率的、効果的に保健サービスを提供することができるようになりますので、制度の違いを越えて、次第に連携もスムースになります。モデル事業では、地域保健側の保健事業担当者が講師となって事業所で健康教室や講演を行ったり(例:北海道、山形県、福島県富山県、愛知県、山口県、高知県)、地域保健と職域保健が共同でポスターやパンフレットを作成したりしました(例:山形県、福島県)。 |
| Q11. |
地域・職域連携推進協議会と保険者協議会は同じメンバーでもよいのですか。 |
| A11. |
保険者協議会のメンバーは国民健康保険や健康保険組合等の医療保険者となりますが、地域・職域連携推進協議会における医療保険者は保険者協議会のメンバーと同様の組織となることから、重なることに問題はありません。 |
| Q12. |
地域・職域連携推進協議会を、新たに設置しなければならないのですか。 |
| A12. |
地域・職域連携推進事業実施要綱では、「協議会は、関係機関が多岐にわたることから、既存の協議する場(会議等)を活用することは可能とする。」とされていますので、新たに立ち上げずに既存の会議等を活用して行うことができます。 |
おわりに
健康寿命の更なる延伸や生活の質の向上を実現し、元気で明るい高齢社会を築くためには、とりわけ青壮年期における健康管理への支援が重要であり、この間に地域及び職域で行われる保健事業を連携して実施することの重要性が高まってきている。地域・職域がこれまで独立して実施してきた保健事業を連携して行うということは、単に足りないところを補完しあうというだけの意義ではなく、ともすれば健康のことは二の次、三の次になりがちな働き盛りの世代に、健康に対する関心を高めることができ、さらには、家族ぐるみの健康管理により子ども世代に好影響を及ぼすことや、健康なまちづくりのための大きな原動力となることが期待できよう。また、退職時における継続的な健康管理に資することはもとより、地域社会活動への参画を容易にし、明るく生きがいのある高齢社会の構築に寄与できる可能性を秘めている。
このガイドラインを参考にしていただき、まずは圏内の関係機関と相互に有する健康情報や保健事業等の情報交換により地域・職域の健康課題についての認識を共有化することからはじめ、健康意識調査やフォーラムの共同開催など、実現可能なところから一歩一歩連携事業を進めていただきたい。さらに、長期的な視点をもって連携事業を推進し、生涯を通じた健康づくりや生活習慣病の予防といった、重要かつ困難な課題に立ち向かっていただくことを強く期待するものである。