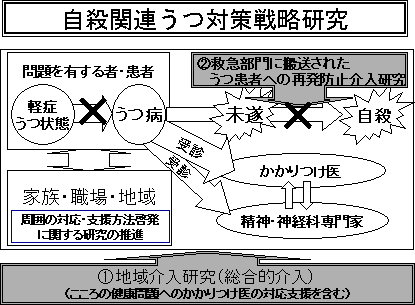| 1 | 経緯 国民的ニーズが高く、確実に解決を図ることが求められている研究課題について、成果目標を設定した大規模な「戦略研究」の必要性が指摘されてきた。そこで、厚生労働科学研究費補助金において、従来の一般公募による研究課題(従来分)に加えて、厚生科学審議会科学技術部会の意見を踏まえながら、研究の成果目標及び研究の方法を定め、選定された機関が実際に研究を行う者や研究に協力する施設等を一般公募する新たな「戦略研究」を平成17年度から創設することになった。このため、平成16年度厚生労働科学特別研究(黒川清主任研究者、自殺関連うつ対策研究は樋口輝彦主任研究者)において、科学的妥当性に基づく5年後の成果目標、それを可能にする発症予防・診断・効果的治療技術に関する研究戦略の骨格をまとめる作業に着手した。 | ||||||||||||||
| 2 | これまでの検討結果の概要
|
戦略研究課題の特徴
厚生労働科学研究
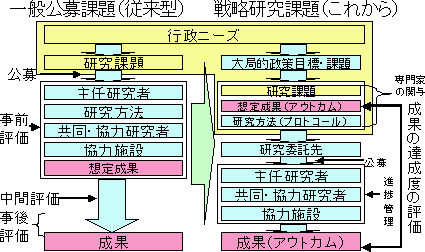
戦略研究の特徴
| 戦略研究 | 一般公募課題 | |
| 課題 | 具体的に設定 | 研究者に一任 |
| アウトカム(成果目標) | 事前に設定 | 研究者に一任 |
| プロトコール | 事前に設定 | 研究者に一任 |
| 事前評価の視点 | 実現可能性についての 「絶対評価」 |
申請課題の中での 「相対評価」 |
| 報告と評価 | 年次報告・評価に加え モニタリング委員会設置 |
年次報告・評価 |
| 応募者 | 団体へ委託 | 個人・団体 |
| 研究期間 | 5年 | 3年 |
| 金額 | 大型(数億円) | 平均約2,300万円 |
| 課題数 | 数課題 | 約1,400課題 |
| 性格 | 競争的研究資金 | 競争的研究資金 |
戦略研究課題の資金配分のしくみと進捗管理機能について
| 1. | 厚生科学審議会科学技術部会・本省:調整・政策評価関係業務を行う。 厚生科学審議会科学技術部会の審議に基づき、本省において政策課題の決定、予算要求、国会対応、取扱規則及び取扱細則等の策定、研究プラットホーム策定委員会の運営、研究プロトコールの承認、機関間調整、省庁間調整、科学技術政策評価等の事務を行う。 |
| 2. | 戦略研究実施委託団体:研究資金配分・研究執行等の事務関係業務を行う。 戦略研究の実施について、本省と委託契約を締結した団体において、研究プラットホーム策定委員会への諮問、研究プロトコールの公開、研究参加者の公募、研究評価委員会の運営、研究参加者の審査・採否決定、研究倫理委員会の運営、研究費の執行・監査、研究モニタリング委員会の運営、研究の実施支援・進捗管理、研究データ管理、研究成果評価、研究成果公開等の事務を行う。 |
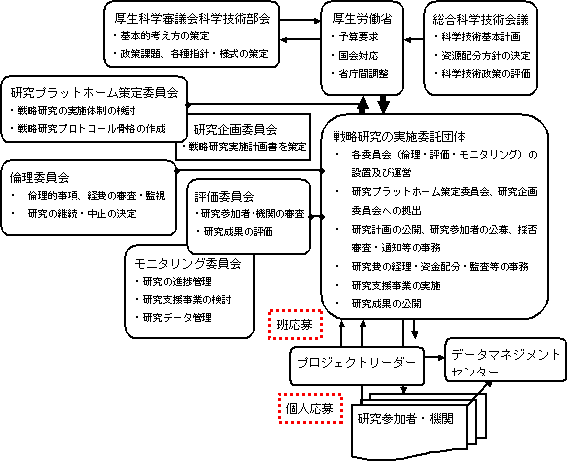
糖尿病予防対策研究〔Japan Diabetes Outcome Intervention Trial: J-DOIT〕
| 研究課題名 | J−DOIT1 | J−DOIT2 | J−DOIT3 |
| アウトカム | IGT(Impaired Glucose Tolerance:耐糖能異常)から糖尿病型への移行率が半減する介入方法の研究 | 糖尿病患者の治療の中断率が半減する介入方法の研究 | 糖尿病合併症の進展を30%抑制する介入方法の研究 |
|
研究方法
〔対象(属性、数、抽出・登録・割付等)、介入方法、精度管理、収集データ(項目、時期、頻度)分析方法、その他〕 |
地域・職域健診の要指導者で30-64歳IGT 4,500名。 全国で20グループを編成。 対面型個別指導群、非対面型(IT)個別指導群、集団指導(対照)群に無作為割付。 対面またはIT活用等による生活習慣(食事・身体活動中心)介入プロトコールを定めて実施。 医学的検査は登録時、最初の6ヶ月間は月1回、それ以降は3ヶ月毎に実施。 登録者全員を解析対象とする。 |
都市部(人口10-20万程度)に在住し、かかりつけ医で治療するII型糖尿病患者。糖尿病診療達成目標を地区医師会全体で共有し、目標達成のための支援としての「患者指導コメディカル派遣・IT診療支援群」「対照群」に割付。初年度は数地区でパイロット研究を行い、本試験の手法および実施可能性等について検討する(約1,600人)。 医学的検査・治療の実施率は、登録時、約3ヵ月ごとに測定。登録全地区・患者全員を解析対象とする。 |
HbA1c≧7.0% II型糖尿病で、収縮期血圧≧140または拡張期≧90mmHgかつ脂質代謝異常のある40-69歳の3,000名。 強化治療群、通常治療群に無作為割付。 生活習慣(減量、食事、運動、禁煙)、血圧、脂質、血糖への介入方法を定めて実施。 医学的検査は登録時、定期的来院時、一年ごと。 登録者全員を解析対象。 |
| その他 必要事項 |
サンプルサイズの縮小、研究グループ単位で審査、予算規模 | パイロットスタディ、糖尿病診療達成目標(共通)の作成、患者指導コメデイカルの訓練・派遣方法整備、IT診療支援システム開発・実証試験 | 中央検査項目の選定、モニタリングネット整備、中断者の要因・動態分析 |
自殺関連うつ対策研究
| 研究課題名 | 地域介入研究 | 救急部門における うつ再発予防研究 |
| アウトカム | 地域における自殺率が20%減少する介入方法の研究 | うつによる自殺未遂者の再発率が30%減少する介入方法の研究 |
| 研究方法 | 人口規模が合計約15万人の複数地域を対象とした非無作為化比較介入研究。 介入地区と対照地区住民における自殺企図の発生の情報を収集し、両地区間の発生頻度を比較する。 介入は、地域教育、かかりつけ医への啓発等複合的な関わりを想定。 |
地域にある救急部門に搬送された「うつ」による自殺未遂者1,000人程度に対する比較介入研究。 ITを用いたケースマネジメント等の複数の介入方法による、うつの再発率を比較する。 |
| その他 必要事項 |
参加地区の選定方法 介入方法の精緻化 |
参加施設の選定方法(救急部門と精神科との連携基盤のある施設) |
糖尿病予防対策研究のフローチャート
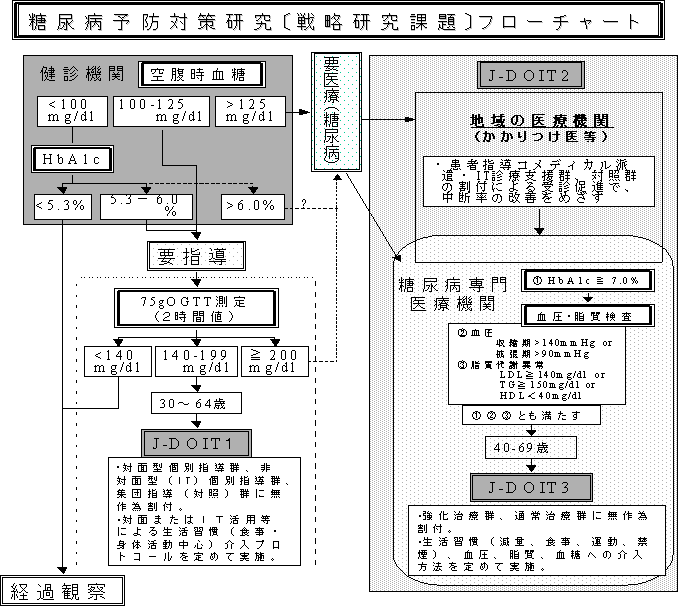
自殺関連うつ病対策研究のフローチャート