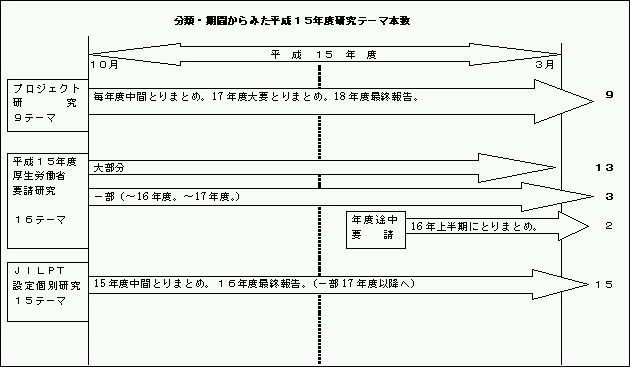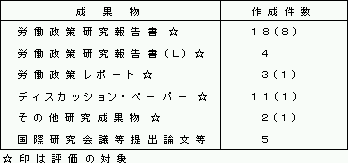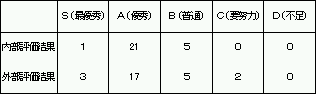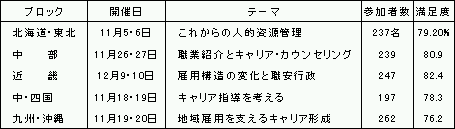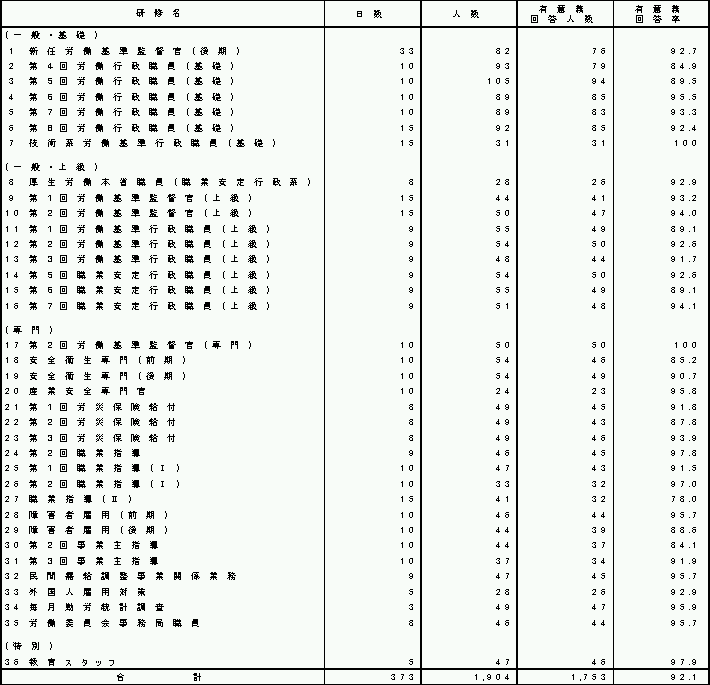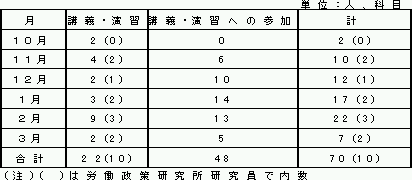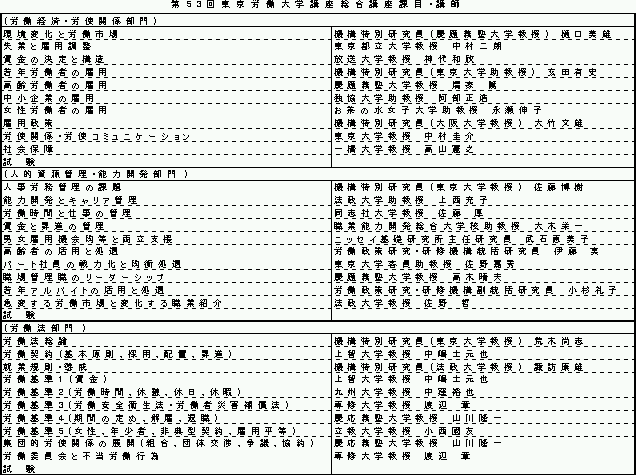| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
|
|
第1
|
業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
第1
|
業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
第1
|
業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
通則法第29条第2項第2号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。
一般管理費等については、効率的な利用に努め、平成18年度において、平成14年度と比べて25%に相当する額を節減すること。また、業務経費については、毎年度1.3%の節減を図ること。 |
一般管理費等について、平成18年度において、平成14年度と比べて25%に相当する額を節減するため、また、業務経費について、毎年度1.3%の節減を図るため、省資源、省エネルギーの推進や一般競争入札の積極的な導入等を進めるとともに、業務処理への情報通信技術の活用や定型業務の外部委託化等業務処理の効率化のための見直しを行い、事業効果を最大限確保しつつ、経費の節減を図る。 |
業務運営における経費削減を図るため、節電・節水による省資源、省エネルギーに努めるとともに、一般競争入札の積極的な導入を進める。また、業務処理への情報通信技術の活用や外部委託化等業務処理の効率化のための見直しを行う。 |
| (1) |
省資源・省エネルギーの推進
毎週水曜日を省資源・省エネルギー推進日と定めて、定時退庁の促進を図るとともに、省資源・省エネルギー等に係る提案を募集するなど意識啓発の取組を進めた。併せて、廊下等の部分消灯等の節電対策及び洗面所の節水コマ取り付けによる節水対策を法人発足時より実施することにより、電気料金及び水道料金について、平成14年度下期実績25,773千円に対し平成15年度下期実績は20,990千円と約19%の節減を実現した。(資料1参照)
また、LANの活用による掲示板システムやメールによる事務連絡の徹底等により、14年度下半期と比較して86,500枚(約5.3%)の用紙の節約を図った。(資料2参照)
|
| (2) |
一般競争入札の積極的な導入
独立行政法人労働政策研究・研修機構会計規程に基づき、契約案件については原則として一般競争入札によることとし経費節減を図った。特に清掃や警備など事務所の維持管理に係る業務についてはすべて競争入札により節減を図った。
これにより、平成15年度の一般競争入札件数は24件となり、平成14年度下半期の11件と比較して2倍以上増加した。また、平成15年度の入札基準価格112,704千円に対し、落札価格は82,418千円であり節減額は約30,286千円(約27%)となった。(資料3参照)
|
| (3) |
情報通信技術の活用や外部委託化等業務処理の効率化のための見直し
LANを活用し、無料ソフトによるオンライン在席状況確認システムの導入やイントラネットによる役員スケジュールの公開等により、事業実施における調整業務の軽減を図るとともに、掲示板システムへの各種届出様式の掲載やメールによる事務連絡の徹底により事務処理の効率化を図った。
また、清掃や警備など事務所の維持管理に係る業務等の継続的な外部委託化により、業務処理の効率化を図った。
なお、職員からの業務効率化に係る提案にもとづき、情報通信技術の活用や外部委託化等業務処理の効率化を一層推進するため、以下のような検討を行った。
| ・ |
出張管理・旅費計算システムの導入による出張手続き業務の効率化 |
| ・ |
事務消耗品管理の合理化による事務の効率化 |
| ・ |
メール便の活用による郵便料金の節減 |
| ・ |
その他外部委託化が可能な業務に関する全組織的な検討に着手 |
|
| (4) |
更なる業務経費の節減
海外出張に係る航空運賃について、理事長のみをビジネスクラス、その他の役職員はエコノミークラスとする運用とし、更なる業務経費の節減を図った。 |
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| 第3 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 |
通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。 |
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
業務の質の向上に資するため、業務全般を通じて以下の措置を講ずる。 |
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| (1) |
業績評価システムの確立
適正で質の高い業務運営の確保に資するため、全ての事業を対象とする業績評価システムを確立し、この中期計画を踏まえて策定する評価基準に基づき毎年度の事業の評価を行う。評価基準、評価結果及び業務運営への反映方針はホームページ等で公表する。
業績評価は、内部評価及び外部評価により行い、このうち外部評価については、外部の有識者等によって構成される総合評価諮問会議を設置して、これに委嘱する。
業績評価システムは、中期目標期間の初年度中に整備を完了して、実施する。 |
|
| (1) |
業績評価システムの確立
適正で質の高い業務運営の確保に資するため、全ての事業を対象とする業績評価システムを確立し、評価基準に基づいて事業の評価を行う。評価基準、評価結果及び業務運営への反映方針はホームページ等で公表する。
業績評価は、内部評価及び外部評価により行い、このうち外部評価については、外部の有識者等によって構成される総合評価諮問会議を設置して、これに委嘱する。
業績評価システムは、15年度末までに整備を完了して、実施する。 |
|
| (1) |
業績評価制度の整備・運用
適正で質の高い業務運営の確保に資するため、全事業を対象とした業績評価システムを確立し、業績評価の実施に取り組んだ。
|
| イ |
業績評価に係る外部評価機関の設置
機構の業務全般について評価を行う外部学識経験者で構成する「総合評価諮問会議」及び調査研究事業全般について評価を行う「リサーチ・アドバイザー部会」を設置した。(資料4参照)。
また、業績評価規程、業績評価規程実施細則等の所要の規程等を整備し、ホームページで公表した。
なお「研修事業」及び「研究基盤整備事業」についても、有識者からなる懇談会を設置し、各事業の事業計画及び事業実績についての審議を行うこととした。(資料5参照)
|
| ロ |
内部評価と業務進行管理
法人のトップである理事長が、適正かつ明確な経営戦略の下で的確な業務運営が行われているかを把握するシステムとして、理事長主催による経営会議において、業績評価規程等に基づいて内部評価を実施するとともに、毎月の業務実績進行管理を行い、次月以降の業務運営に反映させた。
| (1) |
内部評価の実施
| ・ |
業績評価規程に基づき、平成15年度第3四半期実績についての中間評価(第9回経営会議:1月9日)を実施した。また平成16年度計画について事前評価(第11回経営会議:2月24日)を実施した。
なお、6月8日の経営会議において、平成15年度業務実績報告書についての自己評価を実施した。 |
|
| (2) |
月次業務進捗状況管理
| ・ |
業績評価規程に基づき、月次業務実績報告を実施し、次月以降の業務運営に反映させた。 |
|
|
| ハ |
外部評価機関による評価の実施
| ・ |
業績評価規程に基づき、総合評価諮問会議において平成16年度計画の事前評価(4月2日)を実施し、委員の意見を計画内容に反映した。また平成15年度の業務実績に対する事後評価の実施に向けた取りまとめ作業を行った。
なお、6月18日に開催した総合評価諮問会義において、「機構の行った自己評価は妥当」との評価を得た。 |
| ・ |
平成16年3月にリサーチ・アドバイザー部会を開催し、平成15年度の調査研究成果について外部有識者による評価を行った。 |
|
| (2) |
業務運営等に関する意見及び評価の把握・反映
|
| イ |
ホームページ等を通じた意見等の把握
ホームページによるWEBアンケート調査を通じて、機構の業務運営等に関する意見・評価・要望等を広く把握し、72件の意見・評価が得られた。これら意見は適宜各部門にフィードバックし業務運営の改善等に努めた。 |
| ロ |
有識者アンケート等の実施
機構の業務運営及び事業成果等について、労働分野の有識者、地方行政官及び労使関係者より意見、評価を把握し、業務改善等に役立てるための「有識者アンケート」及び機構ホームページ利用者から広く意見等を集め業務改善等に役立てるための「ホームページ利用者アンケート」を3月8日から28日まで実施し、両アンケートとも、回答者の90%以上から機構の業務活動全般に対して「有益である」との高い評価を得た。(資料6参照) |
|
| (2) |
業務運営等に関する意見及び評価の把握
ホームページ等を通じて、業務運営及び事業成果に対する意見及び評価を広く求めるとともに、これを各事業部門へフィードバックし、業務運営の改善に資する。 |
|
| (2) |
業務運営等に関する意見及び評価の把握
ホームページ等を通じて、業務運営及び事業成果に対する意見及び評価を広く求めるとともに、これを各事業部門へフィードバックし、業務運営の改善に資する。
|
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| 第3 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 1 |
労働政策についての総合的な調査研究
現在、我が国が直面する別紙に掲げる中長期的な労働政策の課題に係る調査研究テーマのほか、行政及び国民各層のニーズを踏まえたテーマについて、政策の企画立案等に資する質の高い成果を出していると認められること。
特に次の具体的な目標の達成を図ること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| イ |
次のような調査研究を実施し、政策の企画立案若しくは実施を支援し、又は政策論議を活性化する高い水準の成果を出す。
| (1) |
中長期的な社会経済システムの構造変化に対応した今後の労働政策の基本的な方向性や政策課題を発見・提示するもの。
|
| (2) |
現下の政策課題に関し、その理論的・実証的説明を行うもの。
|
| (3) |
職業指導等に関する実務的ノウハウや職業適性検査等のツール開発に係る研究等、研修を通じて個別の施策の効果的な実施や、高度化に資するもの。 |
|
|
| イ |
次のような調査研究を実施し、政策の企画立案若しくは実施を支援し、又は政策論議を活性化する高い水準の成果を出す。 |
| (イ) |
プロジェクト研究
中期目標第3の1で示された9つの中長期的な労働政策の課題に係る調査研究テーマに対応して、プロジェクト研究を実施する。
|
| (ロ) |
個別研究
労働政策研究に対する行政の要請や労使の関心など国民各層のニーズを広く把握し、機構において実施することが必要と判断した「個別研究」について、研究の趣旨・目的、概要・必要性等を記載した研究計画を作成し、計画的に実施する。
プロジェクト研究、個別研究のテーマは別紙1のとおり。 |
|
| イ |
中長期的な労働政策の課題に対応する調査研究テーマに係る9件のプロジェクト研究及び行政の要請や労使の関心など国民各層のニーズ等を踏まえた31件の個別研究、さらに年度途中で厚生労働省から要請のあった2件の個別研究を実施した。(資料7参照)
また、年度途中においては、研究員に対して進捗状況のヒアリング(12月実施)を行い、計画の見直しを適宜行った。 |
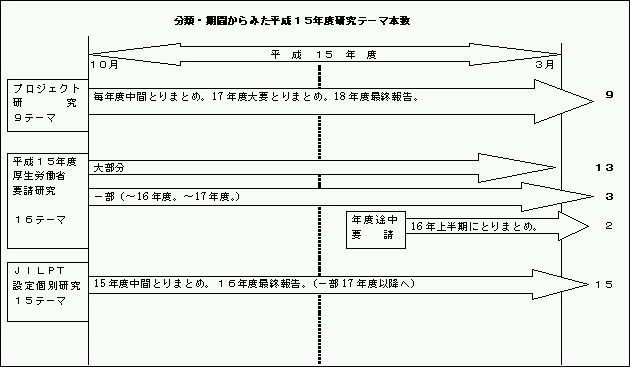
| (イ) |
テーマ設定
平成15年度下期の研究計画については、厚生労働省から研究要請を聴取し、「調査研究テーマ設定会議」を開催して労使の意見を聴いたうえで、各研究テーマについて、趣旨・目的、最終成果物等、明確な目標を示す研究計画を策定して研究を実施した。
特に、プロジェクト研究については、中期計画期間全体についての研究プランも併せて作成した。
○研究ニーズの把握状況
| ・ |
厚生労働省からの要請
年度当初における研究要請の受諾と行政担当者からの説明会の開催(平成15年4月25日開催)
年度途中における研究要請の受諾 |
| ・ |
労使からの意見を聴くための「調査研究テーマ設定会議」の開催(資料8参照)
労働部会:平成15年7月31日、経営部会:平成15年7月30日 |
|
| (ロ) |
研究の実施と成果
平成15年度の研究テーマは、厚生労働省の年度途中からの要請も含め、42テーマが計画され、このうち39テーマについては、ほぼ研究計画どおり実施し、研究成果(中間的なものを含む。)をとりまとめた。
なお、3テーマは、行政的な手続きに時間を要したこと等により、調査の実施を16年度に変更した。(資料7参照*再掲)
また、適切な研究の進捗管理を行う等のため、「研究活動記録システム」の開発に着手し、平成16年4月当初より運用を開始した。
|
| (ハ) |
政策に資する質の高い成果の確保
研究成果は、労働経済白書をはじめとする様々な媒体で150件を超える引用があるとともに、成果に基づく研究員の審議会等への参画や議員・行政へのレクチャーが30件に上るなど、政策の企画立案、政策研究の発展、政策論議の活性化等に貢献した。
| ○ |
研究成果の行政(地方行政を含む)における活用状況
| ・ |
平成15年版労働経済白書での引用(旧研究所成果)
6件(労働経済白書CD−ROM1件含む) |
| ・ |
その他の白書での引用件数 2件 |
| ・ |
厚生労働省その他行政機関の審議会・研究会等への参画 20件 |
|
(厚労省9件、他省庁3件、東京都7件、神奈川県1件) |
| ・ |
行政・政党・議員に対するレクチャー、情報提供問合せ対応等 10件(議員7件、行政等3件) |
|
○
|
外部機関による研究成果の表彰 3件
| ・ |
平成15年度沖永賞
小倉一哉『日本人の年休取得行動−年次有給休暇に関する経済分析−』(3月10日受賞) |
| ・ |
第2回産業カウンセリング学会学術賞
下村英雄『看護職者の快適職場感−快適職場づくりのために−』(10月受賞) |
| ・ |
平成15年度日本進路指導学会研究奨励賞
下村英雄『自己分析課題がコンピューターによる情報検索および進路選択に対する自己効力に与える影響』(10月11日受賞)
|
|
| ○ |
研究成果の一般による活用状況
| ・ |
大学からの講師(講座)依頼 |
20件 |
| ・ |
外部機関からの講演等依頼 |
43件 |
| ・ |
研究成果の転載願(正式に承認依頼のあったもの) |
3件 |
|
東大社研データアーカイブ寄託済みデータの利用申請件数 |
8件 |
| ・ |
専門図書等での調査研究成果掲載引用(研究雑誌の文献目録に基づく)
|
129件 |
| ・ |
(専門図書64件、学会誌9件、専門誌27件、紀要21件、政府関係機関(独法等)報告書1件、政府関係機関の雑誌4件、政府関係機関以外の報告書3件)(資料9参照) |
|
新聞(全国紙・地方紙)・ビジネス誌等への成果の引用 |
17件 |
| ・ |
新聞(全国紙・地方紙)・ビジネス誌等研究員名の掲載 |
36件 |
| ・ |
マスコミ取材への対応 |
14件 |
|
ホームページに公表した調査研究成果に対するアクセス件数 |
113,499件 |
|
|
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| |
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
|
|
|
|
(1)調査研究の実施
| ロ |
調査研究の実施体制
| (1) |
プロジェクト研究
中期目標で示された9つの中長期的な労働政策の課題に係る調査研究テーマに対応して、プロジェクト方式による研究(以下「プロジェクト研究」という。)を実施する。プロジェクト研究は、機構内外の幅広い人材の参加を得て、中期目標期間を通じて実施する。
それぞれのプロジェクト研究に関して責任を持って実施する研究部門を設けて、これをプロジェクト研究推進の中核とする。各研究部門の部門長として、プロジェクト研究のリーダーとなる研究員には、他の研究員に対する効果的な研究指導を行い、組織全体の研究能力を向上させる能力を有する人材を充てる。
プロジェクト研究は、中期目標期間中にとりまとめる最終報告のほか年度ごとに中間的なとりまとめを行い、公表する。
中期目標期間中のプロジェクト研究及び担当研究部門は別紙1のとおりとする。
|
| (2) |
個別研究
機構が行うプロジェクト研究以外の研究(以下「個別研究」という。)は、上記(1)により設ける研究部門のうちもっとも関連の深いものが中心となって、単独で、又は研究チームを組織して、原則として1年以内の期間で実施する。
個別研究のテーマは、政策の企画立案に資すると考えられる調査研究のシーズを機構の事業活動の中から発見・発掘し、これに基づいて機動的に設定する。シーズの発見・発掘及びテーマの設定は、行政の要請を踏まえるほか、労使の関心など国民各層のニーズを広く把握した上で行う。
個別研究の実施計画は年度計画において定めることとし、原則として、年度ごとに最終結果をとりまとめ、公表する。
|
| (3) |
上記の他、年度途中において行政から調査研究の要請があった場合には、これに的確に対応する。 |
|
| ハ |
他の政策研究機関等との連携
研究テーマに応じて、内外の他の政策研究機関等との連携を図り、効果的、効率的な研究の推進を行う観点から、共同研究を実施する。 |
|
(1)調査研究の実施
| ロ |
調査研究の実施体制
| (1) |
プロジェクト研究
| ・ |
上記の9つのプロジェクト研究を機構内外の幅広い人材の参加を得て実施する。 |
| ・ |
それぞれのプロジェクト研究に関して責任を持って実施する研究部門を上記イ(イ)のとおり設け、これをプロジェクト研究推進の中核とする。各研究部門に、リーダーとして、他の研究員に対する効果的な研究指導を行い、組織全体の研究能力を向上させる能力を有する人材をおく。 |
|
| (2) |
個別研究
個別研究は、上記(1)により設ける研究部門のうちもっとも関連の深いものが中心となって、単独で、又は研究チームを組織して、原則として1年以内の期間で実施する。
個別研究のテーマは、政策の企画立案に資すると考えられる調査研究のシーズを機構の事業活動の中から発見・発掘し、これに基づいて機動的に設定する。シーズの発見・発掘及びテーマの設定は、行政の要請を踏まえるほか、労使の関心など国民各層のニーズを広く把握した上で行う。
個別研究の実施計画は年度計画において定めることとし、原則として、年度ごとに最終結果をとりまとめ、公表するが、必要に応じて年度を越えて研究期間を設定する場合には、年度ごとに中間報告をとりまとめることとする。
|
| (3) |
上記の他、年度途中において行政から調査研究の要請があった場合には、これに的確に対応する。 |
|
| ハ |
他の政策研究機関等との連携
研究テーマに応じて、内外の他の政策研究機関等との連携を図り、効果的、効率的な研究の推進を行う観点から、共同研究を実施する。
| ○ |
国内の政策研究機関等との間で機関同士の話し合いの場を持つなど連携を図り、共同研究の実施に向けた調整・提案を積極的に行う。 |
| ○ |
海外の政策研究機関等とは、国際的な観点での政策的知見の発見や調査研究の深化に資することを目的に、共通テーマに基づく研究、特定分野における各国研究者との研究会議等を通じて共同研究に取り組む。
|
| − |
内外の他の政策研究機関等との共同研究を4件以上実施する。 |
|
|
(1)調査研究の実施
| ロ |
調査研究の実施体制
| (イ) |
研究の実施体制
研究体制については、プロジェクト研究に対応した9つの研究部門を設け、各研究員の専門性に配慮した配置を行うとともに、各部門にリーダーとして統括研究員を配置した。また、それぞれの研究部門に外部の優れた学識者を特別研究員として計14名委嘱した。個別研究は、これら部門のうち研究課題が最も関連深い部門が中心となって担当した。プロジェクト研究、個別研究ともに担当部門が単独又は他部門とチームを編成して実施した。(資料10参照)
また、研究実施体制整備の一環として、計画作成から研究実施、成果のとりまとめまでの一連の業務の流れのほか、外部研究者の参加等の研究体勢整備までを網羅した「研究業務マニュアル」を作成した。
|
| (ロ) |
研究ニーズの把握・シーズの発見
平成16年度の研究計画策定に向けて、研究テーマ設定部会等を開催し、行政・労使など国民各層のニーズを広く把握し、調査研究のシーズの発見・発掘に努めた。 |
| ○ |
労働政策研究の的確な推進の基礎とするため、理事長を座長とし、労働政策担当者を交えた研究会「労働政策を支える基本哲学研究会(理事長研究会)」を開催し、政策課題について広く意見交換を行い、研究のシーズの発見、発掘に努めた。(5回実施)。 |
| ○ |
厚生労働省の平成16年度研究要請の把握を行うために、要請研究内容説明会を2月5日、10日、12日、18日に開催し、16年度要請研究予定15テーマについての意見交換を行った。 |
| ○ |
労使からの研究ニーズを把握するため、研究テーマ設定会議経営部会(1月29日開催)、研究テーマ設定会議労働部会(2月3日開催)を開催した。 |
| ○ |
機構内に研究テーマ設定に向けて議論する場として研究企画調整会議を設置し、次年度研究計画案の検討を行った。
|
| (ハ) |
行政への機動的対応 |
| ○ |
中長期的視点から労働行政の基本的視点を検討する「労働者の生活を中心とする社会のあり方に関する厚生労働大臣懇談会」への協力要請に対応して、理事長が同懇談会の座長に就任するとともに、同懇談会の下に設置されたプロジェクトに研究員が参画した。 |
| ○ |
15年度の年度途中要請として、職業安定局雇用政策課からの以下の2件に対応した。
| ・ |
第二新卒者の採用の実態に関する調査 |
| ・ |
地域労使就職支援事業に伴う求人ニーズ調査データの分析のとりまとめ |
|
|
| ハ |
他の政策研究機関等との連携
他の政策研究機関等と4件の共同研究を実施した。
| (イ) |
国内研究機関との連携
研究上の必要性に基づき、外部の研究者等の研究参加を求め、平成15年度に実施した調査研究のうち22テーマについて他機関の研究者・実務家57名の参加を得た。
このほか、高齢・障害者雇用支援機構、雇用・能力開発機構職業能力開発総合大学校能力開発研究センターとの間において、研究企画部門間で相互の研究に関する意見交換を行った。
|
| (ロ) |
海外研究機関との共同研究
年度計画に基づき、下記の4件の共同研究を実施した。共同研究の実施に当たっては、効率的に研究を進め所期の成果を上げるため、(1)各国の研究機関がこれまでの研究成果を持ち寄って比較研究を行う、(2)特定の研究課題に関する共通の研究手法を設定し各国が自国の状況について研究する、(3)機構のプロジェクト研究の推進に海外の研究者の協力を仰ぐ、など目的に応じて多様な形態を採用して行った。研究成果は、海外の研究者の活用を勘案し必要に応じて英文を交え、印刷物、ホームページ等で公表するとともに、機構の研究活動の基礎資料として活用を図っている。
| (1) |
中国労働社会保障研究院(CALSS)、韓国労働研究院(KLI)と「女性雇用政策の現状と課題」をテーマに、10月31日に韓国・済州島で日中韓ワークショップを開催した。この中で機構研究員が3本の論文を発表した。ワークショップで発表された3カ国の論文をホームページに掲載した結果、2500件を超えるアクセスがあり一般にも広く活用されている。ワークショップに対する中国、韓国側の評価も高く継続して実施したいとの強い要請があった。さらに機構研究員の発表論文は韓国語に翻訳されてKLIのホームページでも公表された。 |
| (2) |
「自動車産業の労使関係」をテーマとした共同研究を日・米・独・韓・豪の5カ国の研究機関と2005年までの3年計画で実施した。この共同研究では各研究機関が共通の手法に基づいて自国の状況を調査し、その成果を研究会議で比較検討する方法を採用しており、平成15年度は年度を通じて各国において調査を実施した。研究成果は2005年に「自動車産業の労使関係に関する国際比較」としてとりまとめる計画である。 |
| (3) |
アジア13カ国の専門家、行政関係者およびOECD、ILOの専門家を東京に招いて「アジアにおける人の移動と労働市場」に関する研究ワークショップを2月5〜6日に実施した。ワークショップでは各国専門家が最近の状況を盛り込んだ研究成果を発表し、OECD等の専門家による欧米の動向に関する研究報告と併せて、今後の政策展開のあり方に焦点を当てて討議、その結果を印刷物で公表した。また一般参加者アンケートで「有益度」を聞いたところ、96%が有益と回答する高い評価を得た。 |
| (4) |
「労働条件の決定メカニズム」および「労働者概念」に関する各国の労働法制の比較を目的に、米、英、独、仏、伊、スウェーデン、オーストラリアに日本を加えた8カ国の研究者による「国際比較労働法研究セミナー」を3月9〜10日に東京で実施した。この比較研究は、(1)労働条件決定システムの再構築に関する研究、(2)多様な働き方を可能とする就業環境およびセーフティーネットに関する研究、の2つのプロジェクト研究の基礎的な情報収集をかねて実施した。このため研究成果は、各国の提出論文を印刷物、ホームページで公表するとともに、両プロジェクト研究の基礎資料として活用することにしている。 |
|
| (ハ) |
その他
研究の推進に当たって、特に海外の研究者との連携が必要な場合は、適宜ワークショップへの参加や、報告論文の執筆を依頼した。 |
| ○ |
海外研究者による報告論文執筆例
| ・ |
コーポレート・ユニバーシティについて、コロンビア大学教育経済学研究所 上席研究員 |
| ・ドイツの雇用政策について、 |
ドイツ社会政策研究所 上席研究員
労働市場職業研究所 研究員 |
|
|
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| |
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
|
|
|
|
(1)調査研究の実施
| ニ |
調査研究のとりまとめ
調査研究のとりまとめにおいては、研究評価の一環として外部の人材を含む評価を行い、政策的観点から、それぞれの分類の成果物に求められる水準を満たしているものと判断されたものを機構の調査研究成果として発表する。 |
|
(1)調査研究の実施
| (1) |
調査研究のとりまとめにおいては、研究評価の一環として外部の人材を含む評価を行い、政策的観点から、それぞれの分類の成果物に求められる水準を満たしているものと判断されたものを機構の調査研究成果として発表する。
|
| − |
調査研究成果は、労働政策研究報告書、システム・ツールの形式で作成した研究開発成果物、資料シリーズ、研究双書、ディスカッション・ペーパー及び紀要論文等としてとりまとめる。
|
| (2) |
とりまとめた研究成果については、中期目標の達成に向け、内部評価を経て、リサーチアドバイザーによる厳正な外部評価を受け、政策的視点から高い評価を得ることをめざす。 |
|
(1)調査研究の実施
| ニ |
調査研究のとりまとめ
研究成果とりまとめ過程においては、必ず一連のピアレビュー(内部研究員に対する所内研究発表会及び内部又は外部研究者による査読(レビュー))を経ることとし、常に質の高い成果の確保をめざした。
平成15年度にとりまとめた研究成果は43件で、このうち27件について外部評価を受け、年度計画に掲げる目標数値5件以上の4倍の20件が5段階評価(SABCD)でA以上の評価を得た。(43件中の残り11件は16年度央の外部評価の対象、5件の国際研究会議等提出論文等は評価対象外)
(研究成果とりまとめの流れ)
所内研究発表会(スケルトン)の開催 → 内部又は外部の研究者によるレビュー
→ レビュー指摘事項に留意した訂正 → 内容確定
→ 内部評価 → 外部評価(リサーチ・アドバイザー部会)
| (イ) |
研究成果の取りまとめ
|
| ○ |
研究成果作成件数 43件(カッコ内は近く公表予定のもの) |
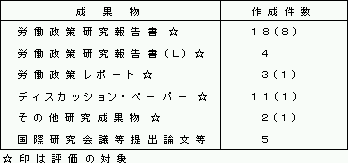
| (ロ) |
研究成果の評価
研究成果については、内部評価委員会において各評価者(1件につき2名)の評価を確認し、研究担当者のリプライを考慮して内部評価を決定した。また、リサーチ・アドバイザー部会における外部評価では、労働問題の各分野で高度な学識を持つ外部専門家による評価を実施した。その結果、評価を受けた27件の成果のうち20件がA(優秀)以上の評価を受けた。(資料11参照) |
| ○ |
研究成果評価結果 |
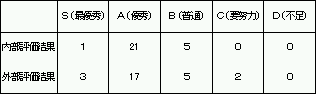
| (ハ) |
関連専門誌等への論文掲載等
関連専門雑誌に論文15件を発表した。うち2件は査読を経て掲載された。 |
| ○ |
学会誌・専門誌への論文掲載 |
15件 |
(学会誌1) |
| うち査読あり |
2件 |
|
| ・ |
『日本労働研究雑誌』(H15/10月号)「人事管理の変化と裁量労働制」(佐藤厚) |
| ・ |
『社会学評論』4月号「労働の変貌−若者の非典型雇用と個人主義」(小杉礼子) |
|
| ○ |
学会発表 |
8件 |
|
| ○ |
一般経済誌等への掲載 |
5件 |
|
|
|
| (1) |
政策の企画立案等に資するために、中期目標期間中において一定の外部評価を受けた研究成果の発表を120件以上とすること。
(13年度及び14年度の平均年26件) |
|
| − |
厳正な外部評価により政策的視点から高い評価を受けた報告書等を中期目標期間中において、30件以上確保する。
(13年度及び14年度の平均年7件) |
|
| − |
(1)のうち、5件以上の成果について、外部評価による総合評価で優秀であるとの評価を得ることをめざす。
|
| (3) |
中期目標の達成に向け、調査研究成果を活用し、関連専門誌等への論文掲載を促進する。
|
|
| − |
外部の媒体等でも高い評価を得るとの観点から、調査研究成果を活用し、関連専門誌等への論文掲載を中期目標期間中において、90件以上行う。
(13年度及び14年度の平均年19件) |
|
| − |
関連専門誌等への論文掲載を10件以上とすることをめざし、そのうち、2件以上は査読を経ることを掲載の条件とする雑誌等への掲載であることをめざす。 |
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| |
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
|
|
|
|
| (2) |
調査研究活動の水準を向上させる仕組みの整備
以下の措置を講ずることにより、政策の企画立案等に資する質の高い成果を確保する。 |
|
| (2) |
調査研究活動の水準を向上させる仕組みの整備
以下の措置を講ずることにより、政策の企画立案等に資する質の高い成果を確保する。 |
|
| (2) |
調査研究活動の水準を向上させる仕組みの整備 |
|
| イ |
優秀な研究者の確保と育成
調査研究事業の中核を担う研究者については、プロジェクト研究等の基礎となる学術分野の研究能力と幅広い関心等を備えた人材を内部常勤研究員として確保、育成する。
同時にまた、任期付研究員や非常勤研究員の採用により、大学や他の研究機関に所属する優秀な研究者の参画を得て、プロジェクト研究等の活性化を図るとともに、政策担当者や労使関係者などの実務家の研究参加を求めるなど外部の幅広い人材の活用を図る。
さらに、研究員の業績評価制度を含む人事制度を実施する。人事関連諸制度については、中期目標期間の初年度中に整備を完了して、実施する。 |
|
| イ |
優秀な研究者の確保と育成
| (1) |
人事諸制度の整備
研究員の業績評価制度を含む人事関連諸制度について、15年度末までに整備を完了する。
|
| (2) |
中核となる内部研究者の確保
プロジェクト研究等の基礎となる学術分野の研究能力と幅広い関心等を備えた人材を内部常勤研究員として、また、常勤研究員ではカバーできない研究分野、研究業績、ノウハウを持つ人材を特別研究員、客員研究員等の内部非常勤研究員として確保又は育成する。
|
| (3) |
外部人材の活用
任期付研究員や非常勤研究員の採用により、大学や他の研究機関に所属する優秀な研究者の参画を得て、プロジェクト研究等の活性化を図る。
また、政策担当者や労使関係者などの実務家の研究参加を求めるなど外部の幅広い人材の活用を図る。 |
|
|
| イ |
優秀な研究者の確保と育成
| (イ) |
研究員の業績評価制度
新人事関連諸制度の整備の一環として、研究員については目標管理による業績評価を導入し、「研究員業績評価規程細則」等の所要の規程を整備するとともに、平成15年度分から評価を実施することとした。
|
| (ロ) |
優秀な研究員の育成
当機構の研究員が平成15年度沖永賞(小倉一哉)、第2回産業カウンセリング学会学術賞及び平成15年度日本進路指導学会研究奨励賞(共に下村英雄)を受賞(再掲)。
|
| (ハ) |
任期付研究員の採用(若干名:平成16年4月1日4名採用) |
| ○ |
労働法専攻任期付研究員の公募
応募者15名について、第1次審査(履歴書、研究業績一覧、小論文)、第2次審査(論文)、第3次審査(研究発表会・面接)を経て内定者1名を決定 |
| ○ |
経済・社会学専攻任期付研究員の公募
応募者28名について、第1次審査(履歴書、研究業績一覧、小論文)、第2次審査(論文)、第3次審査(研究発表会・面接)を経て内定者2名を決定(うち1人は博士号の取得者) |
| ○ |
心理学、職業研究専攻任期付研究員の公募
応募者11名について、第1次審査(履歴書、研究業績一覧、小論文)、第2次審査(論文)、第3次審査(研究発表会・面接)を経て内定者1名を決定(博士号の取得者)
(参考)平成15年度における研究員の外部転出等
| 大学等への転出 4名 |
主任研究員 → 同志社大学教授 |
| 副主任研究員→ 国学院大学助教授 |
| 副主任研究員→ 職業能力開発総合大学校助教授 |
| 任期付研究員→ 明治大学専任講師 |
(注)このほかに、定年退職者が1名いた。 |
| (ニ) |
外部人材の活用
優秀な人材を幅広く活用するため、特別研究員等非常勤研究員の任用を積極的に行っている。また、常勤研究員及び非常勤研究員ではカバーできない研究分野、研究業績、ノウハウを持つ他機関等から、22の研究テーマについて、57名(特別研究員を除く)の参加を得ている。 |
| ○ |
特別研究員14名の研究参加状況
特別研究員は、プロジェクト研究を中心として研究方針、論点整理等に関し、外部の専門的立場から指導を行った。
| ・樋口美雄 |
「失業の地域構造分析に関する研究」 |
| ・大竹文雄 |
「失業の地域構造分析に関する研究」 |
| ・藤村博之 |
「労働条件決定システムの再構築に関する研究」 |
| ・荒木尚志 |
「労働条件決定システムの再構築に関する研究」 |
| ・諏訪康雄 |
「我が国における雇用戦略のあり方に関する研究」 |
| ・鈴木宏昌 |
「我が国における雇用戦略のあり方に関する研究」 |
| ・佐藤博樹 |
「多様な働き方を可能とする就業環境及びセーフティネットに関する研究」
「仕事と生活の調和を可能とする社会システムの構築に関する研究」 |
| ・大内伸哉 |
「多様な働き方を可能とする就業環境及びセーフティネットに関する研究」 |
| ・宮本光晴 |
「企業の経営戦略と人事処遇制度等の総合分析に関する研究」 |
| ・守島基博 |
「企業の経営戦略と人事処遇制度等の総合分析に関する研究」 |
| ・今野浩一郎 |
「職業能力開発に関する労働市場の基盤整備の在り方に関する研究」 |
| ・玄田有史 |
「仕事と生活の調和を可能とする社会システムの構築に関する研究」 |
| ・大根田充男 |
「総合的な職業情報データベースの開発に係る研究」 |
| ・山下利之 |
「ホワイトカラーを中心とした中高年離職者の再就職支援に関する研究」 |
|
| ○ |
他の研究機関等からの研究参加
大学や民間の実務家(教育機関、企業等)、行政の政策担当者の研究参加を求めることにより、研究活動の活性化を図った
| ・ |
大学その他研究機関47名(大学38名、その他研究機関9名) |
| ・ |
民間の実務家10名(厚労省関係団体1名、高校教諭2名、企業関係者6名、マスコミ1名) |
| ・ |
政策担当者の研究参加 13研究 |
|
|
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| |
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
|
|
|
|
| (2) |
調査研究活動の水準を向上させる仕組みの整備 |
|
| (2) |
調査研究活動の水準を向上させる仕組みの整備 |
|
| (2) |
調査研究活動の水準を向上させる仕組みの整備 |
|
| ロ |
適切な研究評価の実施
業績評価システムに基づき、事前、中間及び事後における研究評価を実施する。研究評価は、所内発表会によるピアレビュー等の内部評価と外部評価を組み合わせて行う。
研究のとりまとめ段階においては、対外的に発表する調査研究成果の質の確保を図るため、外部の研究者等の参加を得て、所内発表会でのピアレビューを行う。また、とりまとめられた調査研究成果については、外部評価を含む評価を行う。
評価結果及び調査研究への反映のあり方については、当該評価結果が出された日から3か月以内に、機構のホームページにおいて公表する。 |
|
| ロ |
適切な研究評価の実施
業績評価システムに基づき、事前、中間及び事後における研究評価を実施する。研究評価は、所内発表会によるピアレビュー等の内部評価と外部評価を組み合わせて行う。
研究のとりまとめ段階においては、対外的に発表する調査研究成果の質の確保を図るため、外部の研究者等の参加を得て、所内発表会でのピアレビューを行う。また、とりまとめられた調査研究成果については、外部評価を含む評価を行うこととし、厳正な評価を行うため、総合評価諮問会議にリサーチアドバイザー部会(仮称)を設け、研究成果等に関する外部の第三者による評価を行う。
評価結果及び調査研究への反映のあり方については、当該評価結果が出された日から3か月以内に機構のホームページにおいて公表する。 |
|
| ロ |
適切な評価の実施
研究評価については、研究業務評価に関する規程等を策定し、内部評価及び外部評価の仕組みを整備した。このうち、研究成果の評価については、内部評価及び外部評価を行うこととし、まず、内部評価は、内部評価委員会において各評価者(1件につき2名)の評価に基づき内部評価を決定した。また、外部評価については、総合評価諮問会議の下に「リサーチ・アドバイザー部会」を設置し、各研究成果ごとに2人の評価者からの査読を経て、外部評価を決定した。
| (イ) |
個々の調査研究
| ○ |
事前評価
研究計画策定過程において、機構内部の研究企画調整会議等における検討、総合評価諮問会議リサーチ・アドバイザー部会での検討を経ることとした。
また、個々の研究テーマの具体的な研究計画については、各担当研究部門が作成した原案につき、理事長以下による当初ヒアリングを実施し、検討の上作成する。 |
| ○ |
中間評価
年度の中間において、理事長以下による研究実施状況に関するヒアリングを実施する。また、必要に応じて研究所長以下により随時ヒアリングを開催することとしている。
・中間ヒアリング 15年度 1回実施 ・随時ヒアリング 15年度 2回実施
なお、平年度においては、年度の中間において開催されるリサーチ・アドバイザー部会において研究の実施状況を説明し、意見をいただくこととしている。 |
| ○ |
研究とりまとめ段階におけるピアレビュー
| 所内発表会・・・ |
とりまとめ段階にあるすべての研究成果について、スケルトンに基づき発表を行い、所内研究員等の間で議論する。 |
| レビュー・・・ |
とりまとめられた研究成果(原稿等)について、内部又は外部の研究者1〜2名によるレビューを実施し、その指摘事項に基づき所要の修正を行う。 |
|
| ○ |
研究成果評価
| 内部評価・・・ |
内部評価委員会により、とりまとめた研究成果のすべてについて、1件につき2名の評価者の査読等による評価結果(6項目の項目別評価と総合評価)に基づき、5段階(S(最優秀)、A(優秀)、B(普通)、C(要努力)、D(不足))の評価を行う。 |
| 外部評価・・・ |
リサーチ・アドバイザー部会により、内部評価において原則としてB以上の評価を受けた研究成果について、内部評価と同様の方法により評価を行う。
(3月11日 3件評価実施、6月7日 24件評価実施) |
|
|
| (ロ) |
研究事業全体
| ○ |
研究事業総合評価
研究成果の評価に併せてリサーチ・アドバイザー部会において、年度ごとの研究事業について、5段階の総合評価を行い、自己評価結果は妥当との評価を得た。(6月7日実施) |
|
| (ハ) |
評価結果の公表
| ○ |
評価結果のホームページでの公表
出された評価については、その概要及びその研究活動へのフィードバックの方向を整理し、機構のホームページに掲出することとしている。 |
|
|
| ハ |
有識者からの評価の調査等
| (イ) |
機構の事業活動に関する有識者アンケート結果(郵送調査3月8日〜22日)
有識者を対象としたアンケートにおいて、機構の調査研究成果を見たことがあると回答した526名のうち、480名(91.3%)から当該成果物が業務・研究の参考になったとの高い評価を得た。
また、学識経験者(勤務先が大学研究機関と回答した者250名)の回答に限ると、237名(95%)から機構の事業活動が有益であるとの回答を得るなど、年度計画を大きく上回る高い評価を得た。
|
| (ロ) |
政策担当者との意見交換
厚生労働省からの要請研究については、政策課題・分析・研究手法について、研究開始時に要請元との意見交換会を実施したほか、要請元の政策担当者に研究会への参加を依頼し、意見交換を行いつつ研究活動を進めた。とりまとめた結果については、担当者間で報告のための会議を開くなどにより成果の提供を行っている。
プロジェクト研究についても、テーマごとの政策担当者との間で、必要に応じ意見交換を行うほか、研究会への参加を得ているものもある。
| ○ |
厚生労働省の平成16年度研究要請の把握を行うために、要請研究内容説明会を2月5日、10日、12日、18日に分けて開催し、16年度要請研究予定15テーマについての意見交換を行った。 |
| ○ |
研究の実施に行政担当者が参加している研究数(オブザーバー参加を含む)
・要請研究:5研究、プロジェクト研究:2研究 |
|
|
|
| − |
外部評価については、定量的な指標により、一定以上の評価を得る。評価の定量化の方法及び達成目標は、計画期間の初年度中に定めて公表することとし、その際、目標とする指標に関しては、経年的な向上の観点を盛り込む。 |
|
| − |
内部評価及び外部評価の体制(研究発表会及びピアレビューの方法、リサーチ・アドバイザー部会の組織、評価の定量化の方法、経年的向上をめざす達成目標の設定等)を確立し、15年度末までに公表する。 |
|
| ハ |
有識者からの評価の調査等
有識者に対し、調査研究事業の成果について、報告書等の配布にあわせて、アンケート調査による有益度調査を行う。 |
|
| ハ |
有識者からの評価の調査等
| (1) |
有識者を対象とし、機構における調査研究事業活動及び調査研究事業の成果について、有益度を含むアンケート調査を実施する。 |
|
|
| (2) |
調査研究事業について、有識者を対象としたアンケート調査により、3分の2以上の者から「有益である」との評価を得ること。 |
|
| − |
イ及びロの取組を行うことにより、有益度調査において、3分の2以上の者から「有益である」との評価を得る
また、プロジェクト研究及び行政からの要請に基づく調査研究を中心として、政策的課題の把握・分析、調査研究方法の検討、結果のとりまとめ等、研究活動の種々の局面で、政策担当者等との意見交換等を実施する。 |
|
| − |
外部の評価・調査機関により、当機構の調査研究事業活動及び調査研究事業の成果について有益度を調査・把握する方法を、平成15年度中に速やかに整備し、この有益度調査において、3分の2以上の者から「有益である」との評価を得る。
|
| (2) |
プロジェクト研究及び行政からの要請に基づく調査研究を中心として、政策的課題の把握・分析調査研究方法の検討、結果のとりまとめ等、研究活動の種々の局面で政策担当者等との意見交換等を実施する。 |
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| 第3 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 2 |
労働事情・労働政策に関する情報の収集・整理
労働に関する政策研究や政策議論に資するよう、内外の労働事情、各種の統計データ等を機動的に収集・整理すること。 |
|
| 2 |
労働事情・労働政策に関する情報の収集・整理
労働に関する政策研究や政策議論に資するよう、以下の通り、内外の労働事情、各種の統計データ等を機動的に収集・整理する。 |
|
| 2 |
労働事情・労働政策に関する情報の収集・整理
労働に関する政策研究や政策論議に資するよう、以下の通り、内外の労働事情、各種の統計データ等を機動的に収集・整理する。 |
|
|
| (1) |
国内労働事情の収集・整理
無作為抽出による統計調査、モニターを対象とするビジネス・レーバー・サーベイ、有識者アンケート、トレンド研究会などを実施することにより、雇用や人事労務管理など国内の労働事情に関する動向を機動的に収集・整理する。 |
|
| (1) |
国内労働事情の収集・整理
企業を対象として一定規模のサンプルを確保した調査を1回、モニター報告を2回、モニターを対象とする機動的なアンケートを1回、有識者アンケートを1回実施して、雇用や人事労務管理など国内の労働事情に関する動向を機動的に収集・整理する。併せて、調査手法の向上を図るための実験的調査を実施する。 |
|
| (1) |
国内労働事情の収集・整理
労働現場における最新の事情・動向を収集・整理し、政策研究の基盤を整備するため、企業、業界団体、労働組合、産業別労働組合等を対象とするビジネス・レーバー・モニター制度(委嘱240件)、地域シンクタンク・モニター制度(委嘱9件)を創設した。また、企業、勤労者等を対象とする調査については、年度計画の6回を上回る13回実施した。調査結果はホームページ、月刊情報誌『ビジネス・レーバー・トレンド』等を通じて公表した。
新聞・雑誌等における引用は年間目標11件を大幅に上回る83件、調査データの利用申請は12件、ホームページに対するアクセス件数は11,711件等、調査成果は広い範囲で活用された。
| イ |
国内労働事情の収集・整理のための調査等実績
調査に当たっては、ビジネス・レーバー・モニター、地域シンクタンク・モニターに定期的なモニター調査を実施するとともに、アンケート調査、実態調査、ヒアリング等を有機的に組み合わせて、効果的、機動的な実施に努めた。なお、モニター企業等については、調査対象、コンタクト・ポイントとして、その幅広い活用を図った。
| (1) |
企業を対象とした調査「労働者の働く意欲と雇用管理のあり方に関する調査」を1回実施し、調査結果については厚生労働省に速やかに提供し、労働経済白書で活用されることとなった。 |
| (2) |
企業や地域シンクタンクを対象としたモニター報告を3回実施し、調査結果については、ホームページや『ビジネス・レーバー・トレンド』で広く公表するとともに、新聞等のマスコミで広く活用された。 |
| (3) |
「職場の若年正社員の姿」をテーマに機動的アンケートを1回実施し、調査結果については、新聞発表やホームページ、『ビジネス・レーバー・トレンド』で広く公表し、新聞、雑誌、テレビ等のマスコミに47件取り上げられるなど広く活用された。 |
| (4) |
労働関係の研究者を対象に、「春闘」をテーマに有識者アンケートを1回実施し、調査結果については、『ビジネス・レーバー・トレンド』で広く公表した。 |
| (5) |
調査手法の向上・改善を図ることを目的として、有識者による研究会、文献サーベイ等の研究を行うとともに、比較調査「生活意識についての調査」を1回実施した。 |
| (6) |
厚生労働省からの緊急の要請に応じた「第二新卒者の採用実態に関する調査」など、機動的な労働情報の収集を行うテーマ別調査を5件実施した。(うち2件は個別研究の再掲) |
| (7) |
厚生労働省からの要請に応じて「中高年齢者の活躍の場についての将来展望」調査を1回実施した。 |
|
|
|
| − |
収集・整理する情報の質を向上させ、年間26件以上新聞・雑誌等に結果が引用されるようにする。
(14年度実績 20件) |
|
| − |
収集・整理する情報の質を向上させ、年度計画期間中に11件以上新聞・雑誌等に結果が引用されるようにする。 |
|
(2)海外情報の収集・整理
| イ |
海外主要国の労働情報を国別及び政策課題別に、継続的・体系的に収集・整理する。 |
|
(2)海外情報の収集・整理
| イ |
海外主要国の労働情報を国別及び政策課題別に、継続的・体系的に収集・整理する。具体的には以下の業務に取り組む。
| (1) |
主要23カ国に海外委託調査員を設置し、労働政策研究の基盤整備となる国別情報を収集する。
|
| (2) |
7カ国程度の海外委託調査員を招へいして連絡会議を開催し、国別情報を収集する。 |
|
|
| ロ |
労働政策研究上の喫緊の課題となる政策課題に関する情報は、海外の研究機関等とのネットワークを活用するとともに、必要に応じて機動的に現地調査を実施して収集する。 |
|
| ロ |
労働政策研究上の喫緊の課題となる政策課題に関する情報は、海外の研究機関等とのネットワークを活用するとともに、必要に応じて機動的に現地調査を実施して収集する。具体的には以下の情報収集に取り組む。
| (1) |
諸外国におけるITを中心とした在宅ワークの実態(再掲) |
| (2) |
産業の空洞化の国際比較(再掲) |
| (3) |
海外進出日系企業の人事労務管理の実態 |
| (4) |
在日外資系企業の労使関係、労働条件の実態 |
|
|
| ロ |
調査結果の一般等での活用
調査結果の一般等での活用については、全国紙、テレビ放送、専門雑誌での引用件数が大幅に目標を上回った。また、東大社研のアーカイブ等を通じて労働経済研究者等から二次分析を目的とした個票データの利用申請があった。
| ○ |
調査結果が新聞・雑誌等で引用された件数 |
83件(資料12参照) |
| ○ |
東大社研SSJアーカイブ等に調査個票の利用申請があった件数 |
12件(資料13参照) |
| ○ |
専門図書等に調査結果が引用された件数 |
26件(資料9参照*再掲) |
(白書3件、政府・国会報告書7件、政府関係機関以外の報告書3件、専門図書6件、専門誌4件、紀要3件) |
| (2) |
海外情報の収集・整理
| イ |
海外主要国の国別労働情報の収集・整理
年度計画に基づき、海外主要23カ国の労働関係情報を下記の方法で、国別に収集、体系的に整理し、機構の労働政策研究活動に対する情報基盤を整備した。また、収集・整理した情報を広く一般への公表を目的としてとりまとめ、年度計画を大きく上回る234件をホームページ等で提供した。国別情報のホームページにおけるページビュー件数は22万件を超え、広い範囲で活用された。
| ○ |
主要23カ国に海外委託調査員(各国とも研究機関、労使団体等3名を原則とし、計56名)を委嘱し、毎月の定期的レポート、特定テーマを示してのレポートの提出を求め、これを情報収集の基本的な方法とした。 |
| ○ |
中国、韓国など7カ国から委託調査員を東京に招いて11月17〜21日、連絡会議を開催実施した。会議では労働政策研究・研修機構の事業目的、計画について理解を深めるための研修とともに、自国の雇用問題など政策課題をテーマとする公開の報告会を行い、一般参加者の87.5%から「有益」との評価を得た。報告会の概要はホームページを通じて公表した。 |
| ○ |
公表情報の一般等での活用状況
| ・ |
ホームページにおける国別情報のページビュー数:222,757件 |
| ・ |
国別情報等が専門紙誌、テレビ番組等に引用、転載された件数:9件 |
| ・ |
専門図書等に調査結果が引用された件数:19件(資料9参照*再掲)
(白書1件、政府関係機関以外の報告書3件、専門図書8件、専門誌1件、紀要3件その他3件) |
| ・ |
引用等では日刊紙「フジサンケイ・ビジネス・アイ」(3月24日号)で各国のパート労働の実態に関する情報が活用されたほか、NHKの番組「防げるか、若年失業」(11月30日)の主要な参考資料として欧米各国の若年失業に関する情報が活用された。 |
| ・ |
国別情報はホームページによる提供を中心としたが、行政機関の強い要望に対応して、簡易な形態で紙媒体「海外労働情報」を毎月作成して提供した。 |
|
|
| ロ |
政策課題別情報収集実績
年度計画に基づき、下記4件の情報を収集し、報告書にとりまとめて印刷物、ホームページで広く一般に提供した。情報収集に当たっては、上記の国別情報、海外委託調査員のネットワーク等を有効に活用しつつ、必要に応じて現地調査を実施して行った。また、海外情報収集と研究活動を有機的に結びつける観点から、「在宅ワーク」「空洞化」の情報収集については研究員等と協力して研究活動の一環として遂行し、収集情報に幅と厚みを持たせた。さらに、後述する「国際シンポジウム」のテーマとして取り上げ、報告書の内容に加えて海外の研究者の見解を加えた厚みのある情報提供へと結びつけた。
日系企業、外資系企業の調査は、いずれも定点観測を意図した継続的な調査であり、調査方法の過去との整合性を図りながらデータ収集に努め、結果を報告書にとりまとめて印刷物、ホームページ等で公表した。
| (1) |
諸外国におけるITを中心とした在宅ワークの実態に関する調査研究 |
| (2) |
産業と雇用の空洞化の国際比較に関する調査研究 |
| (3) |
海外進出日系企業の労務管理の実態(アンケート調査):対象は61カ国・地域、約3000社、有効回 答率33.1% |
| (4) |
在日外資系企業の労使関係、労働条件の実態(アンケート調査):対象は外国資本比率1/3超の企業約 2,150社、有効回答率15.3% |
|
|
|
| − |
収集・整理して公表する海外情報は、中期目標期間中で1,100件以上とする。 |
|
| − |
収集・整理して公表する海外情報は、年度計画期間中で160件以上とする。 |
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| |
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
|
|
|
|
| (3) |
各種統計データ等の収集・整理
広範囲の情報源を活用して、労働関係の各種統計データを収集する。また、これらを分析・加工し、既存の数値情報では得られない有益かつ有効な情報を作成する。 |
|
| (3) |
各種統計データ等の収集・整理
広範囲の情報源を活用して、労働関係の各種統計データを収集する。
また、これらを整理し、「主要統計指標」や「最近の統計調査から」として取りまとめるともに、分析・加工し、労働統計加工指標、国際比較労働統計等既存の数値情報では得られない有益かつ有効な情報を作成する。
さらに収集した情報を労働統計データベース等として蓄積するとともに、データの拡充を図り、有益性を向上させる。 |
|
| (3) |
各種統計データ等の収集・整理
労働経済等に関する各種統計情報を収集整理し、労働統計データベース等として蓄積するとともに、これら情報を加工し、労働統計加工指標や国際比較労働統計など独自の統計情報を作成した。ホームページの統計情報へのページビュー数は20万件を、労働統計データベースには10,000件を超えるアクセスがあった。
|
| イ |
各種統計データの収集・整理実績
| (1) |
新たな各国の統計データを収集・整理し、国際比較労働統計として取りまとめた。本年度は新たに特集コラムページを設け、多面的な情報提供に努めた。また、ホームページ上では統計表題に英語訳を併載し、利用者の利便性を高めた |
| (2) |
推計等の加工作業を実施し、労働統計加工指標として取りまとめた。特に本年度は指数等の基準年を1995年から2000年に改めた。 |
| (3) |
収集・整理した統計情報は随時労働統計データベースに蓄積を行い、利用者への迅速な情報提供に努めた。 |
| (4) |
統計データの収集・整理を行い、「主要労働統計指標」「最近の統計調査結果から」として取りまとめた。
「主要労働統計指標」は新たに都道府県別有効/新規求人倍率を追加し、提供情報の拡充に努めた。 |
|
| ロ |
収集・整理した情報の普及実績
| (1) |
国際比較労働統計は「国際労働比較2004」として刊行するとともに、ホームページを通じてエクセル・PDFファイルで全資料を公表した。 |
| (2) |
労働統計加工指標は「ユースフル労働統計2004」として刊行するとともに、ホームページを通じてPDFファイルで全ページを公表した。また、労働大学校の教科書としても幅広く活用することとした。 |
| (3) |
労働統計データベースはホームページを通じて随時更新し、常に最新の情報提供に努めた。 |
| (4) |
「主要労働統計指標」「最近の統計調査結果から」はホームページを通じて随時更新し、常に最新の情報提供に努めた。 |
|
| ハ |
収集・整理した情報の一般等での活用
| ○ |
外部からの問い合せ・照会件数 |
43件 |
| ○ |
新聞・雑誌等での引用件数 |
7件(資料14参照) |
|
| ・ |
日本経済新聞や経済学教科書等、高レベル・知名度の高い媒体で提供情報が引用された。 |
|
| ○ |
ホームページでの統計情報のページビュー数 |
203,536件 |
|
| ・ |
当機構ホームページを利用した人のうち、65.2%が「統計情報を利用した」と回答するなど幅広く活用されている。(有識者アンケート調査より) |
|
| ○ |
労働統計データベースのアクセス件数 |
11,587件 |
|
| ・ |
利用者より高い評価を受け、今後も内容の充実を望む声が寄せられている。(有識者アンケート調査より) |
|
|
| (4) |
図書資料等の収集、整理
|
| イ |
図書資料の収集・整理・保管
労働分野を中心に、その関連分野である経済、産業等も含めた内外の図書資料を、関係部署を網羅した図書資料委員会での基本的検討、当該月の刊行リスト一覧による選書、各部署からの随時の要求、寄贈等により、体系的に収集・整理・保管し、労働政策研究事業及び研修事業の基盤整備に努めた。
○図書資料収集実績
| ・ |
図書:13万8千冊(和書:10万8千冊、洋書:3万冊)、うち製本雑誌1万9千冊(和:1万2千冊、洋:7千冊) |
| ・ |
逐次刊行物:1,100種(和雑誌等400種、洋雑誌:200種、紀要500種) |
|
| ロ |
図書資料の活用実績
収集・整理した図書資料を閲覧、貸出、レファレンスへの回答、コピーサービス等により、行政関係者、外部研究者、労使実務家等に積極的に提供したことにより、外部利用者アンケートでほぼ8割の人からサービス内容について「良い」との高い評価を得た。また、ホームページ、定期刊行物等を通じて図書館の広報に努めた。
| ・ |
外部閲覧者: |
896名 |
(前年同期間:561名) |
| ・ |
貸出冊数: |
3,104冊 |
(前年同期間:2,375冊) |
| ・ |
レファレンス件数: |
1,598件 |
(前年同期間:557件) |
| ・ |
コピーサービス枚数: |
16,635枚 |
(前年同期間:11,295枚) |
|
| ハ |
図書資料加工情報の収集・整理
収集した図書資料については、毎月「労働文献目録」として整理・提供するとともに、蔵書データベース・調査研究成果データベース・論文データベースとして随時蓄積するとともに、インターネットを通じて提供した。
| ・ |
上記データベースへのアクセス件数:81,289件
(蔵書:10,752件、調査研究成果:29,191件、論文:41,346件) |
|
|
| (4) |
図書資料等の収集・整理
内外の労働関係図書資料を、総合的・体系的に収集、整理、保管し、調査研究事業及び研修事業の効果的な推進等を支援する。
また、図書資料を一般公開し、行政関係者及び外部の研究者等の利用に供して、その有効活用を図る。 |
|
| (4) |
図書資料等の収集、整理
内外の労働に関する図書資料等を体系的に収集、整理、保管し、機構の調査研究事業及び研修事業の効果的な推進等を支援する。
併せて、これら図書資料は、閲覧・公開、レファレンス・サービス等を通じて、行政関係者及び外部の研究者、労使実務家等の利用にも供し、その有効活用を図る。
さらに、上記の収集・整理の蓄積を踏まえて加工した労働関係情報を継続的に作成し、これら情報資源のより積極的な利用を図る。
| ・ |
「JIL労働文献目録」の作成 |
| ・ |
蔵書データベース、論文データベース、調査研究成果データベースの収録情報の作成・蓄積 |
|
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| 第3 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 3 |
研究者・有識者の海外からの招へい・海外派遣
各国で共通する労働分野の課題について、各国の研究者、研究機関とネットワークを形成し、相互の研究成果の交換、活用を図ることによって、労働問題の情報を共有し、政策の企画立案等に貢献すること。 |
|
| 3 |
研究者・有識者の海外からの招へい・海外派遣
海外の研究機関等とのネットワークの形成及び研究者等招へい・派遣等の研究交流を通じて、共同研究の基盤づくりを行うとともに、研究論文の発表やフォーラム等の開催などの有益な成果をあげる。
その場合、研究者の招へい・派遣に関しては、目的を明確にし、効果を高める。
このため、以下の通り業務を実施する。 |
|
| 3 |
研究者・有識者の海外からの招へい・海外派遣
海外の研究機関等とのネットワークの形成及び研究者等招へい・派遣等の研究交流を通じて、共同研究の基盤づくりを行うとともに、研究論文の発表やフォーラム等の開催などの有益な成果をあげる。このため、以下の業務を実施する |
|
|
| (1) |
海外の研究機関等とのネットワークの形成
先進国及びアジアの研究機関及び研究者とのネットワークを形成し、相互の研究成果の交換、活用を図る。 |
|
| (1) |
海外の研究機関等とのネットワークの形成
| (1) |
先進国の労働関係研究機関によって構成される情報交換を目的としたネットワークに参加し、各国の研究課題、研究動向、研究成果等に関する情報を交換するとともに機構の研究の推進に活用する。
| ・ |
EU財団の主催する労働関係研究機関会議への参加 |
| ・ |
ドイツ・ベルテルスマン財団の主催する情報交換ネットワークへの参加(情報の提供等) |
|
| (2) |
アジア地域労働関係研究機関会議の開催
ILOアジア太平洋総局(在バンコク)と協力し、15カ国の研究機関による共通の研究テーマ(ITとディーセントワーク)に基づいた研究活動を進める。 |
|
|
| (1) |
海外の研究機関等とのネットワークの形成
年度計画に基づき、先進国の労働関係研究機関によって構成される情報交換を目的とした下記のネットワークに参加するとともに、アジア地域15カ国の研究機関と共通テーマに基づく研究を実施することにより、各国研究機関の研究動向等に関する情報を収集するとともに、将来の共同研究の基盤づくりに努めた。
| ○ |
EU財団主催の「労使関係」をテーマとした国際ワークショップに参加し「日本の労使関係の現状」に関して発表するとともに、研究成果の相互交換等について参加研究機関と協議した。(アイルランド・ダブリン、11月6、7日) |
| ○ |
ドイツ・ベルテルスマン財団が主催し先進国15カ国20研究機関で構成される労働市場、労使関係に係わる「国際リフォーム・モニター・ネットワーク」に参加し、日本の情報を提供するとともに、構成研究機関の研究動向等に関する情報を収集した。 |
| ○ |
ILOアジア太平洋総局と協力し、アジア地域15カ国の研究機関と「ITとディーセントワーク」をテーマとする各国別研究(2004年までの3年計画)を実施、各国の中間報告をとりまとめるとともに、各研究機関の研究動向について情報を収集した。研究成果は2004年の最終報告をとりまとめて公表する。 |
|
| (2) |
研究者等招へい
中期計画・年度計画に基づき、日本の労働問題研究者の育成や将来における国際共同研究の基盤づくり等を目的とした長期招へい、具体的テーマを決めて日本の労働問題を研究する短期招へいの実施に関する「招へい事業実施要綱」を整備し、これに則って年度計画どおり下記の6名を招聘した。各招聘研究員は機構研究員等のアドバイスを受けながら研究成果を論文にとりまとめ、所内研究会で報告した上で提出した。また帰国後、長期招へい研究員の論文はいずれも所属研究機関に提出され、所属機関の印刷物に掲載されている。
| ○ |
長期招へい(2名)
| ・ |
チェン研究員(中国国際労働研究所)
| 研究テーマ |
「企業における賃金分配のメカニズムに関する研究」 |
|
| ・ |
リム研究員(韓国労働研究院)
| 研究テーマ |
「自動車産業における国際競争に対する労働組合、使用者、地方自治体の対応に関する研究・地域経済とグローバル化の相互作用に関する研究」 |
|
|
| ○ |
短期招へい(4名)
「アジアにおける国際的な人の移動と労働市場」をテーマとした国際ワークショップに講師として1名招へい
「労働条件の設定メカニズム・雇用形態の多様化」をテーマとした比較労働法セミナーに講師として3名招へい
| ・ |
ダウシュミット教授(インディアナ大学/アメリカ) |
| ・ |
ロンマー講師(ルンド大学講師/スウェーデン) |
| ・ |
バーナード講師(ケンブリッジ大学/イギリス |
|
|
| (3) |
研究者等派遣
中期計画・年度計画に基づいて、研究者の育成を目的とした長期派遣、海外の労働政策や労働問題の研究、国際学会への出席等を目的とした短期派遣の実施に関する「派遣事業実施要綱」を整備し、これに則って年度計画どおり下記の9名を派遣した。国際学会で発表した論文はホームページで公表している。
| ○ |
長期派遣(1名):ILO事務局(ジュネーブ)に1名派遣(10〜3月) |
| ○ |
短期派遣(8名)
| ・ |
「集団的労使紛争解決システムに関する調査」を目的に1名を米国に派遣 |
| ・ |
「高齢者雇用」をテーマとした韓国労働研究院主催セミナー(ソウル)に講師として1名を派遣 |
| ・ |
「労使関係教育」をテーマとした韓国労働教育院主催セミナー(ソウル)に講師として2名を派遣 |
| ・ |
「労使関係」をテーマとしたEU財団の国際研究会議(アイルランド)に発表者2名を派遣 |
| ・ |
「英国の能力開発指導者要請に関する調査」を目的に2名を英国に派遣 |
|
|
| (4) |
英文情報の整備・提供
英文情報については、年度計画で予定した3件に加え、招聘研究員、海外の研究機関等の要望に応えて、機構の調査研究報告書の要約の英訳版等を追加して計5件整備し、印刷物、ホームページ等を通じて提供した。英文情報の内容は、英文雑誌、英文メールマガジン、共同研究の機会などを活用して、海外の研究者等のニーズを把握することに努めながら整備し、普及に努めた。英文情報全体のホームページにおけるアクセス件数は21万件を超え、広く活用されている。
| (1) |
日本の労働問題の最近の状況に関する基本的なデータとその分析をまとめた英文「日本の労働問題と分析」を機構研究員の執筆により作成し、印刷物、ホームページで提供した。 |
| (2) |
日本の労働法の英訳版(「労働基準法改正版」、「最低賃金法」、「賃金支払確保法規則」、「労働者派遣法改正版」)を作成し、印刷物、ホームページ等で提供した。中でも2003年6月に大幅改正のあった内容を反映した「労働基準法改正版」は特にニースが高く、印刷物を増刷して提供した。また、『世界各国の労働法・労使関係百科事典』を発行している世界的に有名なオランダの出版社クルーワー社から「英訳労働法の質が高いので転載させてほしい」との依頼があり、これを許可した。 |
| (3) |
外国人研究者等に日本の労働政策研究に関する情報の提供を目的に、わが国初の英文による労働政策に関するクオリティージャーナルとして、英文雑誌「Japan Labor Review」(季刊)を創刊し1月に第1号を刊行した。配布約2,500部。読者の内容に関するニーズや有益度等についての意見を把握するためアンケート調査をしたところ「有益」と答えたものの割合が77.6%という高い評価を得た。また、海外の大学図書館等から多くの提供依頼が寄せられた。 |
| (4) |
「15年版労働経済白書」の要約英文資料を作成しホームページで提供するとともに、在日外国人研究者、外国大使館労働担当者等を対象とした「労働問題ブリーフィング」を開催して解説を加えて資料提供した。(12月18日開催)(参加者42人に対しアンケートで有益度を調査した結果、回収33人のうち「有益」と回答した割合は88%であった) |
| (5) |
調査研究報告書の「要約」11点(No.150〜No.160)の英訳を作成、HPで提供した。この資料の整備は年度計画になかったが、招聘研究員、共同研究のカウンターパート研究機関等からの要望が強く追加して実施した。 |
|
|
| (2) |
研究者等招へいについては、日本の労働問題研究者の育成や将来における国際共同研究の基盤づくり等を目的とした長期招へい、具体的テーマを決めて日本の労働問題を研究する短期招へいを実施する。 |
|
| (2) |
研究者等招へいについては、日本の労働問題研究者の育成や将来における国際共同研究の基盤づくり等を目的とした長期招へい、具体的テーマを決めて日本の労働問題を研究する短期招へいを実施する。 |
|
| − |
上記の目的のため、招へいする研究員等は、中期目標期間中に36人以上とする。 |
|
|
| (3) |
研究者等派遣については、研究者の育成を目的とした長期派遣、海外の労働政策や労働問題の研究、国際学会への出席等を目的とした短期派遣を実施する。 |
|
| (3) |
研究者等派遣については、研究者の育成を目的とした長期派遣、海外の労働政策や労働問題の研究、国際学会への出席等を目的とした短期派遣を実施する。 |
|
| − |
上記の目的のため、派遣する研究員等は、中期目標期間中に60人以上とする。 |
|
|
| (4) |
わが国の労働問題や労働政策研究の動向に関する情報など、研究交流等に資する英文情報について、調査研究成果等を活用しつつ整備し、提供する。 |
|
| (4) |
わが国の労働問題や労働政策研究の動向に関する情報など、研究交流等に資する英文情報について、調査研究成果等を活用しつつ整備し、提供する。
15年度においては以下の英文情報を作成する。
| (1) |
英文「日本の労働問題と分析」 |
| (2) |
日本の労働法の英訳版 |
| (3) |
英文雑誌(季刊) |
|
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| 第3 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 4 |
調査研究結果等の成果の普及・政策提言
調査研究等の成果を迅速に関係者に情報発信することにより、その普及を図るとともに、調査研究等の成果を積極的かつ効果的に活用し、定期的に政策論議の場を提供すること。
特に次の具体的な目標の達成を図ること。 |
|
| 4 |
調査研究結果等の成果の普及・政策提言
調査研究成果等が労働政策の企画立案に貢献し、国民各層における政策議論の活性化に寄与するものとなるよう、調査研究等の成果の普及・政策提言の業務を以下の通り実施する。 |
|
| 4 |
調査研究結果等の成果の普及・政策提言
年度計画期間中の調査研究、情報の収集・整理の成果等が労働政策の企画立案に貢献し、国民各層における政策論議の活性化を促進することを目的として、以下の調査研究等の成果の普及・政策提言の業務を的確に行う。 |
|
|
| (1) |
査研究成果等の迅速な提供
調査研究成果等は、とりまとめた後、迅速に発表し、必要な関係者に提供する。
調査研究成果は、「労働政策研究報告書」、「労働政策レポート」等、適切な形態で発表する。 |
|
| (1) |
調査研究成果等の迅速な提供
調査研究の完了後、速やかに成果をとりまとめ発表し、関係者に迅速、的確に提供することによって、成果の普及、活用促進を図る。
調査研究成果は、以下の形態で取りまとめ、発表する。
| (1) |
労働政策研究報告書 |
| (2) |
労働政策レポート |
| (3) |
資料シリーズ |
| (4) |
ディスカッションペーパー |
| (5) |
システム・ツールの形式で作成した研究開発成果物 |
|
|
| (1) |
調査研究成果等の迅速な提供
|
| イ |
研究成果の取りまとめ実績
研究成果は、労働政策研究報告書、労働政策レポート、ディスカッションペーパー、システム・ツールの形式で作成した研究開発成果物等としてとりまとめるとともに、労働政策研究報告書、労働政策レポートについては分かりやすいサマリーを作成し、政策担当者等読者の便宜を図った。
平成15年度にとりまとめた研究成果は43件で、このうち27件について外部評価を受け、年度計画に掲げる目標数値5件以上の4倍の20件が5段階評価(SABCD)でA以上の評価を得た。(11件については16年度央の外部評価の対象、5件の国際研究会議等提出論文等は評価対象外)
|
| ロ |
研究内容の意見把握
報告書(サマリー)に葉書を添付してアンケート実施し、テーマに関する関心、役立ち度、分かりやすさその他の意見の把握を行い、その結果は総じて好評を得ている。
| 「興味深いテーマである」 |
79% |
| 「役立つ内容である」 |
69% |
| 「わかり易い構成である」 |
81% |
|
| ハ |
研究成果の迅速な提供
とりまとめた研究成果は、ただちにサマリー及び成果物本体を機構ホームページに掲載して、関係者への迅速な提供に努めるとともに、サマリー及び研究成果の刊行物を関係者に配付している。
このうち、理事長のリーダーシップの下に作成したコンパクトで分かりやすいサマリーは、忙しい政策担当者をはじめとする読者に好評を得ている。また、ホームページへの掲載については、PDFファイルで全文をダウンロードできるように利用者の利便性を図ったことで、研究成果へのアクセス件数も113,499件に上るなどの効果を上げた。
|
| ニ |
『ビジネス・レーバー・トレンド』記事掲載 14件
研究員の研究成果は、『ビジネス・レーバー・トレンド』にも適宜掲載し広く一般への普及を図った。当該読者アンケートでは90%近くから有益であるとの評価を得るなど、政策担当者のみならず広く国民一般における政策論議の活性化にも貢献した。
・11月号:5(特集記事1、成果紹介4)
・12月号:4(特集記事)
・ 1月号:1(特集記事)
・ 2月号:2(特集記事)
・ 3月号:1(成果紹介)
・ 4月号:1(論文)
|
| ホ |
研究成果作成件数
| (1) |
研究成果作成件数 43件
(報告書22、労働政策レポート3、ディスカッションペーパー11、その他研究成果物2、国際研究会議等提出論文等5) |
| (2) |
国際研究会議・セミナー等提出論文 4件 |
| ・ |
「男女雇用均等政策の展望に関する研究」(日中韓共同ワークショップ:奥津、堀(春)、原) |
| ・ |
「労働教育に関する論点とりまとめ」(ILO、日中韓国際シンポジウム:江上、呉) |
| ・ |
「日本の労働市場の構造変化と高齢者雇用政策」(高齢化における労働市場政策に関する国際セミナー:岩田) |
| ・ |
「労使関係の動向に関する研究」(EU、日米共同ワークショップ:岩田) |
| (3) |
その他 |
| ・ |
「雇用と能力開発の政策形成−ディアローグ編」 |
| ・ |
「雇用と能力開発の政策形成−資料編」 |
|
| ヘ |
政策論議の場のへの研究員の参加
| (1) |
労働政策フォーラム 6名(パネリスト3名、コーディネーター2名、コメンテーター1名) |
| (2) |
国際フォーラム 2名(コメンテーター1名、パネリスト1名) |
| (3) |
国際シンポジウム 1名(基調報告兼パネリスト1名) |
|
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| |
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
|
|
|
|
| (2) |
調査研究等の成果の普及
調査研究成果等は、上記(1)の他、ホームページ、データベース、メールマガジン、定期刊行物その他の媒体・方法を効果的に活用して、その普及を図る。 |
|
| (2) |
調査研究等の成果の普及
調査研究成果等は、上記(1)の他、ホームページ、各種データベース、和文・英文メールマガジン、定期刊行物その他の媒体・方法の効果的な活用(メディアミックス)を図ることによって、その広範な普及を促進する。 |
|
|
| イ |
ニュースレター及びメールマガジン
調査研究等の成果については、当該成果を速やかに整理して情報発するメールマガジンと背景の分析・解説を加えたニュースレターにより、国民各層に幅広く提供する。 |
|
| イ |
ニュースレター及びメールマガジン
調査研究、内外の情報収集・整理等の成果については、当該成果を速やかに整理して情報発信するメールマガジンと背景の分析・解説を加えたニュースレターを発行することによって、分かりやすい形で国民各層に提供する。 |
|
| イ |
ニュースレター及びメールマガジン
| (イ) |
発行実績
機構の研究やリサーチ活動等に基づいた労働政策課題の発見に努め、それが「何故」起こっているのかを的確に解説したニュースレター「ビジネス・レーバー・トレンド」を毎月1回発行するとともに、内外の最新の労働関係情報を迅速に提供する和文メールマガジン及び英文メールマガジンを発行した。年度末における読者数は年度計画を上回り、和文メールマガジンは約22,050名、英文メールマガジンは1,630名であった
| ○ |
ニュースレター「ビジネス・レーバー・トレンド」毎月1回(年度中6回)発行
| (1) |
11月号「フリーター・若年無業からの脱出−キャリア形成と支援のあり方」(10月30日発行) |
| (2) |
12月号「基幹化する非正社員−多様化とその行方」(11月25日発行) |
| (3) |
1月号「仕事と育児−−共働き世帯の現実」(12月25日発行) |
| (4) |
2月号「職場の若年者の姿−「余裕喪失」から「やる気創出」へ−」(1月25日発行) |
| (5) |
3月号「パートタイム労働の国際比較−均衡処遇の現状と将来像−」(2月25日発行) |
| (6) |
4月号「『春闘』はどこへ向かうのか−終焉か?再構築か?」(3月25日発行) |
| * |
行政機関、労使関係団体、企業等に有料講読も含めて4,300部普及している。 |
|
| ○ |
和文メールマガジン「メールマガジン労働情報」
| ・ |
毎週水曜日と金曜日の2回発行した
(発行回数)44回:No1〜No44 |
| ・ |
読者数:22,050人と目標を上回った。 |
|
| ○ |
英文メールマガジン「The Japan Labor Flash」
| ・ |
毎月2回発行した
(発行回数)11回:No1〜No11 |
| ・ |
読者数:1,630人と目標を上回った。
|
|
|
| (ロ) |
一般等での活用
ニュースレター及びメールマガジンについて、読者を対象に有益度調査を行った結果、回答者の90%近くから有益であるとの高い評価を得た。また「有識者アンケート」においても、認知度及び有益度とも90%を超える高い評価を得た。
| ○ |
ニュースレター「ビジネス・レーバー・トレンド」
4月号で行った読者アンケートの結果、89%から「役に立っている」(「大変有益である」17%、「有益である」(72%)との評価を得るとともに、日刊紙「フジサンケイ・ビジネス・アイ」や北海道新聞の夕刊コラムに掲載記事が紹介されるなど、読者ニーズに応える内容の情報を提供した。
|
| ○ |
和文メールマガジン「メールマガジン労働情報」
読者に対して有益度等についてのアンケート調査(3月24日付から3回実施)を実施し、99%から「役に立っている」(「非常に役に立っている」30%、「役に立っている」(69%)との評価を得た。
|
| ○ |
英文メールマガジン「The Japan Labor Flash」
読者に対して2月に掲載記事に関するニーズや有益度等を把握するためにアンケート調査を実施し、「有益」と答えたものの割合が92%という高い評価を得た。 |
|
|
|
| (1) |
調査研究等の成果について、ニュースレターを月1回以上、メールマガジンを週2回以上、関係者に情報発信すること。 |
|
| − |
ニュースレターは月1回、メールマガジンは、和文は週2回、英文は月2回発行する。 |
|
| − |
労働に関する時宜にかなった政策課題を取り上げ、同課題に関する調査研究成果を踏まえて、課題の背景や論点等を分析するとともに、企業の動向を探る「ビジネス・レーバー・サーベイ」の調査結果、事例など現場の実態、海外の動向、労使・研究者の意見・主張など課題を多角的に捉えて情報発信するニュースレター「ビジネス・レーバー・トレンド」を月1回(年度中6回)発行する。 |
|
| − |
メールマガジンの読者は、中期目標期間終了時点で、和文24,000人以上、英文2,000人以上を目標とする。 |
|
| − |
労働政策論議の活性化、労働政策の研究・企画立案材料の提供、行政職員の資質向上に資する基礎知識の提供を目的に、調査研究成果等に関する情報に加えて労働問題に関する広範な情報をもリンクした和文メールマガジンを週2回発行する。和文メールマガジンの読者数は15年度末までに22,000人以上とする。
また、政策研究等のための英文等情報基盤の整備事業において作成した英語によるわが国の労働問題、労働法制、労働関係の研究動向、研究成果等に関する情報を活用しながら、日本の労働問題に関する時事的なトピックスを加えた英文メールマガジンを月2回発行する。同メールマガジンの読者は15年度末までに1,600人以上とする。 |
|
| − |
ニュースレター、メールマガジン読者へのアンケート調査において「有益である」と答えた者の割合を70%以上となるようにする。 |
|
| − |
ニュースレター、和文・英文メールマガジン読者へのアンケート調査を行い、読者ニーズを把握し、コンテンツの充実に努める。また、読者アンケートにおいて、「有益である」と答えた者の割合を70%以上となるようにする。 |
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| (2) |
中期目標期間中におけるホームページへのアクセス件数を2,100万件以上とすること。(12年度から14年度までの平均 年456万件 ) |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ロ |
ホームページ、データベース等
調査研究等の成果については、ホームページで迅速に提供する。
長期的に蓄積・整理して体系的に提供することが求められる調査研究成果や内外の情報等については、データベースとして整備し、提供する。
データベースは、論文データベース、調査研究成果データベース、蔵書データベース、労働統計データベース、研究者情報データベース及び職業情報データベースとする。
以上の取組みに加え、利用者ニーズに沿ったホームページを提供することにより、ホームページへのアクセス件数を、2,100万件(ページビュー数)以上とする。
(12年度から14年度までの平均年456万件) |
|
| ロ |
ホームページ、データベース等
調査研究、情報収集・整理等の成果については、国民各層に幅広く公開するため、ホームページを通じて迅速に提供する。
長期的に蓄積・整理して体系的に提供することが求められる調査研究成果や内外の情報、データ等については、各種データベースとして整備・提供し、政策関係者等の活用を促進する。
平成15年度に整備・提供するデータベースは、論文データベース、調査研究成果データベース、蔵書データベース、労働統計データベース、研究者情報データベース及び職業情報データベースとする。
以上の取組みを通じて、ホームページへの年度計画期間中のアクセス件数を、320万件(ページビュー数)以上とする。 |
|
| ロ |
ホームページ、データベース等
新法人の発足に合わせて、機構の調査研究、情報収集・整理等の成果を各種媒体を通じて広く国民各層に迅速に提供するため、広報体制の強化を図った。
特に提供媒体の柱であるホームページやデータベースは、情報・内容の更新、拡充に努めるとともに、利用者の利便性向上を考慮した改善を図るなど、適切な運用・管理に取り組んだ。
この結果、15年度のホームページ、データベースへのアクセス件数は4,687,332件となり、年度計画期間中の目標数値(320万件)を50%近く上回った。
| ○ |
新法人の発足に合わせてホームページを一新し、著作権や個人情報保護等に関する適切なサイトポリシーを定めて運用するとともに、労働政策研究報告書の全文情報の掲載やデータベースの検索機能等の強化など、掲載情報の充実と利便性の大幅な改善を図った。
主な変更・改善点は以下のとおりである。
| (1) |
ホームページ全体のデザインを一新し、サイト内の各ページのデザイン、表現等の統一化を図った |
| (2) |
著作権や個人情報保護に配慮した利用規約をホームページに掲載した。 |
| (3) |
PDFファイルやExcelデータの表示方法、音声ブラウザへの対応などの基準を定めてホームページの運用を始めた。 |
| (4) |
音声ブラウザに対応できるようバリアフリー対策を行った。 |
| (5) |
労働政策研究報告書、ディスカッションペーパーなどの成果物は、刊行と同時にサマリーと全文情報をホームページに掲載するなど、調査研究成果を積極的に公表・公開する仕組みを構築した。 |
| (6) |
各データベース間の連携機能及び各データベース検索機能を強化した。 |
| (7) |
アクセス情報の解析システムを導入し、ユーザーのニーズ把握の一助とした。 |
|
| ○ |
以下の情報収集・整理等の成果を迅速にホームページで公開するとともに、長期的、体系的な観点から整理し、蓄積の必要なものは、各種データベースに登録し、提供した。
| (1) |
調査研究成果 |
| (2) |
各種統計データ |
| (3) |
国内労働情報 |
| (4) |
海外労働情報 |
| (5) |
図書資料収集・加工情報 |
| ※ |
データベースへの登録情報件数は平成16年3月末現在で251,495件。 |
|
| ○ |
「ホームページ利用者アンケート」では、回答者の約9割から「(ホームページは)利用しやすい」との評価を得た。またコンテンツ全体についても、回答者の平均75%から「満足」との評価を得た。 |
|
| ハ |
研究専門雑誌
| (イ) |
『日本労働研究雑誌』
レフリー(審査員)制の研究専門雑誌『日本労働研究雑誌』を計画どおり毎月1回発行した。政策立案の現場で重要な論点となっているテーマについてそれぞれ毎号の特集として取り上げるなど、各分野の第一線で活躍する専門家の論稿を多数紹介し、政策提言の促進や政策論議の活性化に貢献した。
| ・ |
『日本労働研究機構』毎月1回(計6回)発行
| (1) |
10月号: |
「ホワイトカラーの労働時間をめぐる最近の動向と課題」(10月25日発行) |
| (2) |
11月号: |
「職場のメンタルヘルス」(11月25日発行) |
| (3) |
12月号: |
「高齢者雇用と年齢差別」(12月25日発行) |
| (4) |
1月号: |
「労働基準法・労働者派遣法・職業安定法改正」(1月25日発行) |
| (5) |
2/3月号: |
「学会展望・労働調査研究の現在−2001〜2003年の業績を通じて」(3月25日発行) |
| (6) |
特別号: |
2003年労使関係研究会議報告「アジアの労働と日本−新しい国際分業体制を目指して」(12月25日発行) |
|
| ・ |
発行部数:3,400部 |
| ・ |
平成15年度の投稿論文数は105点にのぼり、労働分野の研究者等から質の高いレフリー制雑誌として評価され、活用されている。 |
| ・ |
「有識者アンケート」では、回答者の9割から有益であるとの高い評価を得るとともに、2/3月号で実施した読者アンケートにおいても、「非常に有意義な雑誌であり今後も期待している」、「最近編集に色々と工夫がされていて、良くなっている」、「高水準の内容を比較的平易に紹介していてよい」などの意見が寄せられており、読者の評価も概ね良好である。 |
|
| (ロ) |
労働関係図書及び論文の表彰
労働に関する研究の奨励と研究水準の向上、及び労働問題に関する一般の関心を高めることを目的として、労働関係図書及び論文の表彰を行った。2002年4月から2003年3月までに刊行・発表された著作・論文を対象に、審査委員会による2回の審査を経て平成15年度の受賞作を決定した。結果は、ホームページ等において発表するとともに、1月21日付読売新聞夕刊でも紹介された。なお、発表後、他新聞社から受賞者に対して取材が申込まれるなどの反響があった。
【受賞作】
| ・図書賞: |
「アジアにおける近代的工業労働力の形成−経済発展と文化ならびに職務意識」(清川雪彦著/岩波書店) |
| ・論文賞: |
「パートが正社員との賃金格差に納得しない理由は何か」 (篠崎武久・石原真三子・塩川崇年・玄田有史)
「高齢者雇用と人事管理システム−雇用される能力の育成と選抜および契約転換の合意メカニズム」(高木朋代)
「ドイツ企業年金改革の行方−公私の役割分担をめぐって」(渡邊絹子) |
| ※ |
受賞図書は、執筆者の15年にもわたる実態調査をもとに執筆された労作で、労働問題研究の水準向上に貢献したとして高い評価を得ている。また、優秀論文賞は研究奨励に資するという観点から、3点とも若手研究者の力作を表彰対象とした。 |
|
|
|
| ハ |
研究専門雑誌
研究者、専門家等による質の高い政策論議、政策提言を促進するため、レフリー(審査員)制の研究専門雑誌を発行する。 |
|
| ハ |
研究専門雑誌
研究者、専門家等による質の高い政策論議、政策提言の促進及び研究水準の向上を目的として、レフリー(審査員)制の研究専門雑誌「日本労働研究雑誌」を発行する。 |
|
|
|
| − |
研究専門雑誌は、毎月1回(年度中6回)発行する。
また、労働に関する研究の奨励と研究水準の向上、労働問題に関する一般の関心を高めるため、労働関係図書及び論文の表彰を年1回行う。 |
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| (3) |
中期目標期間中におけるフォーラム、国際シンポジウム等の開催のべ件数を39件以上とすること。 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
|
|
|
|
| (3) |
政策論議の場の提供
政策的対応が特に求められる諸課題について、機構内外の研究者、政策担当者、労使関係者等の参加を得て労働政策フォーラムを定期的に開催し、調査研究成果等を踏まえた、開かれた政策論議の場を提供する。
また、調査研究成果を普及し、政策論議の活性化を図るため、フォーラム、シンポジウム等を随時開催する。
さらに、わが国でも関心を集めている先進国に共通する課題に関して海外の研究者・有識者、政策担当者等を交えて国際シンポジウムを実施する。また、海外の政策担当者等を報告者とする小規模のフォーラムを開催する。
以上の取組みを通じて中期目標期間中のフォーラム、シンポジウム等の開催のべ件数を39件以上とする。 |
|
| (3) |
政策論議の場の提供
政策的対応が特に求められる諸課題について、機構内外の研究者、政策担当者、労使関係者等の参加を得て、労働政策フォーラムを定期的に開催する。また、労働政策フォーラムでの議論を迅速に議事録等にとりまとめホームページに掲載することにより、web上でバーチャルフォーラムを開催し、より広範な国民の政策論議への参加を促進する。
その他、調査研究成果を普及し、政策論議の活性化を図るため、経済・社会情勢等の変化に応じた政策ニーズに即して、フォーラムシンポジウム等を機動的に実施する。
さらに、わが国でも関心を集めている先進国に共通する課題に関して、海外の研究者・有識者、政策担当者等を交えて国際シンポジウムを実施する。また、海外の政策担当者等を報告者とする小規模のフォーラムを開催する。 |
|
| (3) |
政策論議の場の提供
フォーラム等を12回開催し、行政、企業労使等延べ2,094人が参加した。試行的に実施したバーチャルフォーラムもより広範な利用に供するものとして好評を得た。参加者の満足度は平均で87.4%と高い評価を得た。
|
| イ |
労働政策フォーラム
年度計画どおり3回開催した。各回とも、現在、政策的対応が求められている重要課題をテーマに取り上げて開催し、時宜を得た情報提供を行うことができた。各回のテーマに沿って行政機関、労使団体、研究者や実務家等に対してきめ細かく開催案内を行った結果、毎回多数の有効な参加者(平均147名)を得ることができた。講師(パネリスト)と参加者との間の質疑応答内容も極めて活発で質の高いものとなり、参加者の平均満足度は95.3%という高い評価を得た。
| (1) |
第1回フォーラム
| ・ |
開催日:1月14日 |
| ・ |
テーマ:「個別労働紛争の解決制度を考える-参審制をめぐる検討会報告を踏まえて-」 |
| ・ |
参加者:192名 |
| ・ |
参加者満足度:100% |
|
| (2) |
第2回フォーラム
| ・ |
開催日:2月19日(木) |
| ・ |
テーマ:「教育から職業へ−欧米諸国の若年就業支援政策の展開−」 |
| ・ |
参加者:160名 |
| ・ |
参加者満足度:92% |
|
| (3) |
第3回フォーラム
| ・ |
開催日:2月26日(木) |
| ・ |
テーマ:「先進諸国の雇用戦略−福祉重視から就業重視への政策転換−」 |
| ・ |
参加者:90名 |
| ・ |
参加者満足度:94% |
|
| * |
1月より、ホームページ上にバーチャルフォーラムのページ(eフォーラム)を構築し、第1回労働政策フォーラム「個別労働紛争の解決制度を考える」、第2回労働政策フォーラム「教育から職業へ」のライブ中継、録画配信を行うとともに、講師のレジュメ、配付資料等を受信者が参照できるように掲載した。 |
|
| ロ |
国際シンポジウム
年度計画を上回って3回開催した。いずれのシンポジウムにおいても現在の重要な政策課題に関する機構の研究成果を広く普及することを意図し、また外国人研究者等との討議を通じて日本と各国との比較研究の成果を生み出すことに努めた。この結果、参加者に対して行った満足度アンケートで「満足」と答えたものの割合が3回の平均で所期の目標70%を大きく上回る88.6%という高率となって現れた。
| (1) |
「日本・EUシンポジウム」:2月10日開催、テーマは「労使関係と変化」、参加者160名、参加者に対する満足度アンケートで「満足」と答えた割合は89.3%。 |
| (2) |
「欧米の在宅ワークの実態から何を学ぶか」をテーマとした国際シンポジウム:3月5日開催、参加者70名、参加者に対する満足度アンケートで「満足」と答えた割合は93.0%。 |
| (3) |
「グローバリゼーションと産業・地域雇用の再生−日独比較−」をテーマとした国際シンポジウム:3月26日開催、参加者は80名、参加者に対する満足度アンケートで「満足」と答えた割合は90.1%。 |
|
| ハ |
国際フォーラム
年度計画に基づき、下記の1回を開催した。フォーラムは上記のシンポジウムと構成を異にし、絞り込んだテーマで比較的少人数による集中的な討議を意図しているが、今年度においては会場定員を大きく上回る参加希望者があり、規模を拡大して実施した。この結果、参加者に対する満足度アンケートで「満足」と答えた割合は93.8%という極めて高い評価を得た。
| ○ |
「アメリカの非典型労働者−その現状とAFL・CIO−の対応−」をテーマとした国際フォーラム:11月7日開催、参加者160名。 |
|
| ニ |
雇用職業研究会を全国5ブロックで開催し、参加者の平均満足度は79.4%であった。 |
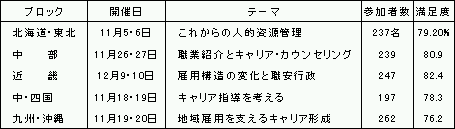
| (注) |
関東ブロックは、旧日本労働研究機構時代の9月29・30日に実施。 |
|
| − |
労働政策フォーラムは年間6回程度、国際シンポジウムは年間2回程度、国際フォーラムは年間3回程度、それぞれ開催する。 |
|
| − |
政策的対応が求められる雇用・労働分野の諸課題について、研究者・行政関係者・労使関係者等の参加する労働政策フォーラムを年度計画期間中に3回程度開催する。
|
| − |
国際的に注目され、わが国においても関心を集めている先進国に共通する課題をテーマに、機構の研究成果等を活用しつつ、海外の研究者、行政関係者、労働関係者等を交えた国際シンポジウムを、年度計画期間中に2回程度実施する。
|
| − |
各国に共通する政策課題について海外の政策担当者等を主な報告者とする小規模の国際フォーラムを、年度計画期間中に1回程度実施する。
|
| − |
職業安定行政職員等を対象とした雇用職業研究会を、全国5ブロックで開催する。 |
|
| − |
労働政策フォーラム、国際シンポジウム及び国際フォーラムの参加者を対象としたアンケート調査において、有益であったと答えた者の割合を70%以上とする。 |
|
| − |
労働政策フォーラム、国際シンポジウム、国際フォーラム及び雇用職業研究会の参加者を対象としたアンケート調査を実施し、ニーズやサービスの満足度の把握を行い、適切な改善に努めるとともに、有益であったと答えた者の割合の70%以上を目標とする。 |
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| 第3 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 第2 |
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 |
|
| 5 |
労働関係事務担当職員その他の関係者に対する研修 |
|
| 5 |
労働関係事務担当職員その他の関係者に対する研修 |
|
| 5 |
労働関係事務担当職員その他の関係者に対する研修 |
|
| 5 |
労働関係事務担当職員その他の関係者に対する研修 |
|
|
研究員による研究成果を活かし、第一線の労働行政機関で実際に役に立つ能力やノウハウが取得できる研修を効果的に実施すること。
併せて、研修の場を通じて、労働行政の現場で生じている問題や第一線の労働行政機関の担当者の問題意識を吸い上げ、研究に活かすこと。
特に次の具体的な目標の達成を図ること。 |
|
|
厚生労働省研修実施要綱及び地方労働行政職員研修計画に基づく研修等を効果的かつ効率的に実施するため、以下の点に重点的に取り組む。
|
|
|
厚生労働省研修実施要綱に基づき、別紙1の研修等を効果的かつ効率的に実施するため、以下の点に重点的に取り組む。
|
|
| (1) |
研修の効果的実施
平成15年度研修実施計画に基づき、以下の研修を効果的かつ効率的に実施した。実践的な能力の向上に寄与するような講義、演習等を実施するなどして各研修の内容の充実を図った。また、外部からの意見を伺って、研修の充実を図るため、研修事業有識者懇談会を設置することとし、16年度当初に第1回の懇談会を開催すべく準備をすすめた。 |
イ 研修実績
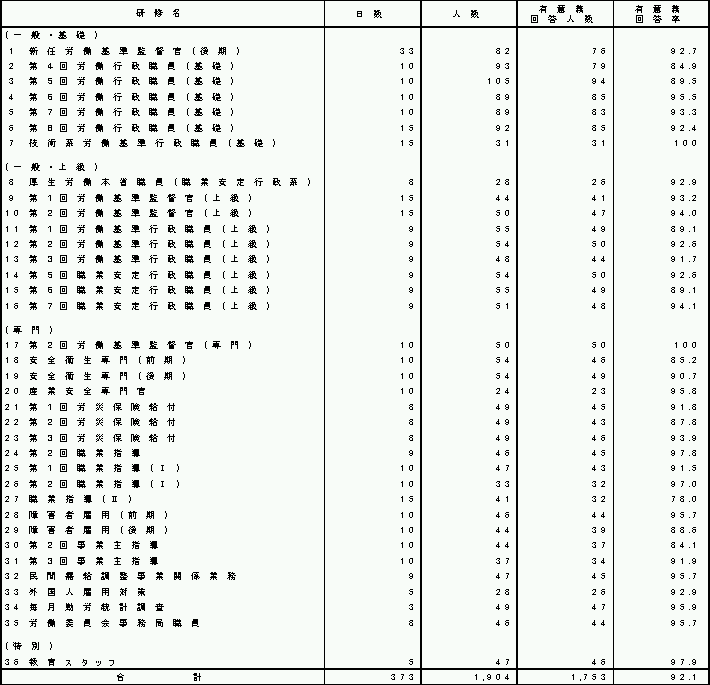
ロ 研究部門研究員の講義への参画状況
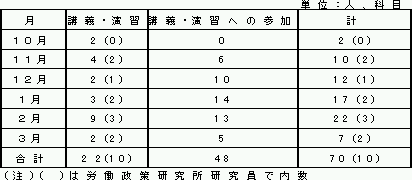
| ハ |
研修に関する研究等
研究部門と連携して研修ニーズの明確化、新規コースのカリキュラム・教材の策定に研究面から参画するとともに、労働行政サービスに係る研修技法及び教材ニーズの把握のため、関係者、研究者よりなる研究会を設置し、検討を行った。
|
| ニ |
研修に対する要望の把握
厚生労働省と平成16年度の研修実施計画を作成するための会議を開催し、先方の要望を踏まえ16年度研修実施計画を決定した。
|
| (2) |
研修と研究の連携
アンケートの集計結果から、研修生の問題意識の吸い上げを行っている。また、一部科目については研究員が講義・演習に机を並べて参加し、モニタリングや研修生との交流等を通じて現場での課題や問題意識の把握に努めた。なお、16年度に労働大学校がその有する研究機能、研修ノウハウを活用して実施する「職業指導/キャリアガイダンスツール講習会」の準備を、労働大学校(研究員、教授職、事務局)が一丸となって行った。
|
| (3) |
研修生からの評価
36研修コースの研修生1,904人のうち、92.1%にあたる1,753人から「有意義だった」との評価を得ており、目標を大きく上回った。 |
|
| イ |
研修内容の充実等
専門的行政分野に従事する職員の専門能力の一層の向上を図るため、ロールプレイ等により実践的な能力を強化するよう、研修内容の一層の充実を図る。
また、研修が効果的に実施できるよう研修環境の整備を図る。 |
|
| イ |
研修内容の充実等
専門的行政分野に従事する職員の専門能力の一層の向上を図るため、ロールプレイ等により実践的な能力を強化するよう研修内容の一層の充実を図る。
また、研修が効果的に実施できるよう研修環境の整備を図る。 |
|
| ロ |
研究員の研修への参画
研究員がその研究成果を活かしつつ研修実施に積極的に参画する。 |
|
| ロ |
研究員の研修への参画
研究員がその研究成果を活かしつつ研修実施に積極的に参画する。 |
|
| ハ |
研修に関する研究等
効果的な研修実施のための研修技法についての研究及び教材の開発等を行う。 |
|
| ハ |
研修に関する研究等
効果的な研修実施のための研修技法についての研究及び教材の開発等を行う。 |
|
| ニ |
研修に対する要望の把握
労働行政機関における職員の研修ニーズに的確に対応するため、研修生の送り出し側の研修に対する要望を的確に把握、分析し、研修内容に反映させる。 |
|
| ニ |
研修に対する要望の把握
労働行政機関における職員の研修ニーズに的確に対応するため、研修生の送り出し側の研修に対する要望を的確に把握、分析し、研修内容に反映させる。 |
|
| (2) |
研修と研究の連携
研究員が研修に参画するなど研修の場を通じて、また、研修生に対するニーズや問題意識等に関するアンケート調査の実施等を通じて、労働行政の現場で生じている問題や第一線の労働行政機関の担当者の問題意識を吸い上げ、研究に活かす。
特に、職業指導等に関する研究など第一線の業務に密接に関連する分野の研究については、研修の実施に積極的に参画しつつ、 研究を実施する。 |
|
| (2) |
研修と研究の連携
研究員が研修に参画するなど研修の場を通じて、また、研修生に対するニーズや問題意識等に関するアンケート調査の実施等を通じて、労働行政の現場で生じている問題や第一線の労働行政機関の担当者の問題意識を吸い上げ、研究に活かす。
特に、職業指導等に関する研究など第一線の業務に密接に関連する分野の研究については、研修の実施に積極的に参画しつつ、研究を実施する。 |
|
| ・ |
研修生に対するアンケート調査により、毎年度平均で85%以上の者から「有意義だった」との評価を得ること。 |
|
| (3) |
上記(1)、(2)を通じ、研修生に対するアンケート調査により、毎年度平均で85%以上の者から「有意義だった」との評価を得る。 |
|
| (3) |
上記(1)、(2)を通じ、研修生に対するアンケート調査により、毎年度平均で85%以上の者から「有意義だった」との評価を得る。 |
|
| 中期目標 |
中期計画 |
平成15年度計画 |
平成15年度の業務の実績 |
| |
|
|
|
(1)方針
| イ |
優秀な人材を幅広く登用するため、研究員については、任期付任用、非常勤としての任用を積極的に活用する。
|
|
(1)方針
| イ |
優秀な人材を幅広く登用するため、研究員については、任期付任用、非常勤としての任用を積極的に活用する。
|
|
(1)方針
| イ |
優秀な人材の確保
優秀な人材を幅広く登用するため、研究員については、任期付任用、非常勤としての任用を積極的に活用した。
| ○ |
非常勤研究員の任用
外部の幅広い人材を活用するために、特別研究員制度を見直して14名の研究者を特別研究員に委嘱した。 |
| ○ |
育成型任期付研究員の任用
定年退職及び大学への転出に伴う研究員の減少分については、すべてを任期付研究員により補充するとの方針で公募を行い、厳正な選考を経て4名の内定者を決定した。(うち2名は博士号取得者)
| (1) |
労働法専攻任期付研究員の公募
応募者15名について、第1次審査(履歴書、研究業績一覧、小論文)、第2次審査(論文)、第3次審査(研究発表会・面接)を経て内定者1名を決定 |
| (2) |
経済・社会学専攻任期付研究員の公募
応募者28名について、第1次審査(履歴書、研究業績一覧、小論文)、第2次審査(論文)、第3次審査(研究発表会・面接)を経て内定者2名を決定(うち1人は博士号の取得者) |
| (3) |
心理学、職業研究専攻任期付研究員の公募
応募者11名について、第1次審査(履歴書、研究業績一覧、小論文)、第2次審査(論文)、第3次審査(研究発表会・面接)を経て内定者1名を決定(博士号の取得者)
(参考)平成15年度における研究員の外部転出等
| 大学等への転出 4名 |
主任研究員 |
→ |
同志社大学教授 |
| 副主任研究員 |
→ |
国学院大学助教授 |
| 副主任研究員 |
→ |
職業能力開発総合大学校助教授 |
| 任期付研究員 |
→ |
明治大学専任講師 |
|
|
|
| ロ |
新人事制度の確立
目標管理制度に基づく業績評価制度及び職務基準の明確化による能力評価制度等を柱とした新人事制度を確立し、評価者研修等を行うとともに、平成16年度からの本格実施に向けて試行的実施を行った。
| ○ |
新人事制度の確立、試行的実施
| ・ |
新人事制度の基本設計及び評価マニュアルを策定した。 |
| ・ |
評価者となる部課長を対象とした評価方法等についての研修及び職員を対象とした説明会をそれぞれ3回実施した。 |
| ・ |
平成16年度の本格運用に向け、一部の部門において試行的な人事評価を実施した。 |
|
| ○ |
リサーチ職の創設
事務職について、研究員との連携も図りつつ、内外の労働事情の調査及び労働関係情報の収集・分析を専門とするリサーチ職を創設した。 |
| ○ |
新たな労働時間管理の検討
研究員について、裁量労働制による労働時間管理の平成16年度からの導入に向けた検討を行った。 |
|
| ハ |
人員の抑制
常勤嘱託やアルバイト等非常勤職員の抑制に努めるとともに、業務上やむを得ない場合も、期間を限定した派遣職員による対応とすることで総数の抑制を図った。
|
| ニ |
職員の専門的な資質の向上
職員を対象とした能力開発計画案の策定や留学制度の創設、職員の自主的な研修会の実施や外部の業務研修への参加の奨励など、職員の専門的な資質の向上に向けた様々な取り組みを行った。
| ・ |
新人事制度の確立に併せて、職員の能力開発計画案を策定した。 |
| ・ |
これに先立って、理事長の指示に基づいて「休職留学制度」を創設し、公募及び厳正な審査を経て1名を一橋大学大学院に留学させた。 |
| ・ |
職員の業務研修への参加等は37件である。(海外労働情報研究会の実施、内部監査基礎講座、給与実務研修会等への参加) |
|
| (2) |
人員の指標
設立当初の常勤職員数は140人、当年度末の常勤職員数は140人であり、平成15年度計画のとおりであった。 |
|
| ロ |
業績評価制度を含む人事制度を研究員及び事務職員を対象として実施する(人事関連諸制度については、中期計画の初年度中に整備を完了し、実施する。)。 |
|
| ロ |
業績評価制度を含む人事制度を研究員及び事務職員を対象として実施する(人事関連諸制度については、15年度末までに整備を完了し、実施する。)。 |
|
| ハ |
業務運営の効率化、定型業務の外部委託化の推進等により、人員の抑制を図る。 |
|
| ハ |
業務運営の効率化、定型業務の外部委託化の推進等により、人員の抑制を図る。 |
|
|
|
|
(2)人員の指標
|
期末の常勤職員数を134人とする。
(参考)期初の常勤職員数 140人 |
|
(2)人員の指標
|
設立当初の常勤職員数
140人
平成15年度末の常勤職員数
140人 |
|