メリット収支率が85%を超え又は75%以下となる場合は、事業の種類に応じて定められている労災保険率から非業務災害率を減じた率を40%(一括有期事業における建設の事業及び立木の伐採の事業については35%)の範囲内で上げ下げし、これに非業務災害率を加えた率を、基準となる3月31日の属する保険年度の次の次の保険年度において当該事業に適用する労災保険率とする。
〔継続事業のメリット制概略図〕
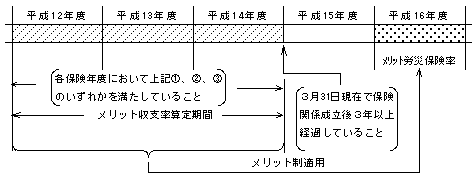
| 1 | 趣旨 事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている労災保険率を個別事業に適用する際、事業の種類が同一であっても作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、事業主の災害防止努力の如何等により事業ごとの災害率に差があるため、事業主負担の公平性の観点から、さらに、事業主の災害防止努力をより一層促進する観点から、当該事業の災害の多寡に応じ、労災保険率又は労災保険料を上げ下げするものである。 |
| 2 | 継続事業(一括有期事業を含む)の場合 |
| (1) | 適用事業 連続する三保険年度中の各保険年度において、次の(1)〜(3)の要件のいずれかを満たしている事業であって、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下「基準となる3月31日」という。)現在において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過している事業についてメリット制の適用がある。
|
| (2) | メリット収支率 労災保険率を上げ下げする基準は、基準となる3月31日において当該連続する三保険年度の間における当該事業の一般保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に調整率を乗じて得た額と、業務災害に係る保険給付及び特別支給金の額との割合により算出される収支率(メリット収支率)による。
|
||||||||||||||||||
| (3) | 第1種調整率 メリット収支率の算定に当たり、分子に算入される年金給付の評価額は労働基準法相当額(一時金)であるが、分母の保険料額は年金たる保険給付に要する費用を基に設定された料率による保険料であるため、調整率を分母に乗じることにより分子との不均衡を調整している。 なお、林業、建設事業、港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業の事業については、特定疾病に係る保険給付分を分子に算入しないことから、分母に乗じる調整率は一般の事業と異なる。
|
| (4) | メリット労災保険率 メリット収支率が85%を超え又は75%以下となる場合は、事業の種類に応じて定められている労災保険率から非業務災害率を減じた率を40%(一括有期事業における建設の事業及び立木の伐採の事業については35%)の範囲内で上げ下げし、これに非業務災害率を加えた率を、基準となる3月31日の属する保険年度の次の次の保険年度において当該事業に適用する労災保険率とする。 〔継続事業のメリット制概略図〕 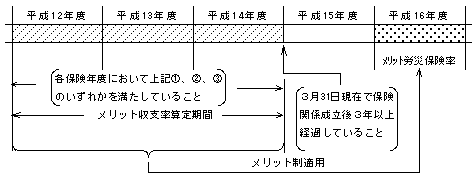 |
| 3 | 有期事業の場合 |
| (1) | 適用事業
|
| (2) | メリット収支率 保険料の額を上げ下げする基準は、当該事業の一般保険料に係る確定保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に調整率を乗じて得た額と、事業終了日から3か月又は9か月を経過した日前までの業務災害に係る保険給付及び特別支給金の額との割合により算出される収支率(メリット収支率)による。
|
||||||||||||||||||||||
| (3) | 第1種及び第2種調整率 事業終了日3か月経過日を算定日とする場合は、上記1(3)と同様の第1種調整率を分母に乗じる。 他方、事業終了日9か月経過日を算定日とする場合は、9か月を経過した日以後の保険給付はメリット収支率算定基礎(分子)に含まれないことから、その分低く算定されることとなる。それを調整するため、有期事業については第2種調整率が設けられており、9か月経過日を算定日とする場合は第2種調整率を分母に乗じる。
|
| (4) | 改定確定保険料額 メリット収支率が85%を超え又は75%以下である場合に、当該事業の確定保険料のうち業務災害に係る額を35%の範囲内で上げ下げする。 〔有期事業のメリット制概略図〕 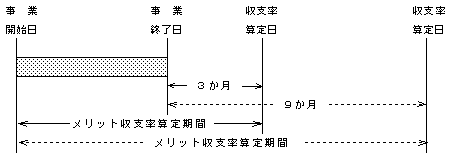
|
| (注) | 3か月を経過した日前までの業務災害に係る保険給付及び特別支給金の額を用いてメリット収支率を計算するのは、メリット収支率がその日以降において変動せず、またはメリット増減率表のメリット収支率階級の範囲を超えて変動しないと認められるときで、これ以外は、9か月を経過した日前までの額を用いて計算する。 |
| 4 | 特例メリット制 特例メリット制は、以下の(1)、(2)、(3)の要件をすべて満たす事業について、(3)の安全衛生措置を行った年度の翌年度の4月1日から9月30日までの間にメリット制の特例の適用の申告があるとき、安全衛生措置を講じた年度の次の次の年度から3年度の間について、メリット制が適用になる年度に限り、適用するものである。
特例メリット制を適用する場合、継続事業の場合と同様に計算したメリット収支率が85%を超え又は75%以下となる場合は、事業の種類に応じて定められている労災保険率から非業務災害率を減じた率を45%の範囲内で上げ下げし、これに非業務災害率を加えた率を、その事業についての基準となる3月31日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とする。 〔特例メリット制概略図〕 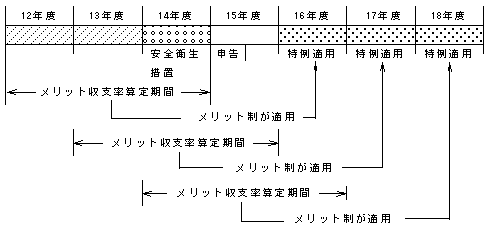
|