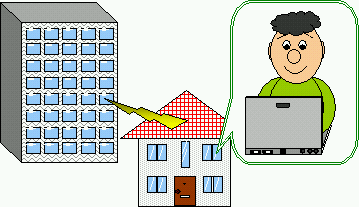戻る
「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び
実施のためのガイドライン」について |
|
情報通信機器を活用して、働く者が時間と場所を自由に選択して働くことができる働き方であるテレワークは広がりをみせてきており、次世代のワークスタイルとして期待されています。
そのような中で、事業主と雇用関係にある労働者が自宅で業務に従事する場合(在宅勤務)、業務に従事する場所が自宅であることや、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯とが混在せざるを得ないことなどから、労働基準関係法令の適用関係等を整理し直し、適切な労務管理が行われることが必要となっています。
このため、厚生労働省では、「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を策定しました。 |
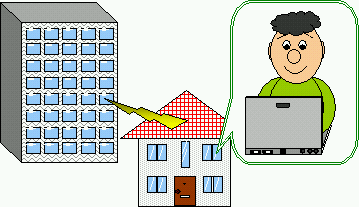
在宅勤務制度の導入を検討している事業主の方々は、このガイドラインを十分御理解いただき、適切な労務管理に努めていただくようお願いします。
また、既に導入している事業主の方々も、このガイドラインにより、制度の再点検等を行い、適切な労務管理に努めていただくようお願いします。 |
37
このガイドラインの中では、「労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態」のことを在宅勤務といいます。この在宅勤務を制度として導入するか否かは、基本的には事業主が労働者等の意向を踏まえ、業務の実態等を勘案して判断するものでありますが、事業主は、在宅勤務を希望する労働者の存在等を随時把握し、在宅勤務の可能な業務の検討などを進めておくことが望まれます。
在宅勤務を制度として導入するに当たっては、以下の注意点に留意するとともに、在宅勤務は労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方であることから、これに伴う在宅勤務の課題の解決について、労働者の合意を得ることが求められます。
(1)労働基準関係法令の適用
| 在宅勤務には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されます。 |
(2)労働基準法上の注意点
| ア | 労働条件の明示
使用者は、在宅勤務を行わせる場合には、労働契約の締結に際し、就業の場所として、労働者の自宅を明示しなければなりません(労働基準法施行規則第5条第2項)。
|
| イ | 労働時間
次の(1)〜(3)のいずれの要件をも満たす形態で行われる在宅勤務には、労働基準法第38条の2で規定する事業場外労働のみなし労働時間制を適用することができます。 |

38

| 在宅勤務について事業場外労働のみなし労働時間制を適用することができる場合 |
| (1) | 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。 |
| (2) | 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。 |
| (3) | 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。 |
| → | ただし、例えば、労働契約において、午前中の9時から12時までを勤務時間とした上で、労働者が起居寝食等私生活を営む自宅内で仕事を専用とする個室を確保する等、勤務時間帯と日常生活時間帯が混在することのないような措置を講ずる旨の在宅勤務に関する取決めがなされ、当該措置の下で随時使用者の具体的な指示に基づいて業務が行われる場合については、労働時間を算定し難いとは言えず、事業場外労働に関するみなし労働時間制は適用されません。 |
|
【在宅勤務に事業場外労働のみなし労働時間制が適用される場合の留意点】
| ○ |
|
就業規則等で定められた「所定労働時間」労働したものとみなされます。 |
| ○ | ただし、通常「所定労働時間」を超えて労働することが必要となる場合には、当該「通常必要とされる時間」労働したものとみなされます。また、労使の書面による協定があるときには、その協定で定める時間が「通常必要とされる時間」とされ、当該協定は労働基準監督署長へ届け出ることが必要です(労働基準法第38条の2)。 |
| ○ | 「労働したものとみなされる時間」が法定労働時間を超える場合には、三六協定の締結、届出及び時間外労働に係る割増賃金の支払いが必要です(労働基準法第36条及び第37条)。 |
| ○ | 深夜に労働した場合には、深夜労働に係る割増賃金の支払いが必要です(労働基準法第37条)。 |
| ○ | 事業主は、労働者が業務に従事した時間を記録した日報等により、労働時間の状況の適切な把握に努め、必要に応じて所定労働時間や業務内容等について改善を行うことが望まれます。 |
|
(3)労働安全衛生法上の注意点
| 事業者は、在宅勤務を行う労働者に対し、必要な健康診断を行うとともに(労働安全衛生法第66条第1項)、在宅勤務を行う労働者を雇い入れたときは、必要な安全衛生教育を行う必要があります(労働安全衛生法第59条第1項)。
また、事業者は在宅勤務を行う労働者に対し、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平成14年4月5日基発第0405001号)等に留意するとともに、その内容を周知し、必要な助言を行うことが望まれます。 |
(4)労働者災害補償保険法上の注意点
| 在宅勤務中に業務が原因で生じた災害は、労働者災害補償保険の保険給付の対象となります(自宅における私的行為が原因であるものは、業務上の災害とはなりません)。 |
39
| その他在宅勤務を適切に導入及び実施するに当たっての注意点 |
|
(1)労使双方の共通の認識
| 在宅勤務制度の導入に当たっては、労使で認識に齟齬のないように、あらかじめ導入の目的、対象となる業務、労働者の範囲、在宅勤務の方法等について、労使委員会等の場で十分に納得のいくまで協議し、文書にし保存する等の手続を踏むことが望まれます。
また、在宅勤務制度が導入された場合には、実際に在宅勤務をするかどうかは本人の意思によることとするべきです。 |
(2)業務の円滑な遂行
| 在宅勤務を円滑かつ効率的に実施するために、業務内容や業務遂行方法等を文書にして交付するなど明確にして行わせることが望まれます。
また、あらかじめ通常又は緊急時の連絡方法について、労使間で取り決めておくことが望まれます。 |
(3)業績評価等の取扱い
| 在宅勤務を行う労働者が業績評価等について懸念を抱くことのないように、評価制度、賃金制度を構築することが望まれます。 |
(4)通信費及び情報通信機器等の費用負担の取扱い
| 在宅勤務に係る通信費や情報通信機器等の費用負担については、あらかじめ労使で十分に話し合い、就業規則等において定めておくことが望まれます。 |
(5)社内教育等の取扱い
| 在宅勤務を行う労働者が能力開発等において不安に感じることのないように、社内教育等の充実を図ることが望まれます。 |
→就業規則の作成及び届出
(3)〜(5)に関して、常時10人以上の労働者を使用する事業主が、在宅勤務を行う労働者について特段の定めをする場合は、就業規則に規定し、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条第2号、第5号及び第7号)。 |
在宅勤務を行う労働者においても、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して自律的に業務を遂行することが求められます。
40
トップへ
戻る