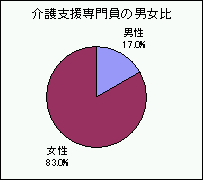
| 介護支援専門員の男女比の割合は、女性が83%、男性が17%と、女性が多くの割合を占めている。 | 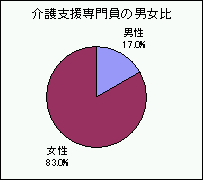 |
| 介護支援専門員の年齢構成は、40代が一番多く、40.9%を占めている。次いで、30代の26.7%、50代の26.1%と続く。30代から50代で93.7%を占めている。 | 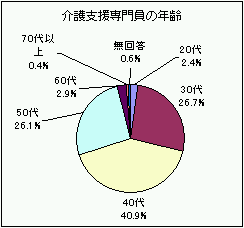 |
| 介護支援専門員の経験年数は、3年以上が56.4%と一番多く、次いで、2年〜3年の19.7%、1年〜2年の11.5%と続いている。 | 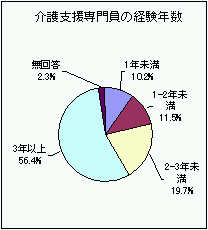 |
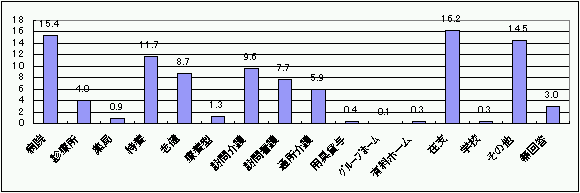
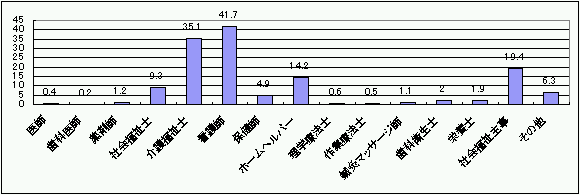
| 介護支援専門員の雇用形態は、常勤専従と兼務を合わせて、92.6%を占めている。居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員は、ほとんど常勤であり、非常勤は6%に過ぎない。 | 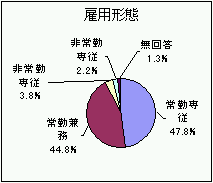 |
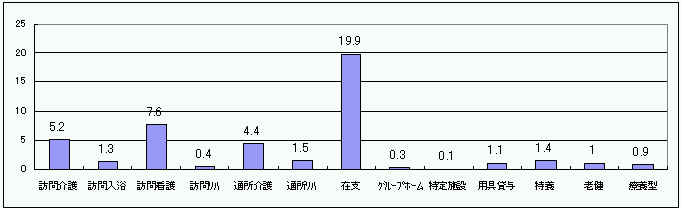
| 居宅介護支援事業所の総利用者数は、51人から100人が一番多く、27.0%、次いで、101人〜150人の21.6%、1人〜50人以下の20.4%、151人〜200人の11.3%と続いている。一方、400人を超える事業所も2.8%存在している。 | 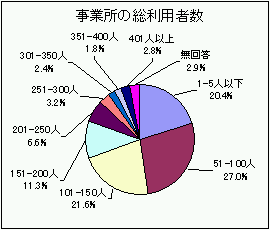 |
| 1人の介護支援専門員が担当している利用者数は、41〜50人が一番多く、21.1%となっている。次いで、51〜60人の19.8%、31〜40人の12.7%と続いている。 | 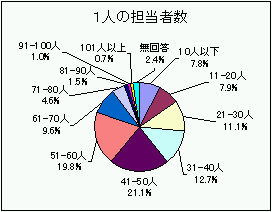 |
| 1人の介護支援専門員が、平成15年10月に居宅介護支援費を請求した件数は、41〜50件が一番多く24.1%を占める。次いで、31〜40件の17.6%、51〜60件の16.2%の順となっている。 | 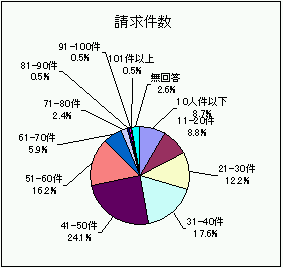 |
| 平成15年10月において、介護支援専門員が休日出勤をしている割合は、47.8%となっている。 | 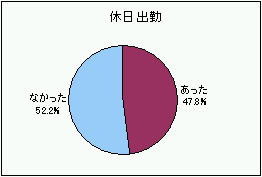 |
| 平成15年10月中において、介護支援専門員が時間外勤務を行った割合は、69.9%と高い割合を示している。 | 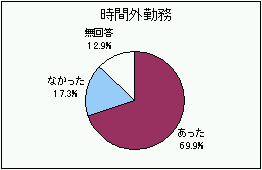 |
| 平成15年10月において、介護支援専門員がサービス残業を行った割合は、70.1%となっている。 | 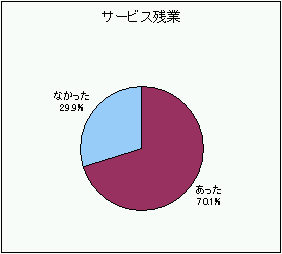 |
| 介護支援専門員の報酬は、21〜25万円が一番多く27.4%を占める。次いで、15〜20万円の20.2%、26〜30万円の17.2%と続いている。30万円以下の報酬が67.9%と約7割を占めている。 | 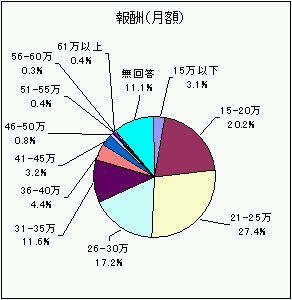 |
| 介護支援専門員は、30.7%が現在の介護報酬に不満を持っている。やや不満を加えると、59%の介護支援専門員が不満を持っていることがわかる。報酬に満足している割合は、「満足」と「ほぼ満足」を加え、27.5%にとどまる。 | 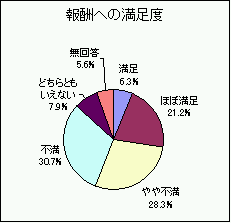 |
| 介護支援専門員が希望する報酬額は、26〜30万円が一番多く、次いで、31〜35万円の20.4%、21〜25万円の16.0%の順となっている。介護支援専門員の半数は、26〜35万円の報酬額を望んでいる。 | 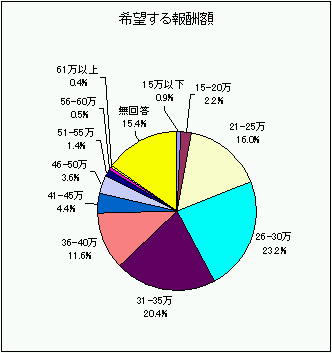 |
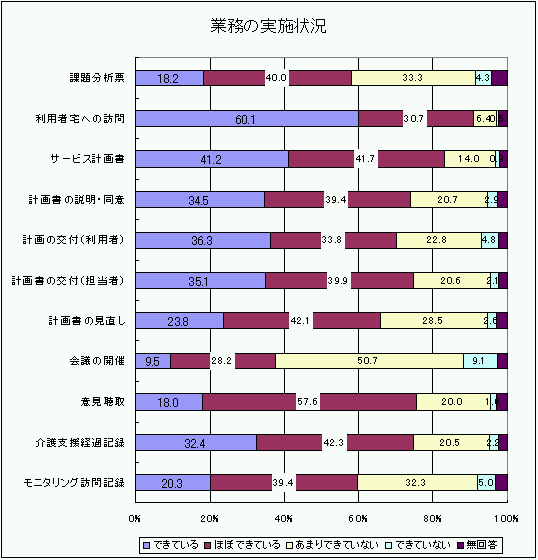
| (1) | 課題分析票の作成(アセスメントの実施) 課題分析票の作成については、「あまりできていない」と「できていない」を合わせると、37.6%となる。できない理由として、24.3%の人が「時間がない」を挙げている。 |
| (2) | ご利用者宅への訪問 利用者宅への訪問は、90.8%の割合でできていることがわかる。ただし、できていない介護支援専門員も6.9%いる。できない理由としては、時間がないことを挙げている。 |
| (3) | サービス計画書(ケアプラン)の作成 サービス計画書の作成は、82.9%の割合でできていることがわかる。しかし、できていない割合が14.9%いる。 |
| (4) | サービス計画書(ケアプラン)の説明と同意 サービス計画書(ケアプラン)をご利用者に対して説明し、同意を求めることについては、73.9%ができている。ただし、「あまりできていない」「できていない」が23.6%あり、できない理由として11.2%の人が「時間がない」を挙げている。 |
| (5) | サービス計画書(ケアプラン)の交付(利用者) 利用者に対するサービス計画書(ケアプラン)の交付については、70.1%ができている。しかし「あまりできていない」「できていない」を合わせると27.6%の人ができていない。できない理由として10.3%の人が「時間がない」を挙げている。 |
| (6) | サービス計画書の交付(サービス担当者) 事業者に対するサービス計画書(ケアプラン)の交付については、75.0%ができている。しかし、「あまりできていない」と「できていない」を合わせると、22.7%ができていない。できない理由としては、11.6%の人が「時間がない」を挙げている。 |
| (7) | サービス計画書(ケアプラン)の見直し サービス計画書(ケアプラン)の見直しについては、65.9%ができているが、31.1%ができていない。できない理由として17.7%の人が「時間がない」を挙げている。 |
| (8) | サービス担当者会議の開催 サービス担当者会議については、37.7%ができているが、59.8%ができていない。できない理由として31.8%の人が「時間がない」を挙げている。 |
| (9) | サービス担当者への意見聴取 サービス担当者への意見聴取については、75.6%ができているが、21.6%ができていない。できない理由として11.9%の人が「時間がない」を挙げている。 |
| (10) | 介護支援経過記録 介護支援経過記録については、74.7%ができているが、22.7%ができていない。できない理由として15.9%の人が「時間がない」を挙げている。 |
| (11) | モニタリング訪問の記録 モニタリング訪問の記録については、59.7%ができているが、37.3%ができていない。できない理由として21.0%の人が「時間がない」を挙げている。 |
| 妥当な担当件数は21〜30人が一番多く44.6%、次いで31〜40人の29.9%、11〜20人の9.5%と続いている。 21〜40人が妥当と考えている介護支援専門員が74.5%いる。 |
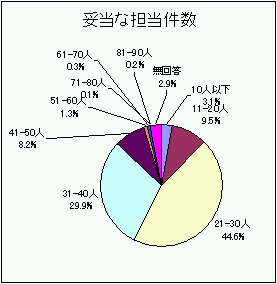 |
| 妥当な介護報酬は1,001〜1,250単位が一番多く28.0%、次いで851〜1,000単位の26.1%、1,251〜1,500単位の20.5%と続いている。 | 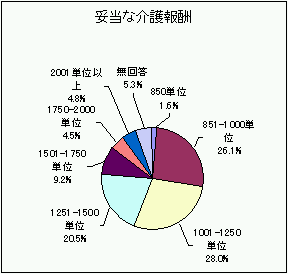 |
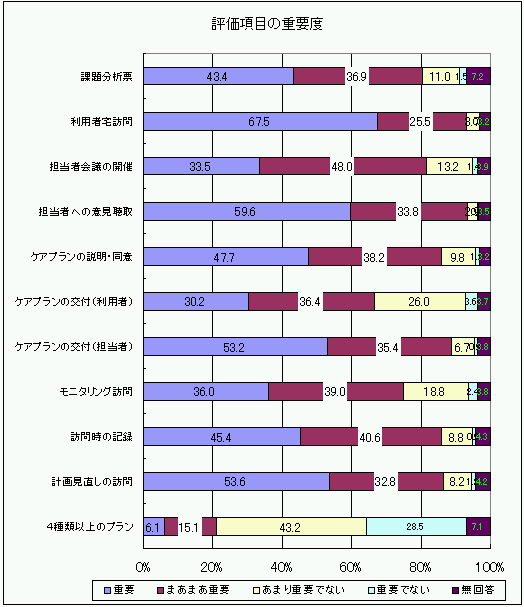
| (1) | 課題分析票の作成 課題分析票は80.3%が重要であると考え、12.5%が重要でないと考えている。 |
| (2) | ご利用者宅への訪問 利用者宅への訪問は93.0%が重要であると考え、3.8%が重要でないと考えている。 |
| (3) | サービス担当者会議の開催 担当者会議の開催は81.5%が重要であると考え、14.6%が重要でないと考えている。 |
| (4) | サービス担当者への意見聴取 担当者への意見聴取は93.4%が重要であると考え、3.1%が重要でないと考えている。 |
| (5) | ご利用者へのケアプランの説明・同意 ケアプランの説明・同意は85.9%が重要であると考え、10.9%が重要でないと考えている。 |
| (6) | ご利用者へのケアプランの交付 ケアプランの交付(利用者)は66.6%が重要であると考え、29.6%が重要でないと考えている。 |
| (7) | サービス担当者へのケアプランの交付 ケアプランの交付(担当者)は88.6%が重要であると考え、7.6%が重要でないと考えている。 |
| (8) | 月1回のモニタリング訪問 モニタリング訪問は75.0%が重要であると考え、21.2%が重要でないと考えている。 |
| (9) | モニタリング訪問時の記録 訪問時の記録は86.0%が重要であると考え、9.7%が重要でないと考えている。 |
| (10) | 計画見直しのための訪問 計画見直しの訪問は86.4%が重要であると考え、9.4%が重要でないと考えている。 |
| (11) | 4種類以上のサービスを盛り込んだケアプラン 4種類以上のプランは21.2%が重要であると考え、71.7%が重要でないと考えている。 |
| わずか3%ではあるが、不正請求につながる不適切な指示があった。 | 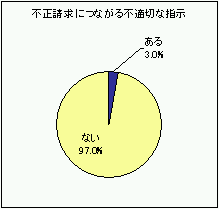 |
| わずか7.7%ではあるが、公平・中立に反するような不適切な指示があった。 | 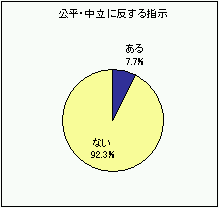 |
| 管理者は、54.4%の方が介護支援専門員の資格を持っているが、介護支援専門員の資格を持っていない管理者も45.6%いる。 | 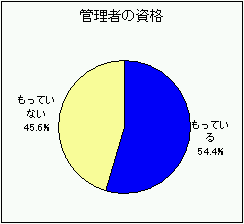 |
| 事業所の独立については、47.5%の人が「独立したほうが良い」と考えており、「独立しなくても良い」と考えている人は、21.6%であった。 事業所が自立すべきとの意見は、多くの介護支援専門員から意見として寄せられた。 |
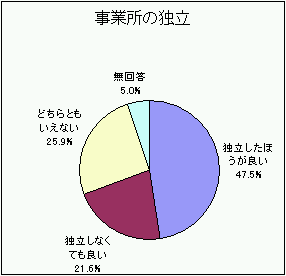 |
| 介護支援専門員としてのやりがいについては、17.9%の人が「非常に感じている」と回答し、43.7%の人が「どちらかといえば感じている」と回答しており、あわせて60.6%の介護支援専門員が、やりがいを感じている。 | 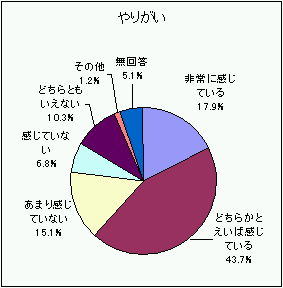 |
| 制度のことで悩んでいる人が最も多く35.4%で3分の1強、次いで利用者のことで悩んでいる人が18.8%となっている。 | 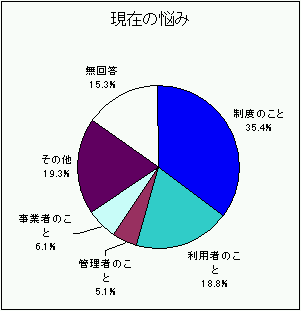 |