表1 地域診断に用いる既存資料等
|
| ( | 3)市町村、保健所、精神保健福祉センター、本庁のうつ対策における役割 市町村、保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉業務については、これまで厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「保健所及び市町村における精神保健福祉業務について(平成12年3月31日 障第251号)」及び厚生省保健医療局長通知「精神保健福祉センター運営要領について」(平成8年1月19日健医発第57号)に基づき行われているところであるが、うつ対策についても精神保健福祉業務の一環として取り組まれるものである。特に、保健所のあり方については、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成6年12月厚生省告示第374号)において、保健所は精神保健について専門的かつ技術的業務の推進を行うこと、市町村の求めに応じて専門的な立場から技術的助言等の援助に努めることが定められている。このように進められる精神保健福祉活動の中で、うつ対策に関する特徴的な活動を具体的にあげることができる。 市町村は、直接住民に接し、さまざまな保健福祉事業を行っているため、地域特性を踏まえたうつ対策を行うことができる。また、基本健康診査や乳幼児健康診査、各種の教室事業、健康相談、訪問指導などの日々の活動を通した対策を実施しやすく、さまざまな福祉事業や公民館等の社会教育活動、教育委員会とも連携しやすい。 保健所は、地域精神保健福祉業務の中心的な行政機関として、うつ対策をすすめる上で重要な役割を果たすことが期待されている。地域の実態把握、地域診断を行い、それに基づき地域の実情に応じた、普及啓発活動、相談事業、訪問指導等を行うことができる。また、市町村への専門的な立場から技術的助言等の援助も重要な役割の一つである。また、保健所の働きかけで所管の市町村同士が連絡会議を持つなどして情報交換を行うことは、うつ対策を評価し、推進する上で有用である。 精神保健福祉センターは、都道府県を単位とした実態把握や啓発活動を行うことができる。また、専門的立場から保健所や市町村等に対し、技術指導、技術援助を行うことが期待される。さらに、保健医療従事者等に対し、うつ病に関する理解を深め、対応技術を向上させることを目的とした研修を実施することも重要な役割である。 本庁は、全県規模の対策検討(協議)会を設置し、健康日本21の地方計画と整合性を保ちつつ、都道府県としての方向性について検討する。特に、都道府県内のマスメディア等と連携し、うつの実態やうつ病についての正しい知識や対処方法等について広域的に情報発信したり、予防キャンペーンを行うことなどが期待される。うつ病に関心を持つNPOや民間団体等への協力要請の働きかけも期待される。また、診断、治療等の医療の受け皿づくりの充実のため、地域の医師会等の医療関係機関や都道府県内外の大学等との連携など、広域的に対応できる。うつ対策の概要を表2に示す。 |
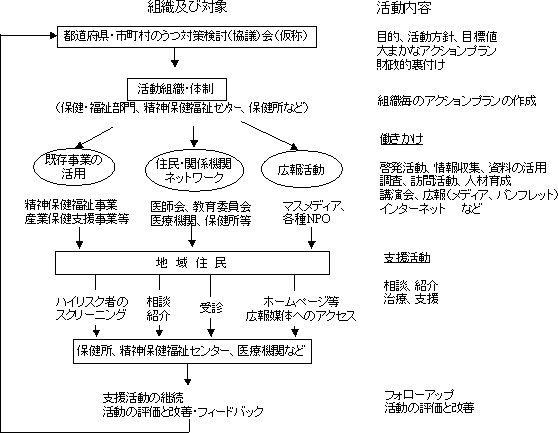
| (4 | )関係部局・機関等との連携方策 これまで述べてきたように、うつ対策を推進するにあたっては、関係部局との連携のもと既存事業を活用し、関係機関とのネットワークを構築することが重要である。特に、市町村、保健所間連携は地域精神保健推進の観点から積極的に進めていきたい。 地域におけるうつ対策の関係部局・機関が、継続的に情報を共有し、共通の目標に向けてそれぞれの役割を果たすためには、「うつ対策検討(協議)会(仮称)」を定期的に開催することが有効である。地域におけるうつ対策ネットワークについて表3に示す。 |
| 中心となる組織 | 既存事業の中でのうつ対策 | 方策の検討する組織、働きかけの主体となる組織、協働する組織 など | 協力を依頼する組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<総合相談窓口>
<母子保健>
<老人保健>
<老人福祉>
<精神保健福祉>
|
<方策の検討>
<ハイリスクグループへのアプローチ>
<うつ病経験者の参加>
<事業場へのアプローチ>
|
|