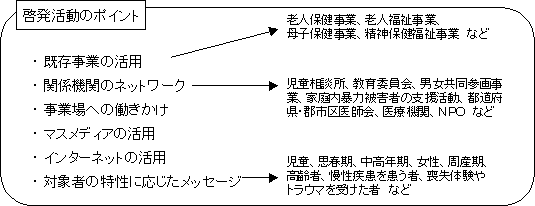| 児童 |
: |
3歳児や就学前検診などがある。小児うつ病をはじめとして、この年代でも薬物療法の対象になる精神疾患があることが以前よりは周知されてきている。保護者の同意を前提とした、児童相談所や、スクールカウンセラー、養護教諭など教育関係機関との連携は不可欠である。 |
| 思春期 |
: |
学校保健との連携が重要である。不登校やいわゆる「ひきこもり」、あるいは拒食や過食など思春期特有な行動がうつ病の表現型である場合も多く、精神科受診が必要な場合があることを、本人や家族・学校関係者に理解してもらうことが重要である。 |
| 中高年 |
期 |
:産業保健との連携が重要である。失業や多額な負債など経済的な問題が自殺の危険因子であることが知られている。出社拒否やアルコール依存などはうつ病の表現型でもある。また、定年後は日常の生活で孤独感を募らせる時期でもある。初老期うつ病あるいは更年期うつ病と診断されることもあり、注意を要する。治療に専念できるよう環境調整を行うことが重要である。 |
| 女性 |
: |
一般にうつ病は女性に多いといわれている。周産期、とりわけ出産後は抑うつ状態になりやすく、育児に対する自信のなさで表現されることがある。また、更年期のうつ病の症状を更年期の一般的な症状として、あるいは単なる過労として見過ごす可能性もあり、うつ病が身体症状に覆われている場合があることも留意しなければならない。 |
| 周産期 |
: |
周産期は女性にとって期待と不安が交錯する時期である。心の健康状態の把握と対応はもとより、家族の理解と協力をはじめとする安心して妊娠・出産を迎えるための環境整備が重要である。 |
| 高齢者 |
: |
高齢になって喪失体験を数多く体験し、慢性疾患に罹患している可能性も高く、また、身体的衰えのみならず、家族や地域からの孤立、経済的不安なども増大する場合があり、抑うつ状態になる可能性もある。高齢者ほど自殺死亡率は高い。また、長期間高齢者を介護している家族も、燃えつき状態になり、単に疲れたり、気力が出なくなっているだけではなく、抑うつ状態になる場合もある。各種老人保健事業や介護保険による様々なサービスとの連携が重要である。また、福祉関係者は家族とともに本人と接する機会も多いため、福祉関係者に対する研修・教育は有用である。 |
| 慢性疾 |
患 |
:慢性疾患や障害にうつ病を合併することがあり、特に悪性腫瘍への合併が知られている。落ち込むのは当然であると思われ、うつ病を見落とされる可能性がある。多くは治療を継続している人たちであるため、うつ病の早期発見・早期治療は医療機関に期待されるところが大きい。患者会などのセルフヘルプグループやボランティアグループの理解と協力も重要である。
一方、長期にわたる介護生活はうつ病の危険因子であり、介護者に対してもうつ病への基本的な対処のほか、ストレスを軽減するため、ホームヘルプ事業や施設の短期入所、デイサービス、入浴サービスなどの情報を提供することも重要である。 |
| 離婚、 |
死 |
別、その他の喪失体験、トラウマとなるような出来事(虐待、暴力など):喪失体験やトラウマとなるような出来事はうつ病の重要な危険因子である。これらの体験から何週間も憂うつな気分が続くのは、誰にもありそうなことではあるが、なんとなく寂しくなって涙もろくなる、興味関心がわかない、疲れやすい、気力が出なくなっている状態が長く続く時、うつ病の可能性もある。 |