<うつ病対策の基本方策>
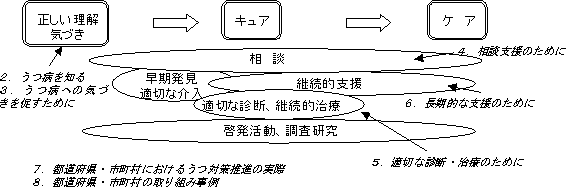
本マニュアルで重要視しているのは、正しい理解・気づき、キュアとケアという考え方。
うつ病は個人を強く苦しめるのはもちろんのこと、社会にも大きな影響を及ぼす疾患で、こうした苦しみを早く解決するためには早期発見、早期治療が重要なことは言うまでもない。これがキュアという考え方。しかし、簡単に治らない場合や再発を繰り返す場合も少なくなく、そうした場合には、長期にわたってその人をケアすることが必要となる。
|
| 本ガイドラインの構成 <うつ病対策の基本方策> 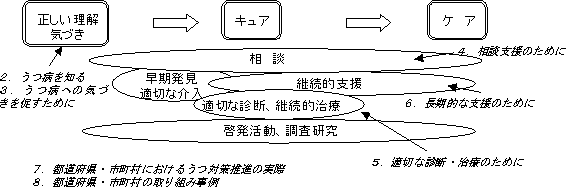 本マニュアルで重要視しているのは、正しい理解・気づき、キュアとケアという考え方。 うつ病は個人を強く苦しめるのはもちろんのこと、社会にも大きな影響を及ぼす疾患で、こうした苦しみを早く解決するためには早期発見、早期治療が重要なことは言うまでもない。これがキュアという考え方。しかし、簡単に治らない場合や再発を繰り返す場合も少なくなく、そうした場合には、長期にわたってその人をケアすることが必要となる。 |