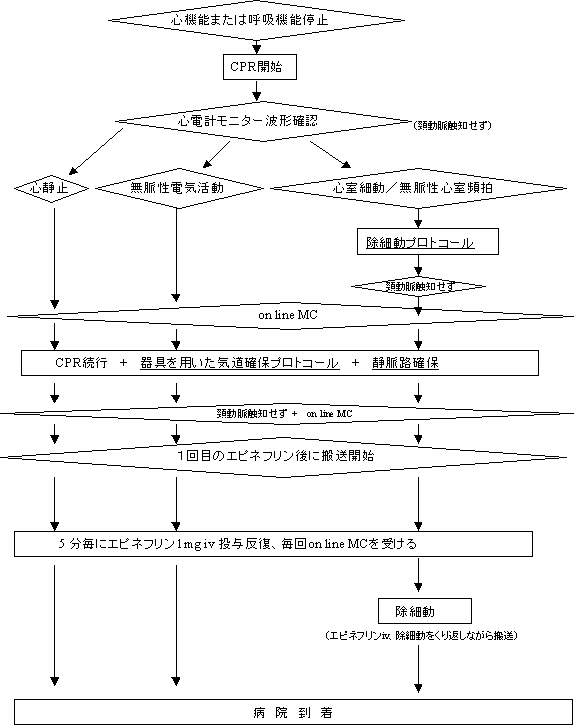
薬剤投与を行うとした場合に必要な救急救命士既資格者に対する追加講習 (エピネフリン1剤使用の場合) 1単位=50分 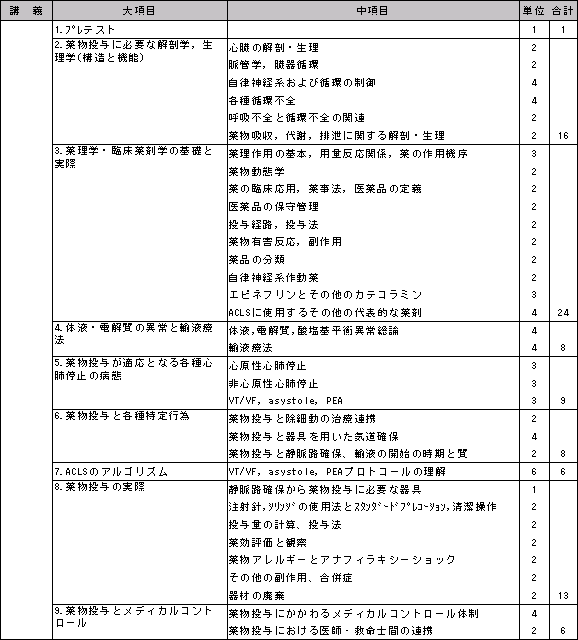 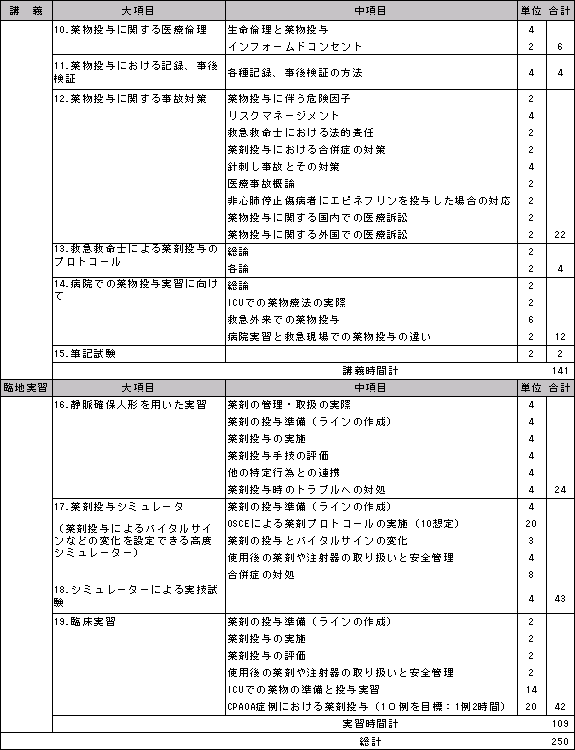 |
エピネフリン、アトロピン、リドカインの3剤使用の場合の業務プロトコール
| 研究班資料2 |
【対象者】
心肺機能停止状態の症例(心停止または呼吸停止のもの)
【適応と考えられるケース】
| 1. | 目撃者のある8歳以上の心肺機能停止症例のうち、心電計モニター波形で (1) 心静止 (2) 無脈性電気活動 の何れかを呈し、頸動脈で脈拍を触知しない例 |
| 2. | 8歳以上の心肺機能停止症例のうち、心電計モニター波形で心室細動/無脈性心室頻拍を呈し、頸動脈で脈拍を触知しない例(目撃者の有無は問わない) |
【禁忌となるケース】
特になし
【薬剤投与を実施する必要はないと考えられるケース】
| 1. | 明らかに発症から20分以上経過していると考えられる心肺機能停止症例のうち、心電計モニター波形で心静止または無脈性電気活動を呈する症例では薬剤投与を実施しても予後の改善が期待できないため、薬剤投与を実施する必要はないと考えられる |
| 2. | 目撃者のいない心肺機能停止症例のうち、心電計モニター波形で心静止または無脈性電気活動を呈する症例では薬剤投与を実施しても予後の改善が期待できないため、薬剤投与を実施する必要はないと考えられる |
【プロトコール】
| 1. | 対象として適合した場合、on line medical controlを受ける |
| 2. | 処置を行うにあたっては、スタンダードプレコーション、すなわち、手洗い、手袋の着用、その他の防護具の着用、針刺し事故対策に努める |
| 3. | 薬剤投与のために静脈路を確保する場合、それに要する時間は1回90秒以内として、試行は原則1回とし、3回以上を禁ずる |
| 4. | 静脈路の確保方法は、特定行為としての静脈路確保方法に準ずる |
| 5. | 投与する薬剤はエピネフリンに限定する |
| 6. | エピネフリンは1mg/1mlに調整したプレフィルドシリンジのものとする |
| 7. | 薬剤投与経路は経静脈に限定し、気管内は禁ずる |
| 8. | エピネフリンを静脈注射した際は、その都度乳酸リンゲル液20mlで後押しするなどし、さらに薬剤を投与した四肢を10〜20秒挙上する |
| 9. | エピネフリンは静脈路確保後すぐに1mgを投与し、その後に患者搬送を開始する |
| 10. | エピネフリン投与後は1分後に効果を確認し、効果がない場合はエピネフリン1mgの投与を前回投与後から5分毎に病院到着まで繰り返してもよい |
| 11. | エピネフリンを再投与する際にも毎回使用前にon line medical controlを受ける |
| 12. | エピネフリンの投与量は年齢、体重にかかわらず1回1mgとする |
| 13. | 薬剤を投与した際には、毎回静脈路を確保した血管を入念に観察し、薬液の漏れを意味する腫脹などがないかどうかを確認する |
| 14. | 静脈路を確保して薬剤を静脈注射した際に薬液の漏れがあった場合は、新たな静脈路の確保は禁ずる |
| 15. | 薬剤投与を行う場合は、原則的に指示を出す医師と継続的に会話ができる状態を保持する |
| 16. | 薬剤投与例は地域メディカルコントロール協議会において事後検証を受けるものとする |
【合併症】
| 1. | 自己心拍再開後の血圧上昇と心拍数増加が心筋酸素需要量増大を招き、心筋虚血、狭心症、急性心筋梗塞を引き起こす可能性がある |
| 2. | 自己心拍再開後に、陽性変時作用による頻脈性不整脈を引き起こす可能性がある |
| 3. | 大量投与は蘇生後神経学的予後を改善せず、蘇生後心筋障害を引き起こす可能性がある |
| 4. | 静脈路確保が不確実な場合、薬液が血管外に漏れると局所の壊死を引き起こす可能性がある |
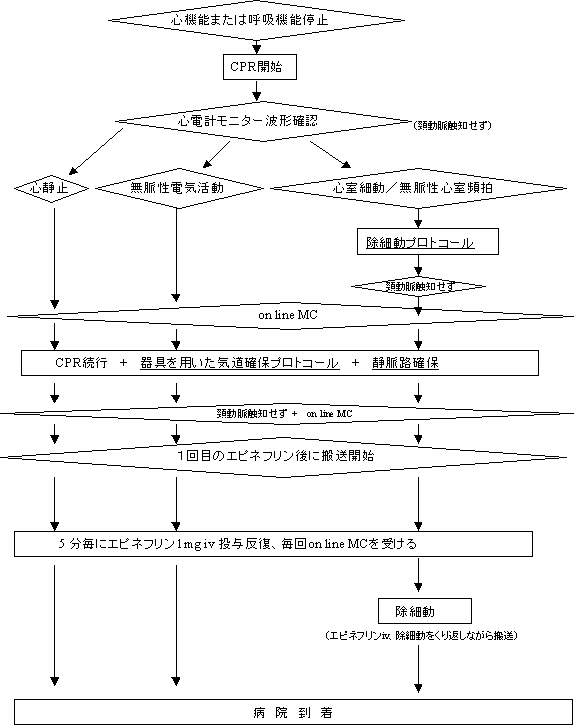
薬剤投与を行うとした場合に必要な救急救命士既資格者に対する追加講習 (エピネフリン1剤使用の場合) 1単位=50分 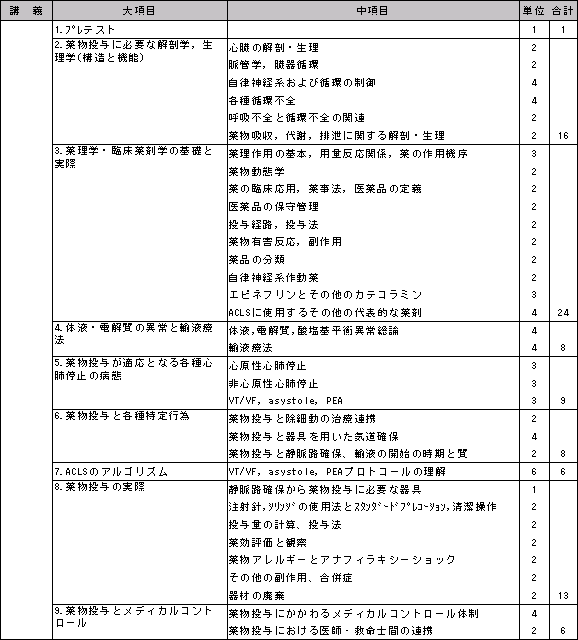 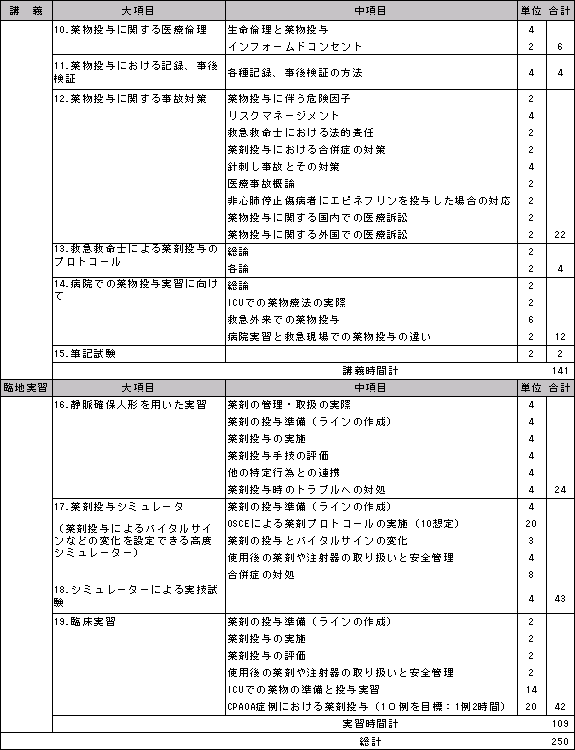 |
エピネフリン、アトロピン、リドカインの3剤使用の場合の業務プロトコール
【対象者】
心肺機能停止状態の症例(心停止または呼吸停止のもの)
【適応と考えられるケース】
【エピネフリン】| 1. | 目撃者のある8歳以上の心肺機能停止症例のうち、心電計モニター波形で (1) 心静止 (2) 無脈性電気活動 の何れかを呈し、頸動脈で脈拍を触知しない例 |
| 2. | 8歳以上の心肺機能停止症例のうち、心電計モニター波形で心室細動/無脈性心室頻拍を呈し、頸動脈で脈拍を触知しない例(目撃者の有無は問わない) |
【禁忌となるケース】
【エピネフリン】| 1. | 頻脈(毎分100以上)を呈する無脈性電気活動 |
| 2. | 心電計モニター波形で心室細動/無脈性心室頻拍を呈する例 |
【薬剤投与を実施する必要はないと考えられるケース】
【エピネフリン】| 1. | 明らかに発症から20分以上経過していると考えられる心肺機能停止症例のうち、心電計モニター波形で心静止または無脈性電気活動を呈する症例では薬剤投与を実施しても予後の改善が期待できないため、薬剤投与を実施する必要はないと考えられる |
| 2. | 目撃者のいない心肺機能停止症例のうち、心電計モニター波形で心静止または無脈性電気活動を呈する症例では薬剤投与を実施しても予後の改善が期待できないため、薬剤投与を実施する必要はないと考えられる |
| 1. | 心静止 |
| 2. | 無脈性電気活動 |
【プロトコール】
| 1. | 対象として適合した場合、on line medical controlを受ける |
| 2. | 処置を行うにあたっては、スタンダードプレコーション、すなわち、手洗い、手袋の着用、その他の防護具の着用、針刺し事故対策に努める |
| 3. | 薬剤投与のために静脈路を確保する場合、それに要する時間は1回90秒以内として、試行は原則1回とし、3回以上を禁ずる |
| 4. | 静脈路の確保方法は、特定行為としての静脈路確保方法に準ずる |
| 5. | 投与する薬剤はエピネフリン、硫酸アトロピン、リドカインの3剤に限定する |
| 6. | エピネフリンは1mg/1mlに調整したプレフィルドシリンジのものとする |
| 7. | 硫酸アトロピンは0.5mg/1mlに調整したプレフィルドシリンジのものとする |
| 8. | リドカインは100mg/5mlに調整したプレフィルドシリンジのものとする |
| 9. | 薬剤の投与経路は経静脈に限定し、気管内は禁ずる |
| 10. | 薬剤を静脈注射した際は、その都度乳酸リンゲル液20mlで後押しするなどし、さらに薬剤を投与した四肢を10〜20秒挙上する |
| 11. | 薬剤を再投与する際にも毎回使用前にon line medical controlを受ける |
| 12. | エピネフリンは静脈路確保後すぐに1mgを投与し、その後に患者搬送を開始する |
| 13. | エピネフリンの投与量は、年齢、体重にかかわらず1回1mgとする |
| 14. | 硫酸アトロピンの投与量は、年齢、体重にかかわらず1回1mgとする |
| 15. | リドカインの投与量は体重が約30kg未満の例では1回40mg、体重が約30kg以上の例では1回50mgとする |
| 16. | エピネフリン投与後は1分後に効果を確認し、効果がない場合はエピネフリン1mgの投与を前回投与から5分毎に病院到着まで繰り返してもよい |
| 17. | 心静止例もしくは徐脈性無脈性電気活動例では、1回目のエピネフリン投与1分後に効果を確認し、頸動脈で脈拍を触知しない場合は硫酸アトロピン1mgを使用する |
| 18. | 硫酸アトロピン投与後は1分後に効果を確認し、効果がない場合は硫酸アトロピン1mgを前回投与から5分後に投与してもよい.但し投与回数は2回までとする |
| 19. | リドカイン投与後は1分後に再度電気的除細動を行うが、除細動できない場合は、前回投与から5分後に再度同量を投与してもよい.但し投与回数は2回までとする |
| 20. | 薬剤を投与した際には、毎回静脈路を確保した血管を入念に観察し、薬液の漏れを意味する腫脹などがないかどうかを確認する |
| 21. | 静脈路を確保して薬剤を静脈注射した際に薬液の漏れがあった場合は、新たな静脈路の確保は禁ずる |
| 22. | 薬剤投与を行う場合は、原則的に指示を出す医師と継続的に会話ができる状態を保持する |
| 23. | 薬剤投与例は地域メディカルコントロール協議会において事後検証を受けるものとする |
【合併症】
【エピネフリン】| 1. | 自己心拍再開後の血圧上昇と心拍数増加が心筋酸素需要量増大を招き、心筋虚血、狭心症、急性心筋梗塞を引き起こす可能性がある |
| 2. | 自己心拍再開後に、陽性変時作用による頻脈性不整脈を引き起こす可能性がある |
| 3. | 大量投与は蘇生後神経学的予後を改善せず、蘇生後心筋障害を引き起こす可能性がある |
| 4. | 輸液路確保が不確実な場合、薬液が血管外に漏れると局所の壊死を引き起こす可能性がある |
| 1. | 薬理作用によって瞳孔が散大してしまう為、瞳孔による神経学的機能の把握が困難となる |
| 2. | 徐脈(毎分60以下)ではない無脈性電気活動などに使用すると、迷走神経抑制による脈拍増加作用により、自己心拍再開後に頻脈性不整脈を引き起こす可能性がある |
| 3. | 自己心拍再開後の心拍数増加が心筋酸素需要量増大により心筋虚血、狭心症、急性心筋梗塞を引き起こす可能性がある |
| 4. | 既往に緑内障を持つ患者では、蘇生後に緑内障が悪化する可能性がある |
| 1. | 投与量が多いと蘇生そのものが困難となることがある |
| 2. | 投与量が多いと中毒症状によるショック、痙攣が生じる可能性がある |
| 3. | 投与量が多いと蘇生後に不穏・せん妄などの精神症状が出現することがある |
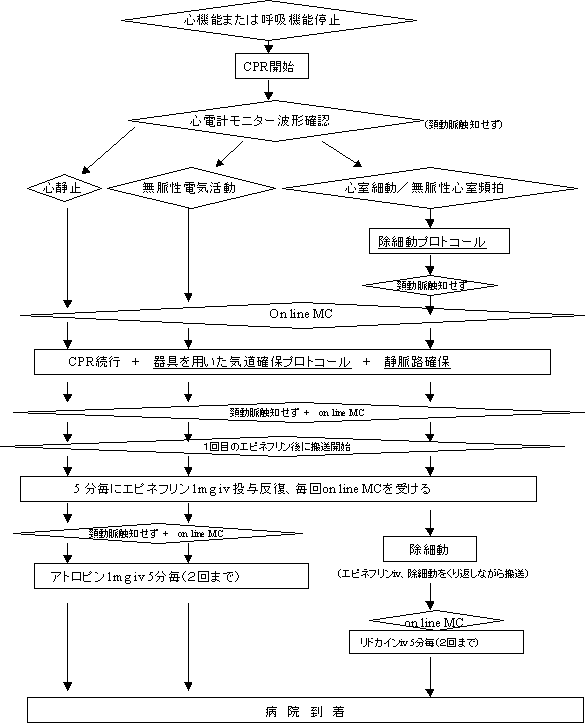
薬剤投与を行うとした場合に必要な救急救命士既資格者に対する追加講習 (エピネフリン、アトロピン、リドカインの3剤使用の場合) 1単位=50分 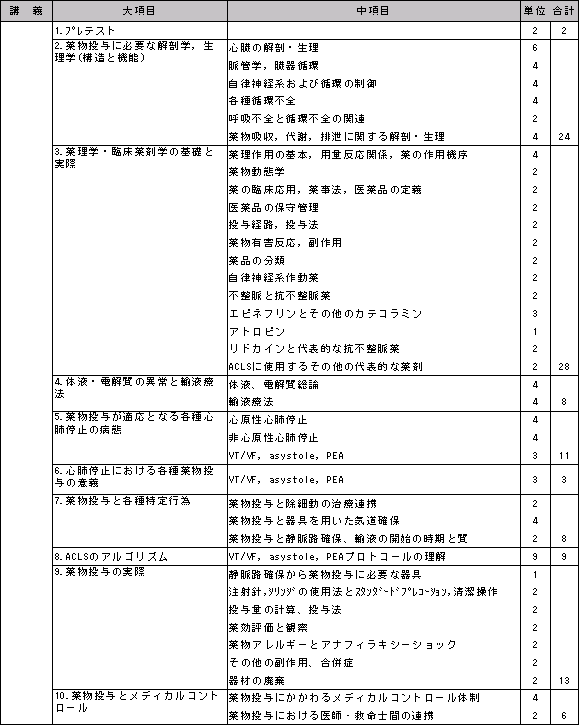 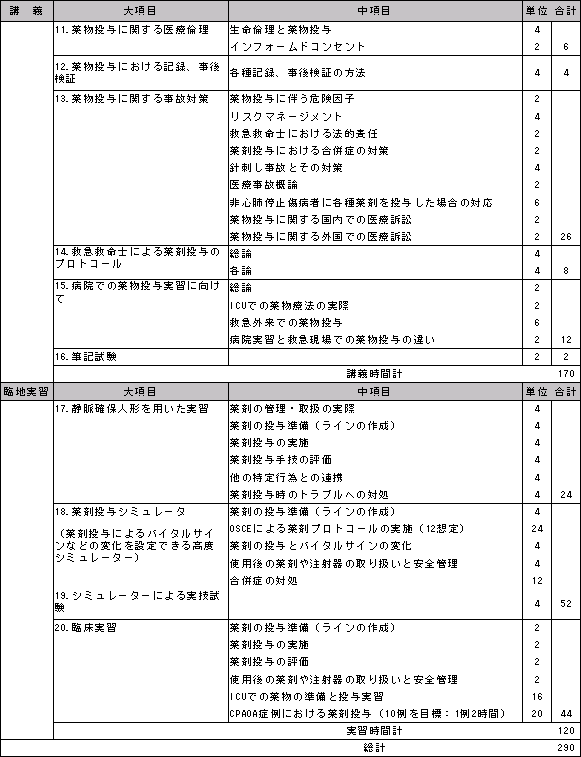 |
| 参考資料 |
本ワーキンググループは救急救命士が薬剤投与を行うとした場合の安全性について、プロトコール、手順、教育カリキュラムなどの観点から検証することを目的として組織された。
【結果】| 1. | 3剤投与について
| ||||||
| 2. | 1剤投与について
|