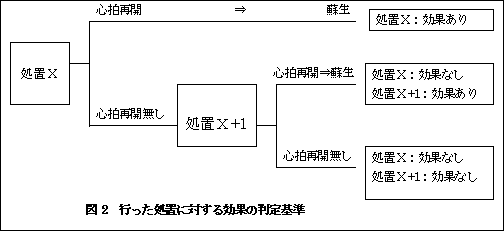
| 研究班資料1 |
I.【研究全体の目的】
救急救命士による心肺停止(CPA)患者に対するエピネフリンを中心とした薬剤投与の有効性について、ドクターカーにおいて研究、検証を行う。| 病院前にて、薬剤を用いた心肺蘇生術を行うことによって、院外CPA患者の蘇生率、1ヶ月生存率が向上するかどうかを検証した。 |
II.【はじめに】
これまでに院外CPA症例に対する薬剤使用の効果に関する研究がいくつか行われているが、薬剤使用の有無とその効果の関係を単純に比較することは誤った結論を導く可能性がある。例えば、なかなか心拍が再開しない重症例に対して多くの薬剤投与が行われる傾向があったとするなら、薬剤使用は救命率を下げる因子として認知される場合がある。逆に、心拍再開の見込みの無い症例に対しては薬剤投与を行わない傾向があった場合、薬剤使用の効果を過大に評価してしまう可能性がある。これらは、薬剤投与を行うか否かの段階で医学的判断が入ってしまい、そのことが分析においてバイアスとして作用してしまうためである。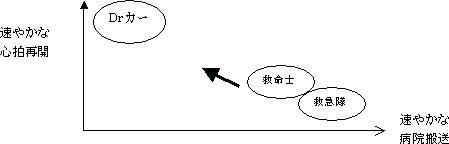
III.【研究の方法】
1.研究デザイン| ・ | エピネフリンを用いた病院前心肺蘇生術の有効性、エピネフリン、アトロピン、リドカインの3種薬剤を用いた病院前心肺蘇生術の有効性について検証した。 |
| ・ | 有効性の評価は、病院到着以前に薬剤を用いての心肺蘇生術が施行されたCPA症例(介入群)の蘇生率および予後と、病院到着以前には薬剤を用いない心肺蘇生術が施行されたCPA症例(対照群)の蘇生率および予後を比較することによって行った。すなわち、ドクターカーにて処置をうけた群が介入群となり、救急隊にて処置をうけた群が対照群となる。 |
| ・ | ドクターカーにおける処置は、三つの段階に分けられ、それぞれにおける処置を評価の対象とした。 |
| 調査地域名* | 面積 (km2) |
人口 (千人) |
高齢化率 (%) |
年間CPR 件数 |
対応機関 |
| 船橋市 | 85 | 550 | 12.6 | 303 | 船橋市立医療センター |
| 相模原市 | 90 | 605 | 11.1 | 303 | 相模原市消防本部 |
| 吹田・豊中・箕面市 | 119 | 860 | 13.8 | 425 | 千里救命センター |
| 堺・高石市 | 148 | 854 | 14.9 | 494 | 堺市高石市消防組合 |
| 中和広域 | 166 | 248 | 16 | 205 | 奈良県立医大 |
| 湖南広域 | 206 | 284 | 12 | 137 | 湖南広域行政組合消防本部 |
| 文京・台東区 | 21 | 332 | 19.4 | 662** | 日本医科大学救命センター |
| 品川区 | 23 | 317 | 17.2 | 529** | 東京消防庁 |
IV.【評価】
介入群、対照群ともに、病院到着後、心拍再開が確認されICU等に入院した症例を「蘇生例」とし評価を行った。蘇生例については、1ヵ月後の予後を追跡し、評価の指標とした。具体的には:| ・ | エピネフリンのみを用いた病院前心肺蘇生術(ドクターカーのPhaseI)による蘇生率および予後を対照群の蘇生率、予後と比較した。(図11) |
| ・ | エピネフリン・アトロピン・リドカインの3種薬剤のみを用いた病院前心肺蘇生術(ドクターカーのPhaseII)による蘇生率および予後を対照群の蘇生率、予後と比較した。 |
| ・ | ドクターカーにおいて行われたあらゆる医学的処置(ドクターカーのPhaseIII)による蘇生率および予後を対照群の蘇生率、予後と比較した。 |
| ・ | CPA症例を内因性CPA症例と外因性CPA症例に分けて上記の評価を行った。 |
| ・ | 心拍再開がなく、処置が次の段階に移行した場合、前の処置については、効果がなかったものと判断した(図2)。 |
| ・ | 統計学的解析は2×2分割表を用いたχ2検定にて行った。P<0.05を統計学的有意差ありと判断した。 |
| (1) | 病院前での心肺蘇生術の効果を、エピネフリン群、エピネフリン・アトロピン・リドカイン群の介入群と救急車の対照群とで比較した。 |
| (2) | 早期薬剤投与の効果を検証する目的で、介入群における薬剤投与後の蘇生率と対照群における病院搬送後の蘇生率を比較した。 |
V.【結果】
1.病院前CPA症例| 調査地域名 | 観察期間 | CPA症例数 | 目撃者有り (再掲) |
目撃者無し (再掲) |
不明 (再掲) |
| 船橋市 | 4〜10月 | 149 | 47 | 64 | 0 |
| 相模原市 | 4〜10月 | 282 | 74 | 208 | 0 |
| 吹田・豊中・箕面市 | 4〜10月 | 169 | 87 | 81 | 1 |
| 堺・高石市 | 4〜10月 | 224 | 99 | 125 | 0 |
| 中和広域 | 4〜10月 | 39 | 12 | 27 | 0 |
| 湖南広域 | 4〜10月 | 79 | 38 | 41 | 0 |
| 文京・台東区 | 4〜10月 | 44 | 16 | 28 | 0 |
| 品川区旗の台付近 | 4〜10月 | 205 | 61 | 111 | 33 |
| 介入群 162 | 対照群 272 | ||
| 平均年齢 | 67.3歳 | 69.4歳 | P=0.255 (t検定) |
| 性別 | 男100(61.7%) | 男169(62.1%) | |
| 女62(38.3%) | 女103(37.9%) | P=0.933 (χ2検定) | |
| 原因 (注) | 内因性120(74.1%) | 内因性222(81.6%) | |
| 外因性41(25.3%) | 外因性44(16.2%) | P=0.025 (χ2検定) | |
| 不明1(0.6%) | 不明6(2.2%) | (不明例除く) |
| (注)介入群において内因性CPA120例中蘇生例は49例(40.8%)であるのに対し、外因性CPA41例中蘇生例は11例(25.0%)と、内因性の方が蘇生率が高い。一方、対照群においては、内因性CPA222例中蘇生例は52例(23.4%)であるのに対し、外因性CPA44例中蘇生例は14例(31.8%)と、有意差はないものの、外因性CPAの方が成績が良い。 内因性と外因性で蘇生率の傾向が異なること、および介入群と対照群で内因性と外因性の割合が有意に異なることから、両者を併せて評価する場合は注意が必要である。 |
| 分析対象症例数 | 平均 | 標準偏差 | ||
| 覚知⇒現場到着 | ||||
| ドクターカー | 161例 | 14.1分 | 6.3分 | |
| 救急隊 | 272例 | 6.2分 | 2.7分 | |
| 覚知⇒病院到着 | ||||
| ドクターカー | 101例 | 46.4分 | 13.6分 | |
| 救急隊 | 270例 | 28.4分 | 8.7分 | |
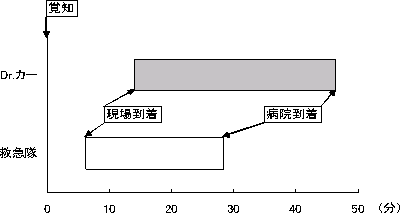 図3 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
3-(2).1ヶ月生存率の比較
表7-1 介入群のPhaseIまでの結果と対照群との比較
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
目撃者ありの全CPA症例を対象として、介入群の蘇生率と対照群における病院前の蘇生率を比較した。(薬剤を使わない心肺蘇生術の結果として、対照群における病院前での結果を用いた。)
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 目撃者ありの症例を対象として、介入群のエピネフリン投与以降の蘇生率と対照群における病院到着後の蘇生率を比較した。 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
4-(2).1ヶ月生存率の比較
表10-1 介入群のPhaseIまでの結果と対照群との比較
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
5-(2).1ヶ月生存率の比較
表13-2 介入群のPhaseIIIまでの結果と対照群との比較
|
|
||||||||||||||||||||||
| (目撃者あり症例) | |||||||||||||||||||||||
6.初期心電図波形と心拍再開
6-1.ドクターカー症例(内因性CPA120例)| VT/VF | PEA | Asystole | |
| エピネフリン投与前に心拍再開 | 10 (27.8%) | 2 ( 5.3%) | 1 ( 2.2%) |
| エピネフリン投与後心拍再開 | 6 (16.7%) | 9 (23.7%) | 5 (10.9%) |
| 三種薬剤にて心拍再開 | 4 (11.1%) | 3 ( 7.9%) | 3 ( 6.5%) |
| 他の処置・投薬にて心拍再開 | 0 ( 0.0%) | 1 ( 2.6%) | 5 (10.9%) |
| 心拍再開せず | 16 (44.4%) | 23 (60.5%) | 32 (69.9%) |
| 計 | 36 (100%) | 38 (100%) | 46 (100%) |
| 初期心電図波形と心拍再開 (ドクターカー症例) |
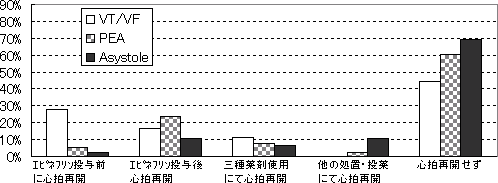 |
| VT/VF | PEA | Asystole | |
| 病院前に心拍再開 | 12 (25.0%) | 0 ( 0.0%) | 1 ( 0.9%) |
| 病院救急室にて心拍再開 | 10 (20.8%) | 15 (26.8%) | 14 (12.1%) |
| 心拍再開せず | 26 (54.2%) | 41 (73.2%) | 102 (87.9%) |
| 計 | 48 (100%) | 56 (100%) | 116 (100%) |
| 初期心電図波形と心拍再開 (救急隊症例) |
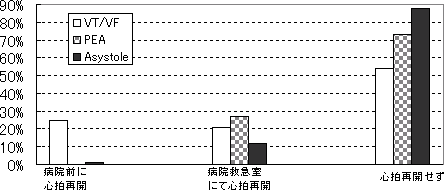 |
7.エピネフリン使用量と心拍再開率
7-1.エピネフリン使用量と心拍再開率の関係
|
||||||||||||||||||
| (サンプル:目撃者あり症例114例) |
| * | エピネフリン投与の有無および投与量と心拍再開率について直接の比較の際は、慎重な解釈を行うことが必要である。エピネフリン投与量が0の症例において心拍再開率が52.0%と表現されると、「約半数の例は薬剤がなくても心拍再開する。」と誤って解釈される危険性がある。実際には、エピネフリン非投与例の中には、エピネフリンを投与しなくても心拍再開した比較的軽症例とエピネフリンを投与しても心拍再開の見込みがないと判断され、投与が行われなかった最重症例が約半数ずつ混在している。同様に「エピネフリン投与量が多いほど、予後が悪くなる」という解釈もできない。 |
7-2.エピネフリン使用量とフエーズの関係
| 図6 |
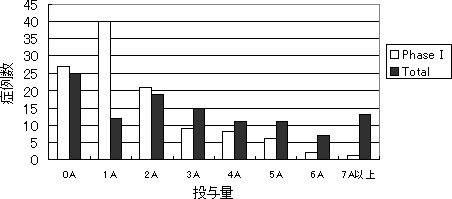 (サンプル:目撃者あり症例114例) |
VI.【結果のまとめ】
薬剤を用いた心肺蘇生術と蘇生率、1ヶ月予後の関係を表に示す。図7、図8は、目撃者ありのCPA症例全体を対象としている。図9、図10は、目撃者ありのCPA症例のうち内因性のものを対象としている。表中のA〜Gは以下のとおりである。| A.病院前: | 薬剤使用なし | 病院: | 薬剤使用なし(参考) | ||
| B.病院前: | 薬剤使用なし | 病院: | 薬剤使用あり(救急隊搬送) | ||
| C.病院前: | エピネフリンのみ使用 | 病院: | 薬剤使用なし | ||
| D.病院前: | エピネフリンのみ使用 | 病院: | 薬剤使用あり(病院前使用の効果)(注) | ||
| E.病院前: | エピネフリン、アトロピン、リドカインのみ使用 | 病院: | 薬剤使用なし | ||
| F.病院前: | エピネフリン、アトロピン、リドカインのみ使用 | 病院: | 薬剤使用あり(病院前使用の効果)(注) | ||
| G.病院前: | 薬剤使用あり | 病院: | 薬剤使用あり(ドクターカー搬送) | ||
| |||||
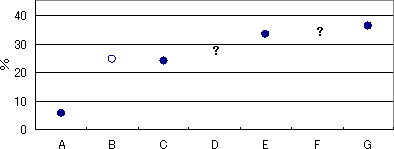
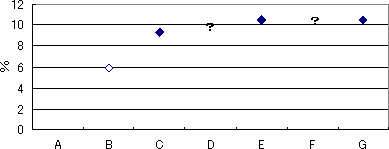
| A.病院前: | 薬剤使用なし | 病院: | 薬剤使用なし(参考) | ||
| B.病院前: | 薬剤使用なし | 病院: | 薬剤使用あり(救急隊搬送) | ||
| C.病院前: | エピネフリンのみ使用 | 病院: | 薬剤使用なし | ||
| D.病院前: | エピネフリンのみ使用 | 病院: | 薬剤使用あり(病院前使用の効果)(注) | ||
| E.病院前: | エピネフリン、アトロピン、リドカインのみ使用 | 病院: | 薬剤使用なし | ||
| F.病院前: | エピネフリン、アトロピン、リドカインのみ使用 | 病院: | 薬剤使用あり(病院前使用の効果)(注) | ||
| G.病院前: | 薬剤使用あり | 病院: | 薬剤使用あり(ドクターカー搬送) | ||
| |||||
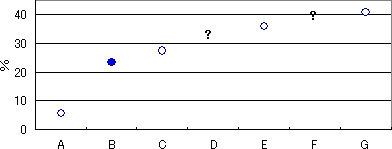
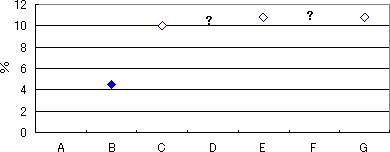
VII.【考察】
1.研究デザイン図11 介入群におけるPhaseI、PhaseII、PhaseIIIの考え方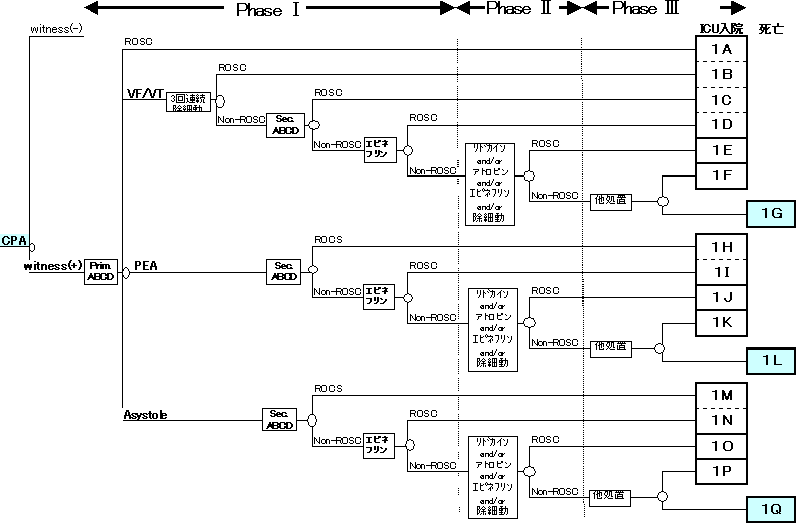 |
図12 対照群における解析の考え方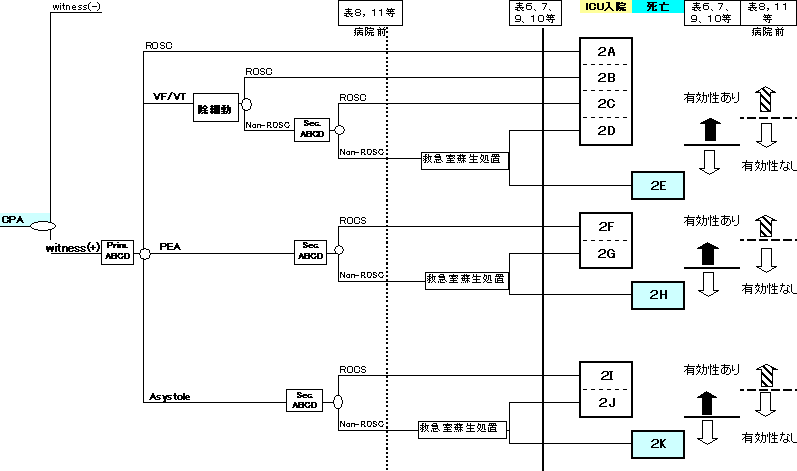 |
図13 表8-3及び表12における解析対象(介入群)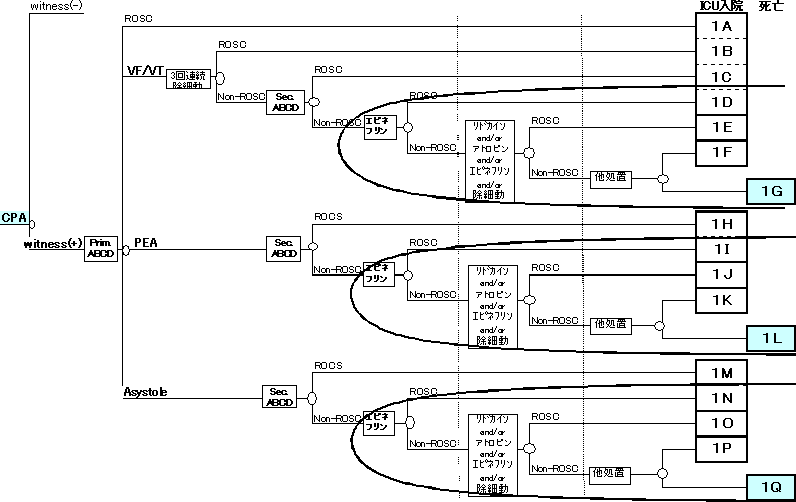 |
図14 表8-3及び表12における解析対象(対象群)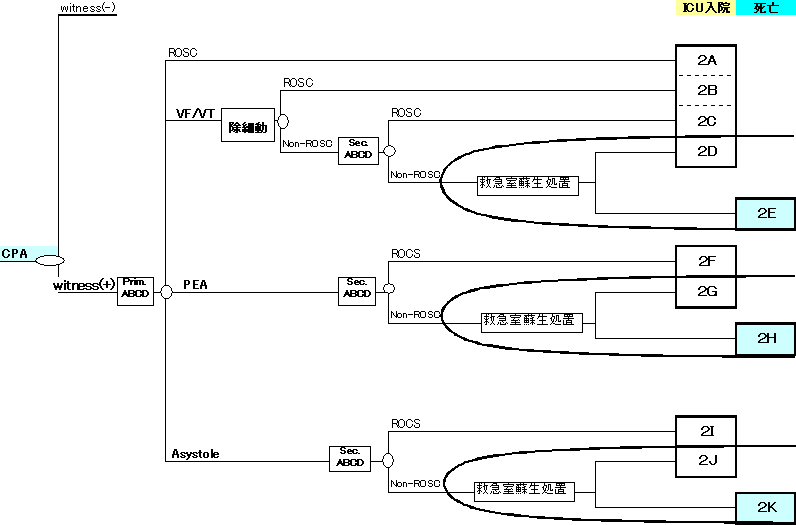 |