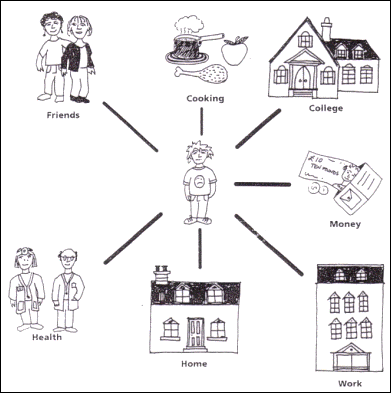
I 障害者からみたコミュニティケア
(英国介護者協会)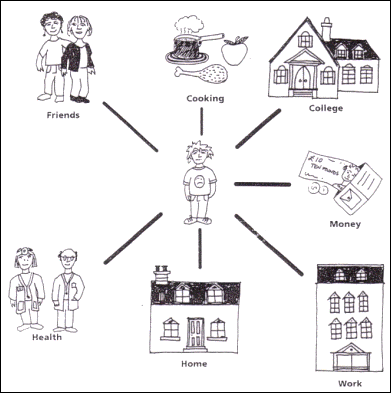 |
| 上図は、地域生活のイメージ(ロンドン・ピープルファースト資料より) |
障害者団体の資料は、それぞれ具体的な対象を示している。
(ロンドン・ピープルファースト)| ・ | 私たち(知的障害者本人) |
| ・ | 施設に入っている人 |
| ・ | 病院に生活している人 |
| ・ | デイセンターに通っている人 |
| ・ | 弱い立場にある人(自分自身のことをうまくやる経験もなく病院に暮らしてきた人や多くの異なる援助を必要としている人) |
| ・ | 全盲や弱視者を含む障害者 |
| ・ | 高齢者 |
| ・ | 他に特別なニーズをもつ人々 |
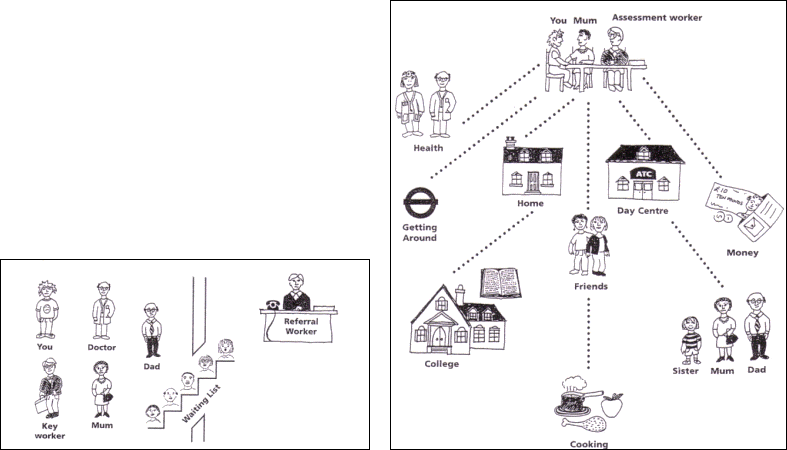 |
| 左図は、申請し待機リストに載るイメージ図。右図は、必要な援助を受けるためのアセスメントを行うイメージ図。(ロンドン・ピープルファースト資料より) |
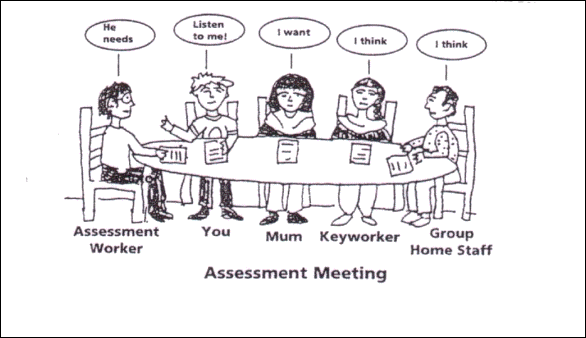 |
| 上図は、アセスメントのための会合。家族やワーカー等が勝手に自分のことを言うので、「私の言うこと、聞いて!」と発言している。(ロンドン・ピープルファースト資料より) |
(英国知的障害者協会)
アセスメントの結果をもとに個別のケアプランを作る。通常、ケアマネジャーの調整により、会合がもたれる。この会合は、障害者、介護者、その他関係者が出席する。
この会合には、障害者が中心に置かれるべきで、障害者のニーズと要望を協議する上できわめて重要である。この会合の結果は、ケアマネジャーが次の段階で確保するためのサービスを決定することにつながる。
この時間は非常に早く過ぎてしまうので、言いたいことをノートに書いておく。なぜなら、会合の中ですべてのことを思い出せないかもしれないから。そして、テープレコーダーにとっておくこともいい。
この会合で、多くの知的障害者や重度の言語障害者は、適切に話をする機会を持てないことがある。ケアマネジャーは、できるかぎり障害者を参加させるべきである。
(ロンドン・ピープルファースト)
ケアマネジャーは、障害者が望むことや必要な援助を実現するよう、障害者と共に働く人のことであると定義している。そして、人によっては援助に協力的であり、また人によってはその逆ということもある。
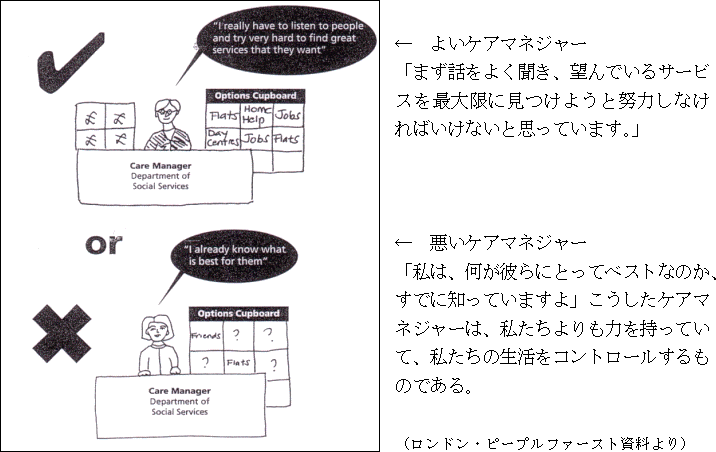 |
| 表1.社会サービスを受けた推計数 | (1999年4月1日〜2000年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2.ダイレクト・ペイメント受給者の推計数 | (1999年4月1日〜2000年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表3.アセスメントを受けた推計数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 表4.地域基盤のサービス(ホームヘルプ)を受けた推計数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表5.地域基盤のサービス(デイケア)を受けた推計数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表6.地域基盤のサービス(レスパイト)を受けた推計数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)イギリスはケアマネジメントを制度化、日本は手法
イギリスのコミュニティケアは、国民保健サービス及びコミュニティケア法1990(1993施行)に基づいて実施されてから、約10年が経過していることもあり、高齢者・障害者の各団体、その関係団体はケアマネジメントをいかに有効に利用するか、その問題点を当事者がいかに工夫し、必要なサービスを得るように行動するかということについて情報交換がされてきている。一方、我が国の場合は当事者団体へ情報が行き渡っていないこと、これまでの措置制度よりも後退することへの不安などから、ケアマネジメントに対する認識は低く、活用に関する情報交換には至っていない。
(2)イギリスは社会サービス部でワンストップ、日本は各相談事業として分化
相談窓口については、これまで身障・知的・精神とそれぞれの発展過程があるために専門職の間でも共通理解されていない部分があり、相談窓口でいかに受止めていくかという課題がある。イギリスの場合、高齢者及びあらゆる障害者がコミュニティケア法でカバーされるので、総合相談窓口は「ワンストップ」で受理するようになっている。
(3)アセスメントは本人・家族は別、日本は勘案事項として家族単位
アセスメントについては、利用者アセスメント・シートと介護者アセスメント・シートが別に用意されており、必要に応じてその両者を併せて書類が作られることになる。一方、我が国の場合、介護者は支援費については勘案事項整理票の中で「介護者の状況」としてまとめられ、ケアマネジメントの第一次アセスメント・シートにおいては、「家族の要望・希望する暮らし」のみで、介護者自身を認知しアセスメントする視点には乏しい。また、地域生活におけるリスクという観点では我が国の3障害各マニュアル類の中で積極的には取り上げていない。イギリスのケアマネジャー・マニュアルでは確認すべきリスクの項目、リスクへの対応、支援が示されている。
(4)ダイレクト・ペイメントは制度化、日本は未着手
支援費制度における、当事者主体、契約という新たなサービスのあり方から考えれば、ダイレクト・ペイメントの制度についても前向きに検討されるべきである。イギリスのコミュニティケアに関するテキストでは、障害の社会モデルと自立生活の考え方に基づき、ダイレクト・ペイメントの情報、アドボカシー、実践的なサポートを示している。我が国においても、今後、パーソナル・アシスタント制度などに関する検討を進め、その活用のノウハウを組み込み、さらに、セルフ・ケアマネジメントを促進していく必要がある。