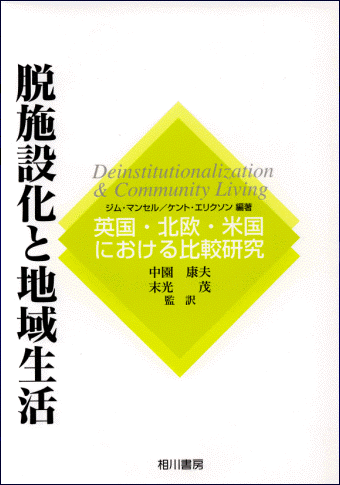
| 資料1 |
| 1. | はじめに |
| 2. | 北欧・英国・アメリカでの「脱施設化」の地域差 |
| 3. | 「知的障害病院」としての特徴 |
| 4. | ニューヨーク州での「脱施設化」の報告 |
| 5. | 脱施設化=施設閉鎖ではない(カスティラーニの主張) |
| 6. | ニューヨーク州の成功の要因 |
| 7. | 保健・医療の確保の重要性と対応 |
| 8. | グループホームの問題点 |
| 9. | 「生活支援プログラム」について |
| 10. | まとめ |
| (1) | 中園康夫、末光茂(監訳)「脱施設化と地域生活―北欧・英国・米国に おける比較較研究―」相川書房、2000年 |
| (2) | 中園康夫、末光茂「障害をもつ人にとっての生活の質―モデル・調査 研究および実践―」相川書房、2002年 |
| 1. | 「脱施設化」と「地域生活」に関するアメリカを中心とする歴史と現状報告 |
| 2. | 「検証」としていくつかの側面を報告 |
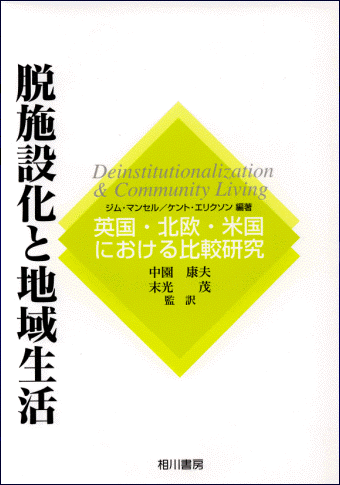
| 1. | 副題「北欧・英国・米国における比較研究」 |
| 2. | 「理念と実証的研究」 |
| 3. | 各国のなかの先駆的リーダー的報告 |
| 4. | 1996年時点のもの |
| ノルウェー (人口440万人) |
|
||
| スウェーデン (885万人) |
|||
| デンマーク (529万人) |
要医療と強度行 動障害限定 |
||
| フィンランド (513万人) |
中央施設の新設 ストップ |
||
| ウェールズ>イングランド> スコットランド>アイルランド |
| 人口:2億8,000万人(日本の2倍) 面積:936万k平方メートル(日本の25倍) 50州と1特別区 |
| 1964年 「公民権法」 | ||
|
||
| 1975年 「発達障害者援助・権利法」 | ||
| 1978年 「発達障害法」(DD Act) | ||
| 1990年 「障害をもつアメリカ人法」(ADA法) | ||
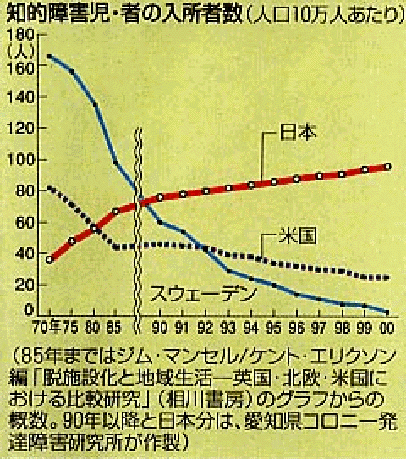
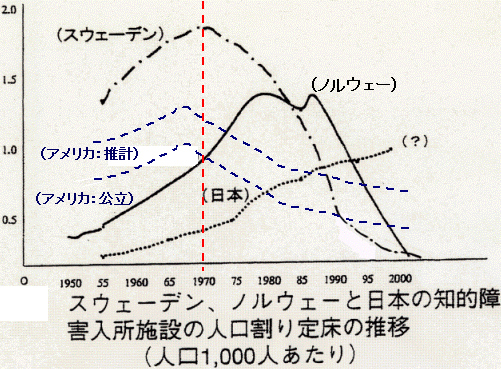
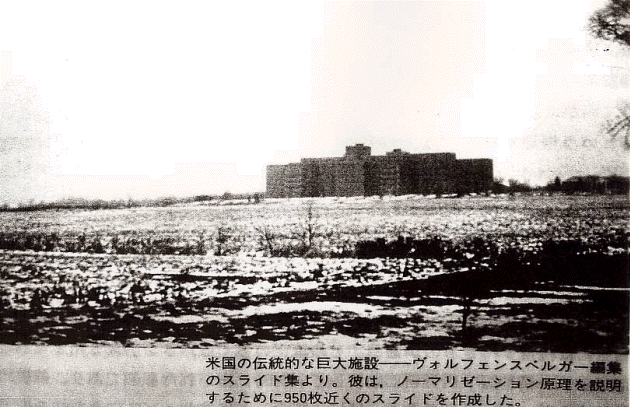
| 欧米 | 日本 |
| 「病院法」 医師・看護師中心 大規模・マンモス施設 |
「知的障害福祉法」「児童福祉法」 保育士・指導員中心 (嘱託医程度) 小・中規模施設 |
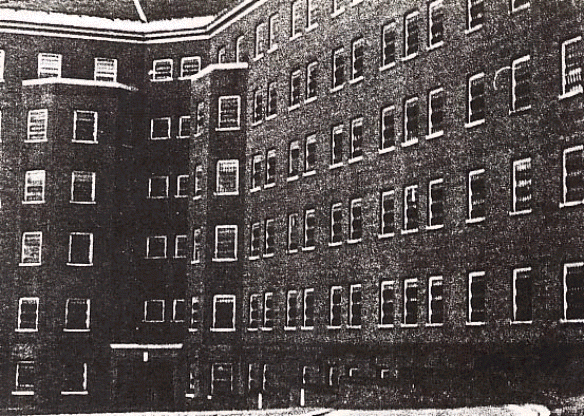
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
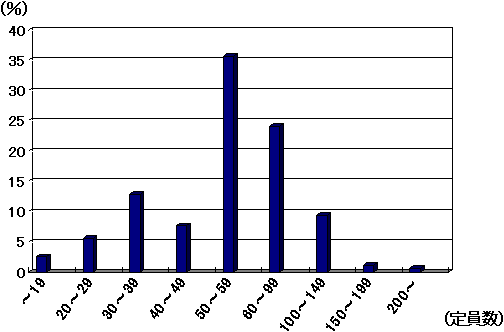
| −人口− | |
| ニューハンプシャー | (123万人) |
| ロードアイルランド | (105万人) |
| ヴァーモント | (61万人) |
| ↓ | |
| アラスカ | (63万人) |
| ハワイ | (121万人) |
| ニューメキシコ | (182万人) |
| ウェストヴァージニア | (180万人) |
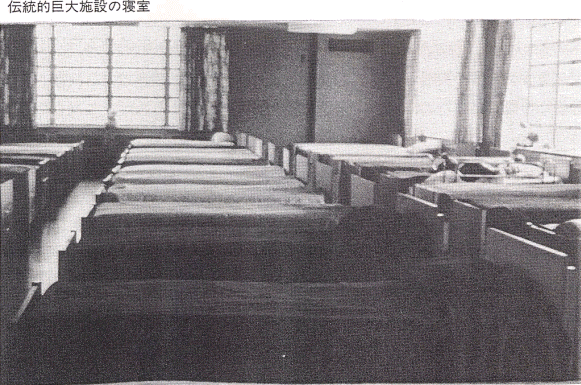
| 1. | 「脱施設化」イコール「施設閉鎖」ではない |
| 2. | 「施設」は過去の遺物ではなかった (機構、政治的、そして経済的な存在) |
| 3. | 「施設」は最後まで(全過程で) 非常に大きな力を発揮 |
| 4. | 「脱施設化」の経験からサービス体制の拡大再構築が政策主導でなされ得る |
(カステラニィ、第3章 p.58〜p.59) |
|
| 1. | 政策策定者の方針決定の不動性 |
| 2. | 運営管理者の力量と経験 |
| 3. | 「施設関係者」のサポート |
| 4. | 保健・医療サービスの確保 |
(第3章から学びたい点) |
|
| 州北部(田園地帯):グループホームや地域プログラムを歓迎し、州主導 ニューヨーク市:関心薄い、いったん反対運動が起こると複雑に。政治的影響力が弱い、民間主導 |
| 1. | 地域施設の建設(反対運動も) |
| 2. | 居住者の移転(親の理解とともに) |
| 3. | 州職員の転職先の確保 (職員雇用対策室→職員配置換え援助プログラム) |
| 4. | 地域内の保健・医療サービス体制の確立 (OMRDDがミニ病院経営も) |
| 5. | 施設の転用問題 (地元へ相当額の州資金の支出が見込まれること) |
| 6. | その他(政策間の統合、縦割り行政間の調整、 議員等の政治的圧力や危機管理等) |
(カステラニィ、第3章) |
|
| 1. | 代替家族 (フォスター・ファミリー) |
| 2. | 制度・財政の違い |
| 1. | イギリスでの調査:むしろサービス低下も |
| 2. | ノルウェーの3つの課題 |
| 3. | アメリカのグループホームでの「不審死」 |
| ↓ | |
| 真の「脱施設化」の結果としての グループホームをめざして |
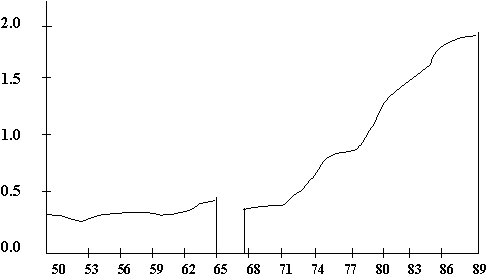
| 合計額 | 5.73 | (5位) |
| 施設サービス | 1.59 | (7位) |
| 地域サービス | 4.14 | (9位) |
| (ドル) | (全州) | |
−個人所得1,000ドル当たりの財政支出− |
||
| 食物による窒息 | 13例 | (40.6%) |
| 肺炎 | 5例 | (15.6%) |
| 転倒 | 4例 | (12.5%) |
| 外出時の交通事故 | 3例 | (9.4%) |
| 腸閉塞 | 2例 | (6.3%) |
| 溺死 | 2例 | (6.3%) |
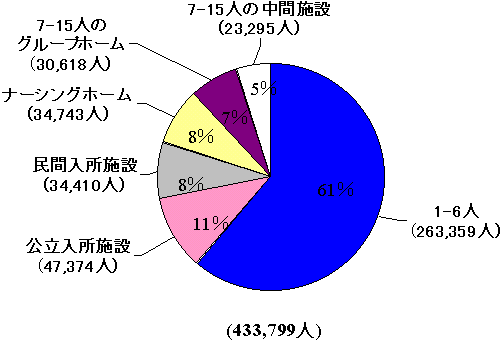
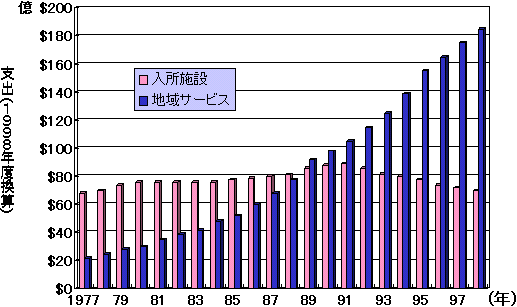
| 1. | ニューヨーク州:州立施設は 縮小したが現存 |
| 2. | テネシー州:アーリントン発達センター
(存続中) |
| 3. | その他裁判にて係争中 |
| 1. | 施設やプログラムよりも個人を基本に |
| 2. | 柔軟性のある支援やサービスを創造 |
| 3. | 個人の選択 |
| 4. | 地域社会とのつながり |
| 5. | 住まいと支援やサービスを分ける |
| │ │ │ |
| 1. | Person-Centered Planning(アメリカ) |
| 2. | Active Support(イギリス) |
願いは「未完成」
(J.W.オブライエン「障害者・家族・専門家の 共働」慶応義塾大学出版会) |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 知的障害者への財政支出状況 (アメリカ) |
| 合計 (ドル) |
施設サービス (ドル) |
地域サービス (ドル) |
|
| ’77 | 2.26 | 1.69 | 0.57 |
| ↓ | ↓ | ↓ | |
| ’98 | 3.69 | 1.03 | 2.66 |
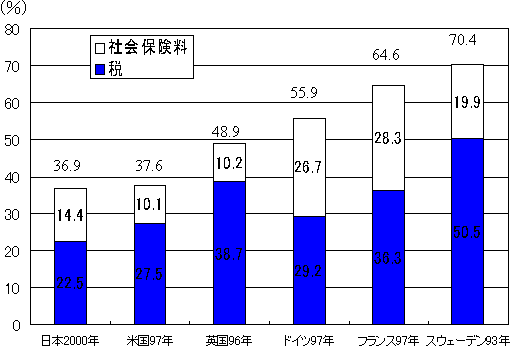
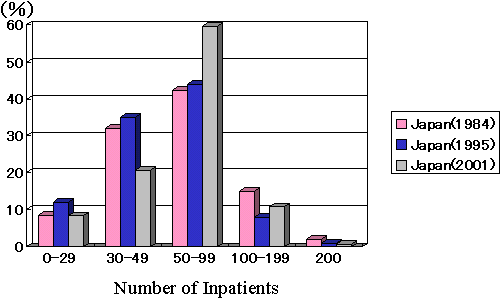
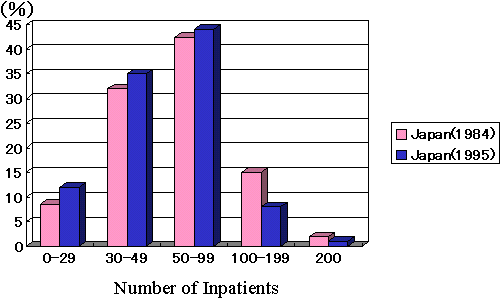
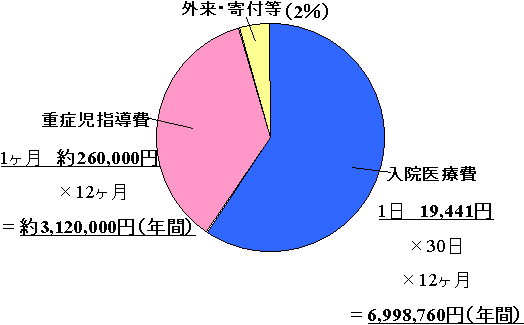
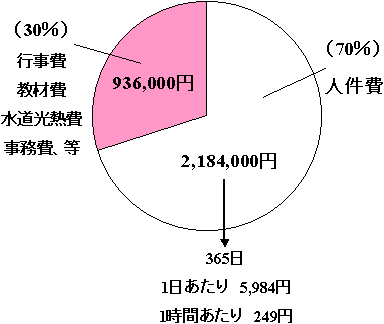
| 末光氏資料3 | (2〜5ページ(PDF:420KB)、6〜9ページ(PDF:412KB)、 10〜12ページ(PDF:250KB)、13〜15ページ(PDF:276KB)) |