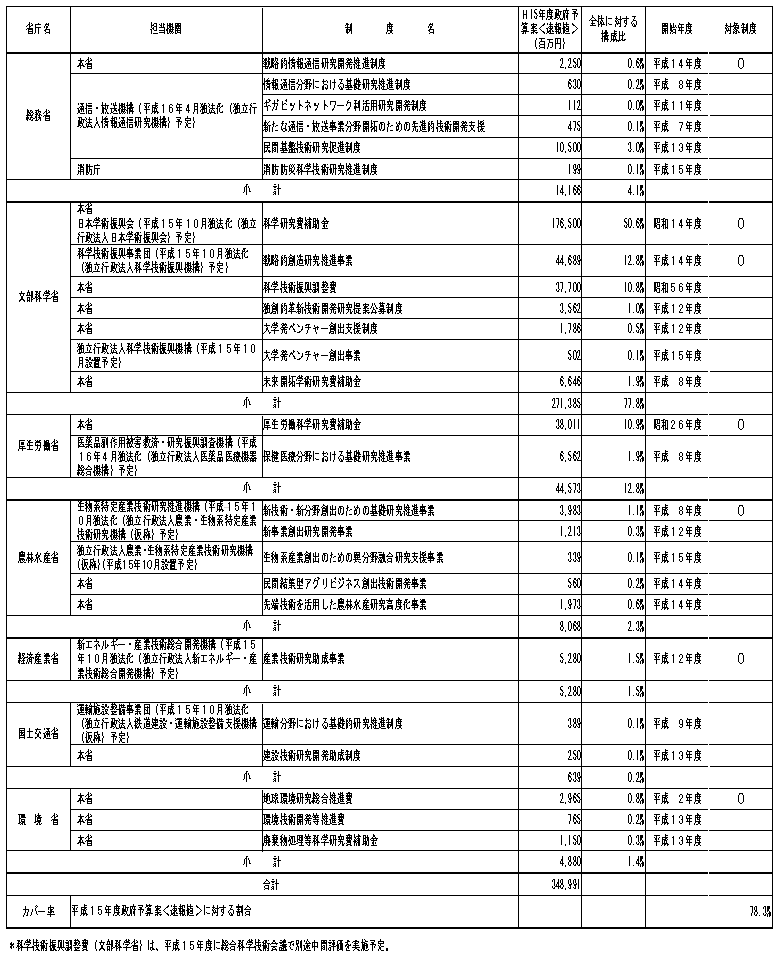(平成15年度予算)
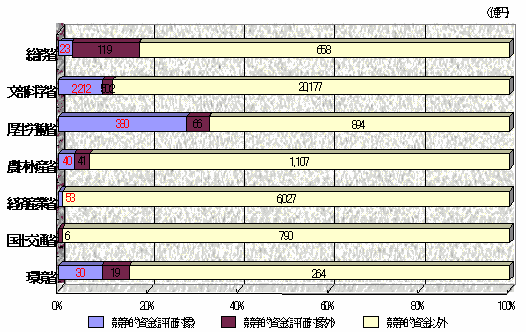
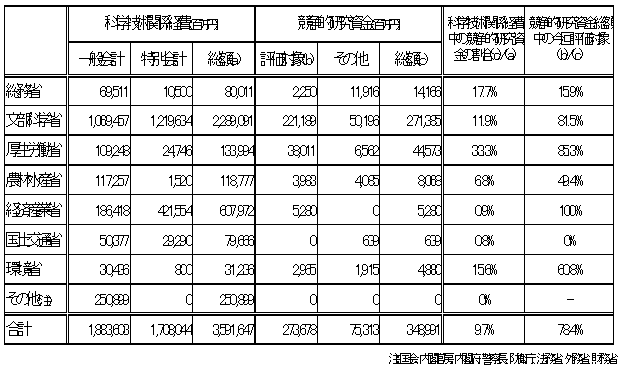
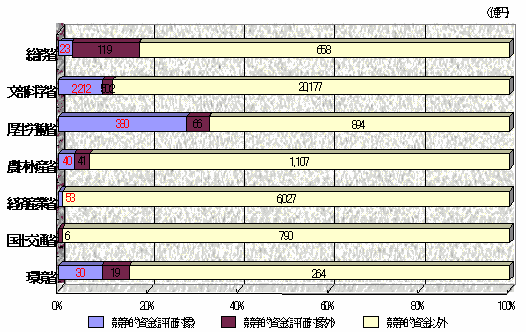
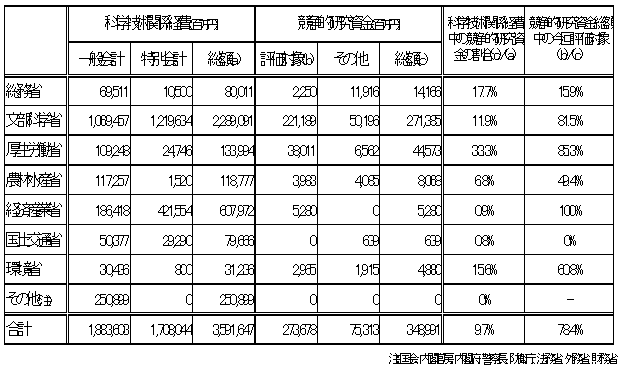
| 第24回総合科学技術会議資料 |
|
平成15年1月28日 総合科学技術会議 |
| (1) | 課題採択・資金配分の全般的状況 |
| (2) | 研究成果及びその他の効果(研究者育成、新分野開拓、
基盤形成等)、等 |
| 1. | 競争的研究資金は、意欲と能力ある研究者の自由な発想と優れた提案に基づいた研究を推進するため、公募方式と専門家の評価によって研究開発課題が決定されるもの。 |
||||||||||
| 2. | 平成15年度政府予算案では、科学研究費補助金(文部科学省)、厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省)等26制度(7省)で3,490億円(平成14年度予算3,443億円に対して1.4%増)が計上されている。 日本の競争的研究資金は、科学技術関係経費(約3.5兆円)全体の約1/10。これに対し、米国の競争的研究資金は約3.6兆円で、全体(約10.2兆円)の1/3以上を占めている。 |
||||||||||
| 3. | 第2期科学技術基本計画(平成13年度〜17年度)においては、 ・資金を計画期間中に倍増(約3,000億円→約6,000億円) ・資金の効果を最大限に発揮させるための制度改革の推進 が盛り込まれている。 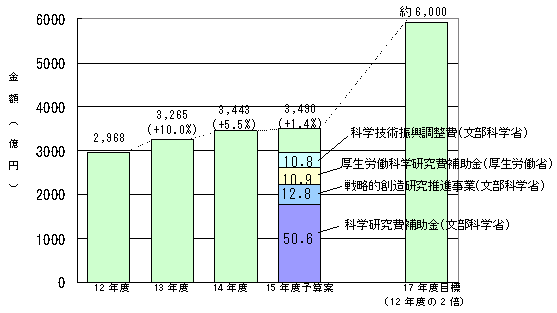
|
||||||||||
| 4. | 制度改革 総合科学技術会議の下に競争的資金制度改革プロジェクトを設置(平成14年3月設置、6月中間まとめ)し、競争原理により個人の能力が最大限に発揮されるシステムを構築すべく制度改革を検討中。
|
| 第21回評価専門調査会(平成15年3月18日)資料 |
| 1. | 対象制度 「資金規模が大きいなど各府省の代表的な競争的研究資金制度」として、以下の7制度を対象とする(参考)。
(2)特に資金規模の小さい国土交通省は選定せず。 なお、近年再編した制度で事業に継続性がある場合は、配分機関(府省もしくは法人)の判断により、必要に応じて再編前の制度による成果等も併せて検討し、評価できるものとする。 |
||||||||||||||||
| 2. | 評価専門調査会における調査・検討日程 【6月上旬】(約3時間x2日間)
【6月下旬】(約4時間x1日間)
【7月上旬】(約2時間) ○評価案の検討 ★7月本会議において評価案を審議・結論 |
||||||||||||||||
| 3. | 初回ヒアリング項目 a)制度概要 (1)目的及び目標 (2)公募対象(公募分野、公募対象者等)及び配分方針 (3)一課題当たりの研究費額及び研究開発期間 (4)運営方法(公募、審査、資金交付、進捗把握等) (5)課題の評価システム(評価時期、体制、方法等) b)配分機関における成果等に係る評価の結果 (1)実施方法(評価者、評価方法等) (2)成果等の状況
|
||||||||||||||||
| 4. | 評価方法 「制度の目的や投入予算に照らして、課題採択や資金配分の結果が適切か、研究成果やその他の効果が十分に得られているか」について、配分機関や関係審議会等における評価結果を十分踏まえつつ、科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観点から、例えば以下のような点に着目して検討する。 a)課題採択や資金配分の結果 ・採択課題の質や件数は適切か。 ・各課題へ配分される研究費額は適切か。 ・応募件数および採択率は適切か。 ・科学技術の分野や領域等の分布は適切か。 ・基礎、応用、開発等の研究性格別の分布は適切か。 b)研究成果やその他の効果 ・成果・効果の質・量は十分か。 ・成果・効果の科学技術上・社会経済上の貢献は十分か。 ・今後期待される成果・効果はどうか。 |
| 参考 |