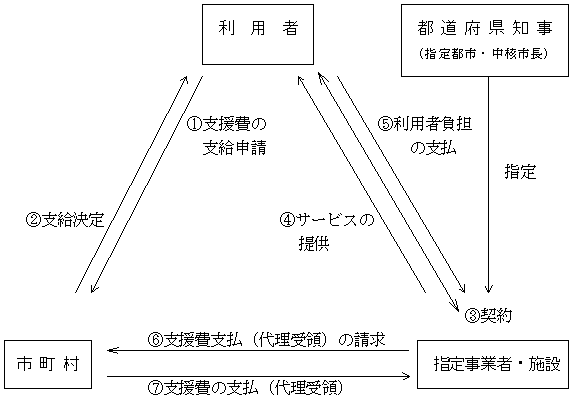
| ※ | やむを得ない事由により上記の方式の適用が困難な場合には、市町村が措置により、障害者福祉サービスの提供や施設への入所を決定する。 |
| 参考資料8−1 |
1 支援費制度の全体像
| (1) | 支援費制度の目指すもの 平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直しが行われた。 この社会福祉基礎構造改革の一つとして、障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、新たな利用の仕組み(「支援費制度」)に平成15年度より移行することとなった。 支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとしたところである。
これにより、事業者は、行政からの受託者としてサービスを提供していたものから、サービス提供の主体として、利用者の選択に十分応えることができるようサービスの質の向上を図ることが求められることとなる。 | ||||||||||||
| (2) | 基本的な仕組み
|
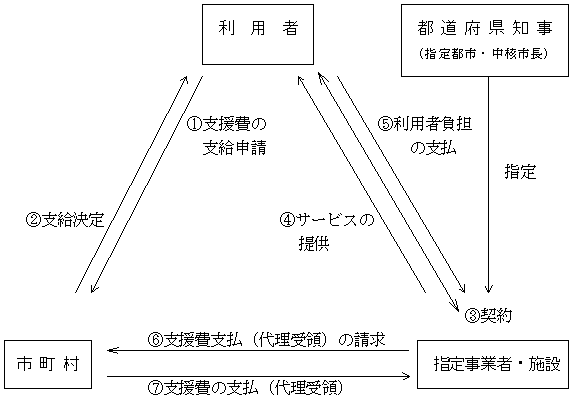
| ※ | やむを得ない事由により上記の方式の適用が困難な場合には、市町村が措置により、障害者福祉サービスの提供や施設への入所を決定する。 |
| (3) | 対象となる障害者福祉サービス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 事業者、市町村、都道府県、国の各役割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
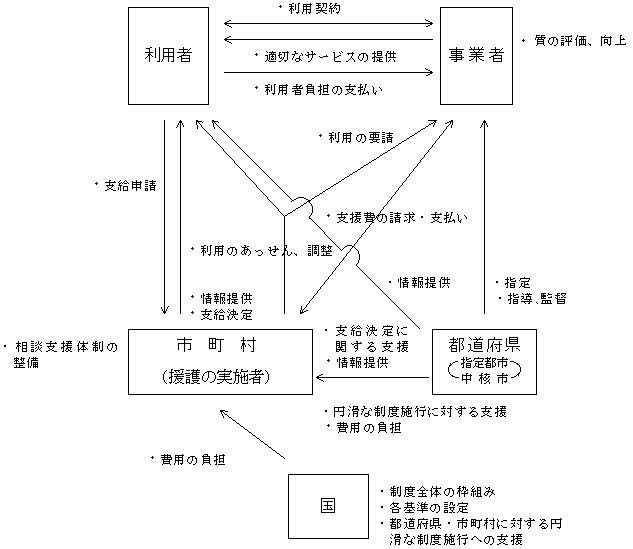
| ・ | 事業者の役割 事業者は、利用者の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに、その質の評価を行うこと等により、常に利用者の立場に立ってサービスを提供することに努める(社会福祉法第5条、第75条第1項、第76条、第77条、第78条第1項及び第82条等)。 |
| ・ | 市町村の役割 市町村は、地域住民に身近な行政主体として、障害者に対する支援体制の整備に努めるとともに、利用者本位のきめ細やかな対応により支援費の支給決定等を行う(社会福祉法第6条及び第75条第2項等)。 |
| ・ | 都道府県の役割 都道府県は、市町村において制度が円滑に行えるよう必要な支援を行うとともに、事業者又は施設の指定及び指導又は監督を行う(社会福祉法第6条及び第75条第2項等)。 |
| ・ | 国の役割 国は、制度全体の枠組みを示し、制度が円滑に行えるよう都道府県及び市町村への支援を行う(社会福祉法第6条、第75条第2項及び第78条第2項等)。 |
| (5) | 制度の基本的な流れ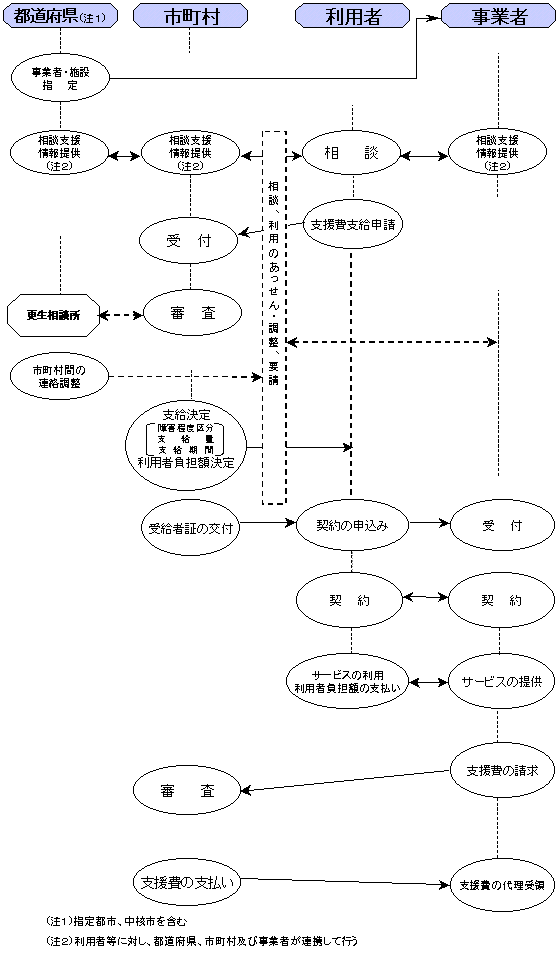
|
| (6) | 支援費制度施行までの日程(案)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 支給決定に関すること
| (1) | 支給決定の際の勘案事項について 支援費の支給決定については、法律上、厚生労働省令で定める事項を勘案して、その要否を決定し、居宅生活支援費であれば、支給量と支給期間を、施設訓練等支援費であれば、障害程度区分と支給期間を定めることとしている。 厚生労働省令で定める勘案事項は、以下のとおりである。
|
| (2) | 支給期間について 支援費を支給する期間については、障害の程度や介護を行う者の状況等の支援費の支給決定を行った際に勘案した事項が変化することがあるため、市町村が障害者の状況を的確に把握し、提供されているサービスの適合性を確認するとともに、適切な障害程度区分又は支給量について見直しを行うため、厚生労働省令で定める期間を超えない範囲で市町村が定めるものである。 省令で定める期間
|
| (3) | 障害程度区分について 障害程度区分は、重度障害者に対する支援が適切に行われるよう、施設訓練等支援費の額について、障害の程度に係る区分に応じた差異を設けるものであり、各施設支援毎(入所・通所別。)に3区分設定する。 ○ 障害程度区分の決定方法 障害程度区分の決定は、各施設支援毎に設定したチェック項目について、市町村が申請者等に対する聴き取りを行うことにより決定する。
各チェック項目については、支援の態様や支援を要する頻度等による選択肢が3つずつ設定されている。 (チェック項目の例)
|
| (4) | 相談支援体制の充実及びサービス利用に係るあっせん・調整、要請について
|
3 事業者・施設指定基準に関すること
| (1) | 指定基準の性格 指定基準は、支援費制度において対象となるサービス提供主体の範囲を特定するものである。 また、指定基準は、支援費の対象となるサービスについて一定のサービスの質を確保するとともに、サービス提供主体としての遵守事項を規定することにより、利用契約制度の円滑な運営を確保する観点から設けられるものである。 |
| (2) | 指定基準の主な内容
|
| (3) | 契約に当たっての基本的な考え方 支援費制度においては、原則として利用者本人と事業者の間でサービスの利用に係る契約を締結する必要がある。 何らかの支援があれば本人の意思を確認できる知的障害者については、本人の意思により本人が契約できるよう、福祉サービス利用援助事業を活用すること等により、本人に対する必要な支援が行われることが重要である。 また、契約の締結にあたって成年後見制度の利用が必要となる場合があることから、国として、成年後見制度の利用の支援策についての措置を講じたところである。 (平成14年度予算において成年後見制度利用支援事業の対象者に知的障害者を加えた。) |
4 厚生労働大臣が定める支援費基準について
支援費は、支給決定障害者が指定施設・事業所からサービスの提供を受けた場合に、そのサービスの対価として市町村から当該支給決定障害者に対して支給されるものであり、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において、市町村長が定めることとされている。
(1) 支援費基準の基本的な考え方
| (1) | 各居宅生活支援及び各施設訓練等支援ごとに、当該サービスに通常要する費用を適切に評価した基準とすること。 |
| (2) | 障害者の地域生活の推進を評価するような基準とすること。 |
| (3) | 施設訓練等支援費は、重度障害者や重複障害者が適切にサービスを利用できるよう、障害程度区分に応じて格差を設けた基準とすること。 |
| (4) | 居宅生活支援費のうち、デイサービス、短期入所及び知的障害者地域生活援助に係る支援費基準についても、障害の程度を考慮した基準とすること。 |
| (5) | 居宅生活支援及び施設訓練等支援を担う事業主体において、安定的かつ効率的に事業運営が行えるような基準とすること。 |
| (6) | 同一のサービスであれば、設置主体にかかわらず、同一の支援費基準とすること。 |
| (7) | 居宅生活支援及び施設訓練等支援に必要な人件費等の水準が同じような地域ごとの基準とすること。 |
| (8) | 利用者や事業者などにわかりやすく、簡素で合理的な基準とすること。 |
| (9) | 現行の措置制度からの円滑な移行に十分配慮した基準とすること。 |
|
基準額(案)
(1) 施設訓練等支援費(例)(1月につき)
(2) 居宅生活支援費(例)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 厚生労働大臣が定める利用者負担基準について
利用者負担額は、身体障害者(知的障害者、障害児)又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準によることとされており、具体的には負担能力に応じてまず利用者本人が負担することとし、その負担額が利用者本人に係る支援費基準により算定した額に満たない場合は、その不足分について負担能力に応じて主たる扶養義務者からの負担を求めることとしている。
| 利用者負担基準の具体的な決定については、平成15年度の予算編成過程において行われるものであるが、現段階で考えられる基準(案)は次のとおりである。 |
(1) 主たる扶養義務者について
| ・ | 利用者が20歳以上の場合 支給決定の際に、同一世帯・同一生計にある配偶者及び子のうち最多納税者 | ||
| ・ | 利用者が20歳未満の場合 支給決定の際に、同一世帯・同一生計にある配偶者、父母及び子のうち最多納税者
|
(2) 負担能力の判定方法について
| ・ | 施設訓練等支援の利用者本人分 利用者本人の前年の収入から必要経費を控除した額に基づき判定。 |
| ・ | 居宅生活支援の利用者本人分 利用者本人の前年の所得税額等に基づき判定。 |
| ・ | 施設訓練等支援・居宅生活支援の扶養義務者分 主たる扶養義務者の前年の所得税額等に基づき判定。 |
| ・ | 障害児に係る居宅生活支援 障害児及び主たる扶養義務者の前年の所得税額等の合算額に基づき判定。 |
(3) 利用者負担額の設定について
ア 施設訓練等支援費
| ・ | 階層区分及び負担基準月額については、現行の費用徴収制度と同様とする。 |
| ・ | 暫定措置としての負担基準月額の上限については、平成8年度以降据え置いていることから、その間の施設における生活費のアップ率を考慮して所要の改定を図る。 なお、指定知的障害者通勤寮については、更生施設、授産施設の通所者と同額とする |
イ 居宅生活支援費
| ・ | 階層区分は、施設の扶養義務者の階層区分と同様。 |
| ・ | 居宅介護を利用する場合30分当たり、デイサービス及び短期入所を利用する場合1日当たりの単位ごとに負担能力に応じた負担額を設定する。 なお、その際、利用者負担額がその支給量に応じて著しく増大しないよう、負担能力に応じた階層区分ごとに、居宅生活支援の利用者負担総額について、本人及び扶養義務者それぞれに施設の通所者に係る扶養義務者分の負担基準月額と同額の上限を設定する。 |
具体的な基準額表については、以下のとおり。
| (1) | 施設訓練等支援費の利用者本人分(案) 別表1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 施設訓練等支援費の扶養義務者分(案)
別表2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 居宅生活支援費の利用者本人分(障害児を除く)及び扶養義務者分(案)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||