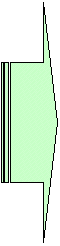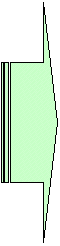|
血液製剤は、人体の組織の一部である血液を原料とする。
↓
倫理性、国際的公平性等の観点から、国内の善意の無償献血によりまかなうことが原則。
| * | 国内製造が困難な場合等は例外。(抗Dグロブリン、テタノブリン等) |
| * | 血液製剤の安全性については、内外共通の規制を実施するが、感染症発生時には国内の方が対応しやすいという面がある。 |
|
| ○ | 国内自給原則や献血推進について、法的な位置付けがない。 |
| ○ | 国内自給達成に向けた進め方が明確でない。 |
| ○ | 血液製剤の使用について、一層の適正化が必要。 |
| ○ | 血漿分画製剤の相当量を輸入(外国血液由来)に依存。
(平成13年の自給率:アルブミン33.8%、グロブリン80.6%) |
| ○ | 現在は全面輸入の遺伝子組換え製剤について、安定供給を図る観点から 適切な位置付けが必要。 |
|
|
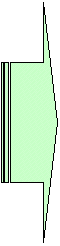 |
| ○ | 法の基本理念を明確化
|
| ○ | 国の責務を規定
| ・ | 国内自給確保のため教育・啓発、適正使用に関する施策の実施等の措置を講ずる。 | |
| ○ | 基本方針を国が策定
|
| ○ | 献血推進計画等により献血を推進
| ・ | 献血確保目標量を設定。 |
| ・ | 採血事業者は献血受入計画を策定。 |
|
| ○ | 適正使用を一層推進
| ・ | 法の基本理念や医療関係者の責務として、適正使用の推進を明確化。 |
| ・ | 血液製剤の使用ガイドラインを見直し。 |
|
| ○ | 血液製剤の需給計画により供給を安定化
| ・ | 毎年の需要・供給見込量を設定。 |
| ・ | 採血事業者及び製造・輸入業者は計画を尊重。 |
| ・ | 実績が著しく適正を欠くときは国が勧告。 |
| ・ | 遺伝子組換え製剤も計画の対象とする。 |
|
|
|