ホーム > 政策について > 審議会・研究会等 > 社会保障審議会 > 市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)
市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)
市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針
の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)
社会保障審議会福祉部会
| はじめに −地域福祉推進の背景と必要性− |
我が国においては、かつての伝統的な家庭や地域の相互扶助機能は弱体化し、地域住民相互の社会的なつながりも希薄化するなど地域社会は変容しつつある。少子高齢社会の到来、成長型社会の終焉、産業の空洞化、そして近年の深刻な経済不況がこれに追い打ちをかけている。このため、高齢者、障害者などの生活上の支援を要する人々は一層厳しい状況におかれている。また、青少年や中年層においても生活不安とストレスが増大し、自殺やホームレス、家庭内暴力、虐待、ひきこもりなどが新たな社会問題となっている。
他方で、近年、市町村の福祉施策が盛んになり、ボランティアやNPO法人なども活発化し、社会福祉を通じて新たなコミュニティ形成を図る動きも顕著となっている。
こうした相矛盾する社会状況の中で、市町村を中心とする福祉行政の役割は極めて重要となっており、加えて地域住民の自主的な助け合いなどの意義も益々大きくなっている。
先の中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会の報告においては、「社会福祉の基礎となるのは、他人を思いやり、お互いを支え助け合おうとする精神である。その意味で、社会福祉を作り上げ、支えていくのはすべての国民である」と述べているが、国民生活の安心と幸せを実現するためには、自立した個人が地域住民としてのつながりを持ち、思いやりを持って共に支え合い、助け合うという共に生きるまちづくりの精神が育まれ活かされることが必要不可欠である。
今こそ、共に生きるまちづくりの精神を発揮し、人々が手を携えて、生活の拠点である地域に根ざして助け合い、生活者としてそれぞれの地域で誰もがその人らしい安心で充実した生活が送れるような地域社会を基盤とした福祉(地域福祉)の推進に努める必要がある。
法制上においても、平成2年のいわゆる福祉八法の改正以降、在宅サービスの法制化、措置権の移譲に伴う保健福祉サービスの市町村への一元化や、高齢者、障害者、児童各分野でのサービスの計画化などにより、地域住民の生活に密着した市町村を中核とする保健福祉サービスの提供体制の基盤づくりが進められてきた。とりわけ、社会福祉事業法においては、地域に即した創意と工夫による福祉サービスの総合的な実施、福祉サービスに対する地域住民の理解と協力が定められる等、実質的に地域福祉の推進が唱えられ、平成12年の社会福祉法においては、「地域福祉の推進」が明確に位置づけられるようになった。
一人ひとりの地域住民への訴え
とかく、これまでの社会福祉は、ややもすると行政から地域住民への給付という形をとってきた。しかしながら、これからは、個人の尊厳を重視し、対等平等の考え方に基づき、地域住民すべてにとっての社会福祉として、かつ、地域住民すべてで支える社会福祉に変わっていかなければならない。そのためには社会福祉に対しての地域住民の理解と協力、つまり地域住民の参加と行動が不可欠なのである。
この際、一人ひとりの地域住民に対して、社会福祉を限られた社会的弱者に対するサービスとしてではなく、身近な日々の暮らしの場である地域社会での多様な人々の多様な生活課題に地域全体で取り組む仕組みとしてとらえなおし、地域住民としてこれらの多様な生活課題に目を向け自発的、積極的に取り組んでいただけるよう訴えたい。また、社会福祉を消極的に単なる特定の人に対する公費の投入と考えるのではなく、むしろ福祉活動を通じて地域を活性化させるものとして積極的な視点でとらえていただけるよう強く訴えたい。
当部会としては、地域福祉計画策定指針原案作成委員会を設置し、この委員会を中心にこのような観点から平成13年7月以来、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について精力的に検討を重ね、今般、報告をとりまとめた。今、この報告を広く一人ひとりの地域住民に問いかけ、これを契機として、それぞれの地域で生活者の視点から地域の特性を活かした地域福祉の推進についての活発な議論が行われることを期待したい。このことを通じて、社会福祉基礎構造改革の趣旨が地域レベルにおいても再度確認され、これらの計画が21世紀の福祉を決定づけるものとして広く地域住民の参加を得て策定されることを求めるものである。また、自治体の首長、議会も、住民主体の地域福祉計画策定を推進する上で、自治体としての責任とリーダーシップを発揮されることを期待するものである。
| 地域福祉推進の理念 |
○ 中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会は、今後の新しい社会福祉の理念について「個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で障害の有無や年齢にかかわらず、その人らしい安心のある生活が送れるよう自立支援することにある」と意見し、こうした理念を地域において具現化するために地域福祉の推進を図るべきであるとした。
これを受けた社会福祉法においては、今後の社会福祉の基本理念の一つとして「地域福祉の推進」を掲げ、地域福祉を推進する主体と地域福祉を推進する目的を次のように定めた。
|
(参考)社会福祉法より抜粋
(福祉サービスの基本的理念)
(地域福祉の推進) |
○ すなわち、地域福祉推進の主体は「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「住民等」という。)」の三者であり、地域福祉を推進することの目的は、これらの者が相互に協力しあうことにより「福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるようにすること」であるとした。こうした地域福祉推進のための方策として「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画」の策定を求めた。
|
(参考)社会福祉法より抜粋
(市町村地域福祉計画)
(都道府県地域福祉支援計画)
|
○ 市町村地域福祉計画は、地域住民に最も身近な行政主体である市区町村(以下「市町村」という。)が、地域福祉推進の主体である住民等の参加を得て地域の要支援者の生活上の解決すべき課題(以下「生活課題」という。)とそれに対応する必要なサービスの内容や量、その現状を明らかにし、かつ、確保し提供する体制を計画的に整備することを内容とする。
また、都道府県地域福祉支援計画は、市町村の区域を包含する広域的な地方公共団体として広域的な観点から市町村を支援し、その際、市町村の規模、地域の特性、施策への取組状況等に応じて、きめ細かな配慮を行う必要があり、このために市町村支援を旨とするものである。
○ なお、ここでいう住民等は、地域福祉計画の策定について意見を述べるだけの存在ではない。計画策定に参加すると同時に自らが地域福祉の担い手であると認識することが重要である。したがって特に関係団体の参加を要請する場合は、代表者の形式的参加で事足りるとすべきではない。
地域福祉の担い手としては、例えば次のような者が考えられる。
- 地域住民
- 要支援者の団体
- 自治会・町内会、地縁型組織等
- 一般企業、商店街等
- 民生委員・児童委員、福祉委員等
- ボランティア、ボランティア団体
- 特定非営利活動法人(NPO法人)、住民参加型在宅サービス団体等
- 農業協同組合、消費生活協同組合等
- 社会福祉法人、地区(校区)社会福祉協議会等
- 社会福祉従事者(民間事業者を含む)
- 福祉関連民間事業者(シルバーサービス事業者等)
- その他の諸団体
○ 地域福祉計画とは、地方公共団体が地域福祉を総合的かつ計画的に推進することにより、社会福祉法に示された新しい社会福祉の理念を達成するための方策である。したがって地域福祉計画は、行政計画でありながら、福祉サービスにおける個人の尊厳の保持を基本に据えて、自己決定、自己実現の尊重、自立支援など住民等による地域福祉推進のための参加や協力に立脚して策定されるべきである。
○ 今後における地域福祉推進の理念としては、少なくとも次の点、(1)住民参加の必要性、(2)共に生きる社会づくり、(3)男女共同参画、(4)福祉文化の創造に留意することが重要である。
-
(1)住民参加の必要性
例えば、障害を有したり、性や年齢が異なることなど、人間はそれぞれ異なるわけであるが、個人の尊厳、その人が生きる価値などの点においては、皆平等であり、すべての地域住民が地域社会の一員としてあらゆる分野の活動に参加する機会が保障されなければならない。
こうしたことは、生活課題を持つ人自身が、権利の主体としてそれを求めることのみではなく、他の地域住民も、それを当然のこととして支持すると共に「一緒になって、それを実現することが当然であり、それが地域社会の誰にとっても望ましい社会なのだ」という地域社会の共通の価値観を持たなければ達成できない。
したがって、地域福祉とは地域住民の主体的な参加を大前提としたものであり、地域福祉計画の最大の特徴は「地域住民の参加がなければ策定できない」ことにある。地域住民の主体的参加による地域福祉計画の策定・実行・評価の過程は、それ自体、地域福祉推進の実践そのものである。(別紙1参照)(2)共に生きる社会づくり
すなわち、地域福祉においては、差異や多様性を認め合う地域住民相互の連帯、心のつながりとそのために必要なシステムが不可欠であり、例えば、貧困や失業に陥った人々、障害を有する人々、ホームレスの状態にある人々等を社会的に排除するのではなく、地域社会への参加と参画を促し社会に統合する「共に生きる社会づくり(ソーシャル・インクルージョン)」という視点が重要である。
さらに、様々な権利侵害に対して、全体として権利を擁護していく地域住民の活動とシステムが不可欠である。(3)男女共同参画
地域福祉を推進する諸活動は、男女共同参画の視点に立脚して展開される必要がある。「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担う」ことは重要であり、そのため、男性も女性も共に日々の暮らしの基盤である地域社会の生活課題に目を向け、その解決のための意思決定、諸活動にも参画していくことが期待される。
(4)福祉文化の創造
具体的には、地域住民が、自らの生活基盤である地域社会での生活課題やそれに対応するサービスの現状、果たすべき役割などを、自らの問題として認識し、自らがサービスの在り方に主体的にかかわり、サービスの担い手としても参画していくことが重要である。こうした地域住民による生活に根ざした社会的活動の積み重ねが、それぞれの地域に個性ある行動様式や態度を育み文化(福祉文化)を創造していくことにつながる。また、このことは、地方分権の趣旨にも沿うものである。
| 地域福祉推進の基本目標 |
○ 社会福祉法の理念に基づく社会福祉を地域において実現するためには、少なくとも次のような基本目標に沿って地域福祉を進める必要がある。
-
(1) 生活課題の達成への住民等の積極的参加
-
○ 地域住民の参加や関係団体と連携した活動が全国で広がりつつあり、また、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)の成立など、新たな活動の基盤整備も進められている。こうした状況を踏まえ、地域福祉の推進においても、地域住民を施策の対象としてのみとらえるのではなく、地域福祉の担い手として位置づけるとともに、地域住民の自主的な活動と関係諸団体及び公共的なサービスとの間の連携を図っていくことが重要である。
○ この際、地域住民も「福祉は行政が行うもの」という意識を改め、行政も「福祉は行政処分で対処するもの」という意識を改めて、地域社会の全構成員(住民等)がパートナーシップの考えを持つことが重要である。パートナーシップは、民間相互のパートナーシップのみでなく、公私のパートナーシップとして行政及び地域社会の構成員が相互に理解し合い、相互の長所を活かし、「協働」することによって大きな創造力が生み出されてくるものである(パートナーシップ型住民参加)。
○ なお、地域福祉計画の策定過程を通じて地域福祉活動における公と私の役割分担について留意する必要がある。もちろん、このことは公行政の役割をいささかも減じるものではなく、公行政は地域住民の健康で文化的なミニマムな生活を保障する役割を担っている。
(2) 利用者主体のサービスの実現
-
○ 利用者本位の考え方に立って、利用者を一人の人間としてとらえ、その人の生活課題を総合的かつ継続的に把握し、制度やサービスの種別、実施主体の相違を越えて、対応する適切なサービスのセットが、総合的かつ効率的に提供され、その利用へのアクセスが阻害されないような体制を身近な地域において構築する必要がある。
○ 具体的には、サービスを総合的に利用できるようにするケアマネジメントを含むソーシャルワークの体制を、相談機能を持つ機関や福祉事務所などで充実する必要がある。
○ このソーシャルワーク機能においては、「人生を生きる主人公は自分自身であり、自己決定により自ら人生を切り拓き自己実現を図っていく」という利用者自身の持っている力を引き出す援助(エンパワーメント)が重要であるほか、地域住民が孤立したり、生活課題を抱えたときに、声を上げられる仕組みや発見する仕組みづくり(コミュニティワーク)にも向けられる必要がある。
○ サービスの内容や評価について、地域住民の信頼と理解を得るためには、情報の公開などを進め、事業運営の透明性の確保を図らなければならない。また、利用者の選択を通じた適正な競争を促進し、福祉従事者の専門性の向上などを通じて、サービスの質の向上と効率の促進を図る必要がある。
(3) サービスの総合化の確立
地域福祉の推進においては、地域の身近なところで総合的な相談が受けられ、サービスの適切な利用と結びつけられる体制を整備することが重要である。
地域住民の生活課題は、必ずしも専門分化した単一の福祉サービスによって充足されるものではなく、しばしば、福祉・保健・医療その他生活関連分野にまたがるものであり、公共的サービス・民間によるサービスやサポートも含めて、複数のサービスを適切に組み合わせて総合化することによって満たされることが少なくない。このため、こうした多様なサービスそれぞれが十分な連携を図って総合的に展開されていくことが不可欠であり、今後は総合的サービスの提供体制を確保していく必要がある。(4) 生活関連分野との連携
地域福祉の範囲として、福祉・保健・医療の一体的な運営はもとより、教育、就労、住宅、交通、環境、まちづくりなどの生活関連分野との連携が必要となる。
生活課題に対応する施策は、個別的には既に存在しているものも多いが、これらに新しいアイデアを取り入れてシステム化し、地域起こしに結びつくような福祉関連産業、健康関連産業、環境関連産業などの領域で、地域密着型コミュニティビジネスあるいはNPOなどを創出していくこと(社会的起業)が考えられる。
ちなみに、地域密着型コミュニティビジネスや地域通貨(エコマネー等)制度は、地域住民の生活課題に柔軟に対応したもので、今後、地域福祉活動の中でソーシャル・インクルージョンの手段としても注目されるところである。 -
○ 地域住民の参加や関係団体と連携した活動が全国で広がりつつあり、また、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)の成立など、新たな活動の基盤整備も進められている。こうした状況を踏まえ、地域福祉の推進においても、地域住民を施策の対象としてのみとらえるのではなく、地域福祉の担い手として位置づけるとともに、地域住民の自主的な活動と関係諸団体及び公共的なサービスとの間の連携を図っていくことが重要である。
| 市町村地域福祉計画 |
(1)計画に盛り込むべき事項
市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項としては、社会福祉法上、(1)地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、(2)地域における社会福祉を目的とした事業の健全な発達に関する事項、(3)地域福祉に関する活動への住民の参加に関する事項の3つが掲げられており、それを踏まえなければ、法上の地域福祉計画としては認められないものである。市町村においては、主体的にこれら3つの事項についてその趣旨を斟酌し具体的な内容を示すとともに、その他の必要な事項を加えて計画に盛り込む必要がある。
-
(1) 地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項
-
○ 地域における福祉サービスの目標の提示
- 地域の生活課題に関する調査(いわゆる「ニーズ調査」)、必要とされるサービス量の調査、提供されているサービスの点検
- 福祉サービス確保の緊急性や目標量の設定
なお、数値目標については、計画の内容を分かりやすくするとともに、その進捗状況を適切に管理する上で可能な限り客観的な指標を掲げることが望ましい。定性的な目標の場合にも、目標の達成の判断を容易に行える具体的な目標とすることが望ましい。
○ 目標達成のための戦略
-
ア 福祉サービスを必要とする地域住民に対する相談支援体制の整備
- 福祉サービスの利用に関する情報提供、相談体制の確保
イ 要支援者が必要なサービスを利用することができるための仕組みの確立
- 社会福祉従事者の専門性の向上、ケアマネジメント、ソーシャルワーク体制の整備
ウ サービスの評価やサービス内容の開示等による利用者の適切なサービス選択の確保
エ サービス利用に結びついていない要支援者への対応
- 孤立、虐待、ひきこもり、サービス利用拒否などの要支援者を発見する機能の充実、ソーシャルワーク体制の整備、近隣の地域住民や訪問機会のある事業者などの活動、福祉事務所の地域福祉活動等の充実・支援
○ 利用者の権利擁護
地域福祉権利擁護事業、苦情解決制度など適切なサービス利用を支援する仕組み等の整備 - 地域の生活課題に関する調査(いわゆる「ニーズ調査」)、必要とされるサービス量の調査、提供されているサービスの点検
(2) 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
-
○ 複雑多様化した生活課題を解決するため、社会福祉を目的とする多様なサービスの振興・参入促進及びこれらと公的サービスの連携による公私協働の実現
- 民間の新規事業の開発やコーディネート機能への支援
○ 福祉、保健、医療と生活に関連する他分野との連携方策
- 民間の新規事業の開発やコーディネート機能への支援
(3) 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
-
○ 地域住民、ボランティア団体、NPO法人等の社会福祉活動への支援
- 活動に必要な情報の入手、必要な知識、技術の習得、活動拠点に関する支援
- 地域住民の自主的な活動と公共的サービスの連携
○ 住民等による問題関心の共有化への動機付けと意識の向上、地域福祉推進への主体的参加の促進
- 地域住民、サービス利用者の自立
- 地域の福祉の在り方について住民等の理解と関心を深めることによる主体的な生活者、地域の構成員としての意識の向上
- 住民等の交流会、勉強会等の開催
○ 地域福祉を推進する人材の養成
- 地域福祉活動専門員、社会福祉従事者等による地域組織化機能の発揮
- 活動に必要な情報の入手、必要な知識、技術の習得、活動拠点に関する支援
(4) その他
-
○ その地域で地域福祉を推進する上で必要と認められる事項
- 市町村社会福祉協議会の基盤の整備強化等
-
○ 地域における福祉サービスの目標の提示
(2)計画策定の体制と過程
-
(1) 市町村行政内部の計画策定体制
-
○ 地域福祉計画は、老人保健福祉計画・介護保険事業計画、障害者計画、児童育成計画、その他の関連する計画との整合性を持ち、かつ、福祉・保健・医療及び生活関連分野との連携を確保して策定される必要がある。
そのため、行政全体での取り組みが不可欠であり、関係部局が一堂に会した地域福祉計画の検討会を開催したり、部局を横断した職員による地域福祉計画策定のためのプロジェクトチームを立ち上げることも有効な手法の一つと考えられる。○ また、市町村が福祉事務所、保健所、市町村保健センター等を設置している場合には、地域福祉計画の策定体制にこれらの組織や職員が積極的に参加することが基本である。とりわけ、社会福祉士や保健師などの地域活動の展開方法や技術に係る専門職が中核的な役割を担うことが望まれる。
○ なお、地域福祉の積極的な推進を担うのは住民等の自主的な努力であるが、その自主性の発揮を側面から様々に援助する役割が必要となる。このためには、例えば、市町村が住民等に一斉に広報するようなことに加えて、小地域ごとに住民等間の地域福祉の推進に向けて中心的な役割を担う者(以下「地域福祉推進役」という。)を見い出し、住民等に対してこの地域福祉活動への参加を促すことが重要である。
(2) 地域福祉計画策定委員会
-
○ 地域福祉計画の策定に当たっては、市町村の地域福祉担当部局に地域福祉推進役としての地域住民、学識経験者、福祉・保健・医療関係者、民生委員・児童委員、市町村職員等が参加する、例えば「地域福祉計画策定委員会」のような策定組織を設置することが考えられる。
○ 地域福祉計画策定委員会は、必要に応じて適宜、委員以外のその他の関連する専門家、地域の生活課題に精通し地域福祉に関心の深い者、その他関係者等の意見を聞くことや、住民等が計画策定に積極的に関わることができる機会を確保することが適当である。
○ また、地域福祉計画策定委員会は原則として公開とし、進捗状況について適宜公表するほか、広く住民等が傍聴できる体制を採るなどの配慮が必要である。
○ なお、具体的な地域福祉計画策定は、平成15年4月の社会福祉法の地域福祉計画条項施行以降、こうした準備が整った市町村から速やかに行われるのが適当である。このため、地域福祉計画策定委員会は14年度の早期に発足することが望ましい。
(3) 地域福祉計画策定方針の決定
地域福祉計画策定委員会は、平成14年度中においては、都道府県が示す地域福祉計画策定ガイドラインを勘案し都道府県と調整しつつ、住民等の主体的参加を実現するため、地域住民同士の交流会、関係団体も含めた懇談会、ヒヤリング、アンケート調査等を実施し、地域福祉計画に住民等の地域福祉の在り方に関する意見を十分に反映させる旨の策定方針を定める必要がある。
(4) 地域福祉計画の目標の設定
地域福祉の推進を具体化する上での個別施策については、計画の達成状況を住民等に明確に示すためにも具体的で計画の達成度の判断が容易に行える目標を示す必要がある。
このため可能な限り数値目標を示すことが望ましいが、地域福祉を推進する施策の中には、数値目標になじまないものもあるため、定性的な目標設定がなされることがある。しかし、その場合でも計画の目標は具体的であることを旨とすべきである。
なお、計画の目標設定を支援するため、都道府県においては先行する市町村の事例を積極的に紹介するよう努めることが望まれる。(5) 地域福祉計画策定の手順
-
○ 地域社会の生活課題をきめ細やかに発見することは、地域社会においてのみなし得ることであり、これを解決する方途を見い出し、実行することもまた地域社会でのみ可能である。そのためには、住民等の主体的参加が欠かせないものであることを、まず住民等に伝えることが重要である。
○ 住民等の参加を得るためには、情報の提供が極めて重要であり、情報を確実に伝えるための工夫が必要となる。例えば、地域の実情や必要に応じて外国語や点字、インターネットやケーブルテレビなどの多様な媒体による情報提供も考えられる。また、地域住民のうち、より多くの支援を必要とする人々ほど、情報が円滑に伝わらないことが考えられるため、特にこうした人々に対する情報伝達に気を配る必要がある。
○ こうした活動によって、住民等や要支援者自身が自ら生活課題を明かにするための調査(いわゆる「ニーズ調査」)に参加したり、要支援者と他の住民等との交流会に参加したりすることにより、地域社会の生活課題を自ら明らかにし、自ら解決に向けて活動する気持ちを醸成することが何よりも重要である。
○ このような住民等による問題関心の共有化への動機付けを契機に、地域は自主的に動き始めることとなる。こうして住民等が、地域社会におけるより多くの生活課題にも視野を広げ、自ら主導的に活動し続けることが地域福祉の推進につながっていく。(別紙2参照)
(6) 市区町村社会福祉協議会の役割
-
○ 地域福祉を推進する様々な団体により構成された市区町村社会福祉協議会は、社会福祉法において地域福祉を推進する中心的な団体として明確に位置付けられている。また、社会福祉協議会は、元来、地域住民主体を旨とした地域住民の参加の推進やボランティア、福祉教育、まちづくり等の実績を有することを踏まえ、地域福祉計画策定に当たっては市町村の計画策定に積極的に協力することが期待される。
○ なお、社会福祉協議会が中心となって策定している地域福祉活動計画は、住民等の福祉活動計画として地域福祉の推進を目指すものであることから、地域福祉計画とその内容を一部共有したり、地域福祉計画の実現を支援するための施策を盛り込んだりする等、相互に連携を図ることは当然である。
(7) 社会福祉法人の役割
社会福祉法人は児童、障害者、高齢者まで幅広い社会福祉の専門機能を有している。今後も各種研修会の開催や地域で行われる勉強会への講師の派遣、住民等の交流会・懇談会の開催のためのコーディネートや場所の提供、実習やボランティアの受け入れ等を通して、地域における福祉サービスの拠点としての役割が期待されている。このため、社会福祉法人は計画策定に積極的に参加し、そのノウハウを活かすことが期待される。
(8) 民生委員・児童委員の役割
民生委員・児童委員については、民生委員法により「住民の立場に立って相談に応じ、援助を行う」こととされていることを踏まえ、地域住民の生活状態の把握、福祉サービスの情報提供等を基本として地域福祉計画の策定に参加するとともに、地域住民の福祉の増進を図る地域福祉活動の担い手の一人となることが期待される。
(9) 地域福祉圏域及び福祉区の設定
-
○ 地域福祉計画は、市町村を単位として構想することが基本である。ただし、他の法定計画等との整合性の確保や個々のサービスの性格等にかんがみ必要に応じて圏域を設定することが考えられる。
○ また、地域福祉計画の策定に当たっては、事業の効率的な実施の観点から、複数の市町村が広域的に事業を実施する場合も含めて考える必要がある。
具体的には、人口、面積等が小規模な市町村においては、複数の市町村が合同して地域福祉計画を策定することは差し支えないこととするべきである。この場合において、個々の市町村が従来行ってきたきめ細かなサービスが引き続き実施されるよう配慮することが望ましい。
○ 人口規模の大きな市町村や相当の面積を有する市町村においては、地域福祉を推進するに当たり、管内を複数に分割する(例えば、政令指定都市における区単位)など、地域の実情を十分に汲み取って計画を策定することができるよう工夫することが望ましい。また、人口、地理的条件、交通等を総合的に検討する必要があるが、地域住民の生活に密着し、また、一定の福祉サービスや公共施設が整備されている区域を「福祉区」として、住民参加の体制を検討していくことも考えられる。
(10) 計画期間及び公表等
-
○ 地域福祉計画の計画期間は、他の計画との調整が必要であることから概ね5年とし3年で見直すことが適当である。また、地域の実情に応じて計画期間が変更されることも考えられる。
○ 市町村は、計画の実施状況を毎年定期的に点検することとし、このためには、例えば「計画評価委員会」のような、計画の進行管理を含む評価体制を確保し、計画策定時点から評価の手法をあらかじめ明らかにしておく必要がある。
また、この計画評価委員会は、地域福祉計画の策定・実施との継続性を確保するために地域福祉計画策定委員会と同一の委員とすることも考えられる。なお、計画評価委員会においては、苦情解決やオンブズパーソンなどの外部評価情報をも積極的に評価の参考とすることが望まれる。○ 計画は、策定後速やかにその内容を公表し、都道府県に提出することとする。都道府県は、これを情報提供の素材とする。
(11) 他の計画との関係
-
○ 地域福祉計画と他の福祉関係計画との関係
現状では、高齢者、障害者、児童といった対象ごとに計画が策定され、それぞれ根拠法を異にしているが、これらとの整合性及び連携を図り、これらの既存計画を内包する計画として、市町村及び都道府県のそれぞれを主体に、「地域住民主体のまちづくり」や幅広い地域住民の参加を基本とする視点を持った地域福祉計画を導入する必要がある。
さらに、障害者、児童に係る計画が未策定の場合には、地域福祉計画の策定に併せて連携を図りつつ策定されることが望まれる。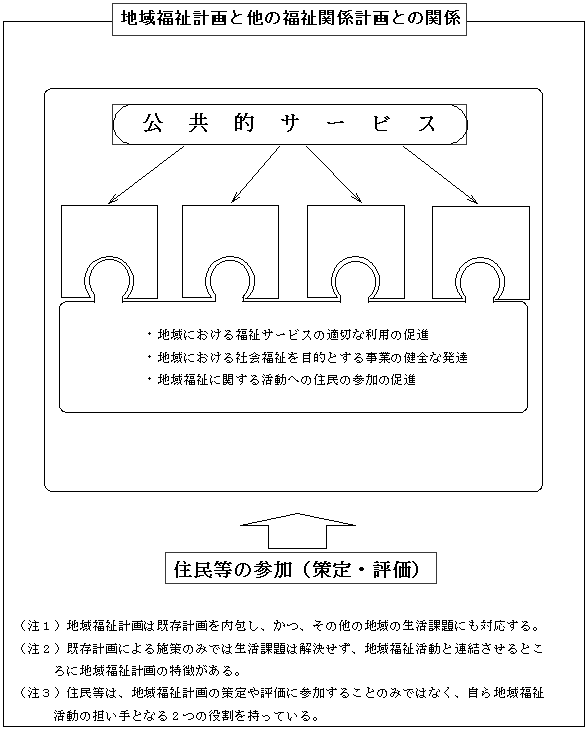
○ 法定計画との関係
地域福祉計画と市町村が既に策定している他の法定計画の対象分野とが重なる場合については、その既定の法定計画の全部又は一部をもって地域福祉計画の一部とみなすことができることとする。この場合において、他の法定計画の全部又は一部をもって地域福祉計画の一部とみなす旨を、地域福祉計画の策定段階において明らかにしておくことが必要である。
なお、地域福祉計画と既存計画の重複する部分については既存計画が優先されるとすることが適当である。○ 法定外計画との関係
地域福祉計画と市町村が既に策定している他の法定計画でない計画(法定外計画)の対象分野が重なる場合については、その既定の法定外計画の対象範囲が明確であり、かつ、住民参加を始めとして地域福祉計画に準じた策定手続を経て策定されているものであれば、その既定の法定外計画の全部又は一部をもって地域福祉計画の一部とみなすことができることとする。この場合において、他の法定外計画の全部又は一部をもって地域福祉計画の一部とみなす旨を、地域福祉計画の策定段階において明らかにしておくことが必要である。○ 既存地域福祉計画との関係
市町村において「地域福祉計画」等の名称を付した計画が既に策定されている場合には、その計画が法定の地域福祉計画において定めるべき事項が盛り込まれており、かつ、それに準じた策定手続を経て策定されているものであれば、その既定の計画をもって社会福祉法にいう地域福祉計画とすることができるものとすることが適当である。
(12) その他
-
○ これまで述べてきた地域福祉推進の基本的な考え方にかんがみれば、地域福祉計画はステレオタイプで形式的なものに留まるものではなく、加えて、外部のコンサルタント会社に策定を請け負わせるようなことがあってはならないことは当然である。
○ 地域福祉計画の策定、実行等に当たって必要となる経費については、その調達を固定的に考えるのではなく、豊富なアイデア、多様な財源や資源を前提とすべきであり、財源難を理由に地域福祉計画の推進が消極的になったり停滞することのないように配慮すべきである。
-
○ 地域福祉計画は、老人保健福祉計画・介護保険事業計画、障害者計画、児童育成計画、その他の関連する計画との整合性を持ち、かつ、福祉・保健・医療及び生活関連分野との連携を確保して策定される必要がある。
| 都道府県地域福祉支援計画 |
(1)支援計画に盛り込むべき事項
都道府県地域福祉支援計画(以下「支援計画」という。)に盛り込むべき事項としては、(1)市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項、(2)社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項、(3)福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項の3つが掲げられており、それを踏まえなければ、法上の支援計画としては認められないものである。都道府県においては、主体的にこれら3つの事項についてその趣旨を斟酌し具体的な内容を示すとともにその他の必要な事項を加えて計画に盛り込む必要がある。
-
(1) 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
-
ア 市町村に対する支援
イ 市町村が実施する広域事業に対する支援
ウ 都道府県管内の福祉サービスに関する情報の収集及び提供システムの構築
(2) 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
-
○ 人材の確保や福祉従事者に対する研修体制の整備等
- 社会福祉に従事する者を確保するための養成研修
- 社会福祉に従事する者の知識・技術向上のための研修
- 社会福祉に従事する者を確保するための養成研修
(3) 福祉サービスの適切な利用の促進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
-
○ 市町村が実施する福祉サービスの相談支援体制及び供給体制の確立のための基盤整備の促進等
- 社会福祉法人、非営利組織、民間事業者等への経営指導方策
- サービスの質の評価等の実施方策
- 広域的事業及び専門性が高い事業の情報提供及び相談体制の確保
- 地域福祉権利擁護事業、苦情解決制度等の実施体制の確保
- 社会福祉法人、非営利組織、民間事業者等への経営指導方策
(4) その他
-
○ その地域で各市町村が地域福祉計画を達成する上で必要と認められる事項
- 都道府県社会福祉協議会の活性化等
-
ア 市町村に対する支援
(2)支援計画の基本姿勢
地域福祉の推進は、市町村の地域福祉計画が中心であることから、支援計画は、あくまで、市町村の自主的な地域福祉計画の達成を支援するためのものである。このため、支援計画には、市町村の裁量を狭め、地域福祉計画の策定意義を失わせるような詳細な規制等を置かないことが適当である。
(3)支援計画策定の体制と過程
-
(1) 都道府県行政内部の計画策定体制
-
○ 支援計画は、老人保健福祉計画・介護保険事業計画、障害者計画、児童育成計画、その他の関連する計画との整合性を持ち、かつ、福祉・保健・医療及び生活関連分野との連携を確保して策定される必要がある。
そのため、行政全体での取り組みが不可欠であり、関係部局が一堂に会した支援計画の検討会を開催したり、部局を横断した職員による支援計画策定のためのプロジェクトチームを立ち上げることも有効な手法の一つと考えられる。○ なお、支援計画策定に係る広域的調整等については、その広域圏の福祉事務所及び保健所に行わせるなど、都道府県の福祉事務所及び保健所が積極的に参加することが基本である。とりわけ、社会福祉士や保健師などの地域活動の展開方法や技術に係る専門職が中核的な役割を担うことが望まれる。
(2) 地域福祉支援計画策定委員会
-
○ 支援計画の策定に当たっては、地域住民、学識経験者、福祉・保健・医療関係者、都道府県職員等が参加する、例えば「地域福祉支援計画策定委員会」のような策定組織を設置することが考えられる。
○ この支援計画策定委員会は、適宜必要に応じて、委員以外の関連する専門家、各市町村の地域福祉計画策定委員会委員長、その他の関係者等の意見を聞くことや、公聴会の開催等地域住民その他の者が支援計画策定に積極的に関わることができる機会を確保することが適当である。
○ また、支援計画策定委員会は原則として公開とし、進捗状況について適宜公表するほか、広く住民等が傍聴できる体制を採るなどの配慮が必要である。
(3) 支援計画策定方針の決定等
-
○ 都道府県は、市町村が地域福祉計画の策定を円滑に進めることができるよう、国の策定指針とその都道府県の地域性を踏まえ、支援計画策定委員会において、あらかじめ、平成14年度のできるだけ早い時期に市町村に提示する地域福祉計画策定ガイドラインを含む策定方針を決定することが適当である。
○ 市町村が計画を策定するに当たり、都道府県からどのような支援を受けることができるのかをあらかじめ知っておく必要があることから、このガイドラインには、市町村への支援メニュー及び住民等の主体的参加を実現するための方策を示す必要がある。
○ 地域福祉の推進は、住民等の主体的参加が不可欠であり、まず、地域福祉計画策定に向けて住民等の間で地域福祉計画策定の気運が醸成されている必要がある。このため、平成14年度中は、住民等による問題関心の共有化・助走期間と位置づけ、支援計画は、管内市町村の地域福祉計画策定状況を踏まえつつ、適当な時期に策定することが適当である。
○ なお、支援計画の策定に当たっては、管内市町村が策定する地域福祉計画と十分な連携を図る必要がある。このためには、例えば、各市町村における地域福祉計画策定委員会委員長会議を開催するなどして都道府県と市町村間との間で十分な協議を行う必要がある。
○ 市町村の人口規模や社会資源は様々であり、産業構造や住民等の意識等も一様でないことは自明のことである。地域福祉計画の策定に当たっては、それぞれの地域にふさわしい計画づくりを行うことが極めて重要なことであり、都道府県の福祉事務所、保健所における地域の実情に応じたきめ細かな支援の下で、多様性を持った計画づくりが可能となるよう配慮する必要がある。
(4) 都道府県社会福祉協議会及び共同募金会等の役割
都道府県社会福祉協議会及び共同募金会は、社会福祉法により地域福祉を推進する団体として明確に位置づけられていることを踏まえ、支援計画の策定に参加するほか、都道府県が市町村の地域福祉推進を支援する上で、大きな役割を果たすことが期待される。
また、その他の社会福祉関係団体も、支援計画の策定に積極的に参加することが望まれる。(5) 地域福祉圏域の設定
支援計画においては、他の法定計画等との整合性の確保や個々のサービスの性格等を考慮し、市町村と相談の上、必要に応じて圏域を設定することが考えられる。
(6) 計画期間及び公表等
-
○ 支援計画の計画期間は、他計画との調整が必要であることから概ね5年とし3年で見直すことが適当である。また、都道府県の実情に応じて計画期間が変更されることも考えられる。
○ 都道府県は、計画の実施状況を毎年定期的に点検することとし、このためには、例えば「計画評価委員会」のような、計画の進行管理を含む評価体制を確保し、計画策定時点から評価の手法をあらかじめ明らかにしておく必要がある。
○ 支援計画は、策定後速やかにその内容を公表し、国に提出することとする。国は、これを情報提供の素材とする。
(7) 他の計画との関係
-
○ 法定計画との関係
支援計画と都道府県が既に策定している他の法定計画の対象分野とが重なる場合については、その既定の法定計画の全部又は一部をもって支援計画の一部とみなすことができることとする。この場合において、他の法定計画の全部又は一部をもって支援計画の一部とみなす旨を、支援計画の策定段階において明らかにしておくことが必要である。
なお、支援計画と既存計画の重複する部分については既存計画が優先されるとすることが適当である。○ 法定外計画との関係
支援計画と都道府県が既に策定している他の法定計画でない計画(法定外計画)の対象分野が重なる場合については、その既定の法定外計画の対象範囲が明確であり、かつ、支援計画に準じた策定手続を経て策定されているものであれば、その既定の法定外計画の全部又は一部をもって支援計画の一部とみなすことができることとする。この場合において、他の法定外計画の全部又は一部をもって支援計画の一部とみなす旨を、支援計画の策定段階において明らかにしておくことが必要である。
-
○ 支援計画は、老人保健福祉計画・介護保険事業計画、障害者計画、児童育成計画、その他の関連する計画との整合性を持ち、かつ、福祉・保健・医療及び生活関連分野との連携を確保して策定される必要がある。
(照会先)厚生労働省社会・援護局地域福祉課地域福祉係(内線2859)
| [ |
|
] |
| I | 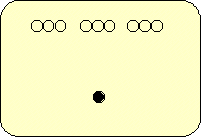 |
|
|||||||
| II | 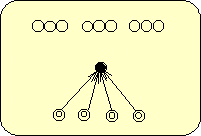 |
|
|||||||
| III | 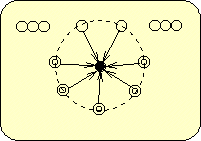 |
|
|||||||
| IV | 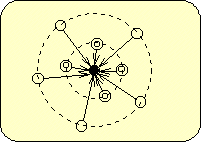 |
|
|||||||
| V | 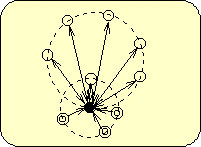 |
|
| 課題 | 市町村レベル | 小地域レベル | |||||||||||||||||||||
| 策定委員会の役割 | 地域福祉推進役の役割 | ||||||||||||||||||||||
| 地域福祉推進役による住民等に対する直接的働きかけ | |||||||||||||||||||||||
| 第一段階 | 地域福祉計画策定委員会 | 住民等自身による課題の把握 | 準備段階 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 第二段階 | 手順(1) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 手順(2) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 地域福祉計画策定 | 手順(3) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 手順(4) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 手順(5) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 手順(6) |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 第三段階 | 地域福祉計画評価委員会 | 計画の実施 | 手順(7) |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 評価 ・ 見直し提言 |
手順(8) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| (敬称略、五十音順) | (平成14年1月28日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーム > 政策について > 審議会・研究会等 > 社会保障審議会 > 市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)

