福祉・介護人材確保対策について
1.なぜ今福祉・介護人材確保対策が必要か
(1) 近年、我が国では、少子高齢化の進行や世帯構成の変化、国民のライフスタイルの多様化等により、国民の福祉・介護ニーズは多様化、高度化している状況にあり、これらのニーズに対応する福祉・介護人材は、質・量の両面において一層の充実が求められている状況にあります。
(参考1)我が国の人口の将来推計
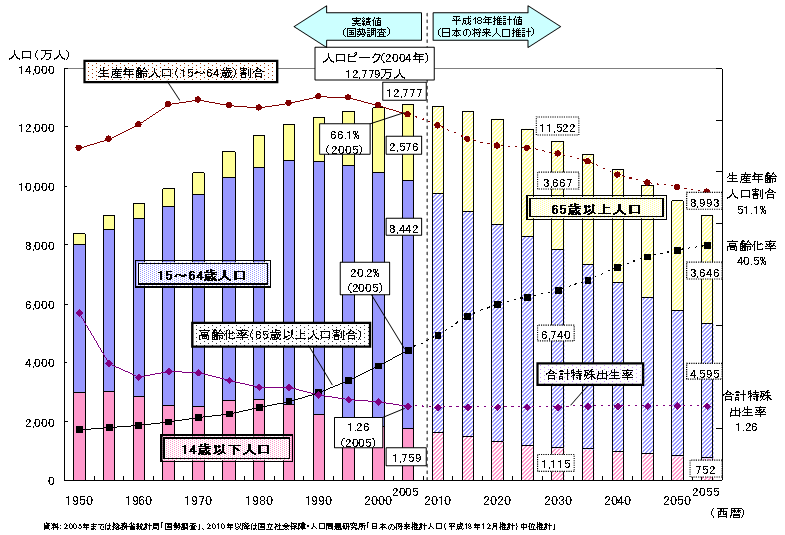
(参考2)高齢者世帯の将来推計
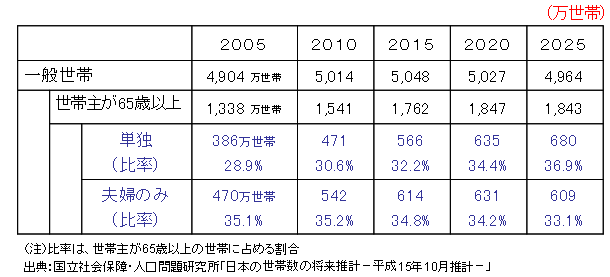
(2) また、こうした少子高齢化の進行等により、労働力人口が減少し、全産業的に労働力の確保が困難となっていくことが見込まれる中で、限られた労働力の中から、国民のニーズに的確に対応できる質の高い福祉・介護人材を安定的に確保していくことは喫緊の課題であり、国民生活を支える福祉・介護制度を維持する上で、不可欠の要素であると言えます。
(参考3)我が国の労働力人口の将来推計
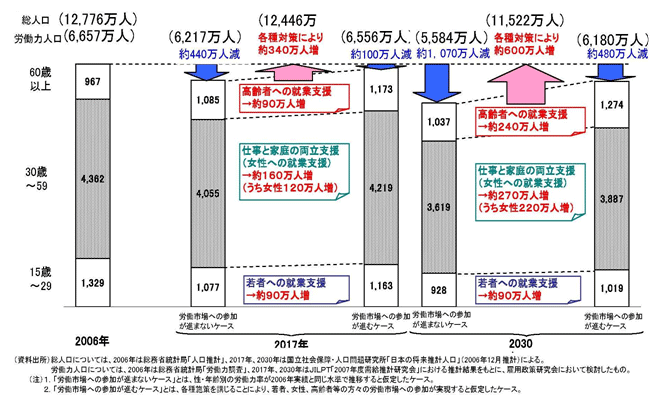
2.福祉・介護人材の現状
(1) 福祉・介護分野に従事する方々は、平成17年現在で約328万人であり、中で高齢者分野に従事する方々が約197万人と約6割を占めており、これらの高齢者分野に従事する方々のうち、介護職員の方々については、今後、平成26年までに約40万人から約60万人の確保が必要となるといった推計がなされています。
(2) また、福祉・介護人材の確保が喫緊の課題となっている中、福祉・介護分野の職場の状況を見ると、
(1) 他の産業と比較して離職率が高い
(2) 常態的に求人募集が行われ、一部の地域では人手不足感が生じている
(3) 介護福祉士国家資格取得者約47万人のうち、実際に福祉・介護分野で従事している方々は約27万人に留まっており、残りの約20万人はいわゆる「潜在介護福祉士」となっている
など、様々な課題があります。
(参考4)福祉・介護人材の現状
○ 福祉・介護従事者の現状
【従事者数(平成17年10月)】 約328万人
※ うち、介護保険サービスで従事する介護職員数 約112万人
【決まって支給する現金給与額】
| 区 分 | 勤続年数 | きまって支給する 現金給与額 |
| 年 | 千円 | |
| 全労働者 | 11.8 | 330.6 |
| 福祉施設介護員(男) | 4.9 | 225.9 |
| 〃 (女) | 5.2 | 204.4 |
| ホームヘルパー(女) | 5.1 | 207.4 |
※ 資料「平成19年賃金構造基本統計調査」
【有効求人倍率(平成19年度介護関連職種)】
| 〔常用〕 | 〔パート〕 | |
| ○ 全 国 | 2.10倍(全職業:0.97倍) | 3.48倍(全職業:1.30倍) |
| ○ 東 京 | 3.52倍(全職業:1.30倍) | 6.27倍(全職業:1.95倍) |
※ 資料「職業安定業務統計」
【入職率・離職率(平成19年)】
| 介護職員+ホームヘルパー | 入職率 27.4%(全労働者:16.0%) |
| 離職率 21.6%(全労働者:16.2%) |
※ 全労働者の数値については、平成18年の数値。
※ 資料:介護職員+ホームヘルパー:事業所における介護労働実態調査(平成20年7月)(介護労働安定センター)
※ 全労働者:「雇用動向調査(平成18年)」
【介護職員数の将来推計】
今後10年間に約40万人から約60万人の介護職員が必要
※ 今後の後期高齢者数や要介護認定者数の伸び率をもとに介護職員数を推計
3.人材確保指針の見直し
(1) 厚生労働省においては、1及び2で述べてきたような状況を踏まえ、将来にわたって福祉・介護人材が安定的に確保されるよう、平成5年に策定された「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」を平成19年8月に見直し、経営者、関係団体等並びに国及び地方公共団体が行うべき人材確保のための取組を改めて整理しました。
(2) この指針では、
ア 就職期の若年層から魅力ある仕事として評価・選択されるようにし、さらには従事者の定着の促進を図るための「労働環境の整備の推進」
イ 今後、ますます増大する福祉・介護ニーズに的確に対応し、質の高いサービスを確保する観点から、従事者の資質の向上を図るための「キャリアアップの仕組みの構築」
ウ 国民が、福祉・介護サービスの仕事が今後の少子高齢社会を支える働きがいのある仕事であること等について理解し、福祉・介護サービス分野への国民の積極的な参入・参画が促進されるための「福祉・介護サービスの周知・理解」
エ 介護福祉士や社会福祉士等の有資格者等を有効に活用するため、潜在的有資格者等の掘り起こし等を行うなどの「潜在的有資格者等の参入の促進」
オ 福祉・介護サービス分野において、新たな人材として期待される、他分野で活躍している人材、高齢者等の「多様な人材の参入・参画の促進」
の5つの視点を柱として、福祉・介護人材確保のために関係者が連携して行うべき取組を整理しています。
(参考5)「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(平成19年厚生労働省告示第289号)
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/fukusijinzai.pdf)
(1〜12ページ(PDF:549KB)、
13〜35ページ(PDF:535KB)、
36ページ(PDF:713KB)、
37〜41ページ(PDF:516KB)、
42ページ(PDF:692KB)、
43ページ(PDF:684KB)、
44〜51ページ(PDF:536KB)、
全体版(PDF:2,098KB))
4.今後の進め方等
(1) 厚生労働省としては、この指針に沿って福祉・介護人材確保のための取組を総合的に進めていくこととしており、平成20年度においては、
(1) 都道府県福祉人材センターにおける無料職業紹介や潜在的有資格者の再就業の支援のための研修の実施等
(2) 福祉・介護の仕事の魅力を伝えるシンポジウム等を行う「福祉人材フォーラム」の開催(7月27日)や国民の「介護」に対する理解を深める「介護の日」(11月11日)の創設
等に取り組んでいます。
(参考6)人材確保指針に関連する厚生労働省の取組
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/fukusijinzai02.pdf)
(PDF:460KB)
(2) また、先の通常国会においては、「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律」が成立し、「平成21年4月1日までに、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え、必要と認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」こととされています。さらに、先般取りまとめられた「社会保障の機能強化のための緊急対策〜5つの安心プラン〜」の中でも、「介護労働者の人材確保及び雇用管理改善の支援」や「福祉・介護サービス従事者の確保・養成の推進」などが盛り込まれているところであり、これらを踏まえつつ、今後さらなる福祉・介護人材確保のための取組について検討を進めていくこととしています。
お問い合わせ先
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader
