II 結果の概要
第1部 たばこに関する状況
第1部 たばこに関する状況
1.喫煙の状況
| 現在習慣的に喫煙している者の割合は、男性で46.8%、女性で11.3%。 |
現在習慣的に喫煙している者(これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている者のうち、「この1ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」と回答した者)の割合は、男性で46.8%、女性で11.3%であり、男性では30歳代、女性では20歳代が最も高く、年齢とともに低くなっていた。 また、過去習慣的に喫煙していた者(これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている者のうち、「この1ヶ月間にたばこを吸っていない」と回答した者)の割合は、男性で年齢とともに高くなっていた。
図1 喫煙の状況
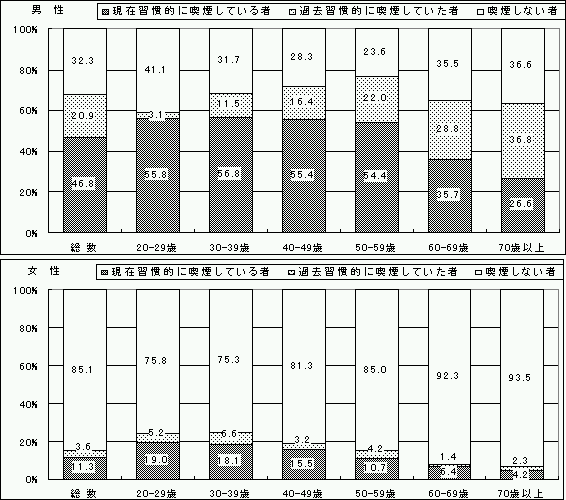
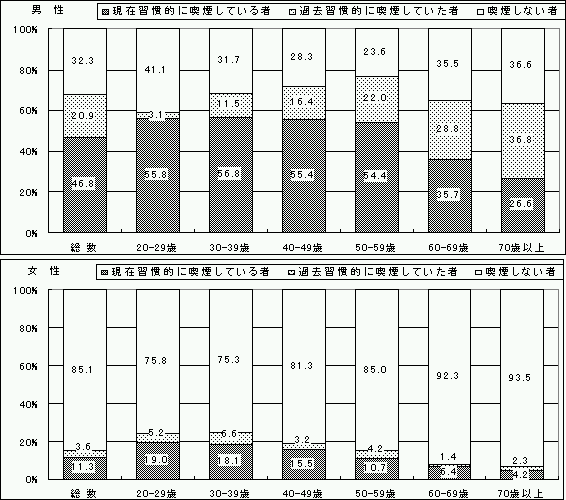
|
2.この1ヶ月間にたばこを吸っている者
|
この1ヶ月間にたばこを吸っている者の割合は、男女とも20歳代が最も高く、20〜50歳代男性では5割以上。 平成10年調査に比べ、この1ヶ月間にたばこを吸っている者の割合は、男女とも総数で低下。 |
この1ヶ月間にたばこを吸っている者(喫煙歴に関係なく「この1ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」と回答した者)の割合は、20〜50歳代男性では5割以上、20〜40歳代女性の約2割であり、男女とも20歳代で最も高く、年齢とともに低くなっていた。
また、「平成10年度喫煙と健康問題に関する実態調査」(以下「平成10年調査」という。)に比べ、この1ヶ月間にたばこを吸っている者の割合は、男女とも総数で低くなっていた。
図2 この1ヶ月間にたばこを吸っている者の割合
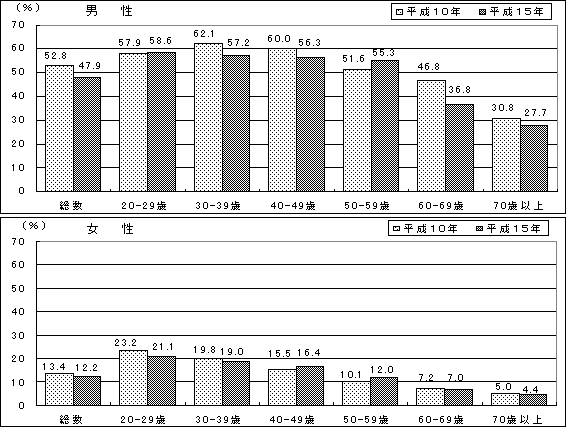
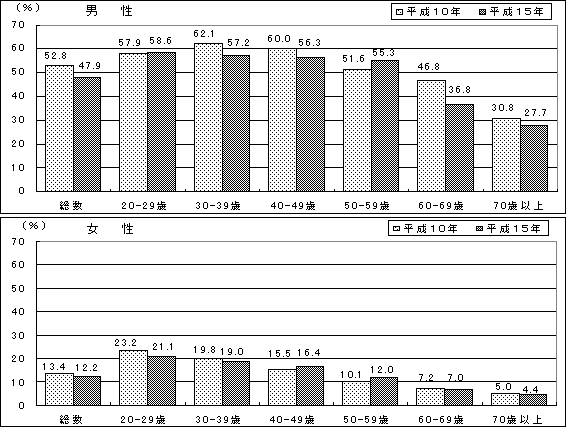
|
喫煙に関する平成10年のデータは、全て「平成10年度喫煙と健康問題に関する実態調査」結果より引用。(調査客体:平成10年国民生活基礎調査により設定された単位区から層化無作為抽出した300単位区内の世帯及び世帯員。20歳以上の客体数は12,034人。) 両調査とも問は以下のとおりであり、この1ヶ月間にたばこを吸っている者の割合の定義は、喫煙歴に関係なく、「この1ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸う」と回答した者が全体に占める割合とした。 問.「現在(この1ヶ月間)、あなたはたばこを吸っていますか。」 1 毎日吸う 2 ときどき吸っている 3 今は(この1ヶ月間)吸っていない |
3.たばこが健康に与える影響の認識
|
たばこが健康に与える影響について「とても気になる」と回答した者の割合は、女性では5割以上、成人男性では3〜4割。 平成10年調査に比べ、「とても気になる」と回答した者の割合は、5.1%増。 |
たばこが健康に与える影響について、「とても気になる」と回答した者の割合は、女性はいずれの年齢階級においても5割以上、15〜19歳男性では約5割であったのに対し、20歳以上の男性では3〜4割であった。
「あまり気にならない」又は「まったく気にならない」と回答した者の割合は、男性では約2割、女性では約1割と男性の方が高かった。
また、総数での平成10年調査との比較では、「とても気になる」と回答した者が増えていたが、「あまり気にならない」又は「まったく気にならない」と回答した者の割合は、変化がみられなかった。
図3 たばこが健康に与える影響の認識
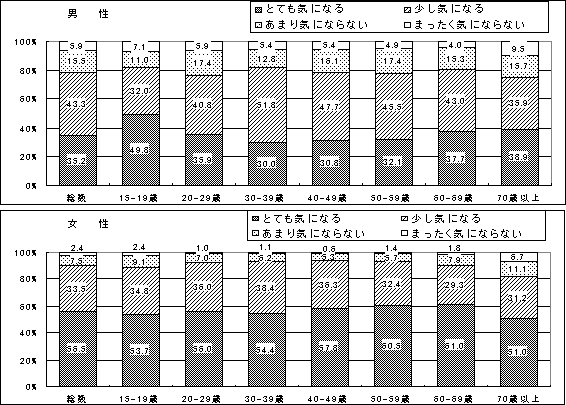
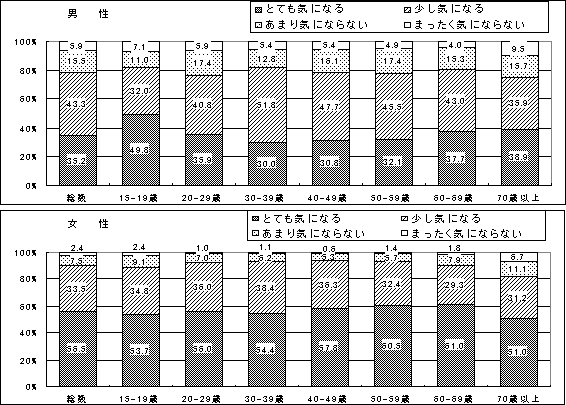
図4 たばこが健康に与える影響の認識(平成10年調査との比較・15歳以上)
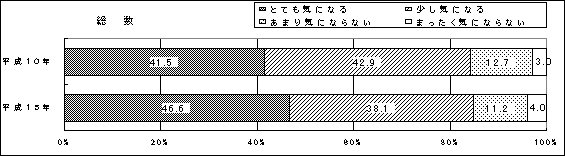
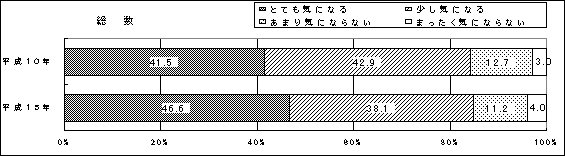
4.喫煙及び受動喫煙の健康影響に関する知識
| たばこが健康に与える影響について、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した者の割合は、「肺がん」、「妊娠への影響」では8割以上、「胃潰瘍」、「歯周病」、「脳卒中」、「心臓病」では5割未満。 |
たばこが健康に与える影響について、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した者の割合は、「肺がん」、「妊娠への影響」では8割以上、「胃潰瘍」、「歯周病」、「脳卒中」、「心臓病」では5割未満であった。
また、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した者の割合は、「胃潰瘍」を除き、平成10年調査に比べ高くなっていた。
「たばこの煙を吸うと病気にかかりやすくなる」と回答した者の割合は平成10年調査に比べ高くなっていたが、「たばこの煙を吸うと心臓病にかかりやすくなる」と回答した者の割合は4割であり、他と比べて低かった。
図5「たばこを吸うと病気にかかりやすくなる」と回答した者の割合(15歳以上・複数回答)
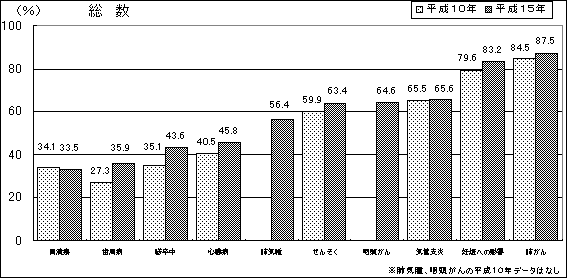
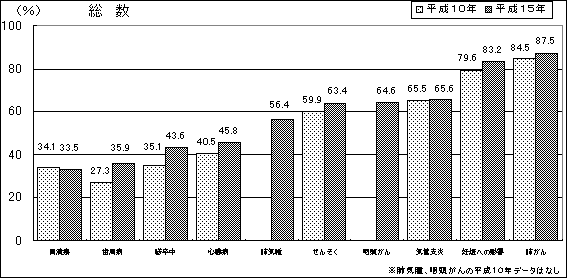
図6「たばこの煙を吸うと病気にかかりやすくなる」と回答した者の割合(15歳以上・複数回答)
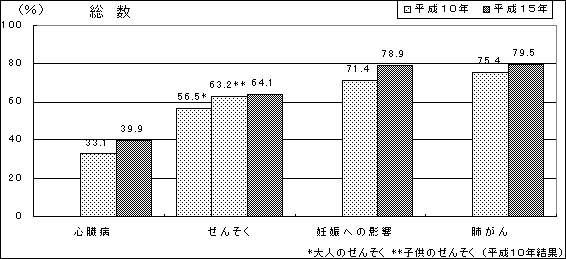
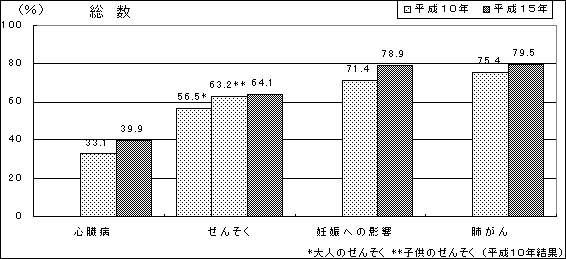
5.禁煙の意思の有無
現在習慣的に喫煙している者のうち、
|
現在習慣的に喫煙している者のうち、「たばこをやめたい」と回答した者の割合は、男性24.6%、女性32.6%、「本数を減らしたい」と回答した者の割合は、男性40.5%、女性35.9%であり、「やめたくない」と回答した者の割合は、男性25.1%、女性19.6%であった。
また、「やめたい」と回答した者の割合が最も高かったのは、男性では60歳代、女性では20歳代で、「やめたい」、「本数を減らしたい」と回答した者の割合をあわせると、全体で男女とも約7割であり、男性では60歳代まで年齢とともに高くなっていた。
図7 現在習慣的に喫煙している者における禁煙の意思
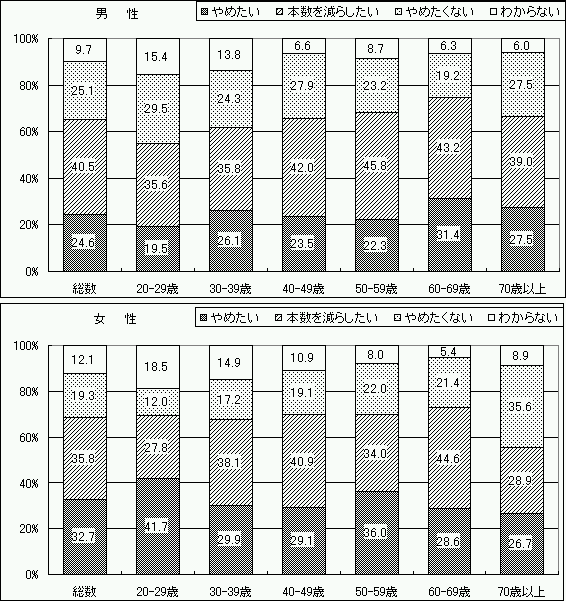
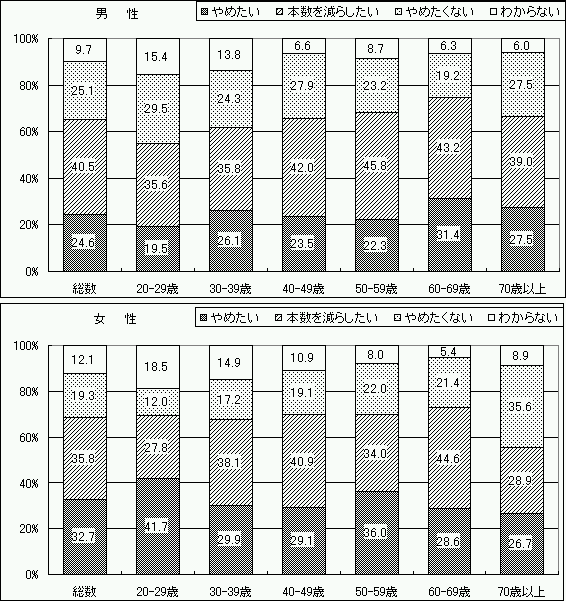
6.禁煙の試み及び禁煙回数
|
現在習慣的に喫煙している者のうち、禁煙を試みたことがある者の割合は、男性で約5割、女性で約6割。 禁煙を試みたことがある者における禁煙回数は、50歳代男性が平均5.7回で 最も多い。 |
現在習慣的に喫煙している者のうち、「禁煙を試みたことがある」と回答した者の割合は、男性で53.5%、女性で61.1%であった。「禁煙を試みたことがある」と回答した者の割合は、男性では20歳代が最も低く、逆に女性では20歳代が最も高かった。
また、現在喫煙している者で禁煙を試みたことがある者の禁煙回数は、平均で男性4.6回、女性3.6回であり、男性では50歳代が5.7回、女性では70歳以上が4.6回と最も高かった。
図8 現在習慣的に喫煙している者における禁煙を試みたことがある者の割合
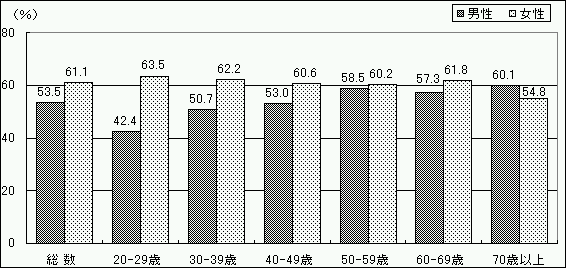
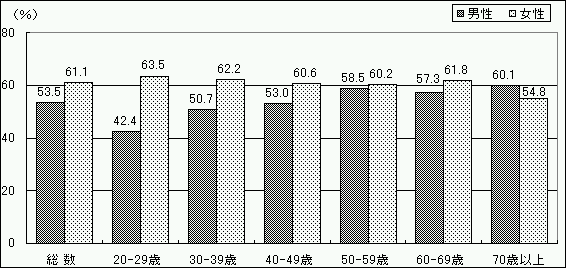
図9 現在習慣的に喫煙している者における禁煙回数(平均値)
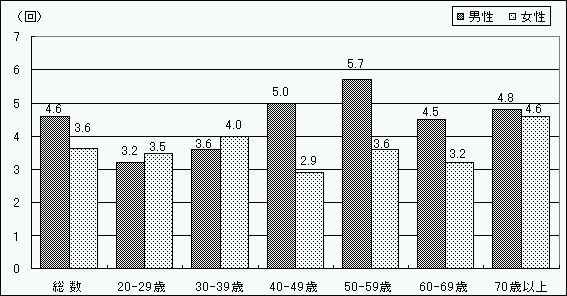
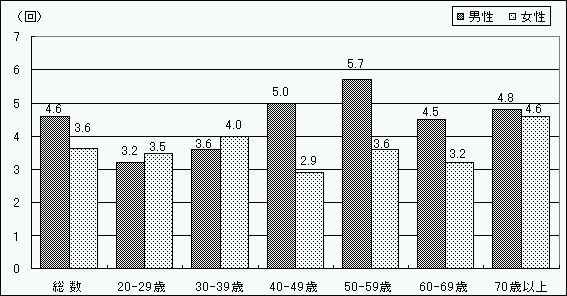
7.1日禁煙することの困難度
|
現在習慣的に喫煙している者のうち、たばこをまったく吸わずに1日過ごすことが「とても難しい」と回答した者の割合は、男性で約5割、女性で約4割。 「難しい」と回答した者をあわせると、男性で約9割、女性で約8割。 |
現在習慣的に喫煙している者のうち、たばこをまったく吸わずに1日過ごすことが「とても難しい」と回答した者の割合は、男性で47.1%、女性で35.3%。「難しい」と回答した者をあわせると、男性で86.6%、女性で80.9%であった。
また、男性より女性の方が、禁煙することに対して「やさしい」、「とてもやさしい」と回答した者の割合が高かった。
図10 現在習慣的に喫煙している者における1日禁煙することの困難度
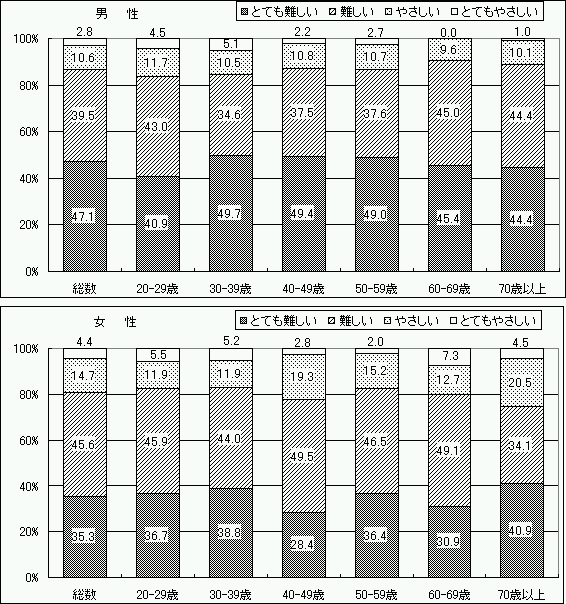
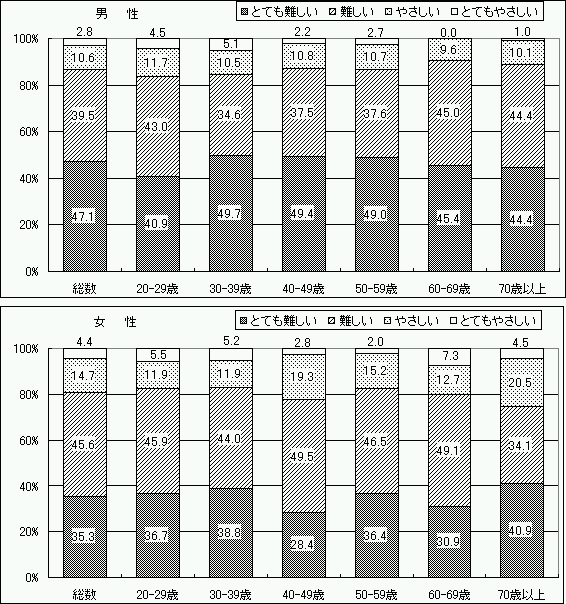
8.1日の喫煙本数
|
現在習慣的に喫煙している者において、男女とも1日に11〜20本喫煙していると回答した者の割合が最も高い。 40〜50歳代男性の約2割は、31本以上喫煙。 |
現在習慣的に喫煙している者において、男女とも1日に11〜20本喫煙していると回答した者の割合が最も高かった。
また、40〜50歳代男性の約2割が、31本以上喫煙していた。
図11 現在習慣的に喫煙している者における1日の喫煙本数
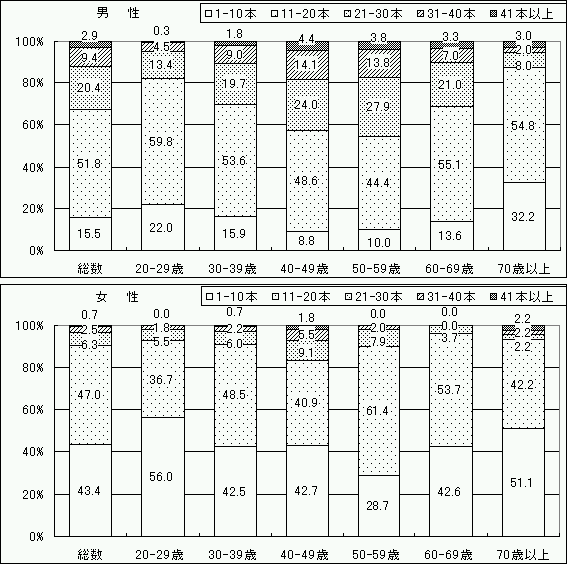
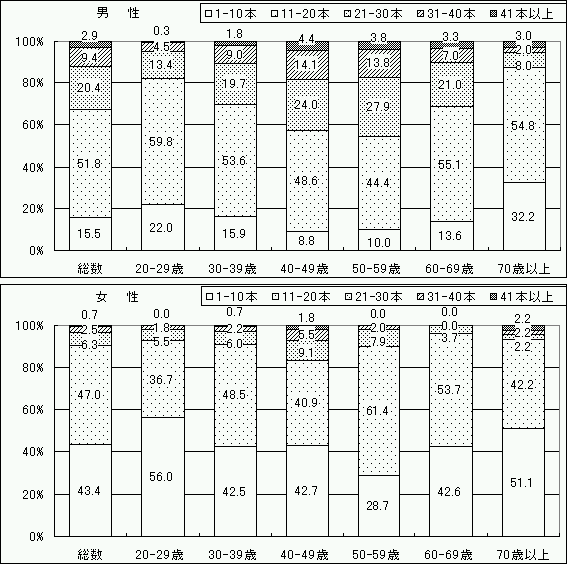
9.受動喫煙と血中コチニン濃度
| たばこを「まったく吸ったことがない」又は「今は(この1ヶ月間)吸っていない」と回答した者のうち、家庭又は職場で受動喫煙の機会が多かった者ほど、血中コチニン濃度が高かった。 |
たばこを「まったく吸ったことがない」又は「今は(この1ヶ月間)吸っていない」と回答した者における、家庭又は職場での受動喫煙(室内等において、他人のたばこの煙を吸わされること)の状況別に血中コチニン濃度をみると、受動喫煙が「時々あった」、「ほぼ毎日あった」と回答した者は、「全くない」と回答した者に比べて、血中コチニン濃度が高かった。
図12 家庭又は職場での受動喫煙状況別、血中コチニン濃度
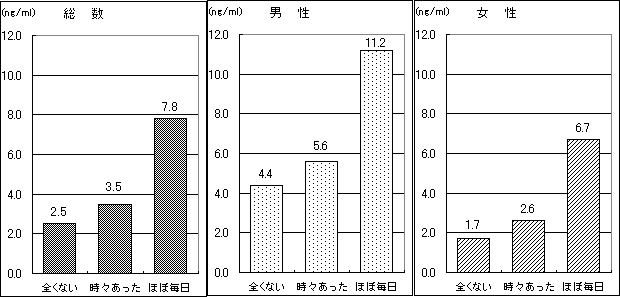
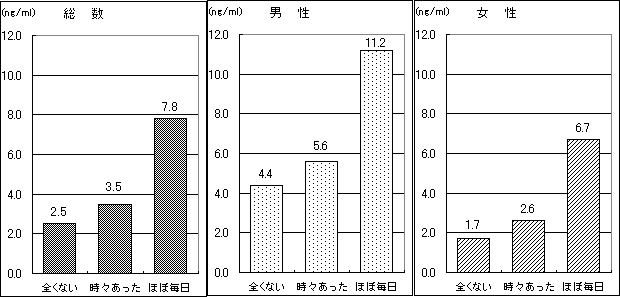
|
コチニン: たばこの煙に含まれる成分の一つであるニコチンが体内で代謝されてできる物質で、受動喫煙の程度を示す指標の一つ。 |
第2部 肥満、運動習慣の状況
1.体型の状況
| 30〜60歳代男性の3割以上が肥満。20歳代女性の2割以上が低体重(やせ)。 |
30〜60歳代男性、60歳代女性の3割以上に肥満がみられた。男性では30〜60歳代まで肥満の割合が横ばいであるのに対し、女性では60歳代まで年齢とともに肥満の割合が高くなっていた。
一方、低体重(やせ)の者の割合は、20歳代女性で2割を超えていた。
図13 BMIの区分による肥満、普通体重、低体重の者の割合
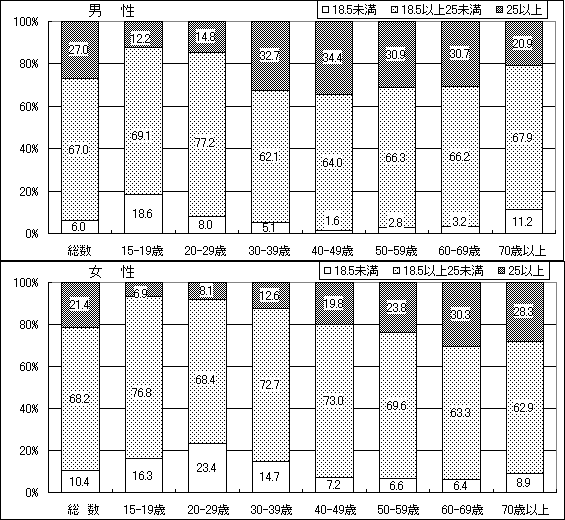
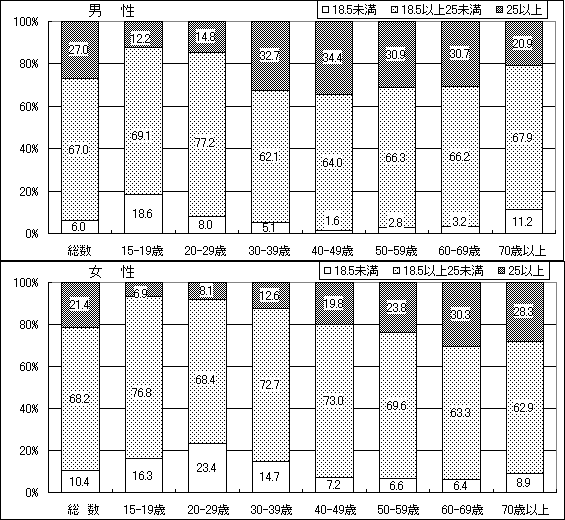
(日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会、2000年)
|
|
2.肥満者の年次推移
| 肥満者の割合は、男性ではいずれの年齢階級においても昭和58年に比べ増加。 |
男性の肥満者の割合は、いずれの年齢階級においても昭和58年に比べ増加していた。
また、女性の肥満者の割合は、昭和58年、平成5年に比べ、70歳以上では増加、40〜50歳代では減少していた。
図14 肥満者の(BMI≧25)の割合
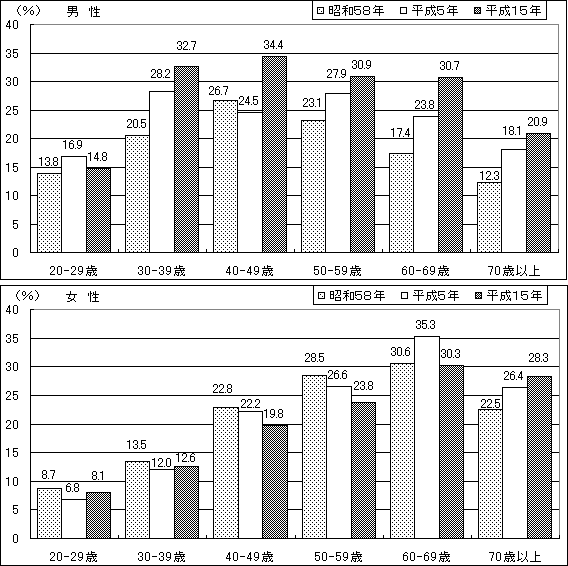
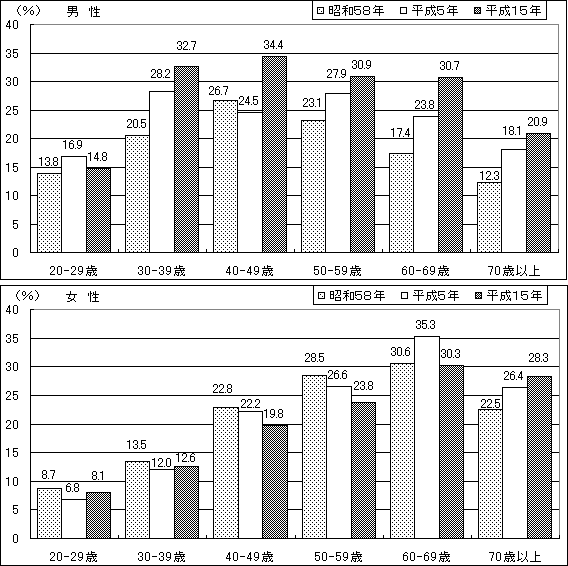
3.BMIと腹囲計測による肥満の状況
| 30〜60歳代男性の約3割が上半身肥満の疑い。 |
平成15年調査から腹囲の計測を始めたところ、上半身肥満が疑われる者の割合は、男性で24.9%、女性で13.8%であった。
また、30〜60歳代男性の約3割に、上半身肥満が疑われた。
図15 BMIと腹囲計測による肥満の状況
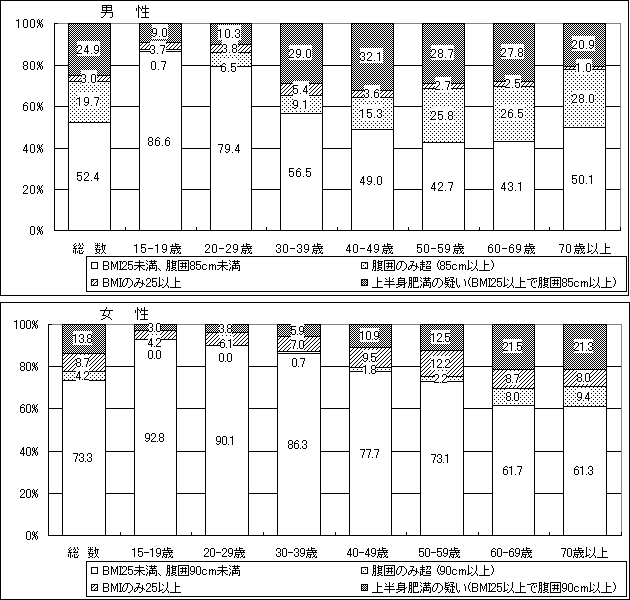
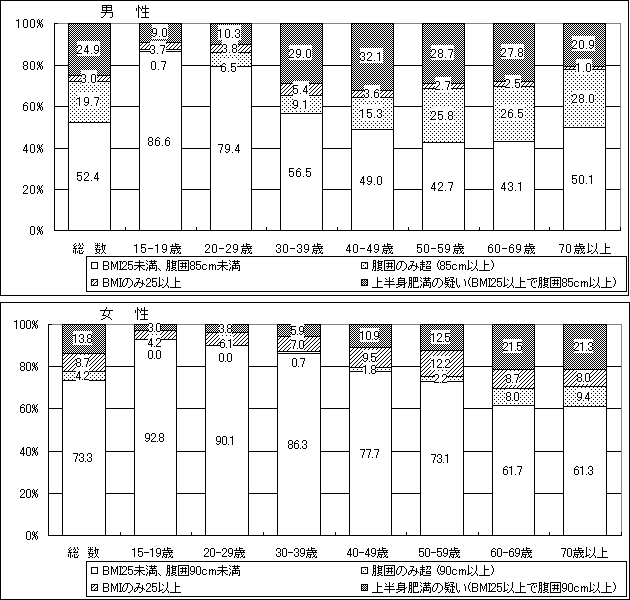
(参考)内臓脂肪型肥満の診断基準:
|
4.運動習慣の状況
|
運動習慣のある者の割合は、男女とも60歳代で最も高い。一方、20〜50歳代男性、20〜40歳代女性では運動習慣のある者の割合が低い。 10年前に比べ、運動習慣のある者の割合は、総数では男女とも増加。 |
運動習慣のある者(1回30分以上の運動を週2日以上実施し、1年以上継続している者)の割合は、男女とも60歳代で最も高く、一方、20〜50歳代男性、20〜40歳代女性では運動習慣のある者の割合が低かった。
また、10年前に比べ、運動習慣のある者の割合は、総数では男女とも増加していた。
図16 運動習慣のある者の割合
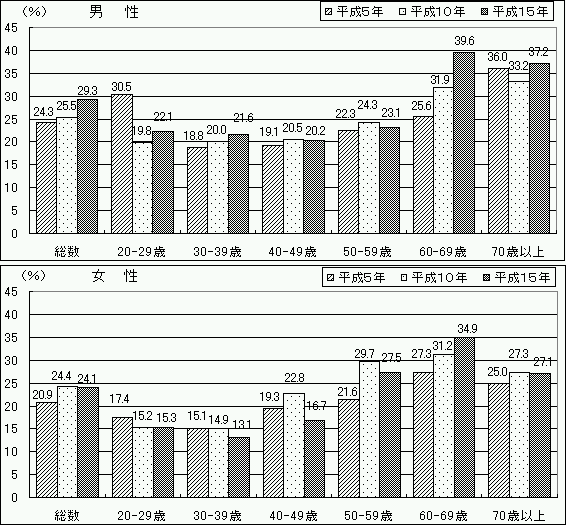
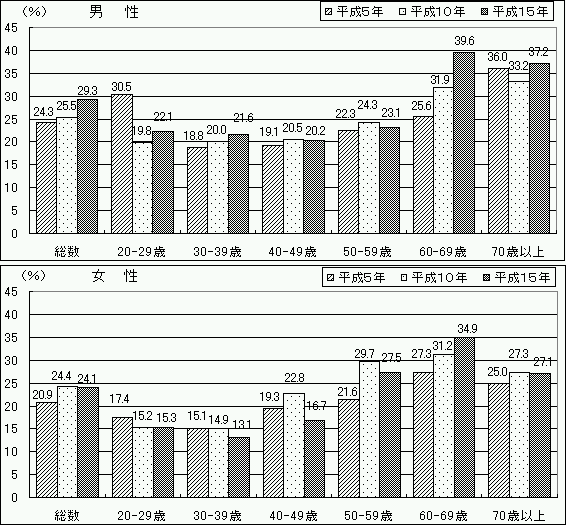
|
運動習慣のある者: 1回30分以上の運動を週2日以上実施し、1年以上継続している者 |
| |||||||||
第3部 栄養素等摂取、食品群別摂取の状況
1.食塩摂取量
| 食塩摂取量は、全体の平均で11.2gであり、年々減少。 |
食塩摂取量は、全体の平均で11.2gであり、平成7年以降年々減少している。 年齢階級別にみると、男女とも年齢とともに摂取量が増加し、60歳代で男性13.5g、女性12.0gと最も高かった。
図17−1 食塩摂取量(年次推移)
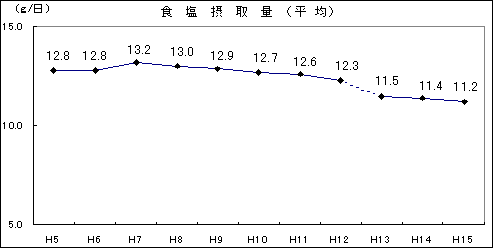
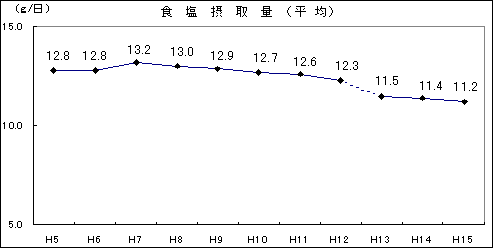
| 注) | 平成12年までは四訂日本食品標準成分表、 平成13年からは五訂日本食品標準成分表を用いて算出している。 |
図17−2 食塩摂取量(性・年齢階級別)
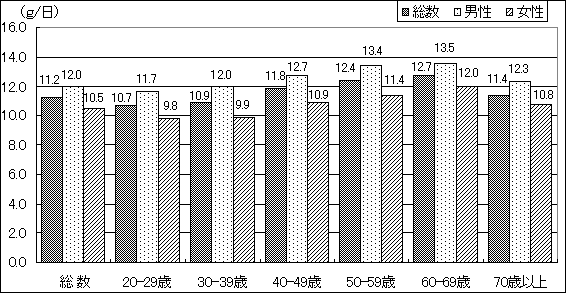
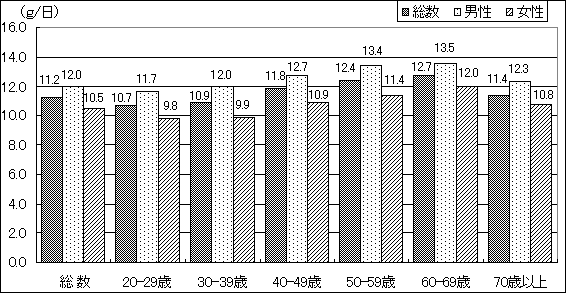
| 食塩摂取量(g)= ナトリウム(mg)× 2.54 / 1,000 |
|
2.エネルギーの栄養素別摂取構成
| 脂肪からのエネルギー摂取割合は、20〜30歳代男性と20〜40歳代女性で、 適正比率である25%を超えていた。 |
図18−1 エネルギーの栄養素別摂取構成比(年次推移 総数)
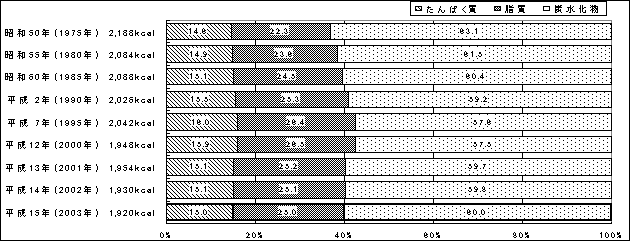
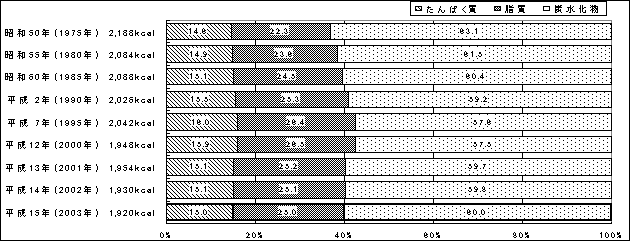
図18−2 エネルギーの栄養素別摂取構成比(平成15年結果 性・年齢階級別)
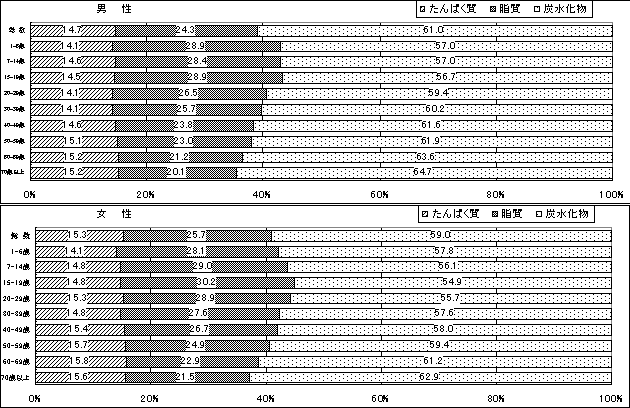
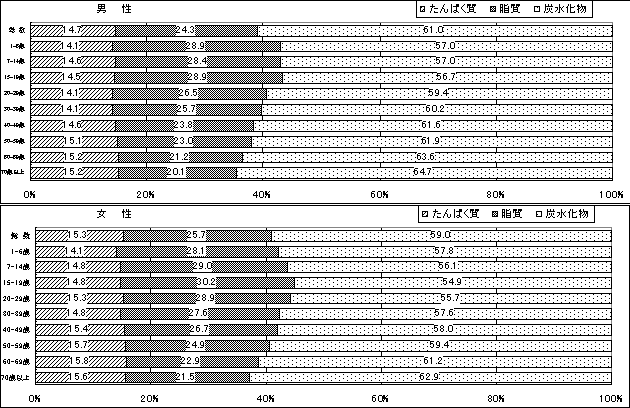
(参考)
|
3.補助食品等からのビタミン・ミネラルの摂取状況
| 20歳以上で、補助食品等からビタミン・ミネラルを摂取している者の割合を栄養素別にみると、最も多いビタミンB1で5.3%。 |
食生活や栄養素摂取の多様化に対応するため、平成15年国民健康・栄養調査から、調査対象としている栄養素のうち、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンC、ビタミンE、カルシウム及び鉄については、補助食品等からの摂取量※)についても新たに把握した。
20歳以上で、補助食品等からビタミン・ミネラルを摂取している者の割合を栄養素別にみると、最も多いビタミンB1で5.3%、ビタミンB2及びビタミンB6で5.2%、ビタミンCで4.1%、カルシウムで2.9%、ビタミンEで2.8%、鉄で1.3%であった。
また、補助食品等を「摂取している者」と「摂取していない者」別の通常の食品からの摂取量は、ほぼ同量であった。補助食品等を摂取している者をみると、その内訳は補助食品からの摂取が多く、ミネラルについては強化食品からの摂取も多かった。
表1 補助食品等の摂取の有無別、ビタミン・ミネラルの摂取状況(20歳以上)
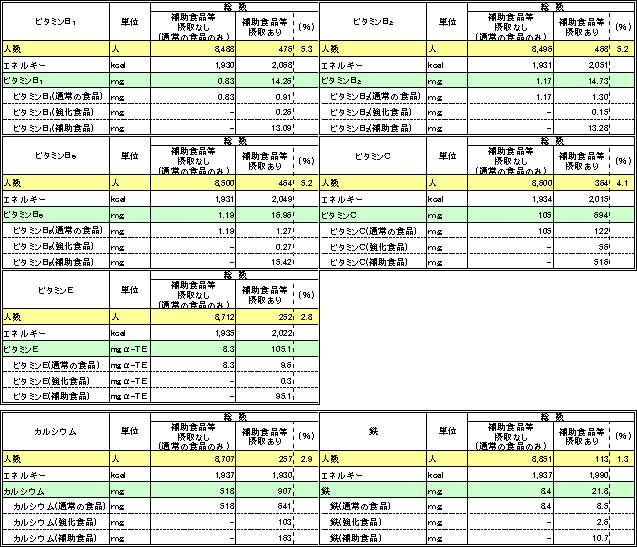
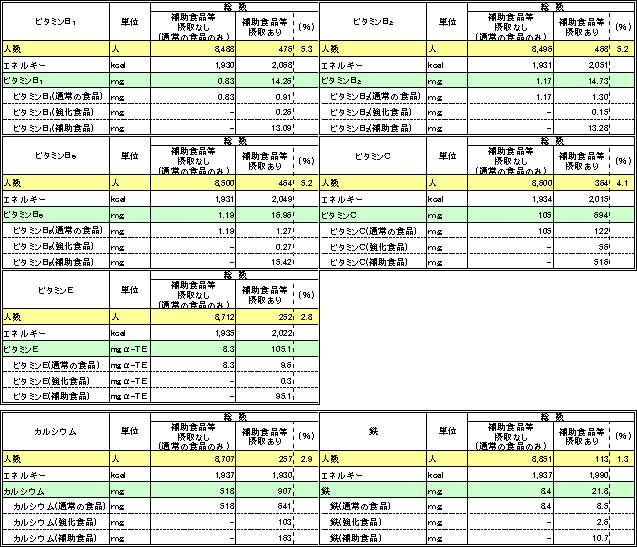
図19−1 ビタミンB1 摂取量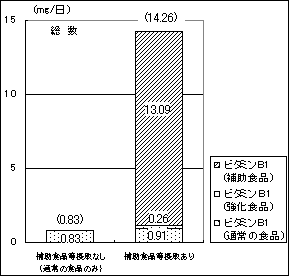 |
図19−2 ビタミンB2摂取量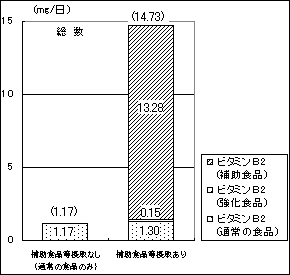 |
|
図19−3 カルシウム摂取量 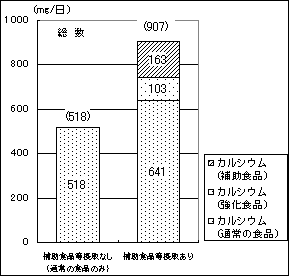 |
図19−4 鉄摂取量 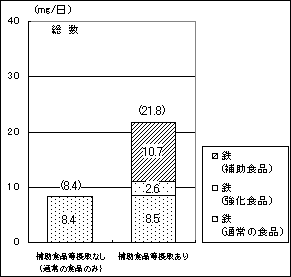 |
|
表中の「通常の食品」「強化食品」「補助食品」は次のとおりである。
|
4.食品群別摂取量
(1)野菜摂取量
| 野菜摂取量は、年齢とともに増加していたが、最も多い60歳代においても、平均で339.3g。 |
野菜類の摂取量は、全体の平均で277.5gであった。若年ほどその摂取量は少なく、年齢とともに増加していたが、最も多い60歳代においても平均で339.3gであった。
図20−1 野菜摂取量(総数)
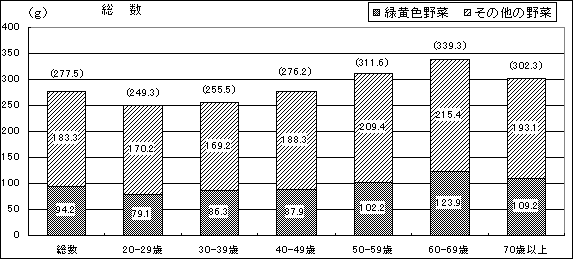
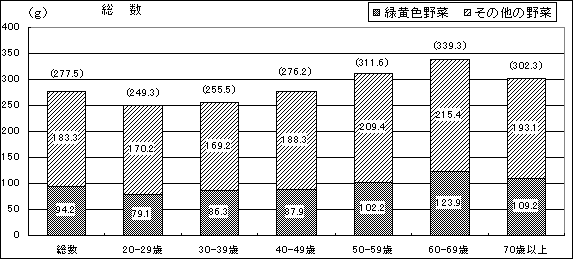
図20−2 野菜摂取量(性・年齢階級別)
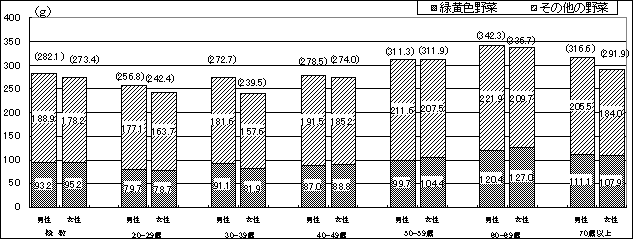
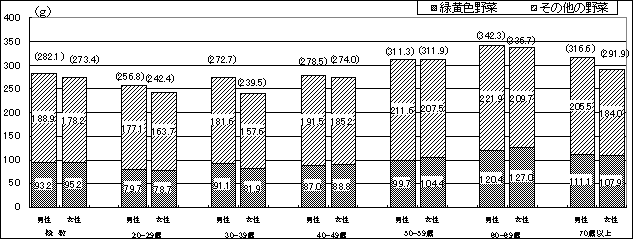
|
( )内は、「緑黄色野菜」と「その他の野菜」摂取量の合計。 なお、数値は四捨五入のため、内訳合計が総数に合わないことがある。 |
|
(2)穀類摂取量
穀類の摂取量は、男性では15〜19歳の625gが最も多く、成人では年齢階級が上がるに従って、摂取量は少なくなっていた。女性では60歳代の419.2gが最も多く、20歳代で375.4gと最も少なかった。
(3)魚介類及び肉類摂取量
魚介類と肉類の摂取量は、男女とも30歳代まで肉類の摂取量が多いが、40歳代からは逆に魚介類の摂取量が多くなっていた。
(4)果実類摂取量
果実類の摂取量は、男女とも30歳代で最も少なく、総数で1日当たり63.2gであった。
表2−1 年齢階級別 食品群別摂取量(総数)
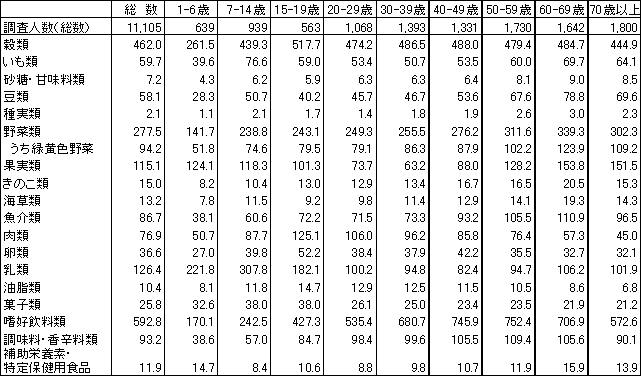
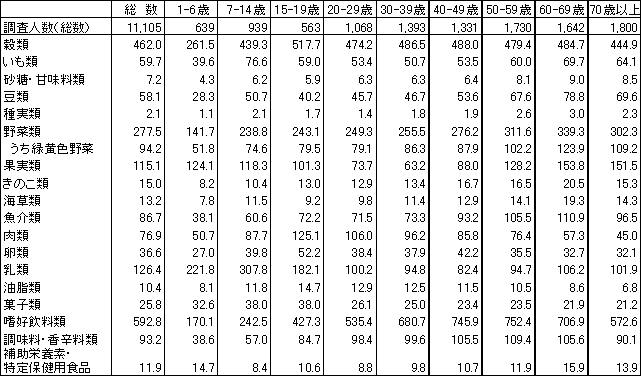
|
補助栄養素・特定保健用食品: 顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品及び 特定保健用食品からの摂取量 |
表2−2 年齢階級別 食品群別摂取量(男性)
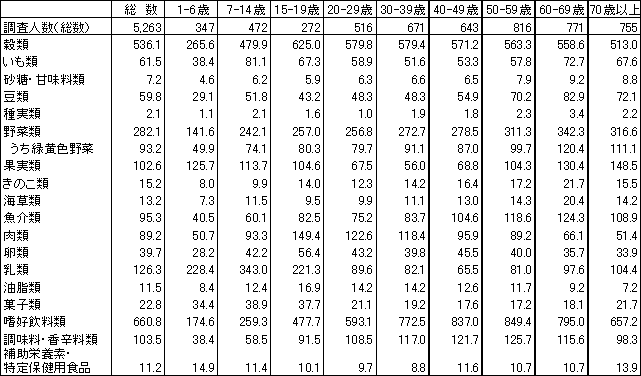
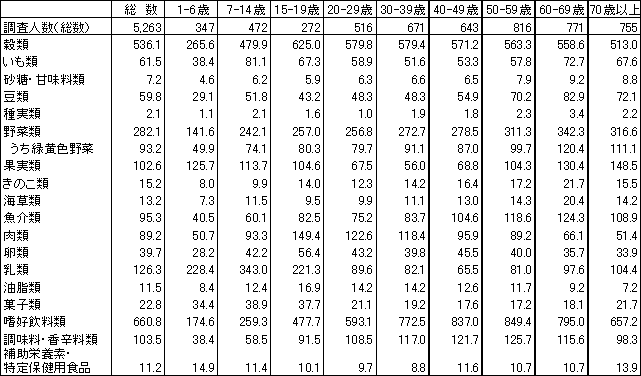
表2−3 年齢階級別 食品群別摂取量(女性)
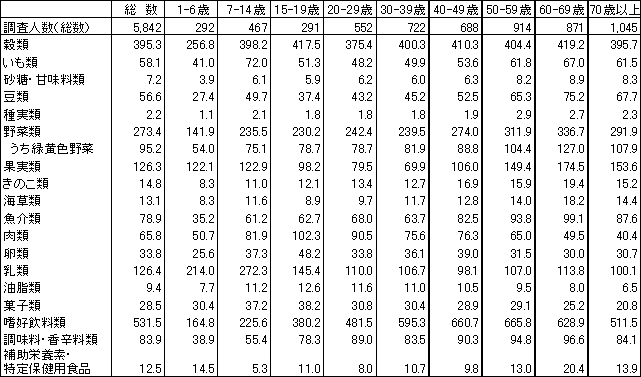
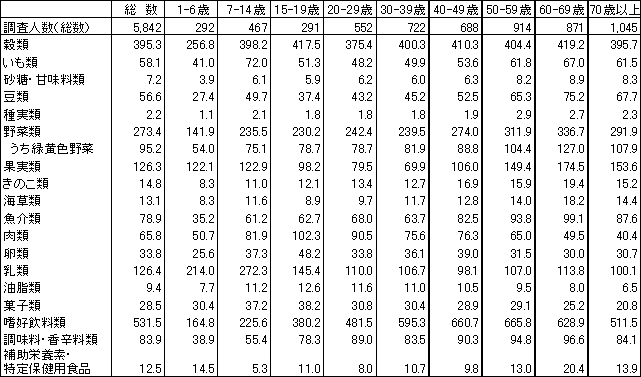
|
補助栄養素・特定保健用食品: 顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品及び 特定保健用食品からの摂取量 |
5.栄養素等摂取量
表3−1 年齢階級別 栄養素等摂取量(総数)
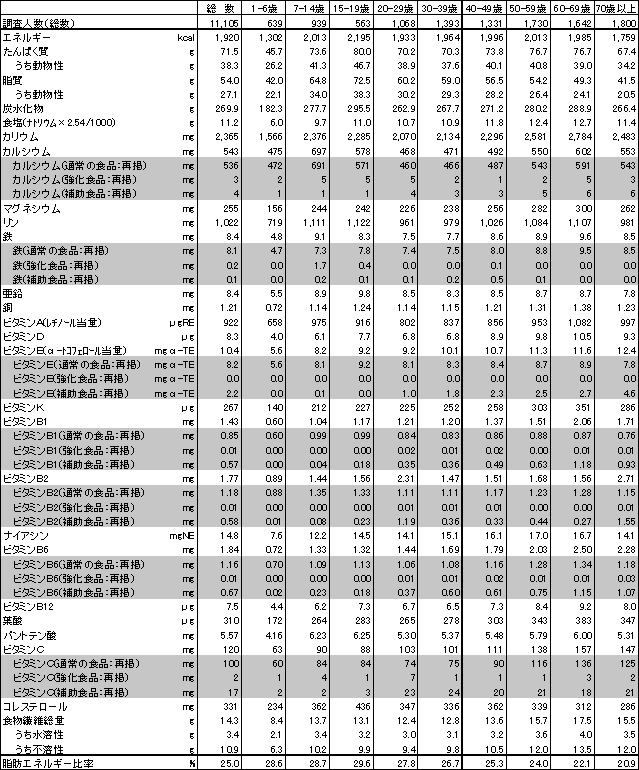
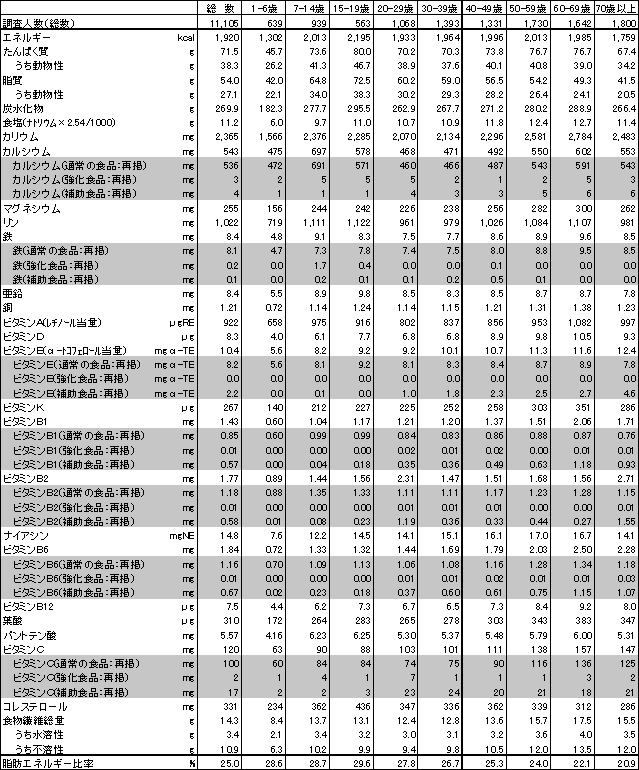
表中の「通常の食品」「強化食品」「補助食品」は次のとおりである。
|
表3−2 年齢階級別 栄養素等摂取量(男性)
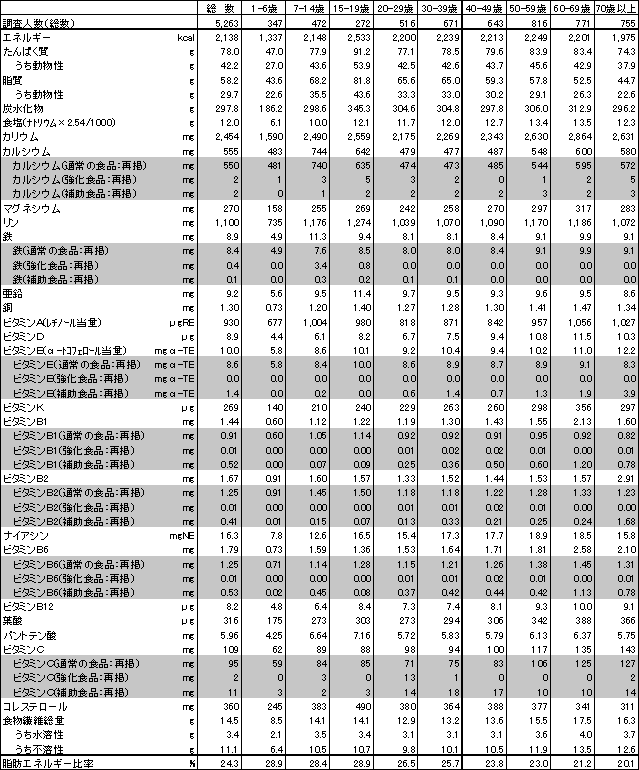
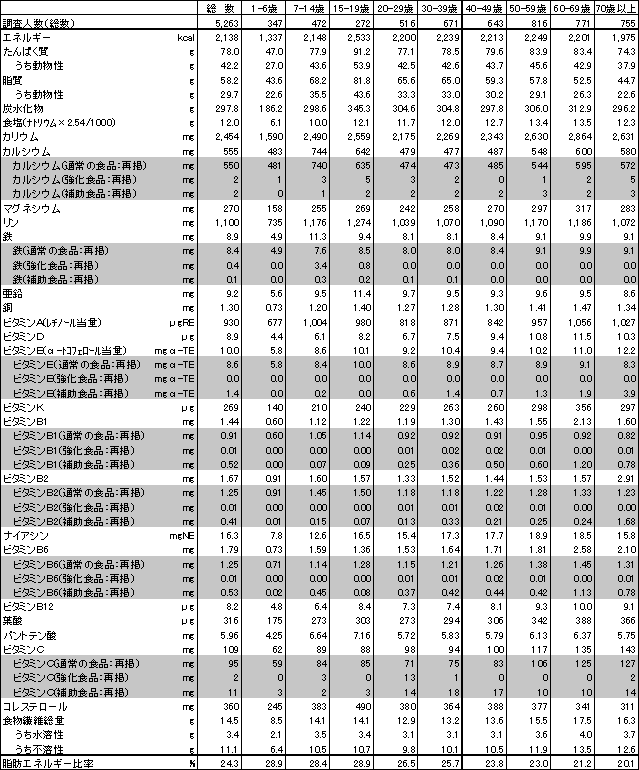
表中の「通常の食品」「強化食品」「補助食品」は次のとおりである。
|
表3−3 年齢階級別 栄養素等摂取量(女性)
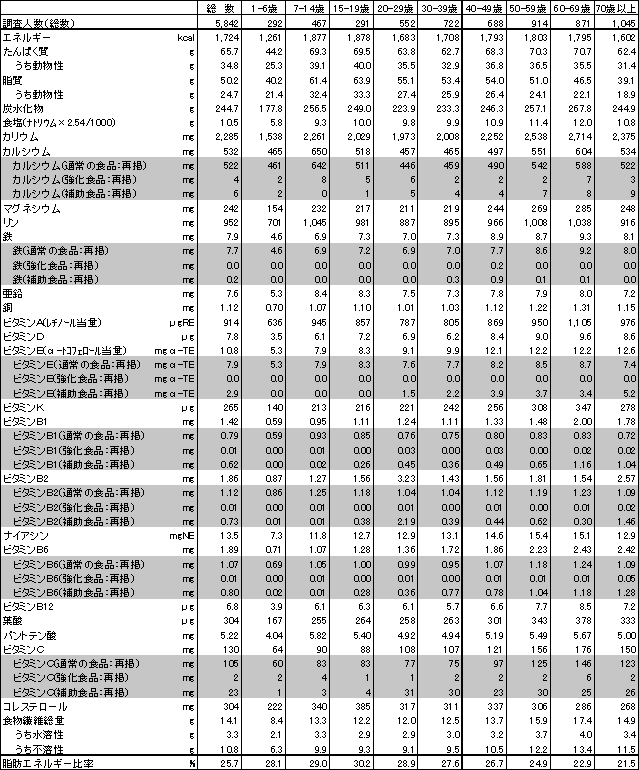
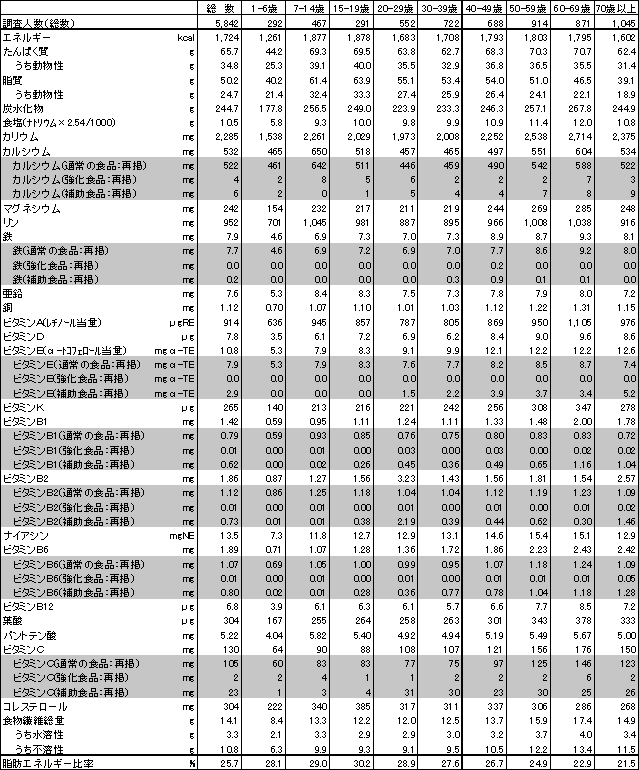
表中の「通常の食品」「強化食品」「補助食品」は次のとおりである。
|