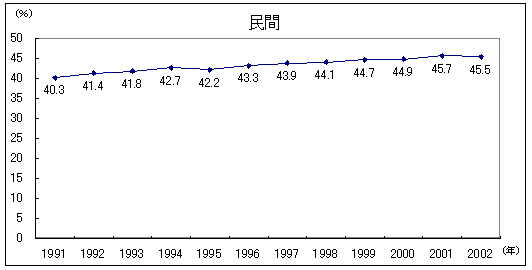
�i�����o���j�@ U.S. Bureau of Labor Statistics "Employment & Earnings"
| �����J���� �����P�U�N�U���Q�Q�� |
|
�@���a�U�O�N�̒j���ٗp�@��ϓ��@�̐�����A�j�������ɑ���Љ�̈ӎ��ɂ͑傫�ȕω���������ƂƂ��ɁA����9�N�̖@�����ɂ���Ă���܂œw�͋`���K��ł�������W�E�̗p��z�u�E���i���܂ߏ����ɑ��鍷�ʂ��֎~����A�܂��A�����ɑ���D���[�u�������֎~�Ƃ����ȂǁA�䂪���̌ٗp�̕���ɂ�����j���̋ϓ��戵���͓O�ꂪ�}���Ă����Ƃ���ł��邪�A�j�������ɂ��̎��Ă�͂��\���ɔ����ł���悤�ȎЉ���\�z���邽�߂ɂ́A�Ȃ��ۑ肪�c����Ă���Ƃ���ł���B
�@���̂��߁A�����J���Ȃł́A�w���o���҂̎Q�W�����߁A�����P�S�N�P�P�����u�j���ٗp�@��ϓ�������v�i�����F���R���ǐ����w�@�w�������j���J�Â��A�j���o���ɑ��鍷�ʂ̋֎~�A�D�P�E�o�Y���𗝗R�Ƃ����s���v�戵���A�Ԑڍ��ʂ̋֎~�A�|�W�e�B�u�E�A�N�V�����̌��ʓI���i����̂S�̎����ɂ��āA�j���ϓ��̎������ǂ����i���Ă����̂��Ƃ����ϓ_�ɗ����Č�����i�߂Ă����B���̂��сA���̌������ʂ��ʓY�̂Ƃ�����܂Ƃ߂�ꂽ�̂ŁA���̓��e�����\����B
�@����A�����J���ȂƂ��Ă͂��̕��A�j���ٗp�@��ϓ��̍X�Ȃ鐄�i�̂��߂̕���ɂ��āA�J�������R�c��ٗp�ϓ����ȉ�ɂ����Č��������Ă����������ƂƂ��Ă���B
| �P | �@�͂��߂� �@�ٗp�̕���ɂ�����j���̋ϓ��戵����}���łS�̌��������͂��ꂼ��d�v�ȉۑ�ł���A��������O�����ȑΉ����]�܂��B����A�{�����āA�W�҂̋c�_���o�ēK�ȑΉ��A�[�u���u�����邱�Ƃ��肤���̂ł���B |
| �Q | �@�j���o���ɑ��鍷�ʂ̋֎~ |
| �i�P�j | �@�����̌o�� �@���蓖���͏������L���Ɉ����邱�Ƃ����e���Ă����ϓ��@�������X�N�����ŏ����ɑ���D���������֎~�Ƃ������A��i�����ł͊T�˒j���o����Ώۂɍ��ʂ��֎~���Ă���A�䂪���̂��̌�̖@���̓������j���o����ΏۂƂ��Ă��铙����A���߂Ēj���o�����ʋ֎~�̈Ӌ`�����邱�Ƃ��K�v�B | ||||
| �i�Q�j | �@�����ɑ��鍷�ʋ֎~��j���o���ɑ��鍷�ʋ֎~�Ƃ���Ӌ`
| ||||
| �i�R�j | �@�j���o���ɑ��鍷�ʂ̋֎~�Ə����J���҂ɌW�����[�u�Ƃ̊W
|
| �R | �@�D�P�A�o�Y���𗝗R�Ƃ���s���v�戵�� |
| �i�P�j | �@�����̌o��
| ||||||||||||
| �i�Q�j | �@�䂪���ɂ�����ٔ���̓��� �@�ō��ٔ����ł͎Y�x�擾�𗝗R�Ƃ����s���v�戵���ɂ��āA�J������Ȃ����������ɉ����������̌��z���͋��e�����Ƃ��Ă��A�@����̌����s�g��}�����A�@�����J���҂Ɍ�����ۏႵ����|�������I�Ɏ��킹��悤�ȕs���v�Ȏ戵���͋�����Ȃ��Ɣ����B | ||||||||||||
| �i�R�j | �@���O���ɂ�����D�P�E�o�Y���𗝗R�Ƃ����s���v�戵��
| ||||||||||||
| �i�S�j | �@�䂪���ɂ����ĔD�P�E�o�Y���𗝗R�Ƃ���s���v�戵������������ɓ������ė��ӂ��ׂ�����
|
| �S | �@�Ԑڍ��ʂ̋֎~ |
| �i�P�j | �@�����̌o��
| ||||||||||||||
| �i�Q�j | �@�Ԑڍ��ʂ̊T�O
| ||||||||||||||
| �i�R�j | �@���O���ɂ�����Ԑڍ��ʖ@���̏�
| ||||||||||||||
| �i�S�j | �@�䂪���ɂ����ĊԐڍ��ʂ���������ɓ������ė��ӂ��ׂ�����
| ||||||||||||||
| �i�T�j | �@�Ԑڍ��ʂƂ��čl�������i�ʓY�j |
| �T | �@�|�W�e�B�u�E�A�N�V�����̌��ʓI���i���� |
| �i�P�j | �@�����̌o�� �@�ߔN�A�����ȍ��ʂ͐���������邪�A�X�l�̈ӎ����ɋN������j���̏������̉��P�́A�|�W�e�B�u�E�A�N�V�����ɂ�邱�Ƃ��K�B�|�W�e�B�u�E�A�N�V�����ɂ��ẮA��Ƃ̃C���[�W�A�b�v��Y������ɂ�������Ƃ̎w�E���Ȃ���A�|�W�e�B�u�E�A�N�V�����ɂ��ẮA��Ƃ̗����͐i�݂��邪�A�Ȃ��傫�ȍL����������������ɂ͎����Ă��Ȃ��B |
||||||||
| �i�Q�j | �@���O���ɂ�����|�W�e�B�u�E�A�N�V�����̎�g ���O���ɂ����čs���Ă����@��(1)�g�p�҂̎���I��g�d�����i�C�M���X�j�A(2)���{���B��Ƃւ̌ٗp���̒�o�`���t���E�R�������{�����A�i�A�����J�j�A(3)�ٗp�����̍쐬���`���t�������i�t�����X�E�X�E�F�[�f���j���l�X�ł���A�����̓o�p���l�X�B |
||||||||
| �i�R�j | �@�䂪���ɂ����ă|�W�e�B�u�E�A�N�V�����̌��ʓI���i�������������ɓ������ė��ӂ��ׂ�����
|
| �� | �@�Ԑڍ��ʂɊY�����邩�ǂ����ɂ��ẮA������̎���ɂ����Ă��A���ۂɂ͌ʋ�̓I�Ȏ��Ă��ƂɎ����F����s���A���f���Ă������̂ł���B |
| �� | �@�O���㐫�����I�Ȋ��������̐��ɕs���v��^���邩�ۂ��y�ѓ��Y����̍������E�������Ɋւ���g�p�҂̍R�قɂ��āA�����I�ɔ��f���s�����̂ł��邱�Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B |
| �� | �@�ȉ��̎���̂���(2)�A(4)�A(6)�A(7)�ɂ��ẮA�����ɕs���v��^���邱�ƂƂȂ����̓K�p���邱�Ƃɂ��ẮA�E�ƂɊւ��铖�Y��������̈ӎv��I���Ɋ�Â����ʂł���Ƃ����_�ő��ƈقȂ��Ă���A��������ʂ̘�ɍڂ��邱�Ƃ͐��ʖ������S������̌Œ艻�ɂȂ��錜�O�����邱�Ƃ���A���������Ԑڍ��ʂ̘�ɍڂ���ׂ����Ăł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ̈ӌ����������������A���ɘ�ɍڂ����ꍇ�ɂ͂ǂ̂悤�ȏꍇ�ɊԐڍ��ʂƂȂ肤��̂��ɂ��Đ����������̂ł���B |
| �@(1) | �@��W�E�̗p�ɓ������Ĉ��̐g���E�̏d�E�̗͂�v���Ƃ������Ƃɂ��A�����̗̍p���j���ɔ�ב������x���Ȃ��ꍇ�ɂ����āA���Y����̍������E�������Ɋւ���ȉ��̂悤�Ȏg�p�҂̍R�ق��F�߂��Ȃ��ꍇ�B
| ||||||
| ��(2) | �@�����E�̕�W�E�̗p�ɓ������đS���]��v���Ƃ������Ƃɂ��A�����̗̍p���j���ɔ�ב������x���Ȃ��ꍇ�ɂ����āA���Y����̍������E�������Ɋւ���ȉ��̂悤�Ȏg�p�҂̍R�ق��F�߂��Ȃ��ꍇ�B
| ||||||
| (3) | �@��W�E�̗p�ɓ������Ĉ��̊w���E�w����v���Ƃ������Ƃɂ��A�����̗̍p���j���ɔ�ב������x���Ȃ��ꍇ�ɂ����āA���Y����̍������E�������Ɋւ���ȉ��̂悤�Ȏg�p�҂̍R�ق��F�߂��Ȃ��ꍇ�B
| ||||||
| ��(4) | �@���i�ɓ������ē]�����]�Όo����v���Ƃ������Ƃɂ��A���i�ł��鏗���̊������������x�j���������Ȃ��ꍇ�ɂ����āA���Y����̍������E�������Ɋւ���ȉ��̂悤�Ȏg�p�҂̍R�ق��F�߂��Ȃ��ꍇ�B
| ||||||
| (5) | �@���������̓K�p��Ƒ��蓖���̎x���ɓ������ďZ���[��̐��ю�i���͎傽�鐶�v�ێ��ҁA��}�{�҂�L���邱�Ɓj��v���Ƃ������Ƃɂ��A���������̓K�p��Ƒ��蓖���̎x�������鏗���̊������j���ɔ�ב������x���Ȃ��ꍇ�ɂ����āA���Y����̍������E�������Ɋւ���ȉ��̂悤�Ȏg�p�҂̍R�ق��F�߂��Ȃ��ꍇ�B
| ||||||
| ��(6) | �@�����̌���ɓ������Đ��Ј���L���Ɉ��������Ƃɂ��A�L���ȏ��������鏗���̊������j���ɔ�ב������x���Ȃ��ꍇ�ɂ����āA���Y����̍������E�������Ɋւ���ȉ��̂悤�Ȏg�p�҂̍R�ق��F�߂��Ȃ��ꍇ�B
| ||||||
| ��(7) | �@���������̓K�p��Ƒ��蓖���̎x���ɓ������ăp�[�g�^�C���J���҂����O�������Ƃɂ��A���������̓K�p��Ƒ��蓖���̎x�������鏗���̊������j���ɔ�ב������x���Ȃ��ꍇ�ɂ����āA���Y����̍������E�������Ɋւ���ȉ��̂悤�Ȏg�p�҂̍R�ق��F�߂��Ȃ��ꍇ�B
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� |
| �� |
| ��L�S�̌����ۑ�͌ٗp�̕���ɂ�����j���̋ϓ��戵����}���ŏd�v�ł���A��������O�����ȑΉ����]�܂��B |
| �i�P�j | �����̌o�� |
| �i�Q�j | �����ɑ��鍷�ʋ֎~��j���o���ɑ��鍷�ʋ֎~�Ƃ���Ӌ` |
| �i�R�j | �j���o���ɑ��鍷�ʂ̋֎~�Ə����J���҂ɌW�����[�u�Ƃ̊W |
| �i�P�j | �����̌o�� |
| �i�Q�j | �䂪���ɂ�����ٔ���̓��� |
| �i�R�j | ���O���ɂ�����D�P�E�o�Y���𗝗R�Ƃ����s���v�戵�� |
| �i�S�j | �䂪���ɂ����ĔD�P�A�o�Y���𗝗R�Ƃ���s���v�戵������������ɓ������ė��ӂ��ׂ����� |
| �i�P�j | �����̌o�� |
| �i�Q�j | �Ԑڍ��ʂ̊T�O |
| �i�R�j | ���O���ɂ�����Ԑڍ��ʖ@���̏� |
| �i�S�j | �䂪���ɂ����ĊԐڍ��ʂ���������ɓ������ė��ӂ��ׂ����� |
| �i�T�j | �Ԑڍ��ʂƂ��čl������� |
| �i�P�j | �����̌o�� |
| �i�Q�j | ���O���ɂ�����|�W�e�B�u�E�A�N�V�����̎�g |
| �i�R�j | �䂪���ɂ����ă|�W�e�B�u�E�A�N�V�����̌��ʓI���i�������������ɓ������ė��ӂ��ׂ����� |
| �E | �@�j���o���ɑ��鍷�ʂ̋֎~ |
| �E | �@�D�P�E�o�Y���𗝗R�Ƃ����s���v�戵�� |
| �E | �@�Ԑڍ��ʂ̋֎~ |
| �E | �@�|�W�e�B�u�E�A�N�V�����̌��ʓI���i���� |
| �i�P�j | �@�����̌o�� �@���s�j���ٗp�@��ϓ��@�́A�����ɑ��鍷�ʂ��֎~���邱�Ƃɂ��A�ٗp�̕���ɂ�����j���̋ϓ��戵�����m�ۂ��悤�Ƃ������̂ł���B���̔w�i�Ƃ��ẮA���ԂƂ��Čٗp�̕���ɂ�����j���̋ϓ��ȋ@��y�ёҋ��̊m�ۂƂ����ϓ_������ƂȂ��Ă���̂́A�����ɑ��鍷�ʂł���Ƃ������Ƃ�����B���̂��Ƃ͂ЂƂ�䂪�������̎���ł͂Ȃ��A�������j���ɔ�וs���Ȉ������鎖��͐��E�I�Ɍ����A���ꂪ�̂ɏ����ɑ��鍷�ʂ�P�p���邽�߂ɍ��ۘA���ō̑����ꂽ���q���ʓP�p���ȂǁA���j�I�ɂ����ۓI�ɂ������ɑ��鍷�ʂ�P�p���邱�Ƃɂ��j�������̎����������g���W�J����Ă����o�߂�����B �@���������āA�j���ٗp�@��ϓ��@�̐��蓖���́A�j���Ɣ�r���ď����ɂ�葽���̋@��^�����Ă��邱�Ƃ�A�������L���Ɉ����Ă��邱�Ƃɂ��ẮA�@�����ڊ֗^����Ƃ���ł͂Ȃ��Ƃ��Ă����Ƃ���ł���B�������A�����X�N�̉����ɂ��A�����̐E��̌Œ艻��j���̐E�������������炵�Ă���Ƃ��āA�����ɑ���D���[�u�������Ƃ��ċ֎~���A���̌��ʁA���˓I���ʂƂ��Ēj���ɑ��鍷�ʂ��֎~����邱�ƂɂȂ�A�j�������̓O��Ɍ������i�W���}���Ă���B �@����A�C�O�ɖڂ�]����ƁA�{������ɂ����čs�������O���̒����̌��ʂ����Ă��A���Ɋ�Â����ʂɂ��Ė@���̋K��̎d���Ƃ��ẮA�C�M���X�̂悤�ɏ����ɑ��鍷�ʂ̋֎~��j���ɂ����p����Ƃ����K��̗���܂߁A������������ʂ��ꎩ�̂��֎~���Ă���A��i�����ł͊T�˒j���o����Ώۂɍ��ʂ��֎~���Ă���ɂ���B�܂��A����11�N�ɐ��������j�������Q��Љ��{�@�╽��14�N�ɒʏ퍑��ɒ�o���ꂽ�u�l���i��@�āv�ɂ����Ă͒j���o����ΏۂƂ��Ă���A���Ԗʂɂ����Ă��A�Ȃ��������ٗp��̉��ŁA��W�A�̗p�𒆐S�ɒj������̍��ʂ̑��k���s���{���J���Ǔ��Ɋ���悤�ɂȂ��Ă��Ă���B �@�����ɑ��鍷�ʂ̋֎~�ɂƂǂ܂炸�j���o���ɑ��鍷�ʂ��֎~���邩�ǂ����Ƃ������́A���s�̒j���ٗp�@��ϓ��@�������ɑ��鍷�ʂ��֎~���邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł��邱�Ƃ���A�@�̊�{���O�ɒ��ڊW������ł���A�@�̌n�S�̂ɉe�����y�ڂ����̂ł��邪�A�����j���ٗp�@��ϓ��@�̎{�s����T�N���o�߂������݁A���߂āA���̖��̈Ӌ`�ɂ��Đ������邱�Ƃ��K�v�ƍl����B �@�����܂ł��Ȃ��A���݂ɂ����Ă��Ȃ��j���̌ٗp�@��ϓ��̊m�ۂ̊ϓ_���猩�āA�����ł���̂͏����ɑ��鍷�ʂł���Ƃ������Ƃ͕ς���Ă��Ȃ��B���ɏ����ɑ��鍷�ʂ̋֎~��j���o���ɑ��鍷�ʂ̋֎~�Ƃ���ꍇ�A���ꂪ�ǂ̂悤�ȈӋ`��L����̂��ɂ��āA���ɏ����ɑ��鍷�ʖ��Ɋւ��Ăǂ̂悤�ȉe����^���邩�Ƃ������_�Ō��Ă����K�v������B |
| �i�Q�j | �@�����ɑ��鍷�ʋ֎~��j���o���ɑ��鍷�ʋ֎~�Ƃ���Ӌ` �@�����ɑ��鍷�ʋ֎~��j���o���ɑ��鍷�ʋ֎~�Ƃ���Ӌ`�Ƃ��ẮA�܂��A�@����A�����ʂ̗��O�����m�ɂȂ邱�Ƃ��������悤�B �@���Ȃ킿�A�����ɑ��鍷�ʂ̋֎~�́A���������u�����v�Ƃ��������Ɋ�Â��s�����ȍ��ʂ��֎~������̂ł���Ƃ���A�����ɑ��鍷�ʂ̋֎~�݂̂ł������A�����ɂ��Ă݂̂̕ی�Ƃ����悤�ȕ����I�ȐF�ʂ������Ď~�߂��邱�Ƃ��������Ȃ��ł��낤�B�j���o���ɑ��鍷�ʂ��֎~���邱�Ƃ͂������������I�ȐF�ʂ���E�p���A�E�Ə�̔\�͓����̍������̂��鍪���Ɋ�Â���������Ƃ����l���m�ɑł��o�����Ƃ��Ӗ����悤�B �@���ɁA�����i���̏k�����n�߁A�����I�Ȓj�������̐��i�Ɏ�����Ƃ������Ƃ���������B�j���o���ɑ��鍷�ʂ��֎~���A�j���o���ɓ����������ʂɊւ���@�I�~�ϑ[�u���K�p����邱�ƂɂȂ�A�����A�j���ɕ�̂���E��ɂ����č������o�����Q�����₷���Ȃ�A���̌��ʁA�j���Ԃ̐E�敪���̐������i�ނƂƂ��ɁA�������܂ޒj���Ԃ̊i���̏k�����}���邱�Ƃ����҂����B �@���̑��A�j���ɑ��鍷�ʂ��֎~���邱�Ƃ����m������邱�Ƃɂ��A�����ʂ̖�肪�j���̑����狤�����Ղ��Ȃ�A���̂��Ƃ������ɑ��鍷�ʂ̐����ɂƂ董�i�I�ɓ������Ƃ����҂����B���s�j���ٗp�@��ϓ��@�ɂ����ẮA�����ɑ���D���[�u�������Ƃ��ċ֎~���A���̌��ʁA���˓I���ʂƂ��Ēj���ɑ��鍷�ʂ���@�Ƃ����ɂƂǂ܂邪�A���ꂪ���ړI�ɒj���ɑ��鍷�ʂ��֎~���A�j���������Ɠ����悤�ɋ~�ς����Ƃ������ƂɂȂ�A�j���������ʂ̖������������̖��ł͂Ȃ��A����̖��Ƃ��đ����������������ƂȂ邱�ƂɂȂ낤�B�����Ă��̂��Ƃ�ʂ��A�j���̑��̗����Ƌ����������Ղ��Ȃ邱�Ƃ͂��̖��̉����Ɍ�������g�̊��Ƃ��ăv���X�ɓ������Ƃ����҂����B |
| �i�R�j | �@�j���o���ɑ��鍷�ʂ̋֎~�Ə����J���҂ɌW�����[�u�Ƃ̊W �@�j���ٗp�@��ϓ��@�͌����Ƃ��āu�����̂݁v��u�����D���v���܂߁A�����ɑ��鍷�ʂ��֎~���Ă���Ƃ���ł��邪�A���@��X���́A���Ǝ傪�ٗp�̕���ɂ�����j���̋ϓ��ȋ@��y�ёҋ��̊m�ۂ̎x��ƂȂ��Ă��鎖������P���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āu�����̂݁v��u�����D���v�̑[�u���s�����Ƃ͖@�ᔽ�Ƃ͂Ȃ�Ȃ����ƂƂ��Ă���B �@���ɒj���ٗp�@��ϓ��@�ɂ����āA�j���o���ɑ��鍷�ʂ��֎~���邱�ƂƂ����ꍇ�A���@��X���ɋK�肷�����[�u�ɂ��āA�E�퓙�ɐ��̕肪����ꍇ�ɂ͒j�������̑ΏۂƂ���̂��ǂ����A�܂��A�j�������̑ΏۂƂ���ꍇ�ɂ́A����[�u�Ƃ��ċ��e�����͈͂ɂ��Č��ݏ����ɑ��ċ��e���Ă�����̂Ɠ����͈͂Ƃ���̂��ɂ��Ă��������s���K�v������B �@���Ȃ킿�A�������s�������O���ł́A��������j���o���ɑ��鍷�ʂ��֎~������Ő����ʂɊւ���ߋ��̌o�߂Ȃǂ܂��Ďb��I�Ɉ���̐��ɑ��鑼���̐��ɂ��Ă̗D���[�u���K�肵�Ă���A���邢�͋K�肵�Ă��Ȃ��܂ł��ٔ��ł͔F�߂��Ă��邪�A�Ⴆ�A�d�t�A�C�M���X�A�X�E�F�[�f���ł́A�j���o���ɂ��Ė����K��ł�������e���Ă���̂ɑ��A�t�����X��h�C�c�ɂ����ẮA�D���[�u�͏����ɂ��Ă̂ݖ����K��ŋ��e���Ă��铙���݂̍���͈�l�ł͂Ȃ��B�܂��A�j���o���ɑ��ėD���[�u�����e���鍑�ɂ����Ă��A���̓��e�ɂ��ẮA�C�M���X�̂悤�ɁA�����K��ŁA����E���ɂ��Ĉ���̐����F������r�I�����̏ꍇ�ɁA���̎d���Ɋւ��A����̐��ɂ̂P���ɂ����ĕX��}�邱�Ƃ≞������シ�邱�Ƃ�F�߂铙���͈̔͂Ɍ��肵�Ă��鍑������A�d�t�̂悤�ɁA���L�͂Ȏ�g�����e���Ă���������i�Q�ƁF�����P�j�B �@���̂悤�ȓ���I�ȗD���[�u�́A���Ƃ��Ƃ́A�Œ�I�Ȑ��ʖ������S�ӎ���ߋ��̌o�܂��珗�����j���Ƌϓ��Ȏ戵�����Ă��Ȃ������Ƃ����̉��P��}�邽�߂ɁA�����I�Ɏb��I�ȑ[�u�Ƃ��Ď��{����Ă������̂ł���B���������āA�j���o���ɑ��鍷�ʂ̋֎~�����[�u�݂̍������������ꍇ�ɂ́A�䂪���̏����̒u���ꂽ�A���ɒj���Ԋi���̌���ɏ\�����ӂ��Č������i�߂���K�v������B |
| �i�P�j | �@�����̌o�� �@�D�P�E�o�Y�͏����݂̂��S���@�\�ł���A���ʂȕی��K�v�Ƃ���ꍇ���������A���̓_�ɂ��Ă̎蓖�Ă��\���łȂ��ƒj���̌ٗp�@��ϓ��̎����͊m�ۂł��Ȃ��B�܂��A���q�E������i�W���钆�ɂ����āA�����������D�P�A�o�Y�ɔ����s���v���畉�S����Ƃ����݂���͖]�܂����Ȃ��A�����������Ȃ�����S���Ďq�����Y�݈�Ă邱�Ƃ��ł�����̊�Ղ������ł����̖����������邱�Ƃ͏d�v�Ȃ��Ƃƍl����B �@�ߔN�A�䂪���ł͔D�P�E�o�Y���𗝗R�Ƃ���s���v�戵�����Ă������̌X���ɂ���B�Ⴆ�A�S���̓s���{���J���ǂɎ������܂ꂽ�j���ٗp�@��ϓ��@�ɌW��ʕ��������̉����̐\�����Ă̂����A���َ��Ă͕���12�N�x�ɂ�69���ł�����������15�N�x�ɂ�123���ƂȂ�A���̂����̖�W����D�P�E�o�Y���𗝗R�Ƃ�����ق���߂Ă���B�܂��A���قɌ��炸�A�D�P���������Ƃ���A�s���v�Ȕz�u�]�������߂�ꂽ��A�p�[�g�^�C���ւ̐g���ύX�����v���ꂽ���̑��k���Ă����Ă���B �@�J����@�y�ђj���ٗp�@��ϓ��@�ɂ����ẮA�ꐫ�ی�̊ϓ_����Y�O�Y��x�Ɠ���ꐫ���N�Ǘ��[�u�̒�߂��u����Ă���Ƃ���ł���A�j���ٗp�@��ϓ��@��W���ɂ����Ă͔D�P�A�o�Y���͎Y�O�Y��x�Ƃ̎擾�𗝗R�Ƃ������ق��֎~����A�J����@��19���ɂ����Ă͎Y�O�Y��x�ƒ��y�юY�O�Y��x�ƌ�30���Ԃ̉��ً֎~�K�肪�݂����Ă��邪�A���وȊO�̋ǖʂɂ��ċK������K��͂Ȃ��B �@����A�玙�E���x�Ɩ@�ɂ����Ă͈玙�x�Ɛ\�o���������Ɩ��͈玙�x�Ƃ��������Ƃ𗝗R�Ƃ���s���v�Ȏ戵�����֎~����K�肪�݂����Ă���Ƃ���ł���B���̌��ʁA�D�P���A�Y�O�Y��x�Ƃ��擾���������̏ꍇ�A�Y�O�Y��x�Ǝ擾��ɐE�ꕜ�A���悤�Ƃ���ꍇ�ƁA�玙�x�ƌ�ɐE�ꕜ�A���悤�Ƃ���ꍇ�ƂŁA�K���A���������Ă���B �@�����ł͔D�P�E�o�Y�Ɋ֘A����s���v�戵���ɂ��ẮA��ʂ̐����ʂƂ͈قȂ�A���ۂɐE�����s���ł��Ȃ���ʂ�A�\���̒ቺ����ʂ��z�肳��邱�Ƃ܂��āA�ȉ��̂悤�ɏꍇ���������āA�������s�����i�ȉ��܂Ƃ߂āu�D�P�A�o�Y���𗝗R�Ƃ���s���v�戵���v�Ƃ����B�j�B
|
| �i�Q�j | �@�䂪���ɂ�����ٔ���̓��� �@��q�̂悤�Ɍ��s�@����A�D�P�E�o�Y���𗝗R�Ƃ����s���v�戵���ɂ��Ă͉��ق̋֎~�Ɋւ���K�肵���݂����Ă��Ȃ����A�ٔ���ɂ����ẮA���وȊO�̋ǖʂɊւ��鎖�Ă�������B�ō��ٔ���Ƃ��ẮA�Y�x�擾�𗝗R�Ƃ����s���v�戵���ɂ��āA���{�V�F�[�����O�����i�������N12��14���@�ō��ٔ����j�A�w�Z�@�l�����w�������i����15�N12��4���@�ō��ٔ����j������A��������J������Ȃ����������ɉ����������̌��z���͋��e�����Ƃ��Ă��A�@����̌����s�g��}�����A�@�����J���҂Ɍ�����ۏႵ����|�������I�Ɏ��킹��悤�ȕs���v�Ȏ戵���͋�����Ȃ��Ɣ������Ă���B
|
| �i�R�j | �@���O���ɂ�����D�P�E�o�Y���𗝗R�Ƃ����s���v�戵�� �@�������s�������O���̖@���ɂ��ėތ^�����Ď����ƁA���̂悤�ɐ������邱�Ƃ��ł���i�Q�ƁF�����Q�j�B
�@��L����e�����ʂɌ�����������܂��ɂ܂Ƃ߂�ƈȉ��̂Ƃ���ƂȂ�B
|
| �i�S�j | �@�䂪���ɂ����ĔD�P�A�o�Y���𗝗R�Ƃ���s���v�戵������������ɓ������ė��ӂ��ׂ����� �@�D�P�A�o�Y���𗝗R�Ƃ���s���v�戵������������ɓ������ẮA�ȉ��̓_�ɗ��ӂ���K�v������B
|
| �i�P�j | �@�����̌o�� �@����9�N�̉����j���ٗp�@��ϓ��@�ɂ��ٗp�̊e�X�e�[�W�ɂ����鏗���ɑ��鍷�ʂ��֎~����邱�Ƃɂ��A�j���ԂňقȂ�戵�������邱�Ƃ́A�@�����O�Ƃ��ċ��e�������̈ȊO�͋�����Ȃ��Ȃ����B�������Ȃ���A�K�������Ӑ}�I�ȍ��ʂł���Ƃ͌������A�ꌩ�j���ԂňقȂ�戵�������Ă���ƌ����Ȃ����̂̒��ɂ��A�������s���ƂȂ鐧�x��^�p�͑��݂��Ă���A���̂悤�ȃP�[�X�ɂ��Ă͌��s�̋K���ł͑Ή�������ȏꍇ������B �@�����������̑��݂͕���9�N�̉����j���ٗp�@��ϓ��@�����������ۂɂ��F������A���O���̖@���̗�ɂ���悤�ɊԐڍ��ʊT�O���������ׂ��Ƃ̋c�_���Ȃ��ꂽ���A���̊T�O���̂��K���������m�łȂ��A��̓I�ɂǂ̂悤�Ȃ��̂��Y������̂��ɂ��Ă̋��ʗ������K�v�ł��������Ƃ���@�Ăɂ͐��荞�܂ꂸ�A���̌�̍���R�c�ɂ����āA���ь��c�ɍ���̌����ۑ�Ƃ��Đ��荞�܂ꂽ�o�߂�����B�����ĊԐڍ��ʂɂ��ẮA��N�ĂɁA�䂪������y���Ă��鏗�q���ʓP�p���Ɋ�Â��ݒu���ꂽ���q���ʓP�p�ψ���̐R���ɂ����Ďw�E�������Ƃ���A�v�X���ڂ����悤�ɂȂ��Ă����B �@����A�����́A���s�̋K���ł͑Ή�������ƂȂ��Ă�����ɑΏ����Ă������߂ɂ́A���ɊԐڍ��ʖ@������������Ă��鏔�O���̉^�p�ɂ��Đ������邱�Ƃɂ��Ԑڍ��ʂƂ����T�O�m������ƂƂ��ɁA�䂪���ɂ����āA��̓I�ɂǂ̂悤�Ȃ��̂���@�ȍ��ʂɊY������̂��ɂ��ẴC���[�W���������Ƃ��K�v�ł���B |
| �i�Q�j | �@�Ԑڍ��ʂ̊T�O �@��ʓI�ɁA�Ԑڍ��ʂƂ́A�O����͐������I�ȋK��A��A���s���i�ȉ��u����v�Ƃ����B�j���A���̐��̍\�����Ɣ�r���āA����̐��̍\�����ɑ������x�̕s���v��^���A���������̊�����E���Ɗ֘A�����Ȃ����������E���������F�߂��Ȃ����̂��w���Ɨ����ł���B �@���[���b�p�ł́A�u�Ԑڍ��ʁiindirect discrimination)�v�Ə̂���Ă��邱�Ƃ��������A���߂Ă��̊T�O���o�ꂵ���̂́A�A�����J�ɂ�����1971�N��Griggs�����A�M�ō��ٔ����ł���A1964�N�������@��V�ҁi�ȉ��u��V�ҁv�Ƃ����B�j�̉��߂Ƃ��āA�u���ʓI���ʁidisparate impact�j�@���v���m�������B���̍��ʓI���ʖ@���́A�ٔ���̒~�ς��o�āA1991�N�ɂ͑�V�҂ɋK�肪�lj�����Ă���B �@����A�A�����J�ɂ����Đ����A���W�������ʓI���ʖ@���̊T�O�̓��[���b�p�ɓn��A�Ԑڍ��ʂƌĂ��悤�ɂȂ����B�d�t�̋ϓ��ҋ��Ɋւ���76�N�w�߂�e�������@�ɂ����ċK�肪�݂����A��͂�ٔ���̏W�ς�ʂ��ď��X�ɋ�̓I�ȃC���[�W���`������Ă������̂ł���i�ȉ��A�A�����J�́u���ʓI���ʖ@���v���܂߁A�u�Ԑڍ��ʁv�ƌĂԂ��ƂƂ���j�B �@�䂪���ɂ����ẮA���݂܂ł̂Ƃ���Ԑڍ��ʖ@���ɗ����Ĕ��f���ꂽ�ٔ���͌ٗp�̕���ɂ͌��o���Ȃ��B�Ƒ��蓖�Ɋւ��āA�j����������̌������߂��J����@��4���ᔽ������ꂽ���Y�����ԉƑ��蓖�����A�Ζ��n����A��������Ƃ��������̍��ɂ��ē������J����@��4���ᔽ������ꂽ�O�z���Y�������͂�����̂́A��������Ԑڍ��ʂ�F�߂����̂ƒf�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A�ٗp�̕���ł͂Ȃ����̂́A����14�N�ɑ�㍂�قŔ����������ꂽ��ЎҎ����x�������������ɂ����ẮA��_�E�W�H��k�Ђ̔�ЎҎ����x�����̐��ю��Зv�������ъԍ��ʋy�ђj�����ʂ��������A���A�����̍��ʂɍ����I���R�����o�����Ƃ��ł����A�����Ǒ��Ɉᔽ����Ɣ�������Ă���A���܂Ŗ����Ɏ��グ���Ȃ������`�Ԃ̍��ʂ�F�߂����̂Ƃ��āA����̓��������ڂ����B
�@�Ԑڍ��ʊT�O�̊�{�I�l�����͊e���قڋ��ʂł��邪�A�Ԑڍ��ʂ̊T�O�𑼂̊T�O�Ƃ̔�r�Ő�������A�ȉ��̂Ƃ���ƂȂ�B
|
| �i�R�j | �@���O���ɂ�����Ԑڍ��ʖ@���̏� �@�������s�������O���̊Ԑڍ��ʂɌW��K���K�p�������R�̂Ƃ���ł���B�@����K�肳��Ă����@���̔��f���@�́A�e���Ƃ��قړ��l�̎�@�ƂȂ��Ă���A�����Ƃ��āA�ꉞ�ǂ̂悤�Ȏ��Ăɂ��Ă��Ԑڍ��ʖ@���̘�ɍڂ肤��d�g�݂ƂȂ��Ă���B�������Ȃ���A�A�����J�ł́A�����̖@���Ƃ̊W���ɂ��A�Ԑڍ��ʖ@�����K�p����Ȃ����Ă���������A�܂��A�e���̒u���ꂽ�����ꂼ��قȂ邱�Ɠ�����A���ۂ̊Ԑڍ��ʖ@���̓K�p�ɂ��ẮA���ɂ���Ă��Ȃ�̈Ⴂ������B�Ȃ��t�����X�ł́A�@�ɂ����ĊԐڍ��ʖ@��������������2001�N�ł���Ƃ������Ƃ�����A��̓I�ȓK�p��͔c������Ă��Ȃ��B
|
| �i�S�j | �@�䂪���ɂ����ĊԐڍ��ʂ���������ɓ������ė��ӂ��ׂ����� �@�䂪���ɂ����ĊԐڍ��ʂ���������ɓ������ẮA�ȉ��̓_�ɗ��ӂ���K�v������B
|
| �i�T�j | �@�Ԑڍ��ʂƂ��čl������� �@�{������ł͊Ԑڍ��ʂƂ��čl������T�^�I�Ȏ���ɂ��ăC���[�W���������߁A����܂ŗl�X�ȂƂ���ŊԐڍ��ʂɊY������̂ł͂Ȃ����Ǝw�E���ꂽ���̂𒆐S�ɁA��lj�����������ɂ��Č������������B���̌��ʂ͎���(1)����(7)�Ɏ����Ƃ���ł���B �@�Ԑڍ��ʂɊY�����邩�ǂ����ɂ��ẮA������̎���ɂ����Ă��A���ۂɂ͌ʋ�̓I�Ȏ��Ă��ƂɎ����F����s���A���f���Ă������̂ł���B �@�܂��A�O���㐫�����I�Ȋ��������̐��ɕs���v��^���邩�ۂ��y�ѓ��Y����̍������E�������Ɋւ���g�p�҂̍R�قɂ��āA�����I�ɔ��f���s�����̂ł��邱�Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B �@�Ȃ��A(2)�A(4)�A(6)�A(7)�ɂ��ẮA�����ɕs���v��^���邱�ƂƂȂ����̓K�p���邱�Ƃɂ��ẮA�E�ƂɊւ��铖�Y��������̈ӎv��I���Ɋ�Â����ʂł���Ƃ����_�ő��ƈقȂ��Ă���A��������ʂ̘�ɍڂ��邱�Ƃ͐��ʖ������S������̌Œ艻�ɂȂ��錜�O�����邱�Ƃ���A���������Ԑڍ��ʂ̘�ɍڂ���ׂ����Ăł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ̈ӌ����������������A���ɘ�ɍڂ����ꍇ�ɂ͂ǂ̂悤�ȏꍇ�ɊԐڍ��ʂƂȂ肤��̂��ɂ��Đ����������̂ł���B �y�Ԑڍ��ʂƂ��čl�������z
|
| �i�P�j | �@�����̌o�� �@�䂪���ɂ����ẮA�Œ�I�Ȑ��ʖ������S�ӎ���ߋ��̌o�܂��珈���ʂŒj���Ԃ̎�����̊i�����c���Ă���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��A�Ⴆ��UNDP�i���A�J���v��j��GEM�i�W�F���_�[�E�G���p���[�����g����j�����Ă������̊���̏͏\���Ƃ͌����Ȃ��B�o�p�A�E��Ȃǂ̖ʂŒj���J���҂̊ԂɎ����㐶���Ă���i���́A�����J���҂ɑ��鍷�ʂ��֎~�����K������炷�邾���ł͉����͂ł��Ȃ����߁A�j���ٗp�@��ϓ��@�ɂ����Ă͑�20���Ŏ��Ǝ傪���̂悤�ȍ��̉�����ڎw���ď����̔\�͔����̑��i�ɂ��Ă��ꂼ��̏ɉ����ċ�̓I�Ɏ��g�ޏꍇ�ɍ������k�E�������s�����Ƃ��ł���|�K�肵�Ă���B �@�܂��A�ߔN�A�����ȍ��ʂ͐���������邪�A�X�l�̈ӎ����Ɠ����̈ӎv����̍\�����ɋN������j���̏������́A�ꗥ�I�ȕ��@�ʼn�������͍̂���ł���B���̂悤�Ȗ��ɑ��Ă͌ʂɋK���������Ă������Ƃ͎��ۏ�s�\�ł���A�܂��K�Ƃ��l����ꂸ�A�ނ���X�̊�Ƃ̒u���ꂽ�ɉ����A�����Ɍ������O�����Ȏ�g�ł���|�W�e�B�u�E�A�N�V�����ɂ�邱�Ƃ��K�ƍl������B����ɁA�|�W�e�B�u�E�A�N�V�����ɂ���Ă������������P���Ă������Ƃ́A���������\�͂����ē������Ƃ𑣐i���A��Ƃ̃C���[�W�A�b�v��Y������ɂ���������̂ł���Ƃ̎w�E���Ȃ���Ă���B �@���̂悤�ɁA�|�W�e�B�u�E�A�N�V�����ɂ��Ă͐ϋɓI�Ȑ��i���]�܂��Ƃ���ł��邪�A����12�N�x�̏����ٗp�Ǘ���{�����ɂ��A�|�W�e�B�u�E�A�N�V�����Ɏ��g��ł����Ƃ̊����́A5000�l�ȏ�K�͊�Ƃł�67.7���ł�����̂́A��ƋK�͌v�ł�26.3����4�Ђ�1�ЂƂ����ł���B���݁A�䂪���ł̓|�W�e�B�u�E�A�N�V�����̕��y�̂��߁A�����̊������i���c��̊J�ÁA�ϓ����i��ƕ\����x���`�}�[�N���ƂȂNJe��̎{���W�J���Ă���A��Ƒ��ɂ����Ă��ϋɓI�Ȏ�g���Ȃ���n�߂�ȂǁA���̈Ӌ`��K�v���ɂ��Ă̗����͐i�݂���ƌ����邪�A�Ȃ��傫�ȍL����������������ɂ͎����Ă��Ȃ��ɂ���B |
| �i�Q�j | �@���O���ɂ�����|�W�e�B�u�E�A�N�V�����̎�g �@�������s�������O���ɂ����čs���Ă����v�Ȏ�@������ƁA�ȉ��̂Ƃ���ł���i�Q�ƁF�����S�A�T�j�B
|
| �i�R�j | �@�䂪���ɂ����ă|�W�e�B�u�E�A�N�V�����̌��ʓI���i�������������ɓ������ė��ӂ��ׂ����� �@�|�W�e�B�u�E�A�N�V���������ʓI�ɐi�߂��@����������ɓ������ẮA�ȉ��̓_�ɗ��ӂ���K�v������B
|
| �������P | �@���O���ɂ����鐫���ʋ֎~�ɌW��K�蓙�i�T�v�j |
| �������Q | �@���O���ɂ�����D�P�E�o�Y���𗝗R�Ƃ���s���v�戵���ɌW��K�蓙�i�T�v�j |
| �������R | �@���O���ɂ�����Ԑڍ��ʂɌW��K�蓙�i�T�v�j |
| �������S | �@���O���ɂ�����|�W�e�B�u�E�A�N�V�����i�o�E�`�j�ɌW��K�蓙�i�T�v�j |
| �������T | �@���O���ɂ����鏗���Ǘ��E�����y�т��̐��� |
| �@ | ��q�@�ނq | �@ | ����c��w��w�@�@�������ȋ��� |
| �@ | �����@���_ | �Ջ���w�o�ϊw�������� |
|
| �� | ���R�@���� | �����w�@�w������ |
|
| �@ | ���V�@���q | ������w�@��w������ |
|
| �@ | �c���@�D�q | �ٌ�m |
|
| �@ | �y�c�@���M | ���{����w�o�ϊw������ |
|
| �@ | ���E�@�T�� | ��B��w��w�@�@�w�����@���� |
|
| �@ | �R��@���� | �c��`�m��w��w�@�@�������ȋ��� |
|
�i���͍����@�T�O�����A�h�̗��j |
|||
| �_���@�j��Y | �@ | ������w��w�@�@�w�����w������ ������r�@�����ۃZ���^�[�q������ |
| ����@�\�q | �@����w�@�w�����C�u�t |
|
| �{��@�R�� | �@����w��w�@���m����ے� |
|
| ���p�@���� | �����w�@��w�@�w�������� |
|
| �i�T�O�����A�h�̗��j | ||
| �@ | �A�����J | EU | �C�M���X | �t�����X | �h�C�c | �X�E�F�[�f�� | ���{ |
| �ٗp�ɂ��� �鐫���� �֎~�̍����@ |
�@�������@��V�� �����l�ȏ������܂�1964�N�������@���ɁA��V�҂Ƃ��Čٗp���ʂ̋֎~�ɂ��Ă̏�����݂����`�ԁB |
�ٗp�A�E�Ƌ���y�я��i�ւ̃A�N�Z�X���тɘJ�������ɂ�����j���ϓ��ҋ������̎����̂��߂̎w�߁i�j���ϓ��ҋ��w�߁j�i76/207/EEC�j ���ٗp�A�E�Ƃɂ����鍷�ʂ̋֎~�ɂ��Ē�߂��w�߁B |
�����ʋ֎~�@ ���ٗp�̕���ɉ����āA����A���i�E�{�݁E�T�[�r�X�̋��^�A�L���Ɋւ��鐫���ʂ܂ŋ֎~����ԗ��I�Ȗ@���B���I����ɂ��K�p�����B |
�J���@�T ���J���W�̏��K������߂�ꂽ �J���@�T�̒��ɐ����ʋ֎~�̋K�� ��݂���`�ԁB |
���@�T �����@�̒��ɐ����ʋ֎~�̋K���݂���`�ԁB |
�@��ϓ��@ ���J�������ɂ�����j���̋@��ϓ��ɂ��Ē�߂��@���B |
�j���ٗp�@��ϓ��@ ���ٗp�̕���̏������ʋ֎~���Ɋւ���@���B |
| �j���o�� �ɑ��� �֎~�K�肩 |
�y�j���o���ɑ��鍷�ʋ֎~�^�z | �y�j���o���ɑ��鍷�ʋ֎~�^�z | �y�����ɑ��鍷�ʋ֎~�̒j���ɑ��鏀�p�^�z | �y�j���o���ɑ��鍷�ʋ֎~�^�z | �y�j���o���ɑ��鍷�ʋ֎~�^�z | �y�j���o���ɑ��鍷�ʋ֎~�^�z ���������A�P���ɂ����āA�@�̖ړI�͒j���̕������i�ł��邪�A���ɏ����̏������̉��P��ڎw���Ƃ��Ă���B |
�y�������ʂ̂֎~�^�z |
| �����ʂ� �֎~���� �����K�� |
�@�@703��(a)�u�ȉ��̍s�ׂ́A�g�p�҂̈�@�Ȍٗp���s�Ƃ���B(1)�l��A�畆�̐F�A�@���A���ʁA�܂��͏o�g���𗝗R�Ƃ��āA�l���ٗp�����A���̌ٗp�����ۂ��A���ق��邱�ƁA���邢�͌ٗp�Ɋւ����V�A���ԁA�����܂��͓��T�ɂ��āA���ʑҋ����s�����ƁB(2)�E�E���ʁE�E�𗝗R�Ƃ��āA�l�̌ٗp�@���D���A�D���\���̂�����@�Ŕ�p�҂܂��͏A�E����҂𐧌��A�����A�ޕʂ��邱�ƁA���邢�͔�p�҂���n�ʂɕs���v���y�ڂ����ƁB�v�i1964�N�j | �w��2���P�@�u�ȉ��̏����ɂ����āA�ϓ��ҋ��̌����Ƃ́A�E�E�E���ړI�܂��͊ԐړI�Ȃ����Ȃ鐫���ʂ��Ȃ����Ƃ��Ӗ�����B�v�i1976�N�j | �E�@1��(1)�u�{�@�̂��ׂĂ̋K��̖ړI�Ɋւ��A�����Ȃ�ꍇ�ɂ����Ă��ȉ��̍s�ׂ��s�����҂́A�����ɑ��鍷�ʂ��s�������̂Ƃ���B�v �E�@2��(1)�u�����ɑ��鐫���ʂɊւ���E�E�K��́A�j���ɑ���戵���Ɋւ��Ă����l�ɓK�p�����ׂ����̂Ɖ��߂��E�E�v�i1975�N�j |
�@123��-1�u�E�E���҂��ȉ��̂��Ƃ��s�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�E�E�E���ʁE�E�Ɋ�Â��ĈقȂ����I����ɏ���������A���ʁE�E���l�����邱�Ƃɂ���āA�̗p�����ۂ�����A���^�����҂ɓ]�𖽂�����A�J���_��̍X�V�����ۂ�����A���������肷�邱�ƁE�E�B�v �i1983�N�j | �@611��a(1)�u�g�p�҂́E�E�E�ٗp�_��̐ݒ�A���i�A�E����̎w���A���ق��s���ꍇ�ɁA���𗝗R�Ƃ��ĕs���v�Ɉ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�E�E�E�v�i1980�N�j | �@15���P���u�g�p�҂́A���E�҂܂��͘J���҂��A���l�̏ɂ��鑼���̐��ʂ̎҂����s���Ɏ�舵���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������g�p�҂����Y�s���v�戵�������ʂɊW���Ȃ����Ƃ��ؖ������ꍇ�͂��̌���ł͂Ȃ��B�v�i2000�N�j | �@6�𑼁u�E�E�J���҂������ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��āA�j���ƍ��ʓI�戵�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v�i1997�N�j |
| �|�W�e�B�u�E �A�N�V���� �iP�EA�j�� ���e���� �����K�� �� |
���@�߂ɖ����̋K��Ȃ��B ���ٔ����ɂ��Ă͌������@706��(g)�Ɋ�Â��A���ʂɑ���~�ϑ[�u�Ƃ��ăA�t�@�[�}�e�B�u�E�A�N�V�����iA�EA�j�𖽂��邱�Ƃ��ł���B ���A�M�ō��ق͌������@��V�҂̎�|�ɍ��v���邱�Ƃ�F�߁A���͈͓̔��ŋ��e�B ��EEOC�K�C�h���C���ɋK��B �EA�EA�̎��{���K�ȏꍇ�Ƃ��āA(1)�s���ȉe���������Ă��銵�s�̑��݁A(2)�ߋ��̍��ʓI���s�̉e���̑����A(3)�ߋ��̔r���������Ƃ���o�p�\�ȑw�̕s�� �EA�EA�̎菇�Ƃ��āA(1)�����I�Ȏ��ȕ��͂ƁA(2)����Ɋ�Â������I�ȍ����Ɋ�Â��v��̉��ł̍����I�ȍs���A(3)����ɂ��ꂪ����������Ă��邱�Ƃ��K�v�B |
�����B�����̐ݗ���� �@�E�Ɛ����̊��s�ɂ�����j���̊��S�ȋϓ��ҋ����m�ۂ��邽�߂ɁA�ϓ��ҋ������́A���������A��菭���̐��ɑ�����҂��E�Ɗ�����Nj����邱�Ƃ�e�Ղɂ��A�܂��͐E�ƌo���ɂ�����s���v��h�~���������͕ۏႷ�邽�߂ɁA���ʂ̕X�����[�u���ێ����܂��͍̗p���邱�Ƃ�W������̂ł͂Ȃ��B�i���141��4���j�i1997�N�j ���j���ϓ��ҋ��w�� �@���������́A���ۂɒj���̊��S�ȋϓ��ҋ���ړI�Ƃ��āA���B�����̐ݗ����141��(4)�̈Ӗ�����͈͓��̎{����ێ��܂��͍̗p���邱�Ƃ��ł���B�i�w��2��8���j�i2002�N�j ��2002�N�����O��2��4�� �u�E�E�����̋@��ɉe�����y�ڂ������̕s������r�����邱�Ƃɂ��A�j���̋@��ϓ��𑣐i����[�u��W������̂ł͂Ȃ��E�E�v |
�������ʋ֎~�@ �@����I�ɁA�ߋ�12�����ԂɁA�O���[�g�E�u���e���ɂ����ē��Y���̎҂ł��̎d�����s���҂��S�����Ȃ�����r�I�����̏ꍇ�ɂ����āA�����܂��͒j���ɂ̂݁A(1)���̐E���ɓK������̂ɖ𗧂P���{�݂̗��p��F�߂邱�ƁA(2)�E�����s���@��̗��p�����シ�邱�Ɠ��̏ꍇ�̂݁A���e�����B�i�@47�𑼁j |
���J���@�T �@�@123��-1,123��-2�̋K��́A�j���̋@��A�Ƃ��ɏ����̋@��ɉe�����鎖����̕s���������ĕ������m�����邽�߂ɁA�����ɑ��Ă݂̂Ƃ���b��I�[�u�̎��{��W������̂ł͂Ȃ��B �i�@123��-3�j�i1983�N�j |
�����ԕ����ΏۂƂ��������̋K��Ȃ��B �����������ΏۂƂ������̂Ƃ��āA�u�A�M�s���@�y�јA�M�ٔ����ɂ����鏗���̌ٗp���i���тɉƒ�ƐE�Ƃ̗����̂��߂̖@���v�i1994�N�j �@�����͂��̖@���̊�Ɋ�Â��A�K���A�\�͂���ѐ��̎d���ɂ��Ă̗D�ʂ��l�����āA�ٗp�𑣐i�����B�X�̕���Ōٗp����Ă��鏗�����j�����������ł������A���߂�ꂽ��ڕW�ɑ����ď����̊��������߂邱�Ƃ��ٗp���i�̖ړI�ł���B�j�����тɏ����̂��߂̉ƒ�ƐE�Ƃ̗��������l�ɑ��i���ׂ����̂ł���B�i�@2���j |
���@��ϓ��@ �EP.A�ɑ��Ă͍��ʋ֎~��K�p���Ȃ��B�i�@15��2���j�i2000�N�j �E�g�p�҂͂��̊����̘g���ŁA�E�Ɛ����ɂ�����j�������𑣐i���邽�߂ɁA�ڕW�Ɍ������w�͂��s���B�i�@3���j�i1991�N�j �E�g�p�҂͋���P���E�\�͊J�����̑��K�ȑ[�u�ɂ��A�e�E��ɂ�����j���䂨��шقȂ�E��Ԃ̒j������ϓ��ɂ���悤�w�͂���B�i�@7���j�i1991�N�j �E�g�p�҂́A���l�ɍۂ��Ēj�����҂�����ł���悤�ɓw�͂�����̂Ƃ���B�i�@8���j(1991�N�j �E�g�p�҂́A�������̐E�킠�邢�͂���J�e�S���[�̘J���҂̒��Ő��̕肪����ꍇ�ɂ́A���Ȃ����̉���҂��̗p����悤�w�͂���B�i�@9���j(1991�N�j |
���j���ٗp�@��ϓ��@ �@���Ǝ傪�A�ٗp�̕���ɂ�����j���̋ϓ��ȋ@��y�ёҋ��̊m�ۂ̎x��ƂȂ��Ă��鎖������P���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ď����J���҂Ɋւ��čs���[�u���u���邱�Ƃ�W���Ȃ��B�i�@9���j�i1997�N�j |
| �@ | �A�����J | EU | �C�M���X | �t�����X | �h�C�c | ���{ | |||||
| �����@�� | ���D�P���ʋ֎~�@�iPDA�j�i�������@��V��701��(k)�j�i1978�N�j ���Ƒ���Ëx�ɖ@�iFMLA�j�i1993�N�j ��FMLA�̓K�p�ΏۂƂȂ�g�p�҂́A�B�ےʏ��ɏ]�����͉e����^���銈�����s��50�l�ȏ�̘J���҂��ٗp����g�p�҂ł���A�ΏۘJ���҂́A12�����ȏ�ٗp����A���߂�12������1250���Ԉȏ�Ζ������J���ҁB |
���j���ϓ��ҋ��w�߁i����76�w�߁j�i2002�N�j ���D�P���y�яo�Y���㖔�͎������̏����̈��S�q�����P���i�[�u�̓����Ɋւ���w�߁i92/85/EEC�w�߁j�i1992�N�j |
���ٗp�����@�i1996�N�j�y��1999�N�o�Y�y�ш玙�x�ɓ��K���i2002�N�K���ɂ������j | ���J���@�T | ���ꐫ�ی�@�i1997�N�j | ���j���ٗp�@��ϓ��@�i1997�N�j ���J����@�i1947�N�j |
|||||
| �D�P�E�o�Y���𗝗R�Ƃ����s���v�戵���Ɛ����ʂ̊W | ���D�P�E�o�Y�y�ъ֘A�����w�I��ԂɊ�Â����ʂ́A���Ɋ�Â����ʂƂ����B�i�������@��V��701��(k)��P���O���j �@���������@��V��703��
|
���w��92/85/EEC�͈͓̔��́A�D�P���͏o�Y�ɔ��������ɑ���s���ȑҋ��́A�{�w�߂͈͓̔��̍��ʂɑ������邱�ƂƂ���B�i����76�w�߂Q���V�j
|
�������ʋ֎~�@�ɂ́u�D�P�E�o�Y�𗝗R�Ƃ����v�Ƃ��������������Ă��Ȃ����߁A�ٗp�����@�Ɋ�Â��ĕs�����f�B�i�p���{����̃q�A�����O�j ��EOC�́A�D�P�E�o�Y�Ɋ֘A�������R�ɂ��s���v�戵���͒��ڐ����ʂɂȂ�Ƃ��Ă���B |
�������ʂł͂Ȃ��A�D�w�ɑ��鍷�ʁi�����{����̃q�A�����O�j | ���D�P�E�o�Y�𗝗R�Ƃ�����ق���̕ی�ƍ��ʋ֎~�͕ʑ̌n�ł��邪�A�D�P�𗝗R�Ƃ���s���v�戵�͐��𗝗R�Ƃ��钼�ڐ����ʂƂ����B | �������ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ������ʂł͂Ȃ��A�D�P�E�o�Y�ɑ���s���v�戵���B�i���ߒʒB�j | |||||
| �D�P�E �o�Y �A �Y�x �擾�� ���R �Ƃ��� �s���v �戵�� |
��W �E �̗p |
���D�P�E�o�Y�y�ъ֘A�����w�I��ԂɊ�Â����ʂ́A���Ɋ�Â����ʂƂ����B�i�������@��V��701��(k)��P���O���A703��(a)�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I��Ԃɂ��e�����Ă��鏗���́A�����������܂ނ��ׂĂ̌ٗp�Ɋ֘A��������ɂ����āA���l�̘J���\�͖��͕s�\�͂̏�Ԃɂ��鑼�̎҂Ɠ����戵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �i�������@��V��701��(k)��P���㔼�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I�ȏ�Ԃ𗝗R�Ƃ���A����҂̌ٓ���̋��ۂ́A�����Ƃ���PDA�ᔽ�iEEOC�K�C�h���C��29CFR1604.10) ���g�p�҂́A�J���҂����̐E���̎�v�ȋ@�\���ʂ������Ƃ��ł������A�D�P���Ă���J���҂̌ٓ��ꋑ�ۂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�iEEOCFacts about Pregnancy Discrimination�j |
���w��92/85/EEC�͈͓̔��́A�D�P���͏o�Y�ɔ��������ɑ���s���ȑҋ��́A�{�w�߂͈͓̔��̍��ʂɑ������邱�ƂƂ���B�i����76�w�߂Q���V�j
�i�Q�l�ٔ���j ���D�P�����ɑ���@����̏A�Ɛ����𗝗R�Ƃ��ĔD�P���������Ԃ̒�߂̂Ȃ��|�X�g�Ɍٗp���邱�Ƃ����₷�邱�Ƃ͋�����Ȃ��B�i�}�[���u���N�����i�Ɓj���B�i�@�ٔ���2000�N�j |
���D�P�E�o�Y�A�ʏ�Y�x�E�lj��Y�x���擾�������Ɩ��͎擾���悤�Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ��邠����s���v�戵���̋֎~�B�i�@47��C�A�K��19���j | ���g�p�҂́A�ٗp�̋��ہA���p���Ԓ��̘J���_������A���̔z�u�]���ɓ�����A�D�P���Ă��邱�Ƃ��l���ɓ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�@122��-25�j ���g�p�҂̏����J���҂̔D�P��ԂɊւ�������W�̋֎~�B�i�@122��-25�j |
�������J���҂́A�̗p�ɍۂ��A���炪�D�P���Ă��邱�Ƃ��g�p�҂ɍ�����`���͂Ȃ��A�g�p�҂���̎���ɓ�����`���͂Ȃ��B�]������\��̋Ɩ����e���A�D�P���̏����̏A�Ƃ��֎~����Ă�����̂ł����l�B | �@ | ||||
| �z�u | ���D�P�E�o�Y�y�ъ֘A�����w�I��ԂɊ�Â����ʂ́A���Ɋ�Â����ʂƂ����B�i�������@��V��701��(k)��P���O���A703��(a)�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I��Ԃɂ��e�����Ă��鏗���́A�����������܂ނ��ׂĂ̌ٗp�Ɋ֘A��������ɂ����āA���l�̘J���\�͖��͕s�\�͂̏�Ԃɂ��鑼�̎҂Ɠ����戵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �i�������@��V��701��(k)��P���㔼�j �����I�Ȕz�u�]���͍��ʐ\���̊�b�ɂȂ肤��B�iEEOC����̃q�A�����Oށj �i�Q�l�ٔ���j ���D�P�T�����ȍ~�̃T�[�r�X�W�̃E�F�C�g���X���A���̎���������W�ɔz�u���邱�Ƃ́APDA�ᔽ�B�iW��O�Ў���2000�N�j |
���w��92/85/EEC�͈͓̔��́A�D�P���͏o�Y�ɔ��������ɑ���s���ȑҋ��́A�{�w�߂͈͓̔��̍��ʂɑ������邱�ƂƂ���B�i����76�w�߂Q���V�j | ���D�P�E�o�Y�A�ʏ�Y�x�E�lj��Y�x���擾�������Ɩ��͎擾���悤�Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ��邠����s���v�戵���̋֎~�B�i�@47��C�A�K��19���j | �����ӂ�����ꍇ�A�����̌��z��Ȃ��ꎞ�I�Ȕz�u�]���͉\�B�i�@122��-25-1�j | �@ | �@ | |||||
| ���E �� �ւ� ���A�� ���� |
���g�p�҂́A���̋x�Ƃ̍ۂƓ������Ԃ����A�D�P�E�o�Y�ɂ��x�Ƃ̏ꍇ�Ɍ��E���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�iEEOC"Facts about Pregnancy Discrimination"�j ���Ƒ���Ëx�ɏI����́A���E���͌��E�ƒ������̑��J�������������̐E�ɕ��A���錠����L����B�iFMLA104��(a)(1)�j |
���Y�x���擾���������́A�Y�x�����ɁA���E���͌��E�ƘJ�������������̐E�ɕ��A���錠����L����B�i����76�w�߂Q���V�j | ���ʏ�Y�x���擾�����J���҂́A�x�ɑO�̐E���ɕ��A���錠����L����B�i�@71��(4)(c)�A�K��18��(1)�j ���lj��Y�x���擾�����J���҂́A�x�ɑO�̐E�����͑Ó��ȕʂ̐E���ɕ��A���錠����L����B�i�@73��(4)(c)�A�K��18��(2)�j ���ʏ�Y�x����̕��A�̌����́A(1)�x�ɂ��擾���Ȃ������ꍇ�Ɠ��l�̔N���A�N���y�їގ��̌������A����(2)�x�ɂ��擾���Ȃ������ꍇ�ɓK�p���������������Ȃ������ł��邱�Ƃ��K�v�B�i�@71��(4)�A(7)�A�K��18��A(1)(a)�i�A�j�A(b)�j ���lj��Y�x����̕��A�̌����́A(1)�x�ɂ��擾����O�̌ٗp�Ǝ擾������̌ٗp���p�����Ă����ꍇ�Ɠ��l�̔N���A�N���y�їގ��̌����A����(2)�x�ɂ��擾���Ȃ������ꍇ�ɓK�p���������������Ȃ������ł��邱�Ƃ��K�v�B�i�@73��(4)�A(7)�A�K��18��(2)�A18��A(1)(a)�i�@�j�j ���Y�x���̏���̏ꍇ�́A�i�ʏ�Y�x���lj��Y�x���ɂ�����炸�j��ւ̌ٗp�����錠����L����B�i�@74��(1)�A�K��10���j �i�Q�l�ٔ���j �����Z�T�[�r�X����̔鏑�����Ă����������A�Y�x���A��A�قȂ镔��̔鏑 �̒n�ʂ���ꂽ���Ƃ́A���A�O�̎d���ɖ߂����Ɣ��f���ꂽ�B�i�o���N�X����1994�N�j |
���ꎞ�I�Ȕz�u�]���́A�D�P���ԏI���܂��͏������]�O�̐E�ɕ��A���邱�Ƃ��\�Ȍ��N��ԂƂȂ�A�I������B�Y�x�I����A�J���ĊJ����ۂɂ́A�]�O�̐E�ɍĔz�u�����B�i�@122��-25-1�A122��-26�j ���Y�x��A�J���҂͎Y�ƈ�̐f�@���闘�v������B���̐f�@�́A�]�O�̐E�ւ̕��A����\�͂��������A�J�������ɓK�����邩�A�ꍇ�ɂ���Ă͉��炩�̑[�u���K�v�����f������̂ł���A���A��W���Ԃ̊Ԃɍs����B(�K��241-51�j ���Y�x�̏I�����ɂ́A�����I�Ɏ����̐E�ɕ�����B���Y�E�������Ȃ��Ă���ꍇ�ɂ́A�����̕�V���ގ��̐E�������B�i�����{����̃q�A�����O�j |
���ꐫ�ی�@�ɋK��Ȃ��B ���J���@�̈�ʌ�������A�J���_��゠�邢�͎��ۂɏA�Ƃ��Ă����E��Ɠ����̐E��ւ̕��A���ۏႳ���B�������A�g�p�҂̎w�����ߌ��͈͓̔��ŁA���܂łƈقȂ����E��E�E���ւ̕��A���F�߂���B |
�@ | |||||
| ���i | ���D�P�E�o�Y�y�ъ֘A�����w�I��ԂɊ�Â����ʂ́A���Ɋ�Â����ʂƂ����B�i�������@��V��701��(k)��P���O���A703��(a)�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I��Ԃɂ��e�����Ă��鏗���́A�����������܂ނ��ׂĂ̌ٗp�Ɋ֘A��������ɂ����āA���l�̘J���\�͖��͕s�\�͂̏�Ԃɂ��鑼�̎҂Ɠ����戵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�������@��V��701��(k)��P���㔼�j |
���w��92/85/EEC�͈͓̔��́A�D�P���͏o�Y�ɔ��������ɑ���s���ȑҋ��́A�{�w�߂͈͓̔��̍��ʂɑ������邱�ƂƂ���B�i����76�w�߂Q���V�j �i�Q�l�ٔ���j ���Y�O�Y��x�Ƃ��擾�������Ƃɂ�菗���J���҂��N�Ɉ�x�Ɛэ�����錠����ے肷�邱�Ƃ́A���������ʂ��邱�ƂƂȂ�B�i�`�{�[�����i���j���B�i�@�ٔ���1998�N�j |
���D�P�E�o�Y�A�ʏ�Y�x�E�lj��Y�x���擾�������Ɩ��͎擾���悤�Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ��邠����s���v�戵���̋֎~�B�i�@47��C�A�K��19���j | �@ | �@ | �@ | |||||
| ���� �P�� |
���D�P�E�o�Y�y�ъ֘A�����w�I��ԂɊ�Â����ʂ́A���Ɋ�Â����ʂƂ����B�i�������@��V��701��(k)��P���O���A703��(a)�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I��Ԃɂ��e�����Ă��鏗���́A�����������܂ނ��ׂĂ̌ٗp�Ɋ֘A��������ɂ����āA���l�̘J���\�͖��͕s�\�͂̏�Ԃɂ��鑼�̎҂Ɠ����戵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�������@��V��701��(k)��P���㔼�j |
���w��92/85/EEC�͈͓̔��́A�D�P���͏o�Y�ɔ��������ɑ���s���ȑҋ��́A�{�w�߂͈͓̔��̍��ʂɑ������邱�ƂƂ���B�i����76�w�߂Q���V�j | ���D�P�E�o�Y�A�ʏ�Y�x�E�lj��Y�x���擾�������Ɩ��͎擾���悤�Ƃ�����
�Ƃ𗝗R�Ƃ��邠����s���v�戵���̋֎~�B�i�@47��C�A�K��19���j �i�Q�l�ٔ���j �����̌��K�������ɑ��A���������̊댯�͂Ȃ��Ƃ̏���������ɂ��ւ�炸�A�D�P�𗝗R�Ƃ��āA�P������O���A�����㏗���̃L�����A���~���Ă��܂����Ƃ́A�D�P�𗝗R�Ƃ������ʁB�i�^�b�v�����F�ٗp�R����1998�N�j |
�@ | �@ | �@ | |||||
| ���� ���� |
���D�P�E�o�Y�y�ъ֘A�����w�I��ԂɊ�Â����ʂ́A���Ɋ�Â����ʂƂ����B�i�������@��V��701��(k)��P���O���A703��(a)�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I��Ԃɂ��e�����Ă��鏗���́A�����������܂ނ��ׂĂ̌ٗp�Ɋ֘A��������ɂ����āA���l�̘J���\�͖��͕s�\�͂̏�Ԃɂ��鑼�̎҂Ɠ����戵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �i�������@��V��701��(k)��P���㔼�j |
���w��92/85/EEC�͈͓̔��́A�D�P���͏o�Y�ɔ��������ɑ���s���ȑҋ��́A�{�w�߂͈͓̔��̍��ʂɑ������邱�ƂƂ���B�i����76�w�߂Q���V�j | ���D�P�E�o�Y�A�ʏ�Y�x�E�lj��Y�x���擾�������Ɩ��͎擾���悤�Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ��邠����s���v�戵���̋֎~�B�i�@47��C�A�K��19���j | �@ | �@ | �@ | |||||
| ���� | ���D�P�E�o�Y�y�ъ֘A�����w�I��ԂɊ�Â����ʂ́A���Ɋ�Â����ʂƂ����B�i�������@��V��701��(k)��P���O���A703��(a)�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I��Ԃɂ��e�����Ă��鏗���́A�����������܂ނ��ׂĂ̌ٗp�Ɋ֘A��������ɂ����āA���l�̘J���\�͖��͕s�\�͂̏�Ԃɂ��鑼�̎҂Ɠ����戵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �i�������@��V��701��(k)��P���㔼�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I�ȏ�Ԃ𗝗R�Ƃ���J���҂̉��ق́A�����Ƃ���PDA�ᔽ�B�iEEOC�K�C�h���C��29CFR1604.10�j |
���w��92/85/EEC�͈͓̔��́A�D�P���͏o�Y�ɔ��������ɑ���s���ȑҋ��́A�{�w�߂͈͓̔��̍��ʂɑ������邱�ƂƂ���B�i����76�w�߂Q���V�j ���D�P�̊J�n����Y�O�Y��x�ɂ̏I���܂ł̉��ق̋֎~�i�J���҂̏Ƃ͊W���Ȃ���O�I�ȏꍇ�Ƃ��č����@���ɂ����ėe�F�����ꍇ�������B�j�B�i92/85/EEC�w��10���j �i�Q�l�ٔ���j ���Y�x�̑�֗v���Ƃ��Ċ��Ԃ̒�߂̂Ȃ��ٗp�_���������Ă��Ȃ���A�̗p����ɔD�P�������߂ɋΖ��ł��Ȃ����Y���������ق��邱�Ƃ͐����ʂƂȂ�A�ٗp�_��̊�{�I�ȕ����̐��s���s�\�ł��邱�Ƃ������Ƃ��Ă����ق͐���������Ȃ��B�i�E�F�b�u�����i�p�j���B�i�@�ٔ���1994�N�j ���ٗp�_�L���ł�����Ԃ̒�߂Ȃ����̂ł���A�D�P�𗝗R�Ƃ�����ق̍��ʓI�Ȑ����ɉe�����y�ڂ��Ȃ��B�i�e���E�f���}�[�N�����i�f���}�[�N�j���B�i�@�ٔ���2001�N�j ���̗p��A�D�P���Ă��邱�Ƃ������������J���҂��A��W�̍ۂɔD�P���Ă��邱�Ƃ���Ȃ��������Ƃ𗝗R�Ƃ��ĉ��ق��ꂽ���Ƃɂ��āA�D�P�𗝗R�Ƃ�����ق͐��ɂ�钼�ڍ��ʂɊY��������������Ȃ��Ƃ����B�i�j�[���\�������i�f���}�[�N�j���B�i�@�ٔ���2001�N�j |
���D�P�E�o�Y�A�ʏ�Y�x�E�lj��Y�x���擾�������Ɩ��͎擾���悤�Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ��邠����s���v�戵���̋֎~�B�i�@47��C�A�K��19���j ���D�P�E�o�Y�A�ʏ�Y�x�E�lj��Y�x���擾�������Ɩ��͎擾���悤�Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ�����ق͕s�����قƂ݂Ȃ����B�i�ٗp�����@99���A�K��20���j �i�Q�l�ٔ���j �������J���҂��A�o�Y�x�ɕ��A��A�o�Y�x�ɒ��̑�֗v���ƘJ�����Ԃ��V�F�A���邽�߂ɁA�x�X�J�����Ԃ��팸����A�ސE�Ɏ������̂́A�I���ȉ��قł���A�����ʂƂ��ꂽ�B�i�M���X�s�[����2002�N�j |
���D�P���A�Y�x���Ԓ��A�Y�x���Ԗ�����S�T�Ԃ̊Ԃ̘J���_��̉����̋֎~�B�i�D�P�ɊW���Ȃ��J���҂ɂ��d��ȉߎ����ɂ��ꍇ�������B�j�i�@122��-25-2�j | ���D�P������яo�Y��S�����܂ł̏����J���҂ɑ��āA�g�p�҂����ٍ��m�̎��_�ŔD�P�E�o�Y��F�����Ă����ꍇ�A�܂��͉��ٍ��m��Q�T�Ԉȓ��ɂ��̎|��ʒm���ꂽ�ꍇ�́A���ٍ��m�͔F�߂��Ȃ��B�i�@9���j�������A�s�������̋��ė�O�I�ɓ��ʉ��ق����邱�Ƃ͉\�B�i�@9��(3)�j | �������A�D�P�A�o�Y�������Ƃ�ސE���R�Ƃ��Ē�߂邱�Ƃ��֎~�B�i�ϓ��@�W��(2)�j ���������A�D�P���A�o�Y���A�Y�O�Y��x�Ƃ��������Ƃ𗝗R�Ƃ�����ق̋֎~�B�i�ϓ��@�W��(3)�j |
|||||
| �َ~�� | ���D�P�E�o�Y�y�ъ֘A�����w�I��ԂɊ�Â����ʂ́A���Ɋ�Â����ʂƂ����B�i�������@��V��701��(k)��P���O���A703��(a)�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I��Ԃɂ��e�����Ă��鏗���́A�����������܂ނ��ׂĂ̌ٗp�Ɋ֘A��������ɂ����āA���l�̘J���\�͖��͕s�\�͂̏�Ԃɂ��鑼�̎҂Ɠ����戵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�������@��V��701��(k)��P���㔼�j |
���w��92/85/EEC�͈͓̔��́A�D�P���͏o�Y�ɔ��������ɑ���s���ȑҋ��́A�{�w�߂͈͓̔��̍��ʂɑ������邱�ƂƂ���B�i����76�w�߂Q���V�j �i�Q�l�ٔ���j ���z�[���w���p�[�Ƃ��ėL���̘J���_����S��X�V�i�����ŏ��̂Q��͌_��̏I�����Ԃ�������Ă������A��̂Q��͌_��̏I�����Ԃ������ꂸ�A��Ɏ莆�ŏI�����������������j���ꂽ�������A�D�P����������A�g�p�҂���A�_����I�������|�������A�_�I�����ꂽ���Ăɂ��āA�J���҂��D�P�������߂ɗL���_����X�V���Ȃ����Ƃ́A�ϓ��ҋ��w�߂ɋK�肷�鐫�ɂ�钼�ڍ��ʂ��\������Ƃ��ꂽ�B�i�����K�[�����i�X�y�C���j���B�i�@�ٔ���2001�N�j |
���D�P�E�o�Y�A�ʏ�Y�x�E�lj��Y�x���擾�������Ɩ��͎擾���悤�Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ��邠����s���v�戵���̋֎~�B�i�@47��C�A�K��19���j | �@ | �@ | ���`���I�ɂ͌ٗp���Ԃ��߂��_��ł����Ă��A���ꂪ�����X�V����A�����ɂ����Ă͊��Ԃ̒�߂̂Ȃ��ٗp�_��ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A���̊��Ԃ̖����𗝗R�Ƃ��Čق��~�߂����邱�Ƃ́u���فv�ɓ�������̂ł��邱�ƁB�i���ߒʒB�j | |||||
| ���� | ���D�P�E�o�Y�y�ъ֘A�����w�I��ԂɊ�Â����ʂ́A���Ɋ�Â����ʂƂ����B�i�������@��V��701��(k)��P���O���A703��(a)�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I��Ԃɂ��e�����Ă��鏗���́A�����������܂ނ��ׂĂ̌ٗp�Ɋ֘A��������ɂ����āA���l�̘J���\�͖��͕s�\�͂̏�Ԃɂ��鑼�̎҂Ɠ����戵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �i�������@��V��701��(k)��P���㔼�j �������ɂ��āA���̈ꎞ�I�J���s�\�̘J���҂Ɠ��l�Ɏ�舵��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�iEEOC"Facts about Pregnancy Discrimination"�j |
���w��92/85/EEC�͈͓̔��́A�D�P���͏o�Y�ɔ��������ɑ���s���ȑҋ��́A�{�w�߂͈͓̔��̍��ʂɑ������邱�ƂƂ���B�i����76�w�߂Q���V�j ���Y�x���擾���������́A�Y�x�����ɁA�x�ɒ��Ɏ���͂��ł������J�������̉��P�̉��b���錠����L����B�i����76�w�߂Q���V�j |
���D�P�E�o�Y�A�ʏ�Y�x�E�lj��Y�x���擾�������Ɩ��͎擾���悤�Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ��邠����s���v�戵���̋֎~�B�i�@47��C�A�K��19���j | �@ | �@ | �@ | |||||
| �Y�x�� �� �擾 �� �� ���� �� |
���D�P�E�o�Y�y�ъ֘A�����w�I��ԂɊ�Â����ʂ́A���Ɋ�Â����ʂƂ����B�i�������@��V��701��(k)��P���O���A703��(a)�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I��Ԃɂ��e�����Ă��鏗���́A�����������܂ނ��ׂĂ̌ٗp�Ɋ֘A��������ɂ����āA���l�̘J���\�͖��͕s�\�͂̏�Ԃɂ��鑼�̎҂Ɠ����戵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �i�������@��V��701��(k)��P���㔼�j �����N�ی��̒ɓ������ẮA�D�P�Ɋ֘A���錒�N��Ԃ𑼂̌��N��ԂƓ��l�Ɏ�舵��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�iEEOC"Facts about Pregnancy Discrimination"�j ����C���̒~�ϋy�ѕt�^�A�x�ɂ̌v�Z�A�����y�шꎞ�I��Q���t�ɂ����āA���̈ꎞ�I�J���s�\�̘J���҂Ɠ��l�Ɏ�舵��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�iEEOC"Facts about Pregnancy Discrimination"�j �����N���t�ɂ��ẮA�Ƒ���Ëx�ɒ��ɋΖ����p�����Ă����Ȃ�Η^�����Ă����͂��̓��e�Ɠ����e�Ōp�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�iFMLA104��(c)�j ���Ƒ���Ëx�ɂ��畜�E����J���҂͋x�ɑO�ɗL���Ă����S�Ă̌ٗp��̌�����L����B�iFMLA104��(a)(1)�j |
���w��92/85/EEC�͈͓̔��́A�D�P���͏o�Y�ɔ��������ɑ���s���ȑҋ��́A�{�w�߂͈͓̔��̍��ʂɑ������邱�ƂƂ���B�i����76�w�߂Q���V�j ���Y�x���擾���������́A�Y�x�����ɁA�x�ɒ��Ɏ���͂��ł������J�������̉��P�̉��b���錠����L����B�i����76�w�߂Q���V�j |
���D�P�E�o�Y�A�ʏ�Y�x�E�lj��Y�x���擾�������Ɩ��͎擾���悤�Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ��邠����s���v�戵���̋֎~�B�i�@47��C�A�K��19���j ���ʏ�Y�x���擾�����J���҂́A�x�ɂ��擾���Ȃ������ꍇ�ɓK�p���ꂽ�͂��̌ٗp�����i�����������j�̗��v���錠����L���A�`�����B�i�@71��(4)(a)�y��(b)�A�K���X���j ���lj��Y�x���擾�����J���҂́A���Ǝ�َ̖��̋`�����琶���闘�v�A�ٗp�_��I���ʒm���Ɋւ���ٗp�������琶���闘�v���錠����L����i�@73��(4)(a)�y��(b)�A�K��17���j�B�܂��A���Ǝ�ɑ���َ��̋`���y�ю��Ȃɂ��ٗp�_��I���ʒm���Ɋւ���ٗp�����ɍS�������B�i�@73��(4)�A�K��17���j�B |
���Y�x�̊��Ԃ́A�Α��N������ɔ�ٗp�҂��L���鏔�����̌���ɓ������Ă͎������ԂƂ݂Ȃ����B�i�@122��-26-2�j ���j���ϓ��ҋ��w�߁i����76�w�߁j�́u�Y�x���̘J�������̉��P�̉��b���錠���v�������@�ŒS�ۂł��Ă���̂��ۂ��͌������B�i�����{����̃q�A�����O�j |
�@ | �@ | |||||
| �D�P�E�o�Y�N���̏Ǐ�𗝗R�Ƃ����s���v�戵�� | ���D�P�E�o�Y�y�ъ֘A�����w�I��ԂɊ�Â����ʂ́A���Ɋ�Â����ʂƂ����B�i�������@��V��701��(k)��P���O���A703��(a)�j ���D�P�E�o�Y���͊֘A�����w�I��Ԃɂ��e�����Ă��鏗���́A�����������܂ނ��ׂĂ̌ٗp�Ɋ֘A��������ɂ����āA���l�̘J���\�͖��͕s�\�͂̏�Ԃɂ��鑼�̎҂Ɠ����戵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�������@��V��701��(k)��P���㔼�j �i�Q�l�ٔ���j �����p���Ԓ��ɁA�D�P�ɂ�錒�N��Ԃ̖�肩�猇�A�x���A���ނ��J��Ԃ��A���ق��ꂽ���Ƃɂ��āA�D�P�ȊO�̗��R�ɂ��J���҂̌������߂����̂łȂ���APDA�ᔽ�ł͂Ȃ��Ƃ����B�i�A�[�~���h����2000�N�j |
���w��92/85/EEC�͈͓̔��́A�D�P���͏o�Y�ɔ��������ɑ���s���ȑҋ��́A�{�w�߂͈͓̔��̍��ʂɑ������邱�ƂƂ���B�i����76�w�߂Q���V�j ���D�P�̊J�n����Y�O�Y��x�ɂ̏I���܂ł̉��ق̋֎~�i�J���҂̏Ƃ͊W���Ȃ���O�I�ȏꍇ�Ƃ��č����@���ɂ����ėe�F�����ꍇ�������B�j�B�i92/85/EEC�w��10���j �i�Q�l�ٔ���j �������J���҂��D�P�ɋN������a�C�������̏A�J�s�\�ɂ�茇�������߁A�Q�U�T�ȏ�a�C�̂��߂Ɍ�����ꍇ�͉��ق����ƋK�肳�ꂽ�ٗp�_��ɏ]���A�i�Y�x�擾�O�ł����Ă��j�D�P���ɉ��ق��ꂽ���Ƃ́A�����ʂƂȂ�B�i�u���E�������i�p�j���B�i�@�ٔ���1998�N�j ���i�Y�x�O�Ƃ͈قȂ�j�Y�x��ɂ��Ă͔D�P�y�яo�Y�������Ő������a�C�𑼂̕a�C�Ƌ�ʂ��闝�R�͂Ȃ��A�o�Y�P�N���100���Ԃ̕a�x���擾���������J���҂����ق����ꍇ�A�����ƒj���ƂŎ戵�����قȂ�Ȃ��ꍇ�A�����ʂƂ͂Ȃ�Ȃ��B�i�w���c�����i�f���}�[�N�j1990�N�j |
�@ | �@ | �@ | ���D�P�E�o�Y�ɔ������̂ł��邱�Ƃ��ʏ�ł���Ǐ�ɂ��x�Ƃ��擾�������Ƃ𗝗R�Ƃ�����ق́A�ʏ�A�J���҂����l�̋x�Ɠ����擾���Ă����قɎ���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����I�ɂ͔D�P�E�o�Y�𗝗R�Ƃ������قƂȂ�\��������B�i���ߒʒB�j | |||||
| �ꐫ�ی�[�u�A�D�P�E�o�Y�x�ɓ� | �yPDA�AEEOC"Facts about Pregnancy Discrimination"�z �����̈ꎞ�I�J���s�\�̘J���҂Ɠ��l�Ɏ�舵��Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�d�����e�̌y���A��֓I�Ɩ��̊����A��Q�x�ɂ̕t�^�A�����̋x�ɂ̕t�^���j�B �����N�ی��i�g�p�҂����錒�N�ی��ɂ����ẮA�D�P�Ɋ֘A���錒�N��Ԃ��A���̌��N��ԂƓ��l�ɃJ�o�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�j ���t�����t�i�g�p�҂��A�x�ƒ��̘J���҂ɉ��炩�̋��t���s���Ă���ꍇ�́A�D�P�E�o�Y�Ɋ֘A�����Ԃɂ��x�ƒ��̘J���҂ɑ��āA���l�ɋ��t���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�j ����C�����i��C���̒~�ϋy�ѕt�^�A�x�ɂ̌v�Z�A�����y�шꎞ�I��Q���t�ɂ����āA���̈ꎞ�I�J���s�\�̘J���҂Ɠ��l�Ɏ�舵���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�j �yFMLA�z �����i�̂���J���҂ɁA(1)�q�̒a���y�ѐ��܂ꂽ�q�̐��b�̂��߁A(2)�J���Ҏ��g���E���𐋍s�ł��Ȃ��悤�Ȑ[���Ȍ��N��ԁi�D�P�ɂ���ē��퐶�����s�\�ɂȂ邱�Ƌy�юY�O�̃P�A���܂ށj�ɂ��邽�߁A(3)�J���҂̔z��ҁA�q���͐e���A�[���Ȍ��N��Ԃɂ���ꍇ�ɁA���̐��b�����邽�ߓ��̎��R�ɂ��x�ɂ̌����i12������12�T�ԁj�̕t�^�B�i�@101��(b)(1)�A102��(a)(1)(2)�j ���B�@�ɂ���ẮA�o�Y�x�ɂ�FMLA�Ƃ͈قȂ�`�ŋ`���Â��Ă�����̂�����i�J���t�H���j�A�B���j�B |
���Œ�14�T�Ԃ̏o�Y�x�Ɂi�o�Y�O��̍Œ�Q�T�Ԃ̋����o�Y�x�ɂ��܂ށj�i92/85/EEC�w�߂W���j ���o�Y�x�ɒ��̌ٗp�_��Ɋւ��錠���A�����̊m�ۋy�т������͏\���Ȏ蓖�̎̕ۏ�B�i92/85/EEC�w��11���j ���D�w���f�̂��߂̋x�ɂ��錠���̕t�^�i�����͑S�z�ۏj�B�i92/85/EEC�w�߂X���j ���g�p�҂́A���S�E���N�ւ̊댯���A�D�P���E�������̘J���҂ւ̉e�������炩�ȏꍇ�A�J�������A�J�����Ԃ��ꎞ�I�ɒ������邱�Ƃɂ��A�K�v�ȑ[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�J�������A�J�����Ԃ̒������ł��Ȃ��ꍇ�A�ʂ̎d���Ɉٓ��B�ʂ̎d���ւ̈ٓ����ł��Ȃ��ꍇ�A�K�v�ȑS�Ă̊��ԁA�x�ɂ��^������B�j�B�i92/85/EEC�w�߂T���j ���D�P���E�������̘J���҂́A���S�E���N���`�����悤�Ȗ\�I�̊댯�̂���Ɩ��̋֎~�B�i92/85/EEC�w�߂U���j ���D�P���̘J���҂́A�f�f���̒�o�������ɁA��Ƃ��s��Ȃ����Ƃ�ۏႳ���i���Ԃ̎d���ւ̓]���B���ꂪ�ł��Ȃ��ꍇ�͋x�ɂ������͏o�Y�x�ɂ̉����j�B�i92/85/EEC�w�߂V���j ��92/85/EEC�w�߂T�C�U�C�V���̏ꍇ�A�J���҂́A�����̊m�ہA�������͏\���Ȏ蓖�̎��̕ۏ�B�i92/85/EEC�w��11���j |
���ʏ�Y�x�̎擾�i�o�Y���邷�ׂĂ̏����J���҂��擾�ł���26�T�Ԃ̋x�ɁB�����Y�x�͏o�Y��Q�T�ԁj�B�i�@71�A72���A�K��7��(1)�j ���lj��Y�x�̎擾�i�ʏ�Y�x���Ƃ錠����L���A�Α��P�N�ȏ�̏����J���҂��擾�ł���A�ʏ�Y�x���ԏI����26�T�Ԃ̋x�Ɂj�B�i�@73���A�K��7��(4)�j���Y�x���́A�@��o�Y���t�Ȃ����o�Y�蓖���x���B�i�Љ�ۏዒ�o�E���t�@1992�N�j ���D�P���������J���҂͏o�Y�O�f�@�x�ɂ̂��ߗL���̃^�C���I�t����邱�Ƃ��ł���B�i�@55���j ���D�P�A�o�Y�A�������̏������A���N�E���S�ɗL�Q�Ȏd���ɂ��Ă���ꍇ�ɂ́A�A�Ƃ𒆒f���錠��������i�@66���j�i�J���҂͑�ւ̎d�������錠����L���A��֘J�����^����ꂸ�x�E����������Ȃ��ꍇ�ɂ́A��V�̎x������ۏ�j�B�i�@64���A68���j�������ʋ֎~�@�̎�|����A�D�P���E�o�Y��̏����ɑ����I�ȏA�Ƌ֎~�K��͑��݂��Ȃ��i�D�P�A�o�Y�A�M��ɑ��댯���̍����Ɩ���v�f�ɂ��Đ��{�̍L���Ɏ�����Ă��邪�A���Ǝ�̓P�[�X�o�C�P�[�X�őΉ��B�K�v�ɉ����ďA�ƒ��f�[�u�B�j�B |
���Y�x�̎擾�i��1�q�A��2�q�͎Y�O�U�T�ԁA�Y��10�T�ԁA��R�q�ȍ~�͎Y�O8�T�ԁA�Y��18�T�ԁB�Ȃ��A�o�q�̏ꍇ�A�Y�O12�T�ԁA�Y��22�T�ԁA�R�q�ȏ�̏ꍇ�A�Y�O24�T�ԁA�Y��22�T�ԁB�j�B�i�@122��-26�j ���Y�x�ɑ�������ۏ� ����w�I�ȏؖ����ɂ��A�D�P�E���ɋN������a����Ԃɂ��ẮA�o�Y�\����O�̂Q�T�ԋy�яo�Y��̂S�T�Ԃ����x�Ƃ��āA�Y�x�̉����B�i�@122��-26�j ����w�I�ɏؖ����ꂽ�D�P�̏�Ԃ܂��͏o�Y����ł���J���҂ɂ��āA(1)�댯�Ɩ��ɏA���Ă���ꍇ�A�ٗp��͎Y�ƈ�̏��������Ă��A���̐E�����Ă��Ȃ���Ȃ炸�A�܂��A(2)��ԘJ���ɏA���Ă���ꍇ�A�{�l�̗v���܂��͎Y�ƈ�̏ؖ��ɂ��A���Ԃ̐E���ɔz�u�]�������B�E�z�u�]���́A�Y�ƈ�̐\�����ɂ��Œ��P�����̉������\�ł���B���̔z�]�ɂ��A�����̌��z�͔F�߂��Ȃ��B���̎��Ə��ւ̔z�]�ɂ��Ă͘J���҂̓��ӂ�K�v�Ƃ���B�i�K��2002-792) �E��ԋƖ��E�댯�Ɩ��ɏA���Ă���ꍇ�A�ٗp�傪�ʂ̐E�����Ăł��Ȃ��ꍇ�A���Y�J���҂̌ٗp�_��͎Y�x�J�n���܂Œ�~�����B�J���_��̒�~���Ԓ��A�J���҂�(1)�ٗp��ɂ�苋�t�����⑫�蓖�A(2)��P���I���a�ی����ɂɂ�苋�t���������蓖����B�i�@122��-25-1-1�A122��-25-1-2�j ���D�P���̏����͋��^��r�����邱�ƂȂ��A�`���I������f����f���邽�߂Ɍ����錠�������B(�@122��25-3) ���������Ԃ̎擾�i�q�̒a����P�N�ԁA�������s���Ă����e�́A�J�����Ԓ��̂P���Ԏ������ԂɎg�����Ƃ��ł���B�j(�@224��-2�j |
�����ЁA�����A�����A�t���^�C���E�p�[�g�^�C���ɊW�Ȃ��A�h�C�c�����ɂ����Čٗp�W�ɂ��邷�ׂĂ̏����J���҂ɑ��K�p�����B�i�@�P���j ���Y�O�U�T�Ԃ͔D�P���̏������ӎv�\���������ꍇ�̂ݏA�Ƃ����邱�Ƃ��ł���B�i�@�R��(2)�j ���Y��W�T�Ԃ̐�ΓI�ȏA�Ƌ֎~�B�i�@�U���P���j ���Y�O�Y��ی���Ԓ��̏����ۏ�i�v�������@�莾�a�ی������҂́A�@�莾�a���ɂɂ��ꐫ�蓖�y�юg�p�҂���t�����t���x������铙�B�j�B�i�@13���j ���g�p�҂ɑ��A�D�P�E�������Ԃ̏����J���҂ɑ���E����Ɠ��e�̍\���Ɋւ���z���`���B�i�@�Q���j ���D�P�E�������Ԓ��̏����J���҂������̓I���S���Ɩ��A�L�Q�ȉe���ɂ��炳���Ɩ��ɏA�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�@�S��(1)�A�U��(3)�j ���g�p�҂́A�D�P���̏����J���҂ɑ��A�A�Ƃ̌p������́E�َ��Ɋ댯���y�ڂ��\��������ƈ�t���f�f�����ꍇ�A�A�Ƃ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�@�R��(1)�j ���Y�㐔�����́A��t�̐f�f���ɂ��A�����J���҂̑̒����J���̂��߂Ɋ��S�ł͂Ȃ��Ƃ��ꂽ�ꍇ�A�g�p�҂͘J���\�͂���A�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�@�U���j ���D�P�E�������Ԓ��̏����J���҂̖�ԁE�x���J���̋֎~�B�i�@�W���j �����ԊO�J���̐����B�i�@�W��(2)�j ���������Ԃ̕ۏ�B�i�@�V���j ���A�Ƌ֎~���̏����ۏ�i�Y�O�Y��̕ی���ԊO�ň�ʓI�y�ьʏA�Ƌ֎~�ɂ��A�A�Ƃł����A�E�����ς�����ꍇ�ɂ����Ă��A����܂ł̕��ϒ����邱�Ƃ��ł���B�j�B�i�@11���j |
���U�T�ԁi���ٔD�P�̏ꍇ��14�T�ԁj�̎Y�O�x�ɁA�W�T�Ԃ̎Y��x�Ɂi�Y��͋����B�A���A�Y��U�T�Ԃ��o�߂����������������A��t���x��Ȃ��ƔF�߂��Ɩ��ɏA�����邱�Ƃ͍����x���Ȃ��B�j�B�i�J��@65��(1)(2)�j ���o�Y�ꎞ���̎x���y�ш��̘J���ɕ����Ȃ��������ԁA�P���ɂ��W����V���z�̂U���ɑ�������o�Y�蓖���̎x���B�i���N�ی��@101,102���j ���g�p�҂́A�D�P���̏��������������ꍇ�A�y�ՂȋƖ��ɓ]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�J��@65��(3)�j ���g�p�҂́A�D�Y�w���댯�L�Q�Ɩ��ɏA�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�J��@64���̂R�j ���D�Y�w�����������ꍇ�͕ό`�J�����Ԑ��̓K�p����������A���ԊO�J���A�x���J���A�[��Ƃ��֎~�����B�i�J��@66���j ���玙���Ԃ̊m�ہB�i�J��@67���j ���g�p�҂́A�����J���҂��D�P���y�яo�Y��̕ی��w�����͌��N�f�����邽�߂̎��Ԃ��m�ۂ��A�w����������邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��邽�߁A�Ζ����Ԃ̕ύX�A�Ζ��̌y�����̕K�v�ȑ[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�ϓ��@22�A23���j |
|||||
| �@ | �A�����J | �d�t | �C�M���X | �h�C�c | ||
| �Ԑڍ��ʂɊւ���K�� | 1964�N�������@��7��703��(k)(1)�i1991�N������j �y703��(k)(1)�z �@�{�҂̉��ł́A�ȉ��̂����ꂩ�̏ꍇ�ɂ́A���ʓI���ʂɊ�Â���@�Ȍٗp���s�ƂȂ�B (i)�������A����g�p�҂̍s�ׂɂ�荷�ʓI���ʂ��������邱�Ƃ��ؖ������̂ɑ��A�g�p�҂��A���ꂪ���Y�n�ʂɂ�����E���Ɗ֘A��������A���Ɩ���̕K�v���ɍ��v���Ă��邱�Ƃ��ؖ����Ȃ������ꍇ (�A)�������A����ɑ���ʂ̕��@�����݂��邱�Ƃ��ؖ������̂ɑ��A�g�p�҂����̗̍p�����ۂ���ꍇ |
�ϓ��ҋ��Ɋւ���76�N�w�ߏC���i76/207/EEC�w�߁j�i2002/73/EC�w�߂ɂ������j �y2��2�z �Ԑڍ��ʁF�O����͒����ȋK��A����͊��s���A���̐��̍\�����Ɣ�r���āA����̐��̍\�����ɓ���̕s���v��^����ꍇ�B�������A���Y�K��A����͊��s���A�����ȖړI�ɂ���ċq�ϓI�ɐ���������A���̖ړI�����������i���K���K�v�ł���ꍇ�͂��̌���ł͂Ȃ��B �@�i�Q�l�F1976�N������76/207/EEC�w�߂̋K��j �y 2��1�z �ϓ��ҋ��̌����Ƃ́A���ړI�����͊ԐړI�ł��邩�ɂ�����炸���ʁA���ɍ�����������͉Ƒ���̒n�ʂɊ֘A�������R�Ɋ�Â������Ȃ鍷�ʂ����݂��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ӗ�������̂ł���B �����ʎ����̋��ؐӔC�Ɋւ���1997�N12��15���̗�����w�߁i97/80/EC�j �y2���z �P�@�{�w�߂ł́A�ϓ��ҋ������Ƃ́A�ԐړI�ɂ����ړI�ɂ��A���ʂɊ�Â��Ȃ��̍��ʂ��Ȃ����Ƃł���B �Q�@��P���Ō��y�����ϓ��ҋ������Ɋւ��āA�O����͒����I�ȋK��A��A���s���A����̐��ʂɑ����鐬���ɕs�ύt�ɕs���v��^����ꍇ�A������K��A��A���s���K���K�v�ł���A���ʂƊ֘A���̂Ȃ��q�ϓI�v�f�ɂ���Đ������ł��Ȃ�����A�Ԑڍ��ʂ����݂��Ă�����̂Ƃ���B |
1975�N�����ʋ֎~�@1��1(2)(b)�A2��(1)�i2001�N������j �y1��1(2)(b)�z �{�����K�p�����K��Ɋւ��邢���Ȃ�ꍇ�ɂ����Ă��A�ȉ��̍s�ׂ��s�����҂͏����ɑ��鍷�ʂ��s�������̂Ƃ���B �E���Y�s�҂��j���ɑ����l�ɓK�p���A���͓K�p����ł��낤�ȉ��̂悤�ȋK��A����͊��s���A�����ɑ��ēK�p�����ꍇ (�@)����ɂ��s���v���鏗���̊������A�s���v����j���̊��������������x�傫���A���A (�A)���Y�s�҂����̓K�p�����҂̐��ʂɊW�Ȃ������ł��邱�Ƃ𗧏������A���� (�B)���̏����ɑ��A�s���v�ƂȂ���� �y2��(1)�z ���̋K��͒j���ɂ��K�p�����B �i�Q�l�F1975�N�����̐����ʋ֎~�@�̋K��j �y1��1(1)(b)�z �{�����K�p�����K��Ɋւ��邢���Ȃ�ꍇ�ɂ����Ă��A�ȉ��̍s�ׂ��s�����҂͏����ɑ��鍷�ʂ��s�������̂Ƃ���B �E���Y�s�҂��j���ɑ����l�ɓK�p���A���͓K�p����ł��낤�ȉ��̂悤�ȗv�����͏������A�����ɑ��ēK�p�����ꍇ (�@)����ɓK�������鏗���̊������A����ɓK��������j���̊��������������x�������A���� (�A)���Y�s�҂����̓K�p�����҂̐��ʂɊW�Ȃ������ł��邱�Ƃ𗧏������A���� (�B�j����������ɓK�������Ȃ����̂ɁA���̏����ɑ��A�s���v�ƂȂ���� �y2��(1)�z �@���̋K��͒j���ɂ��K�p�����B |
���@��611������1���A612���3���i�Ԑڍ��ʂɂ��Ă̖��m�ȋK��͂Ȃ����A���߂ɂ���āA��L�K��Ɋ܂܂�Ă���Ɖ�����Ă���B�j �i�Q�l�j �y611����(1)�z �@�g�p�҂́A��p�҂Ɩ����Ȃ��A���͘J���҂Ɋւ���[�u���u����ꍇ�ɁA���Ɍٗp�_��̐ݒ�A���i�A�E����̎w���A���ق��s���ꍇ�ɁA���𗝗R�Ƃ��ĕs���Ɉ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A����[�u����p�҂̐��s����E���̐����Ɋ�Â��A���A���̐������Y�E���̕s���̑O��ł���Ƃ��ɂ́A���ɂ��قȂ����戵�����������B�������������ꍇ�ɁA��p�҂����ɂ��s���v�戵���𐄑������߂鎖����a�������Ƃ��ɂ́A�g�p�҂͕s���v�戵�������ɂ��Ȃ������I�ȗ��R�Ɋ�Â����̂ł��邱�Ɩ��͂��̐������s�����E���ɂƂ��ĕs���̑O����Ȃ����̂ł��邱�Ƃɂ��A���ؐӔC�����̂Ƃ���B �y612��(3)�z �@�ٗp�_��ɂ����ē��ꖔ�͓����Ƃ݂Ȃ����J���ɑ��A���ʂ𗝗R�Ƃ��āA�����̐��̎҂��Ⴂ��V���肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B��p�҂̐��𗝗R�ɓ��ʂȕی�K�肪�K�p����邱�Ƃ͒Ⴂ��V�̖��𐳓���������̂łȂ��B611������P����R���͏��p����B |
||
| �Ԑڍ��ʂƂ��ď�������鎖�Ă͈͓̔� | �y��舵�����Ă̓����z �E�̗p�E���i�Ɋւ��鎖�Ă������A���ق͏��Ȃ��B �E�����ɂ��Ă͓�������@�ŋK�肵�Ă��邱�ƂƂ̊W�œK�p��͂Ȃ��B �E�p�[�g�^�C���J���҂�ƒ�ӔC�̗L�����ɌW�鎖�����Ԑڍ��ʂƂ��ꂽ��͂Ȃ��B �y�Ԑڍ��ʂƂ��ď�������鎖�āz �E�j���̐����I�ȑ���Ɋւ����i��F�g���A�̏d�v�����ۂ����ƁA�̗̓e�X�g�ɂ��I�l���j �E�ߋ��̋����̍��ʓ��������ŁA����O���[�v�ɂ����Ė������ɂ�����i��F��ʒm�\�e�X�g�A�w���A�o���v���A����v���A��ϓI�I�l���蓙�j �i�Q�l�ٔ���j �E�g�p�҂��A���d���̍�ƈ��̎��i�v���Ƃ��āA�����ȏ�̊w���ƈ�ʓI�m�\�E����̓e�X�g�ւ̍��i��v�������P�[�X�ɂ��A�A�M�ō��ٔ����́A������̗v����(1)�ߋ��̋����̍��ʂ̂��߂ɍ��l�ɑ��č��ʓI�Ȍ��ʂ������炵�A���A(2)�E���̏\���Ȑ��s�Ƃ̖����ȊW���Ȃ��A�Ɩ���̕K�v����E���֘A�����F�߂��Ȃ��Ƃ����������w�E������ŁA�g�p�҂ɍ��ʈӎv���Ȃ������Ƃ��Ă���V�҈ᔽ�����������Ƃ����B���̔����́A��V�҂̖ړI���A���炩�ȍ��ʂ̋֎~�ɂƂǂ܂炸�A�ٗp����}�C�m���e�B�����ʓI�ɔr��������ʂ����u�l�דI�A���ӓI���s�K�v�ȏ�ǁv�̏������܂ނ��Ƃ��������Ă���B�i�O���b�O�X�����@�A�M�ō��ف@1971�N�j �E�Y�����̊Ŏ�ɂ��āA�̏d120�|���h�ȏ�A�g��5�t�B�[�g2�C���`�ȏ�Ƃ����v���������ɑ��č��ʓI�Ȍ��ʂ�L���A�E���֘A�����F�߂��Ȃ��̂ŁA��@�Ɣ��f���ꂽ�B�i�h�T�[�h�����@�A�M�ō��ف@1977�N�j �E��s�Ɍٗp����Ă��鍕�l�����̌����͉��債���S�̃|�X�g�̂�����ɂ��̗p����Ȃ������B���Y��s�́A����҂�]�����邽�߂̊m���������L���Ă��炸�A�ē҂̎�ϓI���f�Ɉς˂Ă���A���������ۂ����ē҂͑S�Ĕ��l�ł������B�n�فA�T�i�R�́A�����̑i�������p�������A�A�M�ō��ق́A���ʓI���ʗ��_�͋q�ϓI��ɂ��I�l�̂����炷���ʓI���ʂ݂̂Ȃ炸�A��ϓI��ɂ��I�l�̂����炷���ʓI���ʂɂ��K�p������Ɣ������A�����߂����B�i���g�\�������@�A�M�ō��ف@1988�N�j �y�Ԑڍ��ʂƂ��ď�������Ȃ����āz �E�^���Ȑ�C�����x�ɂ���Đ������ٗp�����̍��ق́A���ꂪ���ʓI�Ӑ}�̌��ʂłȂ�����A��@�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�i�������@��V��703���ih�j�j �E���ʂ𗝗R�Ƃ����V�ɂ����鍷�ʂ͌����Ƃ��Ĉ�@�����A���ɂ������i������������@�iEPA�j�̋K��ɂ�营�F����Ă���ꍇ�́A��V�҈ᔽ�ɊY�����Ȃ��B
�i�Q�l�ٔ���j �E��w�̊Ō�w���i�命���������j�̋������A�������E���̉��l���C�G����命����j������߂�w���̋����̒������Ⴍ�A�e�w���̐E���̎s�ꉿ�l�Ɋ�Â��Ē�����ݒ肷��Ƃ����\�ʏ㒆���I�ȑ�w�̕��j�A�s�ׂ����ʓI���ʂ�L����@�ł���Ƒi�������A��V�҂���̉�����A�M����͋@��̕����ł���A���ʂ̕����ł͂Ȃ��A�s�ꉿ�i�͖{���I�ɐE���Ɋ֘A������̂ł���A�����̎咣��F�߂邱�Ƃ́A�g�p�҂ɓƗ������o�c���f�ł͂Ȃ������i���̐ӔC���ۂ����ƂɂȂ��Ɣ��������B�i�X�|���f�B���O�����@�A�M��X����ٔ����@1984�N�j |
�y�Ԑڍ��ʂƂ��ď�������鎖�āz �E�p�[�g�^�C���J���҂ƃt���^�C���J���҂ƂňقȂ鏈���� �i�Q�l�ٔ���j �E�퍐��Ђ̔N�����x���A�p�[�g�J���҂́A���v20�N�̂���15�N�ȏ�t���^�C���ŋΖ������ꍇ�̂ݔN�����ł��邱�ƂƂ��Ă��邱�Ƃɂ��āA�ł��Ȃ������������A�Ƒ���q���̖ʓ|�����邽�߂ɂ͏����͒j�������p�[�g�J���ɏ]�����邱�Ƃ��������߁A������s���v�ȗ���ɒu�����̂Ƃ��A�i�������Ăɂ��A���B�i�@�ٔ����́A�p�[�g�J���҂��N�����珜�O����邱�Ƃ����Ɋ�Â������Ȃ鍷�ʂɂ��֘A���Ȃ��q�ϓI�ɐ���������鎖�R�Ɋ�Â��Ă��邱�Ƃ���Ƃ��ؖ����Ȃ�����A���119���ɒ�G����Ƃ����B���̍ہA��Б��ɍ��ʂ̈Ӑ}�͕K�v�ł͂Ȃ��B�i�r���J�����i�Ɓj���B�i�@�ٔ����@1986�N�j �E�ŃA�h�o�C�U�[���i�����̖Ə�������Ζ����Ԃ��A�t���^�C���ƃp�[�g�^�C���ƂňقȂ邱�ƂƂ���̂́A�u���[�����̐Ŏ������ŋΖ�����119���̃p�[�g�^�C���̂���110���������ł��邱�Ƃ���A�Ԑڍ��ʂƂ��đi�������Ăɂ��A���B�i�@�ٔ����́A�{���͎��ۂɏ����ɐ����ʓI���ʂ�^���Ă���A�����Ƃ��Ďw�߈ᔽ�ł���A���Ɋ�Â����ʂƊW�̂Ȃ��v���ɂ���Đ������ł���ꍇ�Ɍ���A���_���قȂ��Ƃ����B�i�R�[�f�B���O�����i�Ɓj���B�i�@�ٔ����@1997�N�j �E�������ق��ꂽ�p�[�g�J���҂̌������������ق�����ꍇ�Ɏg�p�҂��Љ�I��Ɋ�Â��I�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��J���҂̃J�e�S���[����p�[�g�J���҂����O���邱�Ƃ͎w�߂Ɉᔽ����Ƃ��đi�������Ăɂ��A���B�i�@�ٔ����́A76�w�߂́A�p�[�g�J���҂��t���^�C���J���҂Ɣ�r�����Ȃ��Ƃ�����ʓI�ȍ����Ɋ�Â��Đi�s���鍑�����[�����A���̑ΏۂƂ����Ƃ����B�i�J�b�q�F���}�������i�Ɓj���B�i�@�ٔ����@2000�N�j |
�y��舵�����Ă̓����z �E�V���O���}�U�[��p�[�g�^�C���J���҂ȂǎЉ�I�Ȗ���ƒ�ӔC���Ɋւ�鎖�Ă������B �y�Ԑڍ��ʂƂ��ď�������鎖�āz �E�j���̐����I�ȑ���Ɋւ����i��F�g���A�̏d�v�����ۂ����ƁA�̗̓e�X�g�ɂ��I�l�j �E�Љ���⏗���ɉƒ�ӔC�����邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�V���O���}�U�[�ɂƂ��Ė������ɂ������p�[�g�^�C���J���҂ƃt���C���J���҂ƂňقȂ��� �i�Q�l�ٔ���j �E������ق̍ہA�t���^�C���J���҂ɂ͐�C�����[����K�p�������A�p�[�g�J���҂��ɉ��ق���Ƃ����J������ɂ��āA�J���R�����y�ьٗp��i�R�������t���^�C���J�����C����Ƃ��邱�Ƃ́A�����ʋ֎~�@�ɋK�肷��Ԑڍ��ʂ��\������Ƃ��A�X�ɁA��C������K�v�Ƃ������ƂƁA�p�[�g�^�C���̗D����ق͈قȂ���̂ł���A���ɍ��ʓI�ł���A�������͔F�߂��Ȃ��Ƃ����B�i�N���[�N�����@�ٗp��i�R�����@1982�N�j �E�q�����Y�����̏������p�[�g�Ζ���\���o�����A�����ꂸ�A�t���^�C���Ζ���v������邱�Ƃ͊Ԑڍ��ʂƂ��đi�������Ăɂ��A�ٔ����́A����Љ�ɂ����鏗���̖����̕ω��ɂ��S��炸�A�j�����������͈玙���傫�ȕ��S�ƂȂ��Ă���͎̂����Ƃ��A�g�p�҂̓t���^�C���œ����Ƃ����v���������������Ƃ������Ƃ������Ă��Ȃ��Ƃ��āA�Ԑڍ��ʂ��F�߂�ꂽ�B�i�z�����Y�����@�ٗp��i�R�����@1984�N�j |
�y��舵�����Ă̓����z �E�p�[�g�^�C���J���҂Ɋւ��鎖�Ă��قƂ�ǂł���B �E�ʏ�̒����ȊO�́A��ƔN����x�ɓ��̕t���I���t�̎x���v���Ɋւ��鎖�Ă������B �i�Q�l�ٔ���j �E���i�v���ł���U�N�̓K���ώ@���ԁi�Α��N���j�̌v�Z�ɂ��T�J�����Ԃ��ʏ�̂S���̂R�ȏ�̘J���҂��P�C�����ȏ�̎҂�0.5�Ƃ��Čv�Z���鋦��K��Ɋ�Â��A�T20���ԘJ���̑�w�����E���̏��i������F�߂Ȃ��������Ăɂ����āA�E����K��ɂ��K���ώ@���ԁi�Α��N���j���Q�{�Ƃ����p�[�g�^�C���J���҂ɂ����鏗���̔䗦��90�����邱�ƁA�܂��A�E�s�����戵���𐳓������闝�R���Ȃ����ƂŁA�Ԑڍ��ʂɓ�����Ƃ��ꂽ��i�j���c�����@�A�M�J���ٔ����@1992�N�j |
||
| ����̐��ɑ���s���v�̗L���̔��f� | �E�u5����4���[���v�ɂ��F��B�iEEOC���j �i���̑I�l�葱�����ɂ�����A����O���[�v�i�l��E�����j�̐��������ł��������̍����O���[�v��5����4�������ꍇ�́A���̑I�l�葱�����́A��ʓI�ɍ��ʓI���ʂ�����Ɣ��f�����B�������A���v�I�L�א��̗L�����ɂ���āA��O�͂���B�j �i�Q�l�ٔ���j �E���K�����琳���Ȏ�����h�m�ɂȂ邽�߂̐g�̕q�����e�X�g�iPAT�j�̃e�X�g�̂P�ɂ��āA�U�l�̏������K�����h�m�͂S�l�������i���Ȃ��������A24�l�̒j�����K�����h�m�͑S�����i�����B�A�M����ٔ����́APAT���ۂ����Ƃ́A�����̍��i�����j���̂W��������邱�Ƃ���A�����ɑ��鍷�ʓI���ʂ�L���Ă������Ƃ�F�߂��B�܂��A�e�X�g�̐E���֘A���ɂ��Ă��؋����Ȃ��Ƃ��A�퍐�ɑ��A���e�X�g�ւ̕s���i�𗝗R�ɉ��ق������������K���Ƃ��čČٗp���A�����𐳎��ȏ��h�m�Ƃ���O��Ƃ��č��ʂ̂Ȃ��e�X�g�̍ĊJ���𖽂����B�i�t�@�[�~���O�r�������@�A�M��Q����ٔ����@1999�N�j |
�E��̓I�Ȕ��f�͊e���̍ٔ������s���B �i��܂������f��͂Ȃ��B�j �i�Q�l�ٔ���j �E�ٗp�����@�ɂ����ĕs�������ق̐\�����Ȃ�����v�����Α��Q�N�ȏ�Ƃ���Ă��邱�Ƃ͒j���ɔ�ׂ���������������Ȃ��A�Ԑڍ��ʂł���Ƃ��đi�������Ăɂ��A���B�i�@�ٔ����́A���̗v���͒j��77.4���A����68.9�����������Ă���A�ꌩ���ď������j���ɔ�ׂđ������x���Ȃ��Ƃ������Ƃ������Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��B�����ٔ����́A�j���������|�I�ɏ����̏����������̑[�u�ɂ��ۂ����v�����[���ł��Ȃ����Ƃ����\�ȓ��v�������Ă��邩�������Ȃ���Ȃ炸�A���������ł���A���̑[�u�����ʂɊ�Â����ʂɊ֘A���Ȃ��q�ϓI�ȗv�f�ɂ�萳��������Ȃ�����A�Ԑڍ����Ɣ��������B �i�V�[���A�E�X�~�X�����i�p�j1999�N�j |
�E��̓I�Ȕ��f�͌ٗp�i�J���j�R�������s���B �E���ʓI���ʂ̗L���ɂ��Ē�܂������f��͂Ȃ��A���ێ������N�����ĐR���������f�������܂Ō��ʂ�\�����邱�Ƃ�����ȌX��������B ��2001�N�����ɂ��A�u�v��������v�́u�K��A����͊��s�v�ɉ������ꂽ�B �i�Q�l�ٔ���j �E�p�[�g�����ł��錴����������ق��ꂽ�ہA�N�����x��50����60�łT�N�ȏ�Α����Ă��������ɂ��ސE���������ɑ��āA��p�̌ٗp�_��ɂ�����J�����Ԃɔ�Ⴕ�ĕt���I�ȋΑ��N�������Z�����d�g�݂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ́A�����ɑ���Ԑڍ��ʂƂ��đi�������Ăɂ��A�J���R�����́A�t���^�C����50�Έȏ�̏������t�̊����i89.5���j�̓t���^�C����50�Έȏ�̒j�����t�̊����i97���j��葊�����x�������Ƃ͂����Ȃ��Ƃ����B�ٗp��i�R�����������������x�������Ƃ����邩�ۂ��͘J���R�����̌��肷�鎖���Ƃ��A�J���R�����̔��f���x�������B�i�u���b�N�����@�ٗp��i�R�����@1994�N�j �E�n���S�^�]��Ƃ��������V���O���}�U�[�̌������A��Ђ��V���ɓ�����������Ζ��̉��ł́A�V�t�g�����̌p�����}�ꂸ�ސE������A�Ԑڍ��ʂƂ��đi�������Ăɂ��A�J���R�����́A2023�l�̒j���^�]��͑S�����K���ł����i100���j���A21�l�̏����^�]��̂����K���ł��Ȃ��̂͌����݂̂ł���A��֏������[���ł��鏗����95.2���ł���A�j���^�]��̐��Ə����^�]��̐����l�����A����ɏ����̕����j�����P�l�e�ƂȂ��Ĉ玙����\�����������Ƃ��l������ƁA���̌���͏����ɂƂ��Ė������ɂ����v���ł���Ƃ����B�T�i�@���J���R�������v�������ʓI���ۂ��f�����Ƃ��Ă��̔��f���x�������B�i�����h���E�A���_�[�E�O���E���h�����@�T�i�@�@1998�N�j |
�E��̓I�Ȕ��f�͘J���ٔ������s���B �E���Y�[�u�̑ΏۂƂȂ�S�Ă̎҂ɂ����āA�s���v����O���[�v�ɂ��������̐��̔䗦���A�s���v���Ȃ��O���[�v�Ȃ����͑S�Ώێ҂ɂ����邻�̐��̔䗦���u�͂邩�Ɂv�����ꍇ�B |
||
| �g�p�҂̍R�� | �E���Y�s�ׂ��A�E���Ɗ֘A��������A���Ɩ���̕K�v���ɍ��v���Ă��邱�ƁB�i�@703��(k)(1)�j �E�g�p�҂����Ƃɂ���ĊJ�����ꂽ�\�̓e�X�g�Ɉˋ������ꍇ�́A��@�ȍ��ʂ��Ӑ}�������̂łȂ�����A�Ԑڍ��ʂƂ͂Ȃ�Ȃ��i�@703���ih�j�j�B�������A�̗p�⏸�i�̑I�l���@�Ƃ��ėp������e�X�g�ɂ��ẮA�e�X�g�̌��ʂƓ��Y�E���̐��s�\�͂Ƃ̊Ԃɍ��x�̊֘A�������݂��邱�Ƃ́u�Ó�������v�����߂���B �i�Q�l�ٔ���j �E�S���x�@���̗̑̓��x���������邽�߂ɉۂ����̗p�����̏����̂P�ɂ��āA�j������҂�69�������i�����̂ɑ��A��������҂�12�������e�X�g�ɍ��i���Ȃ��������߁A�e�X�g�ɗ������������i�����B�퍐���͂��̏����������ɑ��鍷�ʓI���ʂ�L���邱�Ƃ�F�߂Ă������߁A���̏������Ɩ���̕K�v���̗L�������_�ƂȂ����B�ٔ����́A���ʓI���ʂł���Ƃ̎咣�ɔ��_���邽�߂ɂ́A���ʓI�ȑ���_�͐E���̗ǍD�Ȑ��s�ɕK�v�ȍŒ���̎��i�𑪒肷����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��A���Y�������A���̂悤�Ȃ��̂ł������Ɣ퍐���������������ۂ����������邽�߁A�n�قɍ����߂����ƂƂ����B�i���j���O�����@�A�M��R����ٔ����@1999�N�j |
�E���Y�K��A����͊��s���A�����ȖړI�ɂ���ċq�ϓI�ɐ���������A���̖ړI�����������i���K���K�v�ł���ꍇ�B�i�w�߂Q���Q�j �E��̓I�Ȕ��f�͊e���̍ٔ������s���ׂ��B �i�Q�l�ٔ���j �E���i�v���ł���U�N�̓K���ώ@���ԁi�Α��N���j�̌v�Z�ɂ��A�T�J�����Ԃ��ʏ�̂S���̂R�ȏ�̘J���҂��P�C�����ȉ��̎҂�0.5�Ƃ��Čv�Z���鋦��K��Ɋ�Â��A�T20���ԘJ���̑�w�����E���̏��i������F�߂Ȃ��������Ƃ́A�E����K��ɂ��K���ώ@���ԁi�Α��N���j���Q�{�Ƃ����p�[�g�^�C���J���҂ɂ����鏗���̔䗦��90�����邱�Ƃ���Ԑڍ��ʂł���Ƃ��đi�������Ăɂ��A���B�i�@�ٔ����́A�p�[�g�j���̔䗦���p�[�g�����̔䗦���ꡂ��ɏ��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�g�p�҂��q�ϓI�ȗv���ɂ���ċ����̋K��𐳓����ł��Ȃ�����A���119���Ɉᔽ�����Ƃ����A������]�����A���ƂȂ��Ă���J������̋K�肪���Ɩ��W�ȋq�ϓI�ɐ������ł���v���Ɋ�Â����̂ł��邩�ۂ���������ɏƂ炵�Č��߂�͍̂����ٔ����ł���Ƃ����B�i�j���c�����i�Ɓj�@���B�i�@�ٔ����@1991�N�j �E�ŃA�h�o�C�U�[���i�����̖Ə�������Ζ����Ԃ��A�t���^�C���ƃp�[�g�^�C���ƂňقȂ邱�ƂƂ���̂́A�u���[�����̐Ŏ������ŋΖ�����119���̃p�[�g�^�C���̂���110���������ł��邱�Ƃ���A�Ԑڍ��ʂƂ��đi�������Ăɂ��A���B�i�@�ٔ����́A�{���͎��ۂɏ����ɐ����ʓI���ʂ�^���Ă���A�����Ƃ��Ďw�߈ᔽ�ł���A���Ɋ�Â����ʂƊW�̂Ȃ��v���ɂ���Đ������ł���ꍇ�Ɍ���A���_���قȂ�B������ɏƂ炵�āA���ɊW�Ȃ��K�p�������̂̎��ۂɒj���ɔ�����ɉe����^����@���̋K�肪�A���Ɋ�Â������Ȃ鍷�ʂƂ��W�̂Ȃ��q�ϓI�ȗ��R�ɂ�萳���������̂��ǂ��������肷��̂́A������]���������@�����߂���i�@������L���Ă��鍑���ٔ����ł���Ƃ����B�i�R�[�f�B���O�����i�Ɓj���B�i�@�ٔ����@1997�N�j |
�E���Y�K��A����͊��s�����ʂɊW�Ȃ������ł��邱�ƁB�i�@�P���P(2)(b)�j �E��̓I�Ȕ��f�͌ٗp�i�J���j�R�������s���B �E�v����������ۂ��g�p�҂̕K�v���ƁA���̗v��������̍��ʓI���ʂ̊Ԃ̃o�����X�Ŕ��f����Ƃ����l���łȂ���邽�߁A���ۂɎ������N�����ĐR���������f�������܂Ō��ʂ�\�����邱�Ƃ�����ȌX��������B �i�Q�l�ٔ���j �E�p�[�g�̐揇�ʉ��ق͊��������ɂƂ��ẮA�q��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A�t���^�C���œ����関���̏�����j���Ɣ�ׂĕs���ł��邽�߁A�������͊����ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ������ʂƂ��đi�������Ăɂ��A�J���R�����͔�r�̂��߂̓K�ȃv�[���́A�t���^�C���Ζ��Ɨ����ł��Ȃ��悤�ȏ������q�̂���ƒ�ł���Ƃ��A�t���^�C���v���́A��ʓI�ɏ������͊��������ł�����[���ł���҂̊����͑������x���Ȃ��͎̂����̗��Ƃ��錴���̎咣���p�������B�ٗp��i�R�������c���q�����������̏������������̏����̕����玙�ӔC��S���Ă���Ƃ͉���ł��Ȃ��Ƃ����B����ɁA�J���R���������Ƃ�����I��葱�����Ԑڍ��ʌ��ʂ�L����ꍇ�ł����Ă��A����̏ɂ����Ă͐��������ꂤ��Ɣ��f���錠��������A�R�X�g������̏�ŕt���I�ȗ��_�����邽�߁A�p�[�g�^�C����揇�ʂʼn��ق��邱�Ƃɐ�����������Ɣ��f���邱�Ƃ���������Ƃ����B�i�L�b�h�����@�ٗp��i�R�����@1985�N�j �E�q�����Y�������A�p�[�g�^�C���Ζ���\���o���Ƃ���A�W���u�V�F�A������҂�������Ȃ����Ɠ����狑�ۂ��ꂽ���ߊԐڍ��ʂƂ��đi�������Ăɂ��A�J���R�������g�p�ґ����p�[�g�^�C���Ζ��ł���悤�ɗl�X�Ȏ�i���u�������Ɠ����l�����A��������F�߁A�����̑i�����p�����A�ٗp��i�R�����������F�߂��B�i�u���������@�ٗp��i�R�����@1997�N�j �E�n���S�^�]��Ƃ��ē����V���O���}�U�[�̌�������Ђ��V���ɓ�����������Ζ��̉��ł̓V�t�g�����̌p�����}�ꂸ�ސE������Ԑڍ��ʂƂ��đi�������Ăɂ��A�J���R�����͏؋��Ɋ�Â��������Ȃ��Ƃ̌��_�Ɏ��錠����L����A��Ђ̌o��ߖ�A�������̕K�v���ƂP�l�e�Ŏq���̐��b�����Ă���҂ւ̍��ʓI���ʂ��l�����ׂ��Ƃ���A��Ђ͕X��}�邱�Ƃ͂ł����͂��Ƃ��Đ������͔F�߂��Ȃ��Ƃ��Čٗp��i�R�����͘J���R�����̔��f���x���A�T�i�@�������F�߂��B�i�����h���E�A���_�[�E�O���E���h�����@�T�i�@�@1998�N�j |
�E�قȂ�戵�������ʂɂ��Ȃ������I�ȗ��R�Ɋ�Â����̂ł��邱�Ɩ��͐��ʂ����s�����E���̕s���̑O����Ȃ����̂ł��邱�ƁB�i�@611��a��P���j |
| �@ | �A�����J | EU | �C�M���X | �t�����X | �h�C�c | �X�E�F�[�f�� | ���{ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �|�W�e�B�u�E �A�N�V���� �iP�EA�j�� ���e���� �����K�� �� |
���@�߂ɖ����̋K��Ȃ��B ���ٔ����ɂ��Ă͌������@706��(g)�Ɋ�Â��A���ʂɑ���~�ϑ[�u�Ƃ��ăA�t�@�[�}�e�B�u�E�A�N�V�����iA�EA�j�𖽂��邱�Ƃ��ł���B ���A�M�ō��ق͌������@��V�҂̎�|�ɍ��v���邱�Ƃ�F�߁A���͈͓̔��ŋ��e�B ��EEOC�K�C�h���C���ɋK�� �EA�EA�̎��{���K�ȏꍇ�Ƃ��āA(1)�s���ȉe���������Ă��銵�s�̑��݁A(2)�ߋ��̍��ʓI���s�̉e���̑����A(3)�ߋ��̔r���������Ƃ���o�p�\�ȑw�̕s�� �EA�EA�̎菇�Ƃ��āA(1)�����I�Ȏ��ȕ��͂ƁA(2)����Ɋ�Â������I�ȍ����Ɋ�Â��v��̉��ł̍����I�ȍs���A(3)����ɂ��ꂪ����������Ă��邱�Ƃ��K�v�B |
�����B�����̐ݗ���� �@�E�Ɛ����̊��s�ɂ�����j���̊��S�ȋϓ��ҋ����m�ۂ��邽�߂ɁA�ϓ��ҋ������́A���������A��菭���̐��ɑ�����҂��E�Ɗ�����Nj����邱�Ƃ�e�Ղɂ��A�܂��͐E�ƌo���ɂ�����s���v��h�~���������͕ۏႷ�邽�߂ɁA���ʂ̕X�����[�u���ێ����܂��͍̗p���邱�Ƃ�W������̂ł͂Ȃ��B�i���141��4���j�i1997�N�j ���j���ϓ��ҋ��w�� �@���������́A���ۂɒj���̊��S�ȋϓ��ҋ���ړI�Ƃ��āA���B�����̐ݗ����141��(4)�̈Ӗ�����͈͓��̎{����ێ��܂��͍̗p���邱�Ƃ��ł���B�i�w��2��8���j�i2002�N�j ��2002�N�����O��2��4�� �u�E�E�����̋@��ɉe�����y�ڂ������̕s������r�����邱�Ƃɂ��A�j���̋@��ϓ��𑣐i����[�u��W������̂ł͂Ȃ��E�E�v |
�������ʋ֎~�@ �@����I�ɁA�ߋ�12�����ԂɁA�O���[�g�E�u���e���ɂ����ē��Y���̎҂ł��̎d�����s���҂��S�����Ȃ�����r�I�����̏ꍇ�ɂ����āA�����܂��͒j���ɂ̂݁A(1)���̐E���ɓK������̂ɖ𗧂P���{�݂̗��p��F�߂邱�ƁA(2)�E�����s���@��̗��p�����シ�邱�Ɠ��̏ꍇ�̂݁A���e�����B�i�@47�𑼁j |
���J���@�T �E�@123��-1,123��-2�̋K��́A�j���̋@��A�Ƃ��ɏ����̋@��ɉe�����鎖����̕s���������ĕ������m�����邽�߂ɁA�����ɑ��Ă݂̂Ƃ���b��I�[�u�̎��{��W������̂ł͂Ȃ��B�i�@123��-3�j�i1983�N�j |
�����ԕ����ΏۂƂ��������̋K��Ȃ��B �����������ΏۂƂ������̂Ƃ��āA�u�A�M�s���@�y�јA�M�ٔ����ɂ����鏗���̌ٗp���i���тɉƒ�ƐE�Ƃ̗����̂��߂̖@���v�i1994�N�j �@�����͂��̖@���̊�Ɋ�Â��A�K���A�\�͂���ѐ��̎d���ɂ��Ă̗D�ʂ��l�����āA�ٗp�𑣐i�����B�X�̕���Ōٗp����Ă��鏗�����j�����������ł������A���߂�ꂽ��ڕW�ɑ����ď����̊��������߂邱�Ƃ��ٗp���i�̖ړI�ł���B�j�����тɏ����̂��߂̉ƒ�ƐE�Ƃ̗��������l�ɑ��i���ׂ����̂ł���B�i�@2���j |
���@��ϓ��@ �EP.A�ɑ��Ă͍��ʋ֎~��K�p���Ȃ��i�@15��2���j�i2000�N�j �E�g�p�҂͂��̊����̘g���ŁA�E�Ɛ����ɂ�����j�������𑣐i���邽�߂ɁA�ڕW�Ɍ������w�͂��s���i�@3���j�i1991�N�j �E�g�p�҂͋���P���E�\�͊J�����̑��K�ȑ[�u�ɂ��A�e�E��ɂ�����j���䂨��шقȂ�E��Ԃ̒j������ϓ��ɂ���悤�w�͂���i�@7���j�i1991�N�j �E�g�p�҂́A���l�ɍۂ��Ēj�����҂�����ł���悤�ɓw�͂�����̂Ƃ���B�i�@8���j(1991�N�j �E�g�p�҂́A�������̐E�킠�邢�͂���J�e�S���[�̘J���҂̒��Ő��̕肪����ꍇ�ɂ́A���Ȃ����̉���҂��̗p����悤�w�͂���B�i�@9���j(1991�N�j |
���j���ٗp�@��ϓ��@ �@���Ǝ傪�A�ٗp�̕���ɂ�����j���̋ϓ��ȋ@��y�ёҋ��̊m�ۂ̎x��ƂȂ��Ă��鎖������P���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ď����J���҂Ɋւ��čs���[�u���u���邱�Ƃ�W���Ȃ��B�i9���j�i1997�N�j |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �|�W�e�B�u�E�A�N�V�����iP�EA�j�{�� | �y���{�̊����z ���哝�̖���11246,11375�� �@50�l�ȏ�̘J���҂��ٗp����N�T���h���ȏ�̐��{�_���������鎖�Ǝ哙�́A�}�C�m���e�B�⏗���̊��p�Ɋւ��铝�v�I���͂ƌv��̎��{���@�荞�v��N�쐬���A���s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ��OFCCP�K���i41CFR60-1.7�j �@��L�̎��Ǝ�ɉ����A100�l�ȏ�̘J���҂��ٗp���鎖�Ǝ�́A���N�A�J���͍\���̕���OFCCP�y��EEOC�ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ��EEOC�ɂ����āA�x�X�g�E�v���N�e�B�X�̕��̍쐬�i1998�N��Q�Łj�E���y ���O���X�V�[�����O�ψ���i1995�N�j ��717���Ɋ�Â��A�M�������̃A�t�@�[�}�e�B�u�E�A�N�V�������{�B �y���Ԓc�̂̊����z ���J�^���X�g�̊��� �@�����284�̂m�o�n�i1962�N�ݗ��j�B�������r�W�l�X�E�E�Ƃɂ����Ĕ\�͂��ő���ɔ����ł���悤�ɂ��邱�ƁA��Ƃ������̍˔\���\���Ɋ��p�ł���悤�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�o�ŁA���������A�������x�A��Ɩ�����ւ̉����A�J�^���X�g�܂̎��^�Ȃǂ̊��������{�B |
����P���A�N�V�����v���O�����i1981�N-1985�N�j �i���ƃ��x���̖@�I�g�g�݂ɂ����P�EA��W�J������j�̒�N�j �������̂��߂�P�EA���i�Ɋւ��闝������̍̑��i1984�N�j �i���������Ȃ�����ł�P�EA�̎��{���j ��P�EA�̃K�C�h�̍���i1988�N�j ����Q���A�N�V�����v���O�����i1986�N-1990�N�j �iP�EA��ʂ��������I�ȓ��ʑ[�u�̗̍p���w�E�B���Ɍ������͔͂ƂȂ�ׂ����ƁA�����̈ӎv����ւ̎Q�摣�i����B�j ����R���A�N�V�����v���O�����i1991�N-1995�N�j �i�u�����̂��߂̋ϓ��v���u�j���̂��߂̋ϓ��v�ƈʒu�Â��𐳂��B�j ����S���A�N�V�����v���O�����i1996�N-2000�N�j ����T���A�N�V�����v���O�����i2001�N-2005�N�j |
�y���{�̊����z �p���t���b�g�����쐬���āA���m�B �y���Ԓc�̂̊����z ���I�|�`���j�e�B�E�i�E�̊��� �@�����������₷������n�������ƎQ���^�̃L�����y�[���������琶�܂ꂽ�A�����c�́A���Ԋ�ƁA��������@�ւɂ��\������Ă�������364�̒c�́B1991�N�Ɋ������J�n���ꂽ�B���T�[�`�A�x���`�}�[�L���O�A�\���A�x�X�g�v���N�e�B�X�̔F���Ɖ���� �̏����s���Ă���B |
�y���{�̊����z ���u�J���@�T�v �E���N��ƈψ���ւ́u�j���̌ٗp�y�ѐE�ƌP���̈�ʏ����̔�r�v���̒�o���`���Â��i�@432��-3-1�j�i1983�N�j �E��Ɠ��̋`���I�N�����ɂ����āA�j���Ԃ̐E�Ə�̕��������Ƃ肠���邱�Ƃɂ��ċ`���Â��B�i�@132��-27�j(2001�N�j �E���Ɋ�Â��A�J�g�̋��c�ɂ��j���E�ƕ����v������肷�邱�Ƃ��z�肳��Ă���i�@123��-4�j�͔͓I�Ȓj���E�ƕ����v�擙�ɑ��č����������s���B �i�K��123��-6�j(1983�N�j �E�J������ɂ����āA�R�N�ɂP�x�j���Ԃ̐E�Ə�̕������m�ۂ��邽�߂̑[�u�y�ъm�F���ꂽ�s���������P���邽�߂̐����[�u�ɂ��Č�����|�K��B �i�@132��-12�j(2001�N�j �y���Ԓc�̂̊����z ���J���g���̊��� �@�E�Ƃɂ����镽���K�C�h�̔z�z�B |
�y���{�̊����z ���u�A�M�s���@�y�јA�M�ٔ����ɂ����鏗���̌ٗp���i���тɉƒ�ƐE�Ƃ̗����̂��߂̖@���v �E�R�N���ɏ����ٗp���i�v��̍쐬�E���\�B�i�@4���j �E���v�����̕A��o(�@5���j �E�����̌ٗp���i�`���i�@7���j �E�������ψ��̔C���i�@15���j ���d�t�̕��j�ɉ����A�Ό��������ӎ��̉��v�Ɍ��������m�B �y���Ԓc�̂̊����z ���d�|�N�I���e�B�[�E�}�l�W�����g�̊��� �@1996�N�ɋ���ݗ��B��Ƃ̎���I�ȋ@��ϓ�����𑣐i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�@��ϓ�����ɂ����ėD�ꂽ��ƂɁu�g�[�^���E�C�[�E�N�I���e�B�v�̏̍���^����^���B�L�͊�ƁA�J�g�c�́A�Ȓ����Q�����Ĕ����B |
�y���{�̊����z ���u�@��ϓ��@�v �E10�l�ȏ�̔�p�҂��ٗp����g�p�҂́A���N�����Ɋւ���E��v��i�J�������A�̗p���Ɋւ���[�u�̊T�v����������A���̂������Y�N�ɊJ�n���邩�A���N�Ɏ��s���邱�Ƃ��v�悵�Ă���[�u�������B�܂��A��������Ɋւ���s���v��̑����I�ȕ��܂ށB�j�����肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�@13���P���A2���A4���j �E���N�̌v��ɂ����ẮA�@13���P���ɂ��v�悵���[�u�̎��{�ɂ��ĕ�����̂Ƃ���B�i�@13��3���j �E�@��ϓ��I���u�Y�}���́A�v�������BP.A���̋K����g�p�҂����炷��悤�w���E�ē������s���i�@30-33���j�ᔽ�����g�p�҂ɑ��ẮA�@��ϓ��ψ���������ۂ����Ƃ��ł���B�i35���j �y���Ԓc�̂̊����z ���o�c�Ғc�́u�X�E�F�[�f���Y�Ɓv����т���ɉ�������Y�ƕʑg�D�̊��� �@�@��ϓ��v��쐬�A���{�ɂ��ẴZ�~�i�[���s���Ȃǂ̌[���B ���J���g���̊��� �@�ٗp�傪�@��ϓ��v����쐬����ۂɘJ���g�������͂Ȃǂ��s���Ċ֗^�B |
�y���{�̊����z ��P�EA���u���悤�Ƃ��鎖�Ǝ�ɑ��鑊�k�����B �������̊������i���c��̊J�ÁB ���p���t���b�g���ɂ����m�E�[���B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���L���ׂ��{�� | ���Ƒ��E��Ëx�ɖ@�i1993�N�j�i�玙�x�ɁA���x�ɁA�a�C�x�ɁA�o�Y�x�ɂ̕t�^�̋`���Â��B�j | �����B�Y�ƌo�c�ҘA���iUNICE�j�A���B������Ƒ̃Z���^�[�iCEEP�j�A���B�J�A�iETUC�j�ɂ��������ꂽ�玙�x�ƂɊւ���g�g�ݘJ������Ɋւ���1996�N�U���R���̎w��96/34/EC�i�����e�̐e�Ƃ��Ă̐ӔC�ƐE�ƓI�ӔC�̗�����e�Ղɂ��邽�߂ɍl�Ă��ꂽ�Œ�v�����K��B�j | �������̏o�Y�x�ɐ��x�i�玙�x�ɐ��x�͂Ȃ��j�B2003�N���畃�e�̏o�Y�x�ɂ��V���Ɏ{�s�B | ���J���@�T�ɂ����āA�玙�x�ƁA�Ō�x�ɁA�t�Y�e�x�ɁA�I�����x�Ƃ��F�߂��Ă���B�x�ɒ��̒����̕�U�Ƃ��āA�Љ�ۏ�@�T�ɂ��A�蓖���x����߂��Ă���B | ���玙�x�Ɛ��x�̉��v�i2000�N�j�i�q����3�ɂȂ�܂ł́u�e���ԁv�̎擾�A�Q�ɂȂ�܂ł̈玙�蓖�̎A�e���Ԓ��̃p�[�g�^�C���J���̋��e�A�e���Ԓ��̉��ق̋֎~���B�j | ���玙�x�Ɂi�e�ی��j�i�q�������W�ɂȂ邩��b�w�Z��P�w�N���I������܂łɁA�����ۏ�t���ō��v480���Ԏ擾�\�B����ɁA�Վ��e�ی�������B�j ���J�����Ԃ̒Z�k�i�W�Έȉ��A��b�w�N��P�w�N�I���܂ł̎q��������ꍇ�́A�J�����Ԃ��S���̂R�ɒZ�k�B�j |
���玙�E���x�Ɩ@�i�玙�x�ƁE���x�Ɠ��̋`���Â��B�j�i��x�F1991�N�A��x�F1995�N�j �������x����ɌW��ٗp���P�̂��߂̎��Ǝ�ɑ��鏕�����̎x���B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ٗp�ґ����ɐ�߂鏗���̊��� | 47.2�� �o�T��(1) |
�@ | 49.4�� �o�T��(1) |
46.0�� �o�T��(1) |
44.9�� �o�T��(1) |
50.3�� �o�T��(1) |
40.5�� �o�T��(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �����̊Ǘ��E���� |
�o�T��(3) |
�@ |
�o�T��(4) |
�o�T��(6) |
�o�T��(5) |
�o�T��(7) |
�o�T��(8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �j�������i��)�i�j����100�j | 76.0�� �o�T��(9) |
�@ | 80.6�� �o�T��(5) |
79.8�� �o�T��(5) |
74.2�� �o�T��(5) |
82�� �o�T��(10) |
66.5�� �o�T��(11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���ϋΑ��N�� | �j���F7.9�N �����F6.8�N �o�T��(12) |
�@ | �j���F8.9�N �����F6.7�N �o�T��(12) |
�j���F11.0�N �����F10.3�N �o�T��(12) |
�j���F10.6�N �����F8.5�N �o�T��(12) |
�j���F10.7�N �����F10.4�N �o�T��(12) |
�j���F13.5�N �����F8.8�N �o�T��(11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���i�o�T�j |
| (1)ILO Year book of Labour Statistics 2001�^(2)�J���͒����i����14�N�j�^(3)Employment ��Earnings 2002�^(4)Woman��Equality Unit(2001)�AOffice for National Statistics(2003)�^(5)ILO Year book of Labour Statistics 2000�^(6)ILO Year book of Labour Statistics 2000�A�t�����X�L���X�g���J���ғ���CFTC�i1999�j�^(7)ILO Year book of Labour Statistics 2000�AWomen and Men in Sweden(1998)�^(8)2000�N���������^(9)Employment ��Earnings 2001�^(10)Wage/salary statistics,Statistics Sweden(1998)�^(11)�����\����{���v�����i����14�N�j�^(12)OECD�@Employment Outlook ,1997 |
| �i���j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | �@�����_�ȉ���Q�ʎl�̌ܓ� |
| �@�i���P�j | |||
| �@ |
|
�@���炩�̖@�I�`�����ۂ���Ă��� | |
| �@ |
|
�@�A�M���{�ƈ��K�͈ȏ�̌_�����������Ɠ��ɑ��`���t�����Ă��� | |
| �@�i���Q�j | �Ǘ��E�̒�`�͍��ɂ��قȂ� |
�@�i�����o���j�e���̃f�[�^�̔N�́i�@�j���Ɏ����Ƃ���
|
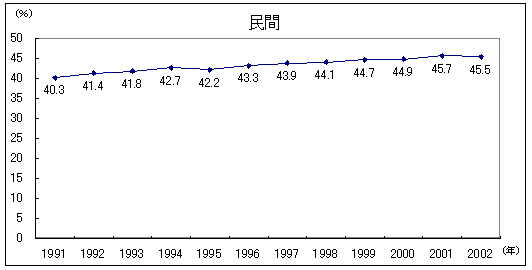
�i�����o���j�@ U.S. Bureau of Labor Statistics "Employment & Earnings" |
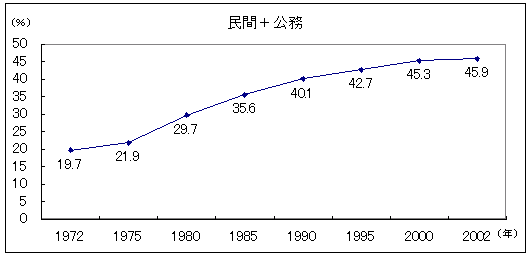
�i�����o���j�@ U.S. Bureau of Labor Statistics "Employment & Earnings" |
| �i���ԁj | �E�哝�̖��߂̐��ւ̓K�p(1967�N�`�j �E�x�X�g�E�v���N�e�B�X�̕��y�@�E�J�^���X�g���̊��� |
| �i�����j | �����Ȍٗp�@��̒𑣐i����[�u���u���邱�Ƃ��`���Â� �i�A�M���{�i1972�N�`�j�j |
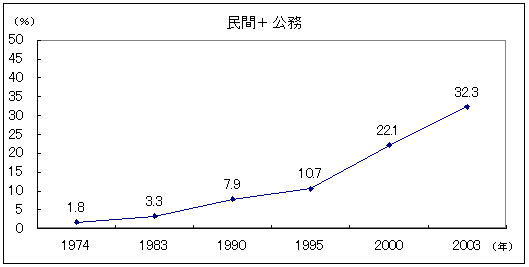
| |
�i�����o���j |
�@�P�X�V�S�`�Q�O�O�O�@Institute of Management and Remuneration Economics �@�Q�O�O�R�@Office for National Statistics |
| �@�E | �p���t���b�g����p�����{�����i |
| �@�E | �I�|�`���j�e�B�E�i�E���̊��� |
| ||||||||||||||||||||||||
�i�����o���j |
�@1996�N�x�u�O���X�E�V�[�����O�����̂��߂̍��ی𗬎��Ɓv �@�i2001�N���l�F�I�|�`���j�e�B�E�i�E�Q�O�O�Q�x���`�E�}�[�L���O�E���|�[�g�j |
|||||||||||||||||||||||
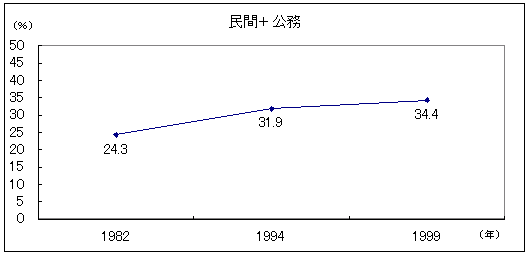
| |
�i�����o���j�@�t�����X�L���X�g���J���ғ���CFTC |
|
| �@�E | ���Ԃɂ��āA�ٗp�̍쐬�A��o���̋`���t���y�э��ɂ������x���̋K�� �i1983�N�`�j |
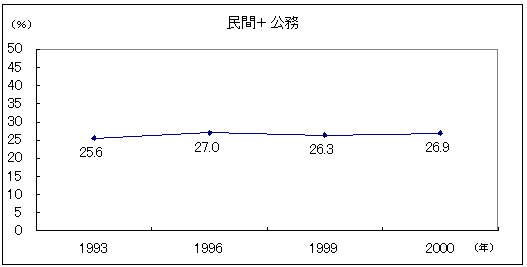
| |
�i�����o���j�@ILO Yearbook 2001 |
|
| �@�E | ���Ԃɂ��ẮA�d�t�̕��j�ɉ������m |
| �@�E | �����i�A�M�s���@�֓��j�ɂ��Ă͏����ٗp���i�v��̍쐬�E���\�̋`�����i1994�N�`�j |
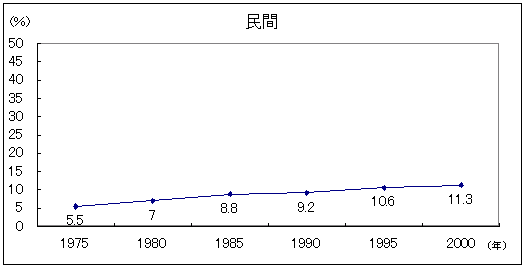
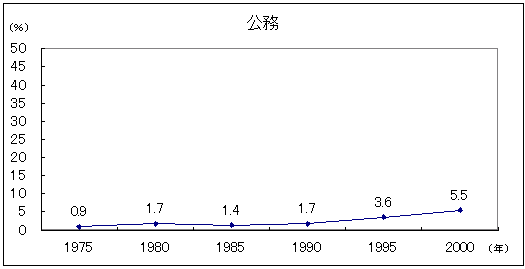
| |
�i�����o���j�@�����ȁ@���������i���o����W�v���ʁj |
|
| �i���ԁj | �E�@�Ɋ�Â��|�W�e�B�u�E�A�N�V�������u���悤�Ƃ��鎖�Ǝ�ւ̑��k�E���� �i1999�N�`�j �E�����̊������i���c��̊J�Ái2001�N�`�j |
| �i�����j | �E�u�������ƌ������̗̍p�E�o�p�g��Ɋւ���w�j�v�̍��� �i�e�{�Ȃ��Ƃɏ����E�� �Ώۂ̌��C�̎��{�A���i�҂ɐ�߂鏗�������� �ւ���ڕW�̐ݒ蓙�j�i2001�N�`�j |