また、試算結果(P.20参照)からは、保険料水準固定方式の下で給付水準を調整する場合、仮に少子化が進行しても公的年金に期待される役割を果たしていける給付水準を維持するためには、前回改正で前提としていた20%の水準は必要である。
| ※ | 20%より低い保険料水準や現行の保険料水準を極力上回らない水準とすべきとする意見もあるが、20%を下回る水準の最終保険料率とした場合には、給付水準の引下げ等給付の在り方の制度的な前提を変える必要がある。例えば、仮に15%を上限とした場合、基礎年金の全額税方式化等の手法をとらない限り、直ちに、現在受給している年金も含め、およそ3割程度一挙に名目年金額を削減しなければならないことになる。 |
| ※ | 国民年金保険料を法定する場合、平成16年改正時の価格表示で将来の保険料額を法定し、その額を毎年度の一人当たり賃金上昇率(可処分所得割合控除前のもの)により、将来の時点の価値に換算することとなる。 |
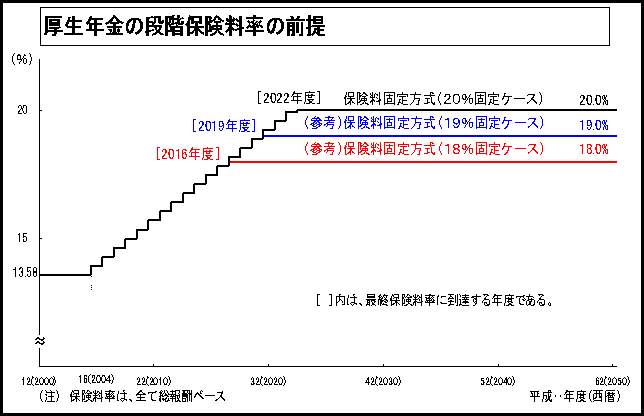
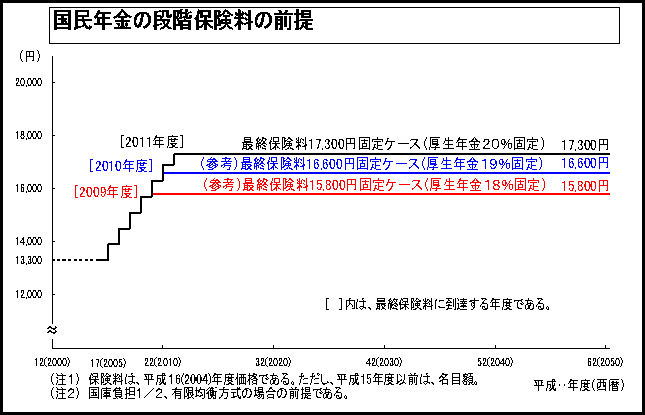
| 単年度当たりの保険料(率)の引上げ幅; | 厚生年金0.354%(総報酬ベース)、 国民年金600円(平成16年度価格) |
| ※ | 厚生年金の保険料負担は、平均的な被用者(月収36.7万円(ボーナスは年2回合計で月収3.6ヶ月分))の場合、毎年、保険料率の引上げにより、月650円程度(ボーナス1回につき1,150円程度)保険料負担(被保険者分)が増加する。 |
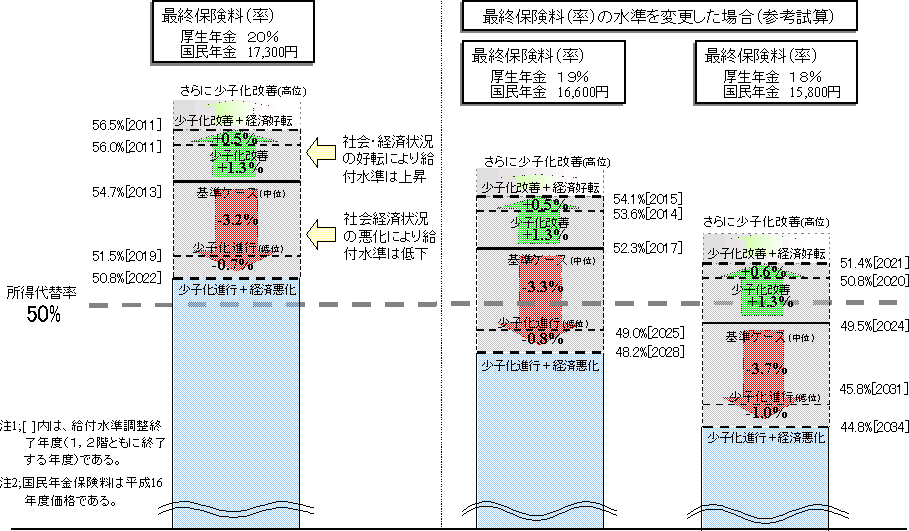
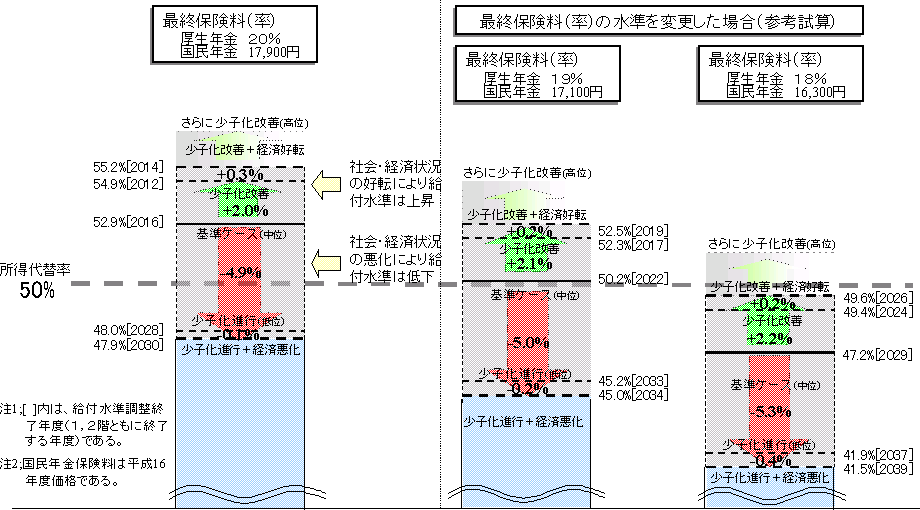
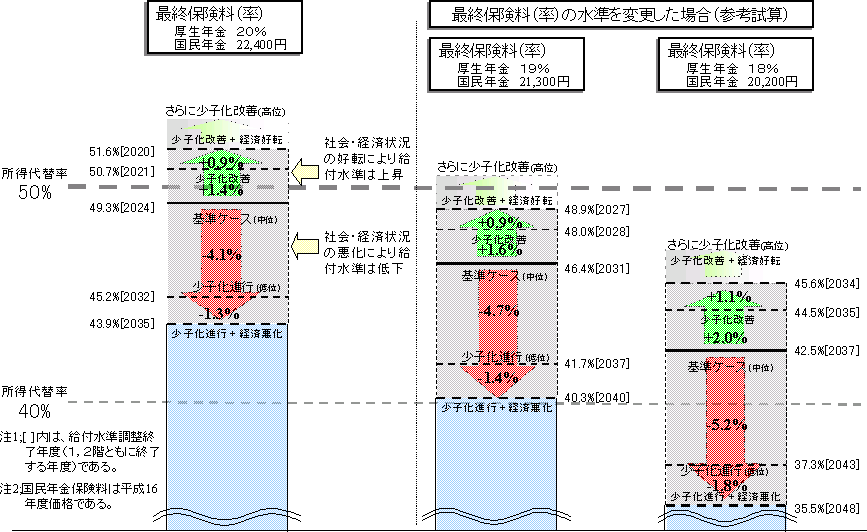
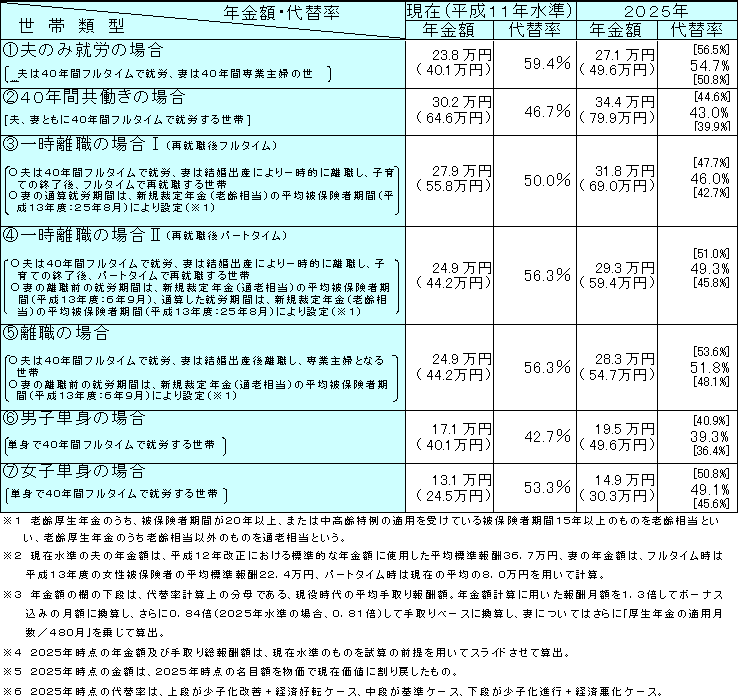
![世帯(夫婦)所得別の年金月額及び所得代替率−[最終保険料率20%、基準ケース]−のグラフ](images/h1117-1g.gif)