別添1
酸素欠乏症等災害発生状況の分析
| 1 | 酸素欠乏症等災害の発生状況の推移(昭和61年〜平成17年)(表1、図1〜3) 休業4日以上の酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下「酸素欠乏症等」という。)による災害の発生件数は年間20件前後、被災者数は30名前後で推移していたが、最近3年間をみると発生件数は年間10件前後、被災者数は10名前後となっている。しかしながら、例年、酸素欠乏症等による被災者の約3割以上が死亡する結果となっており、被災者に占める死亡者の割合が高い傾向にあることに変化はみられない。 平成17年においては、酸素欠乏症等による災害の発生件数が10件、休業4日以上の被災者数が12名と、発生件数、被災者数ともに平成15年に次いで低い数となっている。しかしながら、被災者に占める死亡者の割合は33%と、依然として高い状況であった。 また、これを酸素欠乏症と硫化水素中毒の別でみると、酸素欠乏症の被災者数は9名(平成16年11名)、うち4名(平成16年2名)が死亡であり、硫化水素中毒の被災者数は3名(平成16年4名)、うち死亡者数は0名(平成16年3名)であり、被災者に占める死亡者の割合は、酸素欠乏症によるものが高い結果となっている。 |
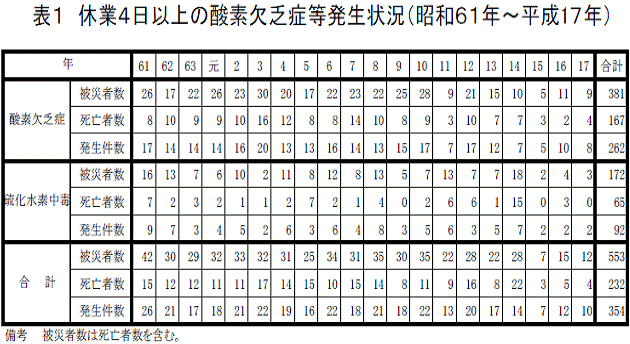
| 図1 | 酸素欠乏症等発生状況(昭和61年〜平成17年) |
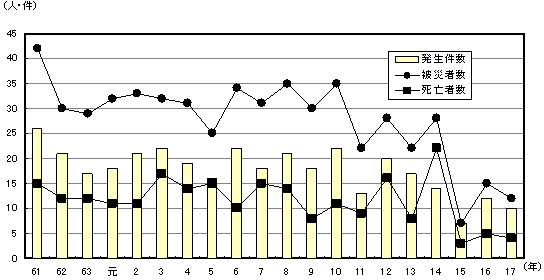
| 図2 | 酸素欠乏症発生状況(昭和61年〜平成17年) |
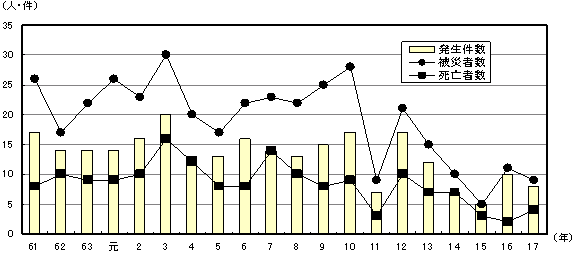
| 図3 | 硫化水素中毒発生状況(昭和61年〜平成17年) |
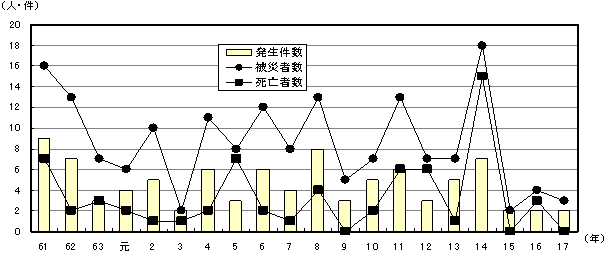
| 2 | 酸素欠乏症等災害の発生原因(平成8年〜17年)(図4) 最近10年間における酸素欠乏症等による災害発生件数154件について、その発生原因について見ると、酸素濃度等の測定の未実施が原因の一つとなっているものが98件(64%)、換気の未実施が86件(56%)、空気呼吸器等の未使用が68件(44%)と他の原因に比べて突出している。酸素濃度等の測定、十分な換気の実施及び空気呼吸器等の使用は、酸素欠乏症等を防止するためには欠かすことのできないものであり、これら基本的な事項が行われなかったことが、災害の発生につながっている。 |
| 図4 | 酸素欠乏症等の発生原因別発生件数(平成8年〜17年) |
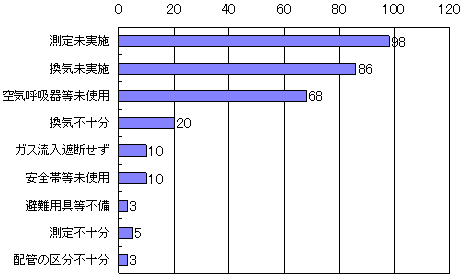
| 3 | 酸素欠乏症等災害の管理面での問題点(平成8年〜17年)(図5) 最近10年間における酸素欠乏症等による災害発生件数154件について、管理面の問題点について見ると、作業主任者の未選任が原因の一つとなっているものが65件(42%)、特別教育の未実施が66件(43%)、作業標準の不徹底が57件(37%)、安全衛生教育の不十分が55件(36%)となっており、事業者における酸素欠乏症等による災害に対する管理面での対策が十分でなかった事案が多くあった。 |
| 図5 | 酸素欠乏症等の管理面での問題点別発生件数(平成8年〜17年) |
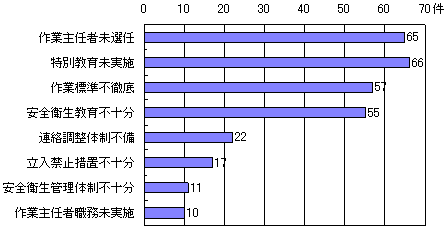
| 4 | 酸素欠乏症等災害の発生形態別発生状況(平成8年〜17年)(図6、7) |
| (1) | 最近10年間における酸素欠乏症による災害発生件数111件について、酸素欠乏空気の発生形態について見ると、無酸素気体に置換されたことによるものが65件(59%)と最も多く、次いで、有機物の腐敗、微生物の呼吸等による空気中酸素の消費によるものが21件(19%)、タンクその他の素材の酸化によるものが13件(12%)となっている。 また、無酸素気体による置換について、その無酸素気体の種類別に見ると、窒素が24件(37%)と最も多く、次いで、二酸化炭素が12件(18%)、プロパンが9件(14%)となっている。 |
| (2) | 最近10年間における硫化水素中毒による発生件数43件について、硫化水素の発生形態を見ると、し尿、汚水等からの発生が35件(81%)と大半を占めている。 |
| 図6 | 発生形態別発生件数(平成8年〜17年) |
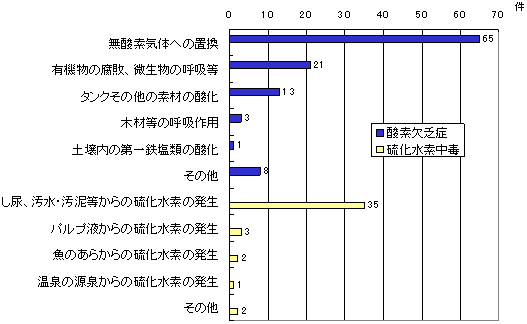
| 図7 | 置換した無酸素気体の種類別発生件数(平成8年〜17年) |
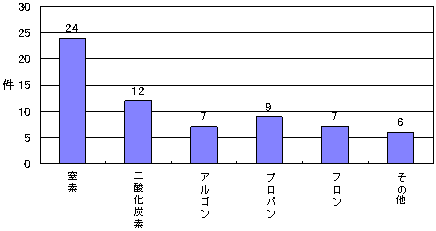
| 5 | 酸素欠乏症等災害の月別災害発生件数(平成8年〜17年)(図8) 最近10年間における酸素欠乏症等による月別災害発生件数について見ると、硫化水素中毒は夏季に発生が多くなる傾向がみられる。腐敗の進行しやすい夏期については、特に硫化水素中毒に対する注意を要するものである。 |
| 図8 | 月別発生件数(平成8年〜17年) |
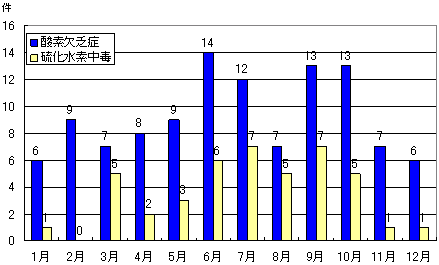
| 6 | 酸素欠乏症等の業種別発生状況(平成8年〜17年)(図9〜10) 最近10年間における酸素欠乏症等による災害発生件数154件について、業種別について見ると、製造業で55件(36%)と最も多く、次いで建設業で41件(27%)、清掃業で25件(16%)となっている。製造業では、食料品製造業及び化学工業における酸素欠乏症等による災害発生件数が、全体の約半数を占めており、また、建設業では酸素欠乏症による災害が、清掃業では硫化水素中毒による災害が多く発生していることがわかる。 主要業種における酸素欠乏症等による災害を発生場所別に見ると、マンホール、ピット、タンク等狭く、通風が不十分な場所で多く発生している。 |
| 図9 | 酸素欠乏症等の業種別発生件数(平成8年〜17年) |
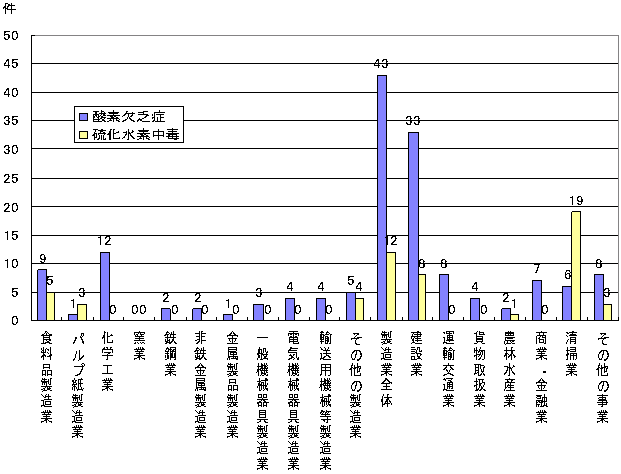
| 図10 | 主要業種の発生場所別発生件数(平成8年〜17年) |
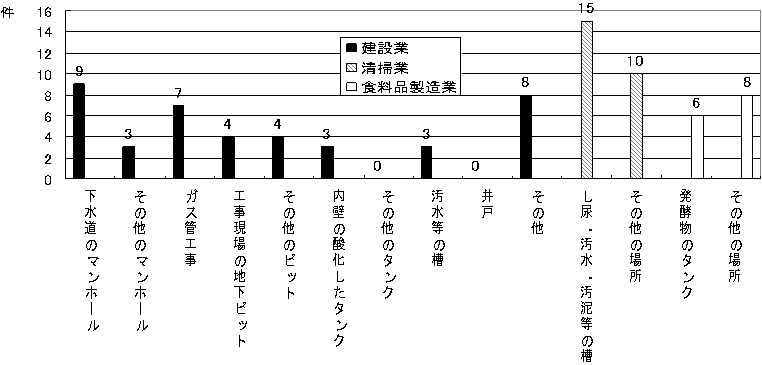
| 7 | まとめ 酸素欠乏症等は致死率が高く非常に危険であるが、酸素濃度等の測定、十分な換気の実施、空気呼吸器等の使用等の措置を適正に実施すれば発生を防ぐことができるものである。 これらの措置を実施するためには、酸素欠乏危険場所の事前確認が重要であり、マンホール、ピット、タンク等の内部が酸素欠乏危険場所に該当するか、作業中に酸素欠乏空気及び硫化水素の発生・漏洩・流入等のおそれはないかを事前確認し、法令に定める措置を実施するために必要な機材をあらかじめ調えるよう、事業主に対して指導する必要がある。 また、災害発生状況に鑑みて、事業者に対して下記事項を特に指導する必要がある。 |
| (1) | 法令で定める資格を有する者の中から作業主任者を選任し、その者に酸素濃度等の測定、空気呼吸器等の使用状況の監視等の職務を行わせるとともに、作業者に対して法令で定める教育を確実に行っておくこと。 |
| (2) | 測定者の安全を確保するための措置を講じたうえで、酸素濃度、硫化水素濃度の測定を実施すること。 |
| (3) | 作業を行う場所の空気中の酸素濃度を18%以上、硫化水素濃度を10ppm以下に保つよう継続的な換気を実施すること。酸素欠乏空気、硫化水素の漏洩・流入がないようにすること。 |
| (4) | 換気できないとき又は換気しても酸素濃度が18%以上、硫化水素濃度が10ppm以下にできないときは、空気呼吸器等を着用させること。空気呼吸器等は、同時に作業する作業者の人数と同数以上を備えておくこと。 |
| (5) | 万一、酸素欠乏災害が発生した場合は、二次災害を防止するため、救出に向かわせる者に必ず空気呼吸器等を着用させること。また、当該空気呼吸器等のほか、はしご、繊維ロープ等の避難用具をあらかじめ準備しておくこと。 |