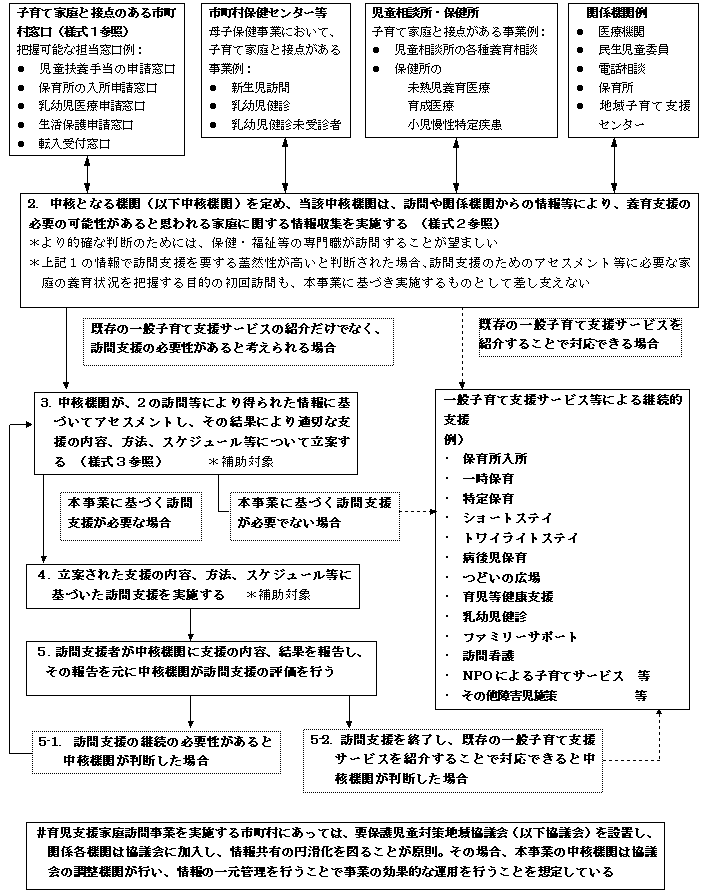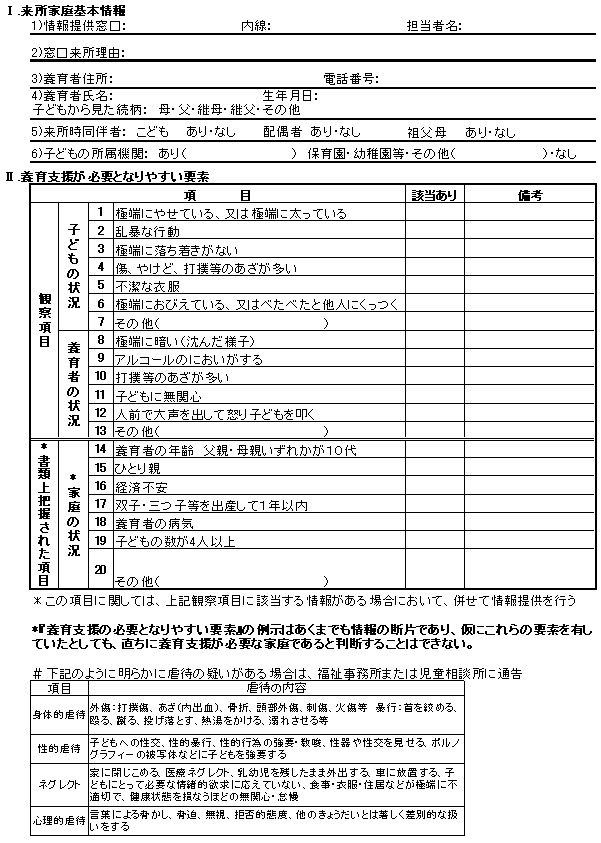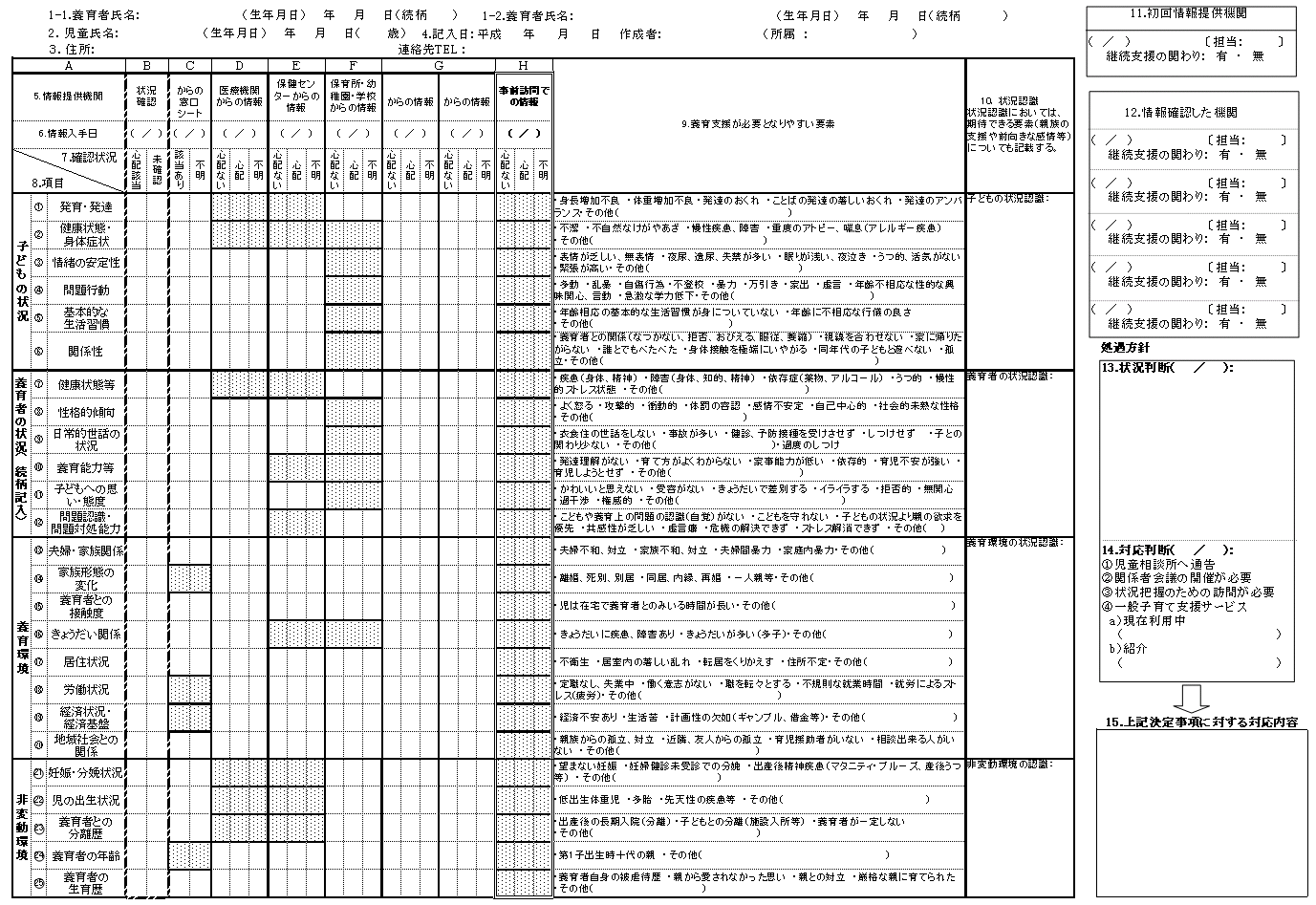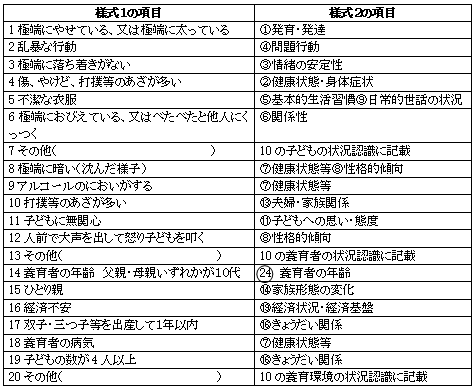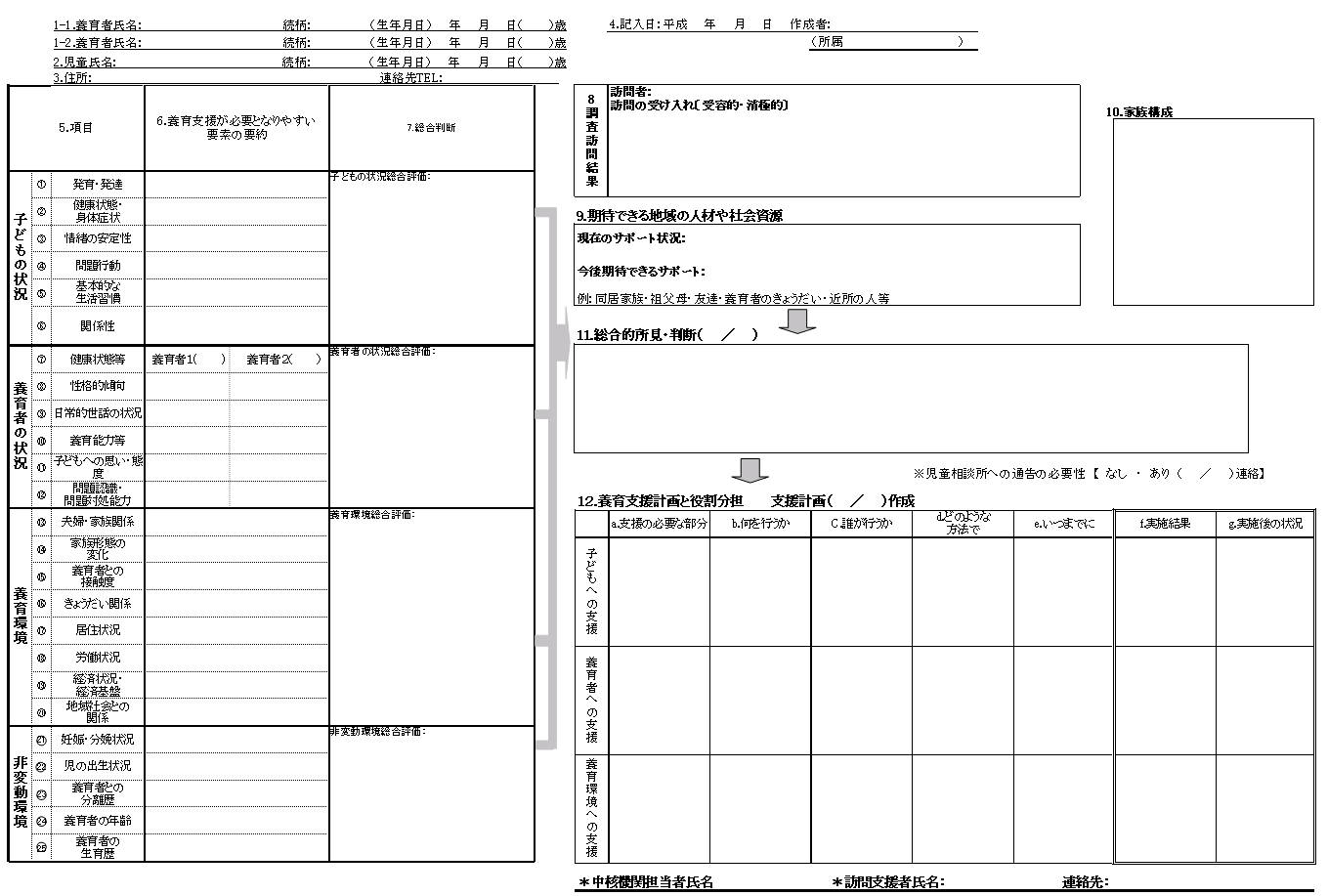育児支援家庭訪問事業の概要等
| 1) |
目的
近年、核家族化、都市化の進展等、乳幼児等を取り巻く環境は大きく変化する中で、家庭や地域における養育機能は低下してきている。
本事業は、本来子どもの養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に過重な負担がかかる前の段階において、訪問による支援を実施することにより、当該家庭において安定した子どもの養育が可能となること等を目的としている。
|
| 2) |
実施主体
本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。ただし、市町村が、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。
|
| 3) |
支援対象
本事業の支援対象は、市町村が「養育支援が必要となりやすい要素の例」を参考に、本事業の支援の効果が期待できると市町村長が判断した次に掲げるような、一般の子育てサービスを利用することが困難な家庭を対象としている。
| (1) |
養育者が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭、又は虐待のおそれや、そのリスクを抱える家庭。なお、妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭も対象とする。 |
| (2) |
ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭や、子どもが児童養護施設等を退所又は里親委託終了後の家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭 |
| (3) |
子どもの心身の発達が正常範囲にはなく、又は出生の状況等からの心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来、精神・運動・発達面等において障害を招来するおそれのある子どものいる家庭 |
|
| 4) |
支援の内容
| (1) |
家庭内での育児に関する具体的な援助
| ア. |
産褥期での母子に対する育児指導・簡単な家事等の援助 |
| イ. |
未熟児や多胎児等に対する育児指導・栄養指導 |
| ウ. |
養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・支援 |
| エ. |
若年の保護者に対する育児相談・支援 |
| オ. |
子どもが児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援 |
|
| (2) |
発達相談・訓練指導
家庭における指導が必要な場合には、理学療法士等を派遣して、家庭の状況等に即した発達相談・訓練指導を行う。 |
|
| 5) |
支援を行う者
4)の(1)養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に対する育児、家事の援助については、子育てOB(経験者)、ヘルパー等が実施する。
4)の(2)産後うつ病、育てにくい子ども等複雑な問題を背景に抱えている家庭に対する具体的な育児支援に関する技術指導については、保健師、助産師、保育士、児童指導員等が実施する。
| ※ |
多様な支援を行う観点から、(1)、(2)ともに実施することが望ましいが、地域の事情により、いずれか一方の実施でも差し支えない。 |
|
| 6) |
支援の方法
次の内容にて市町村長が養育支援が必要と認めた家庭に対し訪問支援を行う。
| (1) |
「養育支援が必要となりやすい要素の例」に該当する家庭等について、必要に応じて関係機関からの情報収集等を行い、家庭の養育状況を把握する。 |
| (2) |
(1)の結果、支援の必要性があると思われる家庭に対し、その支援内容を明確に
した上で養育支援を行う。 |
| ※ |
「養育支援が必要となりやすい要素の例」に照らし、様々な機関からの情報で訪問支援を要する蓋然性が高いと判断される場合は、訪問支援のためのアセスメントに必要な家庭の養育状況を把握する目的の初回訪問も、本事業に基づき実施するものとして差し支えないものとする。 |
|
| 1) |
運営の手順
育児支援家庭訪問事業の運営手順はおおよそ以下のとおりであるが、あくまでも例示であり、地域の実情に合わせて、アセスメント項目や支援計画の記載事項を変更し、市町村独自の様式を用いて差し支えない。
| (1) |
子育て家庭と接点のある市町村窓口や保健センター、産科等の医療機関等において、以下のような養育支援が必要となりやすい状況をあらゆる機会を通じて把握し、中核となる機関(以下「中核機関」という。)に情報提供する(様式1参照)。
| ・ |
妊娠期において将来の子育てに不安を抱いている |
| ・ |
生後間もない時期 |
| ・ |
転居直後 |
| ・ |
健診や予防接種を受けるていない |
| ・ |
家族に障害や疾病のある人がいる |
| ・ |
経済的な困窮 |
| ・ |
一人親家庭等 |
|
|
| (2) |
中核機関は、「支援内容を判断するための一定の指標(様式2参照)」を参考に、関係機関から提供された情報を集約し、養育支援の必要の可能性があると思われる家庭の状況を判断し、以下の4つの対応を決定する。
| ア. |
情報を集約した結果、虐待が疑われ、緊急な支援が必要な場合は、児童相談所へ通告 |
| イ. |
状況判断に必要な情報は集積されているが、具体的な支援の方向性等の状況判断が困難な場合は、関係者会議を招集 |
| ウ. |
訪問や関係機関からの情報等から本事業に基づく訪問支援を決定 |
| エ. |
当面訪問による支援は必要ないと思われる場合、一般子育て支援等の通所型育児支援サービスを紹介 |
|
| (3) |
(2)のウに該当する場合は、得られた情報を踏まえ、適切な支援の内容、方法、スケジュール等について立案する(様式3参照)。
|
| (4) |
中核機関が各訪問支援者に支援を依頼し、依頼を受けた訪問支援者は、立案された支援の内容、方法、スケジュール等に基づき、明確な役割分担のもとに訪問による支援を実施する。
|
| (5) |
訪問支援者は、支援を終了した後、中核機関に訪問支援の内容、結果を報告し、その報告を基に中核機関が訪問支援の評価を行う。
|
| (6) |
本人の意向、状況を踏まえ、訪問支援の継続の必要性があると中核機関が判断した場合は、改めて適切な支援の内容、方法、スケジュール等について中核機関が立案する。また、本事業に基づく訪問支援の継続の必要性がない場合であっても、適宜通所型の子育てサービス等一般の子育て支援サービスを紹介し、継続的な支援体制を確保する。 |
|
| 2) |
運営に関わる人の役割分担
| (1) |
情報提供機関
子育て家庭と接点のある市町村窓口や保健センター、産科等の医療機関等、は、積極的に「養育支援が必要となりやすい要素の例」に該当する家庭についての情報を把握し、中核機関へ情報提供を行う。
|
| (2) |
中核機関
中核機関は、情報提供機関からの連絡を受けて、「養育支援が必要となりやすい要素の例」に照らし、専門職として内容を確認し、さらに状況確認が必要な項目について各関係機関に問い合わせや状況把握のための訪問を行う等して情報を集約する。日頃から情報提供機関との連携を密にし、支援を必要とする対象者を適切に把握するよう努める。
次に、得られた情報をアセスメントし、適切な支援の内容、訪問支援者、方法、スケジュール等について立案する。
立案した計画を訪問支援者に伝え、訪問支援を依頼する。適宜、訪問支援者から訪問の結果等について報告を受け、訪問支援者への支援体制を構築する。
|
| (3) |
訪問支援者
立案された支援の内容、方法、スケジュール等に基づいて依頼を受け、訪問支援を実施し、中核機関に支援の内容や結果を報告する。 |
|
| 3) |
運営に用いる記録様式
本事業に関わる各機関がアセスメント等に用いる様式については、下記を例示するが、地域の実情に合わせて、アセスメント項目や支援計画の記載事項を変更し、市町村独自の様式を用いて差し支えない。
| (1)様式1: |
子育て家庭に接点のある行政窓口において意識してほしい養育支援が必要となりやすい要素の例(行政窓口等の情報提供者が用いる様式) |
| (2)様式2: |
支援の必要性を判断するための一定の指標(例示)・情報集約のための様式(中核機関が用いる様式) |
| (3)様式3: |
支援の必要性を判断するための一定の指標(例示)に基づく、適切な支援の内容、方法、スケジュール等についての立案・実施状況に関する様式(中核機関および訪問支援者が用いる様式) |
|
| 4) |
訪問支援者に対する研修、マニュアル等
本事業の実施にあたっては、訪問支援者が適切かつ効果的な支援を行うことができるよう、中核機関等が訪問支援者に対する研修及び訪問支援者向けのマニュアル作成を行うことが想定される。その際に参考となる資料を以下に示す。(各資料について示している具体的な該当箇所は、あくまで例示である)
なお、以下の資料は厚生労働省ホームページに掲載している(*については掲載予定)。
| (1) |
育児支援家庭訪問事業について
「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成17年12月26日雇児発第1226003号各市町村長・特別区区長あて厚生労働省雇用均等・児童家
庭局長通知)*
1の(2)育児支援家庭訪問事業
|
| (2) |
児童虐待の概況について
平成16年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)*
平成16年度児童相談所における児童虐待相談処理件数等*
|
| (3) |
支援の基本的事項について
| (1) |
子ども虐待対応の手引き(平成17年3月25日改定版)*
「子ども虐待対応の手引きの改正について」(平成17年3月25日雇児発第0325001号各都道府県・指定都市、児童福祉主管部(局)長・母子保健主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)
第1章子ども虐待の援助に関する基本事項
第2章発生予防
第8章援助(在宅指導) |
| (2) |
平成14年度こども未来財団児童環境づくり等総合研究事業「児童虐待等における家庭支援マニュアルの開発についての研究」(主任研究者 桐野由美子)*
第3章 子ども家庭支援員の基礎知識 |
|
| (4) |
市町村及び関係機関の役割について
| (1) |
市町村児童家庭相談援助指針
「市町村児童家庭相談援助指針について」(平成17年2月14日雇児発第0214002号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
第5章 関係機関との連携 |
|
| (5) |
関係法令等
| (1) |
児童虐待の防止等に関する法律(平成12年5月24日法律第82号) |
| (2) |
児童福祉法(昭和22年12月12日法律第64号) |
| (3) |
子ども・子育て応援プラン(平成16年12月24日少子化社会対策会議決定)
| (4) |
特に支援を必要とする子どもと家庭に対する支援の推進 |
|
|
|
| 1. |
一定の指標を用いて、養育支援の必要の可能性があると思われる家庭を様々な関係機関を通じて把握する |
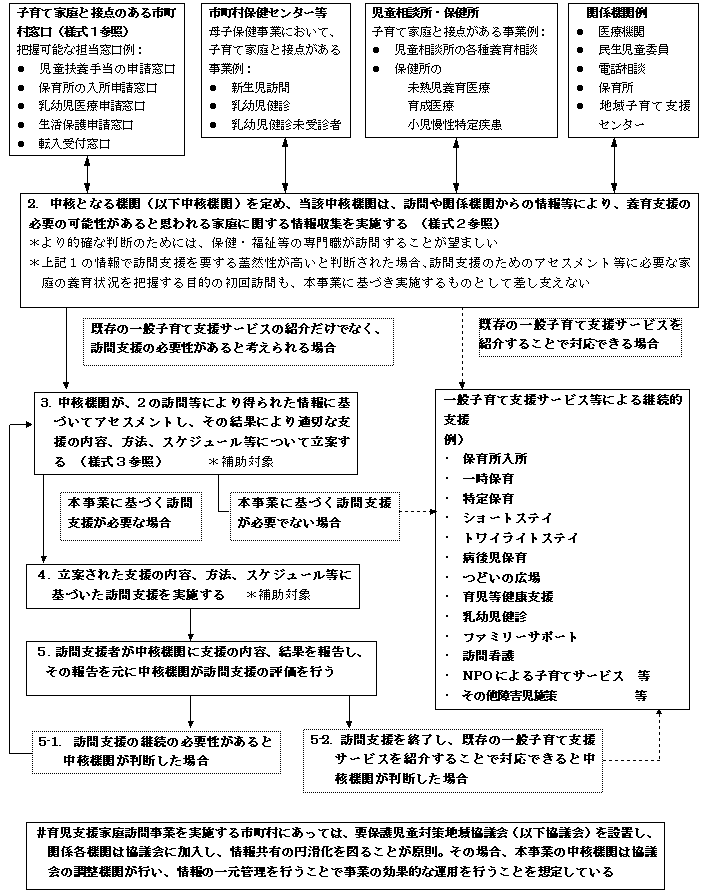
様式1
[NO. ] 子育て家庭に接点のある行政窓口において意識してほしい
養育支援が必要となりやすい要素の例
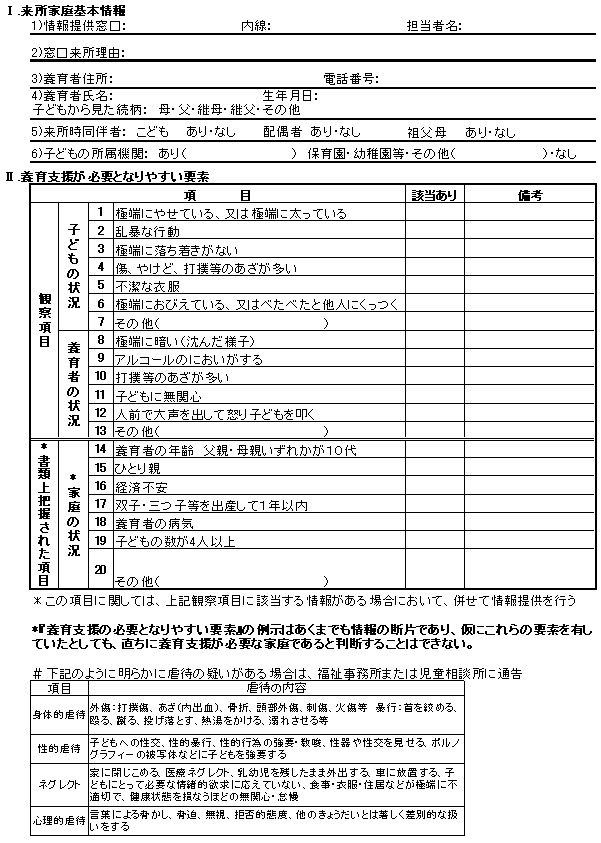
|
『養育支援が必要となりやすい要素を持つ家庭』に接点のある行政窓口における対応
(様式1の説明)
【趣旨】
虐待の発生を予防していくためには、養育支援が必要となりやすい状況(例:ひとり親家庭・若年親・未熟児・転居間もない時期等)がありながらも、社会的な支援が得られにくい状況にある家庭を早期に確実に把握し、子どもの立場に立って必要な支援を必要な時に行うことが重要です。こうした社会的支援が得られにくい家庭に積極的に支援を行っていくために、今回育児支援家庭訪問事業として、支援が必要な家庭に訪問型育児支援サービスを創設いたしました。支援が必要な家庭を的確に把握していくためには、まずは支援が必要な状況をあらゆる機会を通じて把握し、その情報を集約する中核機関を設け、確実な支援体制を構築することが必要です。(別添
フロー図1参照)
今回、厚生労働省が行った虐待死亡事例125事例の分析によると、児童扶養手当担当窓口・生活保護担当窓口等、今まで直接的には虐待対策と関わりの薄いと考えられていた相談窓口とも接点があったことが明らかになりました。そこで、このような窓口において養育支援が必要となりやすい状況を把握し、中核機関に積極的に情報提供を行い、支援につなげていくことは、虐待の効果的予防対策として重要な意味を持っていると考えています。
よってこのたび、従来直接的には虐待対策とは関わりの薄かった窓口においても、養育支援が必要となりやすい状況に気づいていくための要素を参考までに例示しました。
(別添
様式1参照)
これらの例示を参考に、養育支援が必要な要素を持つ家庭に出会った場合は積極的に、育児支援家庭訪問事業の中核機関である
への情報提供をお願いいたします。
なお、中核機関に情報提供を行うにあたっては、育児の負担感を軽減するためにこの事業をご利用いただくものであり、ご本人の了解を得ることが基本となります。子育て家族と接触のある関係機関においては、積極的に利用してもらうよう養育者に十分な理解と説明をお願いします。
また、窓口においての情報の収集はあくまでも養育状況を把握するための断片的な情報であり、窓口で把握した情報のみで養育支援の必要性を判断することは不可能であることから、養育支援の対応判断は、育児支援家庭訪問事業の中核機関が情報集約後、支援関係者と協議して行うこととなっております。
さらに、情報を受けての対応結果は、支援関係者の協議後、貴担当窓口等支援関係者へ対応結果を連絡し、養育支援へむけての共通認識を深めていきたいと考えておりますので、積極的なご協力をお願いいたします。
【対応の手引き】
子育て家庭に接点のある行政窓口において意識してほしい養育支援が必要となりやすい要素の例を様式1のように参考例示いたしました。
項目の中の観察項目(I-5)・II-1〜13)については、窓口の来所時に観察された内容について、該当する項目を○印を記入。また、その他気になる点についてII-7・13・20に詳細を記載。
さらに書類上把握された項目(項目I-2)〜4)、II-14〜20)については、上記の観察項目において該当する項目がある場合、養育支援に必要な情報として各種手当てや、制度の申請手続きの際に添付される書類等から把握された情報について、該当する項目に○または、必要事項を記載します。
なおII.養育支援が必要となりやすい要素の各項目の解説は以下のようになっておりますので、これらを参考に各項目への該当の有無を判断され、原則として一つでも該当がある場合について、育児支援家庭訪問事業の中核機関への情報提供をお願いいたします。
| ◆ |
観察項目
| ◎ |
子どもの状況
主に養育者との関係性に不自然さを感じたり、活気がなかったり、基本的な人間関係がとれる年齢になっても、極端におびえたり・乱暴な言動をする等コミュニュケーションがうまくとれない状況等、気になる子どもの様子の詳細について以下の例示項目を参考に該当する項目に○をつけてください。さらに、以下の例示項目に該当しない気になる点がある場合はその他の欄に記載して情報提供をお願いします。なお、窓口への来所者が養育者のみで子どもの同伴が無い場合等、子どもの状況が直接観察できなかった場合は、斜線を入れてください。 |
| 1. |
極端にやせている、又は極端に太っている
食事を十分にとれてないこと等の理由により、不自然にやせている状況が疑われる場合。又は、適切な食事が与えられず、スナック菓子等のカロリーの高いものばかりを摂取して結果的にブヨブヨ太りして極端に太っている場合等親の体型や養育態度と併せて状況を確認
|
| 2. |
乱暴な行動
壁や机を叩いたり、暴言を吐いたり、制止にさらに反応してパニックになっている状態。また、これらの行動に対する養育者の反応が、全く無関心な場合や、暴力で制する等の親の問題行動についても併せて状況を確認
|
| 3. |
極端に落ち着きがない
社会性が育ち、他人との基本的コミュニュケーションがとれる年齢になっている(おおむね4歳以上)にも関わらず、話しかけても全く応答せずただひたすら走り回る上、人や物にぶつかっても全く気にせずコミュニュケーションが全くとれない状態。また、これらの行動に対する養育者の反応が、全く無関心な場合や、暴力で制する等の親の問題行動についても併せて状況を確認
|
| 4. |
傷、やけど、打撲等のあざが多い
ひっかき傷や、青あざ、青あざの時間が経過して黄ばんだようなあざ、たばこを押しつけた後のような小さい円形状のやけどの後等の不自然な傷が目に付く場合。
|
| 5. |
不潔な衣服
破れた衣服や、何日も洗濯していないため異臭が漂うような衣服を着ている状況。また、真冬で本人が寒そうにしているのにも関わらず半袖を着ている等、養育者が子どもの世話を怠っていることが一目で判断できるような身なりをしている状況。
|
| 6. |
極端におびえているまたは、べたべたと他人にくっつく
養育者の一挙一動にびくびくして、必要以上に養育者の顔色をうかがっている様子。または、何気なく養育者が手をあげたりする行動に対しても、体を硬くしたり、手で頭をかばう等の防御行動にでる状況。また、子どもが乳幼児であれば、あやしても全く反応をしなかったり、逆に極端に職員に甘えてくる状況。
|
| 7. |
その他 |
| ◎ |
養育者の状況
窓口来所時の養育者の態度や、言動から、心配な養育者に出会った場合、その気になる様子の詳細について以下の例示項目を参考に該当する項目に○をつけて下さい。よって、以下の項目に該当しない気になる点がある場合はその他の欄に記載して情報提供をお願いいいたします。 |
| 8. |
極端に暗い(沈んだ様子)
相談している間、下をむいたままで目が合わず思いつめている様子。また、ぼーっとした感じで問いに対しても反応せず、自分の殻に閉じこもっている様子。さらに、極端に緊張して表情が硬かったり、ちょっとした物音にも過敏に反応する等、心が不安定な様子がうかがわれるような状況。
|
| 9. |
アルコールのにおいがする
昼間からお酒を飲む等、アルコール依存傾向が疑われる状況。また、相談している内容が要領を得ず何度も同じことを繰り返しからむように話してくる等、酔っぱらってるような様子がうかがわれる状況。 |
| 10. |
打撲等のあざが多い
DV(夫婦間暴力)や、夫婦不和等が原因で養育者自身も配偶者から虐待を受けている恐れがある場合。
|
| 11. |
子どもに無関心
子どもの傍若無人な振る舞いや、反対に甘えてくる状況に対しても無視をし続け、基本的に子どもに関わる姿勢が全く読みとれない状況。
|
| 12. |
人前で大声を出して怒り子どもを叩く
しつけと称して子どもに暴力をふるい、養育者自身はそれが当たり前だと思っていて問題意識を持っていない場合。
|
| 13. |
その他 |
|
| ◆ |
書類上把握された項目
| ◎ |
家庭の状況
上記、来所時に観察された心配な状況の背景となる家庭の情報を、窓口申請書類上可能な範囲で、上記観察項目と併せて情報提供をお願いします。これらの情報は、養育支援が必要となりやすい状況に対し支援を行う際、その困難要因に適応した支援の方向性を検討する上で重要な情報となります。よって、なぜこのような情報が支援の方向性を検討する上で重要なのかを以下に説明します。 |
| 14. |
養育者の年齢 父親・母親いずれかが10代
養育者が若年の場合は、養育者としての責任や自覚に乏しくなる可能性があり、未熟な存在であることが比較的多いことから、育児に関する知識・生活力等、家族生活を送っていく上で基本的な力が欠けることが予測される。
|
| 15. |
ひとり親
養育者が一人の場合は、養育に過重な負担がかかりやすい状況が想定される。その結果、肉体的にも精神的にも疲労が重なり、特段の支援が必要となる状況。
|
| 16. |
経済不安
経済的に不安定な場合は、養育者も過重なストレスにさらされる場合が多く、その結果家庭生活も不安定になることが予測される。また、食事も十分にできないほどに生活に困っている場合や、借金に追われて住居を転々としている場合等は不適切な養育に陥りやすく、まずは生活の安定をはかるための支援が必要である。
|
| 17. |
双子・三つ子等を出産して1年以内
生後間もない時期は、母親も肉体的・精神的に過重な負担がかかりやすい上、双子・三つ子等の出産は未熟児の場合が多く、子どもだけの長期入院となる場合に、長期分離が母子の愛着形成をはかっていく上で障害になってくる場合も考えられる。さらに、同じ月例の乳児を複数世話することは、肉体的にも精神的にも疲労が重なりやすく特段の支援が必要となる場合が多い。
|
| 18. |
親の病気
養育に支障をきたすような養育者の疾患、例えば精神疾患や、疲れやすい慢性の病気等がある場合、子どもの養育そのものがストレスになる場合もあり、親の病状等により養育支援が必要な場合がある。
|
| 19. |
子どもの数が4人以上
子どもがたくさんいると一人一人に対して、十分世話が行き届きにくい状況が予想され、さらに経済的な問題が重なる等、生活が不安定になりやすい状況
|
| 20. |
その他 |
|
様式2
[NO. ] 支援の必要性を判断するための一定の指標(例示)・情報集約のための様式
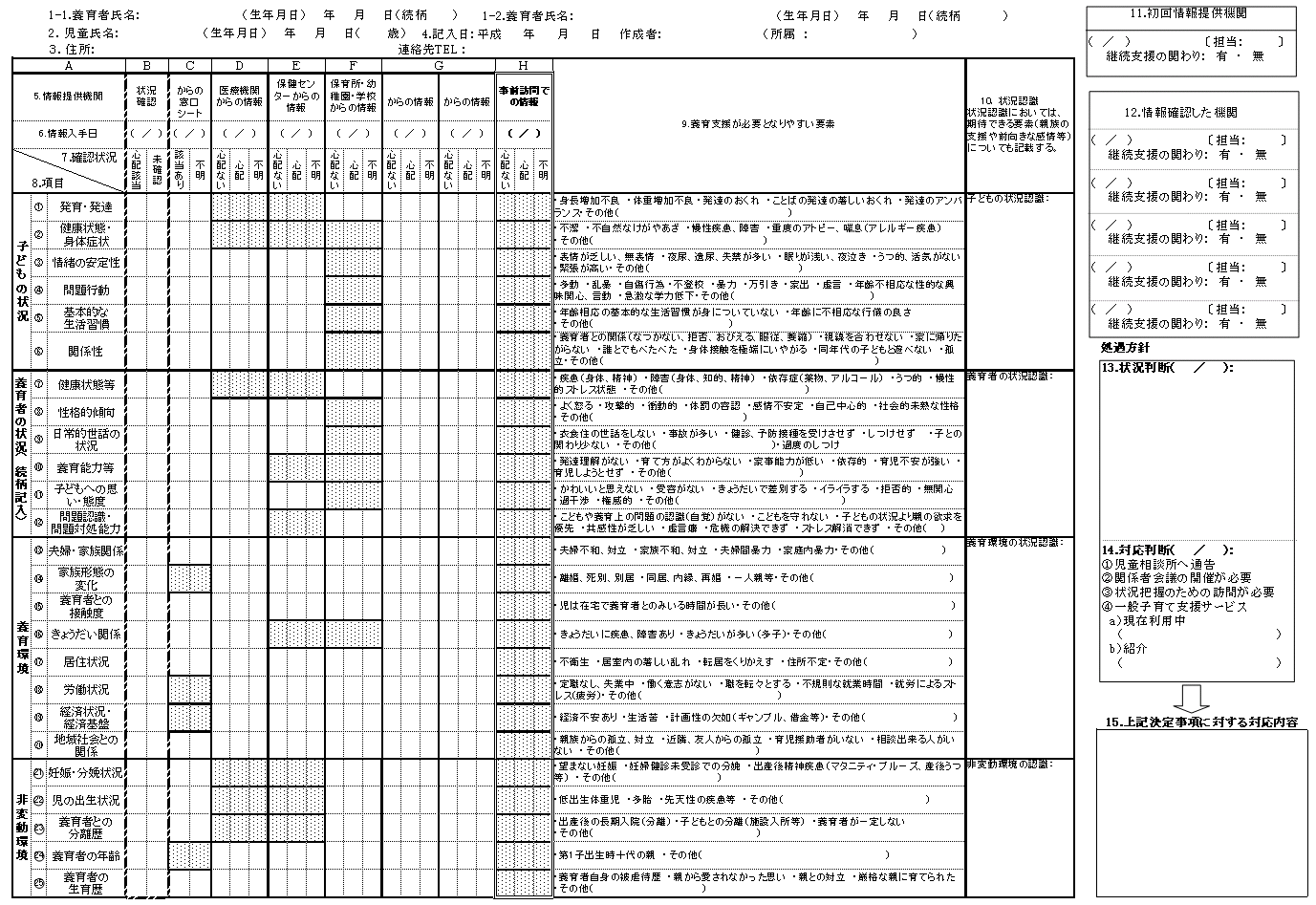
| 様式2: |
支援の必要性を判断するための一定の指標(例示)・情報集約のための様式(中核機関が用いる様式)における記載要領 |
| 1. |
養育者氏名: (生年月日) 年 月 日( 歳)
支援の対象となる、養育者の氏名・生年月日、また続柄は支援対象となる子どもからみた続柄を記載。また、支援の対象となる養育者が夫婦等複数の場合は両者について記載 |
| 2. |
児童氏名: (生年月日) 年 月 日( 歳)
支援の対象となる、子どもの氏名・生年月日を記載。続柄については支援対象となる養育者からみた続柄を記載。(例:長男(実子)・次女(養子)等)。また当該家庭にいる児童数が複数の場合は、様式3の家族構成の欄に記載した上、それぞれの子どもの状況が認識できるように様式2の記載方法を工夫 |
| 3. |
住所・連絡先電話
支援の対象となる家庭の現在の居住地・連絡先について記載 |
| 4. |
記入日:平成 年 月 日 作成者: (所属 : )
原則として情報集約者の氏名・所属を記載。なお、記入日についてはBの状況確認を行った日付を記載する。 |
| C. |
からの窓口シートの列
様式1を用いた、情報提供を受けた場合の情報について、情報提供機関名を下線の部分に記載し、該当ありと○がついた項目について下記の、様式1のシートと、様式2の各項目の対象表を参考に8-C各項目欄に転記。なお、C−6.情報の入手日については、情報提供様式1を受理した日付を記載。 |
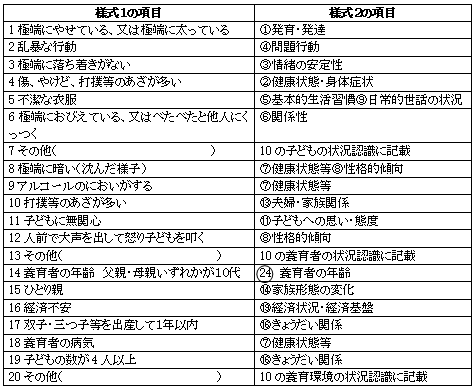 D〜Gの各関係機関の列
D〜Gの各関係機関の列
| 6.情報入手日: |
情報提供を受けた日付、又は情報照会を行った日付を記載 |
| 7. |
確認状況のチェック方法
| 心配: |
支援を要する状況ありの場合に○を記入 |
| 心配なし: |
支援を要する状況なしの場合に○を記入 |
| 不明: |
支援の要否の判断に迷う場合に○を記入 |
|
| 8.項目: |
各項目欄に以下のような網掛けになっている欄は、該当する項目の情報照会を行う際に、9、養育支援が必要となるやすい要素を参考に、問い合わせ先として、列頭にある機関に優先的に情報照会を行う項目である。 |
 |
| H. |
状況把握訪問での情報の列
| 6.情報入手日: |
状況把握のための訪問を行った日付を記載 |
| 7. |
確認状況のチェック方法
| 心配: |
支援を要する状況ありの場合に○を記入 |
| 心配なし: |
支援を要する状況なしの場合に○を記入 |
| 不明: |
支援の要否の判断に迷う場合に○を記入 |
|
| 8.項目: |
状況把握のための訪問においては、9、養育支援が必要となるやすい要素を参考に可能な限りすべての項目の状況について確認し、該当する欄に○を記入 |
|
| B. |
状況確認の列
C〜Hの各関係機関から得られた情報状況を集約し、一機関でも心配という欄に○がついた項目については、心配該当の欄に○を記入。また、どの関係機関も把握できていない未確認の項目がある場合については未確認の欄に○をして、情報の収集状況について集約
また、情報入手日の欄については情報集約を行った日付を記載 |
| 10. |
状況認識の列
子ども・養育者・養育環境・非変動環境の状況認識について、親族の支援や、子どもの問題対処能力等、前向きな情報も含めて集約された情報より、Bの状況確認を行った時点での状況認識について記載 |
| 11. |
初回情報提供機関
支援の対象になる家庭について、最初に情報提供を行った機関と、受理した日付、担当者名を記入すると同時に、情報提供機関の支援的関わりの有無についての情報を記載 |
| 12. |
情報確認した機関
C〜Hの関係各機関から情報提供を受けた場合や、情報照会を行った際に確認した日付、担当者名を記入すると同時に、情報提供機関の支援的関わりの有無についての情報を記載 |
| 13. |
状況判断
10、状況認識の結果を参考に、対応判断の根拠となる状況判断について記載し、状況判断を行った日付についても記入 |
| 14. |
対応判断
13の状況判断の結果、当該家庭の状況を判断し、以下の4つの対応を決定し、その決定に対し決裁がおりた日付を記入
| (1) |
情報を集約した結果、虐待が疑われ緊急な支援が必要な場合は、児童相談所へ通告 |
| (2) |
状況判断に必要な情報は集積されているが、具体的な支援の方向性等の状況判断が困難な場合は、関係者会議を招集 |
| (3) |
訪問や関係機関からの情報等から本事業に基づく訪問支援を決定 |
| (4) |
当面訪問による支援は必要ないと思われるが、一般子育て支援等の通所型育児支援サービスを紹介する場合は紹介先を(b)に記入、すでに支援を利用している場合は利用先を(a)に記入 |
|
| 15. |
上記決定事項に対する対応内容を記載
14.対応判断を受けて、具体的な対応内容について記載
例えば、対応(1)であれば通告した児童相談所の担当者名や、児童相談所名、通告内容について記載。対応(2)であれば、関係者会議を呼びかけたメンバーや、会議の予定日等について記載。対応(3)であれば、状況把握のための訪問依頼者や、訪問状況把握日について記載。対応(4)であれば、一般子育て支援等の通所型育児支援サービスを紹介する場合は紹介先の連絡先や担当者を記載 |
様式3
[NO. ] 支援の必要性を判断するための一定の指標(例示)に基づく、支援計画の立案・実施状況に関する様式
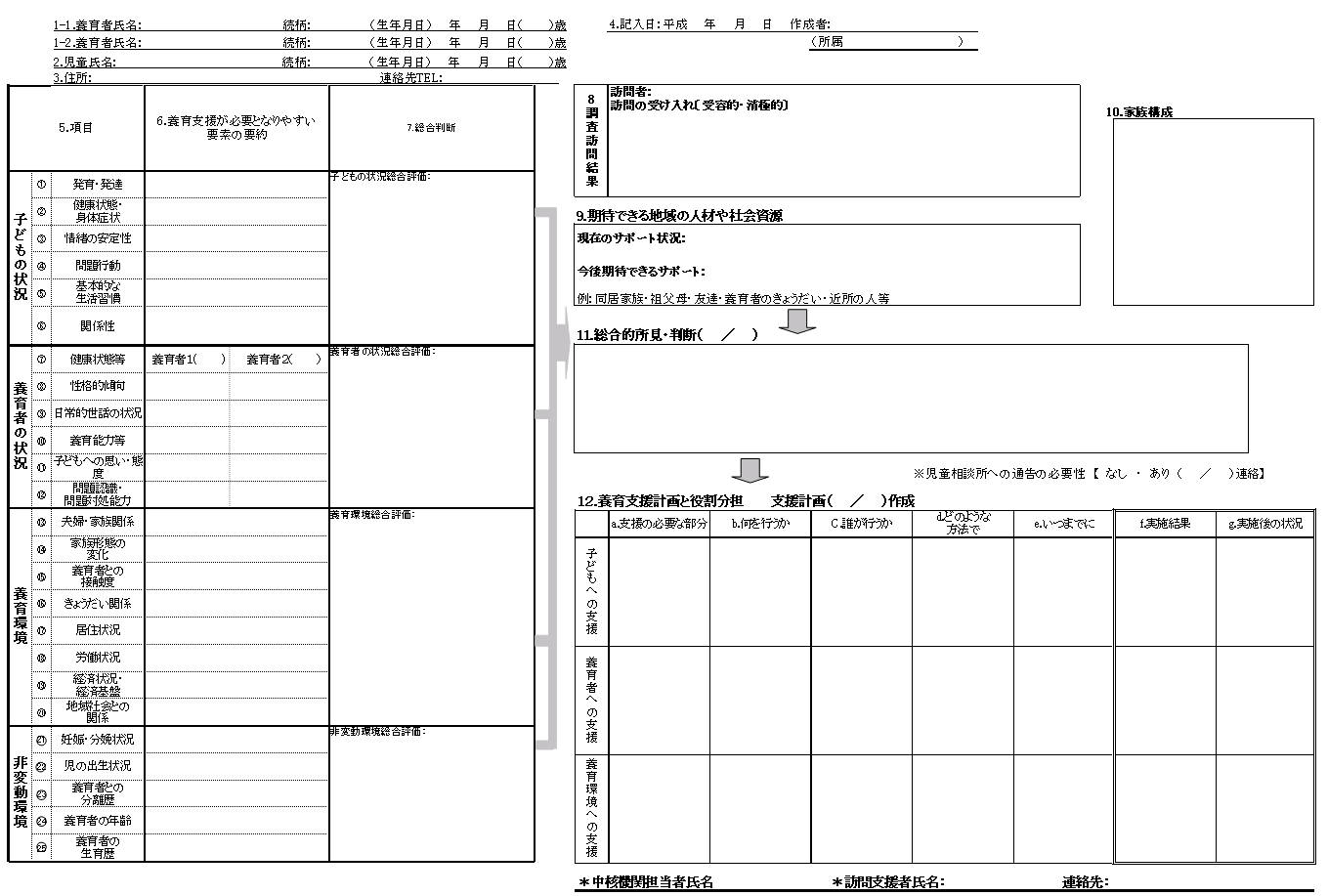
| 様式3: |
支援の必要性を判断するための一定の指標(例示)に基づく、適切な支援の内容、方法、スケジュール等についての立案・実施状況に関する様式(中核機関および訪問支援者が用いる様式)記載要領 |
| 1. |
養育者氏名: (生年月日) 年 月 日( 歳)・・・様式2より転記
支援の対象となる、養育者の氏名・生年月日、また続柄は支援対象となる子どもからみた続柄を記載。また、支援の対象となる養育者が夫婦等複数の場合は両者について記載
|
| 2. |
児童氏名: (生年月日) 年 月 日( 歳)・・・様式2より転記
支援の対象となる、子どもの氏名・生年月日、また続柄は支援対象となる養育者からみた続柄を記載。(例:長男(実子)・次女(養子)等)。また当該家庭にいる児童数が複数の場合は、10.家族構成の欄に記載した上、それぞれの子どもの状況が記載できるよう記載欄を工夫
|
| 3. |
住所・連絡先電話・・・様式2より転記
支援の対象となる家庭の現在の居住地・連絡先について記載
|
| 4. |
記入日:平成 年 月 日 作成者: (所属 : )
原則として中核機関担当者の氏名・所属を記載。なお、記入日についてはBの状況確認を行った日付を記載する。
|
| 6. |
養育支援が必要となりやすい要素の要約
様式2の情報集約のシートを参考に、関係者会議を開いた場合はその事務局が、訪問状況把握を行った場合には、状況把握のための訪問者が、各項目毎に養育支援が必要となりやすい状況を要約し、記載する。
|
| 7. |
総合判断
6.養育支援が必要となりやすい要素の要約を参考に、子ども・養育者・養育環境・非変動環境についてそれぞれ評価を行い、その結果を記載する。
|
| 8. |
状況把握訪問結果
様式2における情報集約の結果の対応判断が、(3)状況把握のための訪問が必要となった場合において、その訪問状況把握の概要について訪問者が記載する。その際に状況把握のための訪問の受け入れ状況等について養育者の反応を記載し、支援の方向性を決めていく際の参考とする。
|
| 9. |
期待できる地域の人材や社会資源
様式2の10.状況認識の列や、状況把握のための訪問結果を参考に、養育支援が期待できる地域の人材や社会資源について具体的に記載し、支援の方向性を決めていく際の参考とする。 |
| 10. |
家族構成 現在同居している家族を中心に、家族構成を図示する。
|
| 11. |
総合的所見・判断( / )
養育支援の必要性や、その内容について総合的な所見を記載。また、その見解に対し決裁がおりた日付を記入。なお総合判断の結果、児童相談所に通告が必要と判断された場合は日付等を欄外に記載
|
| 12. |
養育支援計画と役割分担 支援計画( / )作成
11.総合的所見・判断にもとづき、養育支援の内容について、a〜eまでの詳細を立案段階で記入し、f・gの項目については支援実施後に、訪問支援者の報告に基づき中核機関が記載する。なお、支援結果の詳細については別途様式等を用いて各訪問支援者が記載する。また初回の支援計画が終了後、訪問による継続支援が必要な家庭かどうかを中核機関が判断し、12の支援計画を新たに作成する。 |