改正少年法の施行に関する児童相談所運営指針(局長通知)改正 新旧対照表
| 改 正 後 | 改 正 前 |
第1章 児童相談所の概要第2節 児童相談所の業務1. 相談の受付(1)・(2)(略) (3) このほか、少年法の規定に基づく警察官からの送致、家庭裁判所からの送致を受けて、援助活動を展開することもある。 (4)・(5)(略) 2〜5(略) |
第1章 児童相談所の概要第2節 児童相談所の業務1. 相談の受付(1)・(2)(略) (3) このほか、少年法の規定に基づく家庭裁判所からの送致を受けて、援助活動を展開することもある。 (4)・(5)(略) 2〜5(略) |
第3節 相談の種類とその対応1.(略)2. 各種相談の対応の基本(1)・(2)(略) (3) 非行相談 ア〜エ(略) オ 平成19年の少年法改正により、警察が調査を行った結果、一定の重大事件に係る触法少年と思料し、又は、当該少年に係る事件につき家庭裁判所の審判に付すことが適当と思料するときは、警察の調査結果を活かし事案の真相解明を踏まえた適正な措置がとられるよう、児童相談所長に送致する制度が設けられた。 また、警察の調査により作成された書類については、警察官から児童相談所長への送致の際にあわせて送付されることとされた。その後、児童相談所長等が家庭裁判所送致の措置をとったときは、児童相談所等の作成書類と共に、警察の作成書類も家庭裁判所に送付することとされている。 このため、児童相談所は、援助内容の決定に当たって、これらの書類を十分活用する。 |
第3節 相談の種類とその対応1.(略)2. 各種相談の対応の基本(1)・(2)(略) (3) 非行相談 ア〜エ(略) |
(4)〜(6)(略) |
(4)〜(6)(略) |
第3章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務第2節 相談の受付と受理会議1.相談の受付児童相談所が受け付ける相談は次の5つに大別される。 (1)〜(3)(略) (4) 警察官からの送致(少年法第6条の6) (5) 家庭裁判所からの送致等(少年法第18条、第23条、第24条) (6) その他関係機関からの援助依頼、調査依頼、照会、届出等 2・3(略)4.管轄児童相談所は則第5条の2に基づき、管轄区域を有しているが、個々の事例の具体的管轄の決定については、以下のことに留意するとともに、子どもの福祉を図るという観点から個々の事例に即した適切な判断を行う。 (1)・(2)(略) (3) 警察からの通告及び送致等は、子どもの保護者の居住地にかかわらずその子どもの現在地を管轄する児童相談所に行われるので、これを受け付けた児童相談所にあっては受け付け後、子どもの状況や家庭環境等について調査、判定を行い、関係児童相談所への移管の適否や移管の方法等について決定する。特に、保護者からの虐待により家出した場合等にあっては、身柄付きで移管を行うなど、子どもの福祉を最優先した判断を行う。 (4)〜(9)(略) 5(略)6.相談受付の方法(略) (1)・(2)(略) (3) 身柄を伴う通告・送致の場合 ア〜エ(略) オ 警察からの身柄を伴う送致への対応 警察官から少年法第6条の6第1項に基づき送致された子どもに関しては、事件の重大性等に鑑みて、警察と児童相談所が相互に協力して子どもの身柄の引継ぎを行うことが必要である。 児童相談所においては、必要に応じ子どもを一時保護するとともに緊急の受理会議を開催して今後の対応方針を決定すること。一時保護は、社会診断、心理診断等の必要な診断を行い、援助方針会議において家庭裁判所への送致の必要性の判断や援助方針を決定するまでの間、行うことが必要である。 |
第3章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務第2節 相談の受付と受理会議1.相談の受付児童相談所が受け付ける相談は次の5つに大別される。 (1)〜(3)(略) (4) 家庭裁判所からの送致等(少年法第18条、第23条、第24条) (5) その他関係機関からの援助依頼、調査依頼、照会、届出等 2・3(略)4.管轄児童相談所は則第5条の2に基づき、管轄区域を有しているが、個々の事例の具体的管轄の決定については、以下のことに留意するとともに、子どもの福祉を図るという観点から個々の事例に即した適切な判断を行う。 (1)・(2)(略) (3) 警察通告等は、子どもの保護者の居住地にかかわらずその子どもの現在地を管轄する児童相談所に行われるので、これを受け付けた児童相談所にあっては受け付け後、子どもの状況や家庭環境等について調査、判定を行い、関係児童相談所への移管の適否や移管の方法等について決定する。特に、保護者からの虐待により家出した場合等にあっては、身柄付きで移管を行うなど、子どもの福祉を最優先した判断を行う。 (4)〜(9)(略) 5(略)6. 相談受付の方法(略) (1)・(2)(略) (3) 身柄を伴う通告・送致の場合 ア〜エ(略) |
|
(4)〜(7)(略) (8) 送致書等による場合 ア 市町村、都道府県の設置する福祉事務所の長又は家庭裁判所から送致を受けたときは、受理会議において検討後一般の事例に準じて行う。 イ 警察官から少年法第6条の6第1項に基づく事例に関して送致を受けたときは、緊急に受理会議を開催して対応方針を決め、迅速に対応する。 |
(4)〜(7)(略) (8) 送致書等による場合 市町村、都道府県の設置する福祉事務所の長又は家庭裁判所から送致を受けたときは、受理会議において検討後一般の事例に準じて行う。 |
|
ウ 家庭裁判所から送致を受けたときは、家庭裁判所の審判等の結果に基づき、その決定の範囲内で、速やかに児童福祉法上の援助を行う。 (9)(略) |
なお、家庭裁判所から送致を受けたときは、家庭裁判所の審判等の結果に基づき、その決定の範囲内で、速やかに児童福祉法上の援助を行う。 (9)(略) |
第4章 援助第4節 児童福祉施設入所措置、指定医療機関委託1・2(略)3. 措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長(1)・(2)(略) (3) 停止 ア〜ウ(略) エ 停止の効果は定められた停止期間の終了と同時に失われる。ただし、当初定められた期間の終了を待たずに子どもが施設に 戻った場合又は期間が不確定であった場合には、援助方針会議で検討し、停止の解除を行い、その結果を施設長、保護者等に通知する。 (4)・(5)(略) 4・5(略) |
第4章 援助第4節 児童福祉施設入所措置、指定医療機関委託1・2(略)3. 措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長(1)・(2)(略) (3) 停止 ア〜ウ(略) エ 停止の効果は定められた停止期間の終了と同時に失われる。ただし、当初定められた期間の終了を待たずに子どもが施設に 戻った場合又は期間が不確定であった場合には、処遇会議で検討し、停止の解除を行い、その結果を施設長、保護者等に通知する。 (4)・(5)(略) 4・5(略) |
第7節 家庭裁判所送致1. 法第27条第1項第4号の規定に基づく送致(1) この措置は、触法少年及びぐ犯少年について、専門的観点から判断して家庭裁判所の審判に付することがその子どもの福祉を図る上で適当と認められる場合に行う。 |
第7節 家庭裁判所送致1. 法第27条第1項第4号の規定に基づく送致(1) この措置は、触法少年及びぐ犯少年について、専門的観点から判断して家庭裁判所の審判に付することがその子どもの福祉を図る上で適当と認められる場合に行う。 |
|
(2)(略) (3) 家庭裁判所の審判に付することが適当と認められる例として以下に掲げる場合がある。 [1](略) [2] 14歳以上の児童自立支援施設入所児童等を少年法第24条第1項第3号の保護処分により少年院に入院させることが相当と認められる場合 [3] 非行の重大性にかんがみ、家庭裁判所の審判を通じて非行事実を認定した上で適切な援助を決定する必要性が高いと考えられる上、被害者保護という観点からも、少年法の手続によって事実解明等を行う必要があると考えられる場合 |
(2)(略) (3) 家庭裁判所の審判に付することが適当と認められる例として以下に掲げる場合がある。 [1](略) [2] 14歳以上の児童自立支援施設入所児童等を少年法第24条第1項第3号の保護処分により少年院に入院させることが相当と認められる場合 |
|
(4)(略) (5) この送致は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対し、根拠法令の条項及び少年審判規則(昭和23年最高裁判所規則第33号)第8条第1項に定める事項、子どもの援助に関する意見を記載した送致書により行う。この場合、書類、その他参考となる資料があるときは併せて送付し、また、文書のみでなく家庭裁判所と十分な連絡を行う。 |
(4)(略) (5) この送致は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対し、根拠法令の条項及び少年審判規則(昭和23年最高裁判所規則第33号)第8条第1項に定める事項、子どもの援助に関する意見を記載した送致書により行う。 この場合、書類、証拠物、その他参考となる資料があるときは併せて送付し、また、文書のみでなく家庭裁判所と十分な連絡を行う。 |
2(略) |
2(略) |
第5章 一時保護第1節 一時保護の目的と性格(略) 1. 一時保護の必要性一時保護を行う必要がある場合はおおむね次のとおりである。 (1) 緊急保護 ア・イ(略) ウ 子どもの行動が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはそのおそれがある場合 エ 一定の重大事件に係る触法少年と思料すること等のため警察から法第25条に基づき通告のあった子ども又は少年法第6条の6第1項に基づき送致のあった子どもを保護する場合 |
第5章 一時保護第1節 一時保護の目的と性格(略) 1. 一時保護の必要性一時保護を行う必要がある場合はおおむね次のとおりである。 (1) 緊急保護 ア・イ(略) ウ 子どもの行動が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはそのおそれがある場合 |
|
(2)・(3)(略) 2. 一時保護の期間、援助の基本(1)〜(5)(略) (6) 一時保護が必要な子どもについては、その年齢も乳幼児から思春期まで、また一時保護を要する背景も非行、虐待あるいは発達障害など様々であり、一時保護に際しては、こうした一人ひとりの子どもの状況に応じた適切な援助を確保することが必要である。 ア 管轄する一時保護所(複数ある場合には全ての一時保護所)における適切な援助の確保が困難な場合には、他の都道府県等の管轄する一時保護所の協力を仰ぐといった広域的な対応や、 イ (略) 等により、適切な援助の確保に努めることが重要である。 (7) 一定の重大事件に係る触法少年と思料される少年の一時保護については、当該少年の心理・行動面での問題の重篤性、一時保護中の他の子どもへの影響、当該少年のプライバシー保護等に配慮して実施することが必要であり、多くの職員の協力が不可欠であることから、当該児童相談所の職員だけで対応することが困難な場合も想定される。このような児童相談所にあっては、重大事件が起きた場合の緊急対応体制をあらかじめ整えておく必要があるので、主管部局が中心となって主管部局等の職員、他の児童相談所、児童自立支援施設等と協力して、万一の際に適切に一時保護ができる体制を整備されたい。 |
(2)・(3)(略) 2. 一時保護の期間、援助の基本(1)〜(5)(略) (6) 一時保護が必要な子どもについては、その年齢も乳幼児から思春期まで、また一時保護を要する背景も非行、虐待あるいは発達障害など様々であり、一時保護に際しては、こうした一人ひとりの子どもの状況に応じた適切な援助を確保することが必要である。 ア 管轄する一時保護所における適切な援助の確保が困難な場合には、他の都道府県等の管轄する一時保護所を一時的に活用するといった広域的な対応や、 イ (略) 等により、適切な援助の確保に努めることが重要である。 |
|
(8) 3(略)4.行動自由の制限(1) 行動自由の制限 一時保護中は、入所した子どもを自由な環境の中で落ち着かせるため、環境、援助方法等について十分留意する。無断外出が頻繁である等の理由により例外的に行動自由の制限を行う場合においても、できるだけ短期間の制限とする。 (2)〜(4)(略) |
(7) 3(略)4.行動自由の制限(1) 行動自由の制限 一時保護中は、入所した子どもを自由な環境の中で落ち着かせるため、環境、処遇方法等について十分留意する。無断外出が頻繁である等の理由により例外的に行動自由の制限を行う場合においても、できるだけ短期間の制限とする。 (2)〜(4)(略) |
第3節 一時保護所の運営1・2(略)3.保護の内容(1)〜(7)(略) (8)特別な配慮が必要な事項 一定の重大事件に係る触法少年と思料される少年については、警察からの通告又は送致を受けて一時保護することとなるが、当該一時保護の期間においては、児童相談所における各種調査・診断を経た上で、援助の内容を決定することが必要である。また、重大事件に係る少年であっても行動自由の制限は、自由に出入りのできない建物内に子どもを置くという程度までであり、個別対応しなければならない事例の場合、個別対応プログラムを作り対応することが基本である。 |
第3節 一時保護所の運営1・2(略)3.保護の内容(1)〜(7)(略) |
4〜6(略)7. 子どもに関する面会、電話、文書等への対応(1)・(2)(略) (3) 一時保護する少年に対して警察が質問等の調査をする場合もあると考えられるが、この場合には、児童福祉法の趣旨を踏まえ、児童に与える影響に鑑み児童の心身の負担が過重なものとならないよう、当該児童の心身の状況に配慮した上で、可能な限り協力されたい。 |
4〜6(略)7. 子どもに関する面会、電話、文書等への対応(1)・(2)(略) (3) 一時保護中の子どもに対して警察等による聴取がある場合には、児童福祉の観点から、本人及び他の一時保護中の子どもに与える影響に特に注意し、本人、保護者等の同意、保護者、職員の立ち会い、聴取の場所、時間等について十分留意する。 |
8〜10(略) |
8〜10(略) |
第4節 一時保護した子どもの所持物の保管、返還等1. 子どもの所持物(1)・(2)(略) (3) 盗品、刃物類、子どもの性的興味を著しく誘発するような文書類等、一時保護中本人に所持させることが子どもの福祉を損なうおそれがある物については、法第33条の2第1項の規定に基づき、児童相談所長は「子どもの所持物」として保管することができる。これらの物については子どもの意思にかかわらず保管できるが、子どもの所有物である場合には、できる限り子どもの同意を得て保管する。 |
第4節 一時保護した子どもの所持物の保管、返還等1. 子どもの所持物(1)・(2)(略) (3) 盗品、刃物類、子どもの性的興味を著しく誘発するような文書類等、一時保護中本人に所持させることが子どもの福祉を損なうおそれがある物については、法第33条の2第1項の規定に基づき、児童相談所長は「子どもの所持物」として保管することができる。これらの物については子どもの意思にかかわらず保管できるが、子どもの所有物である場合には、できる限り子どもの同意を得て保管する。
|
|
(4)・(5)(略) 3. 所持物の返還(1)(略) (2) 返還請求権者に対する返還 ア 保管物中、その子ども以外の者が返還請求権を有することが明らかな物については、これをその権利者に返還しなければならない。(法第33条の2第3項) |
(4)・(5)(略) 3. 所持物の返還(1)(略) (2) 返還請求権者に対する返還 ア 保管物中、その子ども以外の者が返還請求権を有することが明らかな物については、これをその権利者に返還しなければならない。(法第33条の2第3項)
|
|
イ なお、返還するに当たって、返還請求権を有する者であるか否かの決定は、返還請求人の申立て、被害事実に関する警察等の公証力のある資料等に基づいて慎重に行う。 |
イ 返還請求権を有する者であるか否かの決定は、返還請求人の申立て、被害事実に関する警察等の公証力のある資料等に基づいて慎重に行う。 |
|
(3)(略) 4〜6(略) |
(3)(略) 4〜6(略) |
第6章 事業に係る留意事項第3節 児童虐待防止対策支援事業1(略)2.事業内容(1)・(2)(略) (3) スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業 ア〜ウ(略) エ 虐待等による子どもの死亡事例を未然に防くとともに、子どもの権利擁護に関する意識を高めるため、援助困難事例における会議や死亡事例検証委員会等を開催するにあたっては、専門的技術的助言・指導等を行うものとする。 (4)・(5)(略) 3(略) |
第6章 事業に係る留意事項第3節 児童虐待防止対策支援事業1(略)2.事業内容(1)・(2)(略) (3) スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業 ア〜ウ(略) エ 虐待等による子どもの死亡事例を未然に防くとともに、子どもの権利擁護に関する意識を高めるため、処遇困難事例における会議や死亡事例検証委員会等を開催するにあたっては、専門的技術的助言・指導等を行うものとする。 (4)・(5)(略) 3(略) |
第7章 各種機関との連携第14節 警察との関係1. 警察の位置付け(1)(略) (2) 児童相談所は、次に掲げる事項について警察と関係を有する。 [1] 触法少年の送致(法第26条)、触法少年及びぐ犯少年の通告(法第25条) |
第7章 各種機関との連携第14節 警察との関係1. 警察の位置付け(1)(略) (2) 児童相談所は、次に掲げる事項について警察と関係を有する。 [1] 触法少年、ぐ犯少年の通告(法第25条) |
|
[2]〜[6](略) 2.児童相談所へ通告される事例(1) 触法少年及びぐ犯少年の通告は法第25条に基づき原則として児童相談所に対し、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第22条第1項第2号並びに第33条第1項第2号及び第3号の規定に基づき警察庁長官が定める様式の児童通告書の文書により行われる。 |
[2]〜[6](略) 2. 児童相談所へ通告される事例(1) 触法少年及びぐ犯少年の通告は法第25条に基づき原則として児童相談所に対し、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第215条に定める児童通告書等の文書により行われる |
|
(2)〜(5)(略) 3. 児童相談所へ送致される事例(1) 平成19年の少年法改正により、警察官は、触法少年に係る事件について調査を行った結果、一定重大事件に係る触法少年と思料し、又は当該少年につき家庭裁判所の審判に付すことが適当と思料する場合には、当該事件を児童相談所長に送致しなければならない旨等が規定された。また、警察の調査により作成された書類については、警察官から児童相談所長への送致の際にあわせて送付されることとされた。その後、児童相談所長等が家庭裁判所送致の措置をとったときは、児童相談所等の作成書類と共に、警察の作成書類も家庭裁判所に送付することとされている。 (2) 警察官から事件が送致された場合を除き、警察官が児童福祉法第25条の規定により児童相談所に通告するときは、あわせて同法の措置をとるのに参考となる警察の調査の概要及び結果を通知することとされた。 |
(2)〜(5)(略) |
4.委託一時保護5. 少年補導、非行防止活動等6. 虐待事例等における連携7. その他 |
3. 委託一時保護4. 少年補導、非行防止活動等5. 虐待事例等における連携6. その他 |
第8章 児童相談所の設備、器具、必要書類第3節 必要書類(1)(略) (2) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、保護者、関係機関等に交付する書類には次のものがある。これらの書類は、逐次児童記録票綴にファイルしていく。 [1]〜[8](略) [9] 警察から送致のあった児童に関する援助結果通知書 |
第8章 児童相談所の設備、器具、必要書類第3節 必要書類(1)(略) (2) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、保護者、関係機関等に交付する書類には次のものがある。これらの書類は、逐次児童記録票綴にファイルしていく。 [1]〜[8](略) |
|
[10] 家庭裁判所調査嘱託回答書 [11] 同意書 [12] 判定意見書、証明書 [13] 1歳6か月児、3歳児精密健康診査受診票 [14] その他 (3)(略) |
[9] 家庭裁判所調査嘱託回答書 [10] 同意書 [11] 判定意見書、証明書 [12] 1歳6か月児、3歳児精密健康診査受診票 [13] その他 (3)(略) |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
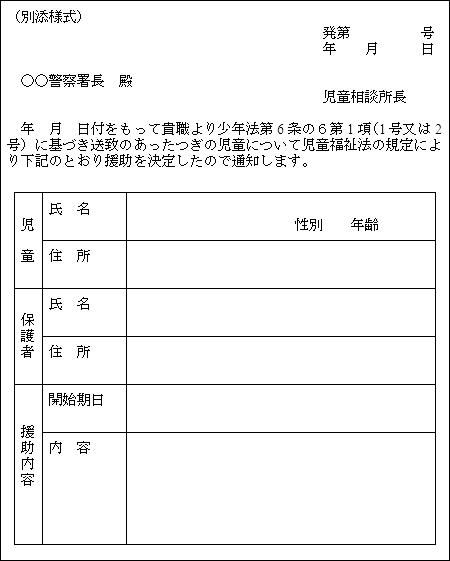 |

