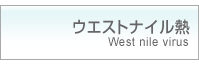
ウエストナイル熱について
ウエストナイル熱の診断・治療ガイドライン
国立感染症研究所ウイルス第一部 倉根一郎
|
病原体:ウエストナイルウイルス 好発年齢:脳炎は高齢者に多い 性差:なし 分布:アフリカ、中近東、西アジア、ヨーロッパ、北アメリカ 好発時期:温帯地域においては夏季 |
|
感染経路:感染蚊が刺すことによる 潜伏期間:2〜14日(通常2〜6日) 感染期間:
|
症状:
|
オーダーする検査:
|
確定診断のポイント:
注意
|
| 治療のポイント:対症療法のみ |
報告の基準:
注意
|
ウエストナイルウイルスの分布地域
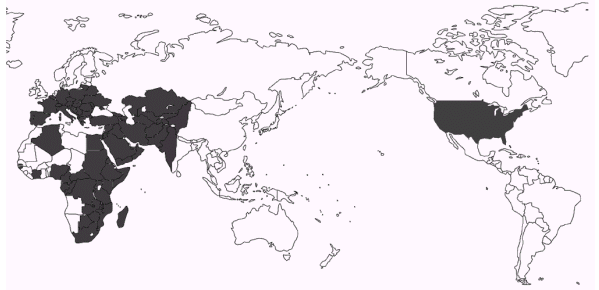
1.ウエストナイル熱の背景
1)疫学状況
| ・ | 従来アフリカ、ヨーロッパ、西アジアでの患者発生報告があった。アメリカ大陸での患者発生はなかったが、1999年アメリカ合衆国のニューヨーク市周辺での流行が報告されたことから、大きな注目を集めるようになった。 近年の主な流行は以下の通りである。
|
| ・ | 日本においては輸入症例の報告、国内感染いずれもない。 |
2)病原体
| ・ | フラビウイルス科フラビウイルスに属するウエストナイルウイルス(West Nile virus)。 |
| ・ | 1937年アフリカのウガンダWest Nile地方で熱発患者から分離された。 |
3)感染経路
| ・ | ウエストナイルウイルスは自然界においては、トリと蚊の感染サイクルで維持される。 |
| ・ | ヒトはウエストナイルウイルス感染蚊に刺されることにより感染する。 |
| ・ | 媒介蚊は、イエカ、ヤブカ等である。 |
| ・ | ヒトからヒトへの感染はない。 なお、輸血、臓器移植、母乳を介しての感染を疑わせる報告がある。(この感染経路に関しては現在米国で調査中であり、本感染経路の重要性については今後の報告に注意する必要がある)。 |
4)潜伏期
| ・ | 2〜14日(普通2〜6日) |
| ・ | 感染の進展は完全には解明されていないが以下のように考えられている。 ウイルスはまず、皮膚や所属リンパ節で増殖し、1次ウイルス血症をおこす。次に網内系において増殖し、2次ウイルス血症をおこし中枢神経に到達する。 |
2.診断と治療
1)臨床症状
| ・ | ウエストナイル熱は突然の発熱(39度以上)で発症する。3-6日間の発熱、頭痛、背部の痛み、筋肉痛、食欲不振などの症状を有する。約半数で発疹が胸部、背、上肢に認められる。リンパ節腫脹も通常認められる。症状は通常1週間以内で回復するが、その後倦怠感が残ることも多い。 |
| ・ | 脳炎は上記症状とともにさらに重篤な症状として、激しい頭痛、方向感覚の欠如、麻痺、意識障害、痙攣等の症状を呈する。 |
| ・ | 米国の例では筋力低下が約半数に認められる。 |
2)検査所見
| ・ | 末梢血中の白血球数正常あるいは軽度増加。リンパ球数低下。 |
| ・ | 脳炎患者においては脳脊髄液中のリンパ球数増加、蛋白増加、糖正常。 |
3)診断
上記臨床症状を有する急性熱性疾患、脳炎および実験室診断。
実験室診断として以下のいずれか:
| ・ | ウエストナイルウイルスが血液あるいは脳脊髄液から分離される。 |
| ・ | ウエストナイルウイルス遺伝子が血液あるいは脳脊髄液中に検出される。 |
| ・ | ウエストナイルウイルス特異的IgMが血液あるいは脳脊髄液中に検出される。 |
| ・ | ウエストナイルウイルス特異的IgG(中和法で確認する)が血液中に検出され、ペア血清において4倍以上の上昇が確認される。 |
注意
| ・ | なお、特異的IgM、中和抗体とも日本脳炎ウイルスと交叉するので、日本脳炎ウイルスに対するよりも高値であることを確認する必要がある。 |
| ・ | IgMにおいてもペア血清で上昇を確認することが望ましい。 |
4)鑑別診断
| ・ | ウエストナイル熱 発疹を有するデング熱等他のウイルス性疾患。 |
| ・ | ウエストナイル脳炎 他のウイルス性脳炎(他のアルボウイルス、ヘルペスウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルス、ムンプスウイルス、サイトメガロウイルス、EBウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルス、ヒト免疫不全ウイルスによる脳炎等) |
5)治療
対症療法のみ
6)経過、予後
| ・ | 感染例の約80%は不顕性感染に終わり、重篤な症状を示すのは、感染者の約1%といわれている。重篤な患者は主に、高齢者にみられ、致命率は重症患者の3〜15%とされる。 |
| ・ | ウエストナイル熱は予後良好。通常1週間以内で回復するが、その後倦怠感が残ることもある。 |
7)2次感染予防・感染の管理
| ・ | ワクチンはない。 |
| ・ | ウイルス侵淫地域では蚊との接触を避ける。 |

