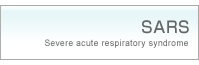
重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報
健感発第0714001号
平成15年7月14日
平成15年7月14日
| 各 | ┌ │ │ └ |
都道府県 政令市 特別区 |
┐ │ │ ┘ |
衛生主管部(局)長 殿 |
厚生労働省健康局結核感染症課長
重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第六項の指定感染症として定める等の政令(平成15年政令第304号。以下単に「政令」という。)及びその関係省令の施行に当たっての留意点等については、重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第六項の指定感染症として定める等の政令及び関係省令の施行について(平成15年7月14日健発第0714006号)により通知したところであるが、重症急性呼吸器症候群の患者及び疑似症患者の判断基準を下記のとおり定めるので、十分にご了知願いたい。
| 1 | 患者及び疑似症患者の判断基準について 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。以下「SARS」という。)の患者又は疑似症患者についての判断基準は、別紙のとおりとすること。 なお、当該基準については、今後の知見の収集・分析の結果を踏まえて、随時改訂していく予定であるので申し添える。 |
| 2 | 感染症発生動向調査との関係について 今般施行される通知については、SARSの患者及び疑似症患者を指定感染症の報告対象としているが、症例定義の改正とそれに伴うSARSコロナウイルスの行政検査の実施等について(SARS対策第13報)」(平成15年5月8日健感発第0508002号)の別紙1における疑い例についても、感染症発生動向調査の一環として報告されたいこと。 なお、この政令が施行される時点においては、「WHOが公表したSARS伝播確認地域」は存在しないため、同通知の(1)2若しくは3、又は(2)2若しくは3に該当する者は存在しないが、今後新たにSARS感染者が発生した場合にはこれらの要件に該当する者は当然に疑い例として対応する必要があること。 |
(別紙)
SARS患者、疑似症患者の判断基準について
| 1. | 定義 SARSコロナウイルスの感染による重症急性呼吸器疾患である。 |
| 2. | 臨床的特徴 多くは2−7日、最大10日間の潜伏期間の後に、急激な発熱、咳、全身倦怠、筋肉痛などのインフルエンザ様の前駆症状が現れる。2−数日間で呼吸困難、乾性咳嗽、低酸素血症などの下気道炎症が現れ、胸部CT、X線写真などで肺炎像が出現する。肺炎になった者の80−90%が1週間程度で回復傾向になるが、10−20%がARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) を起こし、人工呼吸器などを必要とするほど重症となる。 致死率は10%弱。WHOは推計として15%と発表としている。 |
| 3. | 報告の基準 |
| (1) | 患者の判断基準 診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、以下の方法によって病原体診断や血清学的診断がなされたもの。
【材料】鼻咽頭ぬぐい液、喀痰、尿、便、血清など
|
| (2) | 疑似症患者の判断基準 疑似症の診断:臨床所見、渡航歴などにより判断する。 以下の(1)又は(2)に該当し、かつ(3)の条件を満たすものとする。
注)他の診断によって症状が説明ができる場合は除外すること。 |