病院における省エネルギー実施要領
厚生労働省医政局
平成20年3月
目 次
1.はじめに
2.病院の省エネ推進体制と管理
3.エネルギー消費の特徴と省エネ対策のポイント
3.1 部門別エネルギー消費の特徴と省エネ対策のポイント
3.2 設備別省エネ対策のポイント
4.省エネについてもっと知りたい場合には
用語解説
1.はじめに
地球温暖化対策は、我が国が総力を挙げて国民全体で取り組んでいる国家的な課題であり、その最も効率的な対策と期待される省エネルギーを更に推進するため、国民運動の強化を図ることが求められています。
私立病院は、なかでも主要業務部門の1つとして位置づけられていることから、「私立病院における地球温暖化対策自主行動計画」を策定し、これに基づく取組を進めることとしているところですが、所管省庁である厚生労働省においても、これと軌を一にした取組を進めるため、私立病院のエネルギー管理において参考となる実施要領を定めることとしました。
病院運営の本分は、患者の療養です。このため、施設設備の24時間稼働、高度医療機器の利用など、エネルギー消費量が大きくなる要素が多いことが特徴ですが、逆に、そのこと故に、効率化を図るべき要素が多いとも考えられます。
しかしながら、抱える診療科の種別によって業務の実態が大きく異なるとともに、病床の規模においても中小病院から大規模な病院まで様々にわたることから、詳細な事項を定めた上で画一的にあてはめることは適切でないと考え、本実施要領では広く共通に取り組める事項を中心に記述するものです。
また、私立病院の運営は、国の医療政策と密接な関係があり、例えば、平成12年の第4次医療法改正において、一般病床の病室に求められる患者一人あたりの床面積が、それまでの4.3平方メートルから6.4平方メートルに変更されるなど、より療養環境の整備を図る方向で政策を進めていることから、エネルギー管理にも影響が及ぶことに留意しておく必要があります。
なお、本実施要領においては、私立病院を、「国、地方自治体、国立大学法人、独立行政法人を開設者とする病院以外の病院」と位置づけ、直接の対象はこれら私立病院としますが、それ以外の医療施設においても必要に応じて参考とされることを視野に入れています。
【参 考】
「私立病院における地球温暖化対策自主行動計画」における目標(平成20年3月26日公表)
○基準年2006年度から目標年2012年までに、エネルギー起源の「CO2排出原単位」(延床面積あたりのCO2排出量)を、年率1%削減。
2.病院の省エネ推進体制と管理
病院運営は、性格の異なる種々の部門から構成されていますが、エネルギー管理については、設備の運用調整(チューニング)等を主に担う施設設備の管理に携わる担当者(以下、設備担当者という)が中心となることが一般的に想定されます。
しかしながら、実際の取組を進めるにあたっては、病院サービスを提供する中で実施していくことが多いため、医療従事者や事務職員など他の病院職員においても、一人ひとりが推進担当者として意識を持った上で取り組むことが必要となります。
また、そういった職員全体の意識啓発を行うとともに、サービスの利用者である患者に対しても理解を求めることにおいて、さらには、省エネに資する設備投資について費用対効果を踏まえた意志決定を行っていくことなどにおいて、管理職が果たす役割も重要です。
いずれにしても病院の職員全員が省エネに関する問題認識を共有し、一体となって取組を行っていくことが大きな力となります。
ここでは、こういった考え方に基づき、病院における省エネの推進体制の一例をフロー図で示します。
この場合の基本的な取組の流れは以下のようになります。
[1]病院内に組織的な管理体制をつくり、管理マニュアルの作成等により個々の役割を明確にする。
[2]エネルギー消費の実態を調査・分析し、問題点の摘出と評価を行う。
[3]エネルギー量削減、コスト削減の目標値につき、原単位分析を中心に設定する。
[4]運用による改善、投資に基づく改修・更新による改善を優先順位により実行する。
[5]実施結果につき、実測・調査し、得られたデータを分析し、成果の確認を行う。
[6]成果が当初の目標を満足していない場合、見直し工程に戻る。
病院のエネルギー推進フロー(イメージ)
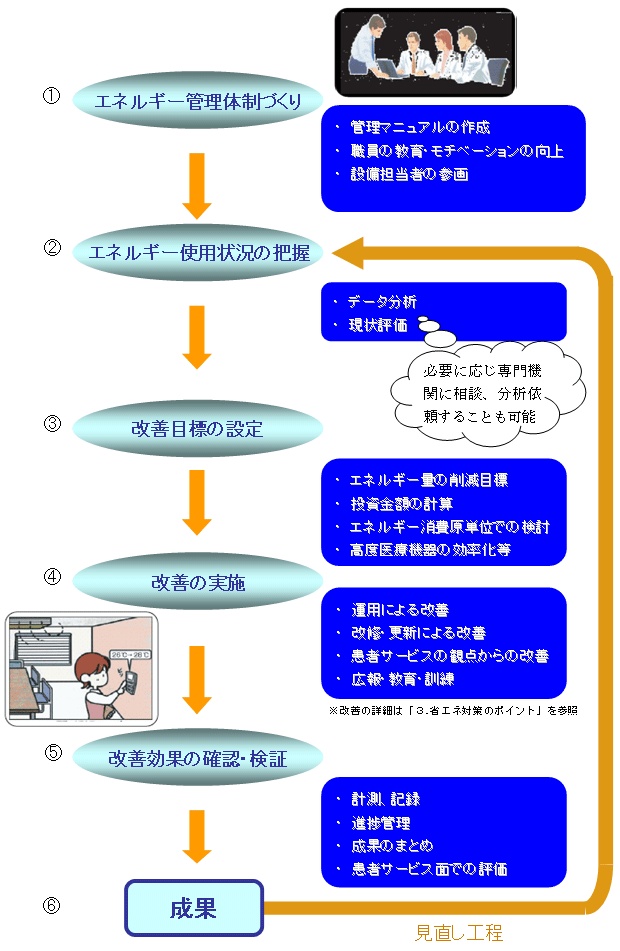
3.エネルギー消費の特徴と省エネ対策のポイント
3.1 部門別エネルギー消費の特徴と省エネ対策のポイント
私立病院等におけるエネルギー使用量や省エネ対策等の実態を把握するために行われた調査は以下のようなものがあり、参考に一部を抜粋して示します。
○エネルギー消費原単位について
地球温暖化対策自主行動計画の策定にあたり、同計画策定のためのプロジェクト委員会が、2005年度および2006年度のエネルギー消費に関するアンケート実態調査※を行いました。
病院施設全体で使用する年間のエネルギー量(熱と電気を熱量(MJ)換算したもの)を延床面積(平方メートル)で割った数値、すなわち、エネルギー消費原単位(MJ/平方メートル)については、病院の規模別のエネルギー消費原単位は下図のようになっています。
病院規模別にみた1平方メートル当りエネルギー消費原単位(2005年度、2006年度)
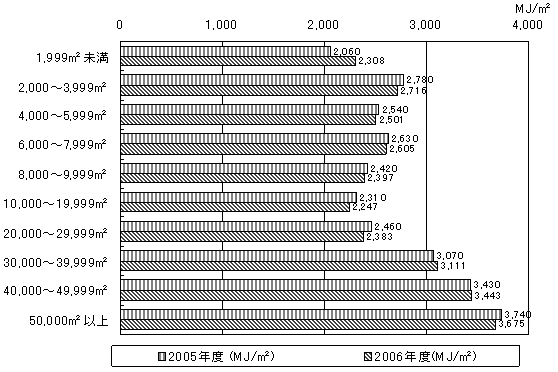
※(社)日本医師会「私立病院における地球温暖化対策自主行動計画策定プロジェクト委員会」
調査:省エネ法の私立病院等指定工場(300床以上の病院)、省エネ法の私立病院特定建築物(延床面積2,000以上の病院)、温対法の私立病院等特定排出者を含む病床数が50床以上の私立病院、973病院を対象に分析したもの。
また、エネルギー消費原単位の推移を下表に示します。
2006年度のエネルギー消費原単位は対前年度1.8%の減少となっています。
| (MJ/平方メートル) | 基準年度比 | |
| エネルギー消費原単位 | ||
| 2005年度 | 2,536 | 101.8 |
| 2006年度(基準年度) | 2,490 | 100.0 |
| エネルギー消費原単位の増減 | -46 (対前年度1.8%減) | |
○部門構成別エネルギー消費の特徴について
(財)省エネルギーセンターがエネルギー消費構造把握のため、平成15〜平成16年度に400床以上の病院47施設(公立含む)に対してヒアリングおよび計測調査を実施しました。
その結果を以下の表と図に示します。
部門の中で病棟や中央診療部門でのエネルギー消費が大きいことが分かります。
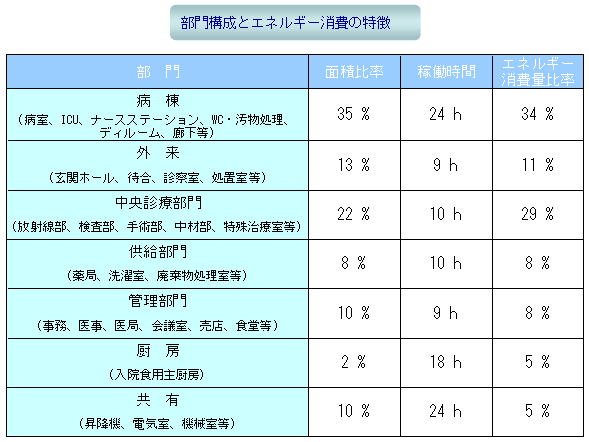
・面積比率:部門ごとの該当施設における床面積の比率
・稼働時間:各部門における職員の平均執務時間
・エネルギー消費量比率:病院施設全体に対する各部門のエネルギー消費量をヒアリングや実測によって割り出した比率
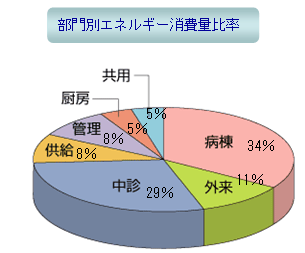
以下に、上記の(財)省エネルギーセンターの調査を踏まえ、病院の各部門別に考えられるエネルギー消費の特徴と省エネ対策のポイントを示します。
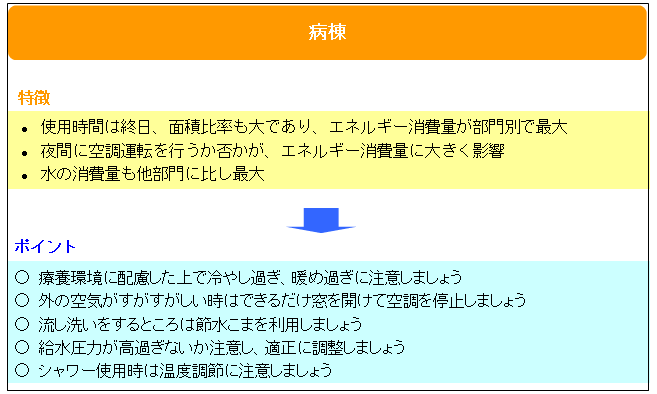
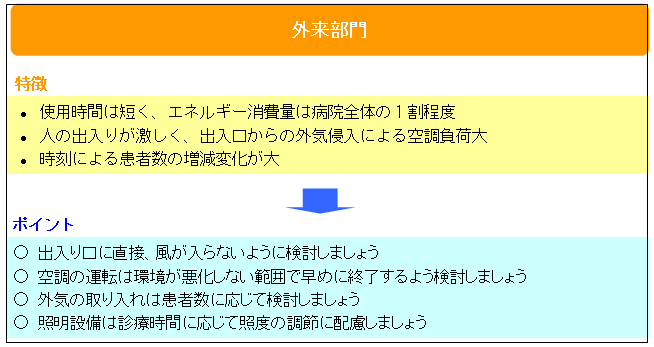
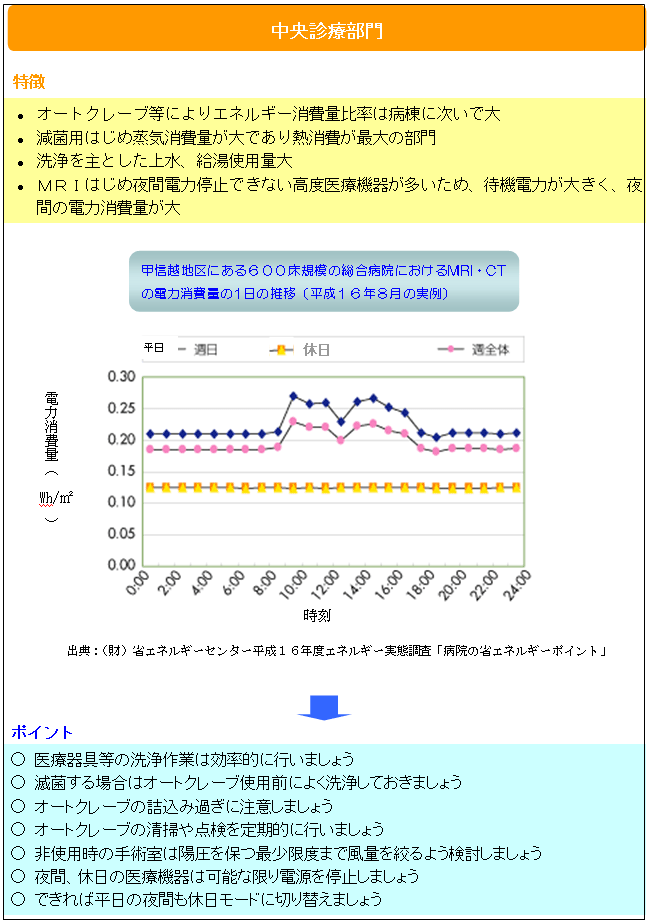
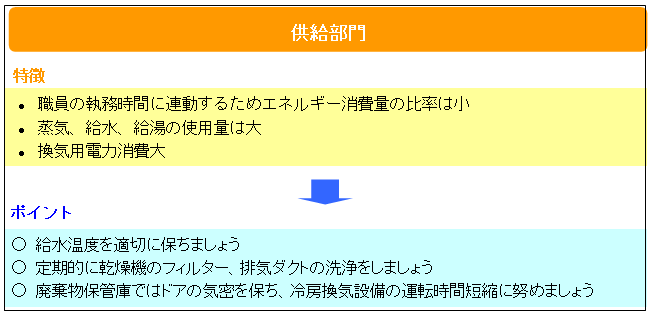
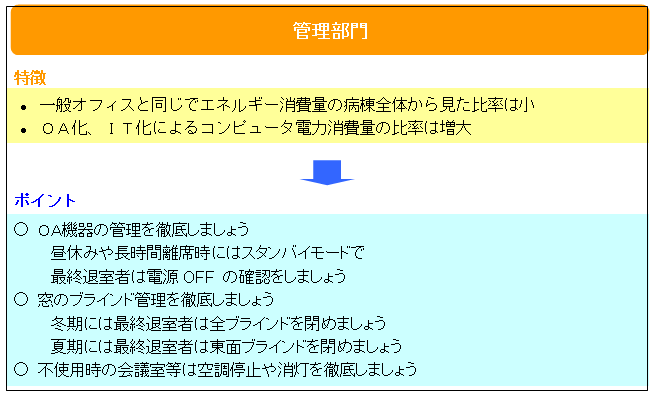
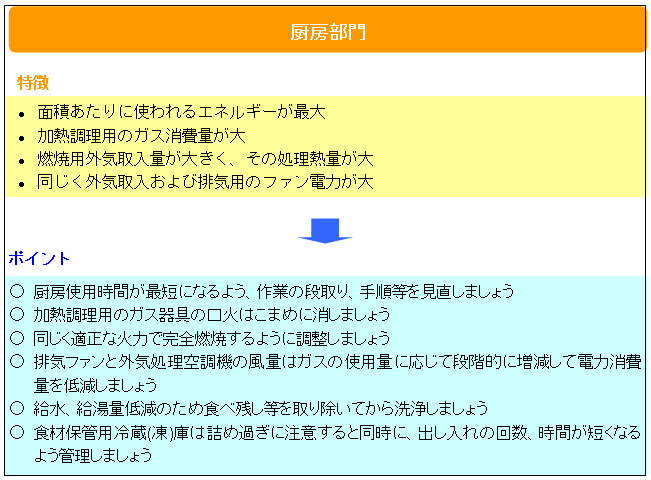
3.2 設備別省エネ対策のポイント
ここでは、同じく(財)省エネルギーセンターの調査を踏まえ、具体的な設備別の省エネ対策のポイントを示します。これらの対策を検討するにあたっては、設備担当者が中心になることが想定されます。
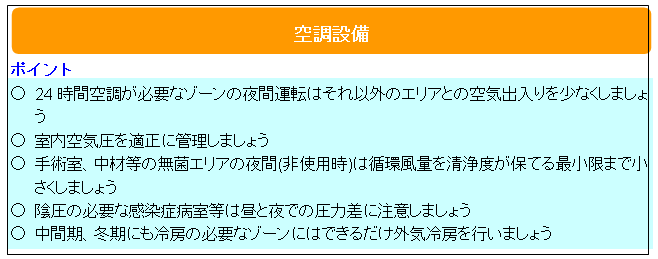
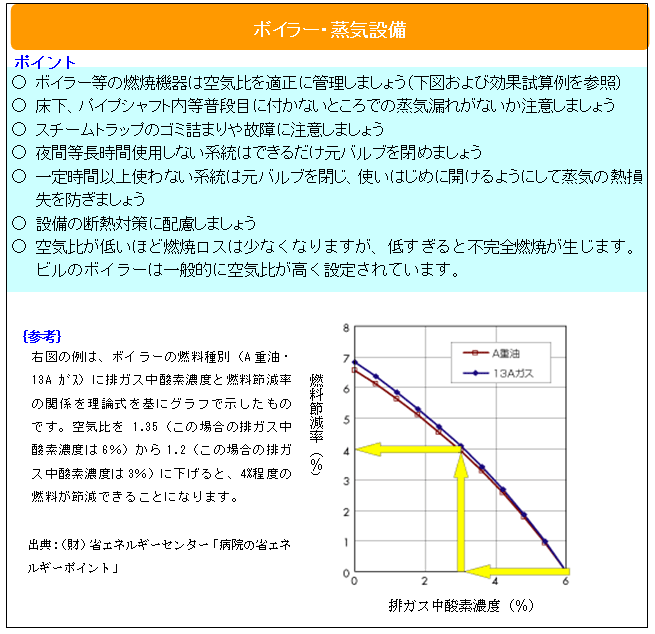
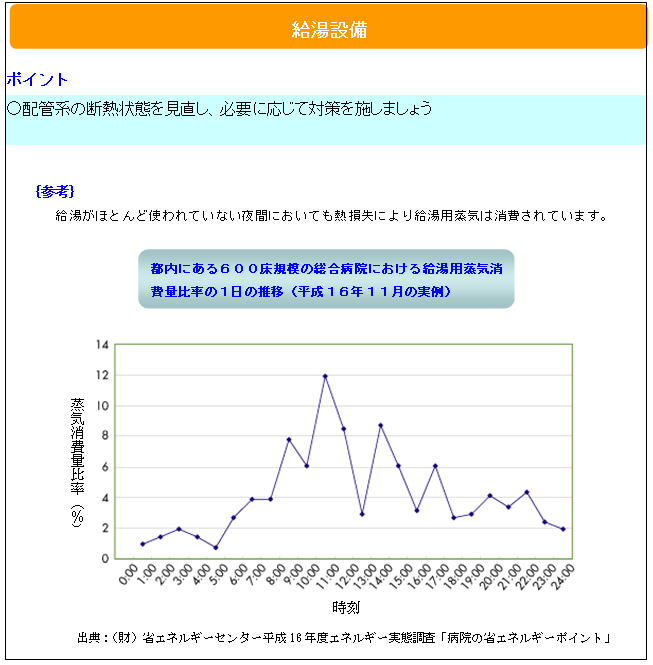
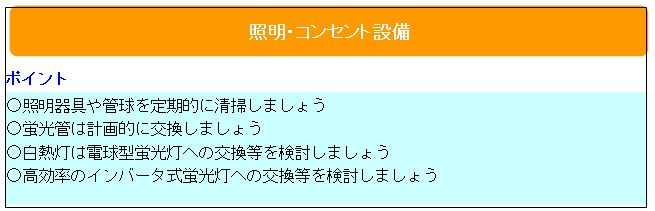
下表に、考えられる省エネ改善手法を参考として示しますので、病院の規模や種別を踏まえ、必要に応じて取組に活用してください。
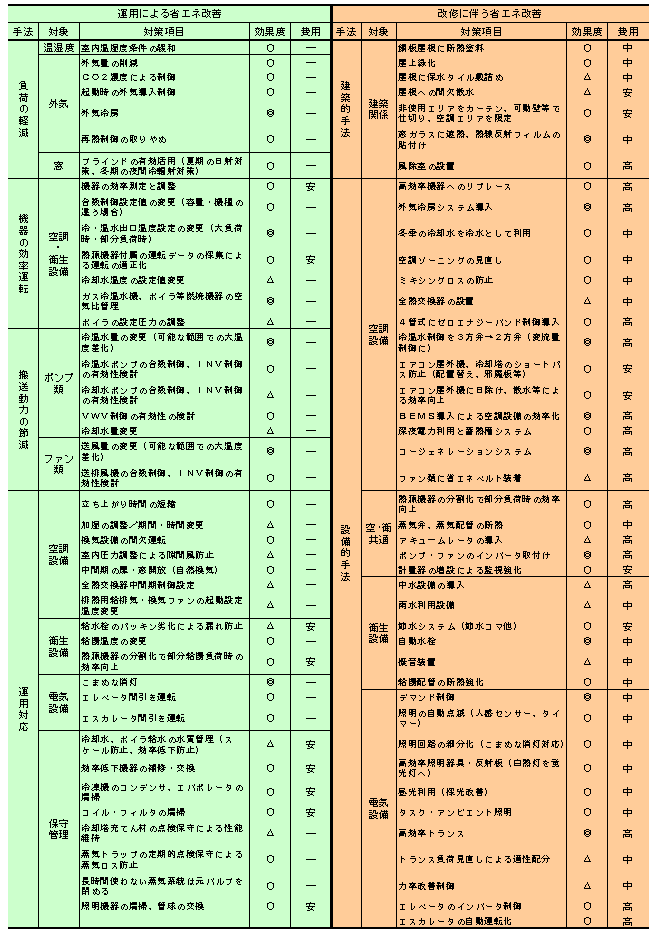
<効果度> ◎:効果大 ○:効果中 △:効果小 <費用> 高:高い 中:中程度 安:安い ―:無し
4.省エネについてもっと知りたい場合には
省エネ対策を実施するにあたっては、そのときどきのエネルギーを取り巻く社会情勢等にも十分注意を払っておく必要があります。
(財)省エネルギーセンターでは、省エネに関する分野別の情報検索や新着情報など情報提供・質問相談コーナーを開設しています。特に業務用ビル分野では、エネルギー実態調査や省エネのポイントを業種別にパンフレットにまとめています。また、運用面における省エネ対策についての、手法やツールが無償で提供されておりますので、詳しくは、ホームページを参照下さい。
各病院においては、これらの活用をはじめとして、幅広く情報等を集めることがよりよい取組につながることにご留意ください。
○情報検索の方法
(1)ホームページの「ビルの省エネ」をクリックする
| http://www.eccj.or.jp/ | |
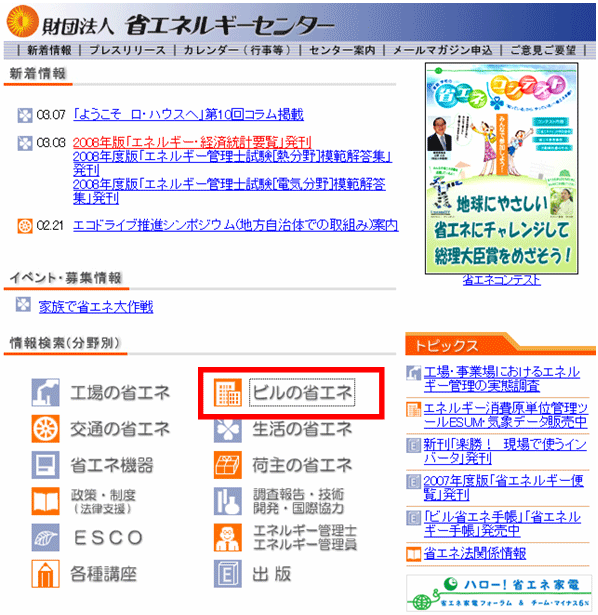
|
|
(2)パンフレットは[1][2][3][4]をクリックする
(3)ツールソフトのダウンロードは[5]をクリックする
| http://www.eccj.or.jp/sub_03.html | ||
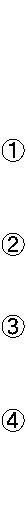 |
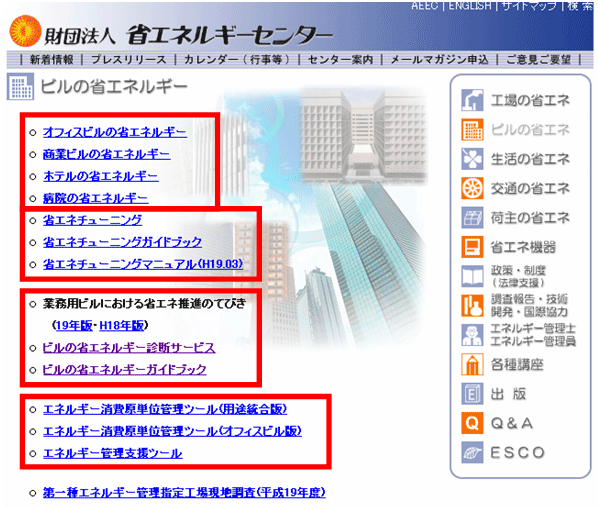 |
|
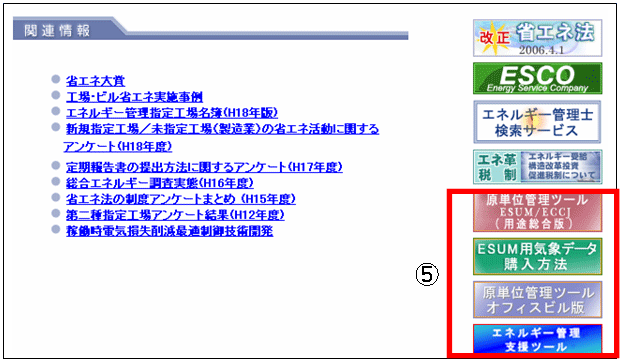 |
||
○省エネ改善提案事例
また、(財)省エネルギーセンターでは、現地調査による省エネルギー診断を行った上で改善提案を行う事業を実施しており、以下のように病院に関する事例がまとめられています。現状の問題点と改善対策および節約金額等の効果なども掲載されていますので、取組の参考としてください。
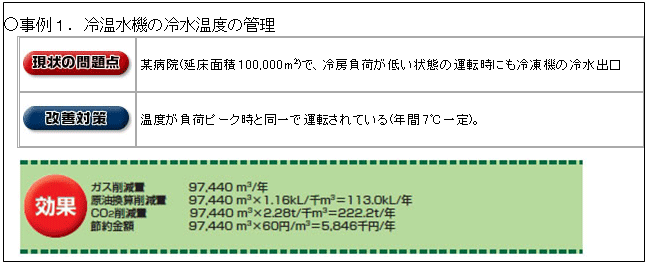
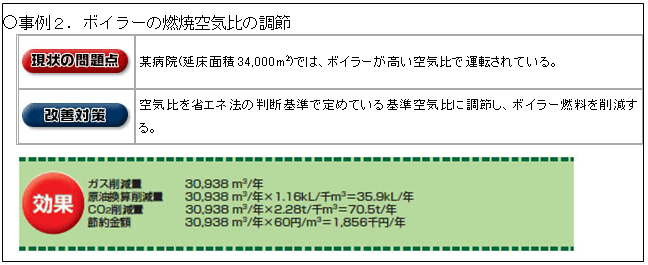
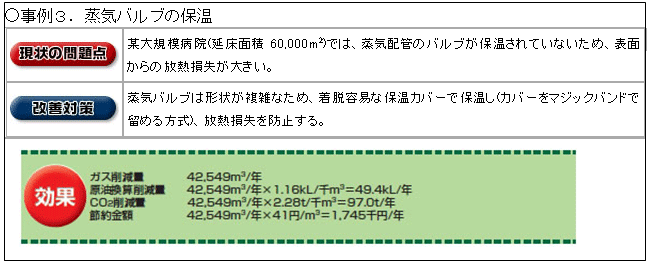
|
出展:(財)省エネルギーセンター「ビルの省エネルギーガイドブック(省エネルギー診断 |
【用語解説】
○MJ メガジュール
熱量を表す国際的な単位のことで、キロカロリーに代わるもの。1メガジュールは約238.9キロカロリー。
○原単位分析
CO2排出量等について、延床面積あたりの数値等を基に、建物全体、年度別、月別等の比較を行い、無駄の原因を分析すること。CO2排出総量でみた場合には、施設の面積等の増加の影響を受けるのに対し、原単位分析では、省エネの取組そのものによる効果をみるのに適していると考えられる。
○ BEMS Building Energy and Environment Management System
施設全体のエネルギー消費の状態を監視しながら、使用の状態に応じて管理することにより、エネルギーの浪費を発見し、省エネルギー改善を図るシステムのこと。
○ 4管式
冷水と温水が別々の配管により供給され、必要に応じて冷水と温水を供給することによって自由な温度設定が可能となる空調設備のこと。
○ゼロエナジーバンド制御
余分な加熱や冷却を避けるため、人が不快に感じない範囲で温度をある一定の幅で設定する空調制御システムのこと。その範囲内では空調の稼働を行わず、範囲を超えた場合に限り冷房または暖房を行う。
○ スチームトラップ
蒸気配管内に発生した凝縮水の速やかな排除、空気などの不凝縮性ガスの排除、蒸気の漏洩防止のための付属品のこと。
○ 空気比
ボイラーや冷温水機等の燃焼装置では、燃焼に必要な理論上の空気量に対し、実際には若干過剰な空気(実空気量)が必要であり、その割合のことをいう。燃焼に際して過剰な空気を送入すると、空気に熱を与える分だけ損失が生じるため、空気比が小さいほど合理的。
空気比=(燃焼に際して実際に必要な空気)÷(燃焼に際して理論上必要な空気)
○ INV制御(インバータ制御)
モーターの消費電力削減のため無段階変速運転を可能とする装置。ファン、ポンプに取り付け、大きな省エネルギー効果を発揮する方式のこと。
○ ミキシングロス
冷風負荷を処理する冷風(または冷水)と暖房負荷を処理する温風(または温水)が混合する時に発生し、エネルギー消費の無駄が生じる状態を言う。
○ デマンド制御
電力消費量のピーク時に一定値(契約電力)を超過しないように、重要度や順位に応じて負荷の遮断・投入を自動的に行う方式のことで、基本料金の抑制に効果がある。
○ タスク・アンビエント照明
タスク(手元)照明により個人の必要とする照度を確保し、アンビエント(雰囲気)照明により、低めの照度で落着いた室内視環境をつくる。
○ アキュームレータ
蒸気を一時的に貯蔵する装置。圧力タンクに蒸気を吹き込み、凝縮させて高温水にして貯蔵する。
○ VWV Valuable Water Volume(可変水量制御)
負荷変動に応じて冷水量または温水量を変える方式で、一定流量方式に比べ、供給水量の無駄を無くすことができるので、ポンプ動力が節減できる。
病院省エネルギー実施要領作成委員会委員名簿
| 委員長 東京大学大学院 工学系研究科 | 教授 | 坂本 雄三 |
| 委 員 岩井整形外科内科病院 | 院長 | 稲波 弘彦 |
| 委 員 特定・特別医療法人協和会 加納総合病院 | 理事長 | 加納 繁照 |
| 委 員 日本医師会総合政策研究機構 | 主任研究員 | 畑仲 卓司 |
| 委 員 (株)エコ・リサーチ | 代表取締役社長 | 河野 好伸 |
| 委 員 厚生労働省 医政局 指導課 | 課長補佐 | 川平 眞善 |
| 厚生労働省 医政局 指導課 | 岩野 健一 | |
| 厚生労働省 医政局 総務課 指導課 | 石毛 雅之 | |
経済産業省 資源エネルギー庁 |
||
| 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー業務室 | 伊東 知彦 | |
| 同 政策課 資源エネルギー調査官 | 茅根 康弘 | |
| 同 政策課 | 鈴木 淳也 | |
| 事務局 (財)省エネルギーセンター | 常務理事 | 石原 明 |
| 同 技術部部長 | ビル調査グループ長 | 本橋 孝久 |
| 同 | 技術部部長 | 山田 富美夫 |
| 同 | 技術部技術専門職 | 阿部 崇彦 |
