厚生労働省職業安定局
雇用開発課就労支援室
雇用失業情勢 (平成19年2月)
◆ 完全失業率(季調) 4.0% (男4.0% 女4.0% )
◆ 完全失業者数 270万人 (男164万人 女106万人)
〔離職理由別〕
非自発的 93万人 自発的 101万人 学卒未就職者 12万人
その他の者 61万人
〔年齢別〕
24歳以下 8.9% 25〜34歳 5.4% 35〜44歳 3.2%
45〜54歳 2.8% 55歳以上 3.3 %
〔地域別〕(平成18年10月〜12月)
北海道 5.4% 東北 4.8% 南関東 3.9%
北関東・甲信 3.3% 北陸 3.1% 東海 2.6%
近畿 4.5% 中国 3.5% 四国 3.4% 九州 4.7%
| ◆ 有効求人倍率 | (季調) | 1.05倍 |
[年齢別]
24歳以下 1.22倍 25〜34歳 1.37倍 35〜44歳 1.18倍
45〜54歳 0.86倍 55歳以上 0.70倍
[地域別]
北海道 0.60倍 東北 0.78倍 南関東 1.15倍
北関東・甲信 1.25倍 北陸 1.23倍 東海 1.57倍
近畿 1.10倍 中国 1.16倍 四国 0.91倍 九州 0.75倍
| ◆ 新規求人数 | 88万人 |
| ◆ 有効求人数 | 228万人 |
| ◆ 新規求職申込件数 | 53万件 |
| ◆ 有効求職者数 | 206万人 |
| ◆ 就職件数 | 16万件 |
失業率と求人倍率の推移
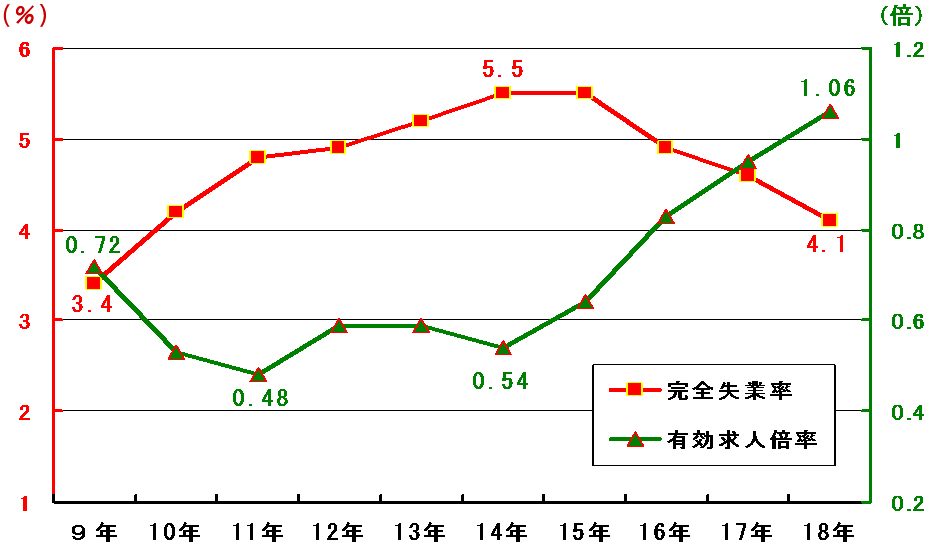
ハローワークの組織と業務
◎ 都道府県労働局 (47局)
◎ ハローワーク (591所):平成18年度
◎ 付属施設
パートバンク ハローワークプラザ
人材銀行 高年齢者職業相談室 学生職業相談室 など
◎ ハローワークの就職支援
○ 求職者の個々の事情に応じたきめ細かな支援
- 職業相談・職業紹介の実施
- 求人自己検索システムを活用した求人情報の提供
- 求職活動支援セミナーの実施
○ 早期再就職専任支援員による支援
特に早期就職意欲の高い求職者に対し、個々人のニーズに応じたきめ細かな就職支援を実施
○ 再チャレンジプランナーによる支援
早期再就職の必要性が高い求職者に対し、再就職に向けた求職活動計画(就職実現プラン)を個々人毎に作成
○ キャリア・コンサルティング
キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを実施
|
 |
福祉事務所とハローワークとの連携による
「生活保護受給者等就労支援事業」の概要
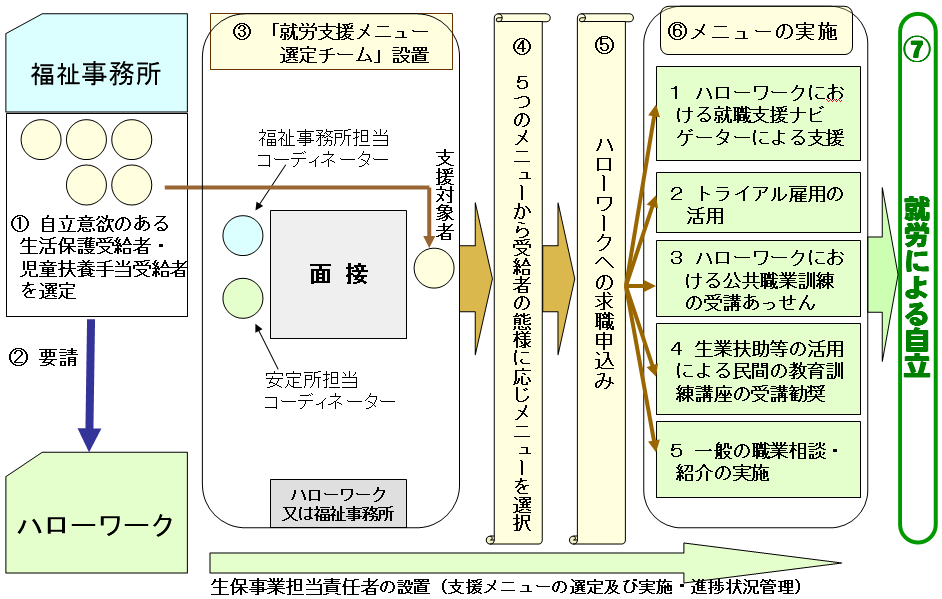
生活保護受給者等就労支援メニュー選定チーム
(目的)
安定所と福祉事務所の担当者による「生活保護受給者等就労支援メニュー選定チーム」が連携して、支援対象者(福祉事務所から安定所に要請があった者)に対する適切な就労支援メニューを選定する
(構成員)
○ 安定所側
- 生活保護受給者等就労支援事業担当責任者、安定所担当コーディネーター
○ 福祉事務所側
- 福祉事務所担当コーディネーター
○ 必要に応じ
- ケースワーカー、母子自立支援員、能力開発支援アドバイザー 等
(担当区域)
安定所担当コーディネーターが担当する一つ又は複数の安定所に係る支援対象者
(配置数)
○ 安定所担当コーディネーター (19年度 175人)
○ 福祉事務所担当コーディネーター (全福祉事務所)
生活保護受給者等就職支援ナビゲーター
(職務)
支援対象者の求職申込みを受け、支援対象者の希望等を聴取した上で、早期就職のための計画を策定し、個々人ごとにきめ細かな就職支援を実施する(3ヶ月間)
(主な支援)
- 支援事業、安定所の活用方法、管内の求人状況、雇用状況の説明
- 求職活動に当たっての心構えの確立や不安の解消
- 個人票に基づく状況の再確認
- 就職に係る希望、ニーズの詳細な把握
- 受講すべきセミナー等の選定
- これまでのキャリアの棚卸し支援
- 履歴書、職務経歴書の作成指導
- 支援対象者のニーズにあった求人の提示と応募する求人の決定支援
- 特定の求人に応募するための面接シュミレーション
- 応募が不調に終わった場合、理由の特定と今後の対応の検討
(配置数)
○ 生活保護受給者等就職支援ナビゲーター (19年度 105人)
生活保護受給者等就労支援事業の実施状況
| 支 援 対象者数 |
支 援 開始者数 |
終了者数 | 就職者数 | |
| 合 計 | 20,236 | 16,917 | 13,362 | 8,675 |
| 生活保護 受 給 者 |
18,893 | 15,803 | 12,609 | 8,038 |
| 児 童 扶 養 手当受給者 |
1,343 | 1,114 | 753 | 637 |
※ 平成17年度は、児童扶養手当受給者は、東京、大阪及び政令指定都市(14)でモデル実施
成長力底上げ戦略(基本構想) 概要
《基本的な姿勢》
1.「働く人全体」の底上げを目指す
経済成長を下支えする基盤 (人材能力、就労機会、中小企業) の向上を図ることにより、働く人全体の所得・生活水準を引き上げつつ、格差の固定化を防止
2.「機会の最大化」により「成長力の底上げ」を図る
意欲のある人や企業が自らの向上に取り組める「機会(チャンス)」を最大限拡大人材の労働市場への参加や生産性の向上を図ることで、他の成長戦略と相まって、経済の活力を維持・向上させ、経済成長を高めていくことを目指す
3.3本の矢
【人材能力戦略】
「職業能力を向上させようとしても、能力形成の機会に恵まれない人」への支援
【就労支援戦略】
「公的扶助(福祉)を受けている人などで、経済的自立(就労)を目指していながら、その機会に恵まれない人」への支援
【中小企業底上げ戦略】
「生産性向上を図るとともに、賃金の底上げをしようとしているが、その機会に恵まれない中小企業等」への支援
【就労支援戦略】
『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』の策定・実施
| ◎ | 「福祉から雇用へ」の基本的考え方を踏まえ、新たに策定する5か年計画に基づき、公的扶助(福祉)を受けている人などについて、セーフティネットを確保しつつ、可能な限り就労による自立・生活の向上を図る |
(1) 『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』 の策定
| [1] | 母子家庭世帯、生活保護世帯、障害者等の就労移行に関する5年後の具体的な目標を設定し、実績を検証しながら計画を推進 |
| [2] | 就労支援方策として、福祉(就労支援) 及び雇用(受入促進)の両面にわたる総合的な取組を展開。19 年度 〜 21 年度を集中戦略期間として施策展開 |
(2) 「工賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げ
| ○ | 授産施設等で働く障害者の工賃水準を引き上げるとともに、一般雇用へ の移行の準備を進めるため、産業界等の協力を得ながら、官民一体となった取組を推進 |
『「福祉から雇用へ」 推進5か年計画』の考え方
〜誰でもどこでも自立に向けた支援が受けられる体制整備〜
| ○ | 福祉を受ける方に対して、可能な限り就労による自立・生活の向上を図る |
| ○ | 緒についたばかりの福祉事務所等とハローワークの連携による「福祉と雇用の連携」施策、地方自治体における自立支援策を加速 |
| ○ | 「福祉から雇用へ」の実効性を高めるため、関係機関の連携を促進するとともに、産業界等の理解・協力を得ながら、『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』 として実施 |
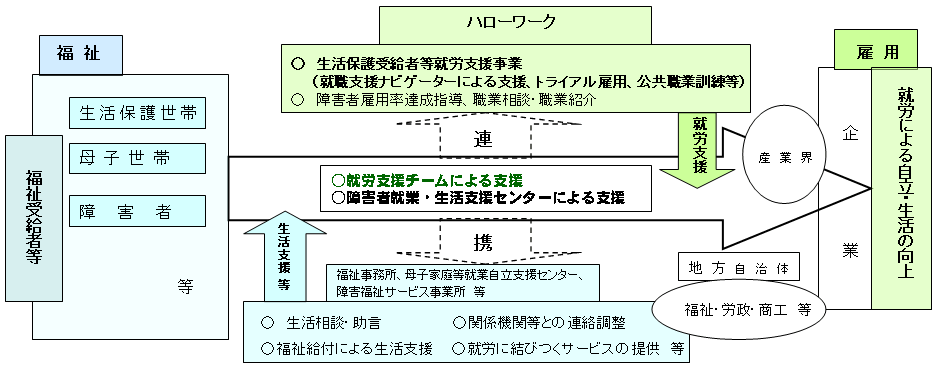
『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』のイメージ
| ○ | 福祉から雇用への移行を推進する「5か年計画」を策定するとともに、具体的な「目標」を定めて取り組む (特に、19〜21年度の3年間に集中的に取組を強化する) |
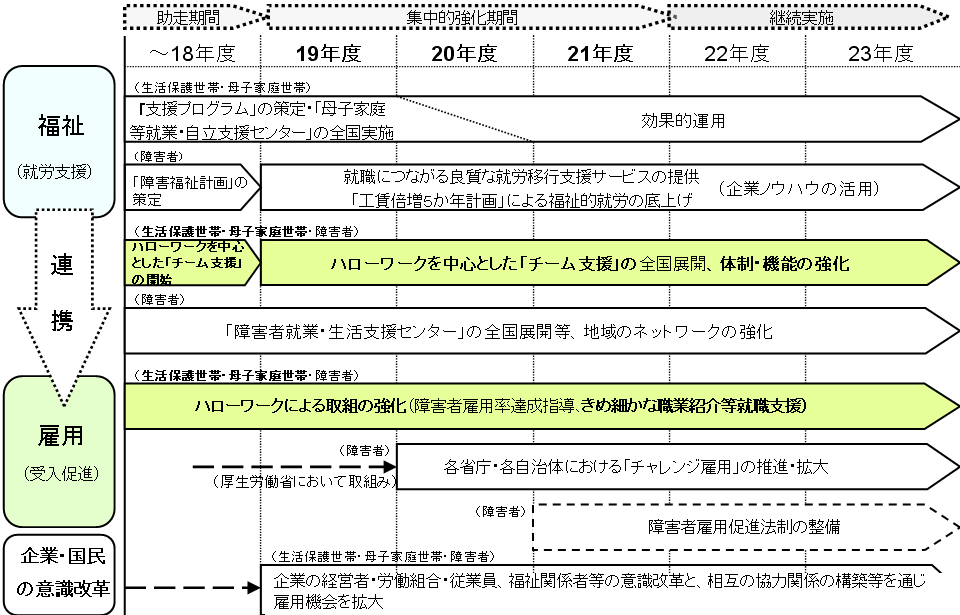
『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』における重点戦略
地域の特性を活かした就労支援体制を全国展開 |
|
ハローワークを中心とした「チーム支援」 |
|
障害者雇用促進法制の整備 |
|
関係者の意識改革 |
|
