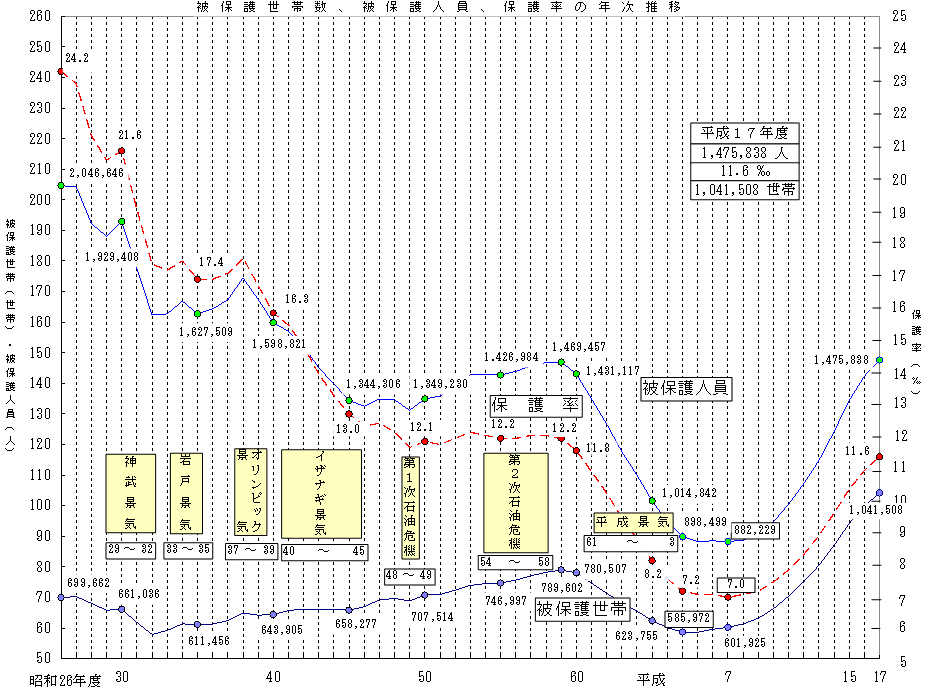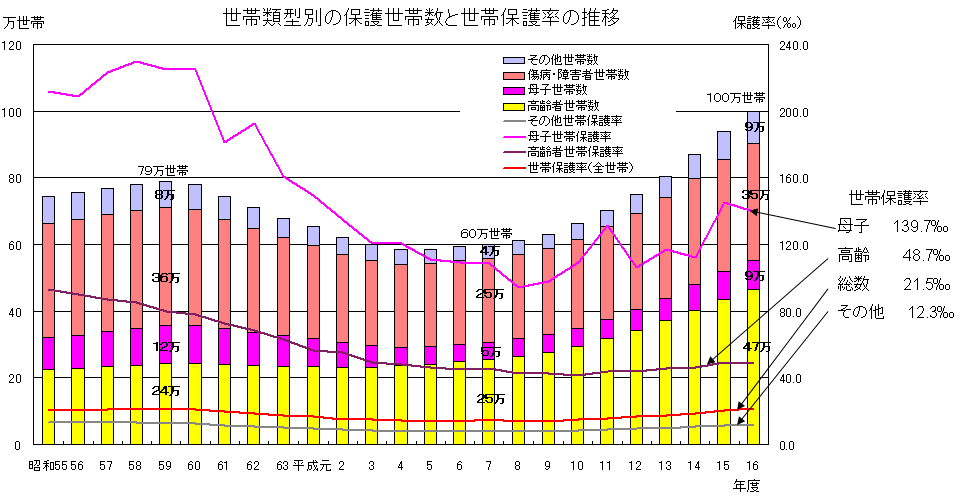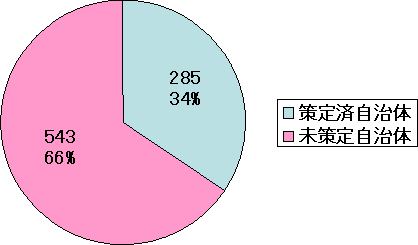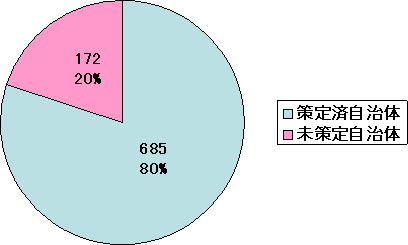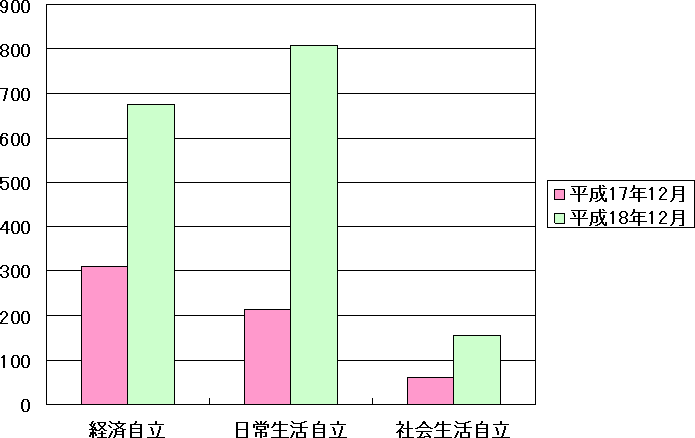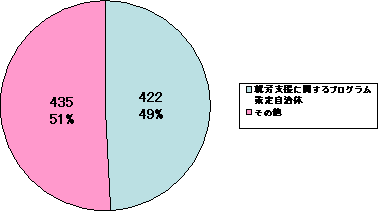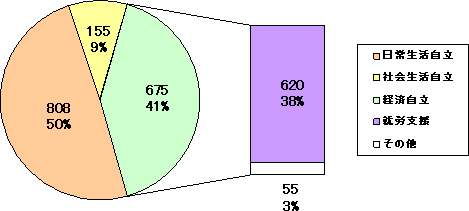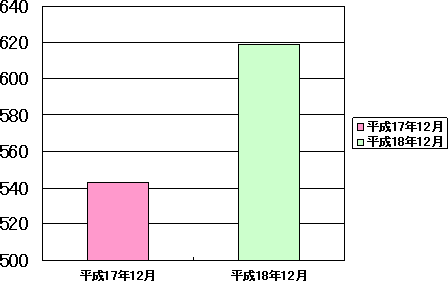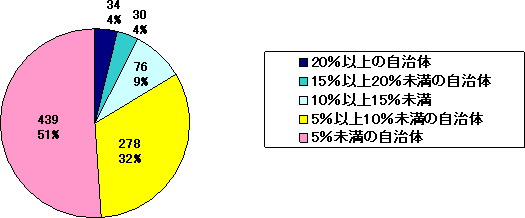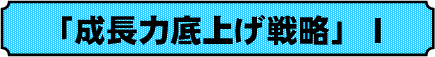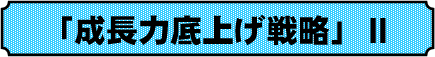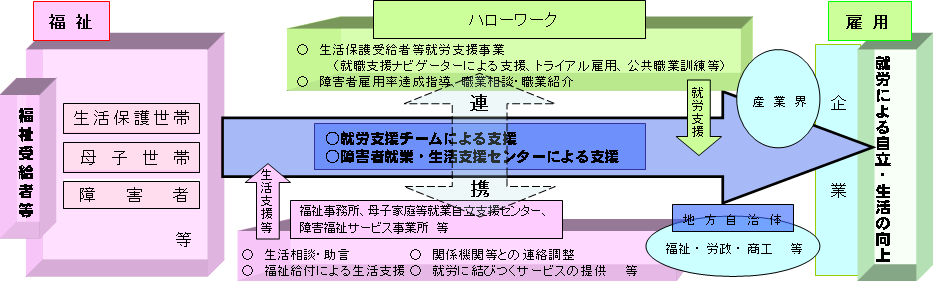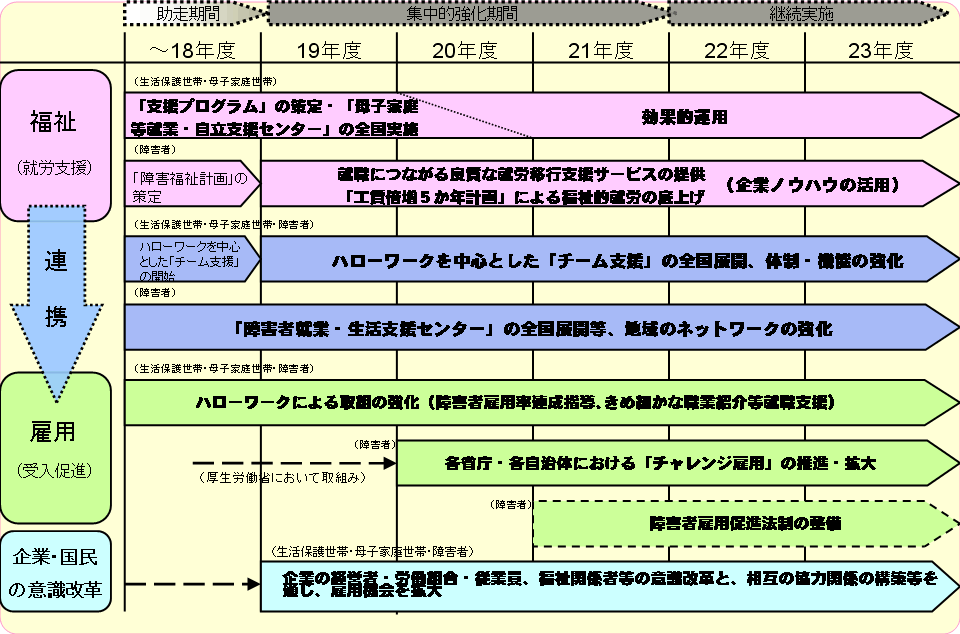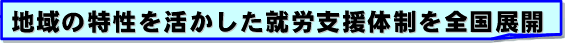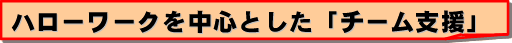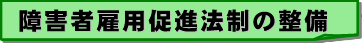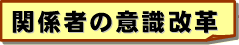生活保護の自立支援
厚生労働省社会・援護局保護課
資料:福祉行政報告例
平成19年度予算に盛り込んだ生活保護の見直し
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」等を踏まえ、生活保護制度の適正な実施を推進する。
(1) 要保護世帯向け長期生活支援資金の創設
一定額以上の不動産を有する要保護高齢者世帯について、死亡時に扶養義務者が不動産を相続することは社会的公平の観点から問題であることから、所有不動産を担保とした貸付制度(要保護世帯向け長期生活支援資金)を創設し、当該制度を利用させることとする。
(2) 公平・自立支援の観点からの母子加算の見直し
母子加算について、自立母子世帯との公平の確保と生活保護を受給する母子世帯の自立を促進する観点から、就労母子世帯等に対して自立支援を目的とした給付を創設(就労の場合・月額1万円、職業訓練等の場合・月額5千円)するとともに、現行の母子加算(15歳以下)を段階的に廃止する。
(3) 自立支援プログラムの着実な推進
17年度より自治体に導入した「自立支援プログラム」の推進により、生活保護受給者の就労や退院を促進する。
自立支援プログラムについて
【 平成19年度の運用方針 】
| ○ |
全自治体で、就労支援に関するプログラムを策定
- 就労支援に関する個別支援プログラムの策定・実施は、生活保護受給者の経済自立に成果が認められる。
|
| ○ |
生活保護受給者等就労支援事業の積極的な活用
- 支援開始者数に対する就職者数の割合が、約50%(平成17年6月から平成18年12月)と、一定の効果が期待できる。
|
| ○ |
稼働能力判定会議の設置
- 就労支援プログラムの策定・実施に伴い、要保護者の稼働能力について、より客観的な判定が必要
- 稼働能力判定会議で、稼働能力の判定、適性職種の検討、就労支援プログラムの選定等を行うことが有効
|
自立支援プログラムの策定状況 I
【 平成18年度の運用方針 】
○ 全自治体で少なくとも1つのプログラムを策定
【 平成17年12月 】 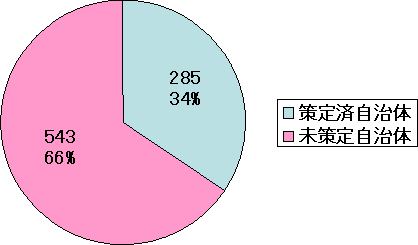 |
【 平成18年12月 】 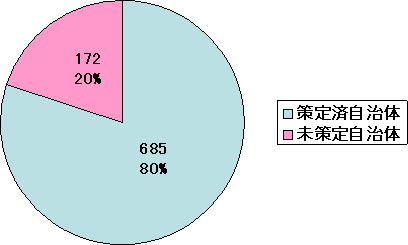 |
| |
平成17年12月 |
平成18年12月 |
| 福祉事務所設置自治体数 |
828 |
100% |
857 |
100% |
| 個別支援プログラム策定済の自治体数 |
285 |
34% |
685 |
80% |
自立支援プログラムの策定状況 II
| |
平成17年12月 |
平成18年12月 |
| 策定済個別支援プログラム数 |
585 |
100% |
1,638 |
100% |
| |
経済自立に関するもの |
311 |
53% |
675 |
41% |
| 日常生活自立に関するもの |
214 |
37% |
808 |
49% |
| 社会生活自立に関するもの |
60 |
10% |
155 |
10% |
自立支援プログラムの策定状況 III
【 平成19年度の運用方針 】
○ 全自治体で就労支援に関するプログラムを策定
【 就労支援に関するプログラム策定状況 】
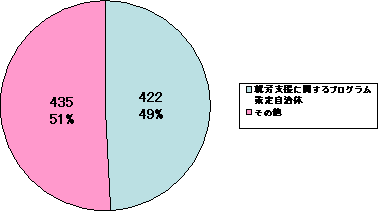 |
| |
平成18年12月 |
| 就労支援に関するプログラム策定済自治体数 |
422 |
49% |
| 就労支援に関するプログラム未策定自治体数 |
435 |
51% |
|
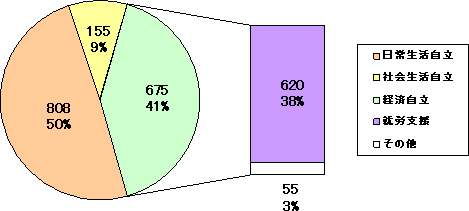 |
| |
平成18年12月 |
| 経済自立に関するプログラム数 |
675 |
41% |
| |
就労支援に関するもの |
620 |
38% |
| その他 |
55 |
3% |
| 日常生活自立に関するプログラム数 |
808 |
49% |
| 社会生活自立に関するプログラム数 |
155 |
9% |
(注)その他は、高校進学プログラム、年金裁定請求プログラム等
|
生活保護受給者等就労支援事業について
【 生活保護受給者等就労支援事業活用自治体 】
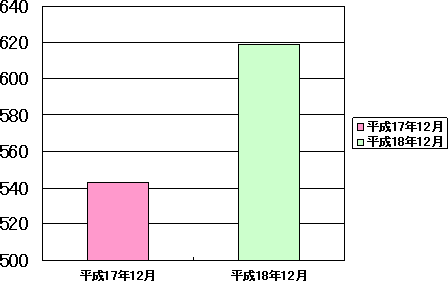 |
| |
平成17年12月 |
平成18年12月 |
| 自治体数 |
822 |
100% |
857 |
100% |
| 事業活用自治体 |
543 |
66% |
619 |
72% |
|
【 生活保護受給者等就労支援事業実施状況 】
| |
支援開始者数 |
支援終了者数 |
支援終了者のうち就職者数 |
支援開始者数に対する
就職者数の割合 |
| 平成17年6月〜平成18年3月 |
7,309 |
4,553 |
3,007 |
41.1% |
| 平成18年4月〜平成19年2月 |
8,494 |
8,056 |
5,031 |
59.2% (注) |
| 累計 |
15,803 |
12,609 |
8,038 |
50.9% |
(注)平成18年度の支援終了者数の中には、平成17年度中に支援開始した者も含む
|
就労支援に関する状況について
| ○ |
就労支援を行うことにより、生活保護を受給している稼働年齢者65万人のうち、6.8%にあたる4.4万人が新たに就職または転職等により増収となっている。 |
【 平成18年4月から12月までに新規就労または転職等により増収した生活保護受給者 】
(人)
| |
生活保護受給者等就労支援事業 |
就労支援プログラム |
プログラム以外 |
合計 (1) |
| 新規就労、増収の人数 |
3,878 |
9,870 |
30,288 |
44,036 |
【 稼働年齢者数 650,350人 】‥‥‥(2)
【 稼働年齢者数に対する新規就労、増収した活保護受給者数の割合((2)/(1)) 6.8% 】
【 稼働年齢者数に対する新規就労、増収の人数の割合からみた自治体数 】
基本的な姿勢
1.「働く人全体」の底上げを目指す
| ー | 戦略は、成長戦略の一環として、経済成長を下支えする基盤(人材能力、就労機会、中小企業)の向上を図り、働く人全体の所得・生活水準を引き上げつつ、格差の固定化を防ぐ。 |
2.「機会の最大化」により成長の底上げを図る
| ー | 単に「結果平等」を目指すような格差是正策とは異なり、意欲のある人や企業が自らの向上に取り組める「機会(チャンス)」を最大限拡大。人材の労働市場への参加や生産性の向上を図ることで、経済成長を高めていくことを目指す。 |
3.「3本の矢」ー「人材投資」を中心に
【人材能力戦略】
『職業能力を向上させようとしても、能力形成の機会に恵まれない人』への支援
【就労支援戦略】
『公的扶助(福祉)を受けている人などで、経済的自立(就労)を目指していながら、その機会に恵まれない人』への支援
【中小企業底上げ戦略】
『生産性向上を図るとともに、賃金の底上げをしようとしているが、その機会に恵まれない中小企業等』への支援
|
2.就労支援戦略
◎『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』の策定・実施
| ー | 「福祉から雇用へ」の基本的考え方を踏まえ、公的扶助(福祉)を受けている人などについて、セーフティネットを確保しつつ、可能な限り就労による自立・生活の向上を図る。このため、『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』を新たに策定し、実施する。 |
(1)『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』の策定
| [1] |
具体的目標の設定
・母子家庭世帯、生活保護世帯、障害者等の就労移行ー5年後の目標を設定 |
| [2] |
推進方策の計画的な実施
・福祉(就労支援)と雇用(受入促進)の両面にわたる総合的な取組を展開。19年度〜21年度を集中戦略期間として施策展開。
<主な施策>
○地域の特性を活かした就労支援体制の全国展開
○ハローワークを中心とした「チーム支援」
○障害者雇用促進法制の整備
○関係者の意識改革 |
(2)「工賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げ
| [1] |
「工賃倍増5か年計画」を全国で策定・推進 |
| [2] |
企業的な経営手法の活用 |
| [3] |
工賃水準の確保につながる企業からの発注に対する措置 |
|
『「福祉から雇用へ」 推進5か年計画』の考え方
〜誰でもどこでも自立に向けた支援が受けられる体制整備〜
| ○ |
福祉を受ける方に対して、可能な限り就労による自立・生活の向上を図る。(※)
− 国民が社会的、経済的、精神的な自立を図る観点から、自ら、働いて生活を支え、健康を維持する、といった
「自助」を基本に、それを「共助」、「公助」が支える福祉社会を構築
※ 自立の支援や生活の向上が目的−自助努力のみでは生活に困窮する方に対しては福祉により適確に対応 |
| ○ |
緒についたばかりの福祉事務所等とハローワークの連携による「福祉と雇用の連携」施策、地方自治体における自立支援策を加速
[ 例 福祉事務所において、自立・就労意欲のある生活保護や児童扶養手当の受給者を選定し、ハローワークにおいて、就労支援を実施 ] |
| ○ |
「福祉から雇用へ」の実効性を高めるため、関係機関の連携を促進するとともに、産業界等の理解・協力を得ながら(※)、『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』として実施
※ 産業界・企業の理解、協力
| ・ | 職業紹介、職業訓練等を受けた後における雇用の機会の確保 |
| ・ | 母子世帯等の実情を踏まえた多様な働き方や、障害者雇用率達成の必要性への理解などの意識改革 |
| ・ | 企業の生産性の向上などにより、安定した雇用機会の創出や、賃金の引上げを図ること |
| 福祉施設関係者、特別支援学校関係者等の意識改革も必要 |
|
|
『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』のイメージ
| ○ |
福祉から雇用への移行を推進する「5か年計画」を策定するとともに、具体的な「目標」を定めて取り組む。(特に、19〜21年度の3年間に集中的に取組を強化する。) |
|
『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』における重点戦略
| ○ |
「障害者就業・生活支援センター」を全障害保健福祉圏域に設置(約400カ所) |
| ○ |
各省庁・各自治体における障害者に対する「チャレンジ雇用」の推進・拡大 |
| ○ |
障害者に対する「就労移行支援事業」を全国展開するとともに、全都道府県において「工賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げを推進 |
| ○ |
平成19年度までに「生活保護の就労支援プログラム(※)」を全自治体で策定
(※)意欲の向上や職業意識の啓発、技能修得、就職支援等、段階的・計画的な支援を行うプログラム |
| ○ |
母子家庭等就業・自立支援センターやマザーズハローワークなどの子育て女性重点支援拠点を全国展開 |
|
| ○ |
ハローワークを中心に福祉関係者等と連携した「就労支援チーム(※)」の体制・機能強化
(※)ハローワークの就職支援担当と福祉事務所、福祉施設等関係機関により編成されるチーム |
| ○ |
ハローワークにおける「就労支援アクションプラン」の推進により、支援対象者(生活保護・母子世帯)の就職率を60%に引上げ 「就職活動プランの策定」、「就労意欲向上プログラム」 など |
|
| ○ |
短時間労働・派遣労働を活用した雇用促進、中小企業における雇用促進等を図るための障害者雇用促進法制の整備 |
|
| ○ |
関係者の意識改革を通じた雇用機会の拡大
企業の経営者・労働組合・従業員、福祉関係者等の意識改革と、相互の協力関係の構築等を通じ、雇用機会を拡大 |
|
○ 母子世帯の自立支援プログラムの事例(釧路市)
| 釧路市では、平成16年度から、就労支援員を配置し、就労支援を実施するとともに、ワーキンググループを設置し母子世帯に対する自立支援プログラムを策定し、平成17年度から、自立支援員を配置して、母子世帯に対する自立支援プログラムを実施。 |
| ○ |
ワーキンググループの設置
学識経験者(地元の大学)、民間福祉事業者、市職員で構成したワーキンググループを設置し、母子世帯への自立支援策を検討、策定 |
|
| ○ |
生活型支援 ・・・ 自立支援員1名を配置し、以下の事業を実施
| (1) |
社会貢献的就業体験研修事業(平成17年7月〜18年1月に15名参加)
介護事業所に委託し、支援対象者がホームヘルパーに同行し、派遣先の高齢者の話し相手をするなどの就業体験を実施 |
| (2) |
自立支援教室(平成17年7月〜18年1月に22名参加)
NPO法人に委託し、精神障害者小規模作業所スタッフの手伝いや親子料理教室、就職準備活動講習会を実施 |
| (3) |
資格講座受講支援事業(平成17年7月〜18年1月に13名参加)
職業訓練機関と連携し、母子OA講座を実施 |
|
| ○ |
就労型支援
| (1) |
インターシップ事業(平成17年7月〜18年1月に2名参加)
介護福祉施設に委託し、就労を体験し、就労への自信を形成するため、施設実習を実施 |
| (2) |
就労支援員と自立支援員が連携し、母子世帯に対する就労支援を実施(平成17年7月〜18年1月に15名参加) |
|
|
| |
支援対象者数 |
参加者数 |
就職者数 |
保護廃止世帯数 |
就職していない求職中
の者・資格所得者の数 |
| 生活型支援プログラム |
56 |
50 |
10 |
0 |
11 |
| 就労型支援プログラム |
30 |
26 |
15 |
0 |
8 |
○ 日常生活の自立支援プログラムの事例(新宿区)
| 新宿区では、平成17年度から、就労支援員を配置し就労支援を実施する他、NPO法人に委託し、生活保護受給者の基本的な生活習慣を確立するための支援も実施。 |
| |
就労支援員 |
支援対象者数 |
就労開始者数 |
保護廃止世帯数 |
収入増加世帯数 |
| 平成17年度 |
1 |
38 |
21 |
2 |
19 |
| ○ |
生活保護受給者の日常生活習慣を確立し、就労意欲の向上、地域社会への適応を図ることを目的として、NPO法人に委託し、健康保持、規則正しい生活、社会生活に関する事業を実施。 |
| ○ |
具体的には、社会福祉士と1対1の面接を行った上で、新宿生活さぽーとセンターで実施する正しい食習慣の確立、居宅の清掃、パソコン教室、公共施設の清掃等の体験、自己紹介の方法や計画的なお金の使い方を学ぶ等の11の講座を実施(平成17年9月〜18年3月で延べ998人が参加)。
|
| ○ |
事業効果として次のような事例が認められる。
| (事例) |
ゴミ収集癖があり、異臭を漂わせた汚れた衣服で、ゴミ袋を持ち歩いていた高齢者が、殆どの講座に参加したことにより、身なりが整い、ゴミ袋を持たなくなり、部屋のゴミも増えなくなってきた。 |
|
|
| ○ |
生活保護受給者の就学児童を対象に、基本的生活習慣を確立し学力を向上させることを目的として、NPO法人に委託し、教員免許又は臨床心理士資格の相談員が家庭訪問し、規則正しい生活や社会生活に関することを助言。 |
| ○ |
また、新宿生活さぽーとセンターの講座に参加(平成18年2月〜3月の支援対象者数は8人) |
| ○ |
福祉事務所職員と相談員、学校関係者、保健師、民生委員等によるケースカンファレンスを毎月実施。 |
| ○ |
事業効果として次のような事例が認められる。
| (事例) |
父親の死亡後、情緒不安定で不登校となった母子世帯の中学生が、相談員の家庭訪問による面接、助言、新宿生活さぽーとセンターの講座に参加することにより、情緒が安定してきて、学校へも登校し始めた。 |
|
|
「生活保護行政を適正に運営するための手引」のポイント
| 生活保護行政の適正運営の観点から、地方自治体における取組事例も参考としつつ、業務の流れに沿って関連事項を整理した手引 |
| ○ |
届出義務の遵守 |
| ○ |
収入申告書等の徴取 |
| ○ |
関係先調査の実施
| ・ |
金融機関等に対する資産の調査に関する個人情報保護法との関係や留意事項を明記 |
|
| ○ |
暴力団員に対する生活保護適用の考え方
| ・ |
暴力団員に対しては保護を適用しないこと |
| ・ |
暴力団員該当性の確認等に関する警察との連携要領 |
|
| ○ |
年金担保貸付利用者への対応
| ・ |
生活保護受給中の者には年金担保貸付を行わない |
| ・ |
過去に年金担保貸付を受け、それが原因で生活保護を受給した者が再度貸付を受けた場合は生活保護を適用しない |
|
|
|
|
| ○ |
法第27条に基づく指導指示と保護の変更・停止・廃止 |
| ○ |
稼働能力のある者に対する指導指示 |
| ○ |
履行期限を定めた指導指示
| ・ |
指導指示に履行期限を付し、期限までに履行されない場合には保護の廃止等を行う方法を明記 |
|
|
| ○ |
収入未申告が疑われる場合の対応 |
| ○ |
ケース診断会議等の開催による対応内容の判断 |
|
| ○ |
費用返還・費用徴収処分の適用の判断 |
| ○ |
費用徴収の方法 |
| ○ |
不正受給事案の告訴等の手順
|
|
|
|