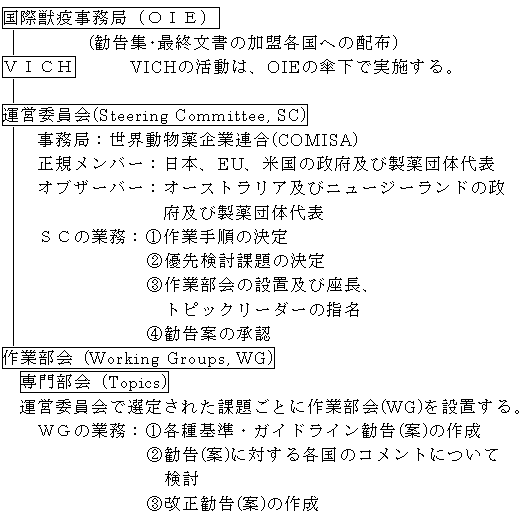戻る
VICHガイドラインの概要について
| 1 |
残留動物用医薬品の基準設定に当たっては、薬事・食品衛生審議会において、動物を用いた急性毒性試験、慢性毒性試験、催奇形性試験、発がん性の試験や細胞などを用いた変異原性試験、微生物に対する影響の試験等、様々な試験データを用いて評価を行っており、必要とされる資料については、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて厚生労働省において定められている。
|
| 2 |
しかし、これらの資料については、国により異なるものがあることから、日本、EU及び米国の3極において、必要な試験の実施方法に関する基準・ガイドラインの調和を図るための国際協力(VICH)が平成8年4月より行われている。
|
| 3 |
VICHの概要は参考1に示すとおりであるが、現在7つの作業部会(WG)が設置され各種のガイドライン案(安全性に関するガイドライン;参考2)について検討が進められてきた。各ガイドライン案については、VICHで合意されると各極でガイドラインとして制定することとなっており、厚生労働省としても「畜水産食品中の残留動物用医薬品等の安全性評価に関する指針(平成7年7月11日策定、平成11年8月31日最終改訂)」(参考3)を見直すこととしている。
|
(参考1)
VICHの概要
| 1. |
VICHとは
VICHの正式名称はInternational Cooperation on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products (動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力会議)。国際獣疫事務局(OIE)の傘下で活動し、日本、欧州及び米国の規制当局及び動物用医薬品業界の代表者を主メンバーとして、動物用医薬品の承認申請資料作成に必要な試験の基準の調和を推進するための国際協力会議(平成8年4月に発足)である。
|
| 2. | 運営方法
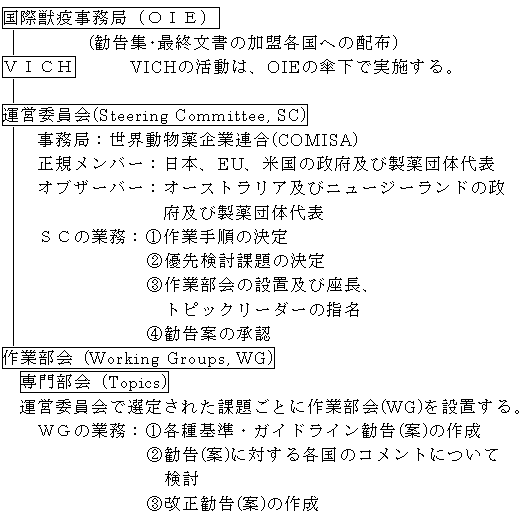
|
(参考2)
VICH安全性に関するガイドラインの進捗状況
(2003.5現在)
| ガイドライン(GL)No、トピック名 |
ステップ |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7・8 |
| トピック決定作業開始 |
WGで案を検討 |
案をSCに提示 |
各極で案を協議 |
WGで改正案作成 |
改正案をSCに提示 |
最終勧告案配布・各極で施行 |
| GL22 繁殖毒性試験ガイドライン |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| GL23 遺伝毒性試験ガイドライン |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| GL28 発癌試験ガイドライン |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| GL31 反復毒性(90日)試験ガイドライン |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| GL32 発達毒性試験ガイドライン |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| GL33 試験の一般的アプローチガイドライン |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| GL36 微生物学的ADI設定の一般的アプローチガイドライン |
● |
● |
● |
○意 |
|
|
|
| GL37 反復投与(慢性)毒性試験ガイドライン |
● |
● |
● |
○意 |
|
|
|
●:討議終了、○意:パブリック・コメント(意見聴取)
(参考3)
畜水産食品中の残留動物用医薬品等の安全性評価に関する指針
本指針は、畜水産食品中に残留する動物用医薬品等(筋肉、乳等の生産物が食用に供される家畜、家禽、魚介類、みつばち等に対して疾病の治療、予防若しくは診断又は生理機能若しくは生理状態を変化させる目的で使用される抗生物質、合成抗菌剤、駆虫剤、ホルモン剤等の物質をいう。以下同じ。)の安全性評価に資することのできる適切な情報及び評価方法の概要を示したものである。
なお、本来、すべての物質について一律の情報及び評価方法を求めていくことは合理的ではなく、また、今後とも科学技術の進歩に応じ新しい試験・評価方法の開発が行われることも考えられるので、得られた所見が安全性評価に資するものである限り、必ずしもここに示した内容に固守することを示すものではない。
I 安全性に関する情報及び評価方法
A.一般事項
1.被験物質
被験物質は通常親化合物とするが、食品中に残留する代謝物及び結合性残留物を摂取することにより毒性学的な問題が懸念される場合には、必要に応じこれら物質のB〜Hの毒性に関する情報が必要となる。
2.必要な情報
単回投与毒性、3か月間の反復投与毒性、3か月を超える反復投与毒性(通常12か月以上投与を行うもの)、生殖毒性、催奇形性、遺伝毒性、代謝等に関する情報に基づいて判断することとなるが(注1)、これらの情報及び被験物質の構造等から当該物質にがん原性が疑われる場合には、がん原性に関する情報等が必要となる。
なお、被検物質の動物用医薬品等としての使用経験が長いと判断される場合には、包括的検討などを含む評価報告書が必要となる(注2)。その報告書に基づき、構造活性相関、遺伝毒性等に関する情報を加えて判断することとなるが、当該物質に催奇形性等の生殖系への影響が認められる場合には、その影響を評価する情報等が必要となる。
これらの情報についてはADI(1日許容摂取量)を設定するためのNOEL(最大無作用量)が求められるものでなければならない。
3.試験系
種及び系統については、寿命、各種自然発生疾患の発生頻度、既知の物質に対する感受性等バックグラウンドデータが明らかなものが選択されていることとする。
同一検体について単回投与毒性試験、反復投与毒性試験及びがん原性試験が実施されている場合には、同一の種及び系統が選択されていることが望ましい。
4.試験実施施設
試験データの質と信頼性を確保するため、試験実施施設は我が国の医薬品、動物用医薬品等の安全性試験に係るGLP(Good Laboratory Practice)又はOECD、FDA等のGLPに適合した試験施設で実施されていることが望ましい。
5.その他
本指針は安全性評価等に必要な情報の原則を定めているが、本指針に規定しているもののほか、「医薬品毒性試験法ガイドライン」等を参考とすることができる。
B.一般毒性
1.単回投与毒性
被験物質の1回経口投与試験により、おおよその致死量が求められているとともに、被験物質の生体への機能的及び形態学的な影響が評価されていなければならない。また、評価にあたっては動物種間の感受性の差、標的器官等が考慮されていることが望ましい。
試験系はラットを含むほ乳動物2種の雌雄とする。
2.反復投与毒性
3か月反復経口投与毒性試験及びこれを超える期間実施された反復経口投与毒性試験により、被験物質の経時的な質的、量的毒性発現が評価されているとともに、生体への機能的及び形態学的影響に係る用量依存性が評価されていなければならない。
また、3か月間反復投与毒性試験においては、被験物質の標的器官、組織への蓄積性等に関する基礎的な知見及び3か月を超える反復投与毒性試験における適切な用量設定を行うための知見が得られていることが必要である。
試験系は2種以上のほ乳動物とし、少なくとも1種はげっ歯類、1種はウサギ以外の非げっ歯類を用いて、雌雄同数で実施されたものであることとする。
被験物質の投与は原則として毎日実施されていることとし、混餌投与、飲水投与いずれであっても差し支えない(注3)が、投与方法は明確にされていなければならない。
少なくとも3段階の投与量が設定されているとともに、陰性対照群がおかれていることが必要である。
高用量群の投与量は毒性影響が明らかに観察される量、低用量群の投与量はなんら影響が観察されない量とし、かつ、用量反応関係がみられるように各用量段階を設定する。
また、混餌投与の場合は、通常、飼料添加濃度5%(w/w)を超える投与量で実施されている必要がない。なお、強制経口投与の場合は、通常、技術的に投与できる最大量又は1,000mg/kgでなんら毒性影響が認められない場合は、それ以上の投与量で実施されている必要はない。
C.生殖毒性及び催奇形性
原則として、二世代の生殖毒性試験及び2種の動物種についての催奇形性試験が実施されていることとする。
種及び系統については、自然発生奇形の発生頻度、既知の物質に対する感受性等バックグラウンド・データが明らかなものであって、繁殖成績が安定しているものが選択されていることとする。
1.生殖毒性
被験物質の生殖機能への影響及び受精から離乳までの個体発生への影響が評価されていなければならない。
試験系は少なくとも1種類の雌雄同数の動物(通常げっ歯類)を用いて実施されたものであること。
被験物質の投与は、雌雄の第一世代(P)の離乳後間もない時期から開始され、第二世代(F2)の離乳まで継続されているものとし、混餌投与、飲水投与のいずれであっても差し支えない(注3)が、投与方法は明確にされていなければならない。
少なくとも3段階の投与量が設定されているとともに、陰性対照群が置かれていることが必要である。
高用量群の投与量は親動物又は児動物に何らかの毒性影響が観察される量、低用量群の投与量は親動物及び児動物のいずれにも影響を及ぼさない量とし、かつ、用量反応関係がみられるように各用量段階を設定する。
また、混餌投与の場合は、栄養障害が起こらないよう十分配慮し、通常、飼料添加濃度5%(w/w)を超える投与量で実施されている必要はない。なお、強制経口投与の場合は、通常、技術的に投与できる最大量又は1,000mg/kgでなんら毒性影響が認められない場合は、それ以上の投与量で実施されている必要はない。
試験結果の報告には、少なくとも次の項目が含まれていなければならない。(注4)
| ○ | 親動物について
一般状態(体重、摂餌・摂水量、生死、外観、興奮、けいれん、鎮静、歩行異常等)、生殖能力(交尾率、妊娠率、出産率、流産・早産、分娩遅延等) |
| ○ | 児動物について
出産児の数、生死、性比、体重、奇形又は機能異常の有無、離乳までの成長・発達 |
2.催奇形性
被検物質の胎児に対する形態異常や機能障害の誘発性が評価されていなければならない。
催奇形性に係る情報は、被検物質の構造が胚・胎児毒性を有する既知の物質と類似している場合、又は1に掲げる生殖毒性試験において胚又は胎児に対する影響が疑われる場合に特に重要である。
試験系は通常げっ歯類及びウサギの2種類とする。
被験物質の投与は妊娠中の試験動物の胎児の器官形成期(マウス:6〜15日、ラット:7〜17日、ウサギ:6〜18日、ハムスター:6〜14日)に強制経口投与により実施されていることとする(注5)。
少なくとも3段階の投与量が設定されているとともに、陰性対照群が置かれていることが必要である(注6)。
高用量群の投与量は母体に体重増加抑制などの毒性影響が観察される量、低用量群の投与量は母体及び胎児のいずれにも影響が生じない量が投与されているものとし、かつ、用量反応関係がみられるように各用量段階を設定する。
また、通常、技術的に投与できる最大量又は1,000mg/kgでなんら毒性影響が認められない場合は、それ以上の投与量で実施されている必要はない。
験結果の報告には、少なくとも次の項目が含まれていなければならない。
| ○ |
母体の一般状態(体重、摂餌・摂水量、生死、外観、興奮、けいれん、鎮静、歩行異常等)、黄体数、着床数、死亡・吸収胚数、生存胎児の数及び体重並びに外表、骨格及び内臓の奇形及び変異 |
D.遺伝毒性
被験物質がDNA等に影響を与え、塩基対置換型またはフレームシフト型などの遺伝子突然変異、あるいは染色体の構造または数の異常を起こす性質があるか否かに関する適切な情報が必要である。
遺伝毒性の評価については、単独の試験のみでは困難であり、適切な試験を複数組み合わせる必要がある。少なくとも遺伝子突然変異の誘発性については細菌を用いる遺伝子突然変異試験、染色体異常の誘発性については、ほ乳類の培養細胞を用いる染色体異常試験、また、げっ歯類を用いる小核試験が必要である。
.なお、上記の試験結果を補足する必要がある場合には、さらに適切な遺伝毒性試験が必要となる。(注7)
E.がん原性
がん原性試験では、試験動物の生涯の大半にわたって被験物質による発かんの可能性を評価されていることが必要である。
試験系は2種以上の動物種とし、雌雄同数の動物を用いる(注8)。
投与期間はラットでは24か月以上30か月以内、マウス及びハムスターでは18か月以上24か月以内とする。
被験物質の投与は試験動物の生涯にわたる期間、原則として毎日実施されていることとし、混餌投与又は飲水投与いずれであっても差し支えないが(注3)、投与方法は明確にされていなければならない。
少なくとも3段階の投与量が設定されているとともに、陰性対照群が置かれていることが必要である。
高用量群の投与量は腫瘍以外の毒性による死亡例がなく、かつ一般状態に著しい変化を示さないような毒性影響(例;軽度の体重増加抑制)が認められる量、低用量群の投与量は試験動物の通常の成長及び寿命に影響しない量とし、かつ、用量反応関係がみられるように各用量段階を設定する。
また、混餌投与の場合は、栄養障害が起こらないよう十分配慮し、通常、飼料添加濃度5%(w/w)を超える投与量で実施されている必要はない。なお、強制経口投与の場合は、通常、技術的に投与できる最大量又は1,000mg/kgでなんら毒性影響が認められない場合は、それ以上の投与量で実施されている必要はない。
試験結果については、統計学的に適切に処理されている必要があるが、がん原性の評価の手法は特に指定しない。
被験物質にがん原性があると判定するための試験結果の評価は次により行う。
| ○ | 陰性対照群に比較して腫瘍発生頻度が高い場合 |
| ○ | 陰性対照群と比較して早期に腫瘍が発現する場合 |
| ○ | 陰性対照群に見られない腫瘍が見られる場合 |
なお、試験の結果、陽性の結果が得られた場合、発がんのメカニズムの解明が行われていることが望ましい。
F.常在細菌叢への影響(薬剤耐性、菌交代症等)
食品中に残留する抗生物質及び合成抗菌剤の摂取は、ヒト腸管内の常在細菌叢に変動をきたすこともあり、その際には自然耐性又は獲得耐性をもつ微生物の増殖を促す。この場合人の健康に対する影響の発生が懸念されるが、常在細菌叢中の特定の耐性菌の比率の変動をもって直ちに人の健康に対する影響を推し図れるものではない。
しかしながら、常在細菌叢の安定的な構成が感染防御機構としての重要な役割を果たしていることから、ヒトの常在細菌叢への影響に対する評価を十分に考慮した試験成績が必要である。
なお、ヒトの腸管内での常在細菌叢への評価にあたっては、常在細菌叢の構成を十分踏まえた上で、細菌数及び感受性への変動等の複数のパラメータを用いることにより細菌叢及び細菌叢の代表的な菌種に対する影響が考慮されていなければならない。その他、病原性を有する菌種についても考慮されていることが望ましい。
試験系については、現在のところ、ヒト被験者を用いた試験の他、ヒトの常在細菌叢を移植した実験動物の試験、当該物質に対して感受性の高いヒトの常在細菌叢中のいくつかの代表的菌種について実施された最小発育阻止濃度試験(注9)がある。なお、in vitroの試験モデルについては、将来十分に発展する可能性のある方法であり、今後、さらに検討を要すべき方法である。
G.アレルギー
一般に医薬品によるアレルギー感作は、アレルギーを起こす可能性がある比較的多量の薬剤に暴落された後に起こる。例えば、ヒトの治療薬としての使用や職業上の暴露によって感作された後、アレルゲンとなる医薬品が少量残留する食品を摂取した際にアレルギー反応が発現する場合等が想定される。
畜水産食品中に残留するアレルゲンとなる医薬品(注10)は、アレルゲンとしてごく少量の場合にはヒトに対してアレルギー感作を起こす可能性は極めて少ないが、アレルギーを起こすこと、またはその可能性があることを示す情報がある場合には安全性評価に際して十分考虜することとする。
残留動物用医薬品等のアレルギー発現に関する情報については、過去における当該医薬品または類似医薬品のアレルギー症に関する情報を検索することとなるが、動物用医薬品等の残留とアレルギー反応との因果関係が推測できる次の事項を踏まえた情報が必要である。
| ○ | アレルギー反応の原因となった食品に動物用医薬品等が残留していること。 |
| ○ | り患者は動物用医薬品等が残留していない同じ食品ではアレルギー反応を起こさないこと。 |
| ○ | 当核反応に関する免疫学的機構が確認されていること。 |
| ○ | 食品中の薬物残留の原因が動物における動物用医薬品等の使用によるものであること。 |
H.結合型残留物
結合型残留物とは、親化合物及び代謝物が生体内の高分子と共有結合することにより通常の抽出条件では抽出されてこない残留物の総称である。これらの物質には、理論上生体内分子の一部として取り込まれる被検物質由来の物質(例;アミノ酸、脂肪酸、糖、核酸)は含まれない。
一般に放射性同位元素で標識された物質を用いた残留試験により、組織への総残留量が決定されるが、可食組織中の総残留量に占める結合型残留物の割合(注11)が比較的大きい場合には、適切な方法(例えば、Gallo-Torres method(注12))を用いることにより、これら物質の生体内吸収率が確認されていることが必要である。なお、この場合、生体内運命に関する知見との対応を考えて適切な動物種による知見が必要である。
通常、毒性学的に考慮すべき動物用医薬品の残留量は抽出可能な残留物の親化合物換算量に加えて生体内に吸収され得る結合型残留物の親化合物換算量を加算することによって得られる(注13)。したがって、結合型残留物のほとんどが生体内に吸収されない場合には、毒性学的に考慮すべき残留量は抽出可能な残留物のみとみなしてよい。
しかし、親化合物に変異原性があり、かつ、催奇形性やがん原性等が認められる場合等、結合型残留物についても毒性学的な検討が必要な場合には、生体内吸収率だけでなく、生体内に吸収される結合型残留物の毒性学的な活性を確認するための適切な試験が実施されていることが必要である。
なお、結合型残留物の安全性評価の手法については、JECFA(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives)において、簡単な評価手順の骨子が提案されているが(注14)、個別の物質の評価の際には今後さらに検討を重ねる必要がある事項である。
II.生体内運命に関する情報等
A.生体内運命
1.被験物質
被験物質は、原則として家畜等に実際に投与する製剤とする。
2.必要な情報
被験物質を最大用量で通常の経路を用いて投与することにより、次の項目が評価されていなければならない。
| (1) | 吸収及び排泄
吸収率、排泄率及び尿路経路、胆汁排泄等の排泄経路が明らかにされていること。 |
| (2) | 分布
主要な組織への分布及び血しょう蛋白への結合性、乳・卵等への移行性脂肪組織への蓄積性等生理学的な分布が明らかにされていること。 |
| (3) | 代謝
主要な代謝物の化学的性質及び生物活性が明らかにされているとともに組織及び体液中の親化合物及び各代謝物毎の濃度、総残留に対する比が経時的に測定されていなければならない。 |
3.試験系
試験系は、実際に被験物質が投与される対象となる健康な家畜等(以下「対象動物」という(注15)。)とする。
4.その他
対象動物を用いた試験の他、ラット等の実験動物による知見についても動物種の差異を考慮するために有用な情報となるが、この場合、毒性及び薬理学的知見との対応を考えて適切な動物種による知見が必要である。.また、医薬品としてヒトへの臨床経験がある被験物質については、ヒトへの投与から得られたデータが示されていることが望ましい。
B.国内外で認められた使用方法による食品中の残留値
国内外で認められた使用方法による食品中の残留値に関する情報は、可食部位毎lkgあたりの総残留量の他、未変化体及び代謝経路から明らかになっている代謝物の食用部位毎lkgあたりの残留量が確認されていることが必要である。
なお、これらの情報については、次の条件が具備されていることが前提となる。
| ○ |
国内外で認められた用法、用量、処方等にしたがって投与されていること。 |
| ○ | 使用動物の個体数は統計学的に有為な推計が可能なものであること。 |
| ○ | 適切に設定された使用禁止期間の前後の必要な時点で組織及び組織液が採取されていること。 |
III.その他必要な情報
その他必要な情報として、起源又は発見の経緯及び外国での使用状況に関する情報、物理化学的性質及び成分規格に関する情報(名称、構造式又は示性式、分子式及び分子量、含量規格、製造方法、性状、安定性、食品中の分析法等)、薬理作用に関する情報、有用性・使用方法に関する情報が必要である。
(注)
| 注1: |
その他、神経毒性、免疫毒性、ホルモン活性に関する情報も必要となる場合がある。 |
| 注2: |
評価報告書には、科学的文献の総説、ヒト及び標的動物種についての信頼できるデータを含む。 |
| 注3: |
被験物質の飼料中あるいは飲水中での安定性が不良の場合等混餌(飲水)投与が困難な湯合には、強制経口投与を実施しても差し支えない。 |
| 注4: |
生殖に関して悪影響が観察された場合、必要に応じて親動物を再交配して確認されているとともに、雌雄の親動物のいずれに原因があるかが明らかにされていることが望ましい。 |
| 注5: |
本試験では、妊娠の開始時期を把握することが重要であり、胎児の観察は出産予定日の1〜2日前に実施されていることとする。 |
| 注6: |
被験物質が溶媒を用いて投与されている場合にあっては、当該溶媒に催奇形性の見られないものが用いられているものとし、対照群には溶媒のみが投与されていなければならない。 |
| 注7: |
本文中で記載されている他、変異原性試験として適用される可能性のある試験法には、現在次のような種類がある。
遺伝子突然変異誘発性を指標とする試験
- ほ乳類の培養細胞を用いる遺伝子突然変異試験
- ショウジョウバエを用いる遺伝子突然変異試験
- げっ歯類を用いる遺伝子突然変異試験
染色体異常誘発性を指標とする試験
- げっ歯類の骨髄細胞を用いる染色体異常試験
- げっ歯類の生殖細胞を用いる染色体異常試験
- げっ歯類を用いる優性致死試験
DNA損傷性を指標とする試験
- 細菌を用いるDNA修復試験
- ほ乳類の細胞を用いる不定期DNA合成(UDS)試験
- ほ乳類の細胞を用いる姉妹染色分体交換(SCE)試験
|
| 注8: |
また、試験系の選択に当たっては、種々の発かん性物質に対して感受性があること及び健康な状態における腫瘍の自然発生率が明確になっていることが必要である。 |
| 注9: |
この場合、腸管内のpH及び嫌気状態、抗生物質及び合成抗菌剤の濃度等の因子も考慮されるべきである。 |
| 注10: |
アレルギー症を起こすことが確認されているものには、例としてペニシリン等ベーターラクタム系薬剤がある。 |
| 注11: |
結合型残留物の量は以下の式により求められる。
結合型残留物=総残留量−(抽出部分+内因性部分) |
| 注12: |
Gallo-Torres,H,E,Methodology for the determination of bioavailability of labeled residues.
Journal of Toxicology and Environment Health,2:827-845(1977) |
| 注13: |
毒性学的に考慮すべき残留物の親化合物換算量の算出法
| 残留物 |
= |
抽出可能な残留物の親化合物換算量+生体内に吸収される結合型残留物の親化合物換算量 |
| = |
| x |
| Po+Σ(Mn×An)+(結合型残留物×生体内に吸収される n=1割合×Ab) |
| Po |
=組織1kgあたりの親化合物の量 |
| Mn |
=組織1kgあたりのn代謝物の量 |
| An |
=n代謝物の親化合物に対する相対毒性 |
| Ab |
=結合型残留物の親化合物に対する相対毒性(情報がない場合はAb=1を使用)
n1〜nx=n1〜nx代謝物 | | |
| 注14: |
| 1) |
Thirty-fourth Report of Joint FAO/WHO Expert Committee on Foods Additives,2.4 Bound Residues |
| 2) | Thirty-sixth Report of Joint FAO/WHO Expert Committee on Foods Additives,2.3 Bound Residues |
|
| 注15: | 対象動物における代謝物で試験を実施する際に、実験動物において生成されたものと同一であるか否かが確認されていることが必要である。
また、ヒトが対象動物の組織とともに摂取する代謝物が、実験動物で生成される代謝物と同一であることが確認されていることが必要である。
なお、適切な動物における生体内変化の結果が既に確認されている物質の組み合わせであって、かつ当該物質の生体内の動態において物質間の相互作用がないこと等が確認されていれば、その後の代謝に関する情報は省略しても差し支えない。 |
IV.附則
策定:平成7年7月11日
一部改訂:平成11年8月31日
トップへ
戻る