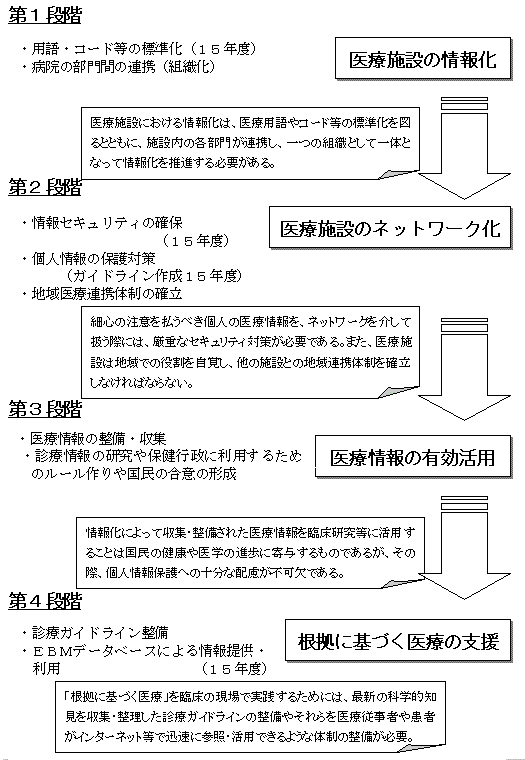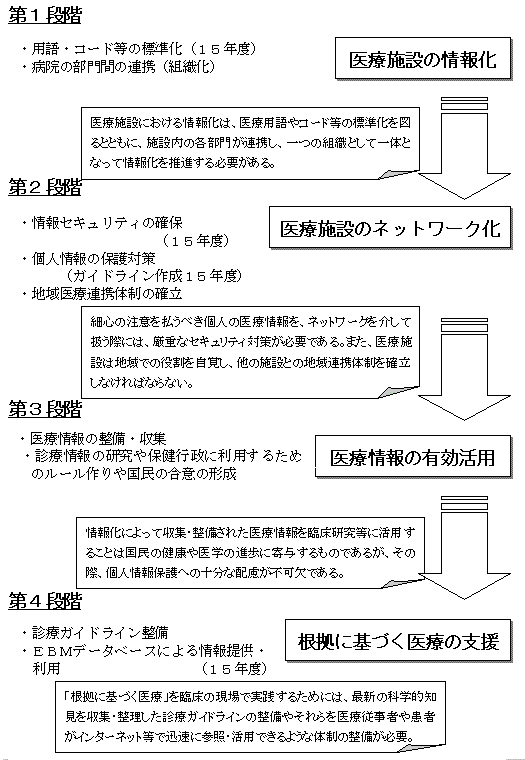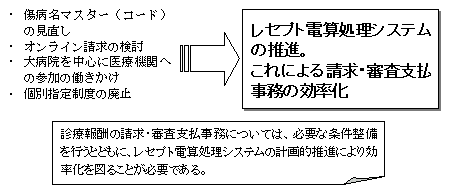戻る
保健医療分野の
情報化にむけてのグランドデザイン
最終提言
保健医療情報システム検討会
-
保健医療情報システム検討会委員
はじめに
医療の将来像を踏まえた医療の課題と情報化
- 情報化で5年後に医療がどう変わる
-
1.医療機関に行く前に
2.診察の時
3.在宅で
4.救急時
5.日本の医療全体として
- 医療情報システム構築の戦略
-
1.医療情報システム構築のための達成目標・発展段階の設定
2.レセプト電算処理システムの計画的推進
- 保健医療福祉総合ネットワーク化への展開
-
1.健康づくり・疾病予防
2.介護・福祉
3.医薬品・医療材料
| (五十音順) ○座長 |
|
石川 准 |
静岡県立大学国際関係学部教授 |
|
井上通敏 |
日本医療情報学会長 |
|
大山永昭 |
東京工業大学教授 |
| ○ |
開原成允 |
医療情報システム開発センター理事長 |
|
齊藤孝親 |
日本大学松戸歯学部口腔診断学教室助教授 |
|
坂本すが |
NTT東日本病院看護部長 |
|
西島英利 |
日本医師会常任理事 |
|
樋口範雄 |
東京大学法学部教授 |
|
藤本利雄 |
保健医療福祉情報システム工業会 |
|
細羽 実 |
日本医用画像システム工業会 |
|
◯ 保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザインに関しては、平成13年3月28日より保健医療情報システム検討会において検討を開始し、保健医療分野の情報化に関する理念と目的、現状、将来像と、それに向けた現在の目標と課題などについて総合的に取り上げ、8月8日に第一次提言として、その基本的な考え方を示したところである。(別添 1)。
◯ その後、平成13年9月25日に、厚生労働省の医療制度改革試案が公表された。この改革試案においては、医療保険制度の改革のみならず、今後の医療のあるべき姿についても別添「21世紀の医療提供の姿」の中で示されるなど、21世紀の我が国の医療に関する総合的・包括的な制度改革案となっている。この中で、保健医療分野における情報化についても重要な柱の一つと位置づけられ、これを着実に実施するため、グランドデザインを策定することが表明されている。
◯ このため、今回の最終提言に当たっては、この「医療制度改革試案」で提示された「21世紀の医療提供の姿」が描く医療の将来像を踏まえ、情報化が我が国医療の将来像にどのような影響を与え、どのように貢献するものであるかを提示することとした。
◯ また、情報化が我が国医療の将来に大きな影響を与えるものである以上、これを国として戦略的に進めていくことが極めて重要である。このような観点から、今後の戦略及び達成目標(年次目標及び数値目標)を示すこととした。
◯ 以上のような基本的考え方に立ち、保健医療分野のグランドデザインについて、以下の視点から最終提言のとりまとめを行った。
-
1) 我が国の医療の将来像を踏まえて、我が国の医療の課題を改めて整理し、これに対応した情報化の目的を提示する。
2) 情報化により医療がどのように変わるのか、国民や患者の視点から将来の医療の姿を分かりやすく提示する。
3) 情報化を段階的に着実に実施していくため、戦略を提示する。
4) その戦略を踏まえ、情報化の各段階において設定された各目標について、国家的視点から実現方策を提示することとし、官民の役割分担、達成目標等を明示したアクションプランを策定する。
5) 健康づくり・疾病予防を中心とした保健政策、介護・福祉政策といった分野についても情報化の進展を見すえ、医療の情報化との連携について、その方向性を示す。
1.「21世紀の医療提供の姿」
厚生労働省は、平成13年9月25日に「医療制度改革試案」〜少子高齢社会に対応した医療制度の構築〜を公表し、その中で、今後の我が国の医療の目指すべき姿と当面進めるべき施策を「21世紀の医療提供の姿」として提示した。
○ この中で、1.患者の選択の尊重と情報提供、2.質の高い効率的な医療提供体制、3.国民の安心のための基盤づくりの3つを柱とする「医療の将来像」が提示されている。
(医療の将来像の概要)
1.患者の選択の尊重と情報提供
○患者の視点の尊重と自己責任
○情報提供のための環境整備
2.質の高い効率的な医療提供体制
○質の高い効率的な医療の提供
○医療の質の向上
3.国民の安心のための基盤づくり
○地域医療の確保、医療の情報化等
|
|
→ |
|
|
○ これは、適切な情報提供のもと、患者が自ら医療機関や治療方針等を選択するなど、医療に自覚と責任をもって参画することを医療の目指すべき姿とし、患者の選択を通じて医療の質の向上と効率化・重点化が図られる、という考え方を基本とするものである。
○ このような医療の姿が実現するためには、公正で客観的な情報が提供されることが大前提となるが、そのためには医療の情報化、さらにその基盤としての情報化基盤、すなわち情報化に向けてのインフラが整備されることが必要となる。
○ このため、この将来像においても、医療の情報化を21世紀の医療提供の姿を考える際に不可欠の要素と位置づけ、その整備を実現すべき具体的な政策課題としている。
○ さらに、この「21世紀の医療提供の姿」で触れられている個別の課題との関連性を見ても、第一の柱である患者への情報提供、第二の柱である質の向上と効率化、第三の柱に含まれる医療安全の確保等のいずれにも情報化は大きな影響を持っている。
○ これらの課題と情報技術を活用した手段との対応関係は、相互に密接に関連しているが、両者の関係について課題を中心にわかりやすく整理すると次のとおりである。
○「医療の課題」とその解決を目的とした情報化(概念整理)
-
| 医療の課題 |
対応する情報技術を活用した手段 |
効果 |
| 情報提供 |
電子カルテシステム |
(比較可能なデータの蓄積と活用)
・適切な情報管理・検索
・目的に沿った情報の加工が容易
(見やすく読みやすく分かりやすい情報)
・患者にとって理解しやすい診療の説明
(医療従事者間での情報提供や診療連携)
・医療機関内、医療機関間、医療機関・他の関係機関との情報ネットワーク化
・セカンドオピニオン※の際に初めの病院で検査した正確な患者情報を容易に参照可能
|
| レセプト電算処理システム |
・健康指導などの保健事業に活用
|
| 質の向上 |
「根拠に基づく医療」支援(Evidence-based Medicine:EBM) |
・質の高い医学情報を整理・収集しインターネット等により医療従事者や国民に提供
・診療ガイドラインの作成支援・提供
|
| 電子カルテシステム |
・患者の診療データの一元管理・共有化、情報の解析等による新たな臨床上の根拠(エビデンス)の創出
|
| 遠隔診療支援 |
・遠隔地の専門医による診断支援、治療指示等が受けられる
・在宅において安心できる療養の継続
|
| 効率化 |
電子カルテシステム |
・フィルム等消耗品の使用量削減
・正確な物流管理による経費節減
|
| オーダリングシステム |
| レセプト電算処理システム |
・診療報酬の請求・審査支払事務の効率化
|
| 個人・資格認証システム |
・医療事務の効率化
|
物流管理システム
(電子商取引) |
・医療資材物流に関する事務の効率化
|
| 安全対策 |
オーダリングシステム |
・診療情報の共有による伝達ミスの防止、入力・処方ミスのチェック
|
※セカンドオピニオン:診断や治療法が適切かどうか、患者が複数の医師等に意見や判断を求めること。
注)医療情報システムとは
「医療情報システム」についての定義は、特に定まったものはないが、当グランドデザインにおいては主に以下のシステムを指すものとする。
-
-
診療録等の診療情報を電子化して保存更新するシステム。様々な段階があるが、現状では診療録や検査結果などの診療情報を電子的に保存、閲覧するために医療施設内での使用が大部分である。
今後は診療情報などを医療機関同士で交換、共有する診療情報のネットワーク化・データベース化が図られ、診療情報が活用されることが期待される。
-
医療機関と医療機関をネットワークで結び、専門医による診断を依頼する画像診断(tele-radiology)、病理診断(tele-pathology)のような専門的診療支援や、医療機関と在宅の間における在宅療養支援などを行うシステムのこと。
-
診療報酬の請求を紙の診療報酬明細書(レセプト)ではなく、電子媒体に収録したレセプトにより行うシステム。なお、現状はフレキシブルディスク又は光ディスク等により行われているが、将来的にはオンライン請求も含む。
-
従来、紙の伝票でやり取りしていた検査や処方箋などの業務を、医師(歯科医師を含む。以下同様。)がオンラインで、検査、処方し、医事会計システムとやり取りすることなどにより、オンライン上で指示を出したり、検査結果を検索・参照したりできるシステム。
-
医療情報システムを用いて検査や処方などを行う際に、医師等の資格確認を電子的に行うシステム。今後は被保険者証をICカード化し、医療施設を受診した際にオンラインで被保険者の資格を確認したり、住所・氏名などの個人情報をカルテ、レセプトへ自動的に転記をしたりすることへの応用が検討されている。
○ 医療制度改革を巡り、医療の情報化が広く議論されるようになってきているが、情報化の進展で診療の場はどのように変わるのか、患者や国民の視点から具体的に分かりやすく示されているとは言い難い。
○ 一方、医療制度改革を実現するためには、患者と医療提供者の双方の理解と協力が必要である。このため、このグランドデザインが想定している情報化が進んだ時点の医療の姿(目標年次である5年後(平成18年)を念頭に置いた情報化進展後の医療の姿)について、特に利用者の立場から提示する。
1.医療機関に行く前に
- 医療機関を選択する環境が整う
現在は、医療機関を選択するための適切な情報が十分提供されているとは言い難い。これは医療における標準化、情報化の遅れが一因であり、今後病名等医療におけるの用語の標準化が進み、医療の情報化が進展することにより、たとえば医療機関ごとの診療実績のデータ分析や医療機関相互の比較を客観的に行う環境が整ってくるものと考えられる。このような環境整備に加えて広告規制の緩和、公的な情報提供の整備、情報開示ルールの定着等と相まって、医療機関に関する比較可能な情報提供が進むことにより、患者自身の医療機関の選択をはじめ、従来から行われてきたかかりつけ(歯科)医による医療機関の紹介の際にも医師、患者の双方に活用され最適な医療機関を選択することができるようになる。
- 分かりやすい医療の情報が容易に手に入れられる
医療に関する最新の科学的データベースが整備され、主な病気についての正確な医療情報がインターネットを利用して自宅において手軽に手に入れられるようになり、事前に自ら必要と考える医療情報を入手し、医療機関にかかるための準備ができるようになる。
2.診察の時
- 待ち時間が短くなる
従来から医療に対する不満として待ち時間の長さの問題が指摘されているが、今後情報化が進展すればインターネットを利用して受診可能な時間の確認や診療の予約を自宅からできるようになると考えられる。また、オーダリングシステム等の普及によって、院内の各部門間のネットワーク化が進み、患者中心とした流れになることにより検査、処方等の手続きが無駄なくスムースに行われるようになる。さらに、受付、薬剤の受取りおよび会計などの待ち時間も短縮され、円滑な受診が実現される。
- 分かりやすい説明を受けられる
患者の医療に対する希望として、自分の病気や治療方針等について分かりやすい説明を十分にしてもらいたいということがあるが、情報化、特に電子カルテシステムの普及により、患者が医師と一緒に電子カルテの画面を見ながら、レントゲン写真や検査結果等の分かりやすい映像とともに病気の状態についての説明を受けたり、治療方針を話し合ったりすることが多くの医療機関で行われることが期待される。また、院内の電子カルテシステムに基づく情報のみならず、国民向けの診療ガイドラインの提供も進むため、我が国で一般的に行われている治療方法等の情報を基に医師とともに治療方針を決定することも可能となる。
- 最新かつ最良の医療情報に基づいた最適な治療が受けられる
情報化の進展により、診療ガイドライン等の医学情報データベースが整備され、これをどこからでもインターネット等を通じて参照できるようになるため、全国どこの医療機関でも最新かつ最良の診断方法や治療方法を参照でき、地域や医療機関ごとの診断や治療の差異が少なくなるとともに最適な治療が受けられる。
- 専門医(歯科医師を含む)等への紹介がスムースになる
専門医等への紹介の際には、カルテや紹介状、またレントゲンフィルムや検査結果を紹介先の医療機関に提供することが必要になるが、医療機関の間でネットワークによる画像等の検査結果の電送が普及することにより、検査データ等を直接簡単に送ることができ、さらに円滑な紹介や逆紹介(専門医等からかかりつけ(歯科)医等への紹介)が行われることが期待される。
- より客観的なセカンドオピニオンが得られる
近年、一人の医師だけでなく複数の医師の診断や意見を尋ねる、いわゆるセカンドオピニオンを求める機会が増えている。その際、情報技術の活用により、はじめの医師が診断に用いた検査データや画像と全く同じものを参照することが可能となり、より客観的なセカンドオピニオンが得られるようになる。
- 離れた地域の専門医の診療が受けられる
情報機器を用いた遠隔診療の発達により、高度医療を提供する医療機関から離れた地域に居住し通院が困難な場合であっても、より高度な専門医による診療を身近な医療機関で受けることができるようになる。
- 医療事故が防止される
病院内におけるインシデント事例※の収集・分析により、多様な医療事故につながる根源的な原因を分析し、それを元に薬剤投与等の際の人的ミスをシステムでチェックすれば事故防止につながることが指摘されている。さらに院内におけるバーコードなどを活用した情報化の推進により、例えば薬剤と疾患との適合性を自動的にチェックしたり、患者の取り違えを防止したり、薬剤等の製造番号や有効期限を確認するなどにより医療の安全性が向上すると期待されている。
- ※インシデント事例:事故(アクシデント)にはならなかったミスや通常とは異なる出来事。
- 医療従事者が患者と接する時間が長くなる
医療の高度化・複雑化、記録の増加により、医療従事者の事務的な業務に要する時間が全業務の3割から4割を占めるともいわれている。今後、治療手順や看護手順等の標準化による業務の効率化や検査記録など診療情報の自動的な入力等による省力化により医療従事者が記録作成等の事務的な仕事に使う時間を節約でき、これにより患者と接するコミュニケーションのための時間をより多く取ることができるようになり、より充実した診療や看護ケア等が受けられるようになる。
- 医療資材の購入価格が安くなる
医療資材に標準化されたバーコードなどが貼付されることにより、流通段階での省力化・効率化が図られ、さらに電子商取引が普及すると価格競争が喚起されるとともに商取引が合理化されるため、医療資材の価格が低下する。
3.在宅で
- 通院の負担が軽くなる
定期的に医師の診察が必要な患者であっても、必ずしも通院が容易な患者ばかりではない。しかし、遠隔診療技術により自宅から医師や看護師とテレビを通じて対話ができ、体温・血圧等の身体の状況や人工呼吸器等の機器の状況を医療機関へ電送することは実用化されつつあり、これら情報通信技術により自宅と医療機関が常に結ばれていれば、万一病状が急変した場合であってもすぐに適切な指示を受けることができ安心して自宅で療養できるとともに、大きな変化がなければ頻回に通院する必要もなくなる。
- 医療の情報が簡単に分かりやすく手に入れられる
在宅で療養生活を行っていても、インターネットを利用して自分の病気の情報やその治療法、専門医療施設の情報等、最新の医学情報や医療機関をデータベースから手軽に手に入れられ、メールなどにより今後の治療方針などについても主治医と相談ができるようになる。
4.救急時
- より早く、適切な救急医療がうけられる
救急搬送時より、患者の血圧や呼吸状態などの生体情報を搬送先の救急医療施設に電送し、それに基づく受け入れ準備があらかじめされるため、適切な治療が速やかにできる。また、搬送時の生体情報より専門医の指示が受けられ適切な医療機関を選択し搬送できる。
- どこで容態が急変しても救急医療機関とかかりつけ(歯科)医との連携がとれる
慢性疾患で通院していた患者が、旅行先等で急変した場合でも、ネットワークを介して、かかりつけ(歯科)医からその患者のそれまでの検査結果や処方内容などの治療経過を参照でき適切な初期治療が速やかに可能となる。
5.日本の医療全体として
最後に、厚生労働省改革試案で提示されている我が国の医療の将来像に照らして、情報化がその実現プロセスにおいてどのような役割を果たすか改めて見ておきたい。
- 患者の選択の尊重と情報提供
情報開示と患者の選択は、今後の医療を考える上でのキーワードである。医療に関する患者の選択とは、受診中の治療方針等の選択と受診に際しての医療機関の選択とに大きく分かれる。このいずれにも情報化が大きな貢献をするものと期待される事は先に述べたとおりである。
- 質の高い正確な情報を国民が得られる環境整備
第一に、患者が医師と十分相談し助言を得て、希望に応じ他の医師の意見を求めながら自らの治療方針について選択していくことは、国民の意識の変化も踏まえれば、今後ますます重要になっていくものと見込まれる。このような患者の治療への参加に当たっては、患者自ら正確な情報を得られるようにすることが極めて重要であり、情報化(情報のデータベースの整備とインターネット等を通じた提供)が進むことが大きく寄与するものと考えられる。
- 質の高い効率的な医療提供体制(競争を通じた医療の効率化・重点化)
第二に、情報化の進展により、医療機関相互の比較を客観的に行う環境が整ってくることが見込まれ、患者による選択を通じて、我が国の医療は今後効率化・重点化と機能分化が進むと見込まれる。患者の側からこれを見れば、診療に関する実績等、医療機関を選択する情報が提示されており、受診の参考にすることができるようになるとともに、急性期医療の充実等により、質が高く、早期に退院して社会に復帰することが可能となる医療の提供を受けることができるようになる。
また、医療資材の開発や流通の面でも効率化が図られ、価格が適正化されることが見込まれる。
- 国民が安心できる安全な医療情報の運用管理体制の整備
今後の医療の情報化の発展にともない、患者の個人情報を治療のためにネットワークでやり取りしたり診療記録等の一元的電子管理が行われたりすることが考えられる。また、大量の診療情報を収集、分析することにより新しい治療法の発見がされ医学の進歩に寄与することも考えられる。しかし、これらの患者の診療情報利用に当たっては、まず患者本人の同意が必要であり個人情報の保護に細心の注意を払うとともに、権限のない人が患者の情報を閲覧したり、持ち出したりすることがないよう厳重な管理体制を確立する必要がある。
- 国民の安心のための基盤づくり
最後に、医療の情報化の役割として、医療の地域偏在を緩和することができると考えられる。すなわち、へき地や離島はもとより都市部においても小児医療や救急医療などの分野において、小児科医や救急医などの専門医と連携を図ることで、いつでも安心して医療が受けられるようになる。
例えば、電子カルテを導入した医療機関では患者の診療記録や検査結果が電送できるため、必要に応じてその記録をもとに専門医と相談することができ、救急搬送された医療機関とかかりつけ(歯科)医との間でも治療経過などの診療情報を交換することにより、より安全で質の高い医療が受けられるようになる。
このためには多くの医療機関が電子カルテをはじめとする情報技術を導入し、専門的な医療施設や一般の医療施設や介護施設とのネットワークを構築することにより包括的で質の高い診療連携体制が実現される。
1. 医療情報システム構築のための達成目標・発展段階の設定
−電子カルテシステムを中心に−
我が国の医療情報システムが目指すべき達成目標を明示する
|
【目標】
- 平成16年度までに
全国の二次医療圏毎に少なくとも一施設は電子カルテの普及を図る
- 電子カルテの普及の際は、地域医療支援病院、臨床研修指定施設またはその地域で中心的な役割を果たしている病院などの地域連携診療の核となるような医療施設が電子カルテを導入するよう推進する。
- 平成18年度までに
全国の400床以上の病院の6割以上に普及
全診療所の6割以上に普及
|
- 先にも述べたように医療の情報化は、厚生労働省の医療制度改革試案の中で示された「今後の我が国の医療の目指すべき姿」の実現のために重要な柱の一つと位置づけられており、これを着実に推進する必要がある。
- ここに示した【目標】は国をはじめ産業界、医療界が共通の問題意識を持ち、医療の情報化を戦略的に推進することにより、達成し得るものと考えられる。
- このため、医療情報システムでも中核をなす電子カルテシステムを中心に「4つの段階」を想定し、それぞれの段階ごとに設定した目標に戦略的に取り組むことを提言する。
- 目標達成の戦略の全体像を「医療情報システム 工程表」としてまとめた。(別添 2参照)
- なお、これらの段階は医療情報システムの発展過程を踏まえて分類したものであるが、医療情報システムの普及に当たってはそれぞれの段階が同時並行して推進されるものである。
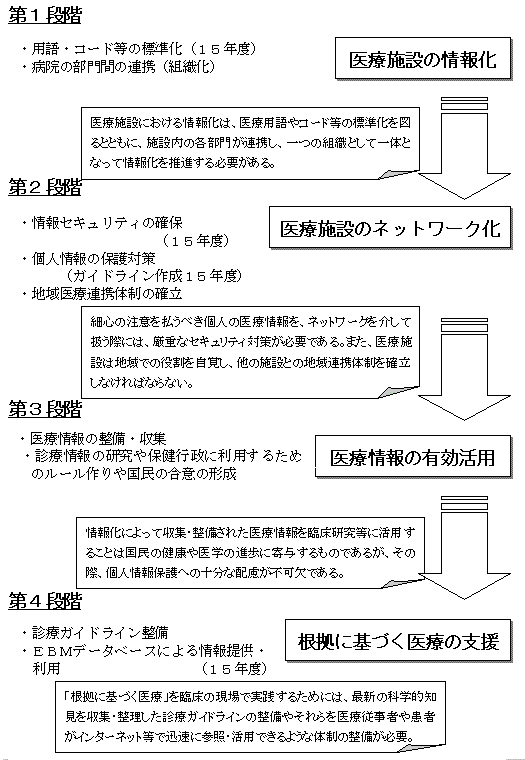
2.レセプト電算処理システムの計画的推進
-
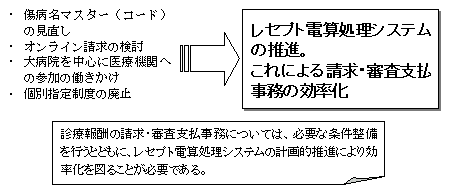
※「レセプト電算処理システム 工程表(別添 3)」を参照
情報技術がもたらす情報の共有、蓄積、分析メリットを活かすことにより、医療機関を中心とした医療のシステムにとどまらず、健康づくり・疾病予防といった保健システム、介護・福祉分野のシステム、さらには医薬産業システム等とのネットワーク化を目指すことが可能となる。
1.健康づくり・疾病予防
保健分野の情報化は、(1)個人の健康づくり支援、(2)科学的根拠に基づく保健政策の展開を進めるために非常に重要であり、医療の情報化との連携によってさらに効果を上げることができる。そのため、保健分野の情報化についても、医療の情報化と整合性のとれた形でコードの標準化、セキュリティの問題等も含め、進めていくべきである。
(1) 個人の健康づくり支援
-
ア.生涯を通じた健康管理体制を構築
-
【現状と課題】
妊婦及び乳幼児の健康診断の情報は母子健康手帳に記載されており、成人期以降の健康診断は、健康保険法、労働安全衛生法、老人保健法等多種多様な制度に基づいて実施され、結果はその都度、紙媒体で本人に通知されている。
その結果、サラリーマンが退職した時のように異なる制度に移行した場合、健診情報が断絶してしまい過去の健康診断の情報が活用できないといった問題が生じている。
【健診情報の電子媒体保存と異なる制度間の連携】
健診情報を電子媒体で保存するとともに、個人情報保護を担保した上で異なる制度間の情報の交換を図ることにより、制度間の連続性が確保され、個人の生涯にわたる健康づくりを支援することが可能となる。
【医療との連携の方向性(イメージ)】
保健事業実施主体と医療機関がネットワーク等を通じて情報共有を図ることにより、過去の健診情報を診療の場で活用し、生活習慣病の予防等に活用したり、逆に医療機関を受診した際に得られる医療情報などを保健事業実施主体が生涯にわたり一貫して活用したりすることが可能となり、個人の健康状態の評価や健康づくりの支援が容易になる。
【現在の取組】
○地域職域健康管理総合化モデル事業(平成13年度)
生涯を通じた健康管理体制を構築するため、地域・職域で相互活用が可能となる総合的な健診情報管理システムを開発し、データベース化するとともに、地域保健事業による健診情報と職域健診情報の両者を含んだ総合的な地域診断を行い、より適切な保健事業を実施する。
ィ.遠隔健康教育の推進
- 日常生活における個人の健康づくりを支援するために衛星放送やケーブルテレビ、インターネットを通じた遠隔集団健康教育の発展が期待される。遠方にある医療機関を受診しなくても自分の都合に合わせ、容易に健康情報を入手できる利便性から今後その役割が増加するものと考えられる。
- また、健康づくりに取り組む個人が自ら測定できる健康指標や栄養・運動・休養・喫煙・飲酒など生活習慣に関する情報をインターネットを通じて専門家に送付し、意見を求める双方性のある遠隔個別健康教育の役割も今後期待される。
(2)科学的根拠に基づく保健政策の展開
- 21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)において、科学的根拠に基づいた計画の立案、実施及び評価を行う際に、科学的根拠に基づいた情報は不可欠である。質の高い情報を効率的に入手するためには戦略的な情報収集システムの確立が求められる。
- 今後、健康日本21を推進するにあたっては、地方計画を策定する都道府県、保健所、市町村自らが調査を行い、データを収集・分析し、その管轄区域の健康課題を明らかにするとともに、これを適切な形でインターネット等により住民に対して積極的に提供するべきである。
- また、国は各地方自治体で実施される調査データを収集し、全国、各都道府県、二次医療圏、市町村別平均値、標準偏差等を算出し、国としての健康目標の設定、評価に活用するとともに、各地方自治体にそのデータを還元することにより、他の地方自治体との比較を可能とすることも重要である。
- これらを実施するためには情報収集解析の際の情報システム化は必須であり、これまでも国、都道府県、保健所、市町村をオンラインで結び、電子媒体による情報の伝達を行ってきたが、今後さらにこれを推進し、業務の省力化、迅速で、かつ、より正確な情報の交換が図られることが期待される。また、医療情報についても情報化が進められ、保健情報との融合を図ることにより、保健医療政策立案に活用されることも期待される。
2.介護・福祉
介護・福祉と情報技術のかかわりには次の三つがある。第一は、介護保険制度によって、その関連事業に情報技術が大幅に導入されたこと、第二は、医療と介護・福祉の連携に情報システムが有効であると思われること、そして第三に、情報技術が障害者に対するバリアフリー化や安全な生活に直接役立つと思われることである。
(1)介護保険制度における情報化の展開
介護保険制度は、最初から情報技術の利用を前提として出発した。
その主な例として、以下のものが挙げられる。
-
ア.要介護認定の情報化
- 要介護認定における一次判定は、全国で認定結果に差異が生じないよう、全国一律の基準に基づき、コンピュータプログラムによる処理が行われている。
イ.国民健康保険団体連合会における審査支払システムの情報化
- 国民健康保険団体連合会における審査支払事務は完全に電子化され、事業所情報や受給者情報と請求情報の突き合わせ等すべてシステム対応がなされている。事業者からの請求も電子媒体によることが原則とされており、当面は紙帳票による提出も認められているものの、現在までに請求の約7割が電子化されている。
ウ.ケアプラン作成における情報化
- ケアマネージャーによるケアプランの作成も、多くの場合、民間で開発されたプログラムが利用されており、介護サービスの実施の記録や介護用品の購入などについても、情報システムを導入して行っているところもある。
エ.WAMNETの活用
- 社会福祉・医療事業団が運営する福祉保険医療情報ネットワークシステム(WAMNET)上において、指定介護サービス事業者の情報を掲載しており、誰でも自由に閲覧することが可能となっている。なお、事業者の基本的な情報については、各都道府県の事業者管理台帳システムと連携しており、各事業所のサービスの空き情報等の個別の情報については、各事業所自らが書き込むことが可能となっている。これにより、リアルタイムの情報がインターネットを通じ、広く一般に情報提供されている。
○情報化支援の取組み
-
ア.介護保険広域化支援事業
- 介護保険行政の運営において、市町村合併や広域連合等により広域化を図ることは、財政基盤の強化やサービス基盤整備の充実、事務処理の効率化等に資するものと考えられる。このため、広域化を図る際に障害となる各市町村の事務処理システムの標準化に要する経費や保健・医療・福祉ネットワークの構築に要する経費等を補助しており、平成14年度概算要求にも盛り込んでいるところである。
イ.高齢者ITケアネットワーク支援事業
- 高齢者や家族と保健・福祉機関等との連携体制を確保する上で、ITを活用したシステムが大きな効果をあげることが期待されており、例えば、(1)痴呆性高齢者が徘徊行動により所在不明となった場合に高齢者を安全・迅速に保護するための「徘徊高齢者保護システム」や、(2)一人暮らしの高齢者に対する「緊急通報システム」、「安全確認システム」等について支援が行われている。また、これにとどまらず、各自治体の取組みとして、高齢者の保健・福祉分野でのIT活用の可能性が考えられるものについて、幅広く補助対象とされている。
○被保険者カードのICカード化
- 介護保険の被保険者カードをICカード化して給付管理システムを構築することは、利用者によるサービスの自由な選択、ケアマネージャーの業務の効率化、支給限度額の確実な把握等を実現する上で大きな効果が期待でき、また、情報化の積極的な推進によって行政サービスの向上、利便性の向上を図ることができることから、介護保険制度の運用における基盤システムの整備として、今後の検討が必要である。
- なお、今後の取組みとしては、上記のシステムが有効に機能し、かつ導入時の安全性を確保するために、事前にモデルシステムの運用を通じて効果の評価と実際の運用に向けた課題と対策を明確化する必要があることから、モデル事業を実施し、システムの評価を行った上で今後の展開に向けての検討を行うこととしている。
(2)医療と福祉の連携
- 第二の医療と福祉の連携については、医療機関及び指定訪問看護事業所からの訪問看護と居宅介護支援をはじめとする福祉サービスの連絡にコンピュータネットワークや移動端末を用いるなど、今後工夫することによって大きな実りある分野がある。
(3)障害者施策へのIT支援
- 第三の点である身体障害者に対する直接的なIT支援については、一人暮らしの障害者の情報技術による遠隔モニタリング、救急時の呼び出しシステムなどの研究があり、経済産業省のプロジェクトには、それに適した構造の家を実験的に建設するテクノハウスプロジェクトなどもある。今後、高齢者のIT支援事業の増加とともに更なる研究が必要となると思われる。
3.医薬品・医療材料
医療機関が医薬品行政とかかわりを持つ場面としては、副作用報告と治験がある。この両者とも情報技術の利用が急速に進んでいる。また、信頼できる医薬品情報を医療従事者や国民に分かり易く、迅速かつ確実に提供していくことを目的としたネットワークを構築しようとする取組もある。
(1)副作用
- 医療機関は、医薬品、医療用具等の使用の結果認められた副作用、感染症、不具合情報を「医薬品・医療用具等安全性情報報告制度」により厚生労働省に報告しているが、将来、ネットワークを活用し、電子化された所定のフォーマットで報告を行うようになることも考えられる。
(2)治験
- 医薬品の治験に係る情報については、医薬品の臨床試験の実施の基準に従いつつ、電子媒体により記録・保管することが望ましい。また、最近では、治験に係る被験者の割付※などについても、情報システムによって行うことも可能となっている。
- ※割付:治験などで治療効果を比較するため、異なる複数の治療法のグループ(治療群と未治療群、治療薬Aと治療薬B等)に患者を振りわけること。
(3)医薬品総合情報ネットワークの構築
- 情報技術を活用した医薬品の情報を無償で提供する体制として、「医薬品情報提供のあり方に関する懇談会」の提言を踏まえ、下記の3つのコンセプトから取り組くんでいる。
-
1.総合的な情報提供
医薬品の安全性、有効性、品質、患者負担等についての総合的な判断に資するよう、添付文書等基本的な情報をはじめ、品質や価格に関する情報も網羅的に掲載するほか、詳細情報等が活用できるよう各関係団体のホームページとリンクする。
2.最新情報の提供
常時、最新の情報を提供する。
3. 国民への情報提供
上記1.の総合的な情報のうち、国民が必要とするものを患者・国民向け医薬品情報として分かりやすく提供する。
(4)医薬品の用語・コードの標準化
- 医薬品の承認、市販後調査、副作用報告、流通、薬価などの目的別に10種類を越えている医薬品コードの統一を推進し、コードの表示手段については技術進歩を踏まえつつ、二次元シンボル等の使用を目指す。
(5)医療材料物流改革サプライチェーン構想
- 情報技術を活用して、製造、流通、販売、回収までの全過程(サプライチェーン)における「もの」と「情報」の流れを把握し、効率的な物流を実現するものである。物流改革サプライチェーン構想は、
-
1. 医療材料商品コードの標準化
2. 医療材料データベースの構築
3. 医療材料バーコード化
4. 電子商取引の推進
の大きく4段階から構成される。
- この施策の期待される効果は、院内外の物流の効率化、医療用具の不具合情報の追跡が容易になることによる安全性の向上、適正な市場競争の活性化などに資すると思われる。さらに医療材料で十分な効果が検証されれば、医薬品等の他の医療資材への適用が考えられる。
トップへ
戻る