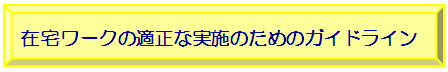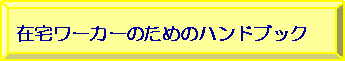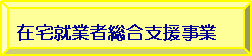情報通信の高度化、パソコン等情報通信機器の普及に伴い、これらを活用して個人が在宅形態で自営的に働く在宅ワークが増加しています。在宅ワークの業務例としては、文書入力、テープ起こし、データ入力、ホームページ作成、設計・製図、デザイン、翻訳などがあります。
それぞれの事情に合わせて柔軟に働くことができる在宅ワークは、仕事と生活を調和させることができる働き方として、その普及に対する社会的な関心や期待も大きいものとなっています。
厚生労働省では、在宅ワークを良好な働き方とするための様々な支援を行っています。
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」は、在宅ワークの注文者が在宅ワークの契約締結の際に守るべき最低限のルールとして、厚生労働省が定めているものです。
平成22年3月には、在宅ワークを取り巻く環境の変化を踏まえ、適用対象の拡大や発注者が明示すべき契約条件の追加などの改正を行いました。
契約をめぐるトラブルを未然に防止するため、在宅ワークの注文者は、在宅ワーカーと契約を結ぶ際には、ガイドラインの内容を守るとともに、契約の内容について在宅ワーカーと良く協議した上で決めることが望まれます。
<ガイドラインの概要>
|
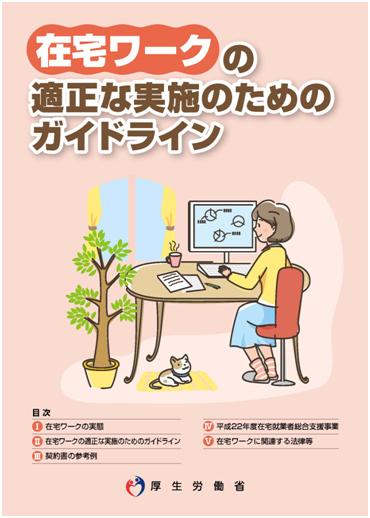 |
(1)報酬の支払
(1)報酬の支払期日
報酬の支払期日については、注文者が在宅ワーカーから成果物を受け取った日から起算して30日以内とし、長くても60日以内としましょう。
(2)報酬の額
報酬の額については、同一又は類似の業務に従事する在宅ワーカーの報酬、注文した仕事の難易度、納期の長短、在宅ワーカーの能力等を考慮することにより、在宅ワーカーの適正な利益の確保が可能となるよう決定しましょう。報酬の額については、最低賃金を参考にすることも考えられます。
(2)納期
納期については、在宅ワーカーの作業時間が長時間に及ばないように設定しましょう。その際には、通常の労働者の1日の労働時間(8時間)を目安としましょう。
(3)継続的な注文の打ち切りの場合における事前予告
同じ在宅ワーカーに、例えば6月を超えて毎月1回以上在宅ワークの仕事を注文しているなど継続的な取引関係にある注文者は、在宅ワーカーへの注文を打ち切ろうとするときは、速やかに、その旨及びその理由を予告しましょう。
(4)契約条件の変更
契約条件を変更する場合には、在宅ワーカーと十分協議の上、上記「1.契約条件の文書明示」に掲げる事項の内容を確認し、文書を交付しましょう。在宅ワーカーが契約条件の変更に応じない場合であっても、それにより不利益な取扱いを行わないようにし、当初の契約内容を守りましょう。
○ガイドラインの全文及び解説はこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/zaitaku/aramashi.htm
| 平成22年7月には、これから在宅ワークを始める方や始めて間もない方向けの基礎知識集として、「在宅ワーカーのためのハンドブック」を作成しました。 このハンドブックは、在宅ワークの始め方、契約、実際の作業、納品、代金の請求といった在宅ワークの仕事の流れに沿って、在宅ワークをする際のポイントや注意点が分かるよう構成されています。また、読者が在宅ワークの契約についてイメージしやすいように、見積書、契約書、請求書の参考例を掲載するとともに、前述のガイドラインや在宅ワークに関連する法律も紹介しています。 |
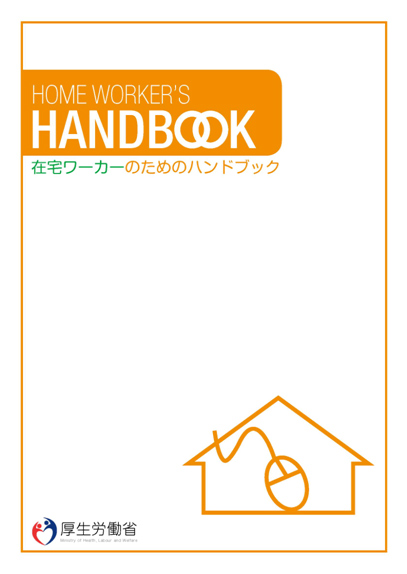 |
(「在宅ワーカーのためのハンドブック」より抜粋)
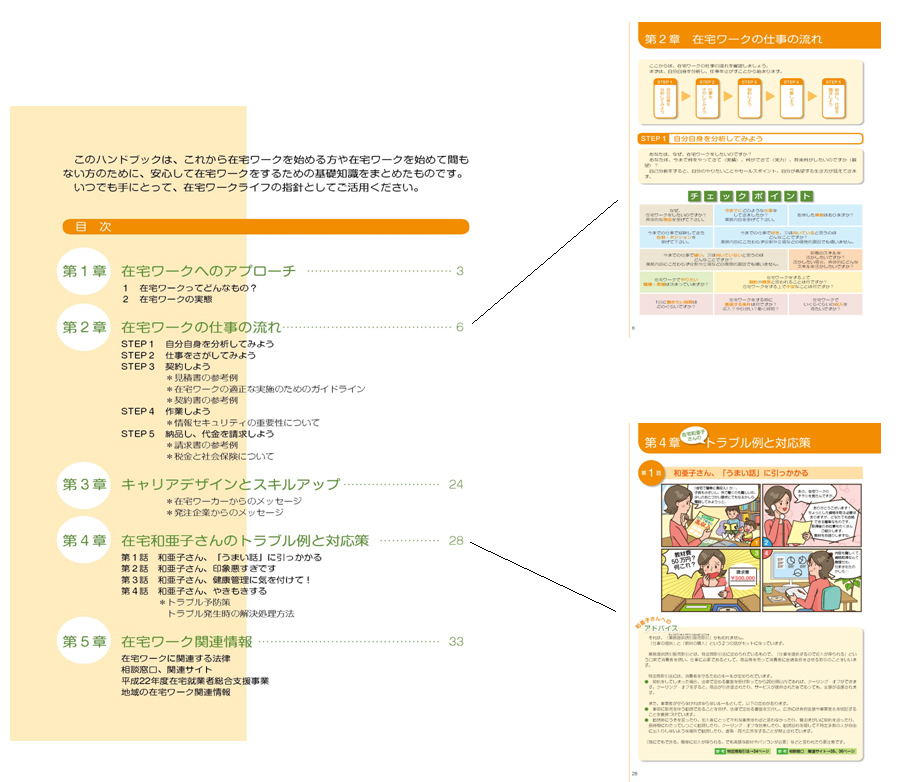
○ハンドブック全体はこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/zaitaku/100728-2.html
公益財団法人日本生産性本部への事業委託により、在宅就業者総合支援事業を実施し、良好な在宅就業の環境づくりに努めています。在宅ワーカーのための情報サイト「ホームワーカーズウェブ」の運営、各種セミナーの開催、在宅ワークに関する疑問にお答えする「在宅ワーク相談室」を実施しています。
また、9月30日に在宅ワーカーや仲介機関のネットワークづくりのためのシンポジウムを開催しますので、ぜひご参加ください。
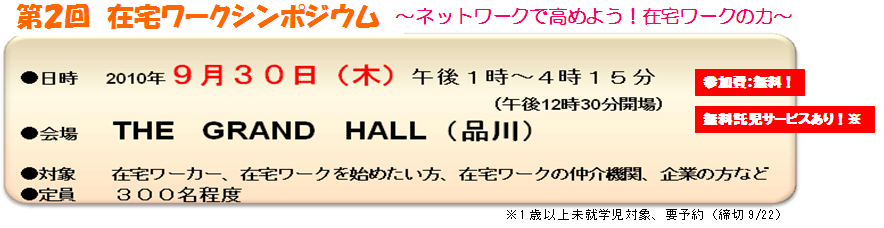
○シンポジウムの詳しい内容はこちらをご覧下さい。
http://www.hw-symposium.com/
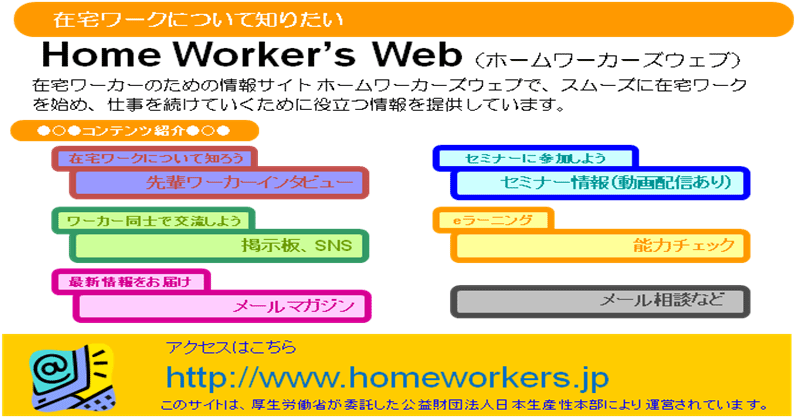
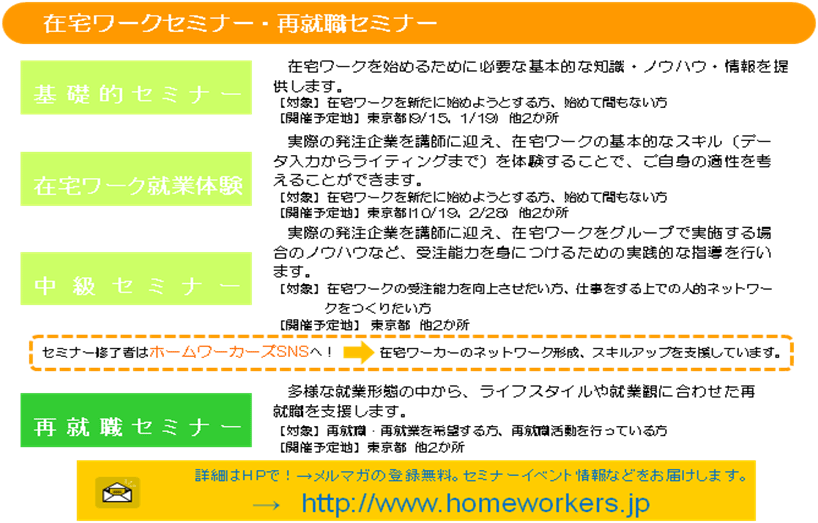
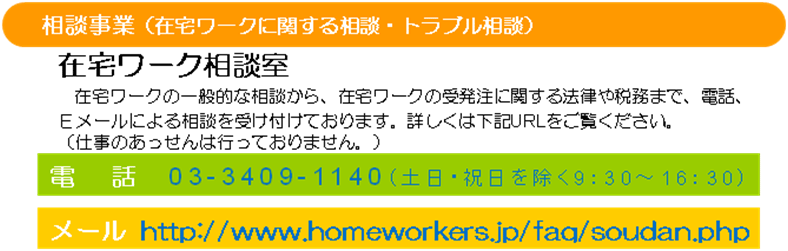
在宅ワークに関する施策の情報は厚生労働省ホームページをご覧下さい。
○ ガイドラインの全文、解説が掲載されています。
○ ハンドブック等の資料をダウンロードすることができます。
○ ホームワーカーズウェブにリンクしています。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/zaitaku/index.htm
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課)