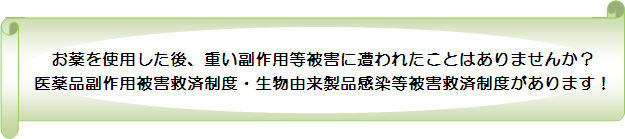医療関係者の方向けの専門誌や病院を訪れた国民の皆様の目に触れる雑誌において制度の丁寧な説明記事を掲載する、学会や地方自治体へ積極的に出向き説明を行う、交通機関、医療機関にポスターを掲出するなどの取組を行っています。

人の健康や生命に欠かせないものである医薬品は、十分な注意を払って正しく使用したとしても、時として重い副作用や感染等被害をもたらすことがあります。
病気の治療に使用した医薬品により重い健康被害に遭われた患者さんなどに対し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が救済給付を行っています。
1 救済制度の趣旨
医薬品は、今日の医療上、必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献していることは言うまでもありません。
しかし、医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものであり、副作用や感染等の予見可能性には限度があるなど、医薬品の特殊性から、その使用に当たり、万全の注意を払い、最新の科学的知見に基づく安全対策を講じたとしても、副作用や感染等を完全に防止することは困難です。また、これら副作用や感染等による健康被害について、民事訴訟においては、その責任を追及することが難しく、多大な労力と時間が必要となる場合があります。
こうしたことから、医薬品副作用被害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度(救済制度)は、製薬企業の社会的責任に基づく共同事業として、医薬品や生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用又は感染等による健康被害者の迅速な救済を図ることを目的として創設された法律に基づく公的な制度であり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施しています。
2 救済制度の内容
制度の対象となる方
病院・診療所で処方された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正な目的で適正に使用し、あるいは血液製剤などの生物由来製品を適正な目的で適正に使用した後に、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けられた方。
(注意)
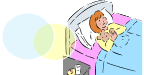
- 昭和55年5月1日以降に使用した医薬品による副作用被害が対象となります。
- 平成16年4月1日以降に使用した生物由来製品介した感染等被害が対象となります。
救済給付の種類及び内容など
| 給付の種類 | 給付の内容 | 給付額 | 請求期限 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療費 | 副作用又は感染等による健康被害の治療に要した費用について自己負担分を補償するもの。 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 | 医療費の支払いのあったときから5年(※1) | ||||||||||
| 医療手当 | 副作用又は感染等による健康被害の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付するもの。 |
|
医療のあった日の属する月の翌月から5年(※1) | ||||||||||
| 障害年金 | 副作用又は感染等により一定程度の障害を負った18歳以上の方の生活保障等を目的として給付するもの。 | 1級の場合 年額 2,720,400円(月額226,700円) 2級の場合 年額 2,175,600円(月額181,300円) |
請求の期限はありません。 | ||||||||||
| 障害児養育年金 | 副作用又は感染等により一定程度の障害を負った18歳未満の方を養育する方に対して給付するもの。 | 1級の場合 年額 850,800円(月額 70,900円) 2級の場合 年額 680,400円(月額 56,700円) |
請求の期限はありません。 | ||||||||||
| 遺族年金 | 生計を維持する方が副作用又は感染等により亡くなられた場合に、その遺族の方の生活の立て直し等を目的として給付するもの。 | 年額2,378,400円(月額198,200円)を10年間 (ただし、亡くなられた方本人が障害年金を受けていた場合は、その期間が7年に満たないときは10年からその期間を引いた期間が給付期間となり、7年以上のときは3年間の給付となります。) |
亡くなられたときから5年(※2) | ||||||||||
| 遺族一時金 | 生計維持者以外の方が副作用又は感染等により亡くなられた場合に、その遺族の方に対するお見舞いを目的として給付するもの。 | 7,135,200円 (ただし、遺族年金が支給されていた場合には、当該支給額を控除した額) |
亡くなられたときから5年(※2) | ||||||||||
| 葬祭料 | 副作用又は感染等により亡くなられた方の葬祭に伴う出費に着目して給付するもの。 | 201,000円(※3) | 亡くなられたときから5年 (※2) |
(※1)平成20年5月1日以降。同年4月30日までに支払った医療費や入院に係る医療手当の請求期限は2年となります。
(※2)医薬品等により亡くなられた方が、当該医薬品等による疾病又は障害について医療費・医療手当、障害年金又は障害児養育年金を受けていた場合は、亡くなられたときから2年となります。
(※3)平成22年3月31日以前に亡くなられた方に係る葬祭料の額は異なりますので、詳細はお問い合わせください。
請求から給付までの流れ
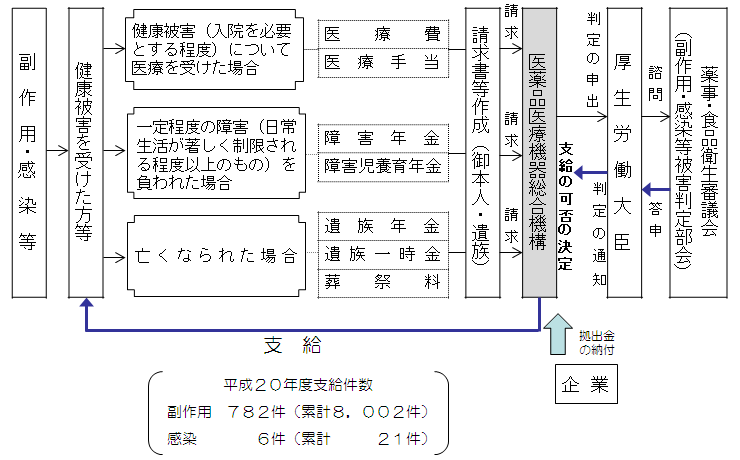
請求の御相談先
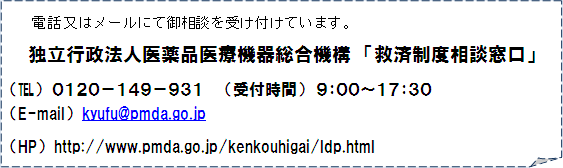
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の決定に不服がある方へ
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行った決定の内容に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内に、厚生労働大臣に対し、審査を申し立てることができます。
申立て手続に関する御相談は、厚生労働省医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室(内線2718)で承っております。
3 救済制度の周知に関する取組
医薬品副作用被害救済制度は、近年、給付件数が伸びてきており、その役割も大きくなってきているところです。
給付件数の推移
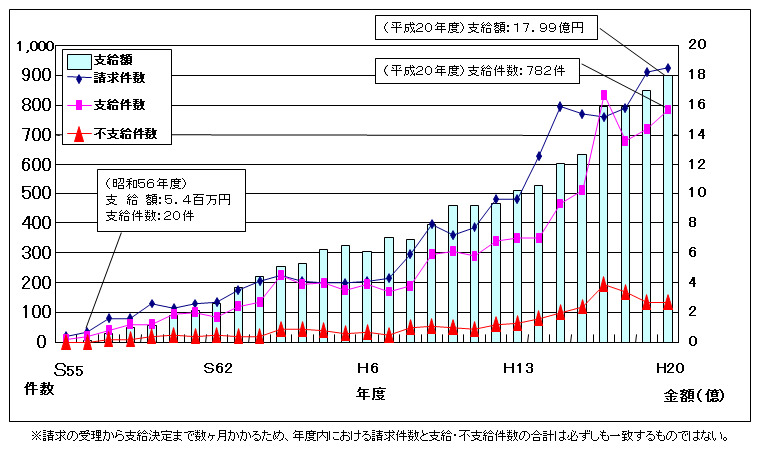
しかし、救済制度に関する認知調査結果によると、まだまだよく知られていないという状況が示されています。そのため、必要な場合に制度が適切に活用されるよう、厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、国民の皆様及び医療関係者の方に向けて広く周知する取組を行っています。
<厚生労働省における取組>
国民の皆様及び医療関係者の方へ直接制度が周知されるように努めています。
医療費・医療手当、障害年金等が支給される場合があります!
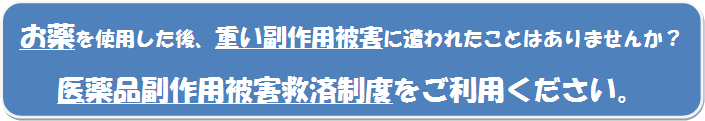
お薬は正しく使ってもまれに重い副作用被害を引き起こすことがあります。
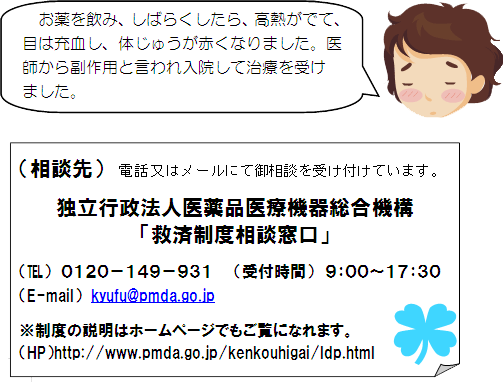
|
医薬品による重い副作用被害に対して、治療にかかった医療費や障害を負った場合の年金などが支給される場合があります。平成16年4月から血液製剤などの生物由来製品を介した感染等による健康被害についても救済の対象となっています。 一部、制度の対象にならないお薬があります。 もしかして、と思われたら、左記相談先まで、お気軽に御相談ください。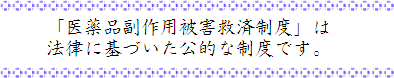
|
また、特に医療関係者の方に本制度を知っていただくことが副作用等被害に遭われた方への周知につながることから、厚生労働大臣に対し副作用等報告を行う医療関係者の方へ本制度のリーフレットを配布するとともに、医療関係者の方から副作用等被害に遭われた可能性のある患者の方への本制度の紹介をお願いしています。