社会保障カード(仮称)について
1 社会保障カードについて
現在、厚生労働省は、「社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会」を開催し、社会保障制度全体を通じた情報化の共通基盤として、社会保障カード(仮称。以下同じ。) の実現に向けた検討を行っています。
このカードは、年金手帳・健康保険証・介護保険証の役割を果たし、年金記録等の確認を可能にするものとして、平成23年度中を目途に導入することとされています。
2 社会保障カードにより実現されること
社会保障カードが、(1)情報アクセスの基盤、(2)情報連携の基盤としての役割を果たすことにより、例えば、次のようなことが可能となります。
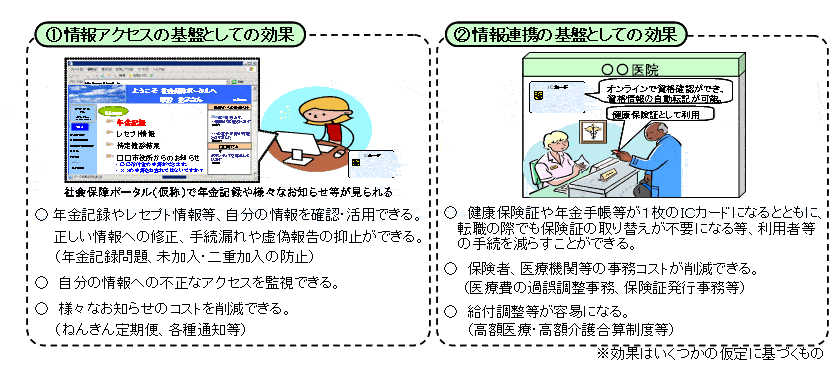
3 社会保障カードの仕組みについて
(1)社会保障カードの仕組みのイメージ
社会保障カードの実現は、2で述べたように、事務の効率化や国民の利便性の向上などのメリットをもたらしますが、そのメリットを実現するための仕組みを構築するに当たっては、プライバシーの侵害・情報の一元的管理に関する利用者の不安を極力解消するとともに、将来的な用途の拡大に対応できるものとする必要があります。
以下、このような観点から検討されている社会保障カードの仕組みのイメージを紹介します。
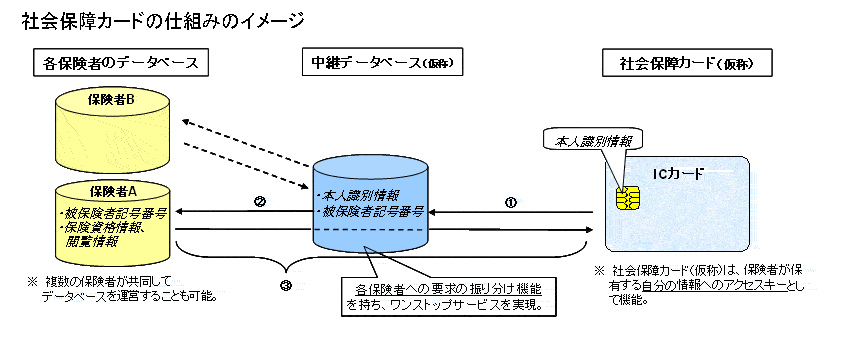
・ 社会保障カードについて
社会保障カードには安全性の高いICカードを活用し、ICチップには、年金・医療・介護といった現行の社会保険制度の被保険者記号番号等とリンクした本人識別情報(各制度、各保険者をまたがって本人を特定するための情報)のみを収録します。
・ 中継データベースについて
利用者からの要求の振り分け機能を持つ中継データベース(仮称。以下同じ。)を構築します。これにより、現在、各保険者が保有している利用者の保険資格情報や年金記録等の閲覧情報を一元的に管理した、いわゆる「メガ・データベース」は作らず、現行どおり各保険者がそれぞれ情報を保有することとしたままで、ワンストップサービスを実現することができます。また、この中継データベースに新たなリンクを追加すれば、カードのICチップを書き換えることなく、用途を拡大することが可能です。
利用者は、この社会保障カードの仕組みを活用し、例えば、次のように年金記録等の情報を閲覧します。
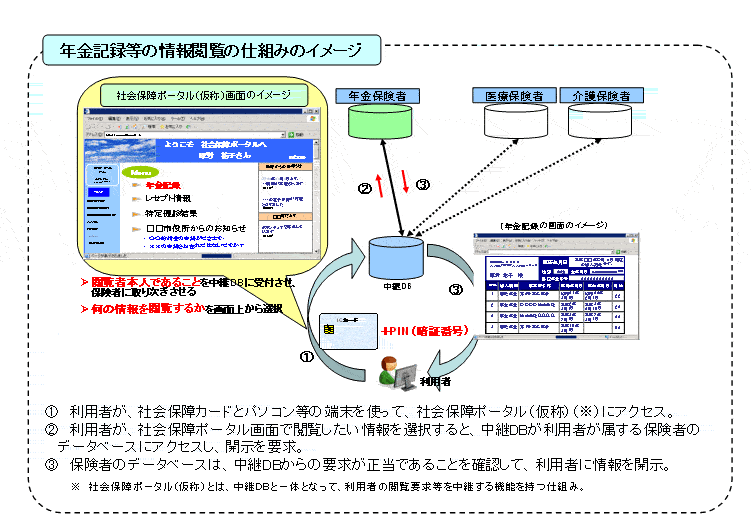
4 今後の予定
社会保障カードの仕組みの実現のためには、検討すべき多くの課題があります。
厚生労働省としては、今後も引き続き、様々な課題を検証しながら、社会保障カードの実現に向けた検討を進めることとしており、平成21年度においては、社会保障カードに関する実証実験を行う予定です。その実施の状況やサービスの体験者の声を踏まえながら、検討を行っていきます。
5 政策レポートをご覧いただいたみなさまへ
社会保障カードの仕組みをより良いものとしていくため、社会保障カードに関するご意見をお寄せいただきたいと考えています。詳しくは、こちら(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/card/index.html)をご覧ください。
