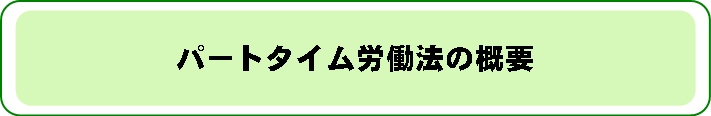〜 平成20年4月1日に改正法が施行されました 〜
パートタイム労働法の対象となる「パートタイム労働者」とは |
||
|
パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。 「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、名称の如何にかかわらず、上記に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。 「通常の労働者」とは、同種の業務に従事する「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。 同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が通常の労働者となります。 同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者もフルタイムの基幹的な働き方をしている労働者もいない場合は、事業所における1週間の所定労働時間が最長の労働者が通常の労働者となります。 |
||
 |
通常の労働者とパートタイム労働者の均衡の考え方 |
パートタイム労働者の待遇は、一般に通常の労働者と比較して働きや貢献に見合ったものとならず低くなりがちであるという状況があります。そこで、パートタイム労働法は、パートタイム労働者の就業の実態を考慮して雇用管理の改善に関する措置を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇を確保することを目指しています。(第3条)
具体的には、法はパートタイム労働者の就業の実態が多様であることから、「職務の内容」、「人材活用の仕組み・運用など」「労働契約期間が無期かどうか」といった就業の実態を表す要素の違いに応じてそれぞれ法に定める措置を講ずることにより均衡のとれた待遇の確保を図ることとしています。
厚生労働省(都道府県労働局)
「 職 務 の 内 容 が 同 じ 」 か ど う か
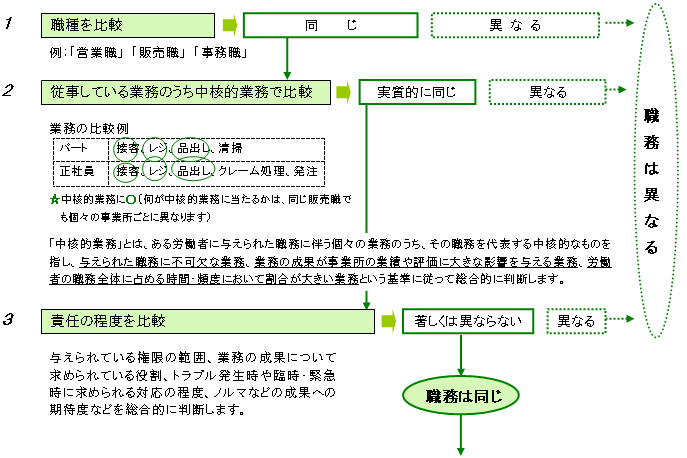
「 人 材 活 用 の 仕 組 み や 運 用 な ど が 同 じ 」 か ど う か
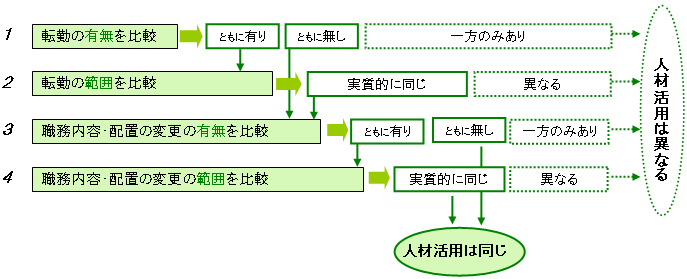
〔各条文の説明〕
- 労働条件に関する文書の交付等(第6条)
-
〔対象:すべてのパートタイム労働者〕
1 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければならない。
2 事業主は、1の3つの事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩、休日、休暇」「賃金」「退職に関する事項」などについては、文書で明示することが義務付けられています(違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。)。
上記に加えて、パートタイム労働法ではパートタイム労働者を雇い入れたときは、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、パートタイム労働者1人につき契約ごとに10万円以下の過料に処せられます。
「雇い入れたとき」とは、初めて雇い入れたときのみならず、労働契約の更新時も含みます。
上記3つの事項以外については、文書の交付などによる明示に努めることとされています(第6条第2項)。
◆ 「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を明示する際の文書の作成例は厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)をご参照ください。
◆ 昇給や賞与の支給を事業所の業績やパートタイム労働者の勤務成績、勤続年数などによって行っており、支給要件を満たさない場合には支給されない可能性があるときは、制度「有り」とした上で、「業績により不支給の場合あり」や「勤続○年未満は不支給」など支給されない可能性があることを明記してください。
- 就業規則の作成の手続(第7条)
-
事業主は、パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
就業規則の作成又は変更に当たっては、労働基準法第90条により、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければならないこととされていますが、パートタイム労働者に適用される就業規則の作成又は変更に当たっては、パートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くことが努力義務とされています。
- 差別的取扱いの禁止(第8条)
-
〔対象者:通常の労働者と職務の内容及び人材活用の仕組みや運用などが同じであり、契約期間が無期契約(実質無期を含む)であるパートタイム労働者〕
1 事業主は、職務の内容、退職までの長期的な人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している者については、パートタイム労働者であることを理由として、その待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
2 1の期間の定めのない労働契約には、反復更新によって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる有期契約を含むものとする。
差別的取扱いの禁止の対象となるパートタイム労働者は、通常の労働者と就業の実態が同じと判断され、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他のすべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
◆ 賃金の支給額については、所定労働時間が短いことに基づく合理的な差異や、また個人の勤務成績により生じる差異によるものについては許容されますが、家族手当や通勤手当のように、一般的に所定労働時間の長短に関係なく支給されるものについては、通常の労働者と同様に支給する必要があります。
◆ 平成20年4月1日以降、要件を満たすパートタイム労働者についての差別的取扱いが禁止されますが、20年4月1日以降支給される退職金や賞与について、20年3月31日以前の働き・貢献を評価して支給されるようなものとなっている場合には、3月31日以前の分も含めて評価し、支給しなければなりません。これは、退職金等の支給を実際に受ける時点において差別的取扱いとならないようにする必要があるからです。
- 賃金の決定方法(第9条)
-
〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕
1 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(基本給、賞与、役付手当等)を決定するように努めるものとする。
〔対象者:職務の内容と一定期間の人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者〕
2 事業主は、職務の内容、人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者については、その同一である一定の期間は、その通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。
パートタイム労働者の賃金を客観的な基準に基づかない事業主の主観や、「パートタイム労働者は一律○○円」といったパートタイム労働者だからという理由で一律に決定するのではなく、通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力義務とされています(第9条第1項)。
さらに、通常の労働者と比較して、パートタイム労働者の職務の内容と一定の期間の人材活用の仕組みや運用などが同じ場合、その期間について、賃金を通常の労働者と同一の方法で決定することが努力義務とされています(第9条第2項)。
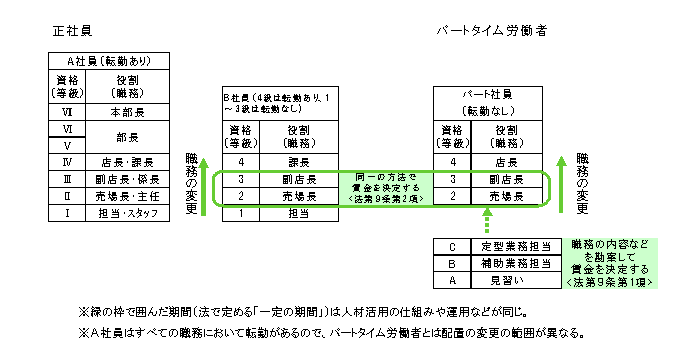
◆ 第9条第1項について、職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等のどの要素を勘案するかは事業主に委ねられていますが、第13条により事業主には説明責任が課せられていることに留意する必要があります。
- 教育訓練(第10条)
-
〔対象者:通常の労働者と職務の内容が同じパートタイム労働者〕
1 事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、その通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容が同じパートタイム労働者が既にその職務に必要な能力を有している場合を除き、そのパートタイム労働者に対しても実施しなければならない。
〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕
2 事業主は、1のほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力及び経験等に応じ、そのパートタイム労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。
パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じ場合、その職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を身につけるために通常の労働者に実施している教育訓練については、パートタイム労働者が既に必要な能力を身につけている場合を除き、そのパートタイム労働者に対しても通常の労働者と同様に実施することが義務付けられています。
上記の訓練以外の訓練、例えばキャリアアップのための訓練などについては、職務の内容の違いの如何にかかわらず、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力及び経験などに応じ実施することが努力義務とされています。
- 福利厚生(第11条)
-
〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、その雇用するパートタイム労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。
福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室について、通常の労働者が利用している場合はパートタイム労働者にも利用の機会を与えるよう配慮することが義務付けられています。
これは、例えば、給食施設の定員の関係で事業所の労働者全員に施設の利用の機会を与えられないような場合に、増築などをして全員に利用の機会が与えられるようにすることまで求めるものではありませんが、施設の利用の対象が正社員に限定されているならパートタイム労働者も利用できるようにし、例えば、個々の労働者の昼食時間帯をずらし、利用しやすくするなど具体的な措置を求めるものです。
8条〜11条をまとめると・・・
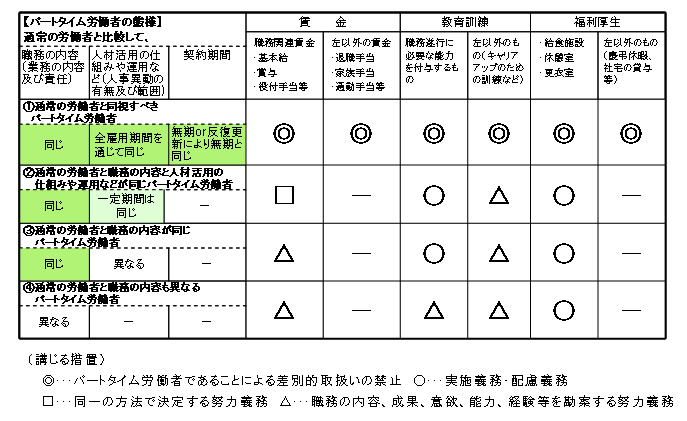
- 通常の労働者への転換(第12条)
-
〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならない。
・ 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
・ 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
・ パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
・ その他通常の労働者への転換を推進するための措置
パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、上記のいずれかの措置を講じることが義務付けられています。
転換を推進するためにも、どのような措置を講じているか、事業所内のパートタイム労働者にあらかじめ広く周知してください。
◆ パートタイム労働者から通常の労働者への転換の要件として、勤続期間や資格などを課すことは、事業所の実態に応じたものであれば問題ありませんが、必要以上に厳しい要件を課した転換の仕組みを設けている場合は、法律上の義務を履行しているとはいえない場合もあります。
◆ パートタイム労働者からいわゆる契約社員へ転換する制度を設け、さらに、契約社員から正規型の労働者へ転換する制度を設ける、といった複数の措置を講じ、正規型の労働者へ転換する道が確保されている場合も本条を履行したことになります。
- 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明(第13条)
-
〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕
事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない。
パートタイム労働者から求められたとき、事業主はそのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務付けられています。
説明義務が課せられる具体的な内容は、パートタイム労働法において事業主が措置を講じることとされている以下の事項(義務及び努力義務事項)です。
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置
◆ 説明に当たっては、例えば賃金の決定方法についての説明を求められた場合、「あなたはパートタイム労働者だから賃金は○○円だ。」という説明では責任を果たしているとは言えません。
他方、[パートタイム労働者が納得するまで説明すること]まで求めているものではありません。
- 指針(第14条)
-
厚生労働大臣は、事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。
第14条に基づき定められている指針では、事業主がパートタイム労働者を雇う上での基本的考え方として、次のように規定しています。
1 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、労災保険法などの労働関係法令を遵守してください
2 労働条件を合理的な理由なく一方的に不利益に変更することは許されないことに留意してください
3 フルタイムで働く「パート」と呼ばれる方にも法の趣旨が考慮されるべきであることに留意してください
4 パートタイム労働者の多くは、フルタイムの労働者に比べて一般的に時間の制約が厳しく、残業も困難であるという事情を十分考慮して労働時間・労働日の設定・変更を行うとともに、できるだけ所定労働時間を超えた残業、所定労働日以外の日の労働をさせないよう努めてください
5 パートタイム労働法第9条で定める職務関連賃金以外の賃金、例えば退職手当、通勤手当などについても、パートタイム労働者の就業の実態や通常の労働者との均衡を考慮して定めるよう努めてください
6 パートタイム労働法第11条で定める福利厚生の措置についても、パートタイム労働者の就業の実態や通常の労働者との均衡などを考慮して取り扱うよう努めてください
7 パートタイム労働法第13条で説明が求められている事項以外の事項についても説明するよう努めてください
パートタイム労働者の雇用管理の改善などの措置を講じるときは、パートタイム労働者の意見を聴く機会を設けるなどの適当な方法を工夫するように努めてください
パートタイム労働法第19条で自主的な解決を図ることが努力義務となっている事項以外に係る苦情についても事業所内で自主的に解決を図るよう努めてください
8 パートタイム労働法第7条に定める過半数代表者であること、もしくは過半数代表者になろうとしたこと、または、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益に取り扱わないようにしてください
パートタイム労働者が法第13条に基づく説明を求めたことを理由として不利益に取り扱わないようにしてください
9 短時間雇用管理者を選任したときは、短時間雇用管理者の氏名を事業所の見やすい場所に掲示するなどして、パートタイム労働者への周知に努めてください
- 短時間雇用管理者の選任(第15条)
-
事業主は、常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。
パートタイム労働者を常時10人以上雇用する事業所ごとに、パートタイム労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間雇用管理者」を選任することが努力義務となっています。
「短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものとされています。
(1) パートタイム労働法やパートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
(2) 労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。
- 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告(第16条)
-
1 厚生労働大臣は、パートタイム労働者の雇用管理の改善等を図るために必要があると認めるときは、パートタイム労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
厚生労働大臣から委任を受けた都道府県労働局長は、法及び指針によって事業主が講ずべき措置とされている事項について、これが十分に講じられていないと考えられる場合には、事業主に対し、報告を求め必要に応じて助言、指導又は勧告を行うこととしています。
また、全国的に重要である事案については、厚生労働大臣が助言等を行うこととしています(施行規則第8条)。
- 苦情の自主的解決(第19条)
-
事業主は、パートタイム労働者からの苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に苦情の処理をゆだねるなどして、自主的な解決を図るように努めるものとする。
パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内の苦情処理制度を活用するほか、人事担当者や短時間雇用管理者が担当するなどして、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務となっています。
- 都道府県労働局長による紛争解決の援助(第21条)
-
都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
パートタイム労働法で事業主の義務として課せられる事項に関する紛争の当事者であるパートタイム労働者、事業主の双方又は一方から紛争の解決のための援助を求められた場合、都道府県労働局長が助言、指導又は勧告を行うことによって紛争の解決の援助を行う仕組みが整備されています。
- 調停(第22条)
-
都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、「均衡待遇調停会議」に調停を行わせるものとする。
パートタイム労働法で事業主の義務として課せられる事項に関する紛争の当事者であるパートタイム労働者、事業主の双方又は一方から申請があった場合で、都道府県労働局長がその紛争の解決に調停が必要と認めた場合、学識経験者などの専門家で構成される第三者機関である「均衡待遇調停会議」に調停を行わせる仕組みが整備されています。
「均衡待遇調停会議」は、必要に応じ当事者や参考人から意見を聴いた上で、調停案を作成し、当事者に対して受諾勧告を行うことができます。
◆ 第19条、第21条、第22条の対象となる苦情・紛争は、パートタイム労働法において事業主が措置を講じることが義務とされている事項及び差別的取扱いの禁止です。
◆ パートタイム労働者が援助を申し出たこと、調停を申請したことを理由として解雇、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の打ち切りなど不利益取扱いをすることは禁止されています。
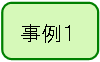 |
パートタイム労働者Aが勤務する事業所では、正社員への転換制度が設けられていますが、要件が「正社員としての能力がある者」とあいまいなものであり、制度が設けられて○年が経過した現在も、未だにパートタイム労働者から正社員に登用された者は一人もいません。Aは、実効性のある転換制度にしてもらいたいと、事業主に主張しましたが、事業主は法違反ではないとの主張を繰り返すばかりで対応してくれません。そこで、Aは労働局長から具体的なアドバイスをしてもらいたいと第21条に基づく都道府県労働局長の援助の申出を行いました。 |
||
|
|||
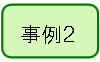 |
パートタイム労働者Bは、パートタイム労働者であることを理由に解雇されましたが、解雇前の職務内容は正社員と同じであり、人材活用の仕組み・運用なども正社員と同じで、契約期間も定められていませんでした。元の職場への復職は望みませんが、違法な解雇に対する金銭補償を求めたいと第22条に基づく調停の申請がありました。 |
||
|
|||
| 労働局名 | 電話番号 | 労働局名 | 電話番号 | 労働局名 | 電話番号 |
| 北海道 | 011-709-2715 | 石 川 | 076-265-4429 | 岡 山 | 086-224-7639 |
| 青 森 | 017-734-4211 | 福 井 | 0776-22-3947 | 広 島 | 082-221-9247 |
| 岩 手 | 019-604-3010 | 山 梨 | 055-225-2859 | 山 口 | 083-995-0390 |
| 宮 城 | 022-299-8844 | 長 野 | 026-227-0125 | 徳 島 | 088-652-2718 |
| 秋 田 | 018-862-6684 | 岐 阜 | 058-263-1220 | 香 川 | 087-811-8924 |
| 山 形 | 023-624-8228 | 静 岡 | 054-252-5310 | 愛 媛 | 089-935-5222 |
| 福 島 | 024-536-4609 | 愛 知 | 052-219-5509 | 高 知 | 088-885-6041 |
| 茨 城 | 029-224-6288 | 三 重 | 059-226-2318 | 福 岡 | 092-411-4894 |
| 栃 木 | 028-633-2795 | 滋 賀 | 077-523-1190 | 佐 賀 | 0952-32-7218 |
| 群 馬 | 027-210-5009 | 京 都 | 075-241-0504 | 長 崎 | 095-801-0050 |
| 埼 玉 | 048-600-6210 | 大 阪 | 06-6941-8940 | 熊 本 | 096-352-3865 |
| 千 葉 | 043-221-2307 | 兵 庫 | 078-367-0820 | 大 分 | 097-532-4025 |
| 東 京 | 03-3512-1611 | 奈 良 | 0742-32-0210 | 宮 崎 | 0985-38-8827 |
| 神奈川 | 045-211-7380 | 和歌山 | 073-421-6157 | 鹿児島 | 099-222-8446 |
| 新 潟 | 025-234-5928 | 鳥 取 | 0857-29-1709 | 沖 縄 | 098-868-4380 |
| 富 山 | 076-432-2740 | 島 根 | 0852-31-1161 |
○お問い合わせ先
雇用均等・児童家庭局 短時間・在宅労働課