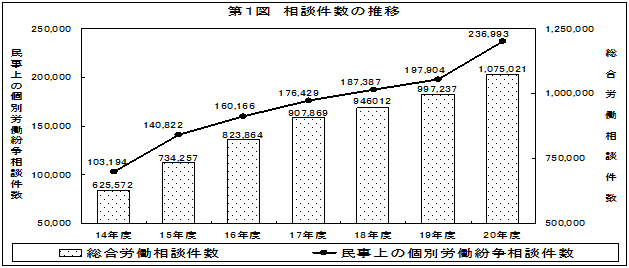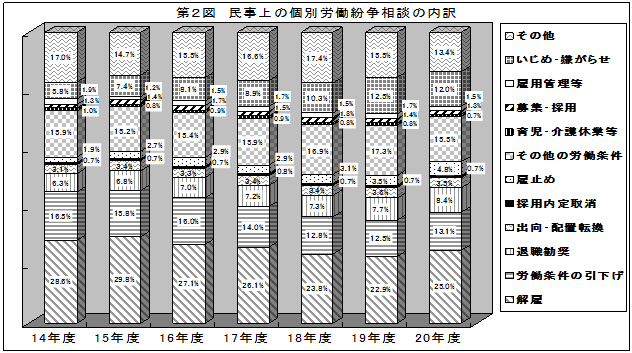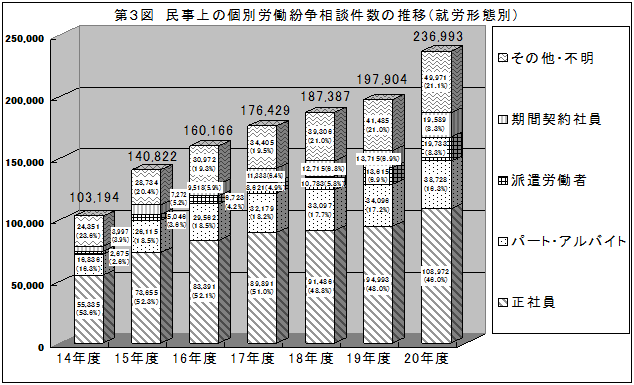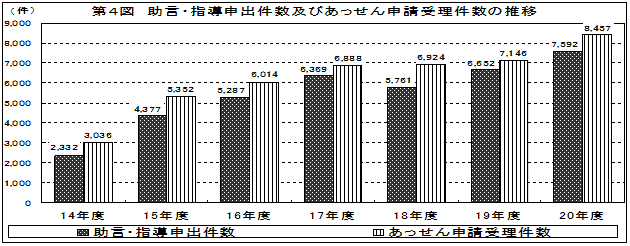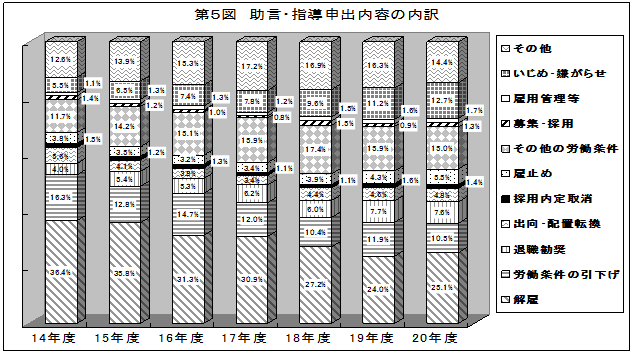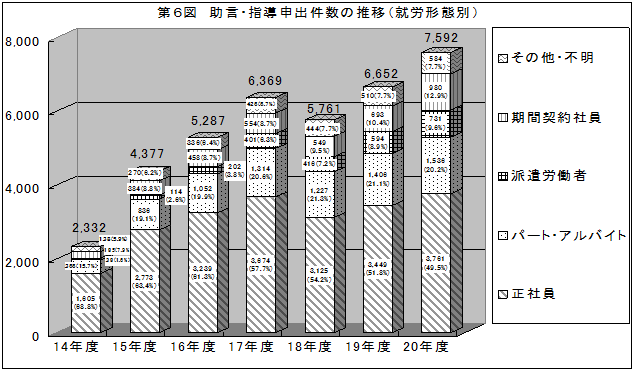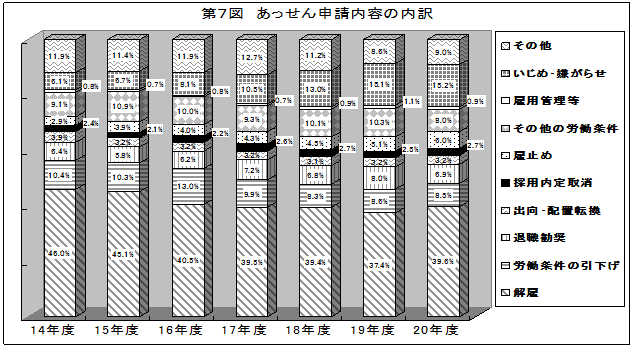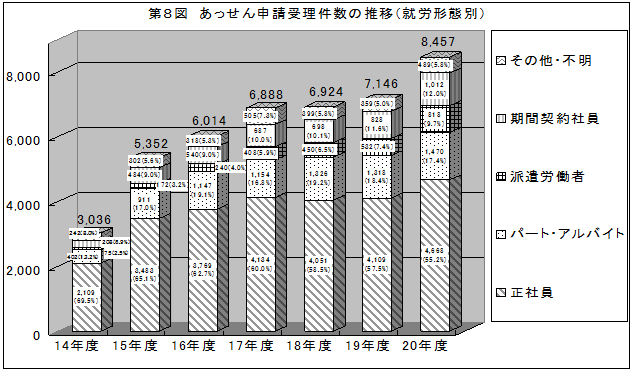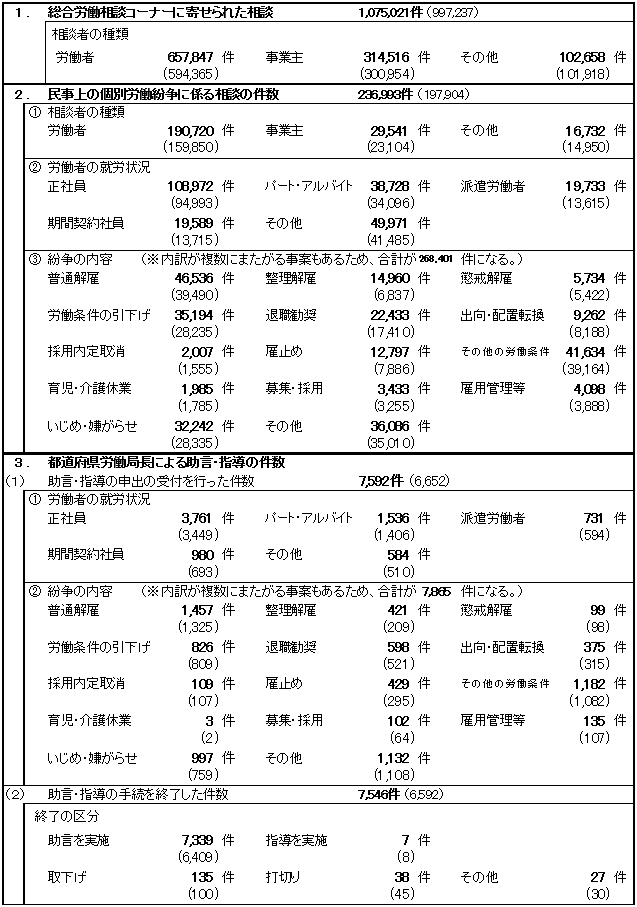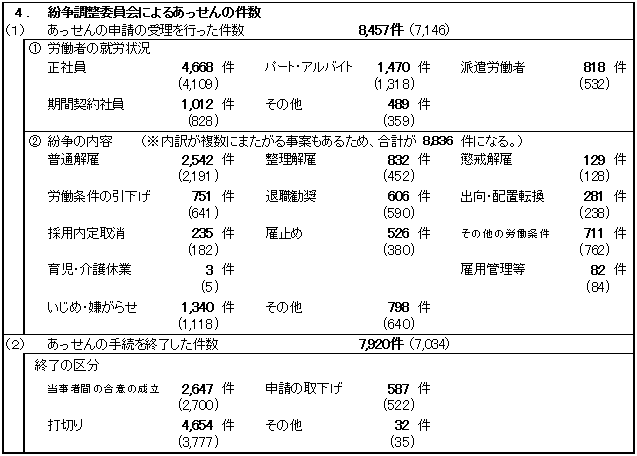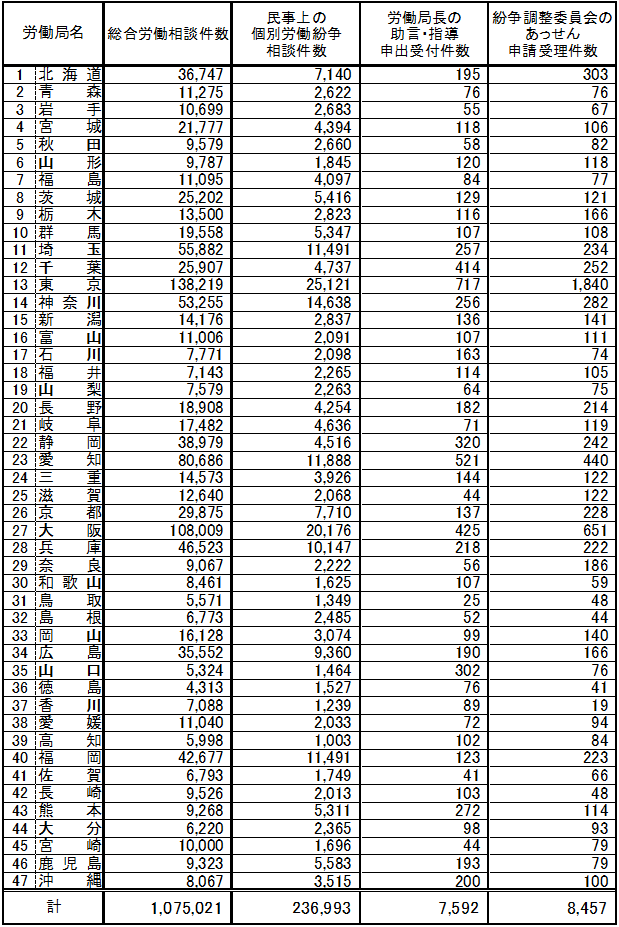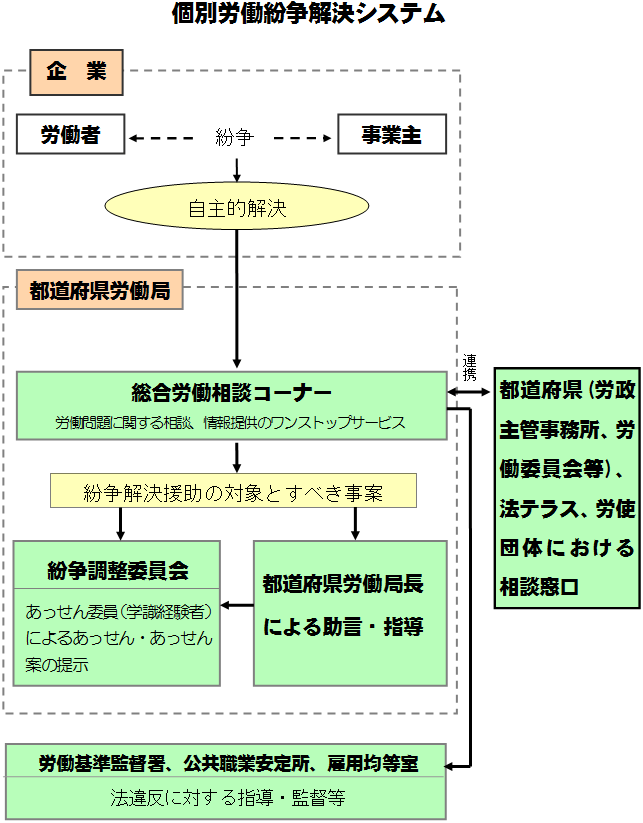担
当 |
平成21年5月22日
大臣官房地方課労働紛争処理業務室
(電話) 03−5253−1111(内線7738)
(夜間直通) 03−3502−6679
|
《 平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況 》
個別労働紛争解決制度の利用が大幅に拡大
| ・総合労働相談件数 | 約108万件 |
| ・民事上の個別労働紛争相談件数 | 約24万件 |
| ・助言・指導申出件数 | 約7,600件 |
| ・あっせん申請受理件数 | 約8,500件 |
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」施行状況 〜平成20年度〜
| 1.総合労働相談件数 |
: | 1,075,021 件( 7.8%増 * ) |
| 2.民事上の個別労働紛争相談件数 |
: | 236,993 件( 19.8%増 * ) |
| 3.助言・指導申出受付件数 |
: | 7,592 件( 14.1%増 * ) |
| 4.あっせん申請受理件数 |
: | 8,457 件( 18.3%増 * ) |
【 * 増加率は、平成19年度実績と比較したもの。】
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から今年で8年を迎えるが、人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化、昨年度後半以降の経済・雇用情勢の急速な悪化等を反映し、全国の総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談の件数は約108万件、民事上の個別労働紛争に係る相談件数も約24万件となり、依然として増加を続けている。
また、助言・指導申出受付件数は約7,600件、あっせん申請受理件数も約8,500件と昨年度実績を大きく上回り、制度の利用が大幅に拡大した。
【参考】
平成20年労働関係民事通常訴訟事件の新受件数 2,441 件(平成19年 2,246件)
平成20年労働審判事件の新受件数 2,052 件(平成19年 1,494件)
(ともに全国地方裁判所)
『個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(別添4、5)』に基づく、個別労働紛争解決制度の平成20年度の施行状況は以下のとおりである(概要は別添2、都道府県労働局別一覧は別添3)。
1.相談受付状況
各都道府県労働局、労働基準監督署内、駅近隣の建物などに、労働問題に関するあらゆる相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置しているところであり、平成20年度1年間に寄せられた相談は107万5,021件と平成19年度比で約8万件(7.8%)増加した。
このうち、労働基準法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別労働紛争に関するものが23万6,993件であり、平成19年度比で約4万件(19.8%)増加した。
制度発足以降確実に件数が増えており、平成20年度は増加件数がさらに拡大した。(第1図)
平成20年度の民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は、解雇に関するものが最も多く25.0%、労働条件の引下げに関するものが13.1%、いじめ・嫌がらせに関するものが12.0 %と続いており、解雇、労働条件の引下げ、退職勧奨等に関するものの割合が特に増加した。(第2図)
なお、解雇に関する相談の内訳を見ると、整理解雇に関するものの伸びが特に著しくなっている。(別添2参照)
また、民事上の個別労働紛争に係る相談者は、労働者(求職者)が80.5 %と大半を占めており、事業主からの相談は12.5%であった。
労働者の就労状況は、正社員が46.0%と最も多いが、パート・アルバイトが16.3 %、派遣労働者が8.3%、期間契約社員も8.3%を占めており、昨年度と比較すると正社員及びパート・アルバイトの割合が若干減少し、派遣労働者、期間契約社員の割合が増加した。(第3図)
2.都道府県労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせんの受付状況
平成20年度の当該制度に係る助言・指導申出件数は7,592件で、平成19年度比で14.1%の増加、あっせん申請受理件数も8,457件で、18.3%の増加とそれぞれ大幅に増加した。(第4図)
3.都道府県労働局長による助言・指導の主な内容
助言・指導の申出の主な内容は、解雇に関するものが最も多く25.1%、いじめ・嫌がらせに関するものが12.7%、労働条件の引下げに関するものが10.5 %と続いており、いじめ・嫌がらせに関するものの割合が引き続き増加しているほか、解雇に関するものの割合が増加した。(第5図)
申出人は、労働者が98.7%と大半を占めるが、事業主からの申出も100件と1.3%あった。事業所の規模は、10〜49人が28.9%と最も多く、次いで10人未満18.4%、100〜299人が11.9%となっており、労働組合のない事業所の労働者が66.1%である。
労働者の就労状況は、正社員が49.5%と最も多く、パート・アルバイトが20.2%と続いているが、期間契約社員が12.9%、派遣労働者が9.6%とこれらの労働者の全体に占める割合が増加している。(第6図)
申出を受け付けた事案の都道府県労働局における処理状況をみると、平成20年度1年間に手続きを終了したものは7,546件である。このうち、助言・指導を実施したものは7,346件で97.3%、申出が取り下げられたものは135件で1.8%、処理を打ち切ったものは38件で0.5%となっている。処理に要した期間は、1ヶ月以内が96.1%となっている。
なお、助言・指導の実施事例は、別添1のとおりである。
4.紛争調整委員会によるあっせんの主な内容
あっせん申請の主な内容は、解雇に関するものが39.6%と最も多く、次いで、いじめ・嫌がらせに関するものが15.2%、労働条件の引下げに関するものが8.5%と続いており、解雇に関するものの割合が特に増加した。(第7図)
申請人は、労働者が8,320件で98.4%と大半を占めるが、事業主からの申請も128件で1.5%となっており、労使双方からの申請も9件で0.1%あった。事業所の規模は、10〜49人が30.5%と最も多く、次いで10人未満が18.7%、100人〜299人が11.9%となっている。また、労働組合のない事業所の労働者が70.5%である。
労働者の就労状況は、正社員が55.2%と最も多く、パート・アルバイトも17.4%と続いているが、期間契約社員が12.0%、派遣労働者が9.7%とこれらの労働者の全体に占める割合が増加している。(第8図)
申請を受理した事案の都道府県労働局における処理状況をみると、平成20年度1年間に手続きを終了したものは7,920件である。このうち、合意が成立したものは2,647件で33.4%、申請者の都合により申請が取り下げられたものは587件で7.4%、紛争当時者の一方が手続きに参加しない等の理由により、あっせんを打ち切ったものは4,654件で58.8%となっている。
処理に要した期間は、1ヶ月以内が54.1%、1ヶ月を超え2ヶ月以内が38.1%となっている。
なお、あっせんの実施事例は、別添1のとおりである。
【紛争調整委員会とは】
弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されている。この紛争調整委員会の委員(約320名)のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施するものである。
別添1
【助言・指導の例】
事例1: いじめ・嫌がらせに係る助言・指導 |
| 事案の概要 |
申出人は、直属の上司から業務指示と称して暴言等を受け、出勤が困難な状況にあるため、所属事業場の責任者に職場環境について相談をしたが、改善が見られない。仕事そのものは続けたいと考えているため、このような職場環境の改善のため、労働局長の助言・指導を申し出たもの。
労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と人事担当責任者が話し合いを行った結果、職場環境の改善がなされた。 |
助言・指導の
内容 |
客観的に状況が判断できる人事担当責任者に、申出人の主張を伝えた上で、パワーハラスメントに関しての法的整理を説明するとともに、それを踏まえ、本人と話し合うことを助言した。 |
事例2: 配置転換等に係る助言・指導 |
| 事案の概要 |
申出人は、現在勤務している事業場の業務縮小を理由として、勤務日数の大幅な削減を通告され、応じられない旨回答したところ、遠隔地の事業場での勤務を命じられた。当初の契約では他事業場での勤務は前提とされていなかったため、労働条件の変更の撤回を求め、労働局長の助言・指導を申し出たもの。 労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社で話し合った結果、従来の勤務地、勤務シフトで働くことができることとなった。 |
助言・指導の
内容 |
労働契約で定められた労働条件を使用者が一方的に変更することは原則としてできないこと、労働契約上勤務地が限定されている場合に、労働者の同意なく行った転勤命令は無効とされる場合があることを踏まえ、再度、申出人と話し合うことを助言した。 |
【あっせんの例】
事例1: 解雇(整理解雇)に係るあっせん |
| 事案の概要 |
申請人は、経営不振を理由として解雇されたが、自分が解雇されることの合理的理由もなく、かつ解雇回避の努力も見られなかったことから、解雇の撤回を求めて、あっせん申請を行ったもの。 |
あっせんの
ポイント |
あっせん委員が整理解雇に関する裁判における考え方を示し、双方の主張を整理し調整を行った結果、申請人の申出内容である職場復帰で合意が成立した。 |
事例2: 退職勧奨に係るあっせん |
| 事案の概要 |
申請人は、上司から会社の退職募集に応募するよう度重なる勧奨を受けたが、退職募集に応募する意思がない旨回答したところ、「応じないのであれば仕事はない。」と通告され、退職を余儀なくされた。上司の過度な退職勧奨により勤務の継続が困難になったことによって生じた精神的苦痛及び経済的損失に対する補償を求めて、あっせん申請を行ったもの。 |
あっせんの
ポイント |
あっせん委員が双方の主張を確かめ、当事者間の調整を行った結果、解決金○○万円を支払うことで双方の合意が成立した。 |
別添2
個別労働解決制度の運用状況(概要)
(平成20年4月1日〜平成21年3月31日)
※括弧内は平成19年度の実績
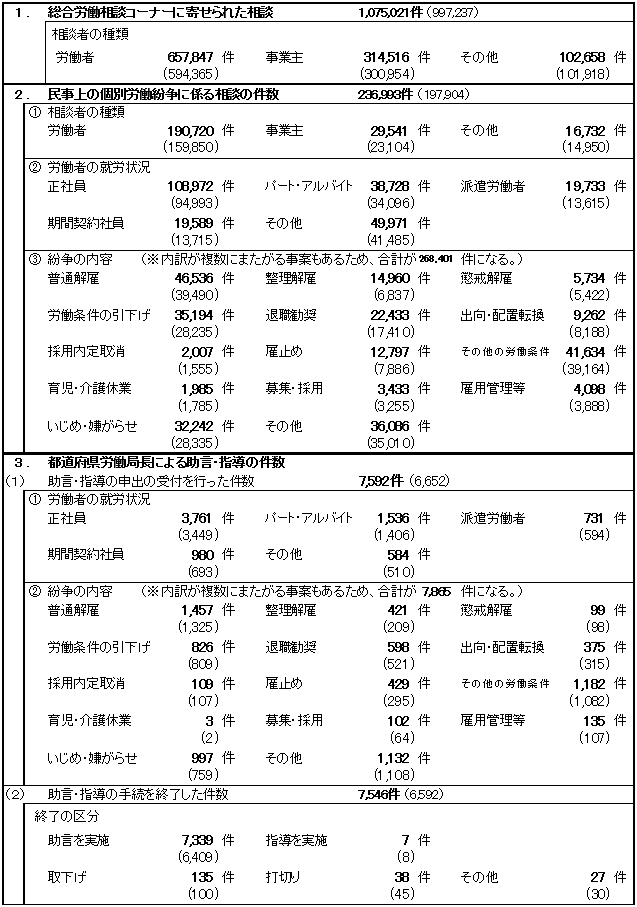
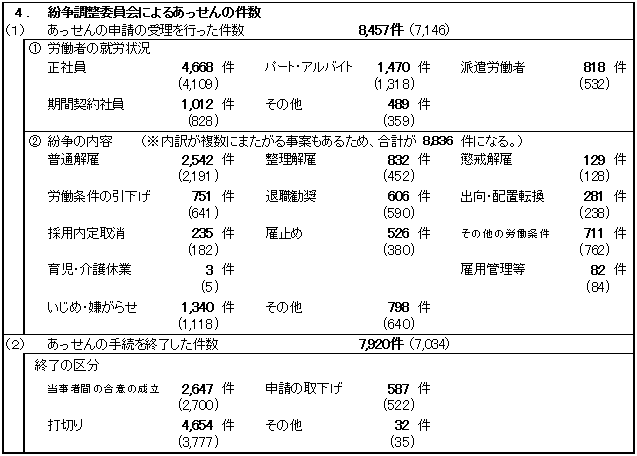
別添3
個別労働紛争解決制度の運用状況について
(平成20年4月1日〜平成21年3月31日)
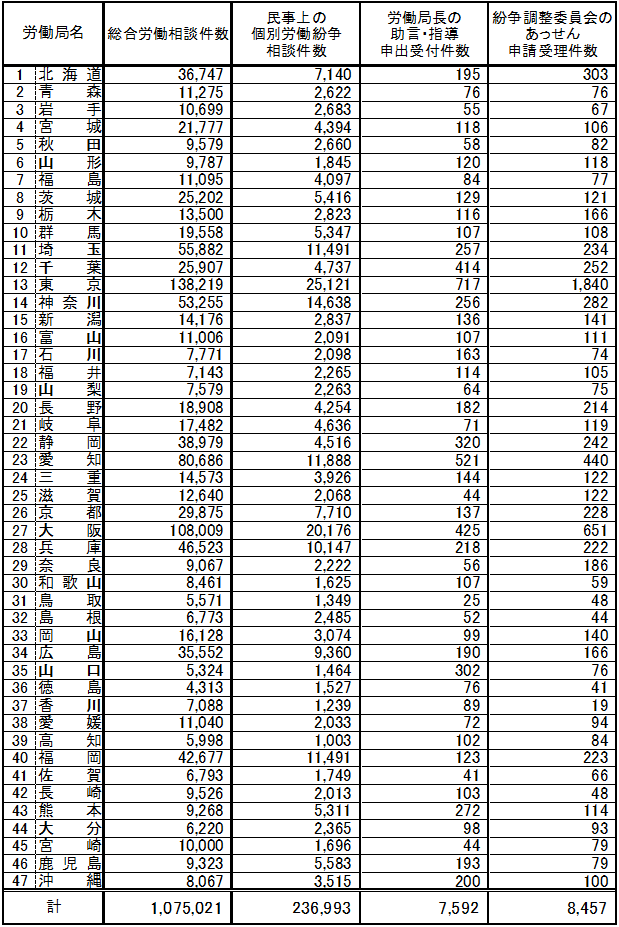
別添4
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要
1 趣旨
企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加していることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会のあっせん制度の創設等により総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。
2 概要
(1) 紛争の自主的解決
個別労働関係紛争が生じたときは、紛争の当事者は、自主的な解決を図るように努めなければならないものとする。
(2) 都道府県労働局長による情報提供、相談等
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の未然防止及び自主的な解決の促進のため、労働者又は事業主に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。
(3) 都道府県労働局長による助言及び指導
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。
(4) 紛争調整委員会によるあっせん
イ 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。
ロ 都道府県労働局に、紛争調整委員会を置くものとする。
ハ あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならないものとする。
ニ あっせん委員は、当事者等から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを当事者に提示することができるものとする。
(5) 地方公共団体の施策等
地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、労働者又は事業主に対し、情報提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとし、国は、地方公共団体の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
また、当該施策として都道府県労働委員会が行う場合には、中央労働委員会が、当該都道府県労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。
別添5