平成19年度厚生労働科学研究費補助金公募要項(二次)
I. 厚生労働科学研究費補助金の目的及び性格
厚生労働科学研究費補助金は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています。
応募された研究課題は、事前評価委員会において「専門的・学術的観点」や「行政的観点」等からの総合的な評価を経たのちに採択研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。
なお、この補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」(以下「補助金適正化法」という。)等の適用を受けます。補助金の目的外使用などの違反行為を行った者に対しては、補助金の交付決定取り消し、返還等の処分が行われますので十分留意して下さい。
平成19年度公募研究事業(二次)
|
※ 平成18年度まで及び本年度において既に採択されている研究課題と同一内容の研究は採択の対象となりません。
II. 応募に関する諸条件等
(1) 応募資格者
1)次のア及びイに該当する者(以下「主任研究者」という。)
ア.(ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者
(ア) 厚生労働省の施設等機関
(イ) 地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ) 学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ) 民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ) 研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人等
(カ) 研究を主な事業目的としている独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条の規定に基づき設立された独立行政法人及び特定独立行政法人
(キ) その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
イ. 研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果のとりまとめ、補助金の適正な執行を含む。)に関して全ての責任を負い、外国出張その他の理由により長期にわたってその責務を果たせなくなること、或いは定年等により退職し研究機関を離れること等の見込みがない者。
2)研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人
※ 不正経理等に伴う補助対象者の見直しについて
研究者が不正経理又は偽りその他不正の手段により本補助金を受給したことにより、平成16年度以降、補助金適正化法第17条第1項の規定に基づき、当該事業の交付決定を全部又は一部取り消された場合(共謀した場合を含む)については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ一定期間、当該研究者は本補助金の交付の対象外となり、分担研究者となることもできません。
・ 分担研究者が不適正経理を行った場合は、分担研究者のみが本補助金の交付対象外となります。
・ 補助金適正化法で定める他の補助金等において不適正経理を行った場合も上記に準じて取り扱います。
○ 厚生労働科学研究費補助金において不正経理等を行った場合
・ 不適正経理を行ったが研究以外の用途への使用がなかった場合(共謀した場合を含む)
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度
・ 研究以外の用途への使用があった場合(共謀した場合を含む)
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2〜5年間
・ 上記にかかわらず偽りその他不正の手段により本補助金の交付を受けた又は当該偽りその他不正の手段の使用を共謀した場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間
○ 他の競争的研究資金等において不正経理等を行った場合
・ 平成16年度以降に他の競争的研究資金等において、ア、イ、当該資金の交付の決定の内容及びこれに附した条件等に違反した場合又は偽りその他不正の手段により特定給付金の交付を受け、若しくは当該偽りその他の不正の手段の使用を共謀した場合
→ 当該競争的研究資金を交付しないとされた期間と同一期間
(注) ここでいう「競争的研究資金等」とは、「厚生労働科学研究費補助金取扱規程第3条第7項の規定による特定給付金及び補助金を交付しないこととする期間の取扱いについて」(平成18年3月31日厚科第0331002号厚生科学課長決定)でいう、特定給付金のことを指します。
○ 競争的研究資金以外の補助金において不適正経理を行った場合
・ 平成16年度以降に補助金適正化法で定める、国が国以外の者に対して交付する補助金及び競争的研究資金以外の補助金等において、不適正経理を行ったが研究以外の用途への使用がなかった場合(共謀した場合を含む)
→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度
・ 平成16年度以降に補助金適正化法で定める、国が国以外の者に対して交付する補助金及び競争的研究資金以外の補助金において、研究以外の用途への使用があった場合(共謀した場合を含む)
→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度以降2〜5年間
なお、不正経理を行った研究者及び偽りその他不正の手段により競争的研究資金を受給した研究者、それらに共謀した研究者に関する情報については、「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針」(平成17年9月9日競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、他府省を含む他の競争的研究資金担当課(独立行政法人である配分機関を含む。以下同じ。)に当該不正経理の概要(不正経理等をした研究者名、競争的研究資金名、所属機関、研究課題、交付(予定)額、研究年度、不正の内容等)の提供を行います。また、悪質な事案についてはその概要を公表することがあります。その結果、他の競争的研究資金担当課が、その所管する競争的研究資金について、当該研究者の応募を制限する場合があります。
※ 不正経理等については平成18年8月31日に総合科学技術会議で策定された「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について(共通的な指針)」を踏まえ、厚生労働科学研究費補助金取扱規程等に反映することを予定しています。
(参考)
「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について(共通的な指針)」
※ 研究上の不正について
科学技術の研究は、事実に基づく研究成果の積み重ねの上に成り立つ壮大な創造活動であり、この真理の世界に偽りを持ち込む研究上の不正は、科学技術及びこれに関わる者に対する信頼性を傷つけるとともに、研究活動の停滞をもたらすなど、科学技術の発展に重大な悪影響を及ぼすものです。そのため研究者は、所属する機関の定める倫理綱領・行動指針、日本学術会議の示す科学者の行動規範等を遵守し、高い倫理性を持って研究に臨むことが求められます。
また、厚生労働科学研究費補助金においては、研究上の不正を防止し、それらへの対応を明示するために、総合科学技術会議からの意見具申『「研究上の不正に関する適切な対応について」に関する意見』(平成18年2月28日)、厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会における検討及び他府省における検討状況等を踏まえ、現在、厚生労働科学研究費補助金における研究上の不正に対する指針等を検討しており、このような不正に対して、補助金の打ち切り及び返還、一定期間交付の対象外とする、申請の不採択、不正の内容及び措置の公表、他府省への情報提供等の対応を予定しています。当該指針等については、平成19年度の厚生労働科学研究費補助金取扱規程等に反映することを予定しています。
(2) 研究組織及び研究期間等
ア. 研究組織
(ア) 主任研究者
公益法人が応募する場合にあっては、主任研究者として当該法人所属の研究者を主任研究者として位置づけること。
(イ) 分担研究者
分担研究者は分担した研究項目について実績報告書を作成する必要がある。
また、分担した研究項目の遂行に必要な経費の配分を受けた場合、その適正な執行に責任を負わねばならない。
(ウ) 研究協力者
主任研究者の研究計画の遂行に協力する。
なお、研究協力者は実績報告書を作成する必要はない。
イ. 研究期間
厚生労働科学研究費補助金取扱規程第9条第1項の規定に基づく交付基準額等決定通知受理後の実際に研究を開始する日から当該年度の実際に研究が終了する日とします。
ウ. 所属機関の長の承諾
主任研究者(分担研究者を含む)は、当該研究を応募することについて所属機関の長の承認を得てください。
なお、当該研究の実施にかかる承諾書の提出は補助金を申請する時に提出していただくこととなります。
(3) 対象経費
ア. 申請できる研究経費
研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。
なお、経費の算出に当たっては、別添「厚生労働科学研究費補助金における補助対象経費の単価基準額一覧表(平成19年度)」により算出して下さい。
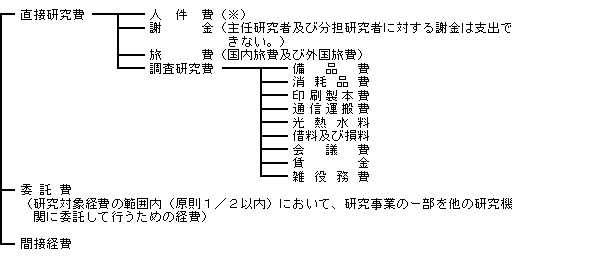
※ 人件費については、厚生労働科学研究費補助金取扱細則の別表第1の(1)の規定に従い補助の対象とする。
イ. 申請できない研究経費
本補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人を対象としているので、次のような経費は申請することはできませんので留意して下さい。
(ア) 建物等施設に関する経費。
ただし、補助金により購入した設備備品を導入することにより必要となる据え付け費及び調整費を除く。
(イ) 研究補助者に対する月極めの給与、退職金、ボーナスその他各種手当。
(若手研究者育成活用事業などの推進事業を利用してください。)
(ウ) 机、いす、複写機等研究機関で通常備えるべき設備備品を購入するための経費。
(エ) 研究実施中に発生した事故又は災害の処理のための経費。(被験者に健康被害が生じ補償を要する場合に当該補償を行うために必要な保険(当該研究計画に位置づけられたものに限る。)の保険料を除く。)
(オ) その他本補助金による研究に関連性のない経費。
ウ. 外国旅費等について
主任研究者又は分担研究者(法人にあっては、当該研究に従事する者であって主任研究者又は分担研究者に準ずる者)が当該研究上必要な専門家会議、情報交換及び現地調査又は国際学会等において当該研究の研究成果等の発表を行う場合に、1行程につき最長2週間(※)の期間に限り、海外渡航に必要な外国旅費及び海外で必要となる経費(諸謝金並びに調査研究費の各費目に限る。)が補助対象となっています。ただし、補助対象となる外国旅費等の総額は、次のとおり上限額が設定されております。
| 区分 | 上限額 |
| (1) 交付額25,000千円以上 | 5,000千円 |
| (2) 交付額3,000千円以上〜25,000千円未満 | 交付額の20% |
| (3) 交付額1,000千円以上〜3,000千円未満 | 600千円 |
※ 天災その他事故によりやむを得ず1行程が2週間の期間を超えた場合には、厚生労働大臣が認めた最小行程を補助対象とする場合がある。
※ 国際学会において当該研究の研究成果の発表を行う際の「学会参加費」については、発表を行うために必要な最低限の費用であることを開催者が発行するパンフレットによって確認できる場合に限り、補助対象とする場合がある。
エ. 国内学会参加旅費について
主任研究者又は分担研究者(法人にあっては、当該研究に従事する者であって主任研究者又は分担研究者に準ずる者)が国内学会において当該研究の研究成果等の発表を行うことを開催者が発行するパンフレット等によって確認できる場合に限り、学会参加に必要な旅費を補助対象とする場合があります。ただし、国内学会の出席に使用できる国内旅費の総額は、次のとおり上限額が設定されております。
| 区分 | 上限額 |
| (1) 交付額25,000千円以上 | 2,500千円 |
| (2) 交付額3,000千円以上〜25,000千円未満 | 交付額の10% |
| (3) 交付額1,000千円以上〜3,000千円未満 | 300千円 |
オ. 備品について
価格が50万円以上の機械器具等であって、賃借が可能なものを購入するための経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。
カ. 賃金について
賃金は主任研究者(分担研究者含む)の研究計画の遂行に必要な資料整理等(経理事務等を行う者を含む)を行う者を日々雇用する経費ですが、これらの者を補助金により研究機関において雇用することができます。
この場合、研究機関が雇用するために必要となる経費は、補助金から所属する研究機関に対して納入してください。(間接経費が支給される場合は除く)
国立試験研究機関(※)の研究者に公募による研究経費が交付された場合、経理事務及び研究補助に要する賃金職員は別途の予算手当によって各機関一括して雇用するため、研究経費からこれらに係る賃金は支出できません。
※ 国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所及び国立保健医療科学院をいう。
キ. 間接経費について
間接経費は、厚生労働科学研究費補助金を効果的・効率的に活用できるよう、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費を、直接研究費等に上積みして措置するものであり、研究費の補助を受ける主任研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に資することを目的としています。
間接経費の補助対象は、平成19年度に新規採択される公募研究課題で3千万円以上の研究費であり、30%を限度に交付を予定しています。なお、本制度については、主任研究者が国立試験研究機関に所属する場合には対象外となります。
(4) 応募に当たっての留意事項
ア. 補助金の管理及び経理について
補助金の管理及び経理の透明化及び適正化を図るとともに、主任研究者及び経費の配分を受ける分担研究者の直接研究費等の管理及び経理事務に係る負担の軽減を図る観点から、補助金の管理及び経理事務は、主任研究者等の所属機関の長に委任してください。
(ア) 間接経費が交付される研究にあっては、必ず主任研究者が所属する研究機関の長に委任してください。
(イ) 間接経費が交付されない研究にあっては、必要に応じて主任研究者に交付される直接研究費により所属機関において関係事務担当者を置くなど(上記(3)オ.賃金について)を参照)して、できる限り主任研究者が所属する研究機関の長に委任してください。
なお、研究機関に委任できない特別な事情がないにもかかわらず、機関に委任しない場合は、採択しないのでご注意願います。
(ウ) 国立試験研究機関の職員が主任研究者等となる場合は、必ず所属機関の長に委任してください。
イ. 経費の混同使用の禁止について
他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に本補助金を加算して、1個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。
ウ. 研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点
各府省が定める以下の法律・省令・倫理指針等を遵守してください。これらの法律・省令・指針等の遵守状況について調査を行うことがありますので、予めご了解ください。また、これらの法令等に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取り消し又は補助金の交付決定取り消し、返還等の処分を行うことがあります。
○ ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)
○ 特定胚の取扱いに関する指針(平成13年文部科学省告示第173号)
○ ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(平成19年文部科学省告示第87号)
○ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
○ 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)
○ 手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成10年厚生科学審議会答申)
○ 疫学研究に関する倫理指針(平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
○ 遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
○ 臨床研究に関する倫理指針(平成16年厚生労働省告示第459号)
○ ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する倫理指針(平成18年厚生労働省告示第425号)
○ 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)又は農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付農林水産省農林水産技術会議事務局長通知)
エ. 臨床研究登録制度への登録について
介入を行う臨床研究を行う場合には、当該臨床研究を開始するまでに以下の3つのうちいずれかの臨床研究登録システムに登録を行うこと。また、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書(様式自由)を別に添付すること。なお、登録された内容が、実施している研究の内容と齟齬がないかどうかについて調査を行うことがありますのであらかじめご了解ください。
○ 大学病院医療情報ネットワーク(UMIN)「臨床試験登録システム」
http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm
○ (財)日本医薬情報センター(JAPIC)「臨床試験情報」
http://www.clinicaltrials.jp/user/cte_main.jsp
○ (社)日本医師会治験促進センター「臨床試験登録システム」
https://dbcentre2.jmacct.med.or.jp/ctrialr/
オ. 本補助金の応募に当たっての留意点について
本補助金の応募に当たっては、「V.公募研究事業の概要等」の<新規課題採択方針>及び<公募研究課題>の記載内容を良く確認し、ご自身の研究内容が行政のニーズを満たすものであるかどうかを十分検討して下さい。
(5) 提出期間 平成19年10月25日(木)〜11月24日(土)
(受付時間は、9:30〜12:00及び13:00〜17:00とし、土・日・祝日の受付は行いません。)
申請書類は、簡易書留等、配達されたことが証明できる方法とし、封書宛名左下に赤字で「研究事業名」及び「公募課題番号」を記入してください。なお、11月24日(土)までの消印も有効としますが、提出期間内にできるだけ到着するよう余裕をもって投函してください。
(6) 提出先 厚生労働省内の研究事業担当課 <「III.照会先一覧」参照>
〒 100−8916
東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館)
研究機関等においては、所属する研究者の研究計画書をできるだけとりまとめの上、提出して下さい。
(7) 提出書類 研究計画書は、様式第1を提出して下さい。
(8) 提出部数 研究計画書20部(研究計画書(正)1部、(正)の写し19部)
(研究計画書は、両面印刷し左上をホチキスで止めること。)
(9) その他
ア. 研究の成果及びその公表
研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、本補助金による研究事業の成果によって、相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあります。
なお、報告書等は公開となります。
また、研究事業の結果又はその経過の全部若しくは一部について、新聞、書籍、雑誌等において発表を行う場合は、本補助金による事業の成果である旨を明らかにしてください。
※ 研究により得られた成果は研究の成果を継続的に追跡して評価するため、「行政効果報告(助成研究成果追跡資料)WEB登録(http://mhlw-grants.niph.go.jp/idshinsei/)」に必ず登録してください。
イ. 厚生労働科学研究費補助金による推進事業の活用について
本公募要項に基づく公募による研究者等への研究費補助のほか、採択された研究課題を支援するため、厚生労働科学研究費補助金により、主に次の事業を関係公益法人において実施します。
(ア) 外国人研究者招へい事業
課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、当該研究の分野で優れた研究を行っている外国人研究者を招へいし、海外との研究協力を推進することにより我が国における当該研究の推進を図る事業。(招へい期間:2週間程度)
(イ) 外国への日本人研究者派遣事業
課題が採択された主任研究者からの推薦に基づき、国内の若手日本人研究者を外国の研究機関及び大学等に派遣し、当該研究課題に関する研究を実施することにより、我が国における当該研究の推進を図る事業。(派遣期間:6ヶ月程度)
(ウ) リサーチ・レジデント事業(若手研究者育成活用事業)
課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、主任又は分担研究者の所属する研究機関に当該研究課題に関する研究に専念する若手研究者を一定期間(原則1年、最長3年まで延長)派遣し、当該研究の推進を図るとともに、将来の我が国の当該研究の中核となる人材を育成するための事業。
(対象者:博士の学位を有する者又はそれと同等の者(満39歳以下の者))
当該事業に係る募集案内については、研究課題採択後に実施団体から直接主任研究者あて行うこととなります。
※ なお、当事業における本年度の公募は終了しています。
ウ. 研究計画書に記載する公募課題番号について
「V.公募研究事業の概要等」の各研究事業公募研究課題に明示されている番号を記載して下さい。
エ. 健康危険情報について
厚生労働省においては、平成9年1月に「厚生労働健康危機管理基本指針」を策定し、健康危機管理の体制を整備しており、この一環として、国民の生命、健康に重大な影響を及ぼす情報(以下、「健康危険情報」という。)については、厚生労働科学研究費補助金により研究を行う研究者からも広く情報収集を図ることとしておりますので、その趣旨をご理解の上、研究の過程で健康危険情報を得た場合には、厚生労働省への通報をお願いします。
なお、提供いただいた健康危険情報については、厚生労働省において他の情報も併せて評価した上で必要な対応を検討するものであり、情報提供に伴う責任が研究者に生じるものではありませんので、幅広く提供いただくようお願いします。
オ. 政府研究開発データベース入力のための情報
本補助金により行う研究については、府省横断的なデータベースである政府研究開発データベース(内閣府総合科学技術会議事務局)への入力対象となります。以下の情報については、研究計画書中の「18.政府研究開発データベース」(様式第3にあっては「17.政府研究開発データベース」)に確実に記入願います。
(ア) 研究者ID
主任研究者又は分担研究者の内、大学関係又は国・特殊法人等の研究機関に所属する研究者は、それぞれ所属機関等により付与された研究者IDを記入して下さい。文部科学省の科学研究費ID(8桁)をもっている大学等の研究者は、20という2桁の数字をあたまに付けた10桁の数字が研究者IDとなります。国立研究機関等の研究者は、IDを所属機関に確認して下さい。
なお、分担研究者にあっては、研究費の配分額の多い者から順に10名までがID記載の対象となります。
また、IDが不明な場合は、所属機関に確認してください。
(イ) エフォート
主任研究者又は分担研究者は、研究者が当該研究の実施に必要とする時間の配分率(%)いわゆるエフォートについて、研究者の年間の全仕事時間(正規の勤務時間に限らない)を100%として小数点以下を四捨五入し整数で記入して下さい。
なお、分担研究者にあっては、研究費の配分額の多い者から順に10名までがエフォート記載の対象となります。
また、このエフォートについては、各研究者が当該研究について何%ずつ分担するのかを問うものではありませんので、誤解のないようお願いします。
(ウ) 研究分野
主たる研究分野を「重点研究分野コード表」(Excel:27KB)より選び、研究区分番号、重点研究分野、研究区分を記入するとともに、関連する研究分野(最大3つ)についても同様に記入願います。
(エ) 研究キーワード
当該研究の内容に則した、研究キーワードについて、「研究キーワード候補リスト」(Excel:35KB)より選び、コード番号、研究キーワードを記入願います。(最大5つ)
該当するものがない場合、30字以内で独自のキーワードを記入して下さい。
(オ) 研究開発の性格
当該研究について、基礎研究、応用研究、開発研究のいずれに当たるかを記入願います。
カ. 研究課題採択後において、厚生労働省が指示する厚生労働科学研究費補助金の交付申請書や事業実績報告書等の提出期限を守らない場合は、採択の取り消しを行うこともありますので十分留意して下さい。また、他省庁等で同一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに「III.照会先覧」に記載された担当課へ報告し、いずれかの研究を辞退してください。なお、この手続きをせず、同一内容の研究課題の採択が明らかになった場合は、当省の採択の取消し、また、交付決定においては、補助金の返還を求めることがあります。
キ. 競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除について
(ア) 本補助金の応募の際には、他府省を含む他の競争的研究資金等の応募・受入状況(研究事業名、研究課題名、実施期間、補助要求額、エフォート等)の研究計画書に記載していただきます。なお、計画書に事実と異なる記載をした場合は、研究課題の採択の取り消し又は補助金の交付決定取り消し、返還等の処分を行うことがあります。
(イ) 課題採択に当たっては、「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針」(平成17年9月9日競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、研究計画書及び他省庁からの情報等により、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中が認められた場合には、研究課題の採択を見合わせる場合等があります。
なお、このような課題の存在の有無を確認する目的で、課題採択前に、必要な範囲内で、採択予定課題及び及び研究計画書の内容の一部(競争的研究資金名、研究者名、所属機関、研究課題、研究概要、計画経費等)を他府省を含む他の競争的研究資金担当課に情報提供する場合があります。
ク. 個人情報の取り扱い
本補助金に係る研究計画書又は交付申請書等に含まれる個人情報は、本補助金の業務のために利用及び提供する他、「政府研究開発データベース」への入力のため内閣府に提供されます。また、上記キに基づく情報提供が行われる場合があります。
なお、採択課題名等(主任研究者名を含む。)及び研究報告書(概要版を含む。)については、印刷物、厚生労働省ホームページ(厚生労働科学研究成果データベース)により公開されます。
III. 照会先一覧
この公募に関して疑問点等が生じた場合には、次表に示す連絡先に照会して下さい。
| 区分 | 連絡先(厚生労働省代表03-5253-1111) |
| 3. 臨床応用基盤研究事業 | |
| (1) 医療技術実用化総合研究事業 | 医政局研究開発振興課(内線4151) |
IV. 研究課題の評価
研究課題の評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」(平成14年8月27日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)に基づき、新規申請課題の採択の可否等について審査する「事前評価」、研究継続の可否等を審査する「中間評価」(※)、研究終了後の研究成果を審査する「事後評価」の3つの過程に分けられます。
「事前評価」においては、提出された研究計画書に基づき外部専門家により構成される事前評価委員会において、「専門的・学術的観点」と「行政的観点」の両面からの総合的な評価(研究内容の倫理性等総合的に勘案すべき事項についても評定事項に加えます。)を経たのち、研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。(なお、大型の公募研究課題については、必要に応じ申請者に対して申請課題に対する研究の背景、目的、構想、研究体制、展望等についてのヒアリングや施設の訪問調査を実施し、評価を行います。)
研究課題決定後は、速やかに申請者へ文書で通知します。
また、採択された課題等については、印刷物のほか厚生労働省ホームページ等により公表します。
※ 研究期間が複数年度で採択された研究課題であっても、中間評価により中途で終了することがある。
(1) 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項
ア. 研究の厚生労働科学分野における重要性
・ 厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるか
イ. 研究の厚生労働科学分野における発展性
・ 厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるか
・ 研究成果が厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか
・ 厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるか
・ 臨床研究の場合は、いわゆる臨床研究登録がなされる予定か
ウ. 研究の独創性・新規性
・ 厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるか
・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか
エ. 研究目標の実現性・即効性
・ 厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるか
・ 実現可能な研究であるか
・ 厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるか
・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか
オ. 研究者の資質、施設の能力
・ 厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるか
・ 臨床研究の場合は、疫学・生物統計学の専門家が関与しているか
(2) 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項
ア. 行政課題との関連性
・ 厚生労働行政の課題と関連性がある研究であるか
イ. 行政的重要性
・ 厚生労働行政にとって重要な研究であるか
・ 社会的・経済的効果が高い研究であるか
ウ. 行政的緊急性
・ 現時点で実施する必要性・緊急性を有する研究であるか
V. 公募研究事業の概要等
<本補助金のうち本公募要項において公募を行う研究類型について>
厚生科学審議会科学技術部会に設置した「今後の中長期的な厚生労働科学研究の在り方に関する専門委員会」の中間報告書(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0421-4.html)に基づき、平成18年度から本補助金を5つの研究類型に整理することとしました。
本公募要項では、「一般公募型」について募集を行います。
1. 一般公募型
従前の一般公募による競争的枠組み。
<各研究事業の概要及び新規課題採択方針等>
1.臨床応用基盤研究事業
(1)医療技術実用化総合研究事業
ア.臨床試験推進研究
<事業概要>
諸外国等で標準的な治療法でありながら我が国では導入されていない治療法について、特に学会において要望の高い適応外の効能や小児を対象とした効能等の有効性、安全性の確認を目指し、エビデンスの確立を目的として、医療機関、教育機関等で実施される倫理性及び科学性が十分に担保された質の高い臨床試験に対して研究資金を提供する。
関連する「第3期科学技術基本計画における理念と政策目標(大目標、中目標)」
理念 :健康と安全を守る
大目標:生涯はつらつ生活
中目標:国民を悩ます病の克服
<新規課題採択方針>
適応外の効能又は用法・用量の開発につながる、倫理性及び科学性の担保された質の高い臨床試験の実施を推進するために、適応外や小児向け効能又は用法・用量の開発につながる臨床試験であって、得られるデータの質が適当なものとなる研究を採択する。
研究の規模 :1課題当たり、3,000千円〜10,000千円程度(1年当たり)
研究の期間 :3年
新規採択予定数:10〜30課題程度
<公募研究課題>
適応外の医療機器等の使用を含む高度先進的な医療技術のエビデンスの確立に係る臨床試験を実施する研究であって、次に掲げるもの(※)。
・ 内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術
・ 悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節の遺伝子診断
・ 腫瘍性骨病変及び骨粗鬆症に伴う骨脆弱性病変に対する経皮的骨形成術
・ 悪性黒色腫又は乳がんにおけるセンチネルリンパ節の同定と転移の検索
・ カフェイン併用化学療法
・ 胎児尿路・羊水腔シャント術
・ 筋過緊張に対するmuscle afferent block(MAB)治療
・ 胸部悪性腫瘍に対するラジオ波焼灼療法
・ 腎悪性腫瘍に対するラジオ波焼灼療法
・ 内視鏡下甲状腺がん手術
・ 骨腫瘍のCT透視ガイド下経皮的ラジオ波焼灼療法
・ 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー治療法
・ 胎児胸腔・羊水腔シャントチューブ留置術
・ 早期胃がんに対する腹腔鏡下センチネルリンパ節検索
・ 副甲状腺内活性型ビタミンD(アナログ)直接注入療法
※ 「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療及び施設基準」(平成18年厚生労働省告示第575号)に規定される技術一覧に規定される技術を参考。
(留意点)
次の条件を満たすものであること。
1)安全性を確保するための観点
被験者に対して、責任と補償の内容について予め説明し同意を得ること。
2)有効性を確保するための観点
研究計画の作成・プロトコールの作成にあたっては、予め諸外国における当該効能等の安全性・有効性等に係るエビデンスが十分にあることを確認の上、プロトコールを作成すること。
3)その他
中央社会保険医療協議会にて取り決められた「臨床的な使用確認試験」に関連する研究であり、臨床試験実施体制の充実や関連機関との連携を図って実施するものであること。
<医療技術実用化総合研究事業の留意点>
ア. 目標を明確にするため、研究計画書の「8.研究の目的、必要性及び期待される成果」に、当該研究により期待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体的に記載すること。また、「11.研究計画・方法及び倫理面への配慮」に、年度ごとの計画及び達成目標を記載するとともに、実際の医療等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した資料を添付すること(様式任意)。
なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度(未達成の場合にはその理由、計画の練り直し案)如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得ることに留意すること。
イ. 介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、WHO等のミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと(II応募に関する諸条件(4)応募に当たっての留意事項 エ.臨床研究登録制度への登録について 参照)。なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書(様式自由)を別に添付すること。
ウ.倫理的妥当性を確保する観点より
・研究計画において、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理指針等に規定する院内の倫理審査委員会の承認が得られている(又はその見込みである)こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び提供される補償の内容について患者又は家族に説明し文書により同意を得ること。
・モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。
VI. 補助対象経費の単価基準額一覧表(平成19年度)
(※下記単価については、個人が所属する試験研究機関等及び法人が定めている単価との均衡に配慮し、決定するものとする。)
1. 人件費等(厚生労働科学研究費補助金取扱細則の別表第1の1(1)に掲げる研究に限る)
(1) 非常勤職員手当
(単位:円)
| 対象となる研究 | 対象期間 | 単価 | 摘要 |
| 厚生労働科学研究費補助金取扱細則の別表第1の1(1)に掲げる研究 | 1か月当たり | Aランク 410,000 |
博士の学位を取得後、国内外の研究機関で実績を積み、かつ、欧文誌等での主著が数件ある研究者 |
| Bランク 290,000 |
博士の学位を取得又はこれと同等の研究能力を有する者 | ||
| Cランク200,000 | 学士の学位を有する者又はこれと同等の研究能力を有する者 |
(2) 保険料 ・・・ 雇用者が負担する保険料とする。
(3) 通勤手当 ・・・ 国家公務員に準ずる。(通勤手当の支給額等を参照)
(4) 住居手当 ・・・ 国家公務員に準ずる。(住居手当の支給額等を参照)
2. 諸謝金
(単位:円)
| 用務内容 | 職種 | 対象期間 | 単価 | 摘要 |
| 定形的な用務を依頼する場合 | 医師 | 1日当たり | 14,100 | 医師以上の者又は相当者 |
| 技術者 | 7,800 | 大学(短大を含む)卒業者又は専門技術を有する者及び相当者 | ||
| 研究補助者 | 6,600 | その他 | ||
| 講演、討論等研究遂行のうえで学会権威者を招へいする場合 | 教授 | 1時間当たり | 9,300 | 教授級以上又は相当者 |
| 助教授 | 7,700 | 助教授級以上又は相当者 | ||
| 講師 | 5,100 | 講師級以上又は相当者 | ||
| 治験等のための研究協力謝金 | 1回当たり | 1,000 | 程度 治験(採血等)、アンケート記入などの研究協力謝金については、協力内容(拘束時間等)を勘案し、常識の範囲を超えない妥当な単価を設定すること。なお、謝品として代用することも可(その場合は消耗品費として計上すること)。 |
3. 旅費 ・・・ 国家公務員の旅費に関する法律に準ずる(旅費に係る単価表を参照)
4. 会議費 ・・・ 1人当たり1,000円(昼食をはさむ場合は、2,000円)を基準とする。
5. 会場借料 ・・・ 50,000円以下を目安に実費とする。
6. 賃金 ・・・ 8,300円(1日当たり<8時間>)を基準とし、雇用者が負担する保険料は別に支出する。
人夫、集計・転記・資料整理作業員等の日々雇用する単純労働に服する者に対する賃金。
注) 1. 時間当たりの単価は、上記の単価×1/8の額を基準とする。
2. 積算は、国家公務員採用(行一)×1/21日(百円単位切り上げ)による。
通勤手当の支給額等
通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする研究者、自動車等を使用することを常例とする研究者及びこれらを併用することを常例とする研究者に支給される手当とする。
1 交通機関の利用者
運賃等相当額。ただし、運賃等相当額が1箇月につき55,000円を超える場合は、1箇月につき55,000円とする。
2 自動車等の使用者
使用距離に応じ次表に掲げる額(ただし、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない場合は、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
|
(単位:円)
| ||||||||||||||||||||||||
| 使用距離(片道) | ||||
| 40km以上 45km未満 | 45km以上 50km未満 | 50km以上 55km未満 | 55km以上 60km未満 | 60km以上 |
| 20,900 | 21,800 | 22,700 | 23,600 | 24,500 |
住居手当の支給額等
居住するための住宅を借り受け、一定額(12,000円)を超える家賃若しくは間代を支払っている研究者又は自宅に居住する世帯主である研究者に支給する手当とする。
1 研究者が居住する借家・借間に対する支給額
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている研究者
家賃額−12,000円(100円未満切捨)
(2) 月額23,000円を超え、55,000円未満の家賃を支払っている研究者
(家賃額−23,000円)×1/2+11,000円(100円未満切捨)
(3) 月額55,000円以上の家賃を支払っている研究者
27,000円
2 配偶者等の居住する借家・借間に対する支給額
単身赴任の研究者で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に配偶者が居住し、月額12,000円を超える家賃を支払っている研究者の場合「1 研究者が居住する借家・借間に対する支給額」により算出される額の2分の1の額(百円未満切捨)とする。
3 研究者自らが所有権を有する住宅に対する支給額
研究者が、自らの所有する住宅(これに準ずる住宅を含む。)に世帯主として居住する場合、当該研究者(これに準ずる者を含む。)により当該住宅が新築又は購入された日から起算して5年間に限り2,500円とする。
旅費に係る単価表
(国内旅費)
1. 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算して下さい。
2. 日当及び宿泊料
|
(単位:円)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注) 1. 私立大学及びその他の施設にあっては、この表の額を超えないようにして下さい。
2. 表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地(車中泊を含む)とは、甲地以外の地域をいう。
a 埼玉県 ・・・ さいたま市
b 千葉県 ・・・ 千葉市
c 東京都 ・・・ 特別区(23区)
d 神奈川県 ・・・ 横浜市、川崎市
e 愛知県 ・・・ 名古屋市
f 京都府 ・・・ 京都市
g 大阪府 ・・・ 大阪市、堺市
h 兵庫県 ・・・ 神戸市
i 広島県 ・・・ 広島市
j 福岡県 ・・・ 福岡市
(外国旅費)
1 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算して下さい。
2 日当及び宿泊料
|
(単位:円)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注) 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の範囲については、国家公務員等の旅費に関する法律に準ずる。
(付) 研究計画書の様式及び記入例

