週休2日制普及率の推移(調査産業計、企業規模30人以上)
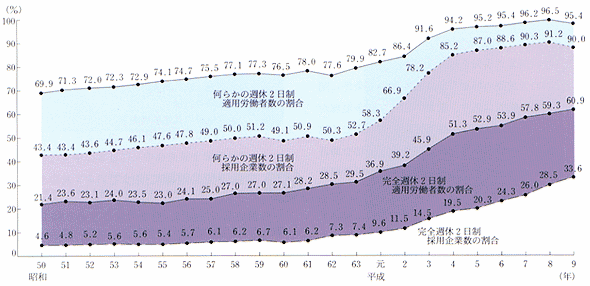
| 資料出所:労働省「賃金労働時間制度等総合調査」 (注)昭和58年以前は各年9月末、59年以降は各年12月末現在。 |
我が国の勤労者生活は、所得面では世界のトップレベルの水準に達しているものの、生活の質的側面では、低い居住水準、長い労働時間、高い生活費等さまざまな問題が指摘されています。一方、本格的な高齢化社会が進展する中で、老後生活を中心に、生活上の不安の高まりがみられ、また、企業規模による福祉面の格差が拡大する等労働生活をめぐり、解決すべき課題が山積しています。 このため、労働省としては、労働条件の確保と向上を図ることはもちろん、真に豊かでゆとりある勤労者生活の実現に向けて、労働時間の短縮、余暇対策をすすめるとともに、勤労者財産形成促進制度、中小企業退職金共済制度等の総合的な勤労者福祉対策を推進しています。 |
労働基準行政は、心身ともに健康でゆとりある勤労者生活の実現を基本的な使命としており、労働者の最低労働条件を確保して一定のレベル以上のものに維持することはもとより、社会経済情勢の変化に即応した課題に積極的に取り組むこととしています。 そこで、まず、労働基準関係法令に規定された労働条件の明示、労働時間の管理、就業規則の作成及び届出、健康管理等の法定労働条件の確保を図るための監督指導を行っています。 また、解雇、賃金不払等の労働条件に関する申告・相談がなされ、労働基準関係法令上の問題が認められる場合には、その解決のための迅速・的確な処理を行うとともに、労働基準関係法令上の問題が認められない場合であっても、関連する裁判例等の情報を提供するなどしています。 さらに、個別の労使間の解雇や配置転換等労働条件に関する紛争事案が増加傾向にあり、簡易・迅速な紛争処理が求められていることから、紛争の当事者の求めに応じて都道府県労働基準局長が紛争の早期解決のための適切な助言又は指導を実施することにより、労使の自主的な紛争解決を促進しています。 このほか、働く人々が意欲にあふれ能力を存分に発揮するとともに安心して働くことができるよう、職場における労働条件や環境の整備を進めることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」が平成10年9月に第143回臨時国会において成立し、その大部分の規定が平成11年4月1日から施行されていますが、労働省では、関係省令等も含め、労使関係者等に対する周知・指導に取り組んでいます。 労働基準行政の関係法律としては、労働基準法のほか、労働安全衛生法、じん肺法、最低賃金法、家内労働法、賃金の支払の確保等に関する法律、労働者災害補償保険法などが制定されており、また、国の一元的な労働基準行政機関として、労働省労働基準局のもとに47の都道府県労働基準局、さらに全国343の労働基準監督署(及び4支署)が設置・運営されています。 |
| 労働基準監督署では次のような仕事を行っています
|
労働時間の短縮は、豊かでゆとりある勤労者生活を実現するために、必要不可欠な国民的課題となっています。 平成7年12月に閣議決定された新経済計画「構造改革のための経済社会計画」においても、年間総労働時間1,800時間の達成・定着が政府の目標とされており、そのために完全週休2日制の普及促進、年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減を3つの柱として労働時間短縮対策を推進しています。 特に、完全週休2日制に相当する週40時間労働制の実現は、我が国を取り巻く国際的環境を踏まえ、昭和62年の労働基準法改正以降約10年をかけて取り組んできた最重要課題です。 この週40時間労働制については、平成9年4月1日から全面的に適用されています。 一方、常時10人未満の労働者を使用する商業・サービス業の事業場(特例措置対象事業場)においては、平成6年4月以来、週46時間労働制とされていたところ、平成13年4月1日から週44時間労働制に移行することとなりました。これに伴い、特例措置対象事業場の労働時間短縮を促進するため、次の2つの助成金が創設されています。
|
||||||||||||||||||
週休2日制普及率の推移(調査産業計、企業規模30人以上)
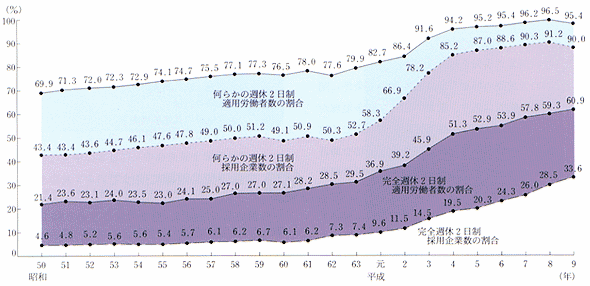
| 資料出所:労働省「賃金労働時間制度等総合調査」 (注)昭和58年以前は各年9月末、59年以降は各年12月末現在。 |
1)業種や職種ごとの事情に応じた労働時間の短縮対策の推進
|
2)年次有給休暇の取得促進
| 「ゆとり休暇推進要綱」に基づき、休暇について国民の関心が高くなる時期を中心に「ゆとり休暇推進フェア」を開催する等効果的な広報啓発活動を実施しています。 |
3)所定外労働の削減対策の推進
| 平成10年の改正労働基準法に基づき「時間外労働の限度基準」が定められ、関係労使には、時間外労働協定の締結に際し、この限度基準の遵守が義務づけられています。またこれとともに、「所定外労働削減要綱」に基づき、所定外労働削減に取り組んでいます。 |
4)労働時間短縮に向けた国民的な気運の醸成
| ゴールデンウィーク、ほっとウィーク(夏季)、「ゆとり創造月間」(毎年11月)を中心とするキャンペーン活動の実施。 |
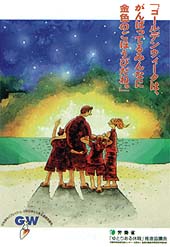 |
 |
労働者1人平均年間総実労働時間の推移(確報)
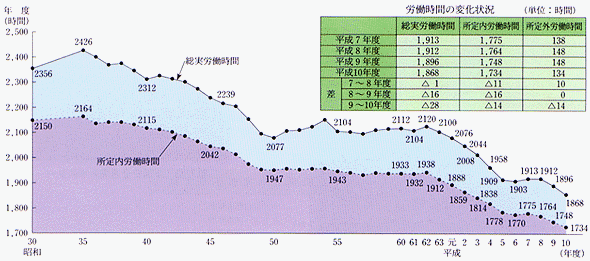
| 資料出所:労働省「毎月勤労統計調査」 (注)事業所規模30人以上。 |
| 労働災害による死傷者数は、長期的には減少していますが、依然として年間約60万人を数え、死亡災害は年間1,800人を超える発生をみています。また、年間約9,000人もの方々が職業性疾病にかかっています。 |
1)労働災害の現状
| 最近の労働災害の発生状況をみると、 | ||||||||
|
||||||||
| などの課題があります。 |
| また、労働者の健康をめぐる状況をみると、高年齢化の進展等に伴い、労働者の約4割が健康診断において何らかの所見が認められるとともに、脳・心臓疾患につながる所見を有する者も増加しています。産業構造の変化、技術革新の進展等により作業態様に変化が生じ、職場での疲労やストレスを感じる労働者が増加するなど新たな課題も生じています。 |
労働災害発生状況の推移
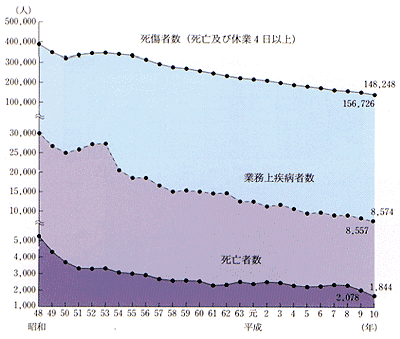
| 資料出所:労働省労働基準局調べ |
2)労働災害防止計画に基づく対策の推進
| 労働省では、このような状況に対応するため、平成10年度から14年度を計画期間とし、「労働災害の総件数の20%の減少を図るほか、労働者の健康の保持増進及び快適な職場環境の形成を推進すること」などを目的とする第9次の労働災害防止計画を策定し、これに基づき各種対策を強力に推進しています。 |
| 労働災害防止計画
労働災害の防止を図るためには、国、事業者など関係者が一体となって、防止対策を総合的かつ計画的に実施することが必要です。このため、 労働安全衛生法6条の規定に基づき、労働大臣は、 中央労働基準審議会の意見を聞いて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた労働災害防止計画を9次にわたり策定しています。 |
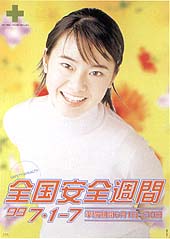
第72回「全国安全週間」ポスター |
3)健康の確保
すべての労働者が心身両面にわたり健康でその能力を十分発揮できるよう、単に疾病予防にとどまることなく、総合的かつ積極的な健康づくりを行うため、労働安全衛生法は、労働者の健康保持増進措置を事業者の努力義務としています。 また、労働省では、小規模事業場の健康管理を支援する地域産業保健センター及び産業医等の専門的な相談に対応する産業保健推進センターの整備を進めています。 |
産業保健推進センターについて
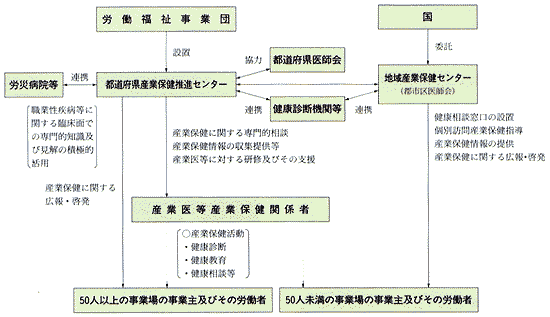
4)快適な職場づくりの推進
| すべての労働者が、疲労・ストレスを生じることの少ない、働きやすい快適な職場環境の形成が求められていることから、労働省では、快適な職場環境の形成に関する指針を策定し、事業者の快適な職場環境の形成の取り組みを支援しています。 |
5)職場における化学物質の管理の推進
有害な化学物質については、危険性の程度により、製造等の禁止、製造の許可、適正な管理の義務づけを行っています。 職場では5万種類を超える化学物質が取り扱われ、毎年約500物質が新たに導入されており、これらの物質の有害性等についても十分に把握し、適切な化学物質管理を進める必要があります。 このため、新規に化学物質を製造し又は輸入する場合、所定の有害性調査を行いその結果を労働大臣に届け出ることや化学物質を譲渡提供する際には有害性等の情報を記載した化学物質安全データシート(MSDS)を譲渡提供先に交付することを義務づける等により、化学物質を取り扱う職場において十分な化学物質管理が行われるよう必要な措置の推進を図っています。また、日本バイオアッセイ研究センターにおいて、実験動物を用いるがん原性試験などの有害性調査を定期的に実施しており、有害性が認められたものについては、公表するとともに、必要な指導を行うこととしています。 さらに、近年、ごみ焼却施設等におけるダイオキシン類対策や内分泌かく乱物質への対応についても積極的に推進しています。 |

がん原性試験場
(日本バイオアッセイ研究センター)
事業者が行う健康の保持増進措置
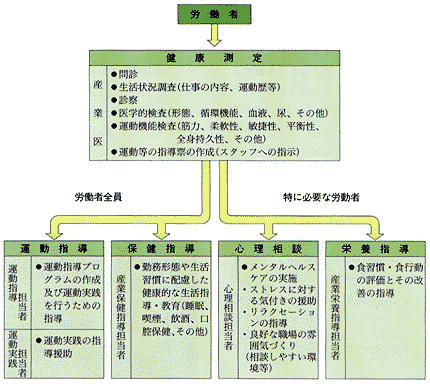
6)労働災害防止及び労働者の健康確保のための研究活動
産業安全研究所においては、産業災害を防止するため、災害現象の解明、災害防止技術の開発等広範な研究を行っており、特に機械設備の自動化・システム化に伴う災害、新工法に伴う災害、不安定物質の爆発災害など、重大災害の防止に研究の重点を置くとともに、最近の災害動向に対処して、人間工学、システム解析など、安全技術への多方面からのアプローチを行っています。 産業医学総合研究所においては、労働者の健康の保持増進及び職業性疾病対策に資するため、[1]労働時間や暑熱などの因子が労働者の健康に及ぼす影響についての研究、[2]職業性疾病の防止に関する研究、[3]化学物質などの有害性評価に関する調査研究、[4]有害因子の計測法などに関する研究、[5]局所排気装置など有害因子対策に関する研究を行っています。 |

土砂崩壊災害研究用の遠心模型実験装置
(産業安全研究所)
| 勤労者財産形成促進制度(財形制度)は、勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者が老後の生活の安定、住宅の取得、その他の資産形成を目的として事業主を通じて貯蓄を行い、事業主及び国がこれを援助する制度です。 |
勤労者財産形成促進制度の概要
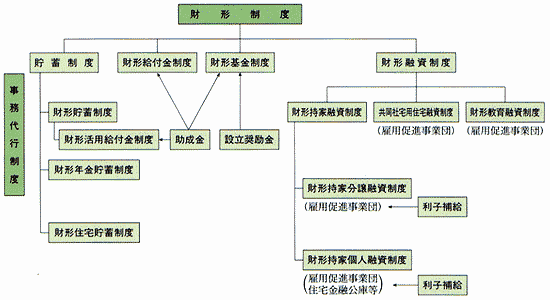
1)財形貯蓄制度
|
2)財形給付金・財形基金制度
財形貯蓄を行う勤労者に対し、事業主が年10万円を限度に拠出し、勤労者の貯蓄を援助する制度です。 また、財形給付金・財形基金制度により拠出を行った中小企業の事業主に対し、一定の助成金を支給する財形助成金制度や、基金が設立されたときに設立奨励金を支給する制度もあります。 |
3)財形活用給付金・助成金制度
| 勤労者が一般財形貯蓄から払い出した金銭を特定の事由(育児、介護、教育等)のために必要な資金に充てた場合に、勤労者に対して一定の給付金を支払う事業主に対し、国が助成金を支給する制度です。 |
4)事務代行制度
| 中小企業の事業主が、財形貯蓄等に係る事務を中小企業団体等(事務代行団体)に委託することができる制度です。 |
5)財形融資制度
|
テレワーク(情報通信を活用したサテライトオフィス勤務、在宅勤務等)は、勤労者にとっては、通勤負担が軽減されることにより、ゆとりある生活や自由時間の増大が実現するほか、企業にとっても、労働生産性の向上に資することが期待されるなど、勤労者及び企業双方にさまざまなメリットがあると考えられます。 このため、テレワークに関するシンポジウム等の開催による周知啓発活動の実施、テレワーク体験・相談センターの開設等を通じてテレワークの推進普及を図ることとしています。 |

テレワークDAYシンポジウム
| 勤労者を取り巻くさまざまな経済社会の構造的な変化の中で、職場、家庭、地域における生活が生涯を通じて充実し、かつ、相互にバランスを保った、ゆとり、安心、活力ある勤労者生活の実現が求められており、このため勤労者の自由時間の充実を図ることが必要となっています。 |
1)勤労者のボランティア活動参加のための環境整備
ボランティア活動に対する社会的な関心が高まる中、勤労者がボランティア活動に参加し、職場以外、特に地域社会とのつながりを深め、普段接することの少ない分野にも視野を広げていくことは、充実した勤労者生活を実現するうえでも重要となっています。 このため労働省では、平成5年度に勤労者ボランティアセンターを開設し、勤労者のボランティア活動に対する企業の理解を深め、ボランティア休暇制度をはじめとした各種の支援を促進することや、勤労者のボランティア活動に関する情報の収集・提供、相談活動を行っています。 |
2)勤労者リフレッシュ対策の推進
長期化する職業生涯の中で、その節目節目に一定期間職務を離れ、心身のリフレッシュを図ることが大変重要となっています。 このため労働省としては、リフレッシュ休暇制度の普及促進を図るとともに、勤労者がリフレッシュ休暇等を活用して、健康増進、自己啓発等を指向した勤労者リフレッシュ活動を推進する事業を行っています。 |
(イ)中小企業における福祉の向上
中小企業における労働者福祉の向上、労使関係の安定等が重要な課題の一つです。これらの課題への対応を図るため、労働省は都道府県を通じて下図1.の事業を、市区町村を通じて2.の事業を行っています。 なお、中小企業勤労者総合福祉推進事業は、中小企業勤労者福祉サービスセンターが実施する、中小企業が単独では実施しにくい、在職中の生活の安定、健康の維持増進、老後生活の安定等にわたる総合的な福祉事業を支援するものです。 |
中小企業福祉補助事業の概要
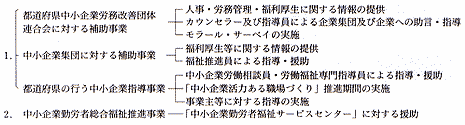
(ロ)中小企業退職金共済制度
この制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業について事業主相互の共済の仕組みと国の援助によって、退職金制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図ることを目的としています。 現在、この制度には常用労働者を対象とした一般の中小企業退職金共済制度と建設業、清酒製造業及び林業において期間を定めて雇用される者を対象とした特定業種退職金共済制度があり、約486万人の中小企業従業員が加入しています。 |
中小企業退職金共済制度の仕組み
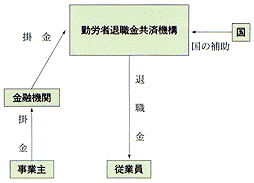
(ハ)中小企業労働福祉推進会議
中小企業には、多種多用の業種・業態があり、経営基盤が脆弱である等のため、人材の確保・育成、労働条件の改善、勤労者福祉の充実の面で多くの問題が存在しており、大企業に比べ、大きな立ち遅れがみられます。このような状況の中で、中小企業の活力を維持し、我が国経済社会の良好な発展を期するためには、規模間格差の問題をはじめ、中小企業が抱える労働問題の解決を図ることが必要となっています。 そこで、今後の中小企業労働対策について検討を行うため、有識者で構成される中小企業労働福祉推進会議を開催しています。 |
(ニ)中小企業の雇用管理の改善
我が国の中小企業は、多くの雇用機会を創出するなど我が国経済上重要な役割を果たしていますが、労働時間、職場環境、福利厚生等の雇用管理面では大企業との格差が大きく、また知名度が低いことなどから、労働力の確保を行ううえで不利な状況に置かれており、厳しい雇用失業情勢のなかにあっても、多くの中小企業が人手不足感を訴えています。 このような状況を踏まえ、「中小企業労働力確保法」に基づき、中小企業の職場としての魅力を高め、労働力の確保を図るため、職場環境の改善や福利厚生の充実等に取り組む中小企業団体等、その構成中小企業及び個別中小企業に対して、財政面、金融面、税制面にわたる総合的な支援措置を講じています。 |
平成10年の15歳から29歳までの働く青少年の人口は1,631万人であり、同年齢人口2,686万人の約60.7%を占めています。 労働省では、勤労青少年福祉法に基づき勤労青少年福祉対策基本方針を定め、都道府県等との連携により、勤労青少年福祉対策を推進しています。 平成8年度から5ヵ年を運営期間とする第6次勤労青少年福祉対策基本方針では、勤労青少年が自律的に職業とのかかわりを持ち、職場以外にも地域、国際社会等さまざまな分野で社会参加できるよう支援することとしており、具体的には、次のような施策を実施しています。
|
ワーキング・ホリデー制度 ワーキング・ホリデー制度とは、日本と相手国との相互理解の促進、友好関係の増進を図るとともに、国際的な視野を持った青少年を育成するため、両国の青少年が、長期休暇を過ごす目的で相手国に入国し、その間の旅行資金を補うための付随的な就労が認められるものである。現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ及び韓国の4ヵ国と日本との間で実施されている。このほか、平成11年度中にフランスとの間でも実施が予定されている。 |
|
|
| 労災保険制度は、労働者が業務災害又は通勤災害を被った場合に、保険給付を行うほか、社会復帰の促進等の労働福祉事業を行っています。 |
適用事業
国内で労働者を使用する事業は、原則としてすべて対象事業場となり、また、中小事業主、自営業者、海外派遣者等には、特別加入制度が設けられています。 |
保険給付
|
[1] 療養補償給付(療養給付) [2] 休業補償給付(休業給付) [3] 傷病補償年金(傷病年金) [4] 障害補償給付(障害給付) [5] 介護補償給付(介護給付) [6] 遺族補償給付(遺族給付) [7] 葬祭料(葬祭給付)) |
このほか、休業特別支給金、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金及びいわゆるボーナス特別支給金がそれぞれの要件の下に支給されます。 一時金及び年金の各給付については、賃金水準の変動率に応じて、毎年、休業補償給付(休業給付)については賃金水準が10%を超えて変動した場合にその率に応じて、それぞれ給付基礎日額を改定して支給します。 |
労働福祉事業
労働福祉事業として、主に次のような事業を行っています。 [1] 社会復帰促進事業 [2] 被災労働者等援護事業 [3] 安全衛生確保事業 [4] 労働条件確保事業 |

労災特別介護施設 |

労災特別介護施設 |
労働条件の主要な要素である賃金については、以下の施策によって、その支払の確保や改善を進めています。 |
1)最低賃金制
最低賃金制は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。 最低賃金には、地域別最低賃金(各都道府県内のすべての労働者に適用されるもの)と産業別最低賃金(全国又は各都道府県内の特定の産業の労働者に適用されるもの)などがあります。 最低賃金額は、労働大臣又は都道府県労働基準局長が、経済情勢等の変化を考慮した額とするため、最低賃金審議会の意見を尊重して、毎年改定しています。 なお、労働省では最低賃金周知旬間(11月21日〜11月30日)を中心に全国的に広報活動を行うことによって、改定された最低賃金額の周知を進めるとともに、最低賃金額以上の支払を確保するための監督指導を行っています。 |
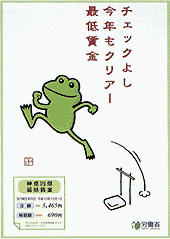
「最低賃金」ポスター
|
||||||||||||||||||||||||
2)賃金・退職金制度の改善
| 各都道府県労働基準局に設置した賃金問題研究会及び賃金相談室等において賃金・退職金制度に関する相談・援助、資料の提供を行うとともに、最近の賃金・退職金制度の改善事例の収集分析等により今後の制度のあり方の研究等を進めています。 |
3)中小企業賃金制度支援事業
| 近年、急速に変化する我が国経済社会に対応した賃金制度の整備・改善への気運が高まってきています。このような気運に対し賃金制度の整備・改善を図ろうとする中小企業団体や中小企業等を支援するため、中小企業賃金制度支援事業として企業の実態に応じたモデル賃金制度、自主点検表等の作成・提供、セミナーの開催等の事業を行っています。 |

平成10年度人事・賃金セミナー
4)賃金支払の確保対策
労働者の生活の安定にとって最も大切な賃金の支払の確保対策等を拡充強化するため、賃金の支払の確保等に関する法律に基づいて次の施策を講じています。
|