民間労働力需給調整事業者の立場からの「官民協力」のご提案
| 木ノ内 博道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■民間から発想する官民協力のあり方 (別紙 図 参照) 今後の労働需給政策においては、民として官に何を協力するかではなく、民間の労働需給調整機能を活用して、課題解決を図る方向で構想すべきであると考えます。 求人情報誌、新聞、折込広告の求人広告は、民間の労働需給調整機能として長年にわたって雇用の開発や新産業への労働力移動に取組んできており、その結果、就職者の入職経路シェアにおいてナンバーワンの位置を占めるに至っています。その立場から言えば、労働市場政策においては、官の仕組みに依存しない、すなわち税金や雇用保険特別会計などの国民負担を伴わない民間主導の労働力需給調整機能を如何に活用するかが第一義的に検討されるべきであると考えます。 今回の官民連携した雇用情報システム(仮称)はあくまで多くの選択肢の中の一つでしかありません。方策の選択にあたっては、政策目的の達成見通し、公共の職業紹介サービスに対する民間部門の代替供給能力、国民負担の問題、民業への影響等を客観的に事前評価していくことが重要と考えます。 民間労働力需給調整事業者の立場からの官民協力のあり方については、(社)全国求人情報誌協会を通じ、下記の方策などを提言してきたところです。 【これまでに行ってきた提案】
【新たな提案】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
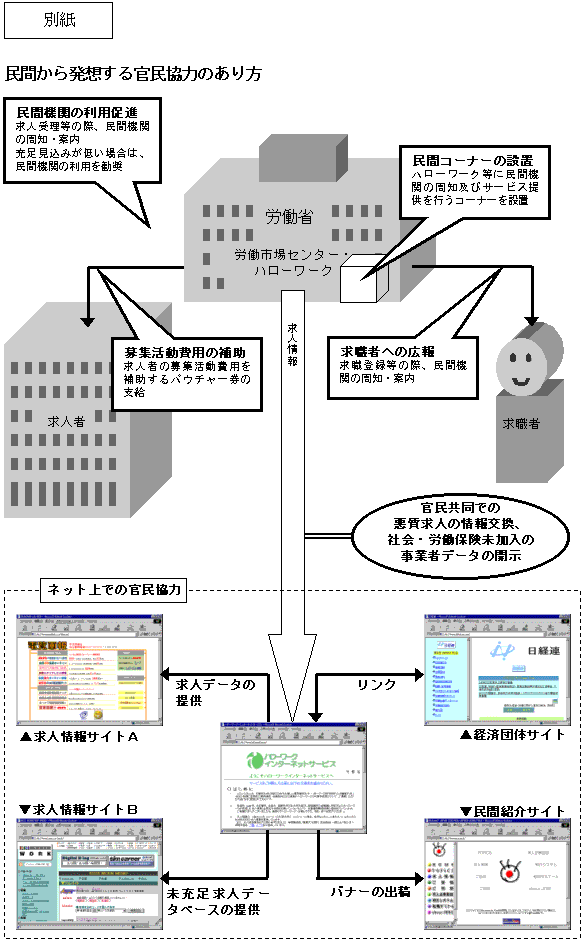 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ホームページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||