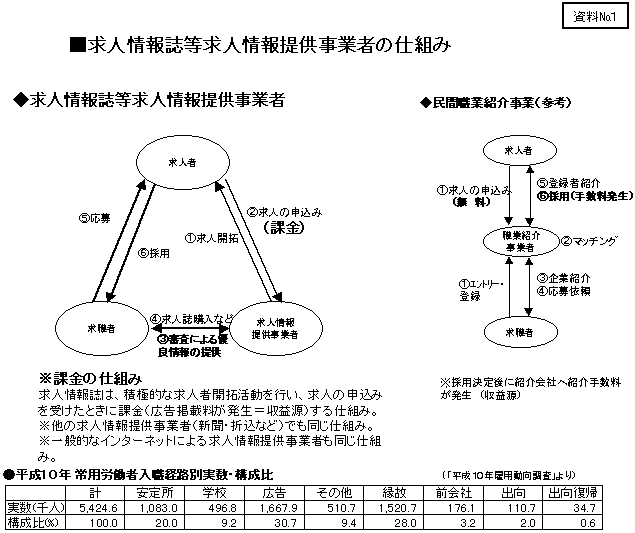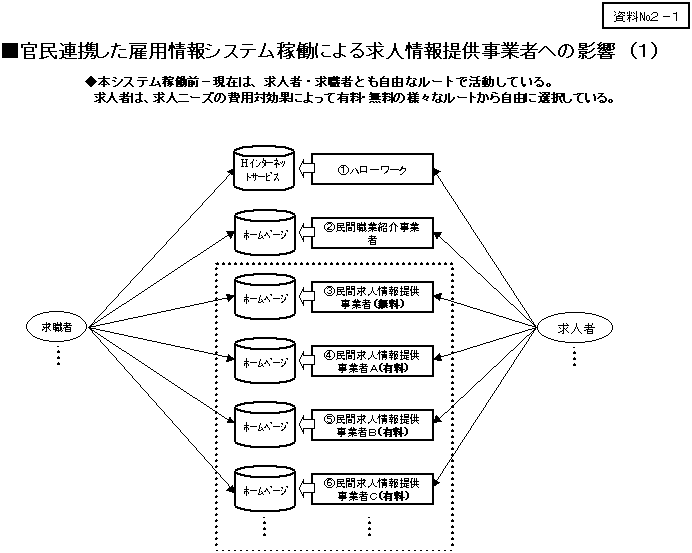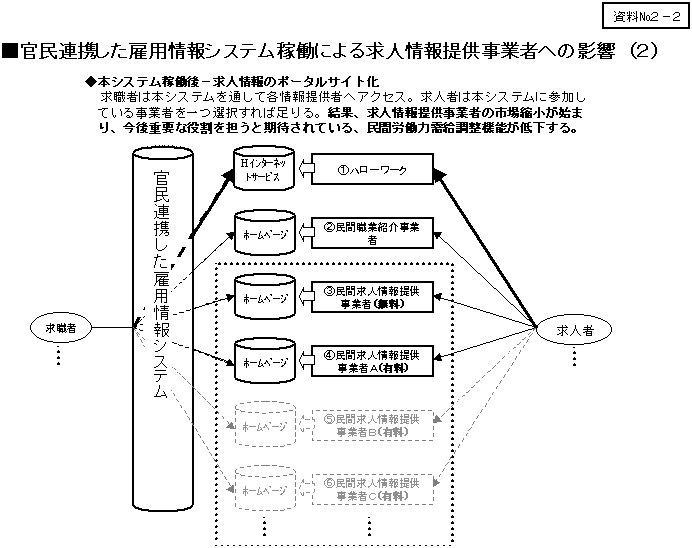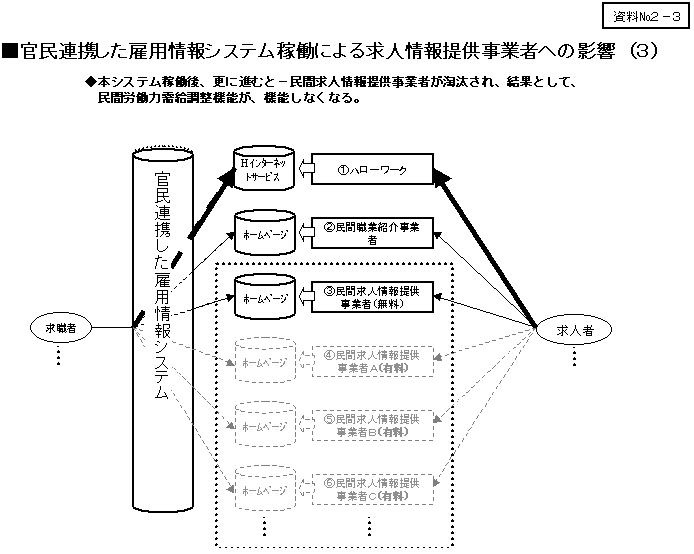|
資料№2-1から2-3までは、先に示されている雇用情報システムが稼動した際に、求人情報提供事業者が受けると考えられる影響について簡略化して図にしたものです。ネット上を想定したものですが、市販の求人情報誌なども同様の影響を受けることになります。
まず、2-1はポータルサイトが稼動していない現在の状態で、それぞれの求人者が目的や効果に応じて求人ルートを使い分けています。ハローワークのほか、有料・無料の職業紹介事業者があり、さらに、点線で囲ってある部分には、民間の求人情報提供事業者(無料の分は便宜上一つにまとめて、有料の分は個々に表示してあります)が存在しています。求人者によってはこれらのうち、複数のサイトやメディアを利用しています。市場原理による自由な活動がなされています。
次に、2-2はポータルサイト稼動後の初期状態です。第一段階としては、例えば、これまで複数のメディアを利用していた求人者は、ポータルサイトで検索した結果に自社の求人情報が出てくれば、非常に多くの求職者に自社の求人情報が伝わり、応募者が出ることが分かります。求人者は民間でいえば、いずれかの求人情報提供事業者に求人広告を申し込めば、ポータルサイトを利用することができるのであるから、余分な費用を掛けて複数社に申し込む必要はなく、求人情報提供事業者1社に申し込めばよいという状態になります。有料民間求人情報提供事業者の市場縮小の始まりです。活力ある自由な労働市場がやせ細り、民間の労働需給機能が低下します。影響は次第に広がり、撤退せざるを得ない事業者も出てくることになります。
最後に2-3は、名実共にポータルサイト完成状態のイメージです。求人者はポータルサイトに求人情報が提供されればよいので、それに掛かる費用(求人広告掲載料金)が安い求人情報提供事業者を選択するようになります。その結果、求人者は有料の求人情報提供事業者に求人広告掲載を頼まなくなり、無料の求人情報提供者が一つあれば、ポータルサイトを利用することができるのであるから、それで事足りることになります。有料の求人情報提供事業者の市場が崩壊します。
前述しましたように、民間求人情報提供事業者は、課金(収益をあげられる)できるからこそ積極的な求人者開拓を行い、広告の審査を行い、質の高い求人情報を提供することにより、潜在的・顕在的求職者を確保するとともに、求職者の就職活動に寄与していたのですが、ポータルサイトに求人情報を掲載すると、求人者にとってはポータルサイトを利用できればよいわけですから、折角開拓した求人者は、無料の求人情報提供事業者または、極めて安価な有料求人情報提供事業者(事業として成り立つなら)に流れていき、自らの首を絞める結果となるわけです。従って、民間求人情報提供事業者は、積極的な求人者開拓も行わなくなり、民間労働力需給調整機能が機能不全に陥る可能性も否定できないと考えます。 |